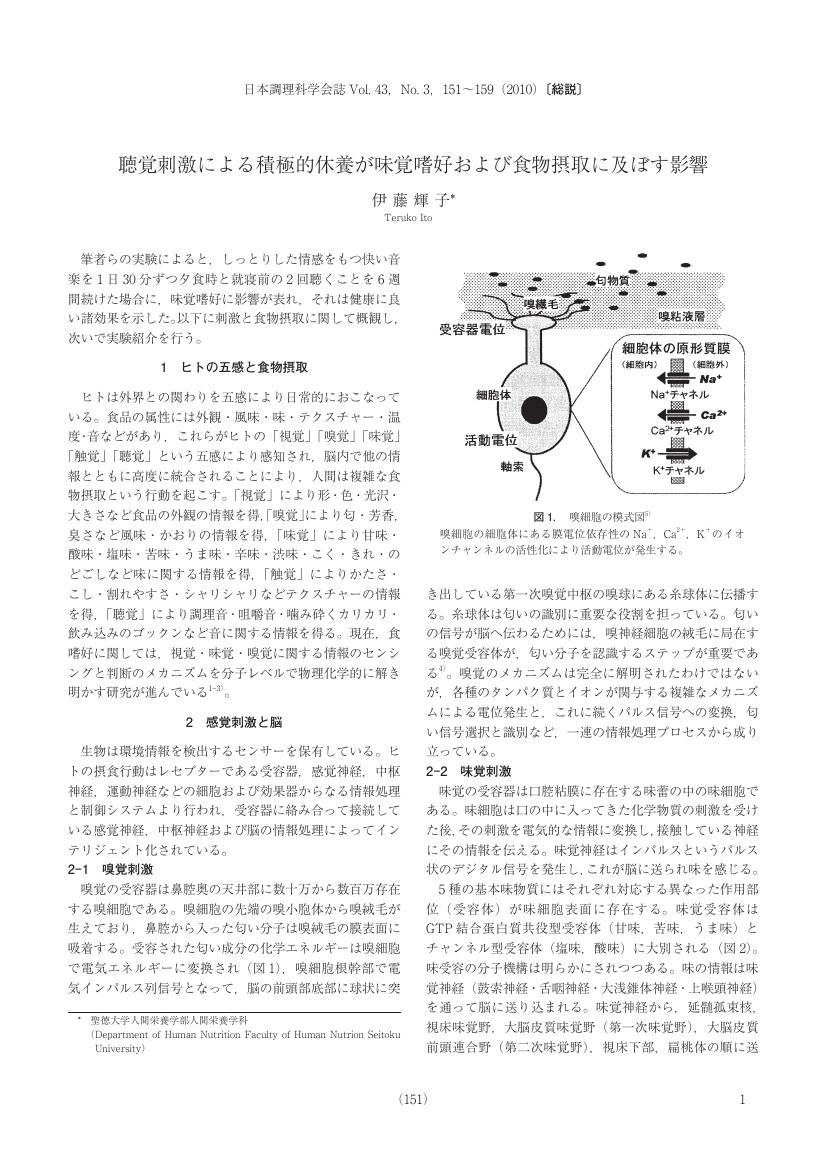1 0 0 0 DDSがアニサキス感染から身を守る: 萌芽から開拓への新展開
アニサキスは、クジラを終宿主とし、鮭・秋刀魚・鱈などの魚を中間宿主とする寄生虫である。昨今、魚の生食に起因するアニサキス感染が話題となっているが、アニサキスを駆虫する治療薬等は開発されていない。本研究は、この状況を打破すべく、研究代表者らが得手とするドラッグデリバリーシステム (DDS) の斬新な学理を基に着想された、JSPS挑戦的研究(萌芽)(19K22778)で芽生えた潜在性を更に引き出す研究であり、アニサキス駆虫研究にブレイクスルーをもたらす可能性を秘めた開拓期の研究である。
1 0 0 0 OA 聴覚刺激による積極的休養が味覚嗜好および食物摂取に及ぼす影響
- 著者
- 伊藤 輝子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.151-159, 2010 (Released:2014-11-21)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 大規模農業地域における土地利用と地下水水質の関係―長野県野辺山原を研究地域として―
- 著者
- 井上 千晶 小倉 紀雄
- 出版者
- 日本水文科学会
- 雑誌
- 日本水文科学会誌 (ISSN:13429612)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.4, pp.149-162, 2000 (Released:2019-01-07)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3 2
The relationship between groundwater quality and landuse was examined on a regional scale for Nobeyama district, Nagano Prefecture which is a large-scale agricultural zone and has a lot of dairy farms in the region. NO3-N, SO42-, Ca2+ and Mg2+ of high concentrations were detected in areas where agricultural activity was high. The concentration of groundwater composition of shallow wells was higher than that of spring water. In particular, high concentrations of NO3-N and SO42- were detected in shallow wells. These show that the effect of human activities for the shallow-well water is stronger than that for the spring water. Many strong correlations were found between the groundwater compositions of the shallow wells, whereas not so many in the spring waters. This suggest that the shallow groundwater quality rapidly reacts to the human impact in limited region. The hexadiagram show that the groundwater has much larger NO3-N and Ca2+ concentrations than the groundwater of the non-polluted control site. The present results indicate that not only NO3-N, Cl-, Ca2+ and Mg2+ but also SO42- could be groundwater composition indicators in an agricultural region like Nobeyama district.
1 0 0 0 OA 機械学習による打音検査の汎化手法について
- 著者
- 新保 弘 尾関 智子 溝渕 利明 野嶋 潤一郎
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- AI・データサイエンス論文集 (ISSN:24359262)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, pp.337-343, 2023 (Released:2023-11-14)
- 参考文献数
- 10
調査点検の生産性向上に向けた打音検査の自動化や機械化には,まず打音評価の定量化が必要である.短時間フーリエ変換等により時間-周波数領域で画像化した打音データをCNN(Convolutional Neural Network)により教師あり学習させることで,健全部と欠陥部の打音を精度よく分類することは可能であるが,部材の特性や環境が異なると分類性能が低下する.ここでは画像化した打音について学習したCNNを特徴抽出器としてのみ利用し,テストサイトの健全打音データの特徴ベクトルから同サイトのテスト打音の特徴ベクトルをマハラノビス距離により評価する方法を提案・検証した.その結果,提案手法により条件の異なるサイトでも健全データからのマハラノビス距離により健全度を定量的に評価できる可能性を示した.
1 0 0 0 OA 認知症有病率の時代的推移―洋の東西の比較
- 著者
- 山本 幹枝 和田 健二
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.547-552, 2018-10-25 (Released:2018-12-11)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1 1
わが国のみならず世界的に認知症者数が増加し,社会経済的な問題となっている.2015年の全世界認知症者数は4,680万人と推定され,2050年には1億3,150万人にのぼることが予測されている.欧州や北米では認知症有病率は低下しているものの,アジアやアフリカなど特に低中所得国での増加が顕著である.わが国では,2012年時点での65歳以上高齢者における認知症有病率は15%(462万人)と推計されている.とくに80歳以降に多く人口の高齢化や生存率の改善を反映していると考えられる.超高齢化社会においては認知症の診断が難しい場合も多く,繰り返し正確な疫学調査が必要である.また,認知症による社会的負担の軽減のためにも,治療法や予防法の確立に向けて世界的に一層の取り組みが進むことが期待される.
1 0 0 0 OA 救急救命士養成施設における学生のバイタルサイン測定の正確性
- 著者
- 竹井 豊 安達 哲浩 長谷川 恵 大松 健太郎 山内 一 神藏 貴久
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.105-109, 2020-06-30 (Released:2020-06-30)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
目的:初期評価は傷病者の処置などの優先順位を迅速に識別する重要な観察である。本研究では救急救命学科学生が呼吸・脈拍数を適切に識別できるのか確認した。方法:4年生大学救急救命学科学生105名を対象として,正常値(呼吸数12回/ 分,脈拍数80回/ 分)と異常値(呼吸数24回/ 分,脈拍数100回/ 分)に設定したシミュレータに対してモニター類を使用せず,それぞれ「遅い」「正常」「速い」の3分類で評価させた。結果:ほとんどの学生が異常所見を正しく識別できた反面,35%の学生が正常を正常と識別できなかった(呼吸12回/ 分:遅い38人・速い2人,脈拍80回/ 分:遅い8人・速い28人)。正常呼吸を正常と識別できた学生の所要時間は中央値で12秒(25-75% 信頼区間:10-16),できなかった学生は9.5秒(7-14.8)であった(p=0.007)。結論:正常呼吸・脈拍を正常と識別できない学生が35%にも上った。バイタルサイン測定の精度は高められなければならない。
1 0 0 0 OA マーケティングにおける信頼
- 著者
- 小野 譲司
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.93-100, 1997-01-10 (Released:2023-11-23)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 顧客適応戦略と標準化戦略
- 著者
- 高嶋 克義
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.40-51, 1997-01-10 (Released:2023-11-23)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 4
1 0 0 0 OA 社会的研究課題及び社会的課題に取り組む学会
- 著者
- 金田 智子
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.168, pp.16-27, 2017 (Released:2019-12-26)
- 参考文献数
- 2
新たな日本語教育学会は,その使命を果たすために,学会を挙げて社会的研究課題に挑戦することと,社会的課題の解決に向けて行動することを事業目標の中に位置付けた。そして,学会は中期計画毎に社会的研究課題と社会的課題を具体的に設定し,学会として取り組んでいくことを決め,調査研究合同会議を発足させ,課題策定を行った。両課題の共有,課題設定目的の理解が会員間に進むことを企図し,なぜ,学会はこれらの課題を設定することにしたのか,今期の課題策定はどのように行ったのか,そして,今後,どのようにその課題に取り組んでいく計画なのかを記すこととする。
1 0 0 0 メディアと情報化の社会学
- 著者
- 井上俊 [ほか] 編集
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 1996
1 0 0 0 OA 「植物の代謝系理解」の再構築
- 著者
- 吉川 博道
- 出版者
- Pesticide Science Society of Japan
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.316-321, 2011-05-20 (Released:2012-11-30)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA チュルク語北東語群の接辞頭子音交替
- 著者
- 江畑 冬生
- 出版者
- 日本北方言語学会
- 雑誌
- 北方言語研究 (ISSN:21857121)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.69-81, 2022-03-20
1 0 0 0 OA 北東ユーラシアチュルク系諸言語の研究: 分岐と接触の歴史的過程の解明
本研究課題ではユーラシア大陸の東西に広がるチュルク諸語のうち北東語群に分類される諸言語を研究対象として,形態音韻プロセスや文法形式の生産性・義務性にも着目しながら,共時的な文法構造の記述と相互分岐と相互接触による歴史的変遷の解明を試みた.その中でも主としてサハ語・トゥバ語・ハカス語という3つの未解明言語に焦点をあて,現地調査とコーパス調査の両方を活用しながら,形態音韻規則・文法形式の義務性・形態法上の特徴・ボイス接辞の用法・証拠性関連接辞の用法・膠着性の度合い・格接辞の用法などに関する記述的・対照言語学的研究において新たな成果を得た.
1 0 0 0 母性行動とプロラクチン受容体発現制御機構に関する研究
- 著者
- 坂口 けさみ 中島 邦夫
- 出版者
- 三重県立看護短期大学
- 雑誌
- 一般研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 1993
プロラクチンは、単に乳腺発育や乳汁分泌維持作用を示すのみでなく母性行動の誘起、維持にも重要な役割を有するホルモンであることが明らかになってきた。今年度私達は、乳仔接触刺激による非妊雌及び雄ラットの母性行動・父性行動を観察すると共に、脳内のプロラクチン受容体mRNAの発現について検討した。また同時に血中プロラクチン濃度の変化についても検討を加えた。雌及び雄ラットの母性行動については各ラットを収容したケージ内に生後3〜16日目の仔ラットを2匹入れ、crouching, licking, nest building, retrieval and groupingの5項目について毎日2時間、2週間仔に対する行動を観察記録した。脳内のプロラクチン受容体mRNAの発現についてはlong form及びshort formの2つの分子種を同時に特異的に検出できるように構築したRNAをプローブとするRNase Protection Assay法により行った。また血中プロラクチン濃度はEIA法により分析した。その結果、仔ラットに対する母性行動・父性行動の発現には性差なく仔ラットへの接触日数と共に、愛着行動の増加していくことが観察された。そこで乳仔に対する母性行動、父性行動が誘導された雌及び雄ラットの脳内プロラクチン受容体mRNAの発現をみると、プロラクチン受容体mRNAのlong formの発現が有意に増加していた。また母性行動、父性行動を示したラットでは明らかに血中プロラクチン濃度が上昇していた。以上、乳仔に対する母性行動・父性行動は性差を問わず、基本的に備わっている能力であり、プロラクチンは脳内プロラクチン受容体遺伝子の発現を誘導し、その結果仔への母性行動あるいは父性行動を促進することが示唆された。
1 0 0 0 OA 個人が知覚する音楽テンポと内受容感覚の精度との関係
- 著者
- 矢ノ倉 萌 渡辺 めぐみ
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第21回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.94, 2023 (Released:2023-10-18)
音楽テンポの知覚と心拍数や内受容感覚の精度の関係を実験で検討した。予備調査より基準刺激のテンポを86.50bpmとし,そのテンポを0.5倍から1.5倍に0.1倍ずつ変えた11種類の比較刺激を作成した。参加者には基準刺激と比較刺激の差を視覚的尺度で回答させ,主観的等価点(PSE)とテンポが実際に位置する基準点の差を得た。実験前後に心拍数測定と内受容感覚として心拍数の自覚回数の報告を行わせた。テンポ倍率を独立変数,PSEと基準点の差を従属変数として一要因分散分析を行うと,テンポが基準値に近い程その差は有意に小さかった。参加者を群分けし,独立変数に基準刺激と心拍数の差または内受容感覚の精度を加えた二要因分散分析を行うと,群間の差に前者では有意差がなく後者では有意傾向が見られた。テンポ倍率が0.7倍と0.8倍の時,内受容感覚が高精度な群の方がPSEと基準点の差は有意に小さく,内受容感覚の精度がテンポ知覚に関わることが示唆された。
1 0 0 0 OA Windows3.0上におけるDOSアプリケーションの実行について
- 著者
- 森 博 牧野 安子 杉江 晶子
- 出版者
- 学校法人滝川学園 名古屋文理大学
- 雑誌
- 名古屋文理短期大学紀要 (ISSN:09146474)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.1-6, 1993-04-01 (Released:2019-07-01)
MS-Windows3.0は,パソコンにとって新しいプラットフォームであり,現在パソコン界の主流OSであるMS-DOSの種々の欠点をカバーするものとして期待されている.ところが米国での成功とは裏腹にわが国においては思ったほどの普及をみせていない.日米におけるハードウェアとソフトウェア環境の違いが主要な原因と考えられるが,それらの環境が整えばわが国においてもWindowsはパソコンの標準的プラットフォームの有力な候補の一つとなりうると考えられる.それまでの間はWindowsと既存のDOSアプリケーションは共存していかなければならないが,両者の親和性についての調査はあまりない.そこで現在まだ広く使われている16ビットパソコンを使い,DOSアプリケーションとして代表的なワープロと表計算ソフトウェアのDOSおよびWindows上でのベンチマークテストを行なった.その結果,実行スピードの点においては予想外に差がでなかったが,EMSメモリーを要求するDOSアプリケーションでは,種々の問題点が存在することが明らかになった.
1 0 0 0 OA 成人における生活習慣病のリスクを高める飲酒量と機能的・伝達的・批判的ヘルスリテラシー
- 著者
- 大内 実結 赤松 利恵 新保 みさ 小島 唯
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.5, pp.202-209, 2023-10-01 (Released:2023-11-23)
- 参考文献数
- 38
【目的】飲酒に関する教育の一助となることを目指し,飲酒状況と機能的,伝達的,批判的の3つのヘルスリテラシー(以下,HL)との関連を示すことを目的とした。【方法】2020年11月実施のインターネット調査のデータを用い,20~64歳の男性3,010人,女性2,932人を対象とした。HLは,機能的,伝達的,批判的の3つのレベルごとに用いた。飲酒状況は,「非飲酒・生活習慣病のリスクを高める飲酒量(以下,高リスク量)未満」「高リスク量」に分類した。HL得点は,男女それぞれの中央値で高群と低群に分類した。HLを独立変数,飲酒状況を従属変数として,ロジスティック回帰分析により各HL高群における「高リスク量」のオッズ比を男女別に算出した。【結果】属性を調整した結果,女性では飲酒状況とレベルごとのHLに関連はみられなかったものの,HL総得点高群に高リスク量の者が少なかった (オッズ比 [95%信頼区間]:0.69 [0.54~0.88])。男性において,属性を調整しない結果では,高リスク量の者が機能的HL高群に少なく,批判的HL高群に多かったが,属性の調整により飲酒状況と各HLに関連はみられなくなった。【結論】本研究では飲酒状況とレベルごとのHLの関連を検討したが,有意な関連はみられなかった。女性では,生活習慣病のリスクを高める飲酒量の防止に向け,総合的なHLを高める重要性が示唆された。
- 著者
- 髙泉 佳苗
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.5, pp.210-218, 2023-10-01 (Released:2023-11-23)
- 参考文献数
- 27
【目的】食生活リテラシーと食環境の認知(食品へのアクセス,情報へのアクセス)および食行動との因果関係を明らかにすることを目的とした。【方法】社会調査会社に登録している30~59歳のモニターから9,030人を層化抽出し,web調査による縦断研究を実施した。ベースライン調査は2018年10月に実施し,追跡調査は2019年10月に実施した。ベースライン調査と追跡調査を回答した解析対象者は2,331人(男性1,200人,女性1,131人)であった。食生活リテラシー得点,食品へのアクセス得点,情報へのアクセス得点,食行動得点の変化量(2019年-2018年)を算出し,因果モデルを作成してパス解析を行った。【結果】男性の食生活リテラシー得点は2018年から2019年で有意に減少していた(p=0.027)。食生活リテラシー得点の変化量は,食品へのアクセス得点の変化量(パス係数=0.07,p<0.01)と情報へのアクセス得点の変化量(パス係数=0.14,p<0.001),食行動得点の変化量(パス係数=0.07,p<0.05)に影響していた。女性の食生活リテラシー得点は有意な経時変化を認めず(p=0.47),食生活リテラシー得点の変化量は,情報へのアクセス得点の変化量(パス係数=0.10,p<0.01)と食行動得点の変化量(パス係数=0.13,p<0.001)に影響していた。【結論】食生活リテラシー得点の向上が食環境の認知得点と食行動得点の向上に及ぼす影響度は強くないが,食生活リテラシーは食環境の認知および食行動の促進要因の一つであることが示された。
1 0 0 0 OA 気候地域の設定-その思潮と問題
- 著者
- 矢澤 大二
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.357-374, 1980-06-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 154
- 被引用文献数
- 1 1
Many theories of climatic classification and of division of climatic regions of the world have been presented in general books on climatology and on physical geography. However, few reports trace the current of thoughts synthetically from the very root of studies up to the present. In the present paper the author has an object to follow the development of thoughts successively and point out how the thoughts of significance had been exploited and developed further. This paper consists of three parts ; namely, an examination of effective methods, a discussion of the problem of humid and arid boundary, and an examination of genetic methods. Effective methods since the 1840's are examined. Some earlier works by Hult, Supan, Köppen, de Martonne, Philipsson etc. were followed by several modern works by Blair, Trewartha, Creutzburg Troll, etc. Special attention is paid to make clear the current of thoughts, regarding representative standards for clamatic classification and for objective divisions into climatic regions. Then, the problem of the boundary between humid and arid regions are reviewed and examined. The concept of effective humidity originated in Linssers's earlier work has been developed by various successors, in order to make clear the water budget or the limit of arid region, indirectly. Physiogeographic consideration by A. Penck was a pioneer work of importance. After genealogic consideration of various methods for evaluating aridity of climate (indices such as Regenfaktor, indice d'aridité, quotient pluviothermique, precipitation effectiveness etc.) and their applicability to distinguish humid and arid climates, the author examines concisely the approach to the rational classification of climate introduced by Thornthwaite, and developed by his successors. It is also pointed out that there are two currents of thoughts regarding the main division of climatic regions of the world. One is to divide, except for the polar region, the world into humid and arid regions, then to subdivide the former into thermal zones and the latter into regions depending upon the degree of aridity. The other is, on the contrary, to divide the world into several thermal zones, and then to subdivide them into subregions, based upon the degree of aridity or humidity of climate. The standpoint of these approachs, therefore, are different to each other. Finally, genetic methods of classification of climate and their applicability to the presentation of climatic regions are examined. The root of such a current could be found in the early works on wind systems or windregions of the world introduced by Mühry, Wojeikof, Köppen, Hettner etc. during the latter half of the last century and the first half of this