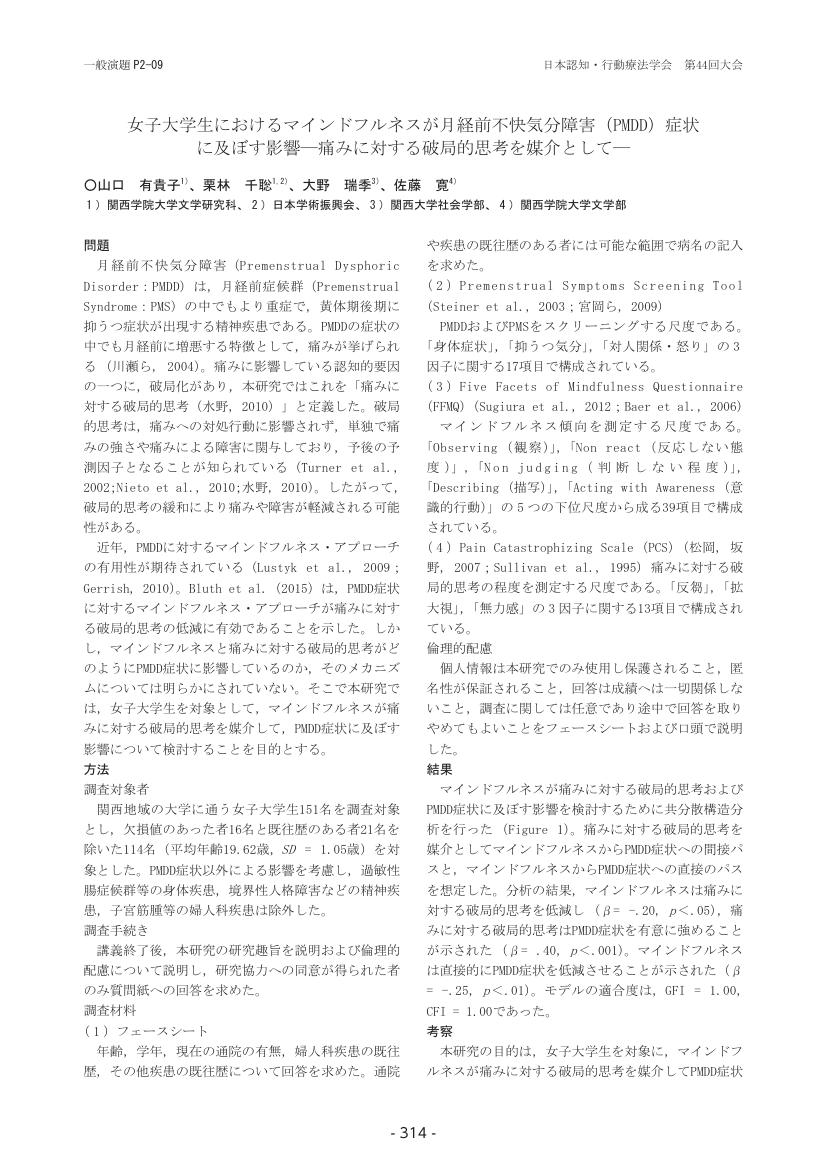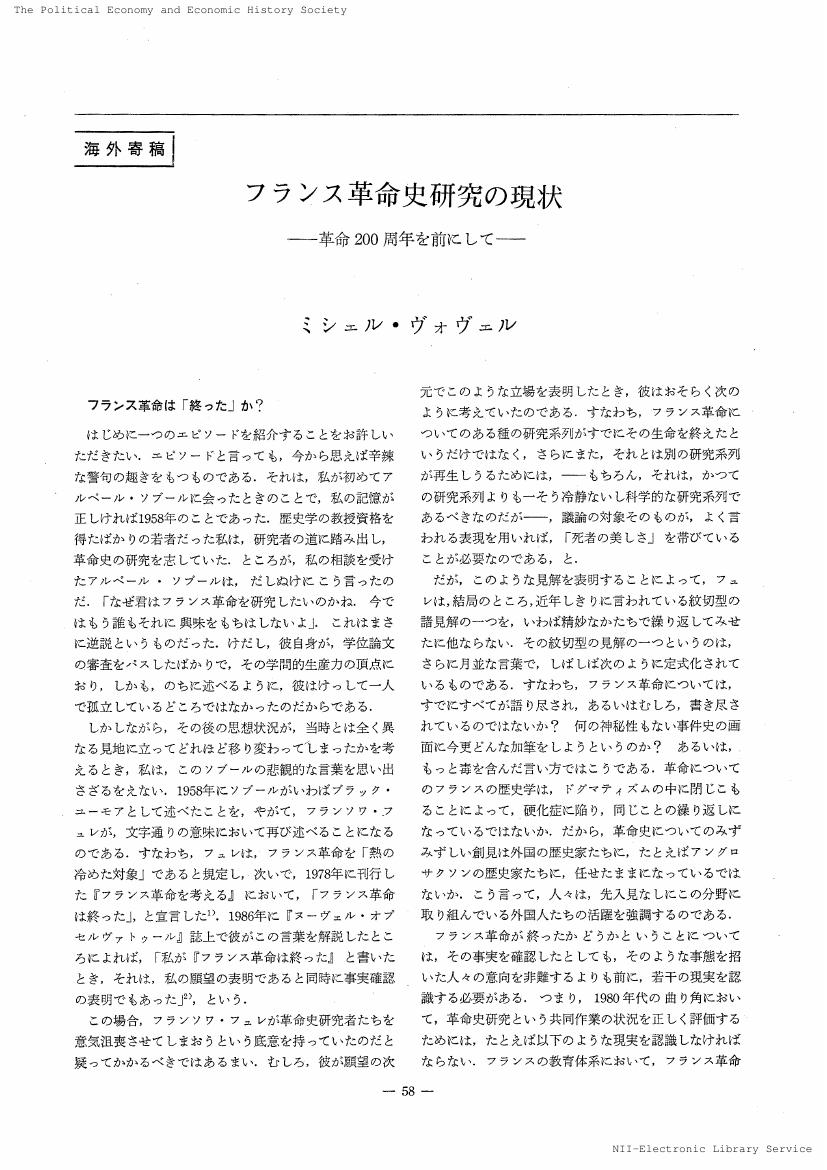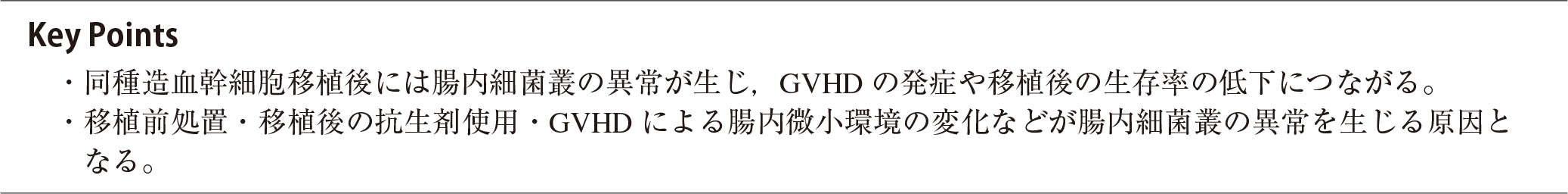- 著者
- 星 博幸
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
Geological and paleomagnetic data suggest that the Japan Sea backarc basin has a two-phase opening history. The first phase may have been relatively slow opening that began in the Eocene or early Oligocene, and the second phase was relatively fast opening occurring in the early Miocene. Paleomagnetic data reported from the Japan arc over the past 40 years show that the second phase was accompanied by differential arc rotation, namely, clockwise rotation of the southwestern lithospheric sliver of the arc (SW Japan) and counterclockwise rotation of the northeastern sliver (NE Japan). However, it is uncertain whether the first phase was also accompanied by differential arc rotation. Here, new paleomagnetic data are presented to address this issue. In this study, Paleocene (~60 Ma) andesite dikes were sampled at 17 sites in the Toki-Mizunami area in SW Japan. These dikes vertically or subvertically intrude a late Cretaceous (~70 Ma) granite batholith and comprise an ENE-striking dike swarm. Stepwise demagnetization experiments were performed on all samples for obtaining characteristic remanent magnetization (ChRM) components. As a result, site-mean directions of ChRM components were determined for 14 sites. Thermal demagnetization of natural remanent magnetization (NRM) and isothermal remanent magnetization (IRM) shows that magnetite is the main magnetic carrier. Comparison of the site-mean directions with the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) suggests that the influence of the preferred orientation of magnetic particles upon the site-mean directions is absent or negligible. Although the site-mean directions display a small dispersion, the presence of dual polarities suggests that the dike emplacement extended over a set of normal and reverse polarity chrons. The overall mean direction of the 14 site-means is therefore interpreted to be a time-averaged paleomagnetic direction at ~60 Ma. It is deflected ~57° clockwise of an expected paleomagnetic direction calculated from a late Cretaceous paleomagnetic pole for the North China Block in the Asian continent, and the amount of clockwise deflection is larger than that (~44°) reported for early Miocene sediments in the Toki-Mizunami area. Therefore, small (~10–15°) clockwise rotation occurred in the study area between the Paleocene and the early Miocene. It is likely that this small rotation is associated with the early opening of the Japan Sea.
1 0 0 0 OA 電磁場の生体影響-動物実験-
- 著者
- 重光 司
- 出版者
- 一般社団法人 日本放射線影響学会
- 雑誌
- 日本放射線影響学会大会講演要旨集 日本放射線影響学会第49回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.27, 2006 (Released:2007-03-13)
電気刺激を臨床に応用しようとする研究は、1950年代の保田等による骨の圧電気現象の発見と微小電流による電気刺激が仮骨を形成させるという報告に端を発しており、電気を用いた治療が整形外科における一手段として定着するようになってきた。一方、1979年に疫学研究により磁界曝露と小児白血病の発症との間に関連性があることが報告された。このような経緯から電磁気現象の生体に及ぼす影響が有益および有害の両面から注目された。近年は、低周波電磁場を中心とした変動磁場ならびに直流磁界の安全性に社会的な関心が集まり、一方では磁場の有効利用の立場から医学への応用についての研究がなされるようになってきた。電磁場の安全性については、問題の発端に関連する発がん実験を始めとして、生殖・発育、行動・感知、神経内分泌等に対する影響を明らかにするため、マウス、ラット、ハムスター、ヒヒならびヒツジなどの動物を用いた研究が行われている。ヒトを対象にした疫学研究や直接曝露実験も行われてきた。動物実験からは安全性、ヒトの健康に有害な影響を及ぼす結果は得られていないが、国際がん研究機関(IARC)は、疫学研究に着目して、「低周波磁場はヒトに対して発がん性を持つ可能性がある(グループ2B)」と結論付けた。一方、低周波電場、直流電磁場については発がんとの関連性はないとされた。 臨床応用としての電気刺激は、低周波領域の電磁場が使われており骨の治癒に対する多くの報告がなされており、骨組織以外の治癒促進を狙った電磁場の応用についても基礎的な研究が行われている。しかし、明確な作用メカニズムは確立されていない。電磁場に関する研究は、安全性および医療への応用を意図した両面からの研究がさらに進められることが期待される分野である。
1 0 0 0 OA ステンレス鋼の海水腐食を通じての電気化学の理解
- 著者
- 竹田 誠一
- 出版者
- 公益社団法人 腐食防食学会
- 雑誌
- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.7, pp.284-293, 2006 (Released:2007-06-28)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2
腐食機構の理解は電気化学の理解が前提である. 物体の電位と電極電位の違いを示した後, 海水中のステンレス鋼の腐食挙動を例にとり, アノード反応, カソード反応とそれによる電極電位の変化について述べることにより, 海水腐食を電気化学にどのように理解すべきかを述べた. 海水腐食に関して, アノード反応の促進原因としてのピット内液の酸性化, カソード反応の促進原因としての寸法効果, 流速, 金属塩, 微生物など各腐食因子の電気化学的意味を説明した.
- 著者
- 村田 康一 近藤 修司
- 出版者
- 研究・技術計画学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.181-184, 2006-10-21
一般論文
1 0 0 0 OA 自然海水中に浸漬したステンレス鋼の電位貴化メカニズムの検討
- 著者
- 伊藤 公夫 松橋 亮 加藤 敏朗 三木 理 紀平 寛
- 出版者
- Japan Society of Corrosion Engineering
- 雑誌
- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.285-291, 2001-06-15 (Released:2011-12-15)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 6 5
Potential ennoblement for stainless steel in natural seawater was analyzed. Open circuit potentials (OCPs) of platinum, gold, palladium, chromium, titanium and nickel ennobled in natural seawater as well as stainless steel, SUS 304 (18Cr-8Ni). Potential ennoblement is not a specific event to only stainless steel. Marine biofilm clearly caused potential ennoblement. Cathodic polarization curves for the ennobled stainless steel elucidated that there were two distinct reduction current increases. One is the limited diffusion current of dissolved oxygen reduction below -500mV vs. Ag/AgCl (KClsat). The other reduction current around 0mV vs. Ag/AgCl (KClsat) was considered to be hydrogen peroxide reduction current in acidic condition. Synergistic effect of hydrogen peroxide and low pH in artificial seawater carried out high OCP of stainless steel like that in natural seawater. Therefore, we concluded that synergistic effect of hydrogen peroxide production and low pH by marine microorganisms is possible cause for potential ennoblement in natural seawater.
- 著者
- Jing Liu Xiangyang Zhang Zhaoxia Yu Tieliang Zhang
- 出版者
- International Heart Journal Association
- 雑誌
- International Heart Journal (ISSN:13492365)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.5, pp.918-927, 2023-09-30 (Released:2023-09-30)
- 参考文献数
- 37
Circular RNAs (circRNAs) are known to play a crucial role in the progression of atherosclerosis (AS). In this study, we aim to explore the function of oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL)-induced macrophage-derived exosomal circ_100696 in AS.THP-1 macrophages were induced by ox-LDL to mimic AS cell model. A quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) assay was applied to determine the expression of circ_100696, microRNA-503-5p (miR-503-5p), and pregnancy-associated plasma protein A (PAPPA). The morphology and size distribution of exosomes were examined by transmission electron microscopy (TEM) and nanoparticle tracking analysis (NTA). Western blot assay was performed for protein levels. Cell proliferation was assessed using 5-ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU) assay. Flow cytometry analysis was performed to analyze the cell cycle. Wound-healing assay and transwell assay were done to examine cell migration. RNA pull-down assay, dual-luciferase reporter assay, and RNA immunoprecipitation (RIP) assay were employed to analyze the relationship among circ_100696, miR-503-5p, and PAPPA.Circ_100696 level was increased in ox-LDL-induced THP-1 macrophages and ox-LDL-treated THP-1 macrophage-derived exosomes (OM-Exo). OM-Exo promoted the proliferation, cell cycle, and migration of vascular smooth muscle cells (VSMCs). Circ_100696 was upregulated in VSMCs cocultured with OM-Exo. Circ_100696 knockdown reversed the effects of OM-Exo on VSMC proliferation and migration. Circ_100696 was demonstrated to function as the sponge for miR-503-5p, and miR-503-5p directly targeted PAPPA. Circ_100696 overexpression facilitated VSMC proliferation and migration, with miR-503-5p upregulation or PAPPA silencing reversing these effects. Moreover, circ_100696 overexpression promoted PAPPA expression by targeting miR-503-5p.OM-Exo promoted VSMC growth and migration by regulating the circ_100696/miR-503-5p/PAPPA axis, thereby promoting AS progression.
1 0 0 0 OA 配偶者および子どもとの資源配分にみる高齢男性の就業選択
- 著者
- 新田 真悟
- 出版者
- 日本老年社会科学会
- 雑誌
- 老年社会科学 (ISSN:03882446)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.231-241, 2022-10-20 (Released:2023-10-20)
- 参考文献数
- 25
本研究では65歳以上高齢男性の妻および子どもとの経済的・時間的資源の配分と高齢男性の就業行動との関連を,「家族についての全国調査」の個票データを用いて検証した.線形確率モデルに基づいた多変量解析の結果,学歴・健康状態などの社会人口学的属性を考慮してもなお,夫婦に占める妻の家事時間が高齢男性の就業確率と正の関連を,子どもへの非経済的援助の提供が負の関連をそれぞれ生じさせることが明らかになった.以上の結果からは,高齢者の就業選択には経済状況や就業機会だけでなく家族内の資源配分を考慮する必要があることを示唆した.
1 0 0 0 OA 人工栄養児のエネルギーおよび各栄養素の摂取量
- 著者
- 神野 慎治 中村 吉孝 菅野 貴浩 金子 哲夫 木ノ内 俊
- 出版者
- 日本酪農科学会
- 雑誌
- ミルクサイエンス (ISSN:13430289)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.63-69, 2014 (Released:2014-08-12)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
1/2-6 ヵ月齢の完全人工栄養児のエネルギー,たんぱく質および微量栄養素の摂取量を算出し,評価した。2006-2007年に33,642名の乳児を対象とした発育・哺乳量に関する全国横断調査を実施し,578名の 6 ヵ月齢までの完全人工栄養児の栄養摂取量を評価した。1 日の平均哺乳量は,1/2-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5,および 5-6 ヵ月齢でそれぞれ819, 834, 869, 864, 869,および928 mL であった。調粉 A 哺乳児のエネルギー摂取量(1-2 ヵ月齢で128 kcal/kg/日,5-6 ヵ月齢で84 kcal/kg/日)は,FAO が示している人工栄養児の推定エネルギー必要量と同水準であった。たんぱく質の摂取量およびビオチン・セレン・ヨウ素以外の微量栄養素の摂取量は,日本人の食事摂取基準で示されている目安量を各月齢とも上回っていた。ビタミン A およびビタミン D の摂取量は,日本人の食事摂取基準で示されている耐容上限量を各月齢とも下回っていた。我々は前報で,これらの完全人工栄養児の発育が 6 ヵ月齢まで母乳栄養児と同等であることを確認している。以上のことから,今回評価対象とした完全人工栄養児のエネルギー摂取量は推定エネルギー必要量との比較による評価において過不足のない量に保たれていること,および各栄養素の摂取量については,ビオチン・セレン・ヨウ素以外は,日本人の食事摂取基準に対して過不足がないことが示された。
- 著者
- 坂井 信三
- 出版者
- 日本アフリカ学会
- 雑誌
- アフリカ研究 (ISSN:00654140)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.87, pp.101-102, 2015-05-31 (Released:2016-05-31)
1 0 0 0 OA 畳み込みニューラルネットワークに隠れたテンソルネットワークを探索する
- 著者
- 林 浩平
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.193-201, 2022-12-05 (Released:2023-01-06)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 8
畳み込みニューラルネットワーク(CNN)は画像など特定ドメインのデータの処理に対して高い性能を発揮することが知られている.しかしながら同時に計算能力も必要とするため,CNNの軽量化は深層学習コミュニティにおいて広く行われてきた.本稿ではテンソル分解を使ったCNNの軽量化に焦点を当てる.まずCNNのコンポーネントである畳み込み層の演算が,複数テンソル間の線形演算の表現方法であるテンソルネットワークによって記述できることを示す.次に畳み込み層の軽量化がテンソル分解によって特徴づけられること,またその分解方法もテンソルネットワークによって記述できることを示す.最後に可能な分解を探索することによって,予測精度と時間/空間複雑さのトレードオフを実験的に比較する.その結果,いくつかの非線形分解は既存の分解を凌駕することがわかった.なお,本原稿は著者らの論文1)を和訳しわかりやすく解説したものである.
1 0 0 0 OA シンポジウム記録 : ドメスティック・バイオレンスのメカニズム
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科応用倫理研究教育センター
- 雑誌
- 応用倫理 (ISSN:18830110)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.41-70, 2009-11
- 著者
- 山口 有貴子 栗林 千聡 大野 瑞季 佐藤 寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 日本認知・行動療法学会大会プログラム・抄録集 第44回大会 (ISSN:24333050)
- 巻号頁・発行日
- pp.314-315, 2018-10-26 (Released:2021-05-18)
1 0 0 0 OA フランス革命史研究の現状 : 革命200周年を前にして(海外寄稿)
- 著者
- ヴォヴェル ミシェル 遅塚 忠躬
- 出版者
- 土地制度史学会(現 政治経済学・経済史学会)
- 雑誌
- 土地制度史学 (ISSN:04933567)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.58-68, 1987-10-20 (Released:2017-11-30)
- 著者
- 桑原 歩 黒川 宏之 谷川 享行 井田 茂
- 出版者
- 日本惑星科学会
- 雑誌
- 日本惑星科学会誌遊星人 (ISSN:0918273X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.176-185, 2023-09-25 (Released:2023-10-05)
近年の観測から,多くの原始惑星系円盤においてダストの空間分布にリング・ギャップ構造が見つかっている.ダストのリング・ギャップ構造の惑星による起源として,従来研究の多くは海王星質量以上の惑星 (≳ 15 地球質量) によるガスギャップ形成の影響を議論してきた.本研究は,∼ 1–20 地球質量程度の小質量惑星に着目する.円盤内に埋もれた小質量惑星は,自身の重力によって周囲のガスの流れを乱す.円盤内に存在する小さなダストはガスの流れの影響を強く受ける.本稿では,小質量惑星が駆動するガス流れ場がダストの動力学に及ぼす影響に関する我々の研究について解説し,ガス流れ場によるダストのリング・ギャップ構造形成シナリオを新たに提案する.そして,本稿が提案するシナリオの観測的検証に向けた議論を行い,ガス流れ場が惑星成長率に及ぼす影響と系外惑星の質量-軌道半径分布への示唆についても議論する.
1 0 0 0 OA 造血幹細胞移植における腸内細菌叢の重要性
- 著者
- 荒 隆英 橋本 大吾
- 出版者
- 一般社団法人 日本造血・免疫細胞療法学会
- 雑誌
- 日本造血・免疫細胞療法学会雑誌 (ISSN:2436455X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.4, pp.228-238, 2023 (Released:2023-10-16)
- 参考文献数
- 77
腸管には100兆を超える腸内細菌が共生し,宿主であるヒトと複雑な共生関係を形成している。近年,次世代シーケンサーを用いた解析によって,腸内細菌叢の異常(dysbiosis)が種々の疾患と関連することが報告されている。同種造血幹細胞移植において腸管dysbiosisは,移植片対宿主病(GVHD)の発症やその他の移植成績に影響を与えうる。移植時に使用される抗菌薬の影響に加え,GVHD自体もdysbiosisを誘導しており,さらなるGVHDの悪化に関与するという悪循環が明らかとなってきた。正常な腸内細菌叢を維持する移植方法を開発することで,移植の安全性や有効性がさらに改善していく可能性がある。本稿では,造血幹細胞移植後の,腸内細菌叢の変化が移植成績に及ぼす影響に関する知見をまとめ,造血幹細胞移植における腸内細菌叢の役割と意義および今後の展望について考察する。
- 著者
- Reiji Kojima Ryoji Shinohara Megumi Kushima Sayaka Horiuchi Sanae Otawa Kunio Miyake Hiroshi Yokomichi Yuka Akiyama Tadao Ooka Zentaro Yamagata the Japan Environment and Children's Study Group
- 出版者
- Japanese Society of Allergology
- 雑誌
- Allergology International (ISSN:13238930)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.3, pp.411-417, 2023 (Released:2023-07-07)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
Background: The relationship between the season of birth, allergen sensitization, and allergic rhinitis have been inconsistent, and there are no studies that simultaneously consider vitamin D and allergen exposure. This study aimed to determine the associations between the season of birth, house dust mite (HDM) and Japanese cedar pollen (JCP) sensitization, and allergic rhinitis and pollinosis, while taking vitamin D levels and allergen exposure into account.Methods: This study included 4323 participants in the Sub-Cohort Study of the Japan Environment and Children's Study. A logistic regression model was used to analyze the association between the season of birth and sensitization to JCP or HDM (judged by specific immunoglobulin E) at age 2 and allergic rhinitis or pollinosis at age 3, adjusted for HDM or JCP exposure and vitamin D levels with potential confounders.Results: Participants born in spring or summer were more likely to have pollinosis than were those born in winter (adjusted odds ratio [aOR]: 2.08, 95% confidence interval [CI]: 1.13-3.82 for spring; aOR: 1.89, 95% CI: 1.03-3.47 for summer). Participants born in summer were more likely to have HDM sensitization than were those born in winter (Der p 1, aOR: 1.53, 95% CI: 1.10-2.15; Der f 1, aOR: 1.44, 95% CI: 1.03-2.01). Exposure to JCP and HDM were associated with pollinosis and HDM sensitization, respectively.Conclusions: Spring and summer births were associated with the development of pollinosis, and summer birth was associated with HDM sensitization, even when vitamin D and allergen exposure were considered. Further studies on mechanisms other than vitamin D and allergen exposure are required.
1 0 0 0 OA 今こそ一緒に学術活動を
- 著者
- 花岡 秀明
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.551, 2023-10-15 (Released:2023-10-15)
約十数年間,病院や通所リハビリテーションの職場で臨床を経験した私には,ある出会いによって転機が訪れた.それを好機と捉え,通信制大学から大学院へ進学した.そして現在,大学で教鞭をとっている.大学院時代から興味を持ってこれまで継続して回想法の研究をしているために回想するわけではないが,学術活動との初めての接点は,養成校を卒業して間もなく日本作業療法学会が松山で開催された時期であったと言える.その時のテーマは確か「再び作業療法の核を問う」であったと思う.当時の自分は,臨床1年目の新人として県士会で事例報告をしたのみで,調査や研究活動を本格的に行った経験がなかった.そのため,学会とは作業療法に関する新しい知見を学ぶ集いの場としか思っていなかった.本来,学会とは専門職がその学術活動の成果を発表し,専門職としての成果を内外に発信し,お互いに知的好奇心を刺激しあい,より高めあう場であるのだが,こうした学会の意義や学術活動の重要性に全く気づくことができていなかった.それからしばらくは,これまでと同様に研修会に参加することはあったものの,主体的に学術活動に取り組むことはなく,臨床に役立つ情報とは,先人の著した著書から得るものだという固定観念から抜け出せていなかった.
1 0 0 0 OA 複雑領域のMartin境界と境界Harnack原理
- 著者
- 相川 弘明
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.1-19, 2003-01-24 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 73
- 著者
- Hiroshi Inoue Zhengying Fan Melchor Lasala Robert Tiglao Bartolome Bautista Debbie Rivera Ishmael Narag
- 出版者
- Fuji Technology Press Ltd.
- 雑誌
- Journal of Disaster Research (ISSN:18812473)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.35-42, 2015-02-01 (Released:2019-07-01)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3
We designed a seismic intensity meter and a data collection network for use in the Philippines. The station unit deployed consists of a digital acceleration sensor with 0.1 gal noise and a compact Microsoft Windows PC. The station unit, which is designed to be installed in local government offices, calculates values every 10 seconds for the PEIS (Philippine Earthquake Intensity Scale), and these values are shown on a display and transmitted to the main PHIVOLCS office over the Internet. One hundred units to be deployed throughout the country are now being distributed to offices.