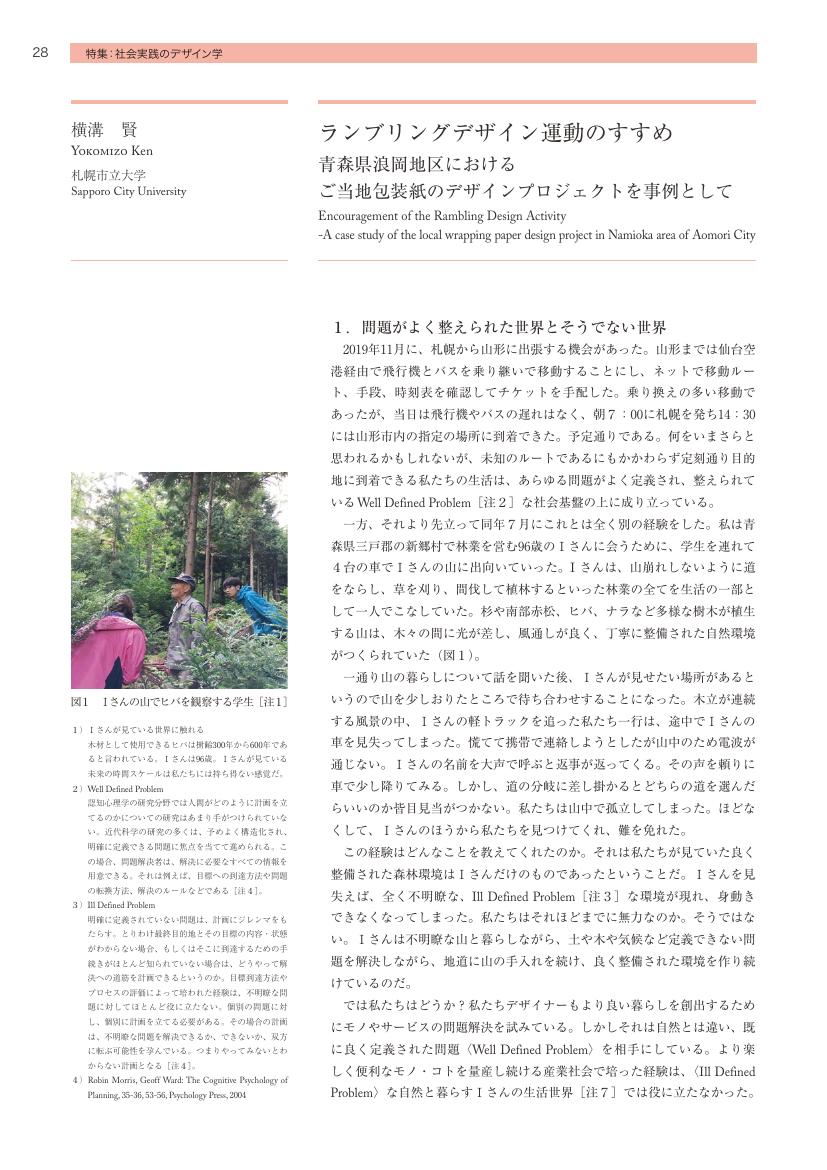1 0 0 0 神楽の中世的展開とその変容
近年、地域の神楽には、都会から多くの見学者が押し寄せるなど、その関心、興味が高まっている。その一方では、担い手たちの高齢化、地域の過疎化によって、休止に追い込まれる神楽も少なくない。また神楽の執行が形式化、イベント化する傾向もみられる。こうした神楽にたいする関心の高まりと地域が抱える問題にたいして、本研究では、これまで重視されていなかった、「中世の神楽」の実態を明らかにすることで、神楽がもつ「宗教性」とともに、その歴史的な展開を示すことで、日本の宗教文化のあらたな面を提示することが可能と考えられる。
1 0 0 0 OA Epidemiology of Developmental Dysplasia of the Hip: Analysis of Japanese National Database
- 著者
- Hiroki Den Junichi Ito Akatsuki Kokaze
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.186-192, 2023-04-05 (Released:2023-04-05)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 2 14
Background: Developmental dysplasia of the hip (DDH) is a cluster of hip development disorders that affects infants. The incidence of DDH-related dislocation (DDH-dislocation) is reportedly 0.1–0.3%; however, the nationwide incidence of DDH-dislocation in Japan has not been previously reported. The primary aim of this study was to report the nationwide incidence of DDH-dislocation in Japan using the National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan (NDB), and to examine its regional variation across Japan.Methods: This was a retrospective birth cohort study using the NDB. Data on patients born between 2011 and 2013 and assigned DDH-dislocation-related disease codes during 2011–2018 were extracted. Among these, patients who underwent treatment for DDH-dislocation between 2011 and 2018 were defined as patients with DDH-dislocation.Results: Across the 2011, 2012, and 2013 birth cohorts, 2,367 patients were diagnosed with DDH-dislocation, yielding the nationwide incidence of 0.076%. Region-specific incidence rates were almost similar across Japan. Secondary analyses revealed that 273 (11.5%) patients were diagnosed at the age of ≥1 year. The effect of birth during the cold months on the incidence of DDH-dislocation was significant (relative risk [RR] = 1.89, 95% confidence interval [CI]: 1.75–2.06). The risk of DDH-dislocation among girls was approximately seven times higher than that among boys.Conclusion: This is the first study to report the nationwide incidence of DDH-dislocation in Japan, which was estimated at 0.076%. The regional variation was trivial and unlikely to be clinically significant. Thus, the incidence rates were approximately equal across all regions in Japan.
1 0 0 0 OA Jリーグ・ディビジョン2に所属するチームにおける 2年間の傷害調査
- 著者
- 齊藤 和快 安斎 健太郎 岡林 務 今城 栄祐 五十子 圭佑 竹内 真太 西田 裕介
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.33-39, 2020 (Released:2020-02-28)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
〔目的〕JリーグのDivision 2に所属するサッカーチームで発生した傷害(外傷と障害)の実態を調査し,その結果を傷害予防の一助とすることを目的とした.〔対象と方法〕対象は2017年から2018年に所属した選手57名で,傷害発生率,受傷状況,傷害のタイプ,受傷部位,重症度を調査した.〔結果〕2シーズンの傷害発生件数は83件であった.練習中の傷害発生率は3.1/1000 phで試合中は10.8/1000 phであった.下肢の傷害が全体の92.8%で,最も多い傷害部位は大腿部であり,筋損傷が多かった.競技復帰までの日数はsevere(29日以上)が最も多かった.〔結語〕サッカー競技において下肢の傷害予防は必須であり,特に選手特性に応じた個別の予防プログラムを確立するだけでなく,競技復帰までの基準を明確化する必要性が示唆された.
1 0 0 0 実習を中心とした共通教科「情報I」の授業実践
- 著者
- 前田 健太朗
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE) (ISSN:21888930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023-CE-171, no.4, pp.1-7, 2023-10-14
令和 7 年度大学入学共通テストで「情報 I」の出題が決まり,令和 4 年度以降に高校へ入学した生徒に対しては大学入学共通テストを受験する可能性があることを踏まえた「情報 I」の指導が必要となっている.東京書籍株式会社が行った調査によると,それまでは授業において実習の割合が多かったが,現在では座学の割合が多いという結果が報告されている.しかし,重要な用語などを暗記させるのではなく実体験を通して知識や思考力を身に付けることが科学的な理解につながると考え,筆者が勤務する高校では従来通り実習を中心に授業を行い,大学入試センターが公表した問題の一部を生徒に取り組ませた.その結果,大学入試センターが公表した問題を解くために必要な知識や思考力などを多くの生徒が身に付いていると推測できた.
1 0 0 0 OA CMOSイメージセンサの現状と将来展望
- 著者
- 大池 祐輔
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.68-74, 2020-02-10 (Released:2020-02-10)
- 参考文献数
- 20
CCDイメージセンサの登場でビデオカメラの小型化に成功し,コンシューマ製品としてディジタルカメラ市場が大きく拓(ひら)けて以来,CMOSイメージセンサにおけるカラム並列AD変換回路や裏面照射構造の開発によって,画質や動画性能の向上が加速した.さらに,3次元積層技術によって,CMOSイメージセンサは小型化・高機能化が進み,現在ではスマートフォンを中心に年間50億個以上が出荷されている.本稿では,CMOSイメージセンサの現在に至る研究開発の経緯と,さらに今後の展望として,センシング技術として検知可能な波長領域を拡張し,さまざまな応用領域への展開を加速させていく技術動向を紹介する.
1 0 0 0 OA 進歩する肺がん治療 分子標的薬と免疫療法
- 著者
- 前門戸 任
- 出版者
- 岩手医学会
- 雑誌
- 岩手医学雑誌 (ISSN:00213284)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.6, pp.203-215, 2019 (Released:2019-03-31)
- 参考文献数
- 4
20年前までの肺がん治療は手術,放射線,化学療法の三本柱であったが,2002年から分子標的薬のゲフィチニブ(イレッサ)が上市され,その中で劇的な効果を発揮する患者が活性型EGFR遺伝子変異を有することが2004年に判明した.その後,ゲフィチニブをはじめとしたEGFR-チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)が複数開発され,肺癌治療の一つの柱となった.EGFR-TKI治療の一つの問題点は,耐性遺伝子変異の出現である.この耐性の原因の50%がEGFR耐性遺伝子変異T790Mであり,この遺伝子変異に対する薬剤オシメルチニブ(タグリッソ)が開発され,耐性克服に繋がっている.このオシメルチニブは,活性型遺伝子変異と耐性遺伝子変異の両方に活性を持っているため,現在は初期治療からオシメルチニブが用いられる様になっている. 進行肺がん治療のもう一つの進歩は,免疫チェックポイント阻害剤である.肺がんの場合,ニボルマブを含め4種類のPD-1/PD-L1阻害剤が使用可能となっている.これらの薬剤はがん免疫に対するバリアを外すことで自己の免疫が腫瘍を攻撃してくれるため,がんが正常細胞と異なるがん抗原を出していることが必要である.一番のがん抗原が遺伝子変異により作り出される変異タンパク質であり,これは喫煙者に多いことが知られている.この免疫チェックポイント阻害剤の出現により進行した肺がんでも治癒する患者が出始めている.進行期肺がん治療も延命ではなく,治癒を目指せる時代に移りつつある.
1 0 0 0 OA スマートフォンを用いた幼児・児童を対象としたオンライン認知検査の開発
- 著者
- 実吉 綾子 稲田 尚子 敷島 千鶴 赤林 英夫
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第21回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.84, 2023 (Released:2023-10-18)
幼児、児童を対象とし、スマートフォンやタブレット等を用いて語彙力、視覚的ワーキングメモリ、推論能力を測定するためのオンライン認知検査を開発した。語彙力は「絵画ごい発達検査」を参考に、4種類のイラストを提示し、音声で提示される言葉に合致するイラストを1つ選択させ、その正答数を測定した。視覚的ワーキングメモリは欠落ドット検出課題(Di Lollo,1977)を参考に、マトリクス内に果物のイラストを配置した二つの画像を1000ミリ秒の刺激間間隔で継時提示し、画像を統合した時に空白となるセルを選択させその正答数を測定した。推論能力は「レーブン色彩マトリクス検査」を参考に、標準図案の欠如部分に合致するものを6つの選択図案の中から1つ選択させその正答数を測定した。全国から無作為抽出された年中児から小学2年生1300人以上から取得したデータについて、成績の分布、課題間の相関、年齢との相関などを検証する。
1 0 0 0 OA 蛋白質のミスフォールデングに起因するアミロイド症の異種動物への伝播性とそのリスク
アミロイドA(AA)アミロイド症は、血清アミロイドAが構造変換して形成されるAAアミロイドの臓器沈着により発症する疾患であり、同種動物および異種動物に伝播する、本研究では、ウシおよびニワトリ由来のAAアミロイドをマウスに接種することにより、その病態や熱に対する抵抗性について解析した。ニワトリおよびウシのAAアミロイドのマウスへの伝播は、マウスに比べて低率であった。マウスでのAAアミロイドの沈着は、時間の経過と共に消失し、再接種により増加した。AAアミロイド症の初期ではIL-6の発現が増加し,その後IL-10が増加した。また、動物由来AAアミロイドは、熱に極めて抵抗性を示すことが明らかとなった。
1 0 0 0 OA 哺乳類の寒冷適応における褐色脂肪組織の役割
- 著者
- 加藤(鈴木) 美羅 岡松 優子
- 出版者
- 低温科学第81巻編集委員会
- 雑誌
- 低温科学 (ISSN:18807593)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, pp.99-108, 2023-03-20
哺乳類には,白色と褐色の2種類の脂肪組織が存在する.白色脂肪組織はエネルギーを中性脂肪として貯蔵する役割を担うのに対し,褐色脂肪組織はミトコンドリアの脱共役タンパク質1(UCP1)により熱を産生する非震え熱産生の部位である.哺乳類は寒冷刺激を受けると交感神経を介して褐色脂肪組織の熱産生を活性化し,体温の低下を防ぐ.寒冷刺激が長期に渡ると褐色脂肪組織が増生するとともに,白色脂肪組織中にUCP1を発現するベージュ脂肪細胞が誘導され(白色脂肪の褐色化),個体レベルの熱産生能が増大して寒冷環境に適応する.本稿では,寒冷適応における脂肪組織の変化とその分子機序を概説するとともに,動物種による褐色脂肪組織の発達や機能の違いについて紹介する.
- 著者
- 平野 泰子 上野 かず子 舟橋 惠子 松原 司
- 出版者
- 日本伝統医療看護連携学会
- 雑誌
- 伝統医療看護連携研究 (ISSN:24355356)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.41-49, 2020-07-31 (Released:2020-09-23)
1 0 0 0 OA 8週間の持久的トレーニングが人の下大静脈横断面積に及ぼす影響
- 著者
- 宮地 元彦 奥津 光晴 中原 英博 斉藤 剛
- 出版者
- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.91-97, 1999-02-01 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2 2
A study was conducted to determine non-invasively the effects of endurance training on the size of the inferior vena cava in humans. Twelve healthy male subjects were assigned to either an exercise-trained group (ET, n=7) or a sedentary control group (S, n=5) . The ET group underwent cycle-endurance training for 8 weeks (80%Vo2max, 40 min/day, 4 days/week) . The S group led normal lives during the 8-week period. Before and after the training period, cross-sectional areas (CSA) of the inferior vena cava and the ascending and abdominal aorta were measured by echography. The CSA of the inferior vena cava after training was significantly larger than that before training in the ET group. There was no significant difference in the S group. These results indicate that the inferior versa cava can be morphologically altered as an adaptive response to endurance training. We consider that this adaptation partly contributes to the improvement in the efficiency of venous return from exercising muscles to the heart. Although the present training also increased the CSA of the aorta, the degree of change was smaller than that seen in the inferior vena cava, implying that the factors of adaptation and adaptability to endurance training in the inferior vena cava differ from those in the aorta.
1 0 0 0 OA 犬の嗅覚はなぜ超高性能なのか
- 著者
- 林 良博
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.1, pp.56-57, 2014-01-10 (Released:2019-09-27)
生まれてから死ぬまで,いつも私たちとともにいる「ニオイ」.知っているようで,わからないことだらけの「ニオイ」.ここでは,身近で不思議な「ニオイ」に関する3つのトピックスについて,エキスパートの先生方に解説していただきます.まず,「犬の鼻はなぜ超高性能なのか」という素朴な疑問について,元日本獣医解剖学会会長であり,現国立科学博物館館長の林良博氏に解説していただきます.次に,誰もが他人事ではない「加齢臭」については,原因物質の発見者であり,加齢臭の名付け親でもある,(株)資生堂リサーチセンターの土師信一郎氏に,その正体と対処法を伝授していただきます.さらに,「香りが人間の心と体に与える影響」について,日本最大の香料メーカーである高砂香料工業(株)の高柳深雪氏に,生理心理的効果の検証実験をご紹介いただきます.[吉川元起・本誌編集委員]
1 0 0 0 OA 4.HOT・補助換気療法
- 著者
- 塩田 智美 高橋 和久
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.6, pp.1618-1623, 2012 (Released:2013-06-10)
- 参考文献数
- 10
COPDによる慢性呼吸不全への標準的治療法である在宅酸素療法は生存率の改善に貢献する.高二酸化炭素血症とその換気障害に伴う臨床症状を有する際は,補助換気療法である非侵襲的陽圧呼吸換気療法(NPPV)の適応である.NPPVは,急性期において気管内挿管への移行や感染症の発生率を有意に低下させ,慢性期において肺胞低換気を改善し,呼吸筋負荷を軽減する.HOT,NPPVの導入には,医師の適切な適応基準の判断が重要である.
1 0 0 0 OA 中国古代における龍と舟と扶桑にみる復活再生観念の研究
太陽を載せるエジプトの三日月の舟の観念は中国にも影響を与えたようだ。太陽が地を潜ったあと復活再生して天空に昇るように、死者もまた舟に乗ってあの世に復活した。中国では仰韶の墓に龍に跨る人の造形がある。龍の原形はワニであり、水平線から天の川を遡り、背に乗る死者の魂を天に運んだのだろう。龍の角は殷・周ではキリンで後に羚羊や鹿の角になる。角をつけなければ空にのぼれないのだろう。戦国から漢代にかけて龍と舟が結びついた。そして被葬者は龍の舟に乗り、あの世に復活再生するという観念が生まれた。これは扶桑の枝に再生する太陽とも重ね合わされた。死者が復活する初期の仙人の原形ともいえる。
1 0 0 0 OA パラオは日本を愛した植民地か? ―日本統治時代を生きた3人のパラオ人女性の語りから―
- 著者
- 熊谷 圭知
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2022年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.86-87, 2022 (Released:2022-11-30)
- 著者
- Yukihiro H. Kobayashi Shizuka Fuse Minoru N. Tamura
- 出版者
- The Japanese Society for Plant Systematics
- 雑誌
- Acta Phytotaxonomica et Geobotanica (ISSN:13467565)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.1-17, 2019-02-28 (Released:2019-03-09)
To evaluate the evolutionary relationships among species of Peperomia subg. Micropiper, a phylogenetic analysis based on the DNA sequences of plastid regions atpB-rbcL, psbK-I, rpL16, rpS16, trnG, trnK (including matK), trnL-L-F, and trnS-G was conducted using 20 species, in addition to four outgroup species. The trnK sequences of 46 species and trnL-L-F sequence of one species were quoted from GenBank and also included in the analysis. The results showed that P. subg. Micropiper includes seven major clades, which are also supported by morphological characteristics. They are recognized as sectionequivalent plant groups, namely Alatoid, Blandoid, Glabelloid, Glaucoid, Japonicoid, Lanceolatoid, and Rotundifolioid. A chromosome analysis of the subgenus yielded nine new counts: 2n = 22 (diploid) for P. alata, P. bicolor, P. diaphanoides, P. flexicaulis, P. hylophila, P. polystachya and P. prosterata, 2n = 44(tetraploid) for P. okinawensis and 2n = 132 (dodecaploid) for P. reticulata. Japonicoid, which occurs outside the Americas, i.e. in Asia, Africa, and the Pacific islands, is tetraploid, decaploid, and dodecaploid (not diploid), while the remaining six plant groups are native to the Americas and diploid (except Glaucoid, which is tetraploid). Further, P. diaphanoides is conspecific with P. glabella. Peperomia boninsimensis from the Ogasawara Islands, Japan, is more closely related to Polynesian species than to other Japanese species. Peperomia okinawensis should be regarded as a variety of P. japonica.
1 0 0 0 OA 2型糖尿病原因遺伝子同定へのアプローチ
- 著者
- 原 一雄 戸辺 一之 赤沼 安夫 門脇 孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床化学会
- 雑誌
- 臨床化学 (ISSN:03705633)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.20-27, 2001-03-31 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 15
- 著者
- 横溝 賢
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究特集号 (ISSN:09196803)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.28-41, 2020-03-31 (Released:2021-04-16)
- 参考文献数
- 6
- 著者
- 本間 洋州 高橋 昌稔 兒玉 直樹 岡田 和将 足立 弘明
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.8, pp.734-739, 2018 (Released:2018-12-01)
- 参考文献数
- 9
反復するげっぷと腹部膨満感を主訴とする27歳男性患者に対して, 各種身体検査にて器質的な消化管疾患を除外し, RomeⅢ基準に基づいて空気嚥下症と診断した. 一般的治療に対して反応性に乏しく, 職場不適応といった心理社会的背景をもつ症例と考えられたので, 生物心理社会的な治療アプローチを試みた. 生物学的観点からは, 空気嚥下の動画や腹部X線写真での腸管ガス像の変化といった生物学的変化を明示して病態理解を促した. 心理的観点からは, 失感情症傾向に対して受容的に関わりながら感情表出を促すとともに, 過剰適応傾向に対して自分の趣味に時間を割くことの重要性を説明して行動変容を促した. 社会的観点からは, 患者の知能特性として処理速度が有意に低いことに基づき職場における環境調整を行った. このような多角的治療アプローチを有機的に組み合わせることで, 難治性消化管症状の改善につながった空気嚥下症症例を経験したので報告する.
1 0 0 0 OA 日本古語と沖縄古語の比較研究 : 熊本・熊襲・八十隈の「くま」を解く
- 著者
- 外間 守善
- 出版者
- 法政大学沖縄文化研究所
- 雑誌
- 沖縄文化研究 = 沖縄文化研究 (ISSN:13494015)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.381-389, 1985-03-15