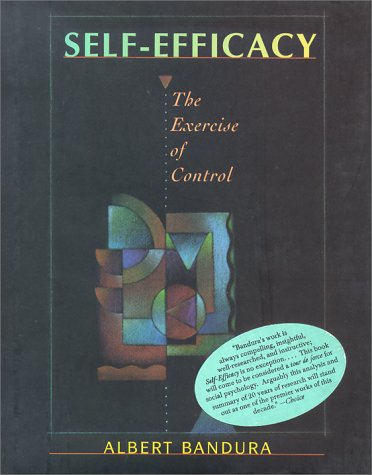1 0 0 0 OA ラインラント共和国運動一九一八-一九一九とその背景
- 著者
- 尾崎 修治
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.10, pp.1756-1776,1838-, 1995-10-20 (Released:2017-11-30)
Die Rheinischen Loslosungsbestrebungen hatten zum Ziel, die rheinische Region von dem PreuBenstaat loszutrennen und so eine selbstandige Republik innerhalb des Deutschen Reiches zu grunden. Diese Bewegungen genossen vor allem in der politischen und verfassungsrechtlichen Ubergangszeit vom November 1918 bis Februar 1919 Unterstutzung durch Politiker und durch Teile der Bevolkerung im Rheinland. In diesem Artikel wird versucht, neben der Betrachtung der Entwicklung dieser Bestrebungen auch die Reaktionen der rheinischen Parteien und der zentralen Regierungen zu analysieren, um die Hintergrunde und die Tragweite der Loslosungsbestrebungen zu klaren. Unter den rheinischen Loslosungsbestrebungen dieser Zeit lassen sich zwei wichtige Richtungen erkennen. Zum einen der "Westdeutsche AusschuB", in dem sich Vertreter aller rheinischen Parteien zusammenschlossen, um eine mogliche Loslosung von PreuBen zu erortern. Diese Bewegung war durch die Furcht vor der Annexion durch Frankreich motiviert, und ihre Mitglieder waren sich daher darin einig, daB man das Konzept einer "westdeutschen Republik" nur dann in die Tat umsetzen durfe, wenn es die einzige Moglichkeit darstelle, um die Annexion durch Frankreich zu vermeiden. Diese Gefahr war jedoch niemals ernst geworden. Zum anderen ist die Richtung der Kolner Zentrumspartei zu nennen. Sie war im Gegensatz zum Westdeutschen AusschuB die aktivere treibende Kraft fur die sofortige Erfullung der Loslosung von PreuBen. Sie kritisierte die Unordnung in Berlin und die Machtlosigkeit der gegenwartigen Regierung und warnte vor der Gefahr der Annexion durch Frankreich. Diese Begrundung fuhrte zur Behauptung, daB das Rheinland sofort zur Selbsthilfe greifen musse. Die ungeduldigen Aktionen der Kolner Zentrumspartei wurden jedoch sowohl von den anderen rheinischen Parteien als auch von der Reichsund preuBischen Staatsregierung heftig kritisiert. Nicht zuletzt wegen dieser Gegenaktion wurde diese Bestrebung zuruckgestellt. Die Handlungen der Kolner Zentrumspartei wurden zwar kritisiert, doch die Motive, die hinter dem Konzept der Selbsttindigkeit von PreuBen steckten, wurden auch von den anderen rheinischen Parteien geteilt. Der Angriff der preuBischen Regierung auf die Rolle der Kirche stieB nicht nur auf den Widerstand des Zentrums, sondern auch auf den des ganzen rechten Lagers. Auch die Abneigung gegen die Revolution war im ganzen rechten und konservativen Lager zu beobachten. AuBerdem spielte das MiBtrauen gegen die zentralen Behorden eine wichtige Rolle. Es wurde dadurch geschurt, daB die Bevolkerung des Rheinlands in Berlin wenig Verstandnis fur ihre Bedurfnisse erkennen konnte und den Eindruck gewann, daB das besetzte Rheinland von der Regierung im Stich gelassen wurde. Daher lag die SchluBfolgerung nahe, daB die Rettung in der Selbsthilfe liege. Die Entstehung der rheinischen Loslosungsbestrebungen laBt sich daher nicht nur von der uberlieferten konfessionellen Besonderheit des katholischen Rheinlandes, sondern auch von den politischen und sozialen Bedingungen nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem der Revolution und der Besatzung, erklaren.
1 0 0 0 OA 「寄せ場」の生産過程における場所の構築と制度的実践
- 著者
- 原口 剛
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.121-143, 2003-04-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 106
- 被引用文献数
- 10 7
Kamagasaki, located in Nishinari Ward, Osaka city, is a daily-hire laborer's concentration area, and is the space where poverty and discrimination converge. Kamagasaki, as a supply ground of the daily-hire labor force (Yoseba), was 'produced' between the 1960s and the early 1970s when policies for Kamagasaki (Airin) were developed in order to cope with a series of protests by the day laborers following the "first riot" in August 1961. This paper employs discourse analysis based on the concept of the construction of place and institutional practice and examines the construction of exclusionary boundaries enclosing daily-hire laborers in the process of the 'production' of Kamagasaki as Yoseba.The mass media began to represent Sanno-cho as a "violence zone" focusing on the prostitution problem after the enforcement of the Anti-Prostitution Law in 1958. In this context, the mass media represented adjoining Kamagasaki as a slum, focusing on the problem of poor families. Nishinari became a place name to signify these areas as a whole. When the "first riot" took place in this context in August 1961, these representations were repeated and the "first riot" was reported as "violence".Moreover, the process of constructing place intensified the confrontation between daily-hire laborers and their neighbors. The neighbors also felt discrimination because these place names and their representations were extensively circulated by the media reports about the "riot" and the resultant policies. Therefore, it became necessary to stop using these symbols, and a new place name, Airin, was created and given to the place that was formerly called Nishinari or Kamagasaki.After 1960, institutional practices followed such discursive transformation. In the first stage (1960-1961), the objective of policy was to improve the living conditions of poor families. In the second stage (1961-1966), it became the objective of policy to distribute families and to institutionalize and to supervise the daily-hire labor market, because it was necessary to cope with the "riot". In the third stage after 1966, when Kamagasaki was specified as the Airin District, comprehensive planning to make Kamagasaki a supply ground of the daily-hire labor force was instituted. At this stage, the state promoted the policies and assessed the existence of day laborers positively from the viewpoint of the necessity to secure a labor force. The Airin General Center and The City Rehabilitation Clinic were embodied as the objective of such policies.Meanwhile, the cheap inns, as the habitation space of the daily-hire laborers, were renewed in the 1960s, in expectation of an inflow of the labor force which was needed to build the site of the International Exposition in 1970. That increased the capacity of the inns and narrowed their size. On the other hand, day payment apartments and squatter huts decreased in number at that time and, therefore, the habitation space for families was reduced. This change of space transformed Kamagasaki into a space exclusively for single daily-hire laborers.The boundaries of the Airin District reflected the representation of Kamagasaki created by discursive formation. It became institutionalized, which reproduced severe exploitation and poverty by being defined as a supply ground of the daily-hire labor force. This spatial boundary construction reproduced itself socially between the daily-hire laborers and their neighbors.
1 0 0 0 OA プロテオミクスの手法によるヒト細胞リボソーム生合成経路とその制御機構の解明
- 著者
- 高橋 信弘 吉川 治孝 泉川 桂一 石川 英明
- 出版者
- 日本プロテオーム学会
- 雑誌
- 日本プロテオーム学会誌 (ISSN:24322776)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.7-15, 2017 (Released:2018-05-21)
- 参考文献数
- 65
光学顕微鏡で認識可能なほど巨大なリボソームは全ての細胞におけるタンパク質合成すなわち生存に必須である.細胞は,その増殖に必要とする総物質量・総エネルギー量の70~80%をこのリボソーム生合成のためだけに消費する.したがって,リボソーム生合成は,細胞増殖だけでなく,細胞の成長・細胞周期の制御,老化・ストレス応答,癌遺伝子や成長因子の作用にも大きく関わっている.しかし,ヒト細胞のリボソーム生合成過程が数百種類のタンパク質とRNAが関わるあまりにも複雑な過程であり,それを解析する手段が近年まで無かった.プロテオミクスの進展に伴い,タンパク質複合体の単離技術,タンパク質の大規模な同定及び定量化の技術が飛躍的に向上した.そして,ヒト細胞におけるリボソーム合成中間体の構成成分の同定とその機能解析が急速に進み,ヒト細胞リボソーム生合成経路とその制御機構が明らかになりつつ有る.本総説では,解明されつつあるヒトのリボソーム生合成過程とその制御機構について我々の知見を含めて概説したい.
- 著者
- Yutaka Tahara Katsuya Obara
- 出版者
- Japan Poultry Science Association
- 雑誌
- The Journal of Poultry Science (ISSN:13467395)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.1-4, 2021 (Released:2021-01-25)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 3 4
Ex ovo culture of avian embryos can be applied not only to embryology but also to various fields of basic research such as embryo manipulation, toxicology, and regenerative medicine. The windowing method, which facilitates various manipulations and observations by opening a hole in one part of the eggshell, and culture systems using surrogate eggshells, are widely used. Despite this, biology lessons in high schools cover shell-less culture systems, which involve the development of avian embryos in artificial vessels, such as rice bowls, without using surrogate eggshells. However, as embryo development stops at its early stages in this method, it is not possible to continuously observe the development of the embryo. This led to attempts to develop an embryo culture method using a complete artificial culture vessel that does not use surrogate eggshells, and Kamihira et al. (1998) succeeded in hatching quail embryos in an artificial culture vessel using polytetrafluoroethylene membranes. In addition, Tahara succeeded in hatching chick embryos in artificial culture vessels that used cling film made of polymethylpentene and reported their detailed methodology (Tahara and Obara, 2014). These technologies are being applied not only to school education but also to various fields of research.
- 著者
- 森上 太郎 大久保 雄 西川 拓也 上林 和磨 乙戸 崇寛 赤坂 清和
- 出版者
- 一般社団法人 日本整形外科スポーツ医学会
- 雑誌
- 日本整形外科スポーツ医学会雑誌 (ISSN:13408577)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.30-36, 2020 (Released:2020-08-21)
- 参考文献数
- 20
目的:異なる頚部および上肢角度にてDraw-inを行なった際の腹部筋活動を超音波画像装置や表面筋電計を用いて評価し,腹部深部筋の賦活化に有効な肢位を検証すること.対象:健常成人男性22人.方法:頚部肢位4通り,上肢肢位3通りを組み合わせて12通りの肢位でDraw-inを行ない,腹筋群の筋形態および筋活動の変化を各肢位で比較した.結果:頚自動屈曲では腹直筋,外腹斜筋の活動量が増加および腹横筋の筋厚が低下し,上肢挙上位では外腹斜筋の活動量が増加した.結論:頚自動屈曲あるいは上肢挙上させることで腹部表層筋の活動量が増加することから,腹横筋の選択的収縮には頚部および上肢を中間位で安静にさせることが有用であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 海洋天然物ポーチミンのC5-C13セグメントの合成研究
- 著者
- 田中 夢乃 藤原 憲秀
- 雑誌
- 日本化学会 第101春季年会 (2021)
- 巻号頁・発行日
- 2021-01-18
- 著者
- 田邉 和彦
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, pp.29-50, 2022-02-21 (Released:2023-06-30)
- 参考文献数
- 23
日本の高等教育においては,性別によって専攻分野が分離している状況が見られる。特にSTEM(Science, Technology, Engineering, and Mathematics)と呼ばれる領域には女子が少なく,このような性別専攻分離の背景として,一部の高校に存在する文理選択制度の影響が指摘されている。すなわち,文理選択に基づいて,男子は理系,女子は文系へと「水路付け」されていくという見方である。 しかし,性別専攻分離には文系-理系の次元とSTEM-ケアの次元が存在しており,後者の分離は主に理系トラックにおいて生じていると考えられる。それゆえ,後者がいかに生じるのかということは,文理選択のジェンダー差とは異なる見地からも検討される必要がある。 日本の高校生を対象としたパネル調査を分析した結果,同じコースに所属していても,女子の方が理系学部における成功確率を低く見積もる傾向が確認され,さらに成功確率を低く見積もっている人の方が,ケア領域を選択しやすい傾向が観察された。また,STEMやケアに関するジェンダー・ステレオタイプは高校生の間に流布しており,それらを内面化している程度は,STEM領域およびケア領域の選択傾向と関連していた。 最後に,本研究で用いた要因をすべて考慮したとき,文系-理系の分離は解消に向かう可能性が示唆されたのに対して,ケア領域における分離は残存する可能性が示された。これは,性別専攻分離において,STEM-ケアの次元へと着目することの重要性をさらに強調するものと捉えられる。
1 0 0 0 OA GUI抽象化規則を用いたモデル生成手法
- 著者
- 水野 佑基 金子 伸幸 中元 秀明 小川 義明 山本 晋一郎 阿草 清滋
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告ソフトウェア工学(SE)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.35(2006-SE-151), pp.121-128, 2006-03-24
本稿では,GUI抽象化規則を用いて実装言語とGUIツールキットに対して柔軟に抽象GUI記述を生成するする手法を提案する.ウィジットと直接操作を表現するGUIプログラミングモデルと,共通GUIツールキットを定義する.抽象GUI記述はGUIプログラミングモデルに従い,共通GUIツールキットを用いて記述される.実装言語やGUIツールキットごとに異なるGUIコードと抽象GUI記述の対応付けをGUI 抽象化規則として定義する.GUI抽象化規則に基づきGUIコードから抽象GUI記述を生成するシステムを提案し,異なる実装言語とGUIツールキットで実装された同一のGUIアプリケーションを同じ抽象GUI記述へと変換できることを確認した.
1 0 0 0 OA 尿道撮影および内視鏡による精丘の形態的研究
- 著者
- 和田 一郎
- 出版者
- 社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.368-388, 1971 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 91
A morphological study of the colliculus seminalis has been made by means of retrograde urethrography in 654 cases, including 107 normal cases, 160 cases of benign prostatic hypertrophy, 22 cases of prostatic cancer, 47 cases of prostatism, 107 cases of seminal vesiculitis and prostatitis, 67 cases of neurogenic bladder, 45 cases of urethral stricture, 36 cases of male sterility, 17 cases of nervous urgency and 46 cases of enuresis. In addition. 80 other different cases have been subjected to a comparative study utilizing radiographic and endoscopic examination.Radiographic pictures of the colliculus seminalis were classified into 7 types (Type I: club-shaped, Type II: tadpole-shaped, Type III: spindle-shaped, Type IV: belt-shaped, Type V: egg-shaped, Type VI: negative contour, Type VII: irregular deformation).In normal cases, Type I was observed in 58%, Type II 24.3%, Type III, IV and V of a few percent. Type VI was observed in about 50% of benign prostatic hypertrophy and prostatic cancer. Type VII was frequently observed in prostatic cancer, in 13.6%, and followed by vesiculitis, prostatitis and neurogenic bladder.The radiographic size of the colliculus seminalis was determined by the transverse diameter. By statistical analysis, above 6mm of the transverse diameter was indicated as an enlargement of the colliculus seminalis. In patients with seminal vesiculitis, prostatitis and male sterility, the transverse diameter showed a significantly larger size than normal cases with a wide distribution. This enlargement would be due to the inflammation or congestion of the colliculus seminalis. Moreover, radiographic pictures of the colliculus seminalis were unable to confirm by endoscopic observation.The first 5 types based on the radiographic study were considered to be formed by the difference in prominence of the colliculus seminalis and urethral crista to the lumen of the urethra.To obtain clear picture of the prostatic urethra, the author prefer to use the contrast medium with a low viscosity, and if high viscous contrast medium was used, diminishing the oblique angle of the body against the X-ray beam would be necessary.
1 0 0 0 OA 途切れなき物語―ジャン・ユスターシュ『ナンバー・ゼロ』と同時代のテレビ作品
- 著者
- 須藤 健太郎
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, pp.27-40,95-96, 2013-05-25 (Released:2023-03-31)
Le present article se consacre à l’étude sur Numéro zéro (1971) de Jean Eustache (1938-81). En soulignant le contexte dans lequel s’inscrit le film, nous essayons de mettre en lumière un aspect curieusement peu commenté jusqu’a present: Jean Eustache l’a réalisé en marge de la télévision. Malgré son apparence naïve, Numéro zéro représente pour le cinéaste une forme de ≪manifeste≫ et de ≪prototype≫ qui joue un rôle déterminant dans l’orientation de son cinema. Cependant, afin de saisir la potentialité du film, il faudrait également traiter de la télévision, en particulier de la série Les Conteurs (1964-73) d’André Voisin et de l’expérimentation de Jean Frapat. Effectivement, souvent plus fréquente à la télévision qu’au cinéma (les emissions de rencontres, d’interviews et de débats), la tentative eustachienne de filmer la parole est enracinée surtout dans la lignée ouverte par André Voisin depuis les anneés soixante avec la collection Les Conteurs. Cinéaste légendaire des années soixante-dix, ≪auteur≫ par excellence du cinéma, Jean Eustache semble développer et radicaliser de telles pratiques apparues au sein de la télévision. Toutefois, son entreprise de toucher à l’≪automatisme≫ du cinéma est incompatible avec la télévision de l’époque.
1 0 0 0 OA 飼料イネサイレージの肉用育成牛および肥育牛への給与技術開発の現状と問題点
- 著者
- 橋元 大介 深川 聡
- 出版者
- 日本暖地畜産学会
- 雑誌
- 日本草地学会九州支部会報 (ISSN:18846408)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.21-25, 2005-01-31 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 6
- 著者
- 田中 琢真
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.10, pp.1189-1193, 2023-10-20 (Released:2023-10-20)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- 酒井 敦 山川 博美 清和 研二
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.207-209, 2013-07-30 (Released:2017-04-28)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 出産の医療化と助産師のジレンマ ――産育コミュニティ形成の可能性をめぐって――
- 著者
- 岡 いくよ
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.3-20, 2020-02-01 (Released:2022-04-07)
- 参考文献数
- 17
本稿の目的は、医療システムに包摂された出産をライフサイクルの中に位置づけなおそうと試みる助産師の実践を通して、妊産婦が当事者として自らと胎児の生命の管理の主体性を取り戻し、現代社会において彼女たちが直面する産前、産後の課題を解決するための新たな可能性に関して検討することにある。 産前から産後にかけての親と子を取り巻く課題は、地球規模の母子の健康問題から妊産婦の心身の不安、出産への恐怖、育児への不安に至るまで、多くの次元に及んでいる。医療機関で異常がないとわかっても、どのように産前から出産後を過ごし親になっていくのか、社会生活から距離を置く時期を過ごす妊産婦の孤独、子のいのちを守ることへの重圧感や言語化できない漠然とした不安を抱える人の増加に対しては十分な議論と対策がなされているとは言い難い。 事例にあげる助産師は、八五歳になる現在まで現役で出産介助を行い、妊娠早期から産後の授乳期に至るまで一貫して妊産婦やその家族を支援してきた。 この助産師の実践を通して明らかになったことは、出産を妊娠から育児までの文脈のなかに位置づけるタイムスパンの導入と、産む女性と医療者という二分法ではなく、それに関与する産育コミュニティという視点を導入し、当事者の生活の必要に応じ生命の管理権を当事者に引き寄せ、いのちの主体として生きることにつながるのではないか、という点にある。人生の通過点として出産が重要な通過儀礼であると捉え、医療施設との共存を果たしながら押し寄せる外部条件に対して対応を積み重ねる過程を蓄積してきたといえる。
1 0 0 0 OA 現代鍛冶技法の保存調査報告 その2 [舟弘]銘・船津祐司の鑿製作
- 著者
- 石社 修一
- 出版者
- 公益財団法人 竹中大工道具館
- 雑誌
- 竹中大工道具館研究紀要 (ISSN:09153685)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.3-68, 2014 (Released:2021-03-20)
- 参考文献数
- 18
本稿は、越後与板の鑿鍛冶である船津祐司の鍛冶技法を記録したものである。船津は[舟弘]銘で全国の一流の大工職人から高い評価を得ている。船津の仕事は、大工道具産地の与板での伝統的な技法と合理的な技法の上に、科 学的な研究を積み重ねたものである。 本調査では、12日間の日常通りの作業工程を記録した。また同じく鍛冶を職業とする調査が詳細に記録を試みた。以下に調査結果の概要をまとめる。 1 鋼は白紙1号の中でも高炭素のものを好んで用いる。その火造りは、コークス炉での鍛接・鍛造の後に、電気炉で4回にわたり段階的に加熱温度を下げながら繰り返す丁寧な鍛錬で、金属組織を微細化している。 2 整形作業は、グラインダーとペーパーバフを効率的にこなす。その一方で、最後はセン床にあぐらをかき、鑢がけを行う鑿鍛冶の昔からの流儀で仕上げる。 3 松炭を用いた焼入れは、暗闇の中で行う。幅寸法の異なる、鑿の1分から1寸4分までの全てが均一に赤められ焼入れされた、まさに熟練の技術といえる。焼戻しは、電気を熱源とした油もどしで行う。 4 3週間の調査期間中に焼入れされた製品は、大入鑿43本・叩鑿など5本・小鉋1枚・平鉋3枚の合計52点であった。 5 鑿鍛冶の枠にとらわれず、鉋など幅広く大工道具を手掛けている。その鍛冶技法は、師である碓氷健吾の科学的データを蓄積した知見に、自らの実証実験からの経験を重ねたものである。本稿は船津65歳という円熟期の記録だが、大工との技術研究から更なる改良をも続けている。
- 著者
- Albert Bandura
- 出版者
- W.H. Freeman
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 OA 東京の県人寮は不要になったのか? 生きられた信濃学寮
- 著者
- 栗林 梓
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2023年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.184, 2023 (Released:2023-04-06)
Ⅰ はじめに 日本では大学進学率が上昇し,同年齢人口の50%以上が大学に進学するようになった.しかし,中には,経済的,心理的負担の問題から離家を伴う大学進学を諦める者もいる.大学進学・学生生活における学生の経済的,心理的負担を軽減し,彼ら/彼女らの教育を支えていくことは,社会的に重要な問題といえる. このような問題へのアプローチの一つとして,教育の地理学的研究においては学生の教育空間を多様な関係性の中で捉え直そうとする動きが強まっている(中澤 2022).栗林(2022b)は,中でも住まいとの関係性に注目し,上述のような問題にアプローチする可能性を示した.住まいの中でも学生の経済的,心理的負担の軽減という意味では学寮に期待が寄せられてきた(例えば, 日下田 2006).しかし,その意味を考察するには,寮生が大学進学・学生生活の中で学寮をどのように位置付け,経験してきたのかを解明しなければならないが,そのような議論は十分になされてこなかった. Ⅱ 研究目的・方法 そこで,本発表では学寮の一形態である県人寮に着目して,大学進学・学生生活においてそれらが経済的,心理的に学生を支える可能性と課題について明らかにすることを目的とする.ここで特に県人寮に着目したいのは,進学先での同郷者の存在が,大学進学・学生生活において心理的な支えとなる可能性が考えられるためである(遠藤 2022).また,県人寮の事例として長野県の県人寮の1つである信濃学寮(男性専用)を取り上げる.信濃学寮は全国学生寮協議会に加盟する41の県人寮の中でも,寮費が最も安価な部類である.また,定員が100名を超える比較的規模の大きい11の県人寮の1つである.さらに,長野県は大学教育の需要の割に大学教育の供給が少ない県のひとつであり,大学進学にあたっては経済的,心理的負担を伴う離家が必要となる場合が多い(栗林 2022a).以上,負担の軽減やデータの入手可能性といった側面から信濃学寮に着目することに一定の意義があると判断した. まず,県人寮の歴史や実態を把握するために,県人寮に関する新聞記事や運営母体の会誌を収集するとともに,信濃学寮の事務局に対して聞き取り調査を行なった.また,大学進学・学生生活における県人寮の可能性と課題について考察するため,寮生に対するアンケート調査を行なった(90部配布,71部回収).アンケート調査では寮を知った契機や入寮理由,寮生活のメリット,デメリットなどを中心に基礎的な事項を把握した.さらに,卒寮前の寮生を対象に,聞き取り調査を行なった(継続中).聞き取り調査では,アンケートの回答に関する質問に加え,大学進学までの人生や学生生活,将来展望などについて寮生に自由に語ってもらい,1時間〜1時間半程度の生活史を聞き取った. Ⅲ 結果および当日の議論 いま東京の県人寮は減少傾向にある.これは,経営難,老朽化,入寮生の減少によるところが大きい.1933年に完成した信濃学寮も入寮者は減少傾向にある.それでは東京の県人寮は役目を終え,不要になったのだろうか? 筆者は,調査結果からも,そのような結論は早計であると主張したい.例えば,信濃学寮の強み(魅力)として,60名が「経済的負担」挙げている一方で,50名が「食事」を,30名が「寮生間交流」を挙げている.寮生の語りからは,これらが学生生活における心理的な支えとなっていることがわかる.もちろんこれらの要素に価値を見出す程度には個人差がある.しかし,やはり寮生の語りからは,寮生が信濃学寮をホームとすることにより学びの継続を可能としている側面があることを理解できる.各地の県人会がその意義を変化させながら存続してきたように(山口2002),信濃学寮も運営母体や理念,役目を変化させながら,長野県出身子弟の大学進学・学生生活を支え続けている. 発表当日は,アンケート調査の結果や学生の語りを拠り所としながら,上述の議論を深めてみたい.また,大学進学おける離家や,彼ら/彼女らを都市空間の中で捉えようとする理論,概念,先行研究での議論が,教育を取り巻く構造の中で,どうにかして東京に進学し学びを継続しようとする学生の存在を周縁化してしまう恐れがあることに若干の批判的検討を加えながら考察を展開したい.
- 著者
- 池田 佳和 十代田 朗 津々見 崇
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 第38回学術研究論文発表会 (ISSN:1348284X)
- 巻号頁・発行日
- pp.146, 2003 (Released:2003-12-11)
本研究では、東京都目黒区の民俗信仰有形物を対象に、その立地、管理形態、状態、活動の実態を明らかにすることで、有形物が都市空間・コミュニティ形成に寄与し、存続していくための示唆を得ることを目的とする。その結果、1.都市化の影響により多くの有形物が寺社、墓地へ移転したこと、2.住民グループによる管理は状態の良い有形物を生むこと、3.管理・活動状態の良い有形物の管理者も高齢化、メンバーの減少といった問題を抱えていること、4.有形物は管理・活動面の実態から4タイプに分類され、「コミュニティ核タイプ」が都市空間、有形物双方にとって有益であること、が明らかになった。