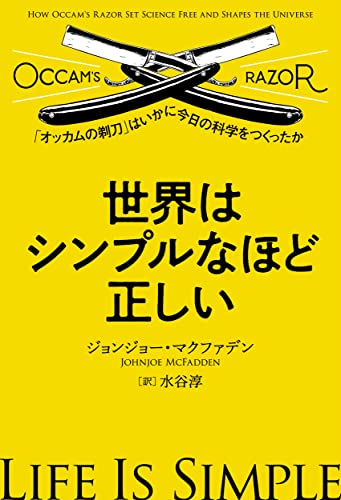1 0 0 0 OA 労働組合機能における契約社員と正社員の比較分析
- 著者
- 梅崎 修 田口 和雄
- 出版者
- 日本労務学会
- 雑誌
- 日本労務学会誌 (ISSN:18813828)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.5-20, 2020-10-01 (Released:2021-01-05)
- 参考文献数
- 18
This study compared the functions of labor unions between a sample of contract workers and full-time salaried workers, based on survey questionnaires. First, it examined the manner in which full-time salaried workers and contract workers were engaged with labor unions. According to the study's findings, labor union membership rate of contract workers was lower than that of full-time salaried workers. In addition, although the full-time salaried workers and contract workers equally voiced their opinions and made requests to their superiors, when the contract workers joined labor unions, they communicated through their union representatives. Second, the effects of labor unions on full-time salaried workers and contract workers were analyzed. Among the full-time salaried workers, the effects of both labor unions and union members on employment security were statistically positive, whereas other effects were statistically non-significant. Meanwhile, the effects of other systems on wages, jobs, and human relations in companies without labor unions were also positive. Third, among the contract workers, the effects of union members on employment security were statistically positive, whereas the effects of labor unions on wages and jobs were statistically positive. In sum, the effects of labor unions on contract workers were greater than those on full-time salaried workers. Despite this finding, there are two possible reasons for the limited number of contract workers to join labor unions. The first reason is that contract workers have a greater incentive to leave a company compared to their full-time salaried counterparts; the second reason is that contract workers are used to consulting their superiors, instead of union representatives.
1 0 0 0 小児気管切開患者の長期経過に関する全国調査
- 著者
- 仙田 里奈 角木 拓也 黒瀬 誠 守本 倫子 高野 賢一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会
- 雑誌
- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.3, pp.228-234, 2023-06-10 (Released:2023-06-10)
- 参考文献数
- 11
小児気管切開術は長期の気道・呼吸管理の管理に必須の治療である。経過の中で多様な合併症を引き起こすため,気管切開術の術式や術後の管理においてさまざまな工夫が求められることも多い。また,気管孔閉鎖においては確立されたプロトコルが存在せず各施設の経験に頼られている部分が大きい。周産期・小児医療の発達により今後も小児気管切開患者の増加が見込まれるため,その管理において指標となるデータおよびプロトコルが必要になると考える。今回われわれは,小児気管切開患者の安全な気道管理および気管孔閉鎖の実現を目的とした全国調査を実施した。対象施設202施設中57施設から回答を得た。過去10年間に小児気管切開術を施行している施設は29施設であり,過去1年間に行われた小児気管切開術症例は全196例であった。術式や術前の経過については各施設直近20症例,長期経過における合併症と気管孔閉鎖については過去10年間の症例で検討した。合併症の発症率が成人と比較して多い可能性や,気管孔閉鎖率が1割程度に留まることが明らかとなった。今後は長期管理や気管孔閉鎖についての共通認識を深めることが望まれる。
1 0 0 0 OA 言語とコミュニケーションの創発に対する複雑系アプローチとはなにか
- 著者
- 橋本 敬
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.9, pp.789-793, 2016-09-10 (Released:2017-04-29)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA コミュニケーションの創発
- 著者
- 有田 隆也
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.39-46, 2009-01-10 (Released:2022-06-29)
- 参考文献数
- 33
- 著者
- 篠原 幸人
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.677-682, 2020 (Released:2020-07-01)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 九州南西部および種子島から採集された標本に基づく稀種Grynaminna tamakii Poore, 2000センニンスナモグリ(新称)(十脚目:アナエビ下目:オオスナモグリ科)の新産地記録
- 著者
- 是枝 伶旺 清水 直人 駒井 智幸
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.9-17, 2023-08-01 (Released:2023-09-06)
- 参考文献数
- 17
The callichirid ghost shrimp Grynaminna tamakii Poore, 2000 was heretofore known only by the original description. The type series consisted of specimens from the south of Shimabara Peninsula, Nagasaki Prefecture, although it was noted that the species occurred also at Hayasaki Inlet on Oyano Island, Kami-Amakusa, Kumamoto Prefecture. In this study, we report on this rarely collected species on the basis of 28 specimens from the western coasts of Kyushu, Kagoshima Bay and Tanega-shima Island, adding new locality records since the original description. Most of the examined specimens were collected from the lower intertidal zone of sand or muddy sand flats at low tide by using yabby pump. The identification was confirmed by genetic analysis using the mitochondrial 16S rRNA gene in comparison with the sequences registered in the GenBank database combined with morphological comparison. The living coloration of the species is first documented. A brief note on biology of the species is also given.
1 0 0 0 OA 桂枝加黄耆湯加味方が奏効した発汗障害の1例
- 著者
- 丸山 泰貴 及川 哲郎 花輪 壽彦 小田口 浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.66-70, 2021 (Released:2022-05-17)
- 参考文献数
- 14
多汗症の治療は漢方治療を含め複数の選択肢が存在しているが,無汗症は一部の疾患でステロイドの有効性が指摘されているのみであり,現代医学的に治療が難しくかつ漢方治療の臨床報告は少ない。発汗低下を訴える症例に対して桂枝加黄耆湯加防風白朮が有効であった症例を経験したために報告する。 症例は69歳女性。発汗の減少,体温感覚の異常を主訴に201X 年6月に当研究所を受診。近医で種々の漢方薬を処方されたが改善がなかった。発汗できず皮下に水気がたまっている病態と考えて桂枝加黄耆湯加味方を処方したところ,汗がでるようになり体温感覚の異常は改善した。大塚敬節は『金匱要略講話』で,「黄耆というものは,まるきり反対の水が多い場合と水がない場合の二つの場合に効くということが云えます。」と述べている。本症例のような発汗障害では漢方治療,特に黄耆を含む処方は有効であると考えられる。
- 著者
- 風間 効
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.202-203, 2009-08-12 (Released:2018-04-20)
1 0 0 0 OA 平沼騏一郎内閣運動と海軍 : 一九三〇年代における政治的統合の模索と統帥権の強化
- 著者
- 手嶋 泰伸
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.9, pp.1507-1538, 2013-09-20 (Released:2017-12-01)
This article focuses on the relationship between the campaign to set up a cabinet under the premiership of Hiranuma Kiichiro and the Japanese Navy during the years of the Saito Makoto cabinet (25 May 1932-8 July 1934), in order to place this campaign within the context of the strengthening of the military supreme command system from the 1930's onward and clarify the influence of Hiranuma's plan upon the Navy, and the influence the resulting changes in the Navy exerted upon the campaign. In order to overcome a divided structure of governance, in particular control over military authorities, Hiranuma's campaign won faction leaders over to its side and utilized the authority of the imperial family. Therefore, Hiranuma's plan for controlling the military authorities did call for institutional reorganization, but rather depended on personal connections. Hiranuma made Fushiminomiya Hiroyasu chief of the Naval General Staff (NGS) with the cooperation of the Kantai (Fleet) Faction led by Admiral Kato Hiroharu, going as far as to reorganize the system by extending the authority of the NGS. However, the Kantai Faction lost its unifying position in the Navy when it was criticized for politicizing the NGS and politically utilizing the imperial family. Since Hiranuma's plan to control the military authorities involved winning over the leaders of the various factions, the fall of the Kantai Faction from power brought about the failure Hiranuma to act as the unifier of the divided governance system. Therefore, the campaign to form a Hiranuma Cabinet and the reinforcement of the supreme command in the navy developed under interrelationship of mutual influence. The collapse of the campaign after the Kantai Faction's attempt to utilize the authority of the imperial family resulted in the loss of its unifying position in the Navy means no less than the failure of Hiranuma's efforts to overcome the divided structure of governance by means of personal connections. Only the extension of NGS power-in other words, the strengthened independence of Supreme Command-remained after Kato's retreat and the collapse of the Hiranuma campaign.
1 0 0 0 OA 虚血性大腸炎の臨床的検討
- 著者
- 丸山 茂雄 八島 一夫 池淵 雄一郎 澤田 慎太郎 磯本 一
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, no.7, pp.643-654, 2018-07-10 (Released:2018-07-10)
- 参考文献数
- 27
虚血性大腸炎(IC)60例の臨床的検討を行った.43例(72%)が5月から10月の時期に発症していた.58例(97%)が夜8時から翌朝の7時までの夕食後比較的短時間に発症し,52例(87%)は,就寝時間帯であった.若年者では,基礎疾患の関与がなく,便秘などの腸管側因子のみが誘因となり軽症例が多いが,高齢者では,基礎疾患に起因する血管側因子に,腸管側因子が複合して重症化する傾向が見られた.内視鏡点数と各臨床因子との相関関係を求めた結果,重症化の要因として,白血球数,年齢,消化器症状が有意な独立因子であった.多くの症例が,比較的湿度の高い時期に発症していることより,湿度も発症の一因になりうると推測した.
- 著者
- 森高 正博
- 出版者
- 日本フードシステム学会
- 雑誌
- フードシステム研究 (ISSN:13410296)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.98-112, 2016 (Released:2016-12-22)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
Facing the decreasing trend of domestic food demand and also the share of domestic products, market penetration to abroad is one of the urgent strategies for domestic agricultural producers. This study firstly examines the possibilities of it with checking the fruits of EPA and TPP negotiations briefly. Secondly, it is revealed that branding and promotion strategies become structural problems among individual producing area brands and All- Japan brand as an umbrella brand. To show the criteria of selecting a branding strategy, strategic choice of advertise and promotion by umbrella brand and each area brands in sequential game is examined. And the criteria is explained mainly by the signs of advertise and promotion's spillover effect and strategic effect.
1 0 0 0 OA ワーケーションの周辺環境および意向との関係に関する探索的研究
- 著者
- 小原 満春
- 出版者
- 一般社団法人 日本観光研究学会
- 雑誌
- 観光研究 (ISSN:13420208)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.65-74, 2021 (Released:2022-06-04)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 2
ワーケーションとは、仕事(work)と休暇(vacation)を組み合わせた造語であり、旅先で仕事とレジャーの両方を行う働き方の一つである。コロナ禍によってテレワークが推奨され注目を浴びるようになった。本研究では、ワーケーション意向者に対して理想とする周辺環境に関する調査を行い、ワーケーション意向との関係について、探索的に研究を行った。その結果、ワーケーション意向者が理想とする周辺環境は自然、歴史、娯楽、寒冷、温暖、芸術、利便性、ワーケーション環境となり、理想とする周辺環境から、ワーケーション意向者は環境無関心、デジタルノマド、日本的ワーケーターの3 つの特徴を持った層に分類された。
1 0 0 0 OA <書評論文>「ひきこもり」当事者の自己呈示とアイデンティティをめぐる問題
- 著者
- 澤田 有希 Yuki Sawada
- 雑誌
- KG社会学批評 = KG Sociological Review (ISSN:21870683)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.1-13, 2021-03-24
1 0 0 0 OA 生徒の学力に影響を与える因子に関する研究 ―マラウイ共和国・MALPを事例として―
- 著者
- 富田 真紀 牟田 博光
- 出版者
- 国際開発学会
- 雑誌
- 国際開発研究 (ISSN:13423045)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.67-80, 2010-06-15 (Released:2019-12-25)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
Heyneman & Loxley (1983) discussed the importance of school related factors on children's learning achievements, which they emphasized were more important than children's family background. Later, Baker et al. (2002) reported that school related factors were no longer the most important factors to determine children's learning achievements now that the economy in developing countries had greatly grown up and the educational investment had been increased by the governments and donors. It is true that the economic growth is acknowledged in many developing countries. However, there are still some countries with the least economic development, similar to the economic situation of countries targeted in Heyneman & Loxley study. What about these countries? Are school related factors still important in such countries compared to children's family background?Data of a pilot survey for Monitoring Achievement in Lower Primary (MALP) in Malawi were analyzed to examine variables explaining fourth grade pupils' learning achievements in mathematics and Chichewa (national language) and the relationship among the variables and pupils' learning achievements. Structural equation modeling (SEM) was applied for the analysis. School variable consisted of teacher variable, head teacher variables and school resource variables was the strongest variable explaining children's learning achievements. The influence of pupils' family background on their learning achievements was insignificant in mathematics. It was significant in Chichewa, however the effect size on pupils' learning achievements was not as large as that of school variable. Thus, this research confirmed the findings of Heyneman & Loxley in Malawi after 25 years of their study, despite the change in the world economic level.
- 著者
- 中川 美恵 栢下 淳
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養士会
- 雑誌
- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.9, pp.465-471, 2023 (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 28
介護老人保健施設入所者を対象に、身体計測、食事形態、握力や歩行能力、口腔機能調査を行い、常食摂取と関連のある要素について検討を行った。本研究は横断研究である。対象者73人の属性は平均年齢82.3±8.2歳、男性20人(27.4%)、女性53人(72.6%)であった。常食群と形態調整食群の2群に分けて検討を行った結果、常食群でBMI、上腕三頭筋皮下脂肪厚(Triceps Skinfold Thickness;TSF)、握力が高く(p<0.05)、咀嚼能力が良好な者の割合が高かった(p<0.05)。歩行能力別の比較では、歩行能力が低下するにつれて、常食摂取者の割合が低下し、形態調整食摂取者の割合が増加した。常食摂取と関連のある要素として、咀嚼力や舌圧値等の口腔機能と握力および歩行能力が示唆された。また、ADLの低下に伴い、食事形態も軟食化傾向となり、栄養状態の低下につながることから、多職種と連携して、口腔機能や筋力の維持に努める必要がある。さらに、形態調整食群ではエネルギー摂取量やたんぱく質量を確保する必要性が示唆された。
1 0 0 0 OA 高齢者の嚥下障害の病態生理とその応用
- 著者
- 杉山 庸一郎 金子 真美 平野 滋
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報 (ISSN:24365793)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.8, pp.983-989, 2023-08-20 (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 34
高齢者の嚥下障害に対する嚥下診療では, 加齢による嚥下機能低下に加え, 高齢者に好発する疾患とそれに伴う嚥下障害を理解し, 嚥下メカニズムに沿って治療を行うことが原則となる. 高齢者では咽頭・喉頭感覚低下, 食道入口部の抵抗増加, 咽頭残留などの加齢に伴う嚥下機能低下に, 脳血管障害や神経筋疾患など原疾患による嚥下機能低下が加わると, 嚥下障害を来す. 原疾患の治療に加えて, 嚥下障害に対して病態に即して対応することが必要となる. そのためには嚥下機能評価が重要となる. 摂食・嚥下は5段階に分類されるが, そのうち咽頭期嚥下障害は誤嚥のリスクに関与するため, 適切に評価し対応する必要がある. 咽頭期嚥下障害に対する嚥下機能評価は嚥下惹起性と咽頭クリアランスの評価に大別される. 嚥下機能評価により病態生理を解析し, 原理原則に沿って嚥下リハビリテーション治療や嚥下機能改善手術などの適応, 治療方針を決定することが重要である.
- 著者
- ジョンジョー・マクファデン著 水谷淳訳
- 出版者
- 光文社
- 巻号頁・発行日
- 2023
1 0 0 0 OA 選択による選好の変化と抑うつ傾向との関連
- 著者
- 宮城 円 中尾 敬 宮谷 真人
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第13回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.142, 2015 (Released:2015-10-21)
同程度に好ましいアイテムから好ましい方を選択すると,自らが選んだものの選好は増加し,選ばなかったものの選好は減少する。この現象は“選択による選好の変化”と呼ばれ,近年自らが選択したものの選択率を上げるといった強化学習によって説明できることが示唆されている。抑うつ傾向者では,ギャンブル課題等において強化学習による価値の学習が生じにくくなることが知られているが,選択による選好の変化について抑うつ傾向との関連は明らかになっていない。本研究は選択による選好の変化と抑うつ傾向との関連についてBlind choice paradigmを用いて検討した。その結果,抑うつ傾向者ほど選ばなかったものの選好が減少しにくいことが明らかとなった。一方,選んだものの選好の変化と抑うつ傾向との関連はみられなかった。このことから,選んだものと選ばなかったものの選好の変化は異なる過程により生じている可能性が示唆された。
1 0 0 0 青年の感情障害の診断横断的治療のための統一プロトコル日本版の開発
1 0 0 0 OA 画像選好判断における親近性と新奇性の影響 ―魅力度と画像特性の関与
- 著者
- 満田 隆 阪口 遼平
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第13回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.131, 2015 (Released:2015-10-21)
画像選好判断において,対象が顔の場合は見慣れた画像を好む傾向(親近性選好)が生じ,対象が風景の場合は初めて見る画像を好む傾向(新奇性選好)が生じる。本研究はその詳細を明らかにするために,まず,魅力が大変高いモデル,魅力の高い高校生,低い高校生の顔写真を用いた選好判断課題を行い,顔の魅力度と親近性選好の関係を調べた。その結果,魅力の低い顔は高い顔と比べて親近性選好が強く生じた。また,魅力が大変高い顔では親近性選好と新奇性選好のいずれも生じなかった。つぎに,ティアラ,リビング,家具,住宅街,銃,食器,星雲,抽象画を用いた選好判断課題を行った。その結果,リビングと星雲で新奇性選好が生じ,その他のカテゴリでは偏りは生じなかった。また魅力度と新奇性選好に相関があった。以上の結果より,魅力の低い顔画像では親近性選好,顔以外の画像では画像全体が変化する魅力の高い画像で新奇性選好が表れることが示された。