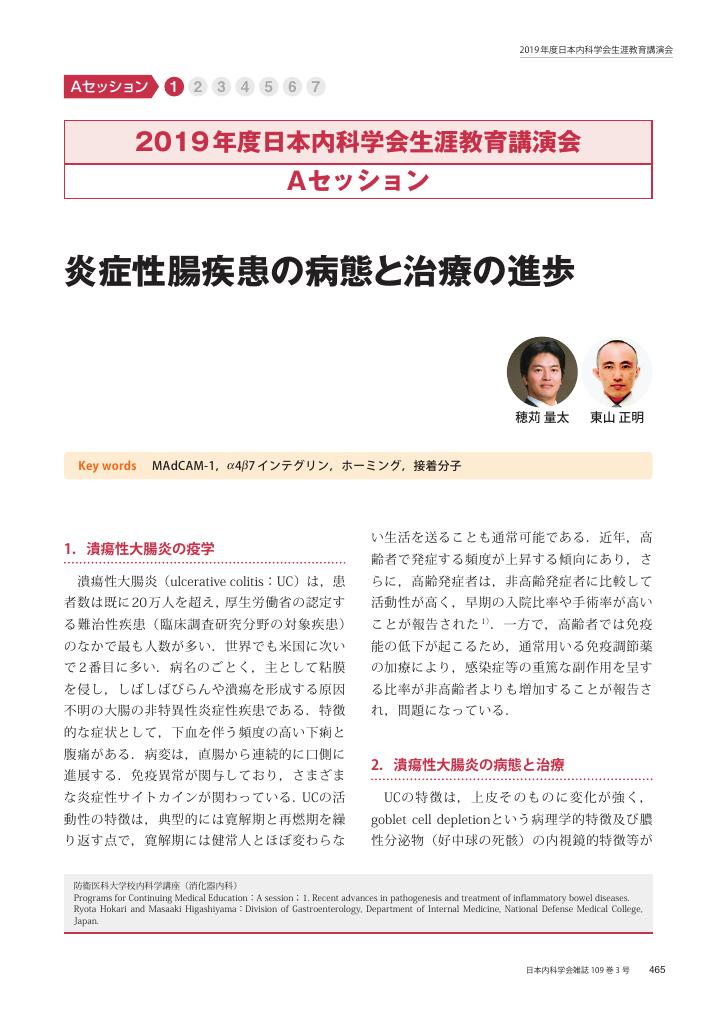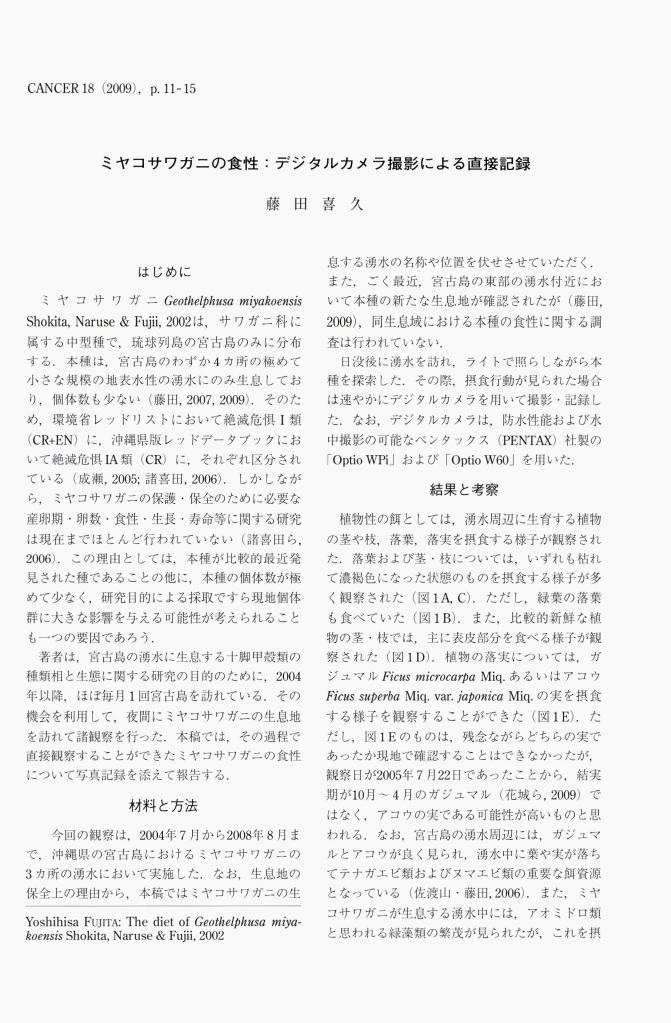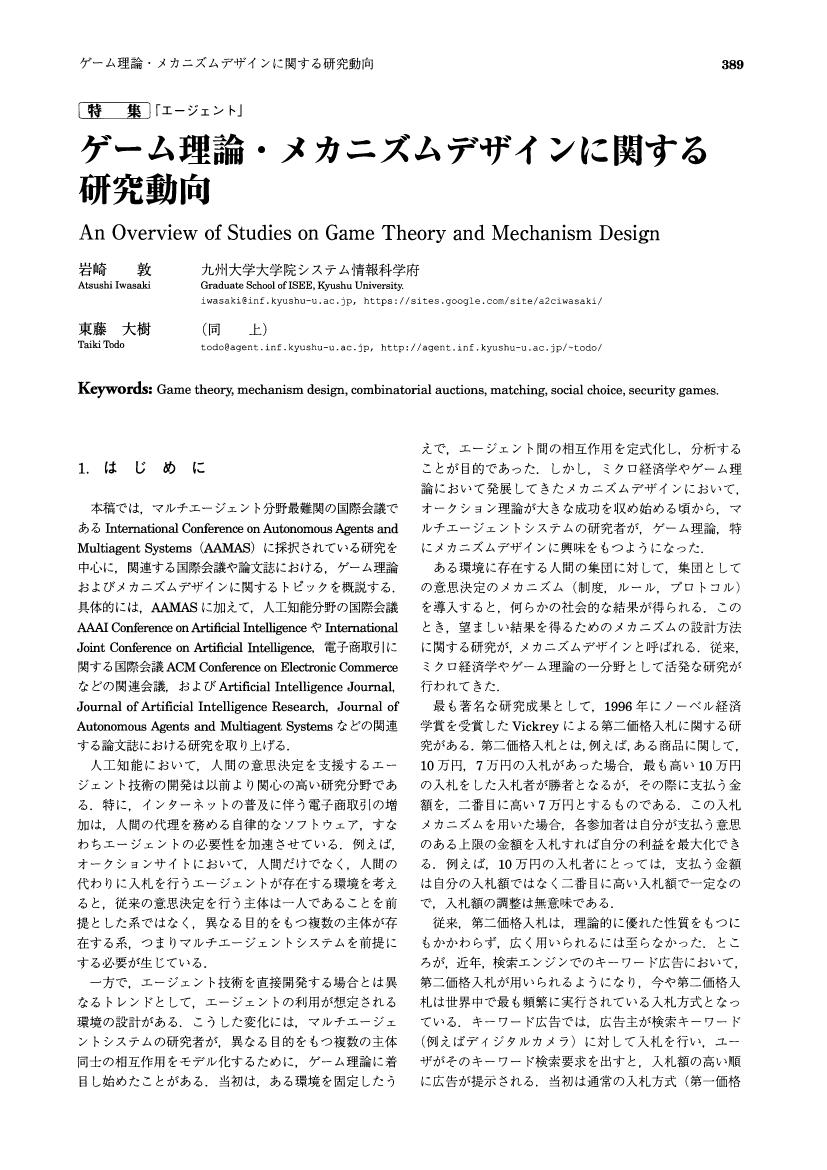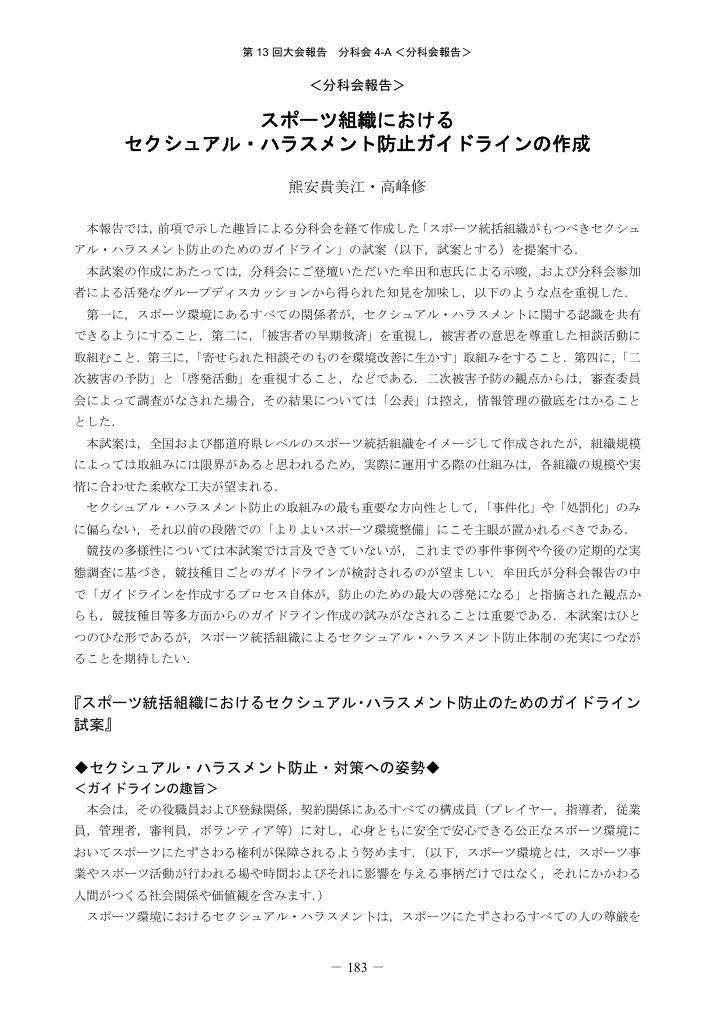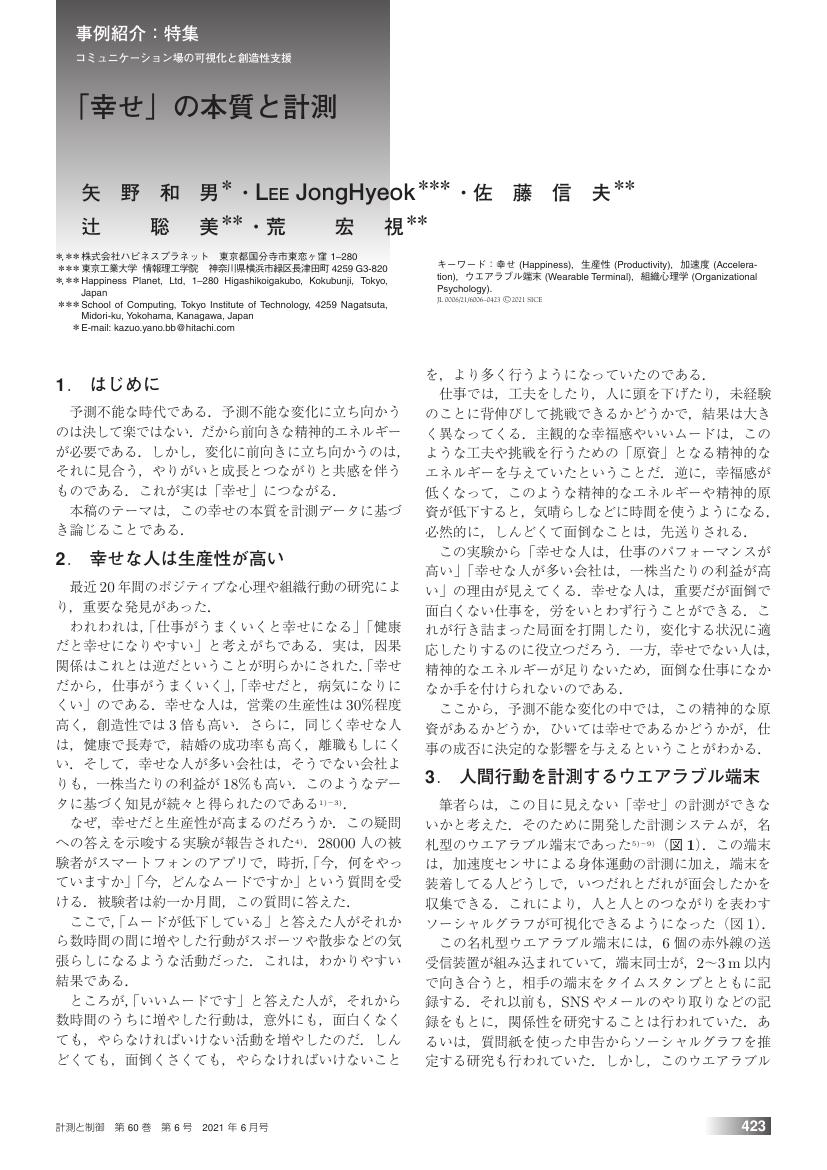1 0 0 0 OA 健常成人における足底圧中心軌跡の特徴
- 著者
- 堀本 ゆかり 丸山 仁司
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.687-691, 2010 (Released:2010-11-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 8 4
〔目的〕本研究の目的は青年期の立脚期歩行パターンを測定し,足圧中心軌跡は踵から第5中足骨付近まで進みその後第1趾に向かうという先行研究と比較し,その特徴を調査することである。〔対象と方法〕対象は調査・計測に関して同意の得られた専門学校学生17例とし,身体計測と10 m歩行計測に加え,立脚期の足底圧中心軌跡の特徴について検討した。〔結果と結語〕その結果,足底圧中心軌跡が中央型となる傾向があり,荷重応答期から立脚終期に時間要因が延長する傾向を認めた。特に初期接地以降の距骨下関節の動きおよび足長,足幅(横アーチ機能),中足趾節関節背屈角度等が足底圧中心軌跡を調整する機能として寄与することが示唆された。
1 0 0 0 OA 1.炎症性腸疾患の病態と治療の進歩
- 著者
- 穂苅 量太 東山 正明
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.3, pp.465-470, 2020-03-10 (Released:2021-03-10)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA ミヤコサワガニの食性 : デジタルカメラ撮影による直接記録
- 著者
- 藤田 喜久
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.11-15, 2009-05-01 (Released:2017-07-05)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA 歩行運動方程式の導出過程─Simplest walking model─
- 著者
- 倉山 太一 小宮 全
- 出版者
- Japanese Society of Assistive Technologies in Physical Therapy
- 雑誌
- 支援工学理学療法学会誌 (ISSN:24366951)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.64-72, 2022-03-25 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 8
本稿はGarcia等が提唱した歩行についての数理モデル「Simplest walking model」の解説である。主な読者として、物理や数学に興味のある理学療法士・作業療法士を想定した。また普段数学になじみのない方でも、その導出の概略を理解できるように、式変換などについて逐次説明するよう心掛けた。解説中に出てくる数学的用語や解法を元に、適宜、専門書などを参照頂ければ、最短経路で歩行の数理を理解できる内容となっているので、意欲のある方は、ぜひ紙とペンを使って式の導出を追って頂きたい。もし、大学の物理に興味のある高校生や、教員がお読み下さったならば、本稿を解析力学の簡単な例題としてお使い頂ければ幸いである。
1 0 0 0 OA 味噌の抗酸化機能について
- 著者
- 山口 直彦
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.10, pp.721-725, 1992-10-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 5 2
味噌の食品機能が注目されるようになったが, 幾つかの機能の中で, 抗酸化機能は特に重要である。酸化されやすいビタミンAも味噌の中では極めて安定している。最近, 味噌を摂取した場合に, 肝臓内での酸化防止効果が認められた。味噌の抗酸化機能を支えるものとして, 褐変色素のメラノイジン及びペプチドの果す役割について解説していただいた。
1 0 0 0 OA フタホシコオロギ
1 0 0 0 OA ゲーム理論・メカニズムデザインに関する研究動向(<特集>エージェント)
- 著者
- 岩崎 敦 東藤 大樹
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.389-396, 2013-05-01 (Released:2020-09-29)
1 0 0 0 OA 8・12天津爆発事故における中国ネット世論の形成―新浪微博の分析を通じて
- 著者
- 陳 雅賽
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.19-37, 2016 (Released:2016-11-22)
- 参考文献数
- 20
本稿は,8・12天津爆発事故(以下8・12事故と略す)について,事故直後どのような世論がどのように形成されたのかを明らかにするために,新浪微博の公式的なニュース配信アカウント「頭条新聞」の8・12事故に関する書き込みの主題,フレーム,情報源,イメージ,批判対象及び人気書き込みに付随する人気コメントの内容を分析した。その結果明らかとなったのは以下の五点である,第一に,,新浪微博の公式的なニュース配信アカウント「頭条新聞」の書き込みは主に情報伝達機能や公権力の監視機能を果たした。それらの書き込みに対するコメントは主に公権力の監視機能を果たした。第二に,爆発原因に関する政府や瑞海集団への責任追及,消防士の不当な救援措置の指摘,死亡者数や事故による環境汚染データへの不信,メディアの報道への不満,市民による事故発生後の詐欺行為など不適切な行為への批判との世論が形成されている。第三に,政府の事故対応がどのような世論が形成されるかに大きな影響を与えている。第四に,事故経験者から発信された事故経緯など第一次情報がまとめられ,ニュースの形態で配信されたオリジナル情報が過半数であったことは,フォロワーが少ない一般ユーザーによる事故経緯などの情報が速く,広く拡散できるルートが新たに生まれたといえよう。第五に,形成されたネット世論が,死亡者数や事故による環境汚染データを隠蔽しようとした天津市政府の情報開示や中央政府が事故原因を追究したことに後押しする力になった。
- 著者
- 三上 紗季 山口 泰彦 斎藤 未來
- 出版者
- 一般社団法人 日本全身咬合学会
- 雑誌
- 日本全身咬合学会雑誌 (ISSN:13442007)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.16-23, 2020-11-30 (Released:2020-12-30)
- 参考文献数
- 17
側方運動を抑制する急傾斜の犬歯誘導を付与したオクルーザルアプライアンス(側方抑制スプリント)で治療した重度の睡眠時ブラキシズム(SB)症例について報告した.患者は,20 歳代女性で,歯ぎしり音を主訴に本院を受診した.SB の臨床診断のもと,当初一般的なスタビリゼーションアプライアンスを用いて治療を行ったが,睡眠時筋電図検査によるSB 評価では全くSB 波形数の低減が認められなかった.それに対し,側方抑制スプリントを適用したところ,大幅なSB 波形数の低減を示した.側方抑制スプリントの長期間の使用によっても,歯や歯周組織,顎関節,筋などに異常は認められず,良好な経過が得られた.本症例の治療経験から,オクルーザルアプライアンスの形態によってはSB が大幅に低減する場合があり得ることが示された.ただし,側方抑制スプリントがすべてのSB 症例に奏効する保証は今のところなく,睡眠時筋電図検査を用いた客観的な効果判定を行い,使用継続の適否の判断を的確に行うとともに,歯や歯周組織などに関する慎重な定期観察が必要と考えられた.
- 著者
- 土手 貴裕 近堂 徹 前田 香織 高野 知佐
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.650-658, 2023-03-15
ITシステムの新たなアーキテクチャとしてマイクロサービスが注目されている.マイクロサービスではシステムが持つ各機能を独立したコンポーネントとして分割し,それらをAPIで疎結合させることで,機能単位での頻繁な改修が容易となり,顧客の要望への迅速な対応が可能となる.しかし,マイクロサービスの導入によりシステム構成が複雑化し,システム状態を把握するための時系列データであるメトリック数も増大するため,障害原因であるコンポーネント(障害原因箇所)の特定が困難となる.本論文では,マイクロサービスにはコンポーネント間でAPI呼び出しによる依存関係があることに着目し,メトリックの定常時からの変化量にコンポーネント間の依存関係を組み合わせることで障害原因箇所を特定する手法を提案する.また,提案手法による障害原因箇所特定システムを開発し,ECサイトを模したマイクロサービスのベンチマークを用いた実験を行った.特定精度および特定に要する時間について評価を行い,これらの結果から提案手法の有効性を示す.
1 0 0 0 OA MRJの空力設計技術(基調講演,市民公開行事)
- 著者
- 藤田 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 流体工学部門講演会講演論文集 2009 (ISSN:24242896)
- 巻号頁・発行日
- pp.3, 2009-11-06 (Released:2017-06-19)
R&D study of Mitsubishi Regional Jet (MRJ) has been conducted since 2003, under the auspice from NEDO. In this study, various fundamental research items for aircraft development including advanced aerodynamics, noise study and multidisciplinary design optimization (MDO) have applied to the design of MRJ. In these R&D activities, state-of-the-art technology developments have been pursued by strong university-government-industry cooperation. This report presents application of CFD and MDO technologies to MRJ design as an example of R&D activities.
1 0 0 0 OA リーディング指導における読みの深化と批判的思考力伸長のための「評価型発問」の活用
- 著者
- 峯島 道夫
- 出版者
- 日本リメディアル教育学会
- 雑誌
- リメディアル教育研究 (ISSN:18810470)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.125-140, 2011-09-30 (Released:2017-06-01)
This paper aims to demonstrate, as a case study using qualitative analysis, the effectiveness of evaluative, as opposed to fact-finding, questions for deepening learners' reading comprehension and developing their critical thinking skills in the instruction of reading. A short narrative was used as the text for 68 low-proficiency EFL college students. They were posed a series of evaluative questions as they read it, such as those that required them to predict the next turn of the plot, detect incongruities in the text, draw elaborative inferences about implicit causality, retell the story from a different view point, and reflect on and evaluate the main characters and the theme of the story. Analyses of learners' responses to these questions reveal degrees of their deepened understanding of the text and use of critical thinking skills.
1 0 0 0 OA ヒマワリ栽培による土壌の放射性セシウムに対するファイトレメディエーション効果の検証
1 0 0 0 OA 自殺企図にてインスリンデグルデクとインスリンリスプロを大量に皮下注射した1型糖尿病の1例
- 著者
- 飯嶋 寿江 加瀬 正人 相良 匡昭 加藤 嘉奈子 清水 昌紀 西田 舞 友常 孝則 田中 精一 青木 千枝 城島 輝雄 鈴木 國弘 黒田 久元 麻生 好正
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.9, pp.707-714, 2015-09-30 (Released:2015-09-30)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
症例は70歳,女性.1型糖尿病,うつ病にて加療中,自殺企図のためインスリンデグルデク300単位,インスリンリスプロ300単位を皮下注射し,注射3時間後に意識障害で家族に発見され,当院救急外来に搬送となり,入院となる.簡易血糖測定では,測定感度以下(30 mg/dl未満)を示し,血清インスリン値は2972.1 μU/mlと極めて高値を示した.直ちに,ブドウ糖の静脈投与を開始した.低血糖は大量注射30時間後を最後に認めなかったものの,大量投与36時間後の血清インスリン値は1327.0 μU/mlと依然として高く,低血糖の予防のため,第6病日まで経静脈的ブドウ糖投与を継続した.本症例の経過より,インスリンデグルデクの大量投与症例では他のインスリン製剤以上に長時間にわたる注意深い観察と対応が必要であると思われた.インスリンデグルデク大量投与による遷延性低血糖の症例は極めて稀であり,文献的考察を加え報告する.
1 0 0 0 OA スポーツ組織における セクシュアル・ハラスメント防止ガイドラインの作成
- 著者
- 熊安 貴美江 高峰 修
- 出版者
- 日本スポーツとジェンダー学会
- 雑誌
- スポーツとジェンダー研究 (ISSN:13482157)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.183-192, 2015 (Released:2017-04-14)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 『獨逸學協會雑誌』掲載論説の変遷に関する考察
- 著者
- 兼田 信一郎
- 出版者
- 獨協学園資料センター
- 雑誌
- 獨協学園資料センター研究年報 (ISSN:18837646)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.22-50, 2010-03-15
1 0 0 0 OA FacebookにおけるCOVID-19関連偽情報の国内主要アクターとその特徴
- 著者
- 澁谷 遊野
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.13-30, 2022-03-31 (Released:2022-04-20)
- 参考文献数
- 52
本稿では,研究蓄積の浅い国内のFacebook上でのCOVID-19関連偽情報等の生成・流通の概要を把握することを目的に,2020年1月から2021年5月までの18ヶ月分の日本語でのCOVID-19関連Facebook投稿を記述的に分析した。その結果,国内外の関連研究で示されている他プラットフォームや他言語による偽情報の傾向と同じように,(1)少数アカウントが偽情報生成・流通で中心的な役割を担っていて, 主流メディアのアカウントと同等もしくはそれ以上の反応数を獲得するなど,COVID-19関連の投稿としては最大級の反応を得ていることが明らかになった。また,(2)偽情報の発信の動機としては,金銭的なインセンティブやイデオロギーに基づいた動機によると考えられるものがあること,(3)YouTube等の外部情報源を利用しながら偽情報を流通させていること,(4)偽情報の中心的なアカウントの周りには緩やかに繋がった大小様々なグループやアカウントが存在し協調的に偽情報の生成・流通に寄与していることが示唆された。偽情報等を展開するアカウントの中には,プラットフォーム事業者によるアカウントや投稿の削除への対策として複数アカウントを運営したり,既存コミュニティとつながることで,偽情報等を受容しやすい潜在偽情報消費者を獲得しているケースもみられた。こうしたことから,COVID-19関連偽情報を巡ってはプラットフォーム事業者等の単一的なアカウントの削除等の対応のみによる効果は限られる可能性が示唆される。今後は国内の偽情報等の生成流通は,プラットフォーム事業者側の問題やリテラシーを中心とした個々の問題としてのみ捉えるだけではなく,社会経済システムの症状としても捉え直し,その背景にある社会・経済・政治な背景や偽情報需要の増減のメカニズムやエコシステムの解明を行うなど,多面的なアプローチも必要と考えられる。
1 0 0 0 OA YouTubeアプリにおけるアーキテクチャ利用のパターンと視聴動画ジャンルの関係
- 著者
- 佐々木 裕一 北村 智 山下 玲子
- 出版者
- 一般社団法人 社会情報学会
- 雑誌
- 社会情報学 (ISSN:21872775)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.17-33, 2021-09-30 (Released:2021-11-10)
- 参考文献数
- 25
本稿では,YouTubeスマートフォンアプリ利用者のアーキテクチャ利用のパターンを明らかにした上で,アーキテクチャ利用のパターンとアプリでの視聴時間および動画ジャンルの視聴頻度の関係を明らかにした。この課題に取り組んだのは,(1)インターネットサービスにおいてアーキテクチャが利用者行動に対して影響力を持ちうる,(2)個人同定と情報推奨というアーキテクチャが接触情報内容の幅を狭めるのか広げるのかという議論には決着がついていない,(3)高選択メディアにおいては視聴動画ジャンルの分断が生じうる,という主として3つの先行研究との関わりゆえである。動画サービス利用が進む中で,動画ジャンルレベルでの利用者行動についての実証研究が乏しいという背景もある。YouTubeアプリを過去7日間に1回以上利用した15〜49歳までの男女604名に対するWebアンケート調査を分析した結果,アーキテクチャ利用のパターンとして5つが確認され,この中でアプリ視聴時間の長いものは「全アーキテクチャ高頻度」群と「登録チャンネル」群であった。また動画推奨アルゴリズムが機能するアーキテクチャを高い頻度で利用する者が高頻度で視聴する動画ジャンルは「音楽」であること,登録チャンネルに重きを置いて利用する者において「スポーツ・芸能・現場映像」,「学び・社会情報」,「エンタメ」の3ジャンルの視聴頻度が平均的な利用者よりも低いことを示した。論文の最後では,この結果について議論した。
1 0 0 0 OA 「幸せ」の本質と計測
- 著者
- 矢野 和男 JongHyeok LEE 佐藤 信夫 辻 聡美 荒 宏視
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測と制御 (ISSN:04534662)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.423-428, 2021-06-10 (Released:2021-06-18)
- 参考文献数
- 18