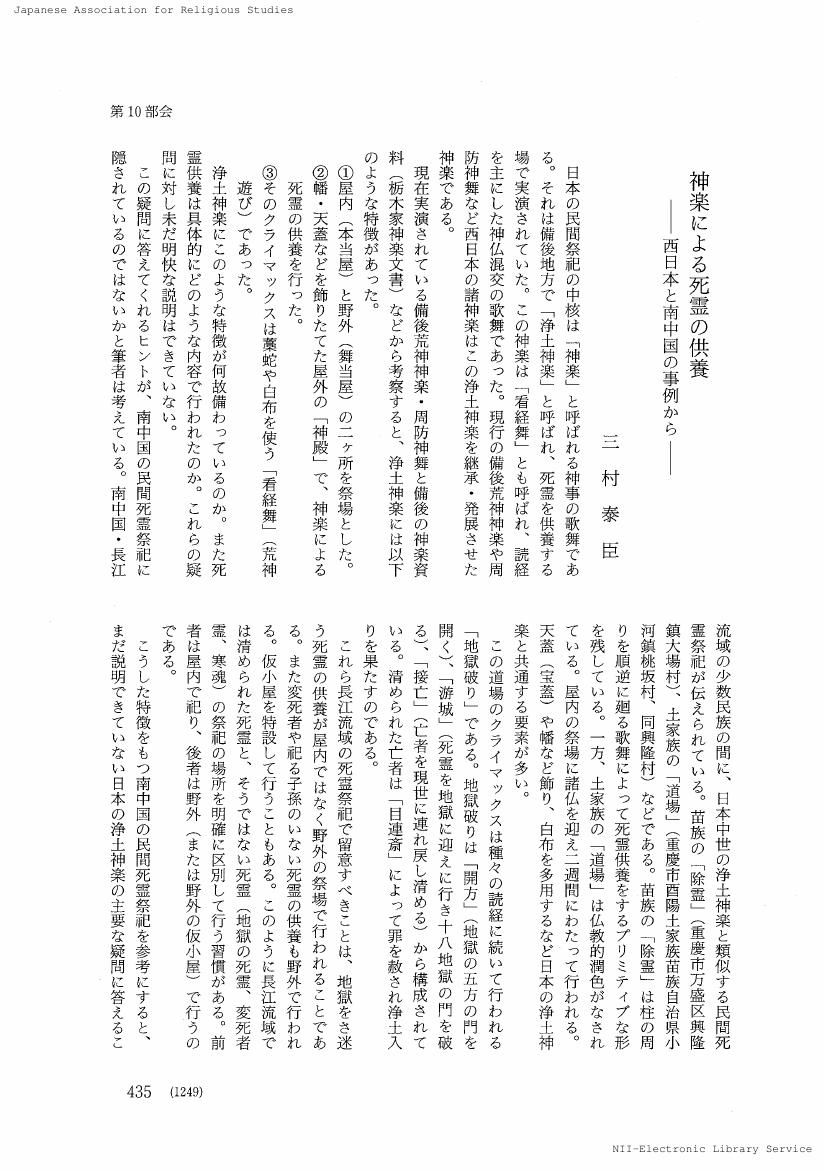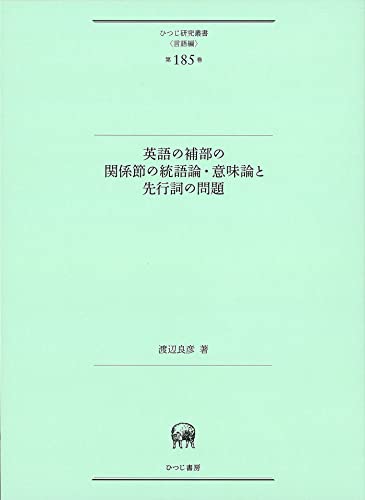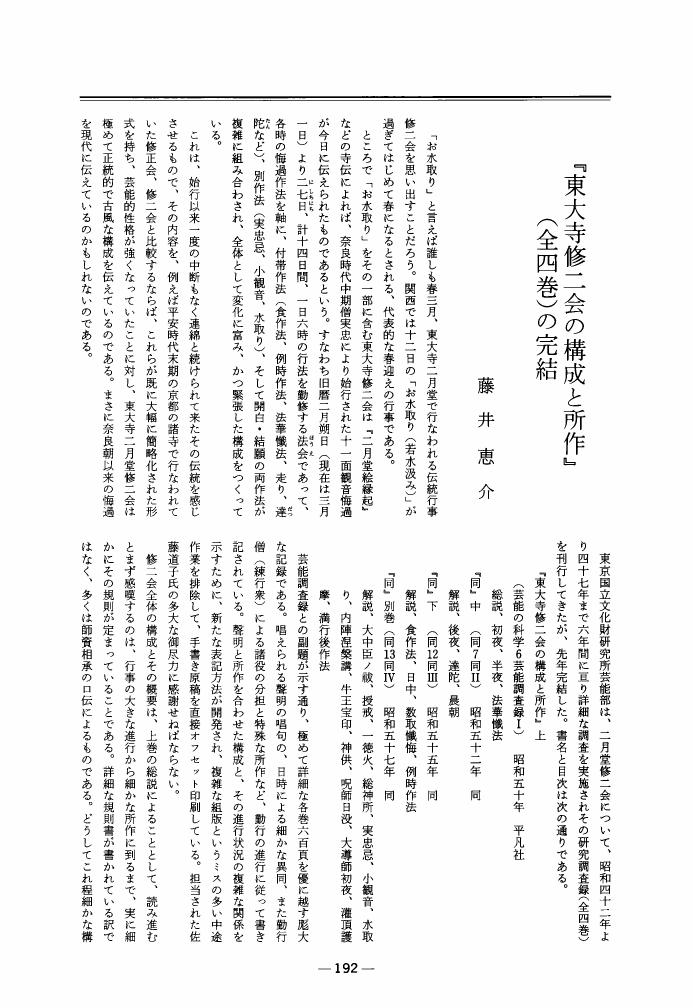1 0 0 0 OA 羽毛布団の耐洗濯性について
- 著者
- 川口 美智子
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.12, pp.526-531, 1986-12-25 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 占いの諸類型とその特質 : 現代日本の占い本を通して
- 著者
- 鈴木 健太郎
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.5-28, 1995-06-10 (Released:2017-07-18)
今日の日本における占い人気の高さは世人の広く認めるところであるが、現代日本の占いを扱った学術的な研究は未だほとんどなされていないのが現状である。そこで、本稿ではまず、今後行われるべき占い研究の足がかりを得るために、複雑多様な様相を見せている諸々の占いを幾つかの類型に分類・整理することを試みる。類型化にあたっては、個々の占いを成り立たせている究極的根拠(占考原理)の種別と、運勢を好転させるための対処策の性格に見られる差異を分類の指標とし、研究の資料には一般読者向けに書かれた「占い本」を用いることにする。さらに後半では、分類作業によって得られた3つの類型のそれぞれが持つ固有の特質を、人間の運勢を左右する基因が人間とどのような関係にあると捉えられているかといった把捉様式のレベルに求めていく。そこには日本の宗教的な思惟・意識の構造を解明するための糸口の一つが潜んでいると考えられるからである。
- 著者
- 三村 泰臣
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.4, pp.1249-1250, 2007-03-30 (Released:2017-07-14)
1 0 0 0 OA 良好なFontan循環に発症した気管支喘息合併鋳型気管支炎の一例
- 著者
- 大塚 雅和 桑原 義典 本村 秀樹
- 雑誌
- 第55回日本小児循環器学会総会・学術集会
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-26
【背景】鋳型気管支炎(Plastic Bronchitis:PB)は気管支内で形成された樹枝状の鋳型をした粘液栓(cast)により気道閉塞から呼吸不全を呈し時に致死的となることがある疾患である。Fontan術後だけでなく気管支喘息や呼吸器感染などでも発症する。今回、Fontan手術11年後でマイコプラズマ感染による気管支喘息発作時にPBを発症した症例を経験したので報告する。【症例】PA-IVSの14歳女児。生後2ヶ月でBTシャント、BAS、9ヶ月にGlenn手術、1歳にcoil塞栓(内胸動脈collateral)、3歳にTCPC(EC)を施行。3歳、4歳で肺炎のため入院既往あり。外来で気管支喘息もフォロー中(FP吸入、LTRA内服)。3年前の心臓カテーテル検査ではCVP9mmHgで良好なFontan循環だった。数日前より咳嗽があり、入院当日に39℃まで発熱し呼吸苦、胸痛も出現した。SpO2 84%(通常95%)でサルブタモール吸入したが改善せず、胸部レントゲンで肺炎があり入院した。酸素投与、抗菌薬AZM投与、PSL全身投与を開始した。入院翌日から断続的にcastの喀出がありPBと診断。Castの喀出で呼吸状態は徐々に改善した。入院11日目より呼吸理学療法を開始すると、さらにcastが排出され、入院16日目に退院した。なお、マイコプラズマ抗体PA法320倍であった。【考察・結語】PBは気管支疾患に多い1型(inflammatory type)と先天性心疾患術後に多い2型(acellular type)に分類される。高い静脈圧、慢性的な高リンパ圧などがFontan術後cast形成に関係する因子とされるが、今回の症例は良好なFontan循環であった。本症例のcastは1型、2型の要素を含んでおり、良好なFontan循環でも気管支喘息発作、肺炎によりPBを発症する可能性がある。PBに確立された治療はないが、呼吸理学療法を積極的に導入し排痰を促すことも重要であると考えられた。
1 0 0 0 OA 理想の自己を追い求める「私恥」概念に関する基礎的研究
- 著者
- 上野 素直 藤本 学 Sunao Ueno
- 出版者
- 久留米大学大学院心理学研究科
- 雑誌
- 久留米大学心理学研究 = Kurume University psychological research (ISSN:13481029)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.7-15, 2015-03-31
恥は大きく3つに大別することができる。本研究はその中で,理想自己と現実自己の乗離によって 生じる感情である“私恥”に注目する。研究1では,はじめに,人がどのような点に目を向けて自己評価しているのかを,自由記述アンケートによって同定した。つぎに,得られた結果を元に,自己評価傾向を4つの側面から測定する尺度を開発した。この尺度は各側面のポジティブとネガティブの両極を測定することから,両価的自己評価尺度(ASES)と命名された。さいごに,ASESの内的整合性と基準関連妥当性を確認した。続いて私恥を感じている人の特性および状態を明らかにするために, 研究2でははじめ,ASESを用いて自己評価の4側面について理想と現実を調査し,それらの差を求めた。つぎに,これらの高低の組み合わせから,調査参加者を4群に分類した。群間比較の結果, 私恥が高い者は自尊感情,自己効力感,自己愛が低い一方で,自己嫌悪感が高いことが明らかになった。
1 0 0 0 OA 40mm卓球ボールの打撃特性
- 著者
- 湯 海鵬 溝口 正人 豊島 進太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.155-162, 2002-03-10 (Released:2017-09-27)
The ball size for table tennis was recently changed in the revision made to the international rules by the ITTF (International Table Tennis Federation), and the new ball has been in use for official games since October 2000. The new rules stipulate that the diameter of the ball should now be 40mm (an increase from 38mm), and the weight of the ball should be 2.7g (an increase from 2.5g). It is estimated that the style of play and game tactics will change to some extent as a result of the new ball. The purpose of this study was to compare the hitting properties of the new ball in comparison with the old one, in order to clarify the influence on play. The reduction ratio of ball speed from the shooting point to the receiving point was calculated using a ball-shooting machine and a speed measurement system. Initial velocities and ball spins were calculated using a golf-swing robot and a high-speed video camera system. The robot hit the balls with different hitting speeds and hitting angles by a racket attached to the robot arm. An all-around wooden bat pasted with a reverse-soft rubber sheet was used. Average rally times for the two kinds of ball were measured, and three kinds of basic shot-drive, chop and serve-were made in the rallies by skilled payers. The following results were obtained: (1) The initial speed of the new ball was 1-2% less, and the ball spin was 5-20% less than for the old ball. (2) No difference in the speed reduction ratio was observed between the new ball and the old one. (3) The average rally time for the new ball was 2-4% longer than for the old ball for drive and chop shots.
- 出版者
- 克誠堂出版
- 巻号頁・発行日
- 1952
1 0 0 0 英語の補部の関係節の統語論・意味論と先行詞の問題
1 0 0 0 OA 小笠原諸島の弟島と父島で採集されたマダニ類
- 著者
- 山内 健生 岸本 年郎 角坂 照貴 杉浦 真治 岡部 貴美子 藤田 博己
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第60回日本衛生動物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.39, 2008 (Released:2008-07-01)
東京都の小笠原諸島は特異な生物相を有する海洋島で,コウモリ類を除く陸生哺乳類は本来分布していなかった.しかし,19世紀以降,様々な陸生哺乳類が同諸島へ持ち込まれ,現在では,こうした哺乳類が外来種問題を引き起こしている.これまで同諸島のマダニ相に関する知見は皆無であったため,われわれは2007年4~10月に同諸島父島列島の弟島(5.2 km2)と父島(23.8km2)においてマダニ相調査を実施した. 弟島では,外来生物対策として駆除されたノヤギとノブタの体表を調査して寄生個体を採集したほか,フランネルを用いて植生上から未寄生個体を採集した.父島では,外来生物対策として駆除されたクマネズミの体表を調査して寄生個体を採集した. 採集されたマダニ類は,Boophilus microplus(弟島),Haemaphysalis flava(弟島),Haemaphysalis hystricis(弟島),Ixodes granulatus(弟島,父島)の3属4種であった.なお,採集法別の内訳は以下のとおりであった. 植生上:H. flava(NL),H. hystricis(NL),I. granulatus(L) ノヤギより:B. microplus(♂♀),H. flava(N),H. hystricis(♂♀N) ノブタより:H. hystricis(♂♀) クマネズミより:I. granulatus(♀) (L:幼虫,N:若虫)
1 0 0 0 OA 岩手県干厩地方における石英閃緑岩の風化について
- 著者
- 中川 善兵衛 小坂 丈予 浦部 和順 山田 久夫
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- 岩石鉱物鉱床学会誌 (ISSN:00214825)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.9, pp.283-290, 1972-09-05 (Released:2008-08-07)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 2
The weathering process of quartz-diorite mass in Senmaya district, Iwate Prefecture, was studied from chemical and mineralogical angles. Especially the relationship between the compositional changes of the weathered rocks and their main constituent minerals was detailedly discussed. The non-altered quartz-diorite is chiefly composed of quartz, plagioclase, hornblende and biotite, together with few apatite and magnetite. As weathering proceeds, most of the primary minerals, plaigoclase, hornblende and biotite, are gradually eliminated and secondary minerals such as vermiculite, kaolin etc. appear in stead. The change in chemical composition of the weathered rocks is almost controlled by the solubility of each chemical component under netural conditions. Among the primary minerals, biotite is most sensitive for weathering, the sequence of the alteration being as follows:biotite-hydrobiotite-vermiculite-kaolin mineral In the earlier stage of the weathering, the alteration process of biotite was mostly affected by its original crystallographic structure, so that the change in chemical composition of that mineral differs markedly from that of the host rock. But it is also controlled by the solubility of each chemical component, thus the compositional change becomes to be similar to that of the host rock in the later stage.
1 0 0 0 OA 医薬品の投与に関連する避妊の必要性の考え方(男性)
- 著者
- 根来 宏光 西山 博之
- 出版者
- 一般社団法人 レギュラトリーサイエンス学会
- 雑誌
- レギュラトリーサイエンス学会誌 (ISSN:21857113)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.55-62, 2022 (Released:2022-01-31)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
医薬品の避妊に関するガイダンスが,AMED(日本医療研究開発機構)研究班「生殖能を有する者に対する医薬品の適正使用に関する情報提供のあり方の研究」でとりまとめられた.このガイダンスでは,生殖可能な患者への医薬品使用による胚・胎児発生に対する潜在的リスクを最小限に抑えるため,投薬治療中および最終投薬後に避妊が推奨される条件および避妊期間に係る基本的な考え方を示している.本稿では,ガイダンスの男性避妊について概説するとともに,「生殖補助医療(配偶子の凍結など)」,「放射性医薬品,再生医療等製品,ワクチン等の生殖発生毒性リスク」,「感染性を有する可能性のある医薬品における性行為に伴うパートナーへの感染リスク」の3点について補足したい.
1 0 0 0 OA クサヤ・パラドックスの研究 ―八丈島の疫学調査より―
- 著者
- 福生 吉裕 吉村 玲子 高橋 修和 大森 暢久 押見 恵子
- 出版者
- 日本未病システム学会
- 雑誌
- 日本未病システム学会雑誌 (ISSN:13475541)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.21-24, 2001-08-15 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 OA ディジタル音響機器接続事始め
- 著者
- 由雄 淳一
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.10, pp.589-595, 2020-10-01 (Released:2021-03-10)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA 尻滑り力の力学シミュレーションを用いたシートスウィング機構の設計
- 著者
- 松岡 由幸 庭野 敦也 森田 敦
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.5, pp.65-72, 2001-01-31 (Released:2017-07-21)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
座り心地の向上を目的として, 尻滑り力を防止するシートスウィング機構が注目されている.しかしながら, この尻滑り力防止に関する力学的解明がなされていないため, シートスウィング機構は的確な設計が行われておらず, その機能が十分に発揮されていない.そこで, 本研究では, 人体モデルを用いて力学シミュレーションを行い, 導出した設計解をもとにシートスウィング機構の設計を行うことを目的とする.本研究では, まず, 人間工学的, 解剖学的な見地から人体モデルを構築した.つぎに, そのモデルを用いて尻滑り力の推定式を立て, 尻滑り力の力学シミュレーションを実行することで最適なバックアングルとクッションアングルの関係を導出した.その結果, バックアングルが45°付近でクッションアングルが最大値をとる尻滑り防止曲線を導出した.さらに, 導出した尻滑り防止曲線をもとに, シートスウィング機構に対する各構成要素の仕様を決定し, 同機構の設計を行った.
1 0 0 0 OA L-グルタミン酸ナトリウムの生体 殊に肝機能に及ぼす影響について
- 著者
- 勝部 正治 Masaharu KATSUBE
- 雑誌
- 論集
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.1-20図巻頭2枚, 1973-08
1 0 0 0 内臓播種性水痘・帯状疱疹ウイルス感染症の1例
- 著者
- 大川 智子 山口 由衣 石田 修一 堀田 亜紗 藤田 浩之 相原 道子
- 出版者
- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会
- 雑誌
- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.212-218, 2013 (Released:2013-10-05)
- 参考文献数
- 39
44歳,男性。両側精巣腫瘍,S状結腸癌の既往がある。上腹部に激痛が生じた翌日に,顔面,体幹部に発赤を伴う小丘疹と小水疱,および口腔内水疱が出現した。Tzanck 試験は陽性であった。激烈な腹痛を伴うことから,内臓播種性水痘・帯状疱疹ウイルス (VZV) 感染症を疑い,アシクロビル (acyclovir; ACV) 750mg/day 開始したが,症状の改善は乏しく,肝機能の悪化,DICを合併した。第4病日より ACV 1,500mg/day に増量,Intravenous immunoglobulin (IVIG) 5,000mg/day(5日間)を追加し,症状は次第に改善した。経過中,血中 VZV-DNA 量が髙値であり,内臓播種性 VZV 感染症と診断した。本疾患は急速に進行し,ときに致死的である。水痘に腹部症状を伴う場合,本疾患を疑い,早期に大量の ACV や IVIG による治療をおこなうことが重要と考えた。(皮膚の科学,12: 212-218, 2013)
1 0 0 0 OA 高齢者総合的機能評価ガイドライン
- 著者
- 鳥羽 研二
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.177-180, 2005-03-25 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 13 16
1 0 0 0 OA 船舶の垂直脱磁について模型試験の組立
- 著者
- 廣田 惠
- 雑誌
- 2018年第79回応用物理学会秋季学術講演会
- 巻号頁・発行日
- 2018-07-10
1 0 0 0 OA 『東大寺修二会の構成と所作』(全四巻)の完結
- 著者
- 藤井 恵介
- 出版者
- 建築史学会
- 雑誌
- 建築史学 (ISSN:02892839)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.192-193, 1984 (Released:2018-10-09)
- 著者
- 松本 暢子 平野 あずさ
- 雑誌
- 大妻女子大学紀要. 社会情報系, 社会情報学研究 = Otsuma journal of social information studies
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.157-168, 2005
現在,多くの自治体では安全で利用しやすい公共トイレの設置が進められているが,実際の公共トイレは「危ない,臭い,汚い,暗い」といわれ,女性や子どもをはじめとして高齢者,障害者などは利用しにくい。そこで,本稿は,東京都新宿区の公共トイレのなかから公衆トイレ(26ヶ所)に注目し,現地観察調査を実施し,高齢社会において求められる多様なニーズに応える公共トイレのあり方を考察している。現地観察調査は,出入り口や施設構造,バリアフリーなどの施設条件,人目があるか,死角がないかなどの周辺立地環境,洗面台やブース内の設備・備品状況,清掃が行き届いているか,臭気はないかなど衛生状態についての把握を行っている。調査結果では,(1)すべてのトイレが不潔で危険なわけではなく,一部の問題のあるトイレでの管理方法を見直す必要があること,(2)不潔で危険なトイレの多くは施設や設備条件に問題があり,その改善が大きな課題であることが明らかになった。その結果にもとづき,(1)立地特性を踏まえ,商業施設等のトイレを含めた公共トイレ全ての配置を検討することと,(2)利用特性を配慮し,バリアフリー化や多目的な利用に応える施設設備条件の改善を進めること,(3)管理業務内容やその方法の見直しを行うことが必要であることを結論としている。さらに,施設設備条件の改善に取り組む際の問題として,施設設備の設計者と管理業務担当者の間の情報交換が不十分な現状を指摘し,情報の共有やフィードバックの必要性に言及している。さいごに,公共トイレの整備および管理の現状をとおして,公共空間の整備・管理の課題である「公共性の醸成」について考察し,住民参加による整備・管理が鍵となることを示唆している。