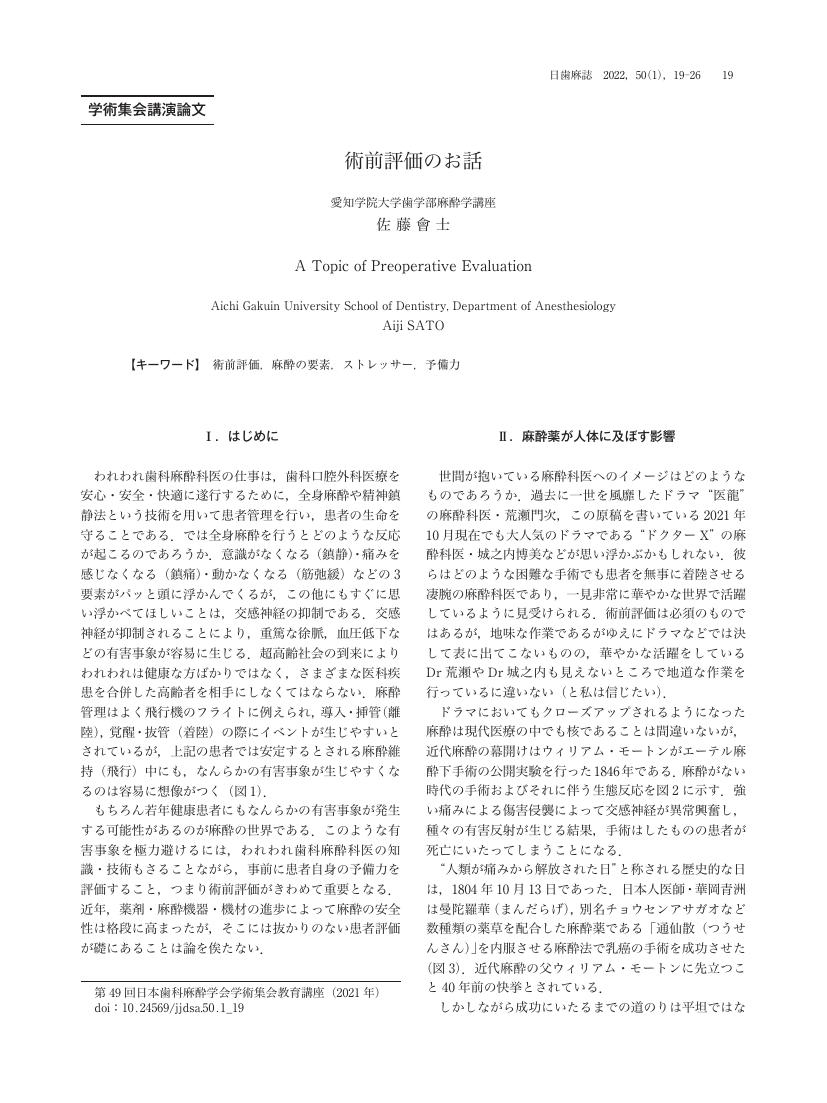- 著者
- 佐藤 裕二 七田 俊晴 古屋 純一 畑中 幸子 内田 淑喜 金原 大輔
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.101-104, 2021-09-30 (Released:2021-10-21)
- 参考文献数
- 6
目的:2021年6月に,2020年6月(医療保険導入後2年2カ月)の社会医療診療行為別統計が公表されたので,これを前報の実施状況と比較することで,最新の口腔機能低下症の検査・管理の実態を明らかにすることを目的とした。 対象と方法:2019年6月,2020年6月および2021年6月に発表された社会医療診療行為別統計により,医療保険導入後2カ月,1年2カ月,2年2カ月の口腔機能低下症の検査・管理の実施状況を調査した。 結果:「65歳以上の初診患者」は225万人(2019年),188万人(2020年),125万人(2021年)と減少していた。そのため,2019年から2020年にかけての検査・管理件数はわずかな増加(1.2倍)であったが,初診患者数に対する実施率は1.8倍になった。 考察:検査・管理件数は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響も考えられ微増(21.2%増)にとどまったが,普及は進みつつある。ただし,口腔機能低下症の有病率と比べると依然として実施率は少ない。 結論:口腔機能低下症の検査・管理は普及してきたが,さらなる普及に向けた努力が必要であることが示された。
- 著者
- Masayuki Yamaguchi Kosuke Kojo Mizuki Akatsuka Tomoyuki Haishi Tatsushi Kobayashi Takahito Nakajima Hiroyuki Nishiyama Hirofumi Fujii
- 出版者
- Japanese Society for Magnetic Resonance in Medicine
- 雑誌
- Magnetic Resonance in Medical Sciences (ISSN:13473182)
- 巻号頁・発行日
- pp.tn.2021-0130, (Released:2022-03-23)
- 参考文献数
- 13
We have developed a new device, consisting of a 3-cm RF coil and an immobilizer, to acquire high-resolution MR images of the testis. With the approval of our institutional review board, we conducted an MRI study on a cohort of healthy volunteers to test this device. With the participants in the supine position, we placed the dedicated immobilizer and RF coil on the scrotum for typically no more than 3 min. Subsequently, T2-weighted images were acquired with an in-plane resolution of 117 µm using a 3-T MR scanner and the periodically rotated overlapping parallel lines with enhanced reconstruction (PROPELLER) sequence. The total scan time ranged from 12 to 30 min (average 20 min). High-resolution MR images of the testis were acquired without deterioration by motion artifacts. Our results showed that the combined use of a small RF coil and an immobilizer is a feasible option for acquiring high-resolution MR images of the testis.
1 0 0 0 電気刺激に対するマガキ心筋の応答
- 著者
- 江原 有信 佐藤 利夫
- 出版者
- 日本動物学会
- 雑誌
- 動物学雑誌 (ISSN:00445118)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.10, pp.358-363, 1971-10
Square pulse (17.5 V, 50 msec) was applied to oyster ventricle which had been isolated and mounted on a separation box. Myocardial activity was intracellularly recorded by means of microelectrode filled with 3 M KCl. Electric stimulation of threshold strength affected the beat interval as follows: Length of beat interval was changed by the simulation applied even during repolarization phase which corresponded to so-called refractory period. Depolarizing current did not always produce an extra action potential, and sometimes delayed the production of succeeding spontaneous action potential according to stimulating moment (Fig. 1). Hyperpolarizing current did not always elongate the interval, and often evoked an extra action potential as the result of rebound excitation th shorten the interval. Compensatory pause could not be found in these experiments. The change in length of the beat interval caused by the stimulation applied before the critical point (Fig. 2) had an opposite relation against that applied after it. The change in the beat interval caused by depolarizing current differed markedly from that produced by hyperpolarizing current. The effect of depolarizing stimulation was essentially similar to that of small potential (Ebara, 1964b) which conceivably had an important role in rhythm formation of the whole ventricle.
- 著者
- 若井一樹 岡田泰輔 鎌田祐輔 佐々木良一
- 雑誌
- マルチメディア、分散協調とモバイルシンポジウム2013論文集
- 巻号頁・発行日
- no.2013, pp.865-872, 2013-07-03
1 0 0 0 OA 図書館forum No.19
- 著者
- 福井大学附属図書館
- 出版者
- 福井大学附属図書館
- 雑誌
- 福井大学附属図書館報 図書館forum
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.1-19, 2022-03
●図書館長インタビュー…横井正信…1●ここが変わった! 附属図書館ホームページ…3●附属図書館の貴重資料…5●福井大学附属図書館所蔵「小島家文書」を読む(9) 福井大学所蔵の貴重資料、「小島家文書」を知っていますか?…長谷川 裕子…7●ようこそ、本の世界へ(5) 伊崎文庫の紹介 ―太宰治研究の新たな拠点として―-…膽吹 覚… 9●BOOK HUNTING…11●図書館withコロナ2021…13●TOPICS with 学生・教職員・部局・学外…15●寄贈に関する報告…18●読者プレゼント 他…19
1 0 0 0 OA 説明変数を含んだマルコフチェインモデルによる都心再開発に伴う消費者回遊行動の変化予測
- 著者
- 斎藤 参郎 石橋 健一
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.439-444, 1992-10-25 (Released:2019-12-01)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 5
CONSIDERING CONSUMERS' SHOP-AROUND BEHAVIORS IN AN AGGLOMERATED COMMERCIAL DISTRICT AS THE AGGLOMERATION EFFECT OF THE ACCUMULATED AND PROXIMATE LOCATIONS OF RETAIL FACILITIES IN THE DISTRICT, THIS PAPER PROPOSES AN EVALUATIVE FRAMEWORK FOR ASSESSING REDEVELOPMENT PROGRAMS OF CITY CENTER RETAIL ENVIRONMENT FROM SUCH A STANDARD AS WHAT AMOUNT OF CONSUMERS' SHOP-AROUND BEHAVIORS THESE PROGRAMS WOULD INDUCE. FOR THE PURPOSE, A STATIONARY MARKOV CHAIN MODEL WITH COVARIATES IS DEVELOPED TO EXPLAIN CONSUMER'S SHOP-AROUND BEHAVIOR WITHIN A SHOPPING DISTRICT. THE MODEL WAS ESTIMATED AND APPLIED TO THE ACTUAL CASE OF CITY CENTER OF FUKUOKA CITY. REDEVELOPMENT PROGRAMS THERE ARE TRIED TO BE EVALUATED BY ITS FORECASTS.
1 0 0 0 貧困と子どものメンタルヘルス
- 著者
- 稲葉 昭英
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.144-156, 2021
<p>貧困・低所得の定位家族で育つことが子どもの内面に与える影響を検討するために,等価世帯所得によって定義される「世帯の貧困」と子ども(中学3年生)のメンタルヘルス(心理的ディストレス)との関連を計量的に検討する.内閣府「親と子の生活意識に関する調査」(2011年)を用いて,対象を有配偶世帯に限定して分析を行った結果,(1)男子では貧困層にディストレスが高い傾向は示されなかったが,女子では貧困層で最も高いディストレスが示された.(2)女子に見られるそうした貧困とディストレスの関連は親子関係の悪さや,親や金のことでの悩み,といった家族問題の存在によって大きく媒介されていた.この結果は貧困世帯において女子に差別的な取り扱いがあること,および女子は男子よりも家族の問題を敏感に問題化する,という二つの側面から解釈がなされた.</p>
1 0 0 0 OA 高齢期における就労と主観的健康感の縦断的関連:システマティックレビュー
- 著者
- 渡邉 彩 村山 洋史 高瀬 麻以 杉浦 圭子 藤原 佳典
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.215-224, 2022-03-15 (Released:2022-03-23)
- 参考文献数
- 23
目的 少子高齢化の進行による労働力不足が課題となる中,高齢者による就労を促進するための諸制度や職場環境の整備が急速に進められている。高齢者が積極的に労働市場に参入することへの期待が高まる中,高齢期における就労と高齢者の心身の健康との関連や課題を明らかにする必要がある。中でも,主観的健康感は,生活機能の低下や健康寿命の延伸にも強く関連し,高齢者の全体的な健康状態を捉えるための重要な健康指標である。そこで本研究は,高齢期における就労と主観的健康感との縦断的関連について,システマティックレビューの手法を用いて整理することを目的とした。方法 文献検索のデータベースは,PubMed, PsycINFO, CINAHL,医学中央雑誌を用いた。「高齢者」「就労」および「主観的健康感」をキーワードとして検索を行い,ⅰ)60歳以上の者を研究対象としていること,ⅱ)就労を独立変数,主観的健康感を従属変数として設定していること,ⅲ)縦断研究であること,を採択基準とした。採択された文献の質評価は,観察研究の質の評価法であるNewcastle-Ottawa Scaleを用いた。結果 最終的に,5件が採択され,4件が日本の研究,1件はアメリカの研究であった。5件のうち3件は,高齢期に就労している者は,非就労の者に比べて主観的健康感が高いことを報告していた。質評価の結果,5件とも6点あるいは7点(9点満点)であり,いずれも一定の水準を満たしていた。5件のうち2件は,高齢期の就労と主観的健康感の間に有意な関連は認められなかった。結論 本研究により,高齢期における就労と主観的健康感との間に一定の関連があることが示唆された。しかし,その効果を縦断的に検討した文献はいまだ少ないことも明らかになった。今後,高齢期における就労がより一般的になることが見込まれる中,高齢者が積極的かつ安心して就労するためにも,就労が高齢者の健康に及ぼす影響やその機序について,さらなるエビデンスを伴った知見の集積が望まれる。
1 0 0 0 OA 『詐欺師フェーリクス•クルルの告白』における存在の不連続性
- 著者
- 若槻 敬佐
- 出版者
- Japanische Gesellschaft für Germanistik
- 雑誌
- ドイツ文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, pp.87-96, 1985-10-01 (Released:2008-03-28)
Als die Bewegung des Expressionismus auch in den Bereich der Literatur einzudringen anfing, hatte Thomas Mann, seiner kritischen Lage in der ganzen Situation der deutschen Literatur bewußt, nach einem Ausbruch gesucht. Gerade damals, , nach der Zurücklegung von "Königliche Hoheit“‘, begann Thomas Mann die "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ zu schreiben, indem er diesen Plan allen anderen vorzog, was übri-gens andeutet, wieviel Gewicht er auf diesen Entwurf gelegt hatte. Er mußte die Arbeit jedoch schon gleich nach dem Beginn des öfteren unter-brechen. Die längste Unterbrechungszeit geht sogar über die beiden Weltkriege hinaus, und erst nach fast vierzig Jahren hat Thomas Mann das Fragment wieder aufgenommen, es aber nicht vollendet, sondern nur erweitert.In der Fortsetzung des Fragments ist zwar in Bezug auf die Handlung noch eine Kontinuität gewahrt. Aber man könnte kaum sagen, es gäbe hier, wie erwartet werden sollte, eine konsequent durchgeführte Gesamt-konzeption. Eher fällt uns eine Art Diskontinuität auf, und zwar in dem anscheinend wesentlichen Punkt des eigentlichen Entwurfs, eben in der Existenzform unseres Helden Felix Krull, oder in seiner Beziehung zur Wirklichen Welt.Bei dem, sonderbaren Entwurf‘, auf den Thomas Mann durch die Lektüre der Memoiren Manolescu's gebracht worden war, habe es sich um eine, neue Wendung des Kunst- und Künstlermotivs‘, um die, Psychologie der unwirklich-illusionären Existenzform‘ gehandelt. Jedenfalls ist Krull kein einfacher Hochstapler, sondern ein durch die Sprache sorgfältig gestaltetes Gebilde, das man verschieden deuten könnte. Hans Mayer z.B. spricht von der, ästhetischen Existent‘ und sieht darin die Verkörperung der Schillerschen Utopie von der Erkenntnis des Wirklichen durch den Schein; für V. Lange ist Krull, im Unterschied zum Künstler, der die Welt in ein Bild verwandelt, eher ein Zauberer, der durch die Manipulation der Formen dem Bild Wirklichkeit verschafft; Hermsdorf will da hauptsächlich nach den Eigenschaften des Schelmenromans suchen; und B. v. Wiese sieht eine utopische Existenzform, bei der sich die Realität in Illusion verwandelt hat; usw.Aber trotz mancher konsequenten Deutungen scheint uns die Diskontinuität wichtiger, zumal wenn wir an eine merkwürdig bewußte Gleichgültigkeit denken, mit der sich die deutschen Schriftsteller der Gegenwart diesem, Repräsentanten‘ der bürgerlichen Bildung gegenüber verhalten.Für den Krull im "Fragment“ vor dem 1. Weltkrieg gibt es keine feste Grenze zwischen dem Wirklichen und dem Illusionären. Auch seine positive Weltanschauung, die auf der Überzeugung beruht, daß er ein Sonntagskind sei, berührt eigentlich, beinahe in fließendem Übergang, Leiden und Qual seines wirklichen Lebens. In dieser doppeldeutigen, im Grunde negativen Beziehung zur Wirklichkeit, wie bei einem Bajazzo, geht er mit der Welt um, was ihn, aufgrund seiner Einsicht, daß die Existenzweise eines Individuums davon abhängig ist, ob es die Welt klein sehe oder groß, zu ihrer Wahrheit führen soll.In der "Fortsetzung“ nach dem 2. Weltkrieg dagegen befindet er sich nicht mehr in der Spannung der Doppeldeutigkeit, sondern in der Welt des reinen Scheins, die der wirklichen scharf gegenübersteht, und aus der alles Reale abgestrichen ist. Der Grund, warum wir these Veränderung inkonsequent finden, liegt vielleicht darin, daß sie von dem gründlichen Wandel des Gesichtspunktes des Erzählers herrührt. Denn der erzählende, bekennende Krull läßt uns schon am Anfang erwarten, daß er das Ganze aus ennem einheitlichen Gesichtspunkt erzählen würde,
1 0 0 0 矢崎千代二と日本製パステル : 日本近代におけるパステル受容
- 著者
- 横田 香世
- 出版者
- 美術史學會
- 雑誌
- 美術史 (ISSN:0021907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.18-35, 2016-10
1 0 0 0 Twitterのスパム検知機能となりすまし検知機能の開発と評価
- 著者
- 若井 一樹 佐々木 良一
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.9, pp.1817-1825, 2015-09-15
Twitterにおけるスパム行為となりすまし行為の検知手法を提案する.これらの検知手法はスパム行為となりすまし行為の様々な特徴から検知対象であるか判定する項目を複数個作成し,それらの項目を数量化理論の適用によって最適な項目の組合せを選定することによって検知するものである.またこれらの手法を実装するとともに,検知結果をユーザに分かりやすく提示するようTwitterの表示系を強化したアプリケーションLookUpperの開発と評価を行った.この結果,本検知手法ではスパム行為となりすまし行為どちらも90%以上の的中率で検知することが可能であった.LookUpperの開発と評価について,本検知手法を実装し検知結果を分かりやすく表示する機能を開発し,被験者10人によってなされたLookUpperのユーザビリティに関する実験結果から全体的に高い評価を得るとともに,今後LookUpperの改良を行っていくためのアイディアを導く種々のコメントが寄せられた.
1 0 0 0 OA 身体各部分の加速度からみた柔道の受け身
- 著者
- 真柄 浩 内匠屋 潔
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.15-22, 1977-03-31 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 22
Ukemi movements against migi-tsurikomigoshi were analyzed by 16 mm kinematography and acceleration transducer in order to obtain some informations usefull in effective instruction of Ukemi in Judo.Movements of Ukemi were considered all complete with in approximately 0.3 sec. There found `pronounced discrepancies between the recorded values and the values claimed by the subjects in their feeling as to the time of completion, sequence of the body parts hitting the mat, and the angle formed between the. arm and the side of the trunk.Subject T. T. whose performance in Ukemi was rated excellent, registered a double hitting on the mat with his left arm which reduced the landing shock to the neck markedly. The highest angular velocity of his neck was 530°J sec.Subject Y. S. whose Ukemi performance was rated very poor, showed pushing movement against the mat rather than the hitting movement in his left arm. The landing shock to his neck was great, as recorded in the angular velocity of his neck which reached 1260°/sec.It was concluded that: (1) avoidance of the confusion between the mechanical phenomena actually took place and the subjective feeling of the performance is necessary; (2) function of absorbing the impact with viscosity and elasticity must be considered; in order to improve the effectiveness of instruction in Ukemi.
1 0 0 0 5.PCM録音とその将来(<小特集>PCM録音)
- 著者
- 伊藤 毅 岡 俊雄 高須 昭彦 中島 平太郎 林 謙二
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.32-38, 1979-01-01
本稿は小特集"PCM録音"の一環として, 昭和53年8月18日機械振興会館で行った座談会を収録したものである.約2時間に亘る話の中から紙面の都合で半分以上を削ってここに掲載した.当日の話題の内容が失なわれないよう配慮したが, かなりの省略を行ったため, 座談の雰囲気および内容について意を充分尽くせない部分もあると思われる.ここに出席者の方々ならびに会員諸兄の御寛恕をお願いする次第です.
- 著者
- 茜 拓也
- 出版者
- 情報文化学会
- 雑誌
- 情報文化学会誌 = Journal of the Japan Information-culture Society (ISSN:13406531)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.48-54, 2006-08-31
- 参考文献数
- 27
1990年代半ば以降,インターネットという新しい技術に象徴される情報通信技術の進展によって,ジャーナリズム活動がマス・メディアだけの問題ではなくなった。これまではマス・メディアが発信する情報の受け手に甘んじてきた人々が自分の求める情報を検索したり,対話的に情報を処理したり,自ら情報発信や意思決定の主体になったりするなど,能動的な情報行動が可能となった。また,マス・メディア側も,失った市民の信頼を回復しようと,米国のパブリック・ジャーナリズムに見られるように,このような能動的な情報行動を行う人々との往復運動の中で,オーディエンスとの双方向性,オーディエンス同士の多方向性を重視したジャーナリズム活動を実践し始めた。そこで,本論文では,日本においてインターネットのウェブログを活用しながらパブリック・ジャーナリズムを実践している既存のマス・メディア,特に地方新聞社による新たな取り組みの一つとして,神奈川新聞社のウェブログ「カナロコ」と中国新聞社の「ふれあい」を取り上げる。そして,「世論」という概念から検討し,日本におけるパブリック・ジャーナリズムの一モデルを提示し,その可能性について論じたい。
1 0 0 0 OA 山地形における地震動の増幅特性
- 著者
- 栗田 哲史 安中 正 高橋 聡 嶋田 昌義 末広 俊夫
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING
- 雑誌
- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.1-11, 2005 (Released:2010-08-12)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 8 3
山地形のような不整形地盤では、地震動の増幅特性が地形の影響を受けることが知られている。不整形地盤に入射した波と内部で反射した波の干渉により、伝達する地震波は複雑な様相を示す。この様な山地形の地震動特性を明らかにするために、横須賀市内の山地において、アレー観測を行ってきている。観測記録はデータベース化され、震動特性の分析に活用されている。本研究では、この山地形を対象として観測記録の分析及び3次元有限要素法による数値シミュレーションを実施した。観測記録を良く説明できる適切な解析モデルを作成し、山地形の増幅特性を評価することを目的としている。検討の結果、山地形を忠実にモデル化することによって観測記録を良く説明できるシミュレーションが可能となった。更に同モデルを用いて、山地形に地震波が入射した時に地震動がどの様な特性を示すのかを解析的に評価した。
機械学習を,アルゴリズムをきちんと理解した上でゼロからプログラミングして実装してみたい方は少なくないに違いない.本書はそのような野心的な読者の夢を叶えてくれるかもしれない.本書は,回帰分析,分類モデル,カーネルモデル,ニューラルネットワーク,強化学習,教師なし学習など,機械学習の全般的な分析法について,原理的なことから丁寧に説明し,Pythonでの実装を示している.分かりやすさを優先して数式的な記述や説明を省いたりせず,Pythonのソースコードについても丁寧に説明されている.機械学習の中身やプログラミングの実装に関し,ブラックボックスな部分が少ないという面で,お薦めの書籍である.
1 0 0 0 OA 1人暮らしの高齢者に安心感をもたらすポスターを生活空間へ導入した1事例
- 著者
- 小池 彩乃 内田 陽子
- 出版者
- 北関東医学会
- 雑誌
- 北関東医学 (ISSN:13432826)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.91-95, 2022-02-01 (Released:2022-03-18)
- 参考文献数
- 12
対象者はA氏,80歳代,女性,要介護1.独居で生活しているが,火の不始末が心配,緊急連絡先への連絡や来訪者の把握が難しいなどの不安を感じていた.そこで,A氏の目に留まりやすくニーズに合わせたデザインのポスターを生活空間に導入した支援を行った結果,安心感をもたらした.その要因として,①A氏の居住空間・動線・目線に合わせたポスターの掲示,②A氏の好むデザインの選択が考えられた.この症例は多くの独居高齢者にも活用できると考えたため報告する.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.793, pp.14-18, 2005-04-04
東地方の最東端に位置する千葉県銚子市。三方を海に囲まれた半島の先端、南側にある外川町は、古くから栄える漁港の町だ。海際からすぐ急斜面となり、細い路地を上っていくと、両側には質素なかわら屋根の家並みが続く。 この風景に溶け込むように、1軒の「蔵」が建つ。正体は豆腐店兼住宅だ。 榊原さん一家は、代々この地で豆腐店を営んできた。
- 著者
- 有馬 光孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- Techno marine 日本造船学会誌 (ISSN:09168699)
- 巻号頁・発行日
- vol.836, pp.136-140, 1999
1 0 0 0 OA 術前評価のお話
- 著者
- 佐藤 會士
- 出版者
- 一般社団法人 日本歯科麻酔学会
- 雑誌
- 日本歯科麻酔学会雑誌 (ISSN:24334480)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.19-26, 2022-01-15 (Released:2022-01-15)
- 参考文献数
- 10