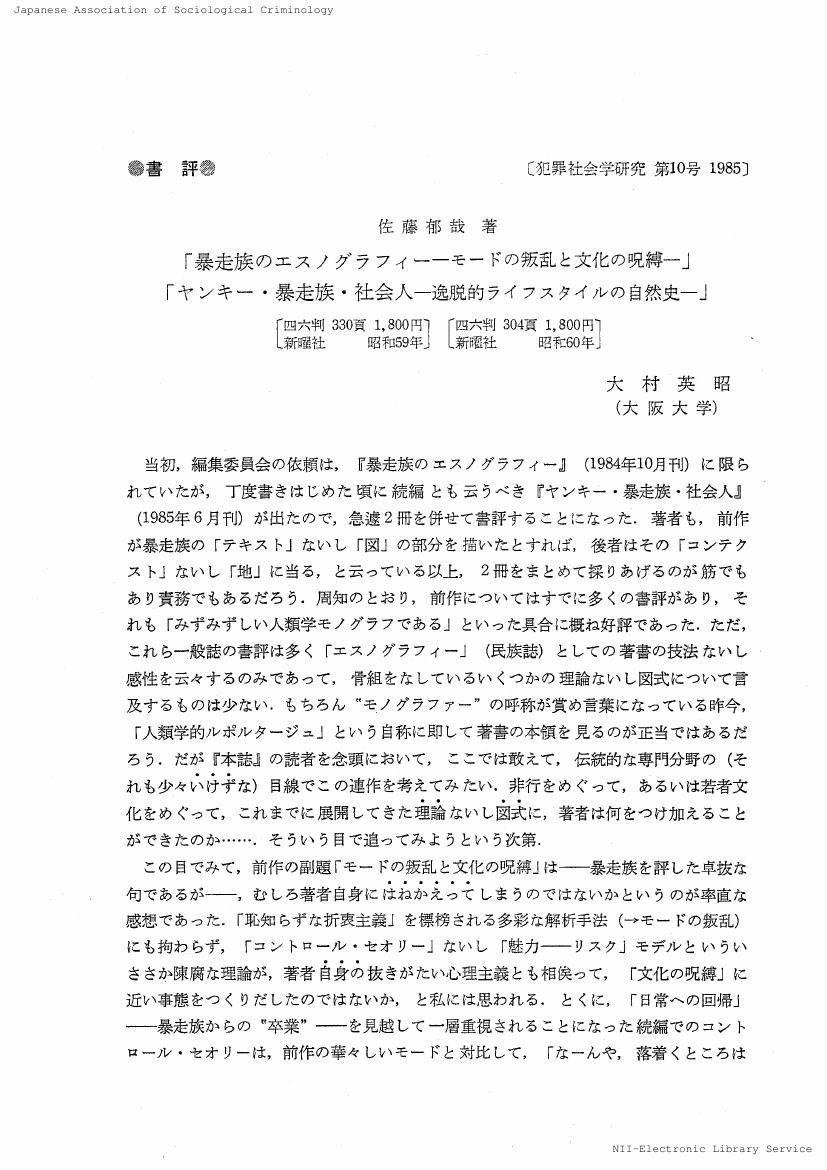- 著者
- 宮崎 慧 星野 崇宏 繁桝 算男
- 出版者
- 日本計算機統計学会
- 雑誌
- 日本計算機統計学会シンポジウム論文集 22 (ISSN:21895813)
- 巻号頁・発行日
- pp.129-132, 2008-11-06 (Released:2017-07-15)
- 著者
- 大村 英昭
- 出版者
- 日本犯罪社会学会
- 雑誌
- 犯罪社会学研究 (ISSN:0386460X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.187-190, 1985 (Released:2017-03-30)
1 0 0 0 全児童生徒に対する色覚検査の必要性と正しい検査法
- 著者
- 馬嶋 昭生
- 出版者
- 公益社団法人 日本視能訓練士協会
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.7-13, 1997
ごく一部の眼科医と,彼らを支持する少数のいわゆる知名人は「学校保健法に基づく一斉色覚検査を全廃せよ」という運動を執拗に続けてきたが,色覚とその異常の本質を理解している研究者と,多くの眼科医の強い反対によって阻止された。しかし,文部省は,「小学校4年生で1度だけ行う」というこれらの意見の折衷案か妥協案のような改訂を行った。本論文では,全廃論に対する反論,小学校1年生での検査の重要性,今後の対策として学校現場での正しい検査法や事後の措置などを解説した。眼科医や視能訓練士は色覚異常者の視機能を十分に考慮した指導や助言ができる学識を身に付けることの重要性,色覚検査廃止論者の好んで使う「異常者の差別」という言葉の誤りを指摘した。筆者は,個人の好まない学校現場での一斉検査が他にもあるのに,全廃論者が何故に色覚検査のみに執拗に拘泥するのかその真意を知りたい。
1 0 0 0 OA 日本人の富士山観の変遷と現代の富士山観
- 著者
- 田中 絵里子 畠山 輝雄
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.6, pp.953-963, 2015-12-25 (Released:2016-01-27)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 2 2
This study clarifies contemporary perceptions of Mount Fuji on the basis of the sensibilities of the Japanese people, who are influenced greatly by subjective and sentimental ways of viewing landscapes. Over the course of history, the way in which the Japanese have perceived Mount Fuji has changed due to experiences in each successive era, whether these have been natural disasters that accompanied eruptions, the shifting vista of Mount Fuji as seen from moving political capitals, or the development of mountain-climbing routes; in other words, reflecting of subjective factors such as individuals' perceptions of nature and culture within the context of such experiences. This study is a quantitative analysis based on a questionnaire survey of contemporary Japanese perceptions of Mount Fuji following its registration on the UNESCO World Heritage List. From the results of the analysis, when considering the way Mount Fuji is perceived from the Japanese sense of landscape, a comparison with ways Mount Fuji was perceived in the past indicates the following: while some aspects of contemporary perception of Mount Fuji have been inherited from a past that reflects underlying Japanese views of nature and culture, there are also newer aspects that have originated from a more recent overall national experience of the movement for World Heritage registration and the social background revealed in media coverage following registration. However, no significant differences are found as to whether individual respondents' had ever climbed to the summit or lived in a region where Mount Fuji is visible. This appears to be a result of increased exposure to various of information on Mount Fuji in the mass media, which have provided supplementary information to citizens living far away or who have no personal experience of Mount Fuji. This can be said to have formed a unified national view of Mount Fuji.
1 0 0 0 OA 窒素フットプリント:環境への窒素ロスを定量する新たな指標
- 著者
- 種田 あずさ 柴田 英昭 新藤 純子
- 出版者
- 日本LCA学会
- 雑誌
- 日本LCA学会誌 (ISSN:18802761)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.120-133, 2018 (Released:2019-12-15)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 1 2
人間活動によって生成した反応性窒素は、人間および環境に対する脅威をもたらしている。窒素フットプリントは、人間活動を通じた環境への反応性窒素放出(窒素ロス)を、消費者の活動を基準として定量化できる新たな指標である。本稿では、窒素フットプリント算出法として提案されている3つの方法(N-Calculator法、N-Input法、N-Multi-region法)について解説するとともに、これらの評価方法の特徴を生かした活用方法や今後の展開について述べる。N-Calculator法は、消費者一人あたりの食料・エネルギーの消費量に基づくボトムアップ型の分析法である。この方法を使うことで、一つ一つの消費行動がどのように窒素フットプリントに影響するかを定量的に評価、可視化することができる。N-Input法は、食料の生産・輸出入量と、その生産のために使われた農地への窒素投入量に基づくトップダウン分析を用いる。この方法は、複数の国から多くの食料を輸入している国について精緻に算出を行うことができる。N-Multi-region法は、各国・各部門からの反応性窒素排出量について、拡張された世界多地域間産業連関表を用いた産業連関分析を適用する。この方法を使えば、グローバルな貿易の影響を含めた多くの国の窒素フットプリントを評価することが可能であり、複雑な国際サプライチェーンや窒素ロスに関与する反応性窒素の種類を解析することもできる。本稿では、さらに、低減策の主なものとして、食品選択、家庭系ごみの削減、ラベル表示(窒素・カーボン・ウォーターフットプリント)、機関レベルのフットプリント分析(窒素・カーボン)、窒素フットプリントのオフセットの現状と可能性について述べる。また、窒素フットプリントに関する研究プロジェクトについてもいくつか紹介する。
1 0 0 0 当院における退院支援での作業療法士の役割:アンケート調査を通して
- 著者
- 小嶋 亜美 四本 伸成 薬師寺 京子 永山 弓子 芝 圭一郎 松崎 裕史 手島 茉李 東 祐二 藤元 登四郎
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.31, 2009
【はじめに】<BR> 当院では精神科医療に関わる多くの専門職がそれぞれの専門分野で対象者と接し,退院支援を行なっている.今回,多職種が関わる精神科医療の中で,それぞれの専門性を最大限に尊重した医療チームを形成し,作業療法士(以下OT)としてどのような役割を担っていくかを検討する為にアンケート調査を実施し,他部門がOTに求める退院支援の取り組みの把握と今後の課題について報告する.<BR>【対象と方法】<BR> 当院に勤める医師3名,看護師39名,精神保健福祉士6名,臨床心理士3名,薬剤師2名,管理栄養士3名,OT7名にアンケートを依頼し,回答を得た63名を調査対象とした.アンケート用紙を直接配布し,目的と内容に説明を加えた上で記入をしてもらい,後日回収した.質問項目は1.スムーズな連携の為に必要な事を記述式で行った.2.他部門からOTに求める退院支援,連携を強めたい退院支援について30項目の選択肢を設け,チェック式で行った.また,30項目はICFのカテゴリーに分けて分類した.<BR>【結果】<BR> アンケートの結果,1.スムーズな連携の為に必要な事として1.情報共有,2.スタッフ間の信頼関係,3. 方向性の統一の順で多く挙げられていた.2.OTに求められている退院支援として,ICFの活動と参加の項目が中心となっていた.その中でも,身辺処理(排泄,入浴,食事,身だしなみ,服装など),基本的交流(挨拶,常識的なマナー),言語的交流(表現,主張,断り方,聞き方など),社会資源(交通機関,公共施設)の利用,作業能力(集中力,持続力など)について,特に期待されていた.また,それらの項目は,OTを含め,看護師,精神保健福祉士も,重要視して支援を行なっている部分であった.<BR>【考察】<BR> 結果より,スムーズな連携の為に必要な項目が挙げられたが,その為には連携の鍵となるカンファレンスやマネジメントする役割が重要である.当院では,退院支援の中で看護師を中心とした多職種との合同カンファレンスが行なわれている.そのような場において,OTとして他部門から期待されている項目である身辺処理,基本的交流,言語的交流,社会資源の利用,作業能力についての情報を積極的に提供,共有していかなければならないと考えた.多職種がお互いに重要視している項目を把握し,専門家として情報を提供することにより,マネジメントを担っている看護師のサポートとなり得ると考えられる.今回のアンケート調査の結果を踏まえ,実際に退院支援を行なっていく中で出てくる問題点や課題を見つけていき,地域へ移行する対象者へのよりよい支援を提供できればと考える.
1 0 0 0 IR ドイツにおけるDNA型検査の現状 : DNA型一斉検査 (大崎隆彦教授退任記念号)
- 著者
- 辻本 典央
- 出版者
- 近畿大学法学会
- 雑誌
- 近畿大学法学 (ISSN:09164537)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.61-80, 2013-12
I. はじめに II. ドイツにおけるDNA型検査の法律状況 1. 立法以前の状況 2. 立法の過程 3. 現行規定 III. DNA型一斉検査 1. 同意要件について 2. 目的拘束性--「家族探索 」の許容性 IV. おわりに
1 0 0 0 OA 桜と蛍の色彩に対する日本人と外国人の感性の比較研究
- 著者
- 白土 淳子 稲垣 照美 穂積 訓
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- pp.TJSKE-D-17-00025, (Released:2017-10-31)
- 参考文献数
- 13
We investigated the RGB and XYZ components of the natural colors (two cherry blossoms, i.e., Someiyoshino and Youkou, and the emission of Heike-firefly), and the physiological effects on Japanese and foreign people were compared. The natural colors were digitally measured as RGB colors, and then they were used as color stimuli. The psychological effects were investigated by administering a questionnaire, which was based on the Semantic differential (SD) method. From the results of the questionnaire, the degrees of expression for the natural colors were quite different between Japanese and foreigners. The kansei on the natural colors between Japanese and foreigners were also different in terms of psychophysical quantity and physical cognition. The results of factor analysis showed that the color of Youkou gave pleasantness to Japanese people, whereas the colors of Someiyoshino and firefly gave pleasantness to foreign people.
- 著者
- 堀江 有里
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 = Journal of religious studies (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.2, pp.373-399, 2019-09
- 著者
- 中村 美香子
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2013
【はじめに】「和美・西公園仮設団地自治会」での活動等を具体的に紹介する。児童公園敷地内の和美仮設団地(16世帯)と隣接する西公園仮設団地(20世帯)は、宮古市中心市街地に立地しており、買い物や通院等において他の仮設団地よりも利便性が極めて高い。入居者の平均年齢は約45歳で、他の仮設に比べて「若い世代」が多い。また、5名を除いて「市街地海寄りでの被災者」が入居しており、以前の自宅と仮設住宅との道のりは1㎞前後と短い。【入居からの出来事等】2011年7月19日から入居開始。当初、小規模仮設団地のためか支援があまり入らず、誰が入居しているのか分からない状態。2011年10月初旬、談話室に支援員配置。利用は常に2名のみ。支援員ごとに他仮設団地の談話室等と対応が異なる。この頃、団地内では挨拶がない。話し相手もいないので漠然と不安を感じた。入居者が依然分からず、救急車に傷病者宅を案内できず。2011年10月後半、この状況の改善のために、中村が仮設住宅全戸への物資配布時に世帯人数等を住民から聞き取り(任意)。2011年12月後半、宮古社会福祉協議会・宮古市役所生活課同席で住民集会。2つの仮設団地合同での自治会の設立を決定。2012年2月、「和見・西公園仮設住宅自治会」が正式に発足。住民間の交流を円滑にするために、①ボランティア訪問等のイベントに極力参加するだけでなく、近所に声掛けや、②平時にも挨拶と声掛けを積極的に行い、③集まる人が増えてきたらフルネームを覚えるように何度も名前を呼ぶ等を実施した。2012年3月、ひな祭り会(ふんばろう東日本主催)、雛人形作り・ひな祭り会(ボランティア団体・ほっとほっと主催)。2012年4月、お花見会(新和会(宮古市山口病院)主催)、懇親会(自治会主催 第1回、夕食会)。2012年5月、懇親会(自治会主催 第2回、夕食会)。2012年6月、バス遠足(新和会主催、遠野市ふるさと村、参加10名)、懇親会(住民有志主催、30~40代5世帯参加)。2012年7月、懇親会(住民有志主催、30~40代5世帯参加)、トリックマスターSoraショー&懇親会 (自治会主催、夕食会)。2012年8月、流しそうめん会(自治会主催、たこ焼き+かき氷+おでん、ハンドベル演奏、3.11教会ネットワーク協賛)、盆踊り(町内会主催、たこ焼き+ポップコーン)。2012年10月、敬老会(町内会主催、70歳以上無料招待)、栗拾い(新和会主催)&昼食会(自治会主催、住民手作り)。2012年12月、忘年会(自治会主催、新和会を招待、住民手作り)。2013 年1月、「修学」旅行(名古屋等からのボランティアに再会)。※2012年4月以降 週の半分は談話室で材料を持ち寄り昼食会(60~80代男女12人前後参加、300円~500円程会費を徴収)。【考察】36世帯の小規模仮設団地でボランティアやイベントが少ないことが逆に自分達で企画を立てるきっかけになる。自治会活動等の経験がない主婦が代表になり、慣例にとらわれない活動を展開した。仮設住宅の住民及び地域の既存自治会が積極的に協力。ボランティアや役所関係、地域の方々等の話を聞き、自分達のことを伝える。問題点として、①人間関係の悪化、②一部住民の駐車場の専有化、③居住実態がない入居者、④交流を円滑に促進する者ほど疲労が蓄積、⑤体力の低下、⑥住民の行動が常に分かる状況等が挙げられる。今後、①プライバシーの確保、②住民間で適度な距離感の確保、③高齢者の見守り、④離れて暮らす家族との連絡方法の確認、⑤連絡先交換、⑥談話室利用のルール作り、⑦警報時等のマニュアル作りと避難マップ作成等に取り組みたい。付記 本発表は、公益財団法人 トヨタ財団 「2012年度研究助成プログラム東日本大震災対応『特定課題』政策提言助成」の対象プロジェクト(D12-EA-1017, 代表岩船昌起)の助成で実施した。
- 著者
- 西岡 裕 西川 眞弓 土橋 均
- 出版者
- 日本法科学技術学会
- 雑誌
- 日本法科学技術学会誌 (ISSN:18801323)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.53-75, 2006
- 被引用文献数
- 1
A fully automated identification system for 35 benzodiazepines and their 29 metabolites was developed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) with a DB-5MS fused silica capillary column after trimethylsilyl (TMS) and trifluoroacetyl (TFA) derivatization, followed by registering both their retention times and mass spectra as the standard library data.<br>All the analytes except for rilmazafone and haloxazolam were detectable with and/or without TMS derivatization. TFA derivatization was found to be more effective in the more sensitive analysis of oxazolo-benzodiazepines except for flutazolam. Also, correction of their retention times by alkanes enabled to accurately identify on the different GC-MS systems with different lots of columns.<br>The present system allowed us to identify benzodiazepines and their metabolites in urine and blood more readily in a much shorter time, and it will be a powerful system for the analysis of benzodiazepines in the forensic chemistry and toxicology fields.
1 0 0 0 サンゴ海のジンベエ餃付鮪群を手釣
- 著者
- 花本 栄二 宇田 道隆
- 出版者
- 水産海洋研究会
- 雑誌
- 水産海洋研究会報 (ISSN:03889149)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.99-101, 1966-03
1 0 0 0 ミジンコウキクサによる排水処理 : デンプン生産システムの構築
- 著者
- 川畑 祐介 池 道彦 藤田 正憲
- 雑誌
- 日本水処理生物学会誌. 別巻 = Journal Japan Biological Society of Water and Waste (ISSN:09106766)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, 2002-10-15
1 0 0 0 OA 義務教育における地形用語の研究
- 著者
- 有井 琢磨
- 出版者
- 日本地理教育学会
- 雑誌
- 新地理 (ISSN:05598362)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.3-10, 1985-09-25 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 15
The purpose of this study is limited to discuss the terminologies of the landforms (following the examples of plateaus, highlands, uplands, plains and basins), for the compulsory education in Japan, from a viewpoint on both domestic and foreign terminologies in relation to demonstrate tentative ones, proposed by the writer, of the landforms.According to his opinion, the schoolchildren in a primary school and the pupils in a junior high school, in Japan, have to learn of the proper geographical terms which will be able to receive an international understanding, since there is no doubt that most of them will be working for an international viewpoint in the 21st century. This is why the present study carry out.In order to make sure of the actual usage for the above mentioned five types of the landforms, an atlas for social study in the primary school course and that for the study in the junior high school one have respectively been examined. The usage of the landforms in the atlases have been discussed in view of the terminological descriptions of the domestic and foreign geomorphologists.The main subjects of this study are summerized as follows;1). The plateau (Kohgen in Japnese; e.g. Kibi Plateau, Mino-Mikawa Plateau and so on) is not an adequate expression but the mountain is a desirable one, judging from the facts the plateaus, in Japan, represent the feature of inclined and dissected erosion surfaces which gradually desend to neighbouring lower lands. These features differ entirely from those in the foreign countries.2). The highland (Kohchi in Japanese; e.g. Abukuma Highlands, Kitakami Highlands and so on) is not a proper expression but mountain is desirable one also, judging from the facts these highlands are not always situated on the most highest regions in Japan. In other regions, Japan, there are some of the mountains being similar to so-called plateaus. And the plateaus, moreover, stand by the lower altitude than those in the foreign countries.3). Speaking of the upland (Daichi in Japanese), it is more reasonable to give a place name or a technical term (e.g. “Nasunogahara”, “Makinohara Dissected Fan” and so on) for those. As the synonym of the upland, the Diluvial upland has customarily been used in Japan, but it differs entirely from the remarkable features (the altitudes, relieves and geologic structures) of the uplands in the foreign countries.4). In general, the plain (Heiya in Japanese) has reasonably been used. However, in the case of the plain where includes the uplands in its extent, the usage is unusual compared with that in the foreign countries. In this case we may use a technical term instead of the plain. For example, we may use “Kantoh Basin” in place of “Kantoh Plain”. If we use the name of “Kantoh Plain”, we have to name “Musashino or Nasunogahara” (the place name) instead of “Musashino Upland or Nasunogahara Upland”.5). Speaking of the usage of the basin, there is no unreasonable one.
1 0 0 0 流しそうめん@阪大坂による竹林の再価値化
- 著者
- 伊藤 愼介 村井 翔 北虎 叡人 松村 真宏
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, pp.4B1OS23a3, 2017
<p>本稿では、大阪大学の待兼山に自生している竹林を阪大坂のブランディングに利用する試みとして行ったイベント「流しそうめん@阪大坂」について報告する。地域住民と一緒に竹林に入って竹の伐採、搬出、加工を行って約30メートルの流しそうめん台を阪大坂に設置し、そこに地元商店街が用意したそうめんを流した。地元商店街と地域住民と阪大生との交流、竹林の維持管理、阪大坂の有効活用が達成され、竹林の再価値化を実現した。</p>
1 0 0 0 IR 不動産取得税・登録免許税と凍結効果--不動産取得税・登録免許税の税法と経済学
- 著者
- 青野 勝広 Katsuhiro Aono
- 出版者
- 松山大学
- 雑誌
- 松山大学論集 (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.1-18, 2006-06
1 0 0 0 IR 蛇女--レイミアとメリュジーヌの比較考察
- 著者
- 高島 葉子
- 出版者
- 大阪市立大学
- 雑誌
- 人文研究 (ISSN:04913329)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.12, pp.997-1018, 1998
1 はじめに : 蛇女とは何ものなのだろうか。それはまず, 水に関係した超自然の生き物つまり水の妖精である。水の妖精の最も代表的な存在は, 人魚, 特に女の人魚であろう。そして, 人魚の姿は, よく知られているように, 上半身は女性で下半身は魚か蛇である。キリスト教的図像では, 人魚は「女性の姿をした蛇」であり, OEDにも, 人魚と同義的に使われるセイレーンは, 「想像上の蛇の一種」と説明されている。蛇女は人魚と同類と言える。……
1 0 0 0 OA 宏文学院編纂『日本語教科書』について
- 著者
- 増田 光司
- 出版者
- 国立大学法人 東京医科歯科大学教養部
- 雑誌
- 東京医科歯科大学教養部研究紀要 (ISSN:03863492)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.11-31, 2011-03-30 (Released:2018-07-06)