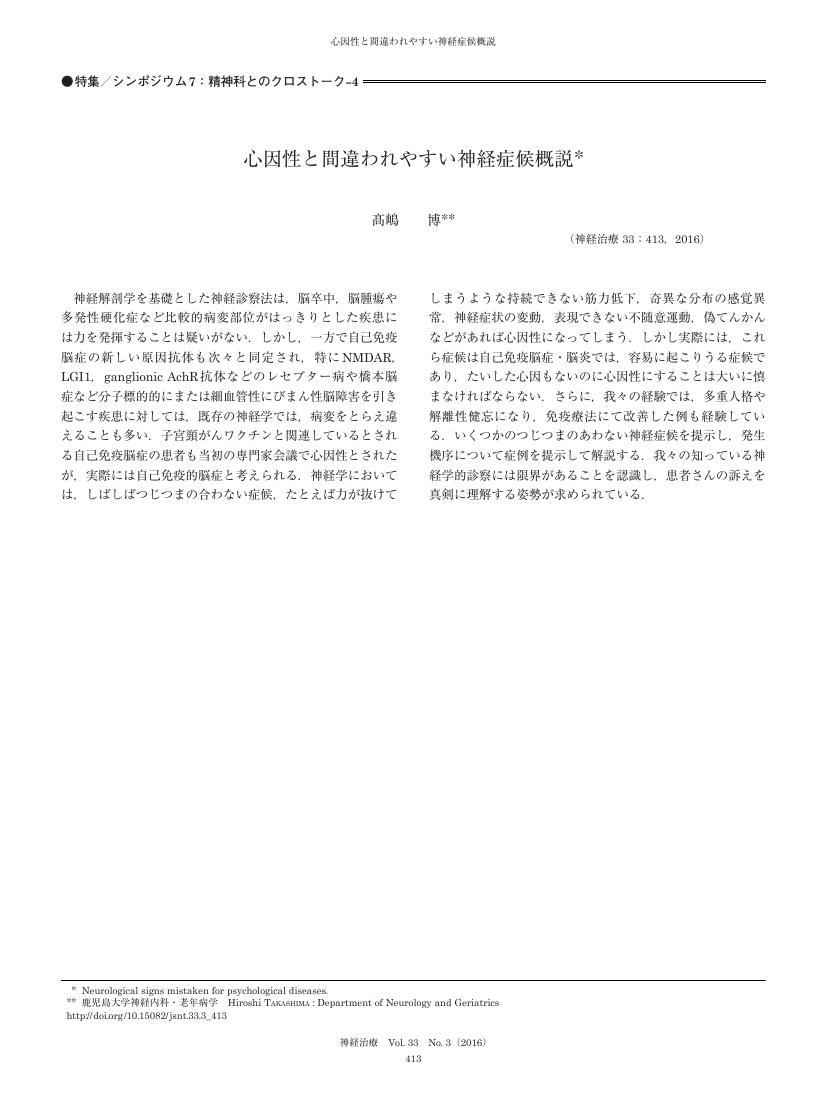31 0 0 0 OA サクラマス自然分布域におけるサツキマスによる遺伝的撹乱
- 著者
- 北西 滋 向井 貴彦 山本 俊昭 田子 泰彦 尾田 昌紀
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.3, pp.400-402, 2017 (Released:2017-05-22)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 5
サクラマス自然分布域におけるサツキマスによる遺伝的撹乱の有無を調べるため,両亜種の在来分布域4道県(サクラマス:北海道,富山県,岐阜県,鳥取県;サツキマス:岐阜県)の個体を対象に,マイクロサテライトDNA解析をおこなった。帰属性解析をおこなった結果,神通川水系上流域(岐阜県)と,甲川および陸上川(鳥取県)において遺伝的撹乱が認められた。
31 0 0 0 OA 心因性と間違われやすい神経症候概説
- 著者
- 髙嶋 博
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.413-413, 2016 (Released:2016-11-10)
- 著者
- IWAO SUGITANI YOSHIHIDE FUJIMOTO
- 出版者
- (社)日本内分泌学会
- 雑誌
- Endocrine Journal (ISSN:09188959)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.209-216, 1999 (Released:2006-11-25)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 69 127
Although the mortality rate associated with papillary microcarcinoma (PMC) of the thyroid generally is very low, some patients present with bulky nodal metastasis or distant metastasis and have an unfavorable prognosis. We retrospectively reviewed clinical aspects, surgical treatment and outcome of 178 patients with PMC in an attempt to determine the prognostic factors. The cause-specific 10-year survival rate was 96%. Three of four patients who showed signs of distant metastasis during the postsurgical period died of the disease, and another died of local recurrence. The most significant prognostic factors were the presence of clinically apparent lymph-node metastasis and hoarseness due to recurrent nerve palsy at the time of diagnosis. All distant metastases and cancer-specific deaths occurred in the 30 patients with symptomatic PMC who had either cervical lymphadenopathy, recurrent laryngeal nerve palsy or both. The 148 patients who had neither symptom had a distinctily favorable outcome. Total thyroidectomy followed by radioactive iodine treatment did not improve the final outcome in patients with symptomatic PMC. We conclude that patients with asymptomatic PMC can expect a truly favorable outcome, but some of those with symptomatic PMC may fall within a high-risk group of patients who do not benefit from aggressive treatment.
31 0 0 0 OA 視点 図書館再考
- 著者
- 佐藤 和代
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.11, pp.849-852, 2016-02-01 (Released:2016-02-01)
- 参考文献数
- 4
31 0 0 0 OA 福島第一原子力発電所事故による放射性物質漏えいに係わる都内環境放射能測定及び被ばく線量測定
- 著者
- 永川 栄泰 鈴木 隆司 金城 康人 宮崎 則幸 関口 正之 櫻井 昇 伊瀬 洋昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.11, pp.467-472, 2011 (Released:2011-11-29)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 8 10
2011年3月11日の東日本大震災に伴い,福島第一原子力発電所の事故が発生した。この事故後から東京都内(世田谷区深沢)で大気浮遊塵,農畜水産物,浄水の放射能濃度及びγ線の空間線量率のモニタリングを行ってきた。5月31日までの測定結果を基に132Te,131I,132I,134Cs,137Csの5核種による内部被ばく線量及び空間線量率による外部被ばく線量を試算した。その結果,測定開始から1年間の積算線量は425.1μSvとなり,ICRPの定める一般公衆の年間被ばく限度(1mSv)を超えないものと推定された。
- 著者
- Tadashi KIHO Shigeyuki USUI Kazuyuki HIRANO Koichi AIZAWA Takahiro INAKUMA
- 出版者
- Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry
- 雑誌
- Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (ISSN:09168451)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.200-205, 2004 (Released:2004-01-24)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 70
A water-soluble and low-molecular-weight fraction (SB) was obtained from tomato paste. The effects of SB on the formation of advanced glycation end-products (AGE) in protein glycation were studied by the methods of specific fluorescence, ELISA and a Western blot analysis, using the anti-AGE antibody after incubating protein with sugar. The results suggest that SB had strong inhibitory activity, in comparison with aminoguanidine as a positive control, and that the inhibitory mechanism of SB differed from that of aminoguanidine to involve trapping of reactive dicarbonyl intermediates in the early stage of glycation. SB contained an antioxidant, rutin, which showed potent inhibitory activity. The results also suggest that rutin chiefly contributed to inhibiting the formation of AGE, and that other compounds in SB may also have been related to the activity.
30 0 0 0 OA 鍼灸の起源を考える
- 著者
- 吉田 集而
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.623-637, 2000-11-01 (Released:2011-03-18)
30 0 0 0 OA 発達障害における遺伝性要因 (先天的素因) について
- 著者
- 神保 恵理子 桃井 真里子
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.215-219, 2015 (Released:2015-11-20)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
発達障害の中でも自閉症スペクトラム障害 (autism spectrum disorders ; ASD) は遺伝性要因が強い疾患である. 発症には, 多数の遺伝子の関与と共に, 遺伝子×環境性要因によるエピゲノム形成が示唆される. 罹患者の約40%にゲノム異常や遺伝子変異が検出されていることから, 今後の分子遺伝学的研究の進展は, 発症機序などの解明に不可欠である. これまでの解析から, ASD候補遺伝子はシナプス恒常性に関与するものが多い. 筆者らは, ASD特異的変異が惹起するシナプス機能性蛋白のloss-of-functionに加え, gain-of-functionの存在を示してきた. ASD, さらに合併疾患にも関与する共通分子機構の解明, 治療へと繋がることを期待したい.
- 著者
- 二木 立
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策 (ISSN:18831850)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.12-21, 2009-04-25 (Released:2018-02-01)
小泉政権の医療改革の新しさは,医療分野に新自由主義的改革方針を部分的にせよ初めて閣議決定したことである。それにより政権・体制内の医療改革シナリオが2つに分裂し,激しい論争が戦わされたが,最終的には「骨太の方針2001」に含まれていた3つの新自由主義的医療改革の全面実施は挫折した。他面,小泉政権は1980年代以降続けられてきた「世界一」厳しい医療費抑制政策をいっそう強め,その結果日本は,2004年には医療費水準は主要先進国中最低だが,患者負担は最高の国になった。安倍政権は大枠では小泉政権の医療費抑制政策を継承したが,ごく部分的にせよ,行き過ぎた医療費抑制政策の見直しも行った。さらに,政権・体制内での新自由主義派の影響力は急速に低下した。日本の医療制度の2つの柱を維持しつつ,医療の質を引き上げるためには公的医療費の総枠拡大が不可欠であり,そのための主財源としては社会保険料の引き上げが現実的である。
30 0 0 0 OA わが国の慢性透析療法の現況 (2022年12月31日現在)
- 著者
- 花房 規男 阿部 雅紀 常喜 信彦 星野 純一 谷口 正智 菊地 勘 長谷川 毅 後藤 俊介 小川 哲也 神田 英一郎 中井 滋 長沼 俊秀 三浦 健一郎 和田 篤志 武本 佳昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.12, pp.473-536, 2023 (Released:2023-12-28)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
日本透析医学会統計調査(JSDT Renal Data Registry:JRDR)の2022年末時点における年次調査は,4,521施設を対象に実施され,施設調査票に関しては4,464施設(98.7%),患者調査票に関しては4,276施設(94.6%)のほぼ例年通りの回答を得た.わが国の透析患者数は近年増加速度が低下していたが,2022年末の施設調査結果による透析患者数は347,474人と,この調査で初めて前年に比較して減少した.人口百万人あたりの患者数は2,781人であった.患者調査結果による平均年齢は69.87歳で,最も多い原疾患は糖尿病性腎症(39.5%),次いで慢性糸球体腎炎(24.0%),第3位は腎硬化症であった(13.4%).2022年の施設調査結果による透析導入患者数は39,683人であり,2021年から828人減少した.患者調査結果による透析導入患者の平均年齢は71.42歳であり,原疾患では糖尿病性腎症が最も多く38.7%で,昨年より1.5ポイント少なかった.第2位は腎硬化症(18.7%)で,昨年同様慢性糸球体腎炎(14.0%)を上回った.2022年の施設調査結果による年間死亡患者数は38,464人であり,前年に比較して大きく増加した.このことが全患者数の減少につながっている可能性がある.年齢調整がされていない年間粗死亡率も,過去最高の11.0%であった.主要死因は感染症(22.6%),心不全(21.0%),悪性腫瘍(7.6%)の順で,2022年は感染症が最も多かった.2012年以降,血液透析濾過(HDF)患者数は急増しており2022年末の施設調査票による患者数は191,492人で,維持透析患者全体の55.1%を占めた.腹膜透析(PD)患者数は10,531人で2017年から増加傾向にある.PD患者のうち20.3%は血液透析(HD)やHDFとの併用療法であり,この比率はほぼ一定していた.2022年末の在宅HD患者数は827人であり,2021年末から79人増加した.2022年は,新規調査として腎性貧血を行い,引き続き,新型コロナウイルス感染症,生体腎移植による腎提供の既往が調査された.2022年末の現況報告では,2018年以来行っていなかった腹膜透析の章も再開した.これらのデータはそれぞれの疾患・患者に関する基礎資料となり,その結果から,より治療効果の高い日常臨床パターンの提案が期待される.
30 0 0 0 OA 核融合開発とトリチウム人体影響 社会的受容性に関わる疑問点
- 著者
- 小松 賢志
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.12, pp.940-945, 1998-12-30 (Released:2009-03-31)
- 参考文献数
- 4
核融合実験炉建設計画に際して,トリチウム人体影響の推定が社会的な大きな関心を集めている。トリチウムによる人体影響を推定するには,原爆被爆者などγ線による人体障害とトリチウム生物実験により求められたRBEから推定しなければならない。現在までにトリチウムRBEに関しては膨大なデータが集積されているが,このうち発癌についてはRBE=2が妥当と思われる。これによれば, 1.4×108Bq (3.7mCi)のトリチウム摂取により1万人に1人の発癌リスクの増加が予想される。一方,体外被曝のγ線と異なり,トリチウムは水素同位体として生体構成成分と結合し,長期間にわたって被曝を続ける可能性がある。特にトリチウムのDNA結合能は遺伝子損傷に直結する可能性を含んでいる。しかし,細胞内に存在するDNA修復機構によりDNA損傷の大部分が修復されるために, DNA結合型トリチウムによるリスクの増加は体外被曝γ線のわずか2倍程度と見なされること,また実験室内モデルエコシステム実験によれば,トリチウムは生物濃縮されないことが推論された。一方,トリチウムの低線量率効果としては賀田効果とホルミーシス効果が知られている。賀田効果が生じる実験条件は試験管内の作用に限られているが,ホルミーシス効果は多くの生物系で報告されており,そのリスク推定における重要性から,実験値の信頼性やその作用機序など低線量率効果について,今後さらに検討する必要がある。
30 0 0 0 OA アレルギー性鼻炎と喫煙との関係
- 著者
- 橋本 佳明 二村 梓
- 出版者
- 公益社団法人 日本人間ドック学会
- 雑誌
- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.652-655, 2010 (Released:2013-07-31)
- 参考文献数
- 11
目的:喫煙習慣の有無によりアレルギー性鼻炎(以下鼻炎と略す)の有病率が異なるかどうかを検討した.対象:職域健診受診男性9,733名,女性3,071名.方法:生活習慣および常用薬剤情報は自記式アンケート調査で得た.有病率の比較はカイ2乗検定で,オッズ比はロジスティック回帰分析で求めた.成績:男性の鼻炎有病率は10.5%で,喫煙状態別では,非喫煙者14.5%,過去喫煙者10.6%,少量喫煙者(1~19本/日)9.7%,中等量喫煙者(20~39本/日)5.8%,多量喫煙者(40本以上/日)3.7%であった.重回帰分析により鼻炎と関連していた年齢で調整して,非喫煙者に対する鼻炎有病率のオッズ比を求めたところ,過去喫煙者0.76,少量喫煙者0.64,中等量喫煙者0.38,多量喫煙者0.25でいずれも有意に低値であった.一方,女性の鼻炎有病率は14.7%で,男性と比較し有意に高率であったが,非喫煙者では差が認められなかった.結語:鼻炎有病率は喫煙量が多いほど低率であることが判明した.また,鼻炎有病率は男性と比較し女性の方が高率であったが,この原因は喫煙量の違いによるものであると考えられた.
30 0 0 0 OA 日本の中絶の安全性は確認されたのか ―日本産婦人科医会の医師らによる中絶実態調査報告の見直し
- 著者
- 塚原 久美
- 出版者
- 日本女性学会
- 雑誌
- 女性学 (ISSN:1343697X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.79-100, 2021-03-31 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 32
Two different surveys have revealed that the surgical abortion method called dilatation and curettage (D&C) is the method of choice for many Japanese OB-GYN doctors for early-term abortions: less than 12 weeks into the pregnancy. The doctors who conducted the second research admit that D&C has a significantly higher rate of complications than the aspiration method. However, they conclude that “there are no major problems with the safety of abortion care in Japan.” This paper considers why the doctors have reached such a conclusion and whether this conclusion is valid. As a result of detailed examinations of the doctors’ report, we have found that the selection of the comparison data, the method of comparison, and the method of citation are inappropriate and unusual. They conclude based on their arbitrarily selected data, which could hardly be called rational. Although there are mistakes that could be mere carelessness or coincidence, we suspect that the authors are intentional because everything has been manipulated to make us believe that “abortion in Japan is safe.” Moreover, we have analyzed their request for cooperation in the questionnaire survey to find their strong intentions to prove the safety of abortion in Japan. Furthermore, the study concludes that the aspiration method is safer than D&C but contradictorily states that there is no major problem with the safety of abortion in Japan. Therefore their purpose of the study is to conclude that abortion in Japan is safe. Thus, it seems highly likely that the reporters have been influenced by the common interests of the medical association members. Their conclusions of the report are questionable, and there is little evidence to support the continued acceptance of the use of D&C.
- 著者
- 丸山 善宏
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.496-503, 2019-12-01 (Released:2020-03-01)
- 被引用文献数
- 3
Category theory was born within developments of algebraic topology in the midtwentieth century, and soon thereafter endorsed as the avant-garde, structural foundation of mathematics that liberates her from material set theory (or its ‘pernicious idioms’ as Wittgenstein calls them). Today it serves as a transdisciplinary foundation of the sciences, including, inter alia, physical, computational, and some social sciences. Despite the striking success in AI and NLP, applications to the life and cognitive sciences have been limited for various reasons. Here we present a critical perspective on an allegedly categorical theory of consciousness, yet another case of ‘fashionable nonsense’or a ‘new kind of science’, and in doing so, we elucidate what it consists in to define consciousness and alleged categories of it. We conclude with the moral of the discussion drawn in light of the epistemology of interdisciplinary studies whilst repurposing the Sokal/co-Sokal affair for a healthier ecology of discourse transgressing the boundaries.
30 0 0 0 OA 2010年宮崎で発生した口蹄疫について
- 著者
- 津田 知幸
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.2_71-2_76, 2011-02-01 (Released:2011-06-18)
- 参考文献数
- 1
30 0 0 0 OA 心霊現象における実証的研究(<特集>幽霊・ポルターガイスト, 第38回日本超心理学会大会)
- 著者
- 小林 信正
- 出版者
- 日本超心理学会
- 雑誌
- 超心理学研究 (ISSN:1343926X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1-2, pp.6-14, 2005-12-09 (Released:2017-08-09)
- 参考文献数
- 15
- 著者
- Hisaki EITO Masataka MURAKAMI Chiashi MUROI Teruyuki KATO Syugo HAYASHI Hiroshi KUROIWA Masanori YOSHIZAKI
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.4, pp.625-648, 2010 (Released:2010-10-05)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 15 17
During a cold-air outbreak, a broad cloud band is occasionally observed over the Japan-Sea Polar-Airmass Convergence Zone (JPCZ) that forms over the Sea of Japan from the base of the Korean Peninsula to the Japanese Islands. On 14 January 2001, a broad cloud band associated with the JPCZ (JPCZ cloud band) extended in a southeastward direction from the base of the Korean Peninsula to Wakasa Bay, and it stagnated for half a day. The JPCZ cloud band consisted of two cloud regions: one was a long cloud band extending along its southwestern edge (a developed convective cloud band), and the other was the region consisting of cloud bands normal to a wind direction of winter monsoon (transversal cloud bands). The structure and formation mechanism of the transversal cloud bands were examined on the basis of observations (e.g., satellite images, in situ measurement and cloud-pro.ling radar data from an instrumented aircraft and upper-air soundings from observation vessels) and simulation results of a cloud-resolving model with a horizontal resolution of 1 km.The transversal cloud bands had the following characteristic structures; they extended along a northeast-southwest direction, which was parallel to the direction pointed by the vertical shear vector of horizontal wind in the mixed layer, they mainly consisted of convective clouds, which slanted with height toward the down-shear side, and they widened and deepened toward southwest, as the depth of the mixed layer increased. An examination of simulation results presented that the transversal cloud bands were accompanied by roll circulations. The axes of rolls were oriented nearly parallel to the direction of the vertical shear vector in the mixed layer. An analysis of the eddy kinetic energy budget indicated that the roll circulations derived most of its energy from the mean vertical shear and the buoyancy.
- 著者
- Makoto Okamoto Kouji Matsuda Tamaki Matsuda
- 出版者
- The Japanese Society of Systematic Zoology
- 雑誌
- Species Diversity (ISSN:13421670)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3-4, pp.131-138, 2010-12-30 (Released:2018-03-30)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1 1
A pelagic juvenile (43.0mm standard length) of the morid Gadella jordani (Bohlke and Mead, 1951) was collected from Kagoshima Prefecture, southern Japan. It has a characteristically elongated body, long dorsal and anal fin bases with 73 rays in each fin, the anus located more anteriorly than the origin of the second dorsal fin, a ventral light organ, and no chin barbel. We describe the morphology of this specimen and also present a color photograph of it in life. This is the first report of any early life stage in this species.
30 0 0 0 OA アイヌ政策の実現に向けて
- 著者
- 加藤 忠
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.9, pp.9_96-9_99, 2011-09-01 (Released:2012-01-24)
- 参考文献数
- 2
- 著者
- 布施 綾子
- 出版者
- システム農学会
- 雑誌
- システム農学 (ISSN:09137548)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.55-62, 2011-04-10 (Released:2015-06-04)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 4
都市部におけるイノシシによるヒトへの危害防止を目的として、2002 年に神戸市において日本で初めて「イノシシ餌付け禁止条例」が制定された。条例が施行され8 年以上が経過したが、条例制定の前後でイノシシの出没状況がどのように変化したかは明らかにされていない。本研究の目的は山林に隣接した神戸市六甲山南部の市街地のイノシシの出没状況と住民の意識から、イノシシとヒトとの関わり方について検討することにある。まず、条例施行前の2000~2001 年に神戸市東灘区天上川流域にてイノシシの出没状況を調査した。次に、条例施行後の2009 年9~12月に、イノシシの出没現場踏査、インタビュー調査、アンケート調査、イノシシの追跡調査、イノシシに対するヒトの意識調査を行った。結果は、条例施行後は道路上でのイノシシ出没頻度は減少し、イノシシへの間接的な餌付け場所となるゴミ集積場での被害も減少することを示した。一方で、河床に生存するイノシシの個体数は増えていることが観測され、河床の段差工の高低差が大きく山に帰る事ができず封じ込め状態にある事が明らかになった。また、市民の条例に対する認識度は74%と高いにも関わらず、天上川河床に生息するイノシシへの直接的な餌付け行為は継続されていた。河床のイノシシに対するヒトの意識は好意的なものが多く、餌付けは感情に基づいたものと言える。餌付け禁止条例の効果はある程度認められたが、今後イノシシとヒトとの適切な関わりを構築するには、イノシシの生息環境やヒトの感情に配慮した施策が求められる。