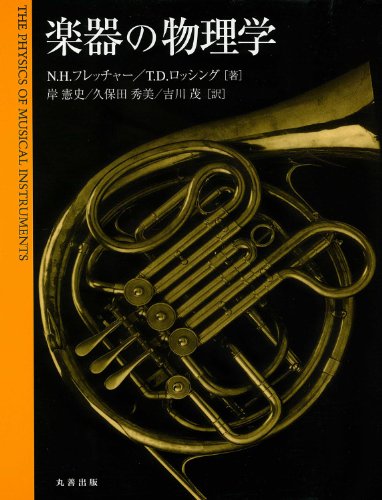1 0 0 0 新しい検眼用フレームの開発と試用経験
- 著者
- 清水 みはる 稲泉 令巳子 寺本 恵美子 澤 ふみ子 中村 桂子 内海 隆 上野 正人
- 出版者
- 公益社団法人 日本視能訓練士協会
- 雑誌
- 日本視能訓練士協会誌 (ISSN:03875172)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.75-82, 1997
検眼用フレームとして現在普及しているものはフィット感や重さ,耐久性が十分とは言い難く,満足できるのがないのが現状である。そこで使いやすさや耐久性を重視し,またカラフルな色彩を採用した検眼用フレームの開発・改良に参加し,試用する機会を得たので報告する。対象は平成8年2月1日から同9月30日までの8ヶ月の間に大阪医科大学附属病院眼科外来を受診した患者のうち,無作為に抽出した2980名と高槻市3歳児検診を受診した350名である。方法は従来からの固定三重枠<sup>®</sup>((株)はんだや)およびシンプルBC<sup>®</sup>((株)高田巳之助商店)を対照に,今回新しく開発した検眼用フレーム(増永眼鏡(株))と比較検討した。新しいフレームは材質としてホルダー部分には抗菌作用や耐磨耗性,強靱性のあるエンジニアリングプラスチックを用い,金属部分にはチタンを使用しているのでかなり軽量である。フィッティングを良くするための独自の工夫と子供が受け入れ易いように配慮したカラフルな色彩が特徴である。結果として,新しいフレームはレンズの装着感が良く,検者側からの評価も高く,患者の満足度も十分で,眼鏡処方時の長時間の装用テストにおいても好評であった。明るい色合いは小児に特に好まれた。今後の実用化が期待される。
- 著者
- 金子 功一 江部 靖子
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.E4P1212, 2010
【目的】近年,在宅生活者の環境面で身体機能面以外にも様々な問題が生じ,在宅生活の継続が困難となっている事例がしばしば様々なメディアで取り上げられている事は周知の通りである.当診療所訪問リハビリテーション(以下,訪問リハ)でもその様な事例を経験している.本研究は,それらの事例を再度確認し,経過・対応方法などを検討し今後の更なる訪問リハ業務の質の向上を目指す目的で実態調査を行った.若干の考察を加え報告する.【対象者と方法】対象者は2002年1月から2009年9月までの訪問リハ利用者298名のうち,明らかに目的で述べた様な状況の5名(男性1名,女性4名)である.方法は対象者の属性に加え,1)対象者側と介護者が抱える問題点,3)訪問リハ介入時難渋した点,4)各事例への対応方法,5)その後の経過を訪問リハ記録より後方視的調査を行った.【説明と同意】その状況上全ての対象者に説明を行なってはいないが,ヘルシンキ宣言と個人情報保護法に基づき,一部の対象者・家族に本研究を説明し,同意を得た.また全事例の担当ケアマネ,介入した行政機関など連携を取った他職種にも同様に同意を得た.調査結果は研究目的以外に使用しない事と個人情報の漏洩に十分に注意した.【結果】1.対象者の属性は,要介護度と寝たきり度の内訳,対象者の家族構成について調査を行った.1)要介護度の内訳は,要介護2が1名,同3が2名,同5が2名であった.2)寝たきり度の内訳はA-2が2名,B-1が1名,C-1が1名,C-2が2名であった.3)家族構成の内訳については,息子と2人暮らし-2名,夫と2人暮らし-1名,妻もしくは夫と子供の3人以上の家族構成-2名であった.<BR>2.対象者と介護者が抱える問題点は以下の通りである(複数回答).1)対象者の抱える問題点は,認知症-3名,精神疾患-3名(うつ状態-2名,統合失調症-1名),その他-2名であった.2)介護者の抱える問題点は,介護放棄-4名,精神疾患-3名(うつ状態-2名,統合失調症-1名),暴力・虐待(ドメスティックバイオレンス含む)-3名,アルコール依存症-2名であった.対象者と介護者が共に何らかの問題点を複数抱えている事例も見られた.<BR>3.訪問リハの介入時難渋した点は,1)対象者への様々なアプローチが困難・時間要す-4名,2)主介護者・家族への介護方法指導が困難-4名,3)他職種と連携が取りにくい-3名,4)訪問リハの介入が困難な環境-2名,5)その他-2名であった(複数回答).<BR>4.各事例の対応は1)頻回なサービス担当者調整会議の開催-5名,2)地域包括支援センターに連絡(担当ケアマネ経由)-5名,3)対象者・介護者の訴えを傾聴,主張の一部受け入れなど-3名であった.4)警察へ通報(緊急時.ケアマネ経由)も2例存在していた(複数回答).<BR>5.その後の経過は,1)終了-3名,2)訪問リハ継続-2名であった.終了事例の内訳は,施設緊急入所-2名,他サービスに移行-1名であった.【考察】1.対象者の要介護度・寝たきり度が軽度でも,何らかの問題を抱えている事例がいた.高次脳機能障害や精神疾患の存在が訪問リハの定期的な継続の妨げになることを再認識した.また調査前,少ない家族構成の対象者に社会的な問題点が生じると考えたが対象者以外の複数の家族が問題点を抱える事例もあった.家族構成と関係なく何らかの問題が起こる可能性がある事が考えられた.<BR>2.対象者と介護者の抱える問題は予想通り多岐にわたっていた.対象者と介護者の両方に何らかの問題が複数あり訪問リハの介入,スムーズな継続を困難にしていた事例も存在した.介護者の暴力・虐待などの背景に複雑な家族関係が存在する事は諸家の報告で明らかにされている.他職種との連携が必須であると考えられえる.<BR>3.しかしながら,介護者の存在が時にはその連携の妨げになっている事例も存在する.本調査でも同様であり通常の事例よりも他職種との連携をより重要視して訪問リハに関わる必要があると考えられる.<BR>4.本調査では全事例において,困難な中でも比較的緊密に他職種と連携が取られていた.これは訪問リハ単独で問題を解決せず他職種と連携して関わる事を担当が意識していたためと考えられる.対象者・介護者へも介入し,関係を改善しようとする担当の姿勢も見られた.ただし,警察への緊急通報,施設へ緊急入所に至った事例もあり,在宅での訪問リハの介入の限界も明らかになった. 訪問リハに従事する理学療法士は理学療法の知識・技術だけではなく他職種と連携し様々な視点で対象者と介護者・家族に関わっていく事が大切である.【理学療法研究としての意義】訪問リハの実践に際しては,対象者の身体機能面へのアプローチだけでなく,その在宅生活全体を取り巻く物理的・社会的環境面へも合わせてアプローチを行なっていく必要がある.しかしながら,その施行に当たって様々な阻害因子が存在している事もまた事実である.様々な面で在宅介護の情勢が変化している昨今,本調査では決して対象者が多いわけではないが, 調査結果はその現状を端的に示唆したといえる.
1 0 0 0 OA 神経幹細胞の足場としての高分子ハイドロゲルの解析 [全文の要約]
- 著者
- 谷川 聖
- 巻号頁・発行日
- 2018-03-22
北海道大学. 博士(医学)
- 著者
- 小久保 諭 梶島 邦江
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. F-1, 都市計画, 建築経済・住宅問題 (ISSN:13414534)
- 巻号頁・発行日
- no.2006, pp.923-924, 2006-07-31
1 0 0 0 OA 大谷エリアにおける環境資源と冷熱エネルギー活用に関する研究
- 著者
- 吉澤 彰太郎 横尾 昇剛
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 平成29年度大会(高知)学術講演論文集 第10 巻 都市・環境 編 (ISSN:18803806)
- 巻号頁・発行日
- pp.161-164, 2017 (Released:2018-10-20)
木県宇都宮市の大谷地域は大谷石の町として栄えてきたが、新建材や海外産材の台頭により、大谷石産業が衰退し、地域全体で耕作放棄地や空き家の増加が進んでいる。このような背景で地域の再生が求められており、地域資源を活用した方策が必要となる。本研究は、大谷地区の地域資源の情報整備と、地下貯留水利用による冷熱システムの検証と効果の把握などを目的とする。
1 0 0 0 OA 相双海岸における丘陵・段丘の開析形態
- 著者
- 中村 嘉男
- 出版者
- THE TOHOKU GEOGRAPHICAL ASSOCIATION
- 雑誌
- 東北地理 (ISSN:03872777)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.172-178, 1967 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 17
In the coastal area of Fukushima Prefecture, there develops a series of landforms consisting of hills 100-50m in height, terraces 50-30m, and alluvial plains. The valleys dissect the hills and terraces, both of which consist of Pliocene sandstone or siltstone. There are two types of valley forms in transverse profiles, concave valley (Muldental) and V-shaped valley (Kerbtal, partly Sohlen-kerbtal). These two types are systematically distributed due to the topographical location, and Muldental is accompanied with an undulating landform of small relief, and Kerbtal with linear or convex slope of relatively large relief.As the undulating landform is introduced from an almost flat plane by means of surface denudation, sufficient running water and potential relief are not always necessary for its formation. On the other hand, Kerbtal can not be formed without sufficient water and potential relief enough to undercut the channel bed. Consequently, the undulating landform is in the core area of hills and terraces, free from the Kerbtal development which is seen in areas with linear slopes surrounding the core area.Where the undulating and the linear slopes exist side by side, there appear breaks of hillslopes, knickpoints, in the longitudinal profiles of streams, and so on, forming a front line of topographic unconformity.The undulating landform area and the linear landform area can be distinguished each other, and patterns of the spatial combination of both areas appear in various features of hill morphology.
1 0 0 0 近代日本の小学校における柔道教育の歴史的研究
1 0 0 0 頬部に発生した炎症性偽腫瘍例
- 著者
- 平田 智也 石永 一 竹内 万彦
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.12, pp.775-780, 2020
<p>Inflammatory pseudotumor is a benign disease that is histopathologically characterized by the presence of non-specific chronic inflammatory cells. Clinically, these tumors often show neoplastic growth, and it is difficult to differentiate them from neoplastic lesions by imaging findings alone. Inflammatory pseudotumors have been found to occur at various sites, but are rarely found in the head and neck region. Although surgical excision and steroid therapy are effective, no evidence has been established yet. We report a case of an inflammatory pseudotumor that occurred in the cheeks.</p><p>A 51-year-old man with right cheek swelling and pain had visited a local physician a month earlier and antibiotics had been prescribed. Since the symptoms did not improve, CT was performed as an aid to diagnosis, and an abscess or neoplastic lesion was suspected in the cheek. Cytologic examination revealed many neutrophils and histiocytes, but no evidence of malignancy. MRI showed an abscess in the masseter muscle with spread of the inflammation to the surrounding tissues. Antibiotics and steroid therapy were initiated and the swelling diminished in size. When the steroid was withdrawn, the swelling enlarged again. Therefore, inflammatory pseudotumor, non-epithelial tumor, and malignant lymphoma were considered in the differential diagnosis. An excisional biopsy was performed and the diagnosis of inflammatory pseudotumor was established. A subset of the cells was positive for IgG4, but there was no definitive evidence of IgG4-related diseases.</p><p>Treatment of inflammatory pseudotumors includes surgical resection, steroid therapy, radiation therapy, chemotherapy; the efficacy of steroid therapy has been reported for inflammatory pseudotumors in the head and neck region. Although evidence has still not been established, steroid maintenance therapy is effective for preventing recurrence. The patient is currently receiving steroid maintenance therapy on an outpatient basis, and has shown no evidence of recurrence of the inflammatory pseudotumor.</p>
- 著者
- 神野 真吾 竹田 美和 茜 俊彦 平田 智也 久野 尚志 羊 億 磯貝 佳孝 渡邊 直樹 藤原 康文 中村 新男
- 出版者
- 日本結晶成長学会
- 雑誌
- 日本結晶成長学会誌 (ISSN:03856275)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, 2002
ErP/InP heterostructure is one of the candidates for realizing new functional high-speed magneto-electronic devices. We have investigated growth morphology of ErP on InP (001) and (111)A. ErP/InP heterostructures were grown by face-down OMVPE. ErP formed islands on each orientation, while island size and height were quite different between two orientations.
1 0 0 0 OA 軍港都市横須賀における商工業の展開と「御用商人」の活動 : 横須賀下町地区を中心として
- 著者
- 双木 俊介
- 出版者
- 筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学専攻歴史地理学研究室
- 雑誌
- 歴史地理学野外研究 (ISSN:09152504)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.55-80, 2010-03
1 0 0 0 楽器の物理学
- 著者
- N.H. フレッチャー T.D. ロッシング著 岸憲史 久保田秀美 吉川茂訳
- 出版者
- 丸善出版
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 OA 世界および日本における風力発電の普及状況と導入支援制度
- 著者
- 七原 俊也
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.1, pp.12-16, 2004-01-01 (Released:2008-04-17)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 8 4
1 0 0 0 IR 仏教・神祇そして密教へ : 大通智勝仏信仰の展開
- 著者
- 頼富 本宏
- 出版者
- 龍谷大学佛教文化研究所
- 雑誌
- 佛教文化研究所紀要 (ISSN:02895544)
- 巻号頁・発行日
- no.45, 2006-11-30
1 0 0 0 OA 拡散方程式モデルを用いたファッションアパレルの商品力と販売力の考察
- 著者
- 高橋 正人 大谷 毅
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.5, pp.497-502, 2017 (Released:2017-12-26)
- 参考文献数
- 12
In fashion Business, turnover of stores is decided by the product appeals of fashion apparels and selling capacity of the fashion apparel store. In order to increase the turnover, the selection of apparel goods which are preferred by consumers of the shop is most important. Next, the selling capacity is important. In previous papers, we discussed about the relation between apparel goods and consumers. Fashion apparel is thought to be a carrier of the information which is proposed by the fashion designer. On this account, we assumed the purchase and sale of fashion apparels are the diffusion phenomena of the information in the behavioral space. From the point of view, we propose a mathematical model describing the purchase and sale of the fashion apparels.
1 0 0 0 IR 看護活動から導かれた職種間連携・協働を推進する要素
- 著者
- 古川 直美
- 出版者
- 岐阜県立看護大学
- 雑誌
- 岐阜県立看護大学紀要 (ISSN:13462520)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.99-110, 2019-03
本研究の目的は、看護基礎教育における職種間連携・協働に関する教育内容の示唆を得るために、職種間連携・協働の実践事例から、看護の専門性に立脚した職種間連携・協働を推進する要素を明確化することである。 対象は、病院(病棟、退院調整部門、外来部門)、福祉施設(特別養護老人ホーム)、市町村保健センター、訪問看護ステーションにおいて、中心的役割を果たしている看護職6 名である。職種間連携・協働が円滑に展開できた事例、円滑に展開できなかった事例について、聞き取り調査を実施した。逐語録から、職種間連携・協働に関わる部分を抽出・解釈し、職種間連携・協働を推進する要素として分類した。 職種間連携・協働を推進する要素は、【原動力となる信念・動機がある】、【利用者に提供される医療・介護サービスの中や、他職種との関係の中で、看護の業務・責務を位置づける】、【必要なケアの判断及びケアの実施に向けてネットワークを拡げる】、【医療チーム・ケアチームでの活動が成立するよう働きかける】、【他職種の方針・判断を把握し、看護の判断・見解を踏まえて調整を図る】、【他職種・他部門・他機関で助け合い、補い合う】、【主体である利用者の参加を支援する】、【取り組みの結果を確認し、学びを得る】、【利用者・他職種・他部門・他機関に看護の役割・機能の理解を促す】、【他部門・他機関と繋がるための基盤を作る】、【ケアの充実に取り組む職場の風土がある】の11 に分類された。 先行研究における職種間連携・協働で重視されていること等の検討から、見いだされた11 の要素は、職種間連携・協働の推進に必要な要素と捉えられた。教育内容としては、原動力となる信念・動機をもつことやチーム活動の展開等に関わる内容が考えられたが、実践現場における継続教育が適することもあるため、看護基礎教育で何をどう教育するか検討が必要である。
- 著者
- Megumi Ueno Takashi Shimokawa Emiko Sekine-Suzuki Minako Nyui Ikuo Nakanishi Ken-ichiro Matsumoto
- 出版者
- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN
- 雑誌
- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.123-130, 2021-03-01 (Released:2021-03-01)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 2
Relatively young (4-week-old) selenium deficient (SeD) mice, which lack the activity of selenium-dependent glutathione peroxidase (GSH-Px) isomers, were prepared using torula yeast-based SeD diet. Mice were fed the torula yeast-based SeD diet and ultra-pure water. Several different timings for starting the SeD diet were assessed. The weekly time course of liver comprehensive GSH-Px activity after weaning was monitored. Protein expression levels of GPx1 and 4 in the liver were measured by Western blot analysis. Gene expression levels of GPx1, 2, 3, 4, and 7 in the liver were measured by quantitative real-time PCR. Apoptotic activity of thymocytes after hydrogen peroxide (H2O2) exposure was compared. Thirty-day survival rates after whole-body X-ray irradiation were estimated. Pre-birth or right-after-birth starting of the SeD diet in dams was unable to lead to creation of SeD mice due to neonatal death. This suggests that Se is necessary for normal birth and healthy growing of mouse pups. Starting the mother on the SeD diet from 2 weeks after giving birth (SeD-trial-2w group) resulted in a usable SeD mouse model. The liver GSH-Px activity of the SeD-trial-2w group was almost none from 4 week olds, but the mice survived for more than 63 weeks. Protein and gene expression of GPx1 was suppressed in the SeD-trial-2w group, but that of GPx4 was not. The thymocytes of the SeD-trial-2w group were sensitive to H2O2-induced apoptosis. The SeD-trial-2w group was sensitive to whole-body X-ray irradiation compared with control mice. The SeD-trial-2w model may be a useful animal model for H2O2/hydroperoxide-induced oxidative stress.
- 著者
- Atsushi Kyodo Makoto Watanabe Akihiko Okamura Saki Iwai Azusa Sakagami Kazutaka Nogi Daisuke Kamon Yukihiro Hashimoto Tomoya Ueda Tsunenari Soeda Hiroyuki Okura Yoshihiko Saito
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-20-0759, (Released:2021-01-27)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 4
Background:The association between unfavorable post-stent optical coherence tomography (OCT) findings and subsequent stent thrombosis (ST) remains unclear. This study investigated the ST-related characteristics of post-stent OCT findings at index percutaneous coronary intervention (PCI).Methods and Results:Fifteen patients with ST onset after OCT-guided PCI (ST group) were retrospectively enrolled. Post-stent OCT findings in the ST group were compared with those in 70 consecutive patients (reference group) without acute coronary syndrome onset for at least 5 years after OCT-guided PCI. The incidence of acute myocardial infarction (AMI) was higher in the ST than reference group (60.0% vs. 17.1%, respectively; P=0.0005). The incidence of incomplete stent apposition (93.3% vs. 55.7%; P=0.0064), irregular protrusion (IP; 93.3% vs. 62.8%; P=0.0214), and thrombus (93.3% vs. 51.4%; P=0.0028) was significantly higher in the ST than reference group. The maximum median (interquartile range) IP arc was significantly larger in the ST than reference group (265° [217°–360°] vs. 128° [81.4°–212°], respectively; P<0.0001). In AMI patients, the incidence of a maximum IP arc >180° was significantly higher in the ST than reference group (100% vs. 58.3%, respectively; P=0.0265).Conclusions:IP with a large arc was a significant feature on post-stent OCT in patients with ST.
1 0 0 0 OA 同一斜面上に生育するヒノキとミズナラ根重の垂直分布に関する知見
- 著者
- 小見山 章 大根 瑞江 加藤 正吾
- 出版者
- THE JAPANESE FORESTRY SOCIETY
- 雑誌
- 日本林学会誌 (ISSN:0021485X)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.2, pp.152-155, 2003-05-16 (Released:2008-05-16)
- 参考文献数
- 11
比較的若齢の造林地が豪雨等で崩壊すると, 広葉樹に較べてヒノキやスギが浅根を示すことがその原因であるといわれることが多い。このことを再検討するために, 48年生のヒノキ造林地で, ヒノキ主林木とそこに侵入したミズナラの根重の垂直分布を比較した。2本の試料木を選んで, 地上部に関する調査を行った後に, 深さ60cmまでに存在する根をトレンチ法により採取した。深さあたりの根重密度の垂直分布パターンを求めたところ, 指数関数にしたがう減少パターンを示した。2本の試料木問で, 深さ方向の根重密度の減少率に有意差は認められなかった。回帰式を積分して個体根重の垂直分布を計算した。地表から30cmまでの深さに含まれる根重の割合は, ミズナラ試料木で89%, ヒノキ試料木で94%となり, 試料木間で根の垂直分布に極端な違いは認められなかった。また, 傾斜地で, ヒノキ試料木は根を谷側に多く配置していたのに対して, ミズナラ試料木は山側に多く配置するという, 根の水平分布上の違いが認められた。