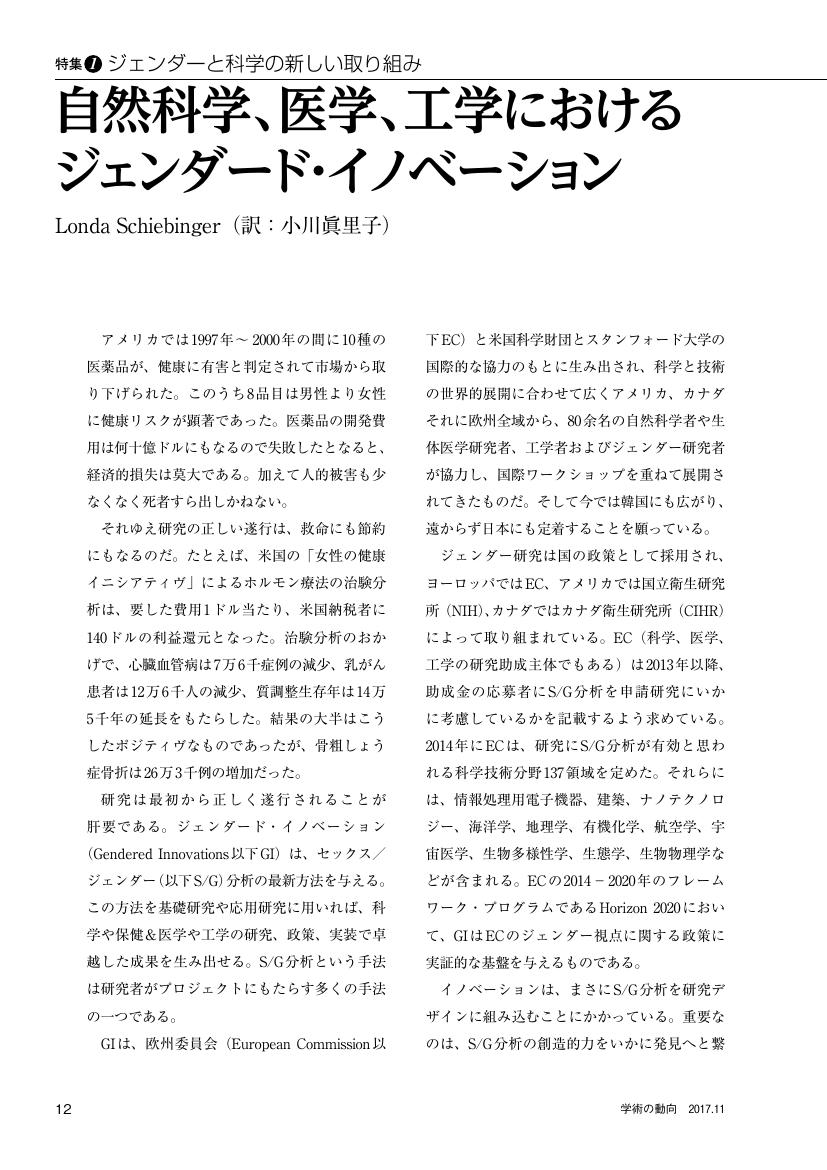3 0 0 0 OA 信頼とコミットメント形成
- 著者
- 山岸 俊男 山岸 みどり 高橋 伸幸 林 直保子 渡部 幹
- 出版者
- The Japanese Group Dynamics Association
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.23-34, 1995-07-30 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 10 12
人間性の善良さに対する信念として定義される, 他者一般に対する信頼である一般的信頼と, コミットメント関係にある特定の相手が, その関係の中で自分に対して不利な行動を取らないだろうという期待として定義される個別的信頼との間で, 理論的区別が行われた。社会的不確実性に直面した場合, 一般的信頼が低い人々は, そこでの不確実性を低減するためにコミットメント関係を形成する傾向が強いだろうという理論に基づき, 売手と買手との関係をシミュレートした実験を行った。実験の結果, 社会的不確実性と被験者の一般的信頼の水準が (a) 特定の売手と買手との間のコミットメント形成および (b) 個別的信頼に対して持つ効果についての, 以下の仮説が支持された。第1に, 社会的不確実性はコミットメント形成を促進した。第2に, コミットメント形成はパートナー間の個別的信頼を促進した。第3に, 上の2つの結果として, 社会的不確実性は集団内での個別的信頼の全体的水準を高める効果を持った。第4に, 人間性の善良さに対する信念として定義される一般的信頼は, コミットメント形成を妨げる効果を持った。ただし, 第2と第4の結果から予測される第5の仮説は支持されなかった。すなわち, 一般的信頼は個別的信頼を押し下げる効果は持たなかった。
- 著者
- Naoya Shimada Yukiko Okuda Kaisei Maeda Daisuke Umeno Shinichi Takaichi Masahiko Ikeuchi
- 出版者
- Applied Microbiology, Molecular and Cellular Biosciences Research Foundation
- 雑誌
- The Journal of General and Applied Microbiology (ISSN:00221260)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.116-120, 2020 (Released:2020-06-17)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2 9
Heterologous production of a useful carotenoid astaxanthin was achieved in a cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 with the aid of marine bacterial genes. Astaxanthin and its intermediates emerged at high levels, whereas β-carotene and zeaxanthin disappeared in the strain. Total carotenoid accumulation was nearly two fold compared with wild type. The astaxanthin-producing strain was capable of only growing heterotrophically, which was likely due to the absence of β-carotene. Further enhanced accumulation was pursued by gene overexpression for possible rate-limiting steps in the biosynthesis pathway.
3 0 0 0 OA はやぶさ試料分析の今
- 著者
- 松本 徹
- 出版者
- 日本惑星科学会
- 雑誌
- 日本惑星科学会誌遊星人 (ISSN:0918273X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.68-76, 2019-03-25 (Released:2019-08-16)
本稿では最近のイトカワ粒子の研究についてレビューする.イトカワの母天体では熱変成が進んでいたと考えられるが,その内部では岩石の隙間をH2O氷と有機物由来の流体が流れていた痕跡が見つかった.この母天体が破壊されて小惑星イトカワが形成したタイミングはArやU-Pbの同位体比を用いた年代測定から推定されている.イトカワの形成後,その表面では太陽風や微小隕石の衝突による宇宙風化(反射スペクトルの変化)が進んでいたが,レゴリスの流動や粒子の破砕が活発に起こり宇宙風化の進行を妨げていた証拠が示された.粒子の表面に見つかった数多くの微小な衝突クレーターは,小天体を取り巻く微小ダストの特性を知る手がかりになるのかもしれない.
3 0 0 0 OA 日本人アスリートの身体部分慣性特性の推定
- 著者
- 阿江 通良 湯 海鵬 横井 孝志
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム (ISSN:13487116)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.23-33, 1992-05-20 (Released:2016-12-05)
- 被引用文献数
- 131 262
Inertia properties of the body segments such as segment mass, location of the center of mass, and moment of inertia can be measured and predicted in a number of ingenious approaches. They can be classified into a) direct measurements on cadavers, b) indirect measurements on living subjects, and c) mathematical modelling. However, there is little information upon which complete inertial estimates for Japanese people, especially male and female athletes, can be based. The purposes of this study were to determine the mass, center of mass location, and moments of inertia of the body segments for Japanese male and female athletes using a mathematical modelling approach, and to develop a set of regression equations to estimate inertia properties of body segments using simple anthropometric measurements as predictors. Subjects were 215 male and 80 female athletes belonging to various college sport clubs. Each subject, wearing swimming suit and cap, was stereo-photographed in a standing position. Ten body segments including the upper and lower torso were modelled to be a system of elliptical zones 2cm thick based on Jensen and Yokoi et al. Significant prediction equations based on body height, body weight, and segment lengths were then sought, and some prediction strategies were examined. The results obtained were summarized as follows: 1) Table 2 provides a summary of mass ratios, center of mass location ratios and radius of gyration ratios for males and females. There were many significant differences in body segment parameters between the two sexes. This suggests the need to develop different prediction equations for males and females. 2) Close relationships were noted between segment masses and segment lengths and body weight as predictors for all body segments. Table 5 provides coefficients of multiple regression equations to predict segment masses. 3) No close relationship was noted between independent variables and estimates of the center of mass location. This indicates that the variance in the center of mass location in proportion to the segment length was very small, and that location of centers of mass could be estimated by the mean ratio provided in Table 2. 4) Close relationships were noted between segment moments of inertia and segment lengths (except hand and foot), and body weight as predictors. Tables 6 and 7 provide coefficients of multiple regression equations to predict segment moments of inertia from segment lengths and body weight.
3 0 0 0 OA 韓流ブーム下での大阪・生野コリアタウンの変容 -エスニック・タウンの価値と地域活性化-
- 著者
- 福本 拓
- 出版者
- 地理空間学会
- 雑誌
- 地理空間 (ISSN:18829872)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.231-251, 2020 (Released:2021-03-16)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
本稿の目的は,SNS等を基盤にグローバルな展開を見せる韓流ブーム下での,生野コリアタウンの観光地化に伴う変容と,地域活性化への課題を明らかにすることにある。2000年代以降,テイクアウト品や化粧品等の新たな消費嗜好に合わせた店舗が増大し,生野コリアタウンとその周辺では地価上昇や店舗の分布範囲の拡大がみられる。またアンケート調査からは,新たに増加した観光客の行動や意識が同地の歴史的特性や日韓の政治問題とは遊離しているものの,それらへの学習意欲が弱いわけではないことが看取された。既存の商店は,経済的価値の向上という部分では近年の変容を肯定的に捉えているが,多文化共生に資するような社会的価値に対しては,過去や現在の諸種の対立・軋轢により関与が難しい状況がある。しかし,後者もまた地域固有の歴史性としてエスニック・タウンの魅力を構成する一要素であり,地域活性化にとって経済的価値と併せて欠かせないものである。
3 0 0 0 OA 保険制度外の訪問看護の実態に関する調査研究
- 著者
- 木全 真理
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.329-335, 2017 (Released:2018-02-09)
- 参考文献数
- 19
目的:本研究は,保険制度外の訪問看護の実践を把握し,その実践をする訪問看護ステーションの特性を明らかにする.方法:多職種が協働する場への参加がある5地域の訪問看護ステーション145カ所に,保険制度外の訪問看護の実態,事業所の体制に関する自記式質問紙を郵送した.分析は保険制度外の訪問看護実践の有無の2群に分けて,事業所の体制の属性を比較検討した.結果:有効回答は58カ所,そのうち20件に保険制度外の訪問看護の実践があった.その実践は,利用者が看護を受けたい,家族が家庭内の役割を担いたい,という理由が多かった.保険制度外の訪問看護の実践は,職員の実人数,利用者の人数や延べ訪問回数,保険制度外の訪問看護の自費設定をしていた事業所が多かった.両群では多職種協働する場への参加に差はなかった.結論:保険制度外の訪問看護は,規模の大きい事業所が利用者や家族からのニーズを汲み取り,実践に組み替えていた.
3 0 0 0 OA サツマイモの生産性
- 著者
- 藤瀬 一馬
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.53-57, 1985-03-01 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 15
3 0 0 0 OA 加賀藩の瞽女と瞽女唄
- 著者
- ジェラルド グローマー
- 出版者
- The Society for Research in Asiatic Music (Toyo Ongaku Gakkai, TOG)
- 雑誌
- 東洋音楽研究 (ISSN:00393851)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.59, pp.23-42,L2, 1994-08-31 (Released:2010-02-25)
The Kaga domain of the Tokugawa period (1603-1868) comprises what are today Toyama and Ishikawa Prefectures. In the past, many blind female performers known as goze wandered throughout this area, singing songs and playing the shamisen. Although the goze of neighboring Niigata Prefecture have been the subject of much research and documentation, the goze of the Kaga domain have as yet received almost no scholarly attention. This study seeks to fill this gap.Records of goze in the Kaga domain go back to 1619, when blind entertainers were sent to entertain the widow of the first head of the domain. Records of goze living in rural villages around Kanazawa also exist from the early seventeenth century.In the Toyama area, goze are recorded as being affiliated with a temple in the city of Takaoka. Later, these goze appear to have entertained visitors to the city's pleasure quarters. Both in Toyama and Ishikawa Prefectures, goze seem not to have formed the types of guilds that one finds in Niigata Prefecture.The last renowned goze of the Toyama area was Matsukura Chiyo (1884-1946, also known as “Chiima”). Recordings of her performances are almost entirely lacking, but people of the area still remember her songs and her activities. The latter half of this study attempts to reconstruct Matsukura's life, tours, and repertory. Several musical examples of performances as remembered by natives of Toyama Prefecture are presented, as is a photograph of Matsukura and her daughter Hana.
3 0 0 0 OA 挙国一致内閣期における立憲民政党 : 民意への対応を中心として
- 著者
- 井上 敬介
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.6, pp.1122-1143, 2008-06-20 (Released:2017-12-01)
The objective of the present article is to investigate the activities of the (Rikken-) Minsei Party (1927-1940) under Japan's national consensus governments of the 1930s, especially its extreme opposition to the claim that the will of the people was being usurped, leading to its refusal to form a government. To begin with, the author examines the process by which the Party decided upon a national consensus platform under the leadership of Wakatsuki Reijiro 若槻礼次郎. The Party's two main factions, led by Wakatsuki and Kawasaki Takukichi 川崎卓吉, respectively, reacted violently to the claim that that they had usurped the will of the people and chose to abandon any effort to form a partisan government. This claim came from the movement to reduce the sentences of the conspirators involved in the 15 May 1932 assassination of Prime Minister Inukai Tsuyoshi by a group of young naval officers, which held the Minsei Party responsible for the London Arms Limitations Treaty of 1930. On the other hand, the opposition faction formed within the Party by Ugaki Kazushige 宇垣一成 and Tomita Kojiro 富田幸次郎 took charge of movements to activate the party politics within the Diet and promote cooperation between the public and private sectors in attempts to find a way to form a Minsei Party government. Then the discussion turns to the efforts by Ugaki to form a new party from within after Wakatsuki stepped down in August 1934, followed by a wavering in the Party's national consensus line, and finally the establishment of such a platform under the leadership of Machida Chuji 町田忠治. The new party movement ended in failure after Ugaki's refusal to stand for party chairman, resulting in the election of Machida. Then leadership of the public-private sector cooperation movement was assumed by Kawasaki, while Tomita abandoned efforts to form a government. The 19^<th> party elections of 1936 pitted Tomita's call for partisan politics against Machida and Kawasaki's appeal for national consensus, as the Machida-Kawasaki line emerged victorious, from which time on, the Minsei Party made no further effort to form a partisan government in the world of Japanese politics following the 26 February 1936 coup d'etat attempt.
3 0 0 0 OA 各種酸類の酸味について (第1報)
- 著者
- 前田 清一 中尾 俊
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.149-154, 1963-06-20 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
酸類の酸味としての閾値(Stimulus Threshold Value)と最低閾値(Minimum Threshold Value)、及び酸類間の酸味の強さについて、味覚試験を用いて測定をおこなった結果 : -(1) Panelの識別能力は非常に優秀なものであり、なかでも、女性Panelは男性のそれよりも全般によい様である。(2) 平均最低閾値は、塩酸、アスコルビン酸、グルコン酸では1×10-4M(各0.0004、0.0019、0.0020%)、ベタイン塩酸塩では2×10-4M (0.0027%) であり、クエン酸、酒石酸、乳酸等その他有機酸では5×10-5M(各0.0010、0.0008、0.0005……%)かそれ以下である。(3) 酸味として感じる閾値は、正確には極限法によっておこなわねばならないが、本実験資料から大略次の値であろうと推定される。クエン酸、酒石酸、フマール酸、グルタミン酸塩酸塩については1×10-4M(各0.0019、0.0015、0.0013%)、アスコルビン酸の4×10-4M(0.0076%)を除いて他の本実験試料酸類は、同一モル数すなわち、2×10-3M(塩酸の0.0008、乳酸の0.00018、酢酸の0.0012、コハク酸の0.0024、グルタミン酸の0.0030等の各%)である。(4) 閾値におけるpHは必ずしも同一ではなかった。
- 著者
- 内田 智之 髙木 祐希 水野 晃宏 岡村 駿 斎藤 宏紀 井手 史朗 大原 慎 井上 盛浩 萩原 政夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.8, pp.857-864, 2020 (Released:2020-09-08)
- 参考文献数
- 10
当院で院内感染として新型コロナウイルス感染症を発症した血液疾患40例と他疾患57例を後方視的に解析した。生存例については60日までを解析期間とした。血液疾患21例(52.5%),他疾患20例(35.1%)の死亡が確認された。血液疾患症例においては高頻度にファビピラビルが使用(21例(52.5%)vs 15例(26.3%),P<0.05)されていたにもかかわらず,生存期間中央値は29日で,全生存率が不良な傾向であった(P=0.078)。血液疾患症例では酸素投与が開始後,急激に呼吸状態が悪化し死に至るもしくは人工呼吸器管理を要する状態に至るまでの日数が有意に短い結果が示された(中央値5日(範囲1~17日),10日(1~24日),P<0.05)。入院中の血液疾患症例が新型コロナウイルス感染症を発症すると極めて短期間に重症化し致死的となる可能性が示唆された。
3 0 0 0 OA 心理学と行動経済学―古典的心理学と確率荷重関数の関係を中心に
3 0 0 0 OA チェロ演奏動画の目視によるデータ獲得とクラスタリングによる分類
- 著者
- 古川 康一 升田 俊樹 西山 武繁
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第30回全国大会(2016)
- 巻号頁・発行日
- pp.1M4OS14a3, 2016 (Released:2018-07-30)
3 0 0 0 OA 先輩看護師の言動に対する病院勤務看護師の被害認識に関する研究
- 著者
- 大鳥 和子 福島 和代 吉田 浩子 鈴木 はる江
- 出版者
- 日本心身健康科学会
- 雑誌
- 心身健康科学 (ISSN:18826881)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.33-42, 2014-02-01 (Released:2014-02-21)
- 参考文献数
- 31
本研究は,先輩看護師の言動に対する病院勤務看護師の被害認識と被害認識に関連する要因を明らかにするために,20~30歳代女性看護師963人を対象に質問紙調査を行った.有効回答478を被害認識の有無で分類し,関連要因は属性,ローカス・オブ・コントロール,心身不調とした.結果,31.8%が被害認識あり群で,20歳代が30歳代よりも被害認識あり群の割合が高かった.30歳代と臨床経験年数10年以上の看護師は,被害認識あり群がなし群よりも外的統制傾向にあった.心身不調10項目中9項目は,被害認識あり群がなし群よりも「有」の回答の割合が高かった.先輩看護師は,自らの言動が「被害を受けた」と認識されることを自覚し,被害認識を与えない言動を行うことが重要であることと,20~30歳代女性看護師のメンタルヘルス対策には先輩看護師の言動に対する被害認識を考慮した方策を盛り込む必要性が示唆された.
3 0 0 0 OA 自然科学, 医学, 工学におけるジェンダード・イノベーション
- 著者
- Londa SCHIEBINGER
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.11, pp.11_12-11_17, 2017-11-01 (Released:2018-03-28)
3 0 0 0 OA 社会科教育学における理論研究の動向
- 著者
- 小瑶 史朗
- 出版者
- 日本社会科教育学会
- 雑誌
- 社会科教育研究 (ISSN:09158154)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.104, pp.63-74, 2008 (Released:2016-12-01)
3 0 0 0 OA 勝川春亭代-とその親族-勝川桂子氏書簡と同家蔵日拝帳より
- 著者
- 佐野 國夫
- 出版者
- 国際浮世絵学会
- 雑誌
- 浮世絵芸術 (ISSN:00415979)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, pp.12-17, 1997 (Released:2021-02-19)
3 0 0 0 OA 勝川春亭考
- 著者
- 岩切 友里子
- 出版者
- 国際浮世絵学会
- 雑誌
- 浮世絵芸術 (ISSN:00415979)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, pp.3-30, 1996 (Released:2021-02-18)
- 著者
- Sachie Kanada Hidenori Aiki Kazuhisa Tsuboki
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- pp.17A-007, (Released:2021-06-22)
- 被引用文献数
- 3
Torrential rain associated with Typhoon Hagibis (2019) caused extensive destruction across Japan. To project future changes of the record-breaking rainfall, numerical experiments using a regional 1-km-mesh three-dimensional atmosphere–ocean coupled model were conducted in current (CNTL) and pseudo-global warming (PGW) climates. The water vapor mixing ratio in the lower troposphere increased by 23% in response to a 3.34 K increase in sea surface temperature (SST) in the PGW climate. The abundant moisture supply by the westward winds of the typhoon caused strong precipitation from its rainbands for a long period, resulting in 90% increase in total precipitation in eastern Japan before landfall. However, the strong PGW typhoon caused high SST-cooling. Mean precipitation in eastern Japan during the typhoon passage increased by 22% when the SST-cooling east of Kanto was strengthened from 0.11 K to 0.72 K from the CNTL to PGW simulations; the increase was above 29% when the SST-cooling was lowered. Since Typhoon Hagibis accelerated as it traveled northward, the magnitude of the SST-cooling and weakening of the typhoon were suppressed. Consequently, strong precipitation in the inner-core of the strong PGW typhoon caused 30% increase in precipitation in the areas on the Pacific side of northern Japan.