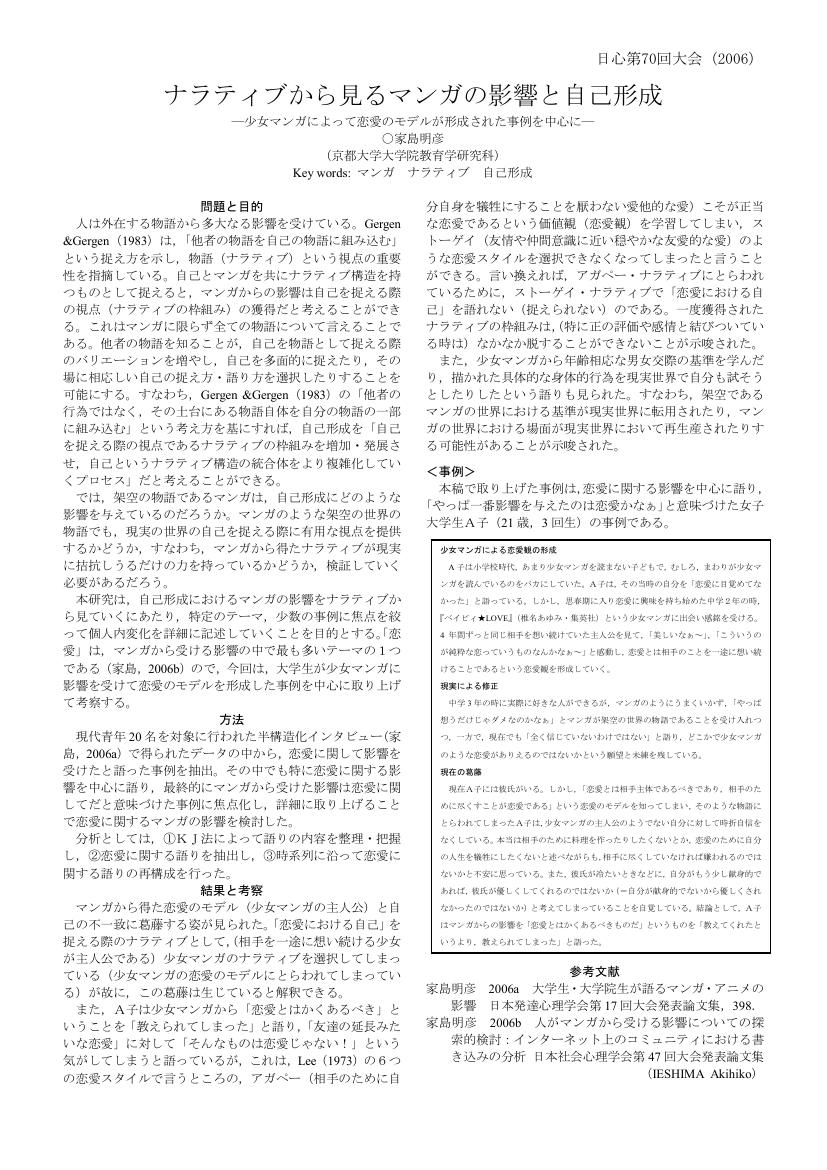1 0 0 0 OA 日本半導体産業に必要な水平分業
- 著者
- 大山 聡
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.4, pp.167-178, 2014-04-25 (Released:2015-04-25)
本稿では日本半導体産業の現状と展望について論じる。日本の半導体産業は一時期強い競争力を誇っていたが、産業構造が水平分業に転換されてからその競争力を失いつつある。最近では、事業売却や合弁会社設立を通じ、本社から半導体事業を切り離している企業も多い。しかし、まだ日本の半導体技術は高く、競争優位が持てる分野も存在する。本稿では、アーキテクチャー論を用い、半導体を分類し、そこで勝つための水平分業を提案する。
1 0 0 0 OA 第17回臨床不整脈研究会 多彩な心房性不整脈が認められたラッサ熱による収縮性心膜炎術後例
- 著者
- 水澤 有香 辰本 明子 伊藤 晋平 小宮山 浩大 小泉 章子 永島 正明 谷井 博亘 南雲 美也子 酒井 毅 山口 博明 呉 正次 岡崎 英隆 手島 保 櫻田 春水 日吉 康長 西崎 光弘 平岡 昌和
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.Supplement4, pp.11-17, 2005-11-30 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 3
症例は66歳,男性.1987年西アフリカのシエラレオネから帰国後ラッサ熱を発症し,収縮性心膜炎を合併したため心膜剥離術を施行した.2003年8月より心房細動あり,他院にてIc群抗不整脈薬を投与された.その後持続する心房粗動を認めたため,2004年5月カテーテルアブレーション目的にて入院した.電気生理学的検査を行ったところ,三尖弁輪を反時計方向に旋回する通常型心房粗動であった.三尖弁一下大静脈間峡部への高周波通電中に頻拍周期が延長し,心房興奮順序の異なる心房頻拍へと移行した.頻拍中に右房内をマッピングしたところ,右房後側壁にP波より60ms先行する最早期興奮部位を認めた.同部位への通電により頻拍は停止し,以後心房頻拍,心房粗動ともに誘発されなくなった.きわめてまれなラッサ熱による心膜炎術後例に多彩な心房性不整脈を合併した症例を経験した.
1 0 0 0 OA ナノインプリント技術による次世代DNAセンサの開発
- 著者
- 大竹 才人
- 出版者
- 愛知工科大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2011
DNAは機能性材料としてバイオナノデバイスへの展開が期待されており、それに必要なDNAナノパターニング技術の開発が求められている。また、オーダーメード医療などの次世代診断に向けて簡便で高感度なDNAセンサが求められている。そこで本研究では、ナノインプリント技術を利用してDNAセンサ開発に向けたDNAのナノパターニングを試みた。ナノインプリントのレジストとして、DNAと強い相互作用を有するポリマーとして知られているポリ-L-リジン(PLL)をガラス基板上に用いた。まず、ガラス基板上のPLL薄膜をSiモールドを用いて120℃、6MPa、5minの条件でナノインプリントした。その後、この基板上に1mg/mlDNA溶液を滴下して2分間紫外光照射して、熱湯で洗浄することでDNAナノパターンを得た。これは、ナノインプリトによってPLLがナノパターン状に改質されて、そのナノパターン部位がDNAをより強固に固定化するためであると考えられる。
1 0 0 0 OA 闇を通して光を
- 著者
- 好村 冨士彦
- 出版者
- Japanische Gesellschaft für Germanistik
- 雑誌
- ドイツ文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.79-90, 1969-03-31 (Released:2008-03-28)
"Geist der Utopie“, geschrieben von Ernst Bloch während des ersten Weltkriegs und auch nach dem Krieg, d.h. nach dem Scheitern. der deutschen proletarischen Revolution, war und ist ein problematisches Buch. Man findet darin eine seltsame Mischung von radikal revolutionärem Pathos und ebenso radikal idealistischer Kontemplation, von kühner Denkungsart und frommer Heilssehnsucht. Die innere Spannung des jungen Bloch gewinnt hier einen gewaltigen Ausdruck, der philosophisch von jüdischer Mystik und vom Marximus, künstlerisch vom Expressionismus genährt ist.Die utopische Funktion konzentriert sich zunächst intensiv nach innen, tief bis zur Selbstbegegnung, welche Bloch in der gotischen, barocken und expressionistischen Kunst und vor allem in der Magie der Musik zu finden glaubt. Dann wendet sich der utopisierende Blick horizontal nach außen und erhält nun eine kosmische Weite. Der sozialistische Gedanke von Marx und der gnostische Glaube an die Seelenwanderung bilden eine utopische Synthese, die einen faszinierenden Wachtraum durch den irdischen und überirdischen Raum hinwachsen läßt.Indem Bloch hier tief ins Dunkel, in die okkulte Unterwelt der Seele hineintaucht, deren Untersuchung bisher ausschließlich Mystikern, Romantikern oder Tiefenpsychologen überlassen war, so gelingt dem Propheten mit Marx- und Engelszungen, wie ihn Martin Walser mit Recht genannt hat, aus der Finsternis heraus das Licht zu erzeugen, welches uns die utopische Perspektive in die Zukunft verschafft, die weder erstarren noch verbleichen, sondern immer neu und ewig lebendig bleiben wird.
1 0 0 0 OA ナラティブから見るマンガの影響と自己形成
- 著者
- 家島 明彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第70回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.2PM001, 2006-11-03 (Released:2018-07-03)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA ウニ卵の初期発生における細胞骨格の動的変化
- 著者
- 浜口 幸久
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.6, pp.262-267, 1987-11-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 36
Microfilaments compose microvilli, fertilization cone, cortical layer, and contractile ring in sea urchin eggs, and microtubules compose sperm aster and mitotic apparatus. These cytoskeletal structures spatially and temporally change during fertilization and cleavage, which has become clear at molecular level using fluorescent analogues of actin and tubulin.
1 0 0 0 OA 水鳥類による各種植栽浮島の利用状況
- 著者
- 百瀬 浩 舟久 保敏 木部 直美 中村 圭吾 藤原 宣夫 田中 隆
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 環境システム研究 (ISSN:09150390)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.45-53, 1998-10-15 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 4 5
A field survey was made on many artificially constructed Floating Islands in Japan in order to evaluate their function as habitat for birds such as nesting or resting site. We searched each island for birds' nesting activity and observed the behavior of birds on and near the island. We also collected plant samples and identified them to make the plant species list found on each island. Floating islands were classified into four basic types according to their structure and bird usage was conpared among these types. It was found that the island type B, in which the surface of the planting material was in lebel with the water furface, was suitable as the nesting place for the several water bird species, and all types of the islands were suitable as the resting place for the water birds.
1 0 0 0 OA マスク用エアフィルタの高性能化と評価技術に関する研究
- 著者
- 湯浅 久史 Yuasa Hisashi
- 出版者
- 金沢大学
- 雑誌
- 博士論文本文Full
- 巻号頁・発行日
- 2015-09-28
博士論文本文Full
1 0 0 0 OA 落花生薄皮茶の抗酸化活性について
- 著者
- 片山 佳子 外山 剛之
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 68回大会(2016)
- 巻号頁・発行日
- pp.172, 2016 (Released:2016-08-04)
目的 落花生は、様々な用途に使用され消費されているが、その加工工程において、薄皮は多量の産業廃棄物となる。しかし、落花生薄皮にはポリフェノールであるレスベラトロールが多く含まれていることから、高い抗酸化作用を持つと考えられる。そこで本研究では、この多量に廃棄されてしまう薄皮をお茶のような飲料として利用できないかと考え、ポリフェノール量および抗酸化活性を測定するとともに、官能評価による嗜好性を分析することを目的とした。方法 落花生薄皮1gに抽出温度(80,85,90,95,100℃)を変えた水200mLで20秒間抽出したものを試料液とした。ポリフェノール量の測定は、Folin-Denis法にて行った。抗酸化活性はラジカル消去能をDPPH法で測定し、Trolox相当量として算出した。嗜好型官能評価は、外観、香り、味、苦味、総合評価の5項目を5点評点法により評価し、分散分析法により検定を行った。結果 ポリフェノール量と抗酸化活性は、抽出温度が高くなるにつれて高い値を示し、抽出温度100℃が最も高い結果となった。これは水溶性の抗酸化物質であるポリフェノーが多く溶出されたためと考えられた。また、ポリフェノール量が多いほど高い抗酸化活性を示したことから両者には高い相関性があり、落花生薄皮茶の抗酸化活性の主体はポリフェノールであることが考えられた。官能評価は、当初、高温抽出では薄皮の渋味が懸念されたが高温の100℃抽出が総合的に好まれた。このことから落花生の薄皮茶は高い抗酸化活性をもつ飲料として利用できることが示唆された。
1 0 0 0 IR 映像による占領--戦後日本における写真と暴力
- 著者
- 今福 龍太
- 出版者
- 札幌大学
- 雑誌
- 比較文化論叢 (ISSN:13466844)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.7-35, 2001-03
1 0 0 0 OA 訴権の濫用 (小山博也教授河中二講教授立田清士教授退職記念号)
- 著者
- 小野寺 忍 オノデラ シノブ Shinobu Onodera
- 雑誌
- 山梨学院大学法学論集
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.354-360, 1997-07-25
1 0 0 0 OA 京都鴨川の景観と春から秋の季節変化の魅力について
- 著者
- 福井 亘 佐竹 悠理 濱田 梓 疋嶋 大作 瀨古 祥子 高林 裕
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.5, pp.609-614, 2017-03-31 (Released:2017-09-13)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1 5
This study was intended to clarify the change of charm and the impression of the season in river landscape and green open space. This study area was Kamo River by autumn from spring in Kyoto. There was direct interview question investigation from visitors on the both sides of the two sections. This investigation was the impression evaluation experiment using the SD method to investigate the impression of the river landscape scene every seasons. There analyzed factor analysis and profile analysis. Thera performed an analysis of variance between seasons (spring, summer and autumn) to check whether the impression evaluation in two sections included significant difference. The answer that there was the most accounted for 19.5% of the whole by a landscape scene. The people more than 90% of the respondent answered that the making of space feeling the four seasons was important. From the result of the SD method, it was easy to feel the change of the tree visually in autumn with spring, and it was thought that a natural element influenced an impression. In addition, an overall element including the urb an river and the townscape influenced an impression in the summer because the colors of the tree were monotonous.
1 0 0 0 OA 遺伝学的情報と法 : 象徴的機能としての遺伝子差別禁止法
- 著者
- 瀬戸山 晃一 SETOYAMA Koichi
- 出版者
- 名古屋大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 名古屋大學法政論集 (ISSN:04395905)
- 巻号頁・発行日
- vol.250, pp.393-403, 2013-07-18
1 0 0 0 OA 第37回日本民族衛生学会―一般講演―抄録
- 出版者
- 日本民族衛生学会
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.279-321, 1972 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 IR アメリカの「テロとの戦争」とOLCの役割
- 著者
- 横大道 聡
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 法学論集 (ISSN:03890813)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.85-128, 2011-03
附記より: 本稿は、2010年10月23日(土)に慶應義塾大学にて行われた慶應義塾大学「市民生活の自由と安全」研究会での報告と、2010年12月11日(土)に九州産業大学にて行われた九州産業大学経済学会(日本臨床政治学会との共催)での報告を基に、そこで寄せられた質問・意見などを踏まえて加除修正を行い、論文の体裁に整えたものである。
1 0 0 0 OA 日本人のみたロシア革命
- 著者
- 宮永 孝
- 出版者
- 法政大学社会学部学会
- 雑誌
- 社会志林 = Hosei journal of sociology and social sciences (ISSN:13445952)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.1-77, 2019-07
- 著者
- 照屋 信治 Teruya Shinji 人文学部准教授 近現代沖縄教育史
- 出版者
- 沖縄キリスト教学院大学
- 雑誌
- 沖縄キリスト教学院大学論集 (ISSN:13498479)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.1-12, 2012-12
本稿の目的は、沖縄県立第三中学校教諭であった豊川善曄(1888-1941)の思想と実践を分析し、1930年代初頭の沖縄における郷土教育の可能性と陥奔とを検討するものである。近代沖縄教育史は、「同化」「皇民化」という用語で説明されてきた。教師たちは日本政府の同化政策を無批判的に推し進めた存在だと理解されてきた。しかし、1930年代初頭の郷土教育が盛んな時期、豊川善曄をはじめ幾人かの教師たちは、強い「沖縄人」意識をあらわにし、その必要性を訴えていた。豊川は、郷土史教育の目的を沖縄の「民族魂」の鼓吹であるとまで高唱していた。なぜそのようなことが戦前日本の公教育の場で可能であったのか、その教育的、社会的背景を探り、その思想の輪郭を描き、陥奔を指摘する。また、それらの作業を通じ、全国的に展開された郷土教育が、沖縄においては異なった様相を呈したことを明らかにする。This paper examines the work of TOYOKAWA Zenyou (1888-1941), a little known teacher in Okinawa's third middle school who sought to develop students with a strong sense of their cultural roots. This examination is grounded in considerations that the Regional Learning Project of the early 1930s in Okinawa had both possibilities and pitfalls toward effective education. The history of Okinawa's modern education has been described in terms of uncritical, widespread "assimilation" (kōminka). That is, teachers were understood to blindly play their crucial roles in carrying out the assimilation policies promulgated by the Japanese government. In the face of these assimilation policies stood TOYOKAWA who expressed the importance of "Okinawan consciousness," insisting that local students understand their history and culture. TOYOKAWA argued that a primary aim of regional history education was to bring up students with a strong awareness and consciousness of Okinawa. What possessed TOYOKAWA to resist the assimilation policy and assert the importance of Okinawan consciousness? What were the principal features of his ideas and their shortcomings? This paper aims to answer these questions. Based on my research, it can be said that the Regional Learning Project in Okinawa was significantly different in its aims from those in the mainland.