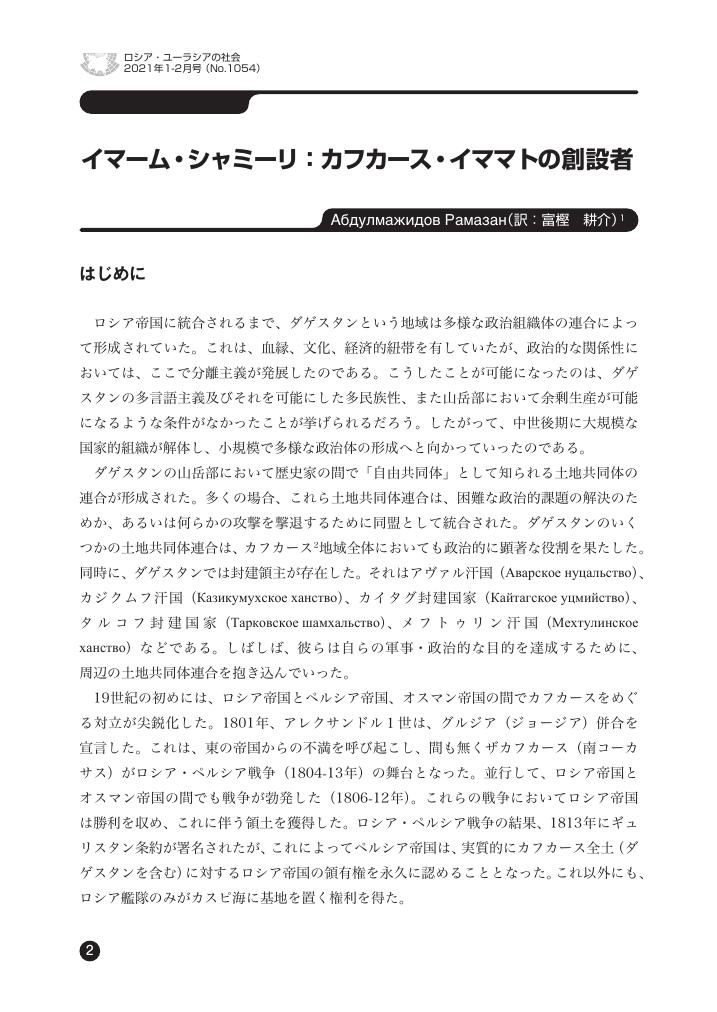2 0 0 0 OA 地域におけるスポーツのコーチの喜びと困惑―コーチ対象の調査の内容分析―
- 著者
- 大橋 恵 井梅 由美子 藤後 悦子 川田 裕次郎
- 出版者
- 日本コミュニティ心理学会
- 雑誌
- コミュニティ心理学研究 (ISSN:13428691)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.226-242, 2017-02-28 (Released:2019-04-05)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 2
Community sports clubs can provide children with adequate opportunities to exercise. However, researchers have indicated certain problems faced by such clubs, which are volunteer associations. The present study conducted an internet based survey and inquired coaches in community sport clubs (N=150) about their work as coaches, about the equipment they use, and about the problems they had faced, among others. Results indicated that coaches usually worked voluntarily, that they attempted to communicate positively with children, and maintained the security of children. On the other hand they had difficulties in maintaining appropriate relationships with parents, in dealing with children having difficult personalities, and in dealing with children that are not serious about playing sports. Although the voices of coaches in community sports clubs were greatly identified, there were certain limitations to the study. Because of the small sample size, we cannot compare responses between different kinds of sports and different goals coaches and parents have.
- 著者
- Thiparpa THAMAMONGOOD Shoko HARA Hiroyuki AKAGAWA Motoki INAJI Yoji TANAKA Tadashi NARIAI Taketoshi MAEHARA
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023-0169, (Released:2023-12-06)
- 参考文献数
- 25
Recently, thyroid autoantibodies were found to be associated with moyamoya disease (MMD). The ring finger protein 213 (RNF213) p.R4810K variant represents the most important susceptibility genotype of this disease, but its relationship with thyroid autoantibodies remains to be elucidated. Thus, in this study, we aimed to evaluate the clinical relevance of thyroid autoantibodies in each RNF213 genotype in patients with MMD. Included in this study were patients with MMD without a thyroid disease history and in euthyroid status; they were then classified into the mutated or nonmutated based on the RNF213 p.R4810K genotype and positive or negative based on thyroid autoantibody (thyroperoxidase and thyroglobulin) levels. Clinical data of each group were thereafter evaluated. Among the 209 patients, the mutated RNF213 p.R4810K variant and positive thyroid autoantibodies were detected in 155 and 41 patients, respectively. Positive thyroid autoantibodies were found to be more common in the nonmutated patients than in the mutated patients (31.5% vs. 15.5%; P = 0.011). In the mutated patients, as compared to autoantibody-negative patients, autoantibody-positive patients were determined to be more likely to have advanced disease with posterior cerebral artery involvement (54.2% vs. 29.0%; P = 0.017), white matter infarction (58.3% vs. 37.6%; P = 0.046), and a higher modified Rankin Scale at last visit (16.7% vs. 3.1%; P = 0.021). These results suggest that thyroid autoantibodies can act as an immunity inducer in patients with MMD lacking the susceptibility gene RNF213 p.R4810K variant. Moreover, the simultaneous presence of thyroid autoantibodies and the variant seems to aggravate the disease, which indicates synergy between thyroid autoantibodies and the variant.
2 0 0 0 OA 村田先生とのおつきあい
- 著者
- 梅原 徹
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物地理・分類研究 (ISSN:03886212)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.9, 2021 (Released:2021-12-27)
2 0 0 0 OA 鉱物科学としての鉱床学・資源地質学の発展と将来
- 著者
- 清水 正明
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.2, pp.257-274, 2022-04-25 (Released:2022-05-13)
- 参考文献数
- 68
- 被引用文献数
- 2 2
Both the history of resource development and the progress of studies of mining and ore deposits in Japan are summarized. Researchers and engineers promoting in studies on ore deposits and resource geology are also reviewed, focusing on Professors Takeo Kato, Takeo Watanabe, Tatsuo Tatsumi, and J. Toshimichi Iiyama as well as other staffs of the Third Professorship, Department of Geology, Faculty of Science, University of Tokyo. Mineralogy, geology and geochemistry are essential for an understanding of resource geology. It is revealed that mineralogy plays an important role in studies on ore deposits and resource geology. Future directions of studies on ore deposits and resource geology are proposed.
- 著者
- Yuki G. Baba Suguru Ohno Ukuda-Hosokawa Rie Akio Tanikawa
- 出版者
- Arachnological Society of Japan
- 雑誌
- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.17-18, 2017-08-31 (Released:2017-09-11)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 新・旧軟式野球ボールの反発特性と新球に適応した金属製バットに関する研究
- 著者
- 酒井 忍 保富 大輔 史 金星 浦上 晃 溝口 正人
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.877, pp.19-00118, 2019 (Released:2019-09-25)
- 参考文献数
- 19
In rubber baseball games, when the rubber ball is hit by a baseball bat, the rubber ball is deformed greatly comparing to an official baseball ball, and the batted ball speed decreases due to the energy loss during the deformation. Since the new rubber ball has been applied in games from 2018, the material properties and the restitution characteristics of the new rubber ball attract plenty of attention among scholars. In this study, the difference of the material properties and the restitution characteristics between the new and old rubber balls is investigated deeply by the static compression and collision tests. According to the static compression test, we find that the new rubber ball is harder and more difficult to generate deformation than the old one. In the collision test, the rebound ball speeds of both of the new and the old balls become faster when using a smaller diameter of steel cylinder instead of baseball bat, and the rebound ball speed of the new ball is slower than that of the old one under the same experimental conditions. Furthermore, to develop high performance baseball bats adapting to the new rubber baseball, the diameter of the baseball bat is studied by the impact simulation based on the finite element analysis. In the simulation, the batted ball speed under the analytical conditions of different offset heights and different barrel diameters of the bat are evaluated considering the initial spin. As a result, the batted ball speed generated by the bat with diameter φ55 mm is faster than generated by the bat with diameter φ70 mm when the offset height range is smaller than 14.6 mm, so that the bat diameter φ55 mm is recommended according to the present work.
- 著者
- Toshiro Kitagawa Takayuki Hidaka Makiko Naka Susumu Nakayama Kanako Yuge Mitsuaki Isobe Yasuki Kihara for the REAL-HF Investigators
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.4, pp.226-234, 2020-04-10 (Released:2020-04-10)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 8 7
Background:We investigated the current medical and social conditions and outcomes of heart failure (HF) patients in Hiroshima Prefecture, a local district in Japan.Methods and Results:From March 2017 to February 2018 we enrolled all adult patients with hospitalized HF in 8 regional core hospitals that provided an interprofessional team approach for HF patients. We collected patients’ clinical characteristics and information regarding living circumstances, cognitive function, quality of life, and interprofessional team approach. For patients discharged home, we followed up the primary endpoint (all-cause death and all-cause unscheduled readmission), conditions of outpatient cardiac rehabilitation, and home nursing-care services over a 1-year period after discharge. Of the registered patients (n=1,218), 39.2% were super-elderly (≥85 years old); more than half of these patients had preserved ejection fraction (≥50%). In the follow-up cohort (n=632), 140 patients (22.2%) were readmitted with HF exacerbation as the primary endpoint, and almost half (n=295, 46.7%) experienced any primary endpoint. The multivariate analysis adjusted for medical and social factors showed that completion of outpatient cardiac rehabilitation (5-month program) remained a strong negative predictor of the primary endpoint (hazard ratio: 0.15; 95% confidence interval: 0.05–0.48; P=0.0013).Conclusions:Our cohort study highlighted the super-aging of current HF patients in Japan. Cardiac rehabilitation through continuous team approach appears to be associated with favorable overall outcomes in this population.
2 0 0 0 OA 睡眠時無呼吸・いびきへの対応: 高齢者への対応
- 著者
- 駒田 一朗 宮崎 総一郎 西山 彰子
- 出版者
- 日本口腔・咽頭科学会
- 雑誌
- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.41-49, 2016-03-31 (Released:2016-06-23)
- 参考文献数
- 49
睡眠時無呼吸の頻度は高齢になるほど増加する. 50歳未満では睡眠時無呼吸の死亡率が高くなるという報告がある一方, 高齢者では死亡率は高くないとする報告がある. 高齢者の睡眠時無呼吸の重症度や日中の眠気が生命予後に影響を与えるとの報告もある. 高齢者では手術加療や口腔内装置選択の適応例が少なくなるため CPAP に依存することが多いと予想される. 睡眠時無呼吸は認知障害と関連があるとの報告が近年増えており, CPAP 治療により認知機能が改善し, 脳画像での改善がみられることが報告されている. 高齢者の睡眠時無呼吸の対応にあたっては生命予後以外に認知機能改善や認知症予防の観点から対応する必要がある.
2 0 0 0 OA 地方寺院の僧侶による葬儀実践の模索―法話に注目して―
- 著者
- 磯部 美紀
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.49-63, 2021-06-05 (Released:2023-06-24)
- 参考文献数
- 36
近年の日本においては、宗教家を介在させない葬儀が一つの葬儀形態として受容されている。また、「故人らしさ」を反映させた個性的な葬儀を望む人々もいる。今や、葬儀に僧侶が関与することは自明ではなくなりつつある。本稿では、このような葬儀を取り巻く状況の変化を受けて、僧侶が自らの役割をどのような点に見出し、いかに葬儀実践を模索しているのかを、新潟県で行われた仏式葬儀を事例に論じる。特に、法話(僧侶によって行われる説法)に注目する。法話の内容を分析すると、故人の生き様を反映させた個別化された要素と、仏教儀礼として定型化された要素が確認できる。この事例研究を通して、両要素は相反するものではなく、相互補完的な関係にあることが示された。法話実践の分析により、僧侶が個性的な葬儀を称賛する現代的ニーズに対応しつつ、同時に死別に際して必要とされる仏法に基づく物語を人々に提供する具体的様相が明らかになった。
2 0 0 0 OA ニクラス・ルーマンの「世俗化」論―近代社会における宗教の存立問題―
- 著者
- 畠中 茉莉子
- 出版者
- 「宗教と社会」学会
- 雑誌
- 宗教と社会 (ISSN:13424726)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.33-47, 2021-06-05 (Released:2023-06-24)
- 参考文献数
- 23
ルーマンは宗教を社会の一つの機能システムとして描きつつも、その存立を自明視はせず、近代社会における宗教の存立の可否を問い続けた。彼の世俗化論はこの問いを中心的な主題としたものである。彼の世俗化論には1977年版、2000年版という複数のテキストがあり、前者から後者へと至る間に宗教に対する彼の見方は変化した。この変容の詳細はまだ解明されていない。その解明が本稿の主眼である。当初、彼は宗教としてキリスト教の教会組織を念頭に置いていた。その後彼は同時代の神学者と宗教社会学者の問題提起を通じて、現代の拡散した宗教的現象において示されている宗教性とは何かという問いに出会う。この問いに向き合う中で彼の宗教をめぐる視点は拡大した。彼は現代の様々な宗教的現象への関心を示す。それらは伝統的な組織の内には収まらない。そのためルーマンは、現代の宗教性を一つの自立した宗教システムとして描くための理論的概念を模索したのである。
2 0 0 0 OA 胸郭出口症候群の診断と治療戦略
2 0 0 0 OA 動体視力に関する研究 : 眼調節のトレーニングが動体視力に及ぼす影響について
- 著者
- 山田 人恒 森田 修朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.73-81, 1969-11-30 (Released:2016-12-31)
In order to achieve accommodation of the eye which influences predominantly upon the kinetic visual acuity which chiefly relates to the accuracy in the timing action, the following studies were performed; that is, at the certain period of time, training to the velocity of accommodation was done repeatedly in every day, and the effect of training and the variations in the kinetic visual acuity accompanying with the training effect were determined. The results were obtained as described here, 1) By the training of accommodation of the eye, the accommodative contraction time shortened and the higher value of the kinetic visual acuity was obtained. 2) Relationship between the daily change in the accommodative contraction time and that in the kinetic visual acuity was due to chiefly to the degree of training for the optimal reaction to the moving object, where the subject himself performed in his daily life.
2 0 0 0 OA 中日韓三ヵ国語における外来語いついての対象研究
- 著者
- 田 静
- 出版者
- アジア日本言語文化研究会
- 雑誌
- 日本言語文化研究 (ISSN:24346780)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.66, 2020 (Released:2021-08-18)
2 0 0 0 OA 突発性難聴に対する治療戦略 - 現代医療における鍼灸の有用性 -
- 著者
- 井畑 真太朗 村橋 昌樹 山口 智
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学系物理療法学会
- 雑誌
- 日本東洋医学系物理療法学会誌 (ISSN:21875316)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.43-46, 2022 (Released:2023-06-28)
- 参考文献数
- 9
突発性難聴は原因不明の急性感音性難聴である。2015 年に厚生労働省「難治性聴覚障害に関する調査研究班」によって改訂された診断基準によると、「純音聴力検査での隣り合う3 周波数で各30dB 以上の難聴が 72 時間以内に生じた」と定義されている。2012 年度の疫学調査の結果、人口10 万人あたり年間 60.9 人発症すると推定され、年代別発症率は、50 歳から 70 歳に多い。治療法ではステロイド剤、代謝・循環改善薬、高圧酸素療法が実施されているが、全ての治療法の効果 の立証が不十分である。 突発性難聴の鍼治療については、2015 年突発性難聴に対する鍼治療の有効性に関するメタ解析が報告されており、標準治療 VS 標準治療+鍼治療の比較では併用群の方が予後良好であったとの報告があるが、抽出された研究の多くは症例数が少なくバイアスリスクが高いため、大規模なラ ンダム化比較試験が必要であるとされている。 当科では医療連携を推進しており、診療各科より鍼治療の依頼がある。近年耳鼻咽喉科より診療依頼があった突発性難聴患者の実態の特徴は、重度の突発性難聴患者が多く、発症から約 1 ヶ 月と通常聴力が固定された後、鍼治療を開始する患者が多かった。この患者群に対し頸肩部等に鍼治療を継続した結果、概ね良好な結果が認められた。以上より、突発性難聴に対する鍼治療は現代医療において有用性の高い治療法である可能性が示唆された。今後はさらに症例を増やし、質の高い臨床研究を推進し、鍼治療の有効性や有用性を明らかにしたい。
2 0 0 0 OA 進行性骨化性線維異形成症の1歳女児例
- 著者
- 八木 夏希 松井 敦 畠山 信逸 外松 学 肥沼 淳一 杉立 玲 柴 梓 清水 真理子 溝口 史剛 荒川 浩一
- 出版者
- 日本小児放射線学会
- 雑誌
- 日本小児放射線学会雑誌 (ISSN:09188487)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.49-53, 2018 (Released:2018-06-14)
- 参考文献数
- 12
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) is a disease that begins in infancy and is characterized by progressive ossification of skeletal muscles throughout the body. Stimuli such as injury and infection can trigger flare-ups involving subcutaneous mass formation, resulting in subsequent ossification at the site. Imaging diagnosis is often difficult in the initial phase where only a mass due to flare-up is present. In most cases, the diagnosis is made only after ossification has occurred, typically several years after the onset. Herein, we report a case of FOP diagnosed 4 months after onset. Careful imaging evaluation of the mass showed characteristics of FOP distinct from those of malignant tumors and other mass-forming lesions. Since early intervention can improve the outcome for patients with FOP, early diagnosis through careful imaging evaluation and awareness of the disease is important.
2 0 0 0 OA 核酸医薬の物性制御による有効性・安全性へのアプローチ 〜核酸医薬との物質共生に向けて〜
- 著者
- 山本 剛史 山吉 麻子
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.131-141, 2022-03-25 (Released:2022-06-25)
- 参考文献数
- 55
近年、新たな創薬モダリティとして「核酸医薬」に大きな注目が集まっている。人工核酸技術により、1)標的親和性・選択性、2)生体内安定性、3)免疫応答などの副作用などの課題が次々と克服され、適応疾患の拡大が精力的に進められている。一方で、高度に最適化された核酸医薬においても未だ副作用が認められ、広い普及には至っていない。本稿の目的は、核酸医薬と生体との物理化学的相互作用を分類・整理することで、より有効で安全な核酸医薬を開発する(核酸医薬と物質共生する)ための糸口を見つけることである。
2 0 0 0 OA ロールプレイングゲームのRTA の最適な戦略の検討
- 著者
- 河村 拓哉 西 康晴
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 年次大会 予稿集 第13回 年次大会 (ISSN:27586480)
- 巻号頁・発行日
- pp.112-115, 2023 (Released:2023-03-30)
- 参考文献数
- 8
ロールプレイングゲームでは、クリアタイムを競うRTA が近年盛んに行われている。RTA の既存プレイヤーは経験でプレイしていて、速い戦略は確立されておらず、新規プレイヤーが参入しにくい。RPG ではバトルで負けてしまうとクリアまでのタイムを大きくロスしてしまう。そこで高い確率で勝てる戦略が必要となるが、高い勝率の戦略はタイムが遅いことが多く、勝率を高くするだけではRTA の戦略として不十分である。そこで本研究では勝率とタイムの関係からRTA で最適な戦略とは何かを議論する。
- 著者
- 三浦 まり
- 出版者
- 上智大学グローバル・コンサーン研究所
- 雑誌
- グローバル・コンサーン (ISSN:24345814)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.122-142, 2020 (Released:2021-02-01)
- 著者
- 山根 巌
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木史研究 (ISSN:09167293)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.531-540, 1996-06-05 (Released:2010-06-15)
- 参考文献数
- 18
旅足橋は、木曽川中流の岐阜県八百津町において、丸山ダム [関西電力] の設置に伴う補償代替道路として、木曽川支流旅足川の合流点に、1954年 [昭和29年] に架設された「下路型単径間補剛トラス吊橋」である。支間114m、幅員4.5mで、支間の中央二分の一部分の補剛トラス上弦材を主ケーブルが兼用した、合理的な吊橋である。この吊橋は、アメリカの吊橋の大家D.B.Steinman博士の設計により、1926年ブラジルに架設された南米最大の吊橋Florianopolis橋の型式を導入した特異な吊橋であり、世界で5橋架設されているが、我が国では唯一の型式である。現在は、国道418号線のバス路線の一部として、地域交通の要となっているが、洪水防禦を目的とした新丸山ダム [高さ122.5m] の嵩上げ工事の為に、2002年 [平成14年] には撤去の予定となっている。ここでは、旅足橋のこの型式への選定の背景と、吊橋としての歴史的、技術的な意義を検討して報告する。
2 0 0 0 OA イマーム・シャミーリ:カフカース・イママトの創設者
- 著者
- アブドゥルマジドフ ラマザン 富樫 耕介
- 出版者
- ユーラシア研究所
- 雑誌
- ロシア・ユーラシアの社会 (ISSN:24353191)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021, no.1054, pp.2-14, 2021 (Released:2023-03-08)