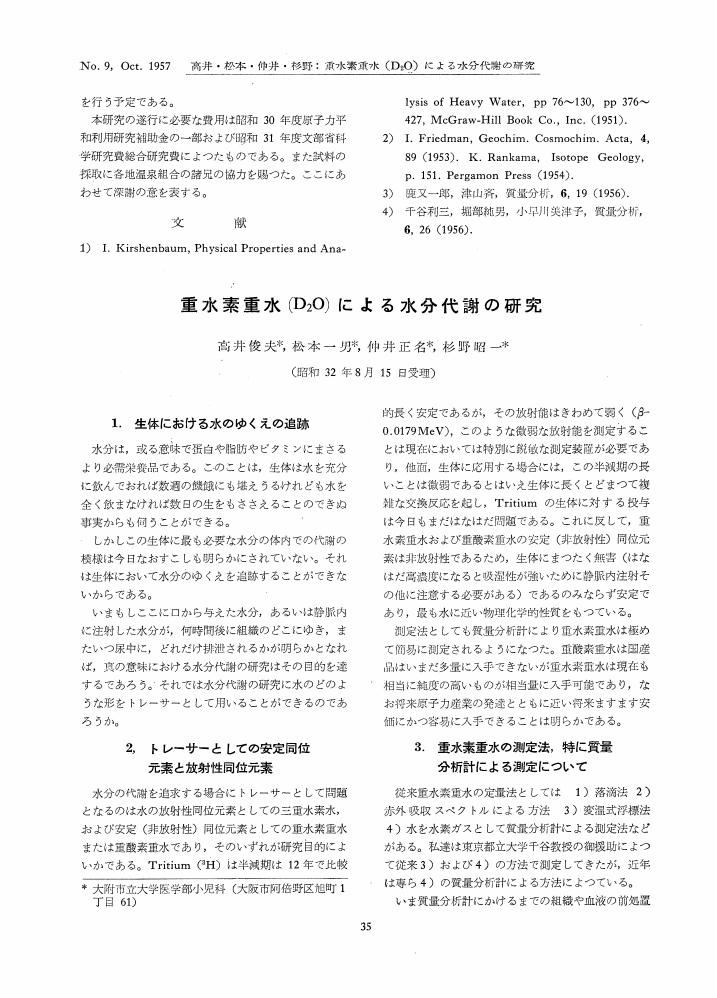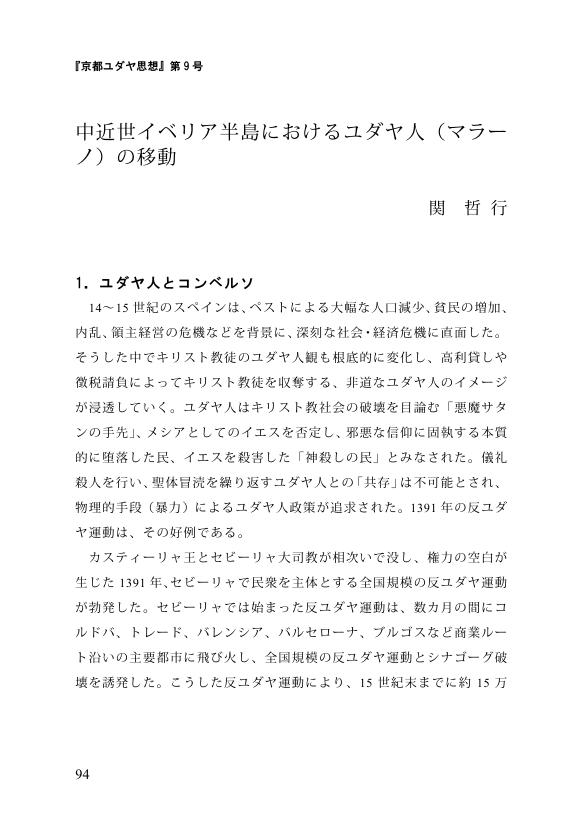- 著者
- 出原 栄一
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.59, pp.11-12, 1987-03-31 (Released:2017-07-25)
2 0 0 0 OA モグリウミツバメとウミスズメの平行進化の形態,解剖学的分析
- 著者
- 黒田 長久
- 出版者
- Yamashina Institute for Ornitology
- 雑誌
- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.111-137, 1967-12-31 (Released:2008-11-10)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 8 11
モグリウミツバメ(Pelecanoides)は翼の長い飛翔型のミズナギドリ目のなかで,外形上は小型ウミスズメに極めて似た翼の小さい潜水型に進化した。ウミスズメ(Synthliboramphus)と外部形態,翼型,翼面積など比較すると一般的類似のなかで,やはり飛翔型由来を反映する測定比例がみられる。一方翼で潜水する適応として初列部の自由な回転(プロペラ効果)など平行的適応がある。剥皮した体型では一次的潜水適応型としてのウミスズメと飛翔型由来の二次的潜水適応型のモグリウミツバメの間に一般体格とその各部(a…zのアルファベット測定)の測定比例の差がみられ,とくに胸郭が太く胸部の短かい点はそれが著しく長いウミスズメと非常に異なる違いである(これは両者の採食法への適応を反映する-後述)。骨学的にもモグリウミツバメは腰骨,肋骨,胸骨などにミズナギドリ目中のウミツバメ科や小形ミズナギドリ科の特徴を保有し,一方潜水適応としての翼骨や脚骨の長さの比例はウミスズメと極めて類似している。ただしモグリウミツバメの腰骨はミズナギドリのなかの潜水性のものほど特化(細長く)していない。また,鎖骨の著しい発達(その形はややウミツバメに近い)は独特の特徴で,これは潜水に必要な胸筋量を前方に増大(後方は腹を圧迫しないように短かい)する効果(適応)があり,飛翔能力も低下させないという補償適応である。この状態はウミスズメ目でもコウミスズメ,エトピリカなど飛翔性の高いものにも平行してみられる傾向である。胸筋ではモグリウミツバメは大胸筋深部をもち(退化しているが),これは他のミズナギドリ目に共通な滑空飛行への適応を保有していることを示す。前胃に多量の食物を貯えるのもモグリウミツバメにみられるミズナギドリ目の特徴で,常時潜水して少しつつ食物をとるウミスズメ目の細い前胃と異なる(この目でもコウミスズメなど飛翔性の高いもので小さい〓のうをみる)。さらに腸の回転型も,恐らく食習性の違いに適応して異なっている。なお,モグリウミツバメはミズナギドリ目特有の体嗅より強い「カモ嗅」を含む嗅いをもつ。
2 0 0 0 OA ASI-Gauss法を用いた動的崩壊解析手法によるWTCの崩壊要因究明
- 著者
- 磯部 大吾郎
- 出版者
- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」
- 雑誌
- 理論応用力学講演会 講演論文集 第57回理論応用力学講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.105, 2008 (Released:2008-09-01)
2001年9月のテロでNY世界貿易センタービルのツインタワーが完全崩壊するという悲劇が起きた.FEMAおよびNISTがまとめた報告書によると,ジェット燃料によって引き起こされた火災が完全崩壊の主要因であるとしているが,火災が起きていなかったとされる下層部も含めて倒壊してしまった直接的な要因については詳細な考察や検討がなされておらず,未だに多くの疑問が残っているのが現状である.筆者らは,接合部の脆弱性が火災下で建物の構造強度に与える影響,および航空機の衝突時に発生する衝撃力が建物の構造強度に与える影響についてASI-Gauss法を用いた動的崩壊解析手法により多角的に調査を行っている.その中で,いくつか興味深い結果が出たのでここに報告する.
2 0 0 0 OA 人工知能の将来と人間・社会
- 著者
- 國吉 康夫
- 出版者
- 科学技術社会論学会
- 雑誌
- 科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.15-29, 2018-12-10 (Released:2020-02-10)
- 参考文献数
- 32
人工知能が今後の人間,社会に与える恩恵や影響を,具体的な技術の現状と課題を踏まえて考える.まず,人工知能技術の基礎(ニューラルネットワーク,深層学習,知識ベースシステム)と現状,および今後の方向性(実世界と人間性)について概説する.次に,人工知能技術が直面する課題(信頼性・安全性,説明可能性,偏向,価値の齟齬,実世界と人間性)および今後の発展に向けた研究状況を紹介する.最後に,人工知能の今後に関して,人工知能は心を持つべきか,および,人工知能が社会にとってどういう存在であるべきかという観点から論じる.
2 0 0 0 OA 脳卒中早期リハビリテーション患者の下肢筋断面積の経時的変化
- 著者
- 近藤 克則 太田 正
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.129-133, 1997-02-18 (Released:2009-10-28)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 14 4
発症後第14病日以内(中央値第1.5病日)に入院した初発脳卒中患者20人の下肢筋断面積をCTを用いて経時的に計測した.(1)「全介助群」で入院2週後の両側大腿,下腿筋断面積は,入院時の79~86%(両側大腿,下腿各々の平均80%,84%)と有意に減少し,4週時に69~79%,8週時に62~72%まで萎縮した.(2)「早期歩行自立群」では,2週時で96~100%と断面積を維持していた.(3)両群の「中間群」では,2週時に89~95%と有意に減少したが,8週時には入院時の94~99%(入院時と有意差なし)まで回復した.早期リハビリテーション患者でも廃用性筋萎縮は見られ,麻痺側でも十分な訓練により筋肥大をきたすが,回復には歩行訓練開始までの期間の3倍以上の長期間かかることが示唆された.
2 0 0 0 OA 旅行速度からみた自動車交通アクセシビリティ
- 著者
- 田中 耕市
- 出版者
- Geographic Information Systems Association
- 雑誌
- GIS-理論と応用 (ISSN:13405381)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.39-46, 2001-03-30 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 2
This study attempts to clarify the actual road traffic circumstances and to investigate the change of accessibility of Nagano Prefecture from 1990 to1997 by using GIS. The main findings are summarized as follows. Firstly, there is a great difference between the speed of automobiles moving in the city and those moving outside the city. Secondly, as a result of extension of highway, time distance from Matsumoto to Hokushin area is reduced largely. Then, movement efficiency of automobile in Nagano Prefecture has improved, and the time required for the movement by 1km is improved from 1.3 minute to 1.0 minute.
2 0 0 0 OA 1.高齢者の救急医療について
- 著者
- 長谷川 浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.114-118, 2020-04-25 (Released:2020-05-29)
- 参考文献数
- 5
高齢者の増加に伴って救急医療の需要はさらに増大し,高齢者の救急搬送も全体の約6割(354万人)を占めている.搬送困難(受入困難)は大きな社会問題である.救急で入院し,原疾患の治療を終えた高齢者がADLの低下や社会的問題で自宅への退院ができなくなった場合,いわゆる出口問題が出現する.救急医療こそ地域連携が重要であり,医療・看護・介護システム(地域包括ケア)の中の資源と捉え,積極的に密接な地域連携を構築することが極めて重要であると考えられる.
2 0 0 0 OA 非アルコール性脂肪肝炎の診断と治療
- 著者
- 徳重 克年
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.8, pp.1670-1676, 2021-08-10 (Released:2022-08-10)
- 参考文献数
- 17
非アルコール性脂肪性肝疾患(nonalcoholic fatty liver disease:NAFLD)は,本邦に約2千万人以上の患者がおり,生命予後に関わる高度線維化群は今後さらに増加することも危惧されている.この2千万人以上のなかから,肝線維化・肝硬変NAFLDの効率的な拾い上げ,また近年非ウイルス性肝疾患を基盤とする肝細胞癌(hepatocellular carcinoma:HCC)が増加しており,そのスクリーニングの必要性も唱えられている.今回,診療ガイドラインの改訂に伴い,1)肝線維化の重要性,2)線維化群の効率的な拾い上げ,フォローアップ方法,3)肝発癌に関するスクリーニング方法,4)新たな治療方針を中心にNAFLDの最新の情報を概略した.今後,NAFLDの肝線維化の重要性が広く認識され,線維化・HCCのスクリーニングが効率的に行われ,最終的に有効な治療につながることを望む.
2 0 0 0 OA 足底圧中心変化に伴う足部周囲筋の筋積分値相対値変化
- 著者
- 山口 剛司 高崎 恭輔 大工谷 新一
- 出版者
- 関西理学療法学会
- 雑誌
- 関西理学療法 (ISSN:13469606)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.103-108, 2005 (Released:2006-01-26)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 12
The foot region plays an important role in postural control. It is often observed that improvement of foot and foot joint functions leads to improvement of movements of the lower limbs, pelvis, trunk, and eventually the entire body. We generally use the position of plantar pressure as a parameter for the evaluation of the foot region and foot joints, because the center of plantar pressure (COP) provides important information. In patients with dysfunction in the foot region, COP is often deviated to the big or little toe side during movements, or induction of COP from the little toe side to the big toe side is often difficult. In therapeutic exercise for control of COP in such patients, closed kinetic chain exercise is considered effective. In such exercises, monitoring of the necessary activities of the peripedal muscles caused by changes in COP is important. In this study, we examined the electromyographic integral of the peripedal muscles caused by changes in COP using a ground reaction force plate and electromyography. In the measurement, a surface electromyograph, Mlyosystem 1200 (NORAXON Co.), was used for recording electromyography. For electromyography analysis, MyoResearch (NORAXON Co.) software was used for calculation of the integrated values of the electromyography. A force plate (Anima Co.) was synchronized with the surface electromyograph. Weight loading on the forefoot and hind foot induced characteristic muscular activity patterns of muscles around the foot. For changing COP, muscular activity of muscles around the foot is necessary, and it is important to know that the muscular activity pattern varies depending on the position of COP.
2 0 0 0 OA 過失犯における注意義務の内容
- 著者
- 古川 伸彦
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.347-360, 2007-04-01 (Released:2020-11-05)
2 0 0 0 OA 重水素重水(D2O)による水分代謝の研究
- 著者
- 高井 俊夫 松本 一男 仲井 正名 杉野 昭一
- 出版者
- 一般社団法人 日本質量分析学会
- 雑誌
- Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan (ISSN:13408097)
- 巻号頁・発行日
- vol.1957, no.9, pp.35-43, 1957-10-01 (Released:2010-06-28)
2 0 0 0 OA 経験の分離と飛び地 ―野宿を経験した一人の男性とハウジング・ファーストの支援実践―
- 著者
- 山北 輝裕
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.5-18, 2020 (Released:2021-05-29)
- 参考文献数
- 13
本稿は、長期野宿者に対して居宅をすみやかに提供し、居宅移行後もケアを継続する支援実践であるハウジング・ファーストを質的調査から検討する。なかでもアパートに出現する「幽霊」に悩む男性の経験をめぐって、その男性、支援者、福祉事務所、不動産屋、地域住民との間で経験の分離がどのように立ち現れ、そしてそれに人々がどのように向き合うのかという問題に着目した。そのことで、ハウジング・ファーストのフィデリティである無条件性がどのように達成されているのかが明らかになった。当事者と支援者は経験の分離から離脱せず、両者が共有する「経験の飛び地」を志向することによって、相互作用を継続させた。そのことが結果的に当事者に変容を迫らない無条件性を成立させていた。しかし経験の分離が保たれたまま「飛び地」を志向することは、両者を取り巻く社会においては容易に共有されず、否定されていた。住居提供にとどまらず、「飛び地」を拡大することに当事者たちの生活を支える社会運動としてのハウジング・ファーストの意義が存在する。
- 著者
- 大友 令史 菊池 英樹 新山 徳光
- 出版者
- 北日本病害虫研究会
- 雑誌
- 北日本病害虫研究会報 (ISSN:0368623X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.69, pp.195-198, 2018-12-21 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 6
ホップの害虫であるアサトビハムシは,ホップの萌芽期に加害を開始する.本種による被害は剪芽における良質な芽の確保に支障をきたす.ホップに既登録のカルタップ75.0%水溶剤およびビフェントリン2.0%水和剤は本種に高い防除効果を示すことから,萌芽時に本種の被害を確認したら,直ちにこれらの薬剤を散布することにより本種の被害を防止できる.
2 0 0 0 OA 中近世イベリア半島におけるユダヤ人(マラーノ)の移動
- 著者
- 関 哲行
- 出版者
- 京都ユダヤ思想学会
- 雑誌
- 京都ユダヤ思想 (ISSN:21862273)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.94-106, 2018-06-21 (Released:2023-04-03)
2 0 0 0 OA 産業保健と法~産業保健を支援する法律論~ 健康情報等の取扱いと法
- 著者
- 林 幹浩 淀川 亮 清水 元貴 三柴 丈典
- 出版者
- 公益財団法人 産業医学振興財団
- 雑誌
- 産業医学レビュー (ISSN:13436805)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.123, 2020 (Released:2020-09-01)
2 0 0 0 OA 薬学における過去の名著 ―日本における薬学書―
- 著者
- 久保 道徳
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.58-62, 1999-01-31 (Released:2011-09-21)
2 0 0 0 OA 新教育課程における学習評価改善の趣旨 資質・能力の育成にどう活かすか
- 著者
- 市川 伸一
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 科学教育研究 (ISSN:03864553)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.69-74, 2023 (Released:2023-07-08)
- 参考文献数
- 11
After the revision of the government course guidelines, the Japanese Ministry of Education changed the form of the cumulative guidance record in 2019. It was determined that the new evaluation is based on three viewpoints: “knowledge and skills”, “thinking, judgment, and expression,” and “self-directed attitude toward learning.” In the present paper, the implications and methods of these evaluations are summarized. Self-directed attitude toward learning is a new point and is often regarded as difficult to understand. It contains two aspects: persistent efforts and self-regulation of learning. The latter is derived from psychological studies about “self-regulated learning” based on the three phases of “forethought – performance – reflection.” However, we should also consider the larger contexts of learning, and improve daily lessons and evaluation methods to foster students’ self-regulation.
2 0 0 0 OA 九~十世紀の貨幣鋳造機関
- 著者
- 竹内 亮
- 出版者
- 奈良県立万葉文化館
- 雑誌
- 万葉古代学研究年報 (ISSN:27583511)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.10-23, 2023 (Released:2023-03-30)
2 0 0 0 OA タガメの卵塊における一斉孵化メカニズムとその意義
- 著者
- 大庭 伸也
- 出版者
- 一般社団法人 日本昆虫学会
- 雑誌
- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.4, pp.157-164, 2002-12-25 (Released:2018-09-21)
- 参考文献数
- 13
孵化の様子を観察した結果,タガメの卵が孵化するとき,卵殻と薄い膜を破って幼虫が出てくる.卵殻を破って出てくることを「卵殻孵化」,透明な膜を破って出てくることを「胚脱皮」と称することとした.卵塊中の全ての卵が卵殻孵化を終えるのに約20分を要するのに対して,それらの卵が胚脱皮を終えるには約5分しかかからない.その後,体を出して前脚を広げた幼虫のうち,1匹の幼虫が中後脚を動かし,卵殻から出て落下しようとすると,その接触刺激が隣接する幼虫へと連鎖的に広がっていき,卵塊レベルで孵化した幼虫が一斉に水中へと落下した.常に湿った状態では,卵殻孵化が胚脱皮よりも時間を要したのに対し,オスが保護してきた,つまり乾燥と給水を繰り返した,孵化直前の卵に水をかけると,全ての卵の卵殻が割れたことから,保護オスが給水により,卵殻孵化のタイミングを調節可能であることが示唆された.胚脱皮は破裂音を伴うので,その振動を感知した他の卵も胚脱皮すると考えられ,1個の卵の胚脱皮が周辺の卵の胚脱皮を誘発し,全ての卵の胚脱皮が短時間で起こる.以上の結果から,タガメの卵塊における一斉孵化のメカニズムには,卵殻孵化については保護オスが,胚脱皮と幼虫の水中への落下については,卵または幼虫のコミュニケーションが関わっていることが明らかになった.
2 0 0 0 OA 広がる地下鉄ネットワーク —東京メトロ副都心線の開通—
- 著者
- 徳永 将志 西村 怜馬 藤田 吾郎 古瀬 充穂
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.128, no.6, pp.342-345, 2008-06-01 (Released:2008-06-01)
本記事に「抄録」はありません。