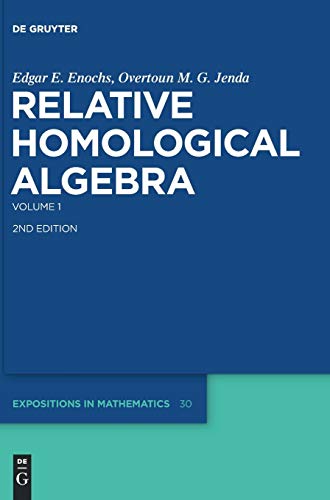1 0 0 0 OA 鎌倉材木座遺跡出土の中世犬骨
- 著者
- 茂原 信生 小野 寺覚
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.3, pp.361-379, 1987 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
鎌倉材木座遺跡(鎌倉時代~室町時代)から出土したイヌ(最小個体数30体)のうち,成獣8体(オス6,メス2)の頭蓋を中心に調査し,他の時代の犬骨と比較検討した。材木座犬骨は繩文犬より額段が小さく原始的である。頭蓋最大長の平均値は,繩文時代の田柄貝塚犬骨の平均値を上回っている。長径が大きくなっているわりに高径や幅径は大きくなっていない。この点で高径や幅径が大きいより後代の中世•近世犬骨とは異なっている。頑丈で,プロポーションは繩文時代犬骨とよく似ている。日本古代犬の体の大きさは繩文時代から鎌倉時代までに変化したが,頭蓋のプロポーションは,鎌倉時代よりあとの時代に大きく変化したと推測される。
1 0 0 0 OA The Effects of Pronunciation Practice with Animated Materials Focusing on English Prosody
- 著者
- SONOBE Hideyuki UEDA Makoto YAMANE Shigeru
- 出版者
- 外国語教育メディア学会
- 雑誌
- Language education & technology (ISSN:04587332)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.41-60, 2009-06
It has often been suggested that prosody, encompassing rhythm, accent and intonation, contributes greatly to the production of natural-sounding English and furthermore, that these suprasegmental elements play an important role in successful communication. Japanese EFL learners, influenced by the mora-timed rhythm of their mother tongue, tend to use Japanese rhythmic patterns when they speak English. This study attempts to demonstrate how the authors' original animated Web materials focusing on English rhythm enabled students to improve their English pronunciation. From our experiment, carried out once a week for five weeks in a CALL classroom, some positive effects of rhythmic pronunciation practice were found on the learners' pronunciation. Clear correlations among the speech duration, pitch ranges, and naturalness of the English produced by Japanese EFL learners were also found.
1 0 0 0 濁音の前の鼻母音--その成立・衰退と音便 (近代語)
- 著者
- 柳田 征司
- 出版者
- 至文堂
- 雑誌
- 国語と国文学 (ISSN:03873110)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.11, pp.1-10, 2002-11
1 0 0 0 女性のトップスポーツリーグの支援施策に関する研究
女性スポーツに少なからぬ影響を及ぼしているメディアとジェンダーの関係を中心に研究をすすめた。メディアで醸成される身体や運動・スポーツに関わる言説は、筋肉に象徴される逞しい男性の身体と、無駄な脂肪の少ないしなやかな女性の身体という、性によって異なる理想の身体像をつくりだした。その背景には、スポーツの産業化の進展によるフィットネスクラブの急増、テレビメディアを介してのスポーツの氾濫があった。「フィットネス」は、より積極的に理想の身体を獲得するための営みとなり、改造可能な身体観がもたらされた。1980年以降のBMIの推移をみると若い女性のスリム化傾向は著しく、男性は体格向上ないしは肥満化傾向にある。身体のジェンダー化は着実に浸透している。身体を重要な要素とするスポーツはジェンダー化された身体像の影響を大きく受けている。スポーツを題材としたテレビコマーシャルの映像分析を行った結果、男性が主人公となるCFが64.8%で女性の14.3%を大きく上回っていた。質的にも異なる描写がなされ、男性スポーツ選手はメディアを介してより偉大に描かれていくのに対して、女性スポーツ選手は矮小化されていくことが明らかになった。女性スポーツ発展のためには、ジェンダーにとらわれない個性ある身体を見直すこと、メディアを批判的に読み解き、是正する声をあげることの重要性が示唆された。また継続して考察を進めてきた女子サッカーリーグの運営と観戦者に関する日米比較研究からは、女性ファンの開拓、スター選手のメディア露出、女子サッカーのプレイ環境の整備などの課題が示唆された。
1 0 0 0 IR 中国雲南方言母語話者による日本語音声の特徴
- 著者
- 永野マドセン 泰子 山元 淑乃 楊 元 Nagano Madsen Yasuko Yamamoto Yoshino Yang Yuan
- 出版者
- 琉球大学留学生センター
- 雑誌
- 留学生教育 : 琉球大学留学生センター紀要 (ISSN:13488368)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.17-34, 2013-03
中国語雲南方言の単一話者による日本語音声を分析し、その全体像を把握した。日本人が聞いて不自然でかつ学習効果が少ないと思われる問題点は「子音の強さ」、濁音が清音になる、および「ら行」の音であった。これらについては音響分析により日本人母語話者との差異を指摘した。母音については、狭母音と広母音の差が少ない中国語の特徴がそっくり日本語の母音のパターンに移されていることが観察された。これらの結果から、雲南方言でも北京方言同様、子音の問題が大きいことが明らかになった。Japanese speech sounds produced by a single Chinese speaker was analyzed. The results showed three areas that are most problematic: obstruents being too strong, voiced obstruent become voiceless, and the realization of /r/ is different. For these, spectrographic analyses showed the difference between a native Japanese speaker and the Chinese learner. The Chinese vowel formant pattern was nearly directly transferred to the Japanese vowel pattern and little effect of learning was observed.
1 0 0 0 OA 南米・北パタゴニア氷原の氷河変動と環境変動の対応解析
本研究期間の2010 年度から2014 年度までの4年間で氷河後退により面積が8.43km2減少した。最大の後退はサン・キンティン氷河の3.35km2であった。その他顕著な後退をした氷河は、コロニア、シュテフェン、HPN3、フィエロ、ベニートである。一方、サン・ラファエル氷河、グアラス氷河、レイチェル氷河(以上氷原西側)、ピスシス氷河、パレッド・スール氷河、レオン氷河(以上氷原東側)、エクスプロラドーレス氷河(北側)、はほとんど変化しなかった。細かく変動を見ると、2013-15年の1氷河当たりの後退速度は2011-12の1/5、2012-13の約1/3となっており、後退速度が鈍化した。
- 著者
- 小澤 実
- 出版者
- 化学史学会
- 雑誌
- 化学史学会 (ISSN:03869512)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.74-77, 2010 (Released:2010-08-18)
1 0 0 0 沖縄県那覇市の住民組織について-「自冶会」研究ノート(その2)-
- 著者
- 高橋 勇悦
- 出版者
- 東京都立大学
- 雑誌
- 総合都市研究. 特別号 (ISSN:03863506)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.149-163, 1995-03-30
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 絶対音感保有者の音楽的音高認知における言語符号化
- 著者
- 宮崎 謙一
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.36-39, 2005 (Released:2011-07-05)
- 参考文献数
- 19
1 0 0 0 OA ナミハダニ黄緑型のキク上での発生消長と寄生部位
- 著者
- 國本 佳範 西野 精二 大辻 純一 有馬 毅
- 出版者
- 日本ダニ学会
- 雑誌
- 日本ダニ学会誌 (ISSN:09181067)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.11-16, 1997-05-25
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 5
奈良県北葛城郡新庄町のキク圃場で, ナミハダニ黄緑型の寄主植物およびキク圃場での発生消長, キクへの寄生部位を調査した。1. キク圃場周辺の数種の雑草でナミハダニの寄生を確認した。2. 慣行の薬剤散布条件で栽培された2品種"紅葉", "リンカーン"上でのハダニの発生消長はピークの期間などに違いはあったが, おおむね一山型であった。3. 両品種とも収穫後の株や翌春伸長したシュートにもハダニが寄生しており, 挿し芽を経て, 苗に寄生したまま新しい圃場へと移動し, 繁殖した。4. キク上のナミハダニは定植後1ケ月以上経過した後の7月以降に急激に密度を増し, 9月ころにピークを迎えた。その後, 個体数は減少するものの, 2月でも寄生が認められ, 周年でキク上にハダニの寄生が認められた。5. キクへのナミハダニの寄生部位は, 植物の生育状況に左右されて変動した。
極性半導体の例としてGaAsを対象にコヒーレントフォノンの生成過程を微視的な理論から明らかにした。また、SbとSiについてコヒーレントフォノンの観測過程のシミュレーションを行った。さらに研究の実施計画にはない点として、応用数理に基づく効率的な固有値解法をBogoribov-de Genness方程式に適用し、その有効性を実証した。GaAsに対して、これまでに開発した手法を適用し、その生成機構の第一原理シミュレーションを行った。これまでに明らかにしてきたSiやSbと同様、Raman過程に伴うコヒーレントフォノンの励起機構が第一原理的に再現されることを確認し、極性半導体のGaAsにおいても既存の理解が適用できることを示し、力の絶対値を評価した。さらに、極性半導体特有のメカニズムである瞬間的な表面電場の消失に伴う物理過程を特徴づけるBornの有効電荷の計算を行った。既存の研究では定常電場を含めた自由エネルギーを最小にするアプローチで第一原理的に計算されていたが、我々は電場を断熱的に加えることで定常電場を模したシミュレーションを行い、我々のアプローチで、理論の先行研究、および実験値と良い一致を見、本アプローチで定常電場がかかった状態をうまく記述できていることを示した。論文をまとめる為の計算結果は概ねとり終わっている。コヒーレントフォノンの生成過程の第一原理シミュレーションでは、Siに対しては十分な結果が得られたが、Sbについては、十分な精度を計算で達成するためには莫大な計算コストがかかることが判明したため、他の物質でのシミュレーションも合わせて論文にまとめる方針を検討している。前年度デュアルディグリープログラムで培った応用数理の知見を活かし、高効率固有値解法である櫻井杉浦法をBogoribov-de Genness方程式に適用し、高効率計算が出来る事を実証し、超大規模系の理論計算の可能性を示した。
1 0 0 0 OA 救急外来トリアージ基準確立のための情報収集システム構築に関する研究
1 0 0 0 OA 帯状疱疹後神経痛治療中に出現したcrowned dens syndromeの1例
- 著者
- 岩田 人美 岡崎 敦
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.94-97, 2012 (Released:2012-06-20)
- 参考文献数
- 13
帯状疱疹後神経痛(以下,PHN)治療中に発症したcrowned dens syndrome(以下,CDS)の診断に難渋した症例を経験したので報告する.症例は78歳女性.左胸部に発症したPHNのためブプレノルフィン口腔粘膜錠(FTB-8127)の第3相臨床試験に参加した.治験開始後1週間でPHNの痛みは軽減したものの,強い頸部痛,後頸部の熱感と頭部後屈制限が発現した.咽後膿瘍や髄膜炎を疑がったが諸検査から否定され,脊椎CTでは,環椎横靱帯に淡い石灰化沈着があり,CDSと診断した.非ステロイド性抗炎症薬投与を行い1週間後には後頸部痛は消失した.CDSは,急激に発症し,強い頸部痛,嚥下痛と頭部後屈制限を呈する疾患であり,確定診断は強い炎症反応と歯状突起周囲環椎横靱帯の石灰化で行う.急激に発症し,強い頸部痛と頭部後屈制限を呈する症例ではCDSを念頭に置く必要がある.
1 0 0 0 OA Crowned dens syndromeの2例
- 著者
- 前田 和政 古市 格 村田 雅和 宮田 倫明 穂積 晃 久芳 昭一 松村 陽介
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.869-871, 2010-09-25 (Released:2010-12-08)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 2 1 1
Crowned dens syndrome(CDS)は急性に発症する重度の頚部痛と頚椎可動域制限を呈し,CT上歯突起周囲の石灰化が認められる症候群である.その病因は,歯突起周囲の結晶沈着といわれている.高齢女性に多いといわれているが,比較的若年者にも発症していた.CDSの2症例を経験したので,報告する.症例1.68歳女性.特に誘因なく,頚部の違和感が出現.後頭部部痛と頚部硬直が出現するも自宅で安静にしていた.数日後近医受診し,くも膜下出血疑いで当院脳神経外科に紹介されるも診断がつかず,当科紹介.CTで歯突起周囲の石灰化を認め,CDSと診断した.症例2.38歳女性.2,3日前からの頚部違和感あり.後頭部痛と頚椎可動域制限出現し当科受診.CT上歯突起周囲に石灰化を認め,CDSと診断した.両症例に対して内服治療を行い,1週間以内に疼痛は軽快した.
1 0 0 0 Relative homological algebra
- 著者
- Edgar E. Enochs Overtoun M. G. Jenda
- 出版者
- De Gruyter
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 OA 菅平湿原のクリプト藻
- 著者
- 恵良田 真由美 千原 光雄
- 出版者
- 筑波大学菅平高原実験センター
- 雑誌
- 菅平高原実験センター研究報告 (ISSN:09136800)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.57-69, 1987-03-25
Collections of cryptomonads were made twice in the Sugadaira-Moor (Nagano Prefecture, Japan) in July, 1982 and November, 1985. The specimens were cultured in unialgal conditon and then examined by the light microscope. As a result, it was recognized that threr were 10 species of cryptomonads, which belonged to four genera and two families, occurred in this moor. Among these species, six were found for the first time in Japan and three which belong to the genus Cryptomonas appeared to be undescribed taxa.クリプト藻植物は2本の鞭毛をもつ単細胞性藻類の一群である。本植物は細胞構造が特徴的であること、および光合成補助色素としてフイコピリンをもつことなどから,他の藻群からよく区別できるまとまった群であるとされている。しかしながら,識別形質があまりにも少ないこと、および細胞が脆弱で容易にこわれてしまい充分な観察がしにくいことなどから,種の階級の分類は非常に困難である。特にわが国においては本植物群の分類学的研究は皆無といってよい。著者らはわが国におけるクリプト藻植物相の知見を蓄積する目的で、国内各地より採集した材料について調査研究を進めている。本報告はその一環として行なった調査の結果である。菅平湿原は筑波大学菅平高原実験センターの西方約2kmに位置する典型的な山地湿原であり(Fig 1.)クリプト藻のみならず多様な淡水藻類の生育が知られている。本報告では菅平湿原から採集したクリプト藻類のうち分類群として明確に認識された4属10種を扱う。クリプト藻類は淡水産のものだけでも全世界で100種以上が記載されており、しかもそれらの大部分は冷涼なドイツ・スイス・オーストリア・北欧を中心に報告されていることから,今後本湿原の調査を重ねることにより、さらに新たな分類群が見出されるものと期待される。
- 著者
- Kristensen Niels P.
- 出版者
- 筑波大学菅平高原実験センター
- 雑誌
- 菅平高原実験センター研究報告 (ISSN:09136800)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.101-102, 1991-03-26
The integument of the dorsal/dorsolateral surfaces of micropterigid larvae (Lepidoptera, suborder Zeugloptera) has a strikingly specialized, non-solid, cuticle which seems unparallelled in the phylum Arthropoda. ・・・
- 著者
- Kristensen Niels P.
- 出版者
- 筑波大学菅平高原実験センター
- 雑誌
- 菅平高原実験センター研究報告 (ISSN:09136800)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.105-106, 1991-03-26
Ongoing morphological research on the lowest glossatan lineages is disclosing massive homoplasy, which considerably impedes reconstruction of the basic phylogeny of this clade. ・・・
1 0 0 0 OA ジェンダーをめぐるコミュニケーション齟齬の研究:専門的概念の再帰性に着目して
学問の世界において生み出された概念である「ジェンダー」は,広く一般に使われる言葉として普及した.だが,その使用が政治的に批判されるようになると,「科学・社会・政治」が交錯し,相互に影響を与える状況が生じた.このような状況は,どのようなコミュニケーション齟齬を生み出したのだろうか.学問の世界における「ジェンダー」概念は,もともとかなり限定された文脈において創案されたものであるが,その文脈から切り離されることで,かえって広範な応用可能性を持つことになった.だが,その一方で,学問的であるか否かにかかわらず,「ジェンダー」概念の使用が批判されるという,複雑な政治的状況を招くことにもなったのである.