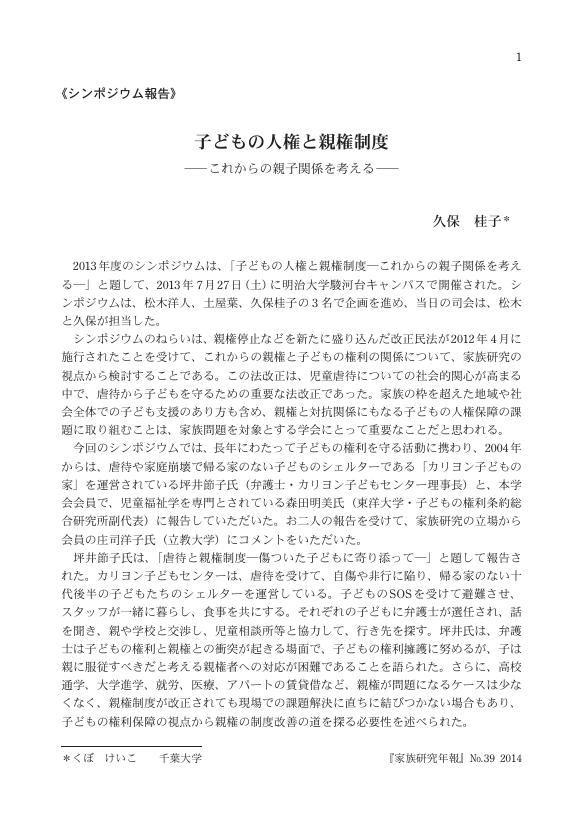2 0 0 0 OA e-教室プロジェクト:
- 著者
- 新井 紀子
- 出版者
- 独立行政法人 科学技術振興機構 情報事業本部
- 雑誌
- 情報科学技術研究集会予稿集 第40回情報科学技術研究集会予稿集
- 巻号頁・発行日
- pp.B61, 2003 (Released:2003-11-14)
- 参考文献数
- 3
「e-教室」プロジェクトは、新井らが開発を行った「NetCommons」という情報共有ポータルシステムを活用して、研究者·教員らが協力しながら、中高校生とともにインターネット上の学びのコミュニティを創出する試みである。「NetCommons」では、インターネット上で提供されているデジタルコンテンツを、ニーズに応じて、柔軟に活用しながら、テキストと画像を組み合わせて投稿できる掲示板システムを提供している。「e-教室」に参加している学習者は、学習支援者とともにコミュニティを形成しながら、インターネット上の学びの空間を体験する。ここでは、デジタル教材を利用しながらも、既存のシナリオにはとらわれない、自由度の高い総合的な学習を実現している。
2 0 0 0 OA デュルケム社会形態学における社会と空間
- 著者
- 島津 俊之
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.333-350, 1993-10-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 98
- 被引用文献数
- 3 2
It is challenging for social geographers to scrutinize the role of space in social theory. The author examines the significance of space in the development of Durkheim's conception of social morphology.The origin of social morphology is found in Durkheim's earlier presentation of the system of sociology. Durkheim, influenced by organicist theory prevailing in the 19th century, elaborated the system of sociology by analogy with that of biology and recognized the presence of‘morphology’inquiring into the way in which society is composed, i.e. into‘structure.’In The Rules of Sociological Method (1895), social morphology was regarded as a branch concerned with the classification of‘social types’in terms of differences in structure. However, at that time, it was to‘function’of society, such as morality or the law, that Durkheim attached much importance as subject matter. In fact social morphology, in the Rules, was assigned to provide for sociological explanations the‘laboratories’(social types) furnished with the value of alleged independent variables, i.e.‘dynamic density’and‘social volume.’On the other hand, Durkheim made his own distinction between the‘base’and‘superstructure’ of society. In his view, the‘base’means social groups from which the‘superstructure’ i.e.‘function’originates, which are called the‘substratum.’In the Rules Durkheim regarded as the subject matter of sociology‘social facts, ’which were classified into two major categories: substratum (morphological facts) and social life (physiological facts). In this classification system the elements of space (dwellings and the network of communications) were incorporated into the concept of substratum for the first time. Durkheim thought that the substratum was social life consolidated while it was a visible vehicle through which invisible social life might be approached.The above significance of the substratum became a precondition for the renewal of social morphology as an explanatory analysis of the substratum. This renewal was completed probably in response to Friedrich Ratzel's conception of geography. In this stage Durkheim incorporated into the substratum various kinds of space connected with society, especially Ratzelian concepts of‘Raum’and‘Grenzen.’Thus it is considered that space is a visible‘social form, ’a visible manifestation of society. The task of social morphology was to explain from the category of‘collective representations’the shaping of the substratum as an amalgam of social groups and space.Durkheim, however, went in the direction of distinguishing analytically between social groups and space. He utilized Georg Simmel's‘form-content’-dichotomy for this distinction. Further, the category of social group was given the term‘population’while that of space was called‘social space.’In the end social morphology was conceived to include a double task of explaining the formation of population distribution and of social space.
2 0 0 0 OA デュルケムの社会空間論 : その意義と限界
- 著者
- 島津 俊之
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.20-36, 1995-03-31 (Released:2017-05-19)
本稿は, デュルケムの社会空間論を発掘し, その意義と限界を明らかにすることを通じて, <社会-空間理論>構築への足がかりを得ようとするものである. これは, 彼の地理学的想像力を再評価する試みでもある. デュルケムにおける社会空間論の起点は, 1893年刊行の『社会分業論』の時点で形成されていた. 彼のいう社会空間は, 一貫して<社会が占める地理空間〉>を意味する概念であり, ラッツェルの刺激によって考案されたとも考えられる. デュルケムの社会存在論のなかで, 社会空間は社会集団とともに<基体=社会の身体>と位置づけられ, <社会の精神>たる社会生命に対峙することになる. 社会空間は, 社会生命が空間に下ろした<足場>ともなる. 一方で, 未開社会を対象に<知識社会学>を展開したデュルケムは, 社会空間が分類体系や空間カテゴリーのモデルになったと推論する. 社会空間は, ある種の社会生命の生成に際して, それに<かたち>を与える媒介変数の地位を与えられたのである. デュルケムの社会空間論は, 様々の限界や矛盾を孕む一方で, 豊かな地理学的想像力の見木を提供するものでもある. それは, 社会空間を社会の不可欠な要素と認識し, その役割を積極的に評価しようとするものであった.
2 0 0 0 OA 土地利用と土壌組成の関係性からみた見沼田圃公有地化推進事業による保全の再検討
- 著者
- 石井 秀樹 斎藤 馨
- 出版者
- 一般社団法人 環境情報科学センター
- 雑誌
- 環境情報科学論文集 Vol.25(第25回環境研究発表会)
- 巻号頁・発行日
- pp.293-298, 2011 (Released:2014-05-08)
本稿では「見沼田圃公有地化推進事業」を事例として,見沼田圃各地に点在する公有地の土地利用と土壌組成の関係性に注目し,地の利にあった土地管理を検討した。見沼田圃の土壌はりん酸が枯渇しやすい黒ボク土だが,地下には大量の植物遺骸が埋没しており腐植が多い。調査の結果,有機物を土壌還元する「見沼田んぼ福祉農園」では,りん酸や加里を充足する土壌システムが形成されている可能性が示唆された。市民活動には,収益性よりも手間・暇をかけ達成感を得ることを目的とする活動も多く,有機物を還元に重きをおいた管理方法は見沼田圃の地の利を活かすとともに,保全活動の魅力を高め,当該事業の持続可能性を高めると考えられた。
2 0 0 0 OA 映像のなかの原爆乙女 —安部公房/勅使河原宏映画『他人の顔』論—
- 著者
- 友田 義行
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.11, pp.38-50, 2011-11-10 (Released:2017-05-19)
安部公房原作脚本・勅使河原宏監督による映画『他人の顔』には、顔の右半分にケロイドを負った女性が登場する。小説から映画へと変成される過程で、彼女の存在は議論の的となった。本稿ではこの作品を、原爆投下という破壊的・暴力的な出来事に対する文化的反応として捉え返し、女性被爆者の表象について考察する。言語(原作・台本)と映像(演出・編集・美術・音響)を横断して、「原爆乙女」の表象(不)可能性と、それをめぐる作家たちの想像力を吟味する。
2 0 0 0 OA 仮名文字の複雑性を表す指標としての周囲長複雑度の妥当性
- 著者
- 齋藤 岳人 樋口 大樹 井上 和哉 小林 哲生
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.93.20237, (Released:2022-02-10)
- 参考文献数
- 24
Perimetric complexity, which is a simple metric of character (letter) complexity defined by an image’s area and peripheral length, has been widely used, especially in alphabetic orthographies. We examined whether perimetric complexity is also a valid index for Japanese kana characters (hiragana and katakana) by comparing it with subjective complexity. We obtained evaluations of subjective complexities from Japanese and English speakers and calculated the mean of each character for each type of speaker for character-based analyses. The analyses revealed three main findings: (a) Perimetric complexity was highly correlated with subjective complexity (rs > .85), and its correlation was higher than that between the subjective complexity and other measures for character complexity (i.e., stroke count). (b) The perimetric complexities were highly correlated across different typefaces, except for significantly different typefaces. (c) Subjective complexity was highly correlated between Japanese and English speakers. These findings suggest that perimetric complexity can also be used as an index for Japanese kana character complexity.
2 0 0 0 OA 嗅覚情報が両眼視野闘争に与える影響
2 0 0 0 OA 愛知県東部中新統設楽層群玖老勢層に産する礫岩: 北設亜層群堆積期における後背地の変化
- 著者
- 藪田 桜子 竹内 誠 斎藤 眞
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.12, pp.689-700, 2021-12-15 (Released:2022-01-19)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 2
中新統北設亜層群最上部の玖老勢層上部には,チャネル構造を呈する複数の礫岩層が分布する.本研究では,玖老勢層礫岩の礫種構成と珪質泥岩礫の放散虫化石による年代を明らかにした.玖老勢層礫岩は,火山岩・凝灰岩・凝灰角礫岩礫を主とし,花崗岩類・石英岩・チャート・珪質泥岩・泥岩・砂岩・マイロナイト礫を伴う.珪質泥岩礫中の放散虫化石は中期ジュラ紀の年代を示す.北設亜層群下部の砕屑物は,主に北設亜層群の基盤岩である領家花崗岩類・変成岩類起源である一方で,北設亜層群最上部玖老勢層ではジュラ系などの古期岩類を含む,より広範囲の地質体から砕屑物が供給されるようになったことが明らかになった.
2 0 0 0 OA 口蓋扁桃アニサキス症 (Pseudoterranova decipiens) の1例
- 著者
- 酒井 昇 酒井 博史 神谷 正男 秋田 久美 白峰 克彦
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.178-183, 2003-05-20 (Released:2013-05-10)
- 参考文献数
- 13
口蓋扁桃アニサキス症の1例と原因幼虫の病理を報告した。症例は35歳女性でボラ生食後咽頭異物感を来し、右口蓋扁桃中央の陰窩に寄生虫が迷入しているのが認められた。摘出した虫体は病理学的にPseudoterranova decipiensの第4期幼虫と判明した。アニサキス症で胃や腸などの消化管以外の異所寄生の報告は時にみられるが、耳鼻咽喉科領域でも口腔、咽頭の症例が少数報告されている。扁桃のアニサキス症はこれまで4例報告されているのみで、いずれも原因幼虫はアニサキスであり、記載不明の1例を除いた3例に急性扁桃炎が伴っていた。本症例では原因幼虫が口蓋扁桃で最初の報告となるPseudoterranova decipiensであり、また扁桃の炎症症状が全くみられなかったが、その理由としてシュードテラノーバ幼虫は感染力が弱く組織侵入が少ないことが推測された。
2 0 0 0 OA 足尾山地鳴神山東方地域から産出した三畳紀・ジュラ紀放散虫化石の報告
- 著者
- 伊藤 剛 中村 和也 日野原 達哉 栗原 敏之
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.345-358, 2021-10-13 (Released:2021-10-20)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 5
本論では,足尾山地鳴神山東方に分布する足尾帯ジュラ紀付加体の大間々コンプレックス及び黒保根–桐生コンプレックスから産出した放散虫を報告する.三畳紀放散虫及びコノドント片が大間々コンプレックスのチャートから産出した.中期ジュラ紀のバッジョシアン期及びバトニアン前期の放散虫が大間々コンプレックスと黒保根–桐生コンプレックスの泥岩から得られた.先行研究で両コンプレックスから報告された中では,泥岩に含まれるバッジョシアン期の放散虫が最も若い記録であった.従って,本研究で報告したバトニアン階下部の泥岩は,より若い記録となる.
2 0 0 0 OA 5 万分の1 地質図幅「桐生及足利」地域の足尾帯ジュラ紀付加体から産出した放散虫
- 著者
- 伊藤 剛
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.287-324, 2021-10-13 (Released:2021-10-20)
- 参考文献数
- 199
- 被引用文献数
- 5
足尾山地には足尾帯ジュラ紀付加体が分布する.このジュラ紀付加体は,黒保根–桐生コンプレックス・大間々コンプレックス・葛生コンプレックス・行道山コンプレックスの4コンプレックスからなる.本論では,5万分の1地質図幅「桐生及足利」地域の足尾帯ジュラ紀付加体の42試料から新たに産出した放散虫について報告する.ペルム紀放散虫は,行道山コンプレックスのチャート9試料から産出した.三畳紀放散虫は,葛生コンプレックスのチャート4試料から産出した.また,ジュラ紀放散虫は,黒保根– 桐生コンプレックスの珪質泥岩1 試料,葛生コンプレックスのチャート2試料,葛生コンプレックスの珪質泥岩4試料,葛生コンプレックスの泥岩2試料及び行道山コンプレックスの泥岩1 試料から産出した.加えて,足尾山地ジュラ紀付加体におけるこれまでの化石産出とその年代についてとりまとめた.これらを踏まえ,各コンプレックスの海洋プレート層序を復元した.
2 0 0 0 OA 足尾山地のジュラ紀付加体の地質と対比:5 万分の1 地質図幅「桐生及足利」地域の検討
- 著者
- 伊藤 剛
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.4, pp.201-285, 2021-10-13 (Released:2021-10-20)
- 参考文献数
- 260
- 被引用文献数
- 5
足尾山地には足尾帯に属するジュラ紀付加体が分布する.5万分の1地質図幅「桐生及足利」の調査結果及び周辺地域の先行研究に基づき,足尾帯ジュラ紀付加体の岩相・層序・化石年代・地質構造を総括する.足尾山地のジュラ紀付加体は,黒保根– 桐生コンプレックス・大間々コンプレックス・葛生コンプレックス・行道山コンプレックス(新称)の4つのコンプレックスに区分される.黒保根– 桐生コンプレックスは破断相から整然相を示し,泥岩とチャートを主体とし,珪質粘土岩を含む.また,玄武岩類・炭酸塩岩類・珪質泥岩・砂岩・泥質混在岩を伴う.泥岩に劈開が発達することで特徴づけられる.本コンプレックスは上部と下部に区分される.大間々コンプレックスは破断相から混在相を示し,玄武岩類・チャート・泥岩を主体とし,炭酸塩岩類・珪質泥岩・砂岩・泥質混在岩を伴う.本コンプレックスは上部と下部に区分され,泥質混在岩は上部で卓越する.葛生コンプレックスはユニット1・ユニット2・ユニット3に区分され,ユニット1及びユニット3はチャート・珪質泥岩・泥岩・砂岩泥岩互層・砂岩が順に累重するチャート– 砕屑岩シーケンスの整然相を主体とする.ユニット2は,玄武岩類と炭酸塩岩類からなり,礫岩・珪質泥岩・泥岩を伴う.行道山コンプレックスは混在相を示し,泥質混在岩及びチャートを主体として,珪質泥岩・泥岩・砂岩を伴う.コンプレックス境界として3条の断層を認めた:桐生川断層(黒保根– 桐生コンプレックスと大間々コンプレックスの境界)・閑馬断層(新称:黒保根– 桐生コンプレックスと葛生コンプレックスの境界)・大岩断層(新称:葛生コンプレックスと行道山コンプレックスの境界).地質構造としては,北東– 南西に伸びる軸跡を持つ複数の褶曲(梅田向斜・飛駒背斜・葛生向斜など)によって特徴づけられる.泥岩の放散虫年代に基づくそれぞれのコンプレックスの付加年代については,大間々コンプレックス及び行道山コンプレックスが中期ジュラ紀の中期以降,黒保根– 桐生コンプレックス及び葛生コンプレックスのユニット2が中期ジュラ紀の後期以降,葛生コンプレックスのユニット1及びユニット3が後期ジュラ紀の前期以降である.美濃帯ジュラ紀付加体の地質体と比較すると,黒保根– 桐生コンプレックスは那比コンプレックスや島々コンプレックスに対比可能である.大間々コンプレックスと葛生コンプレックスは,それぞれ舟伏山コンプレックス・白骨コンプレックスと上麻生コンプレックス・沢渡コンプレックスに対比できる.行道山コンプレックスについては,ペルム系チャートを含む点などでは久瀬コンプレックスと類似する.しかし久瀬コンプレックスが玄武岩類や炭酸塩岩類を含むのに対し,行道山コンプレックスはこれらを欠く.
- 著者
- 松岡 喜久次 桑原 希世子
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科学 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.2, pp.119-124, 2021-04-25 (Released:2021-06-30)
- 参考文献数
- 28
The Capitanian (Permian) radiolarians were found from a siliceous tuff block within volcaniclastic rocks in the Sumaizuku Unit of the Northern Chichibu Belt in the Kanto Mountains. The Sumaizuku Unit is composed of chaotic rocks consisting of exotic blocks of chert and mafic rocks in Jurassic clastic matrix. The rocks of studied area consist of limestone-basalt conglomerate, lime-sandstone, volcaniclastic rocks and chert. The volcaniclastic rocks are composed of clasts of basalt lava and volcanic glass accompanied with clasts of limestone, siliceous tuff and fragment of plagioclase. The clasts of siliceous tuff containing radiolarian tests are angular pebble to boulder. The siliceous tuff is regarded as blocks which were mixed in volcaniclastic rocks by slumping. We consider that the volcaniclastic rocks deposited immediately after Capitanian age, and this deposition formed on the lower flank of a seamount.
2 0 0 0 OA 子どもの人権と親権制度
- 著者
- 久保 桂子
- 出版者
- Japanese Council on Family Relations
- 雑誌
- 家族研究年報 (ISSN:02897415)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.1-4, 2014 (Released:2015-03-31)
- 著者
- 小澤 一仁 佐藤 侑人 成田 冴理
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.8, pp.575-592, 2018-08-15 (Released:2018-10-10)
- 参考文献数
- 177
- 被引用文献数
- 1
アルカリ玄武含に普遍的に含まれるスピネルカンラン岩捕獲岩の圧力推定についてレビューを行い,それがどのような理由でいかに困難であるかを共通認識として持てるように,これまで提案されてきた圧力推定方法の問題点をそれぞれの方法について指摘した.さらに,それらの問題をどのようにして解決し,充分な精度を持ったスピネルカンラン岩相の圧力推定方法を確立できるのかについての指針を示した.さらに,その推定値を検証するための方法として,マントル物質がマグマに取り込まれてから急冷するまでの時間スケールと上昇速度を組み合わせた方法を提案し,マグマの上昇に関するこれまでの研究をレビューし,有望な反応過程について考察した.
2 0 0 0 OA もう一つの原発震災―すべての被災者に目を
- 著者
- 斎藤 義浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.526, 2011 (Released:2019-09-06)
2 0 0 0 OA オカシサを計算する
- 著者
- 増山 英太郎
- 出版者
- 日本笑い学会
- 雑誌
- 笑い学研究 (ISSN:21894132)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.40-51, 2003-07-19 (Released:2017-07-21)
2 0 0 0 OA パノラマエックス線画像における根分岐部病変を自動検出するAIモデルの開発
- 著者
- 田島 聖士 園田 央亙 小林 誉
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.119-128, 2021-09-30 (Released:2021-09-30)
- 参考文献数
- 59
AI(Artificial Intelligence)を用いたダブルチェックを行うことが医療の標準化に寄与できるとされている。歯科および口腔外科診療において日常的に撮影されるパノラマエックス線画像は,顎口腔領域の状態を把握できる標準化された画像である。今回われわれはパノラマエックス線画像を用いた根分岐部病変を検出するAIシステムを開発したので報告する。教師用データとして,根分岐部病変を認めるパノラマエックス線画像10,640枚を用い,深層学習アルゴリズムの転移学習により,根分岐部病変を自動検出するDCNN(Deep Convolutional Neural Network)を構築した。評価用データとして下顎大臼歯に根分岐部病変の所見が認められるパノラマエックス線画像170枚を用いた。正答率,感度,特異度,適合率,再現率,F値を評価した。結果は,正答率は96.4%,感度は95.6%,特異度は97.1%,適合率は96.3%,再現率は95.6%,F値は0.96であった。パノラマエックス線画像を用いたDCNNの深層学習により根分岐部病変を検出するAIシステムは,歯科医療従事者および患者にも有益なものと考えられる。
2 0 0 0 OA 炎症性腸疾患に対する術前ステロイド投与例における周術期の管理
- 著者
- 大北 喜基 荒木 俊光 近藤 哲 奧川 喜永 藤川 裕之 廣 純一郎 問山 裕二 大井 正貴 内田 恵一 楠 正人
- 出版者
- 一般社団法人 日本外科感染症学会
- 雑誌
- 日本外科感染症学会雑誌 (ISSN:13495755)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.6, pp.655-659, 2018-12-31 (Released:2019-04-20)
- 参考文献数
- 21
近年の炎症性腸疾患に対する内科的治療は,従来から使用されてきたステロイドとともに免疫調節薬,生物学的製剤などの新しい内科的治療が開発され,治療薬の選択は多様化している。内科的治療は進歩したものの,治療抵抗や腸管合併症などの理由で手術を余儀なくされる症例は存在し,手術症例においては内科的治療が周術期管理に影響を与える可能性がある。長期ステロイド投与患者では,急性副腎不全に対する予防としてステロイドカバーが行われるが,従来の侵襲の大きさにかかわらず一律に高用量ステロイドを投与する方法から,近年では侵襲の程度に応じて投与量を決定する方法が推奨されている。炎症性腸疾患に対する手術は,内科的治療による免疫抑制のみならず,低栄養,慢性炎症などが原因で術後合併症,とくに感染性合併症の発生頻度が高いと考えられている。これまで多くの報告で術前ステロイド高用量投与が術後合併症のリスクとなることが示されており,ステロイドの投与量は手術タイミングと術式の選定,周術期管理を行ううえで重要な情報となる。
- 著者
- 奥山 亮 辻本 将晴
- 出版者
- 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター
- 雑誌
- イノベーション・マネジメント (ISSN:13492233)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.141-156, 2020-03-31 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 45
創薬は典型的なサイエンス型研究開発であり、基礎研究が新薬創出に大きく貢献してきたことは繰り返し指摘されている。しかしながら、医科学の基礎研究は主に生体機能の解明を目指してなされており、創薬を一義的に狙ったものではない。このことは、基礎研究で明らかにされる多数の新規生体分子や生理的機序といった科学的知見の中から、実際に創薬に結びつく分子やメカニズムを正しく選別する能力(本稿では「創薬標的選定能力」と呼ぶ)が創薬研究者に極めて重要であることを意味する。しかしながら、この「創薬標的選定能力」の概念は、これまでの研究では殆ど考慮されてこなかった。本稿では、日本発の革新的創薬事例を取り上げ、その研究プロセスの詳細な分析より、基礎研究成果の中から適切な創薬標的となる分子やメカニズムを選択する研究者の「創薬標的選定能力」が、創薬研究の競争優位を生むことを述べる。また、「創薬標的選定能力」の醸成には、生体機能を解明する医科学基礎研究への理解に加え、疾患の発症機序や先行薬剤の作用機序に対する深い理解と洞察が必要なことを述べる。本研究がもたらす学術的、実務的意義についても論ずる。