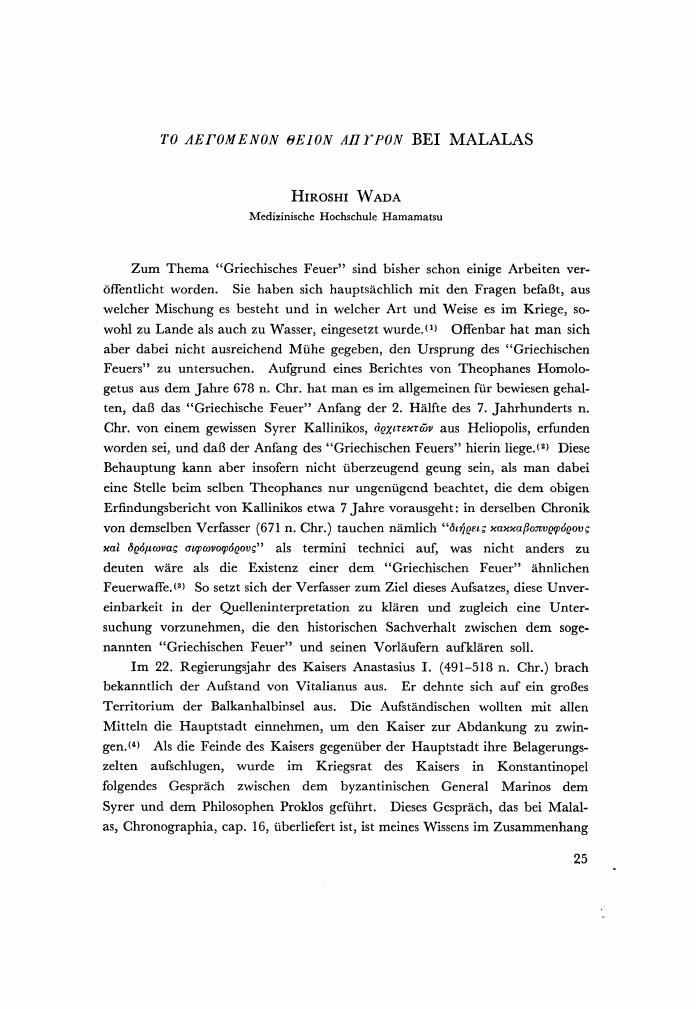1 0 0 0 緊急腹腔鏡にて診断・治療した特発性胆嚢穿孔の1例
- 著者
- 畑 倫明 村尾 佳則 則本 和伸 奥地 一夫
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 = The journal of the Japan Surgical Association (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.7, pp.1773-1776, 2002-07-25
- 被引用文献数
- 10
1 0 0 0 給電系に両平面回路を用いた平面アレーアンテナ
- 著者
- 江頭 広三 西山 英輔 相川 正義
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. B, 通信 (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.5, pp.798-804, 2003-05-01
- 被引用文献数
- 17
本論文では,誘電体基板の両面に複数種類の伝送線路を配置する「両平面回路」技術をアレーアンテナ給電系に適用することを提案する。すなわち,ここでは誘電体基板の表面にマイクロストリップライン,その裏面にスロットラインを配置して,互いに電磁結合させることにより新たな給電系を構成している。更に,この給電系を用いた4素子アレーアンテナについて,試作・実験を行った。その指向性を測定した結果,放射素子への鏡面対称給電による相補性の効果が得られ,不要な交差偏波を大幅におさえた良好な特性を確認した。
1 0 0 0 超磁歪効果を利用した選択方向強化複合材料の創製
構造用複合材料における材料設計の目的は、望みの力学的性質すなわち製品の応力方向へ高い強度や靱性を得ることである。近年、形状記憶合金繊維の形状記憶ひずみにより生じる内部応力を利用して複合材料の力学的性質を改善する試みがなされているが、強化方向が繊維の方向で決められてしまうことは、通常の繊維強化複合材料と変わりがない。本研究は、方向や大きさの制御が可能である内部応力の起源として「磁歪」に注目し、等方的な磁歪粒子強化複合材料に磁化熱処理を行うことにより、選択方向を強化した異方性複合材料を創製することを目的とした。モデル材料系には、分散粒子には超磁歪材料Tb_<0.3>Dy_<0.7>Fe_2(Tafenol-D)、マトリクスにはAl, Pb, Snを選んだ。はじめに押し出しによる粉末法により、Al/Tafenol-D, Pb/Tafenol-D複合材料を作製し緩和プロセスを観察したが、磁化熱処理中にひずみの緩和は観察されなかった。押し出しでは粒子を分散させるのに加工度が不十分であると考えられたので、繰り返し圧延接合法(ARB法)によりSn/8vol%Tafenol-D複合材料を作製した。水冷電磁石にオイルバスを設置し、最大0.8T、453Kでの磁化熱処理を施し、緩和プロセス中のひずみ変化を測定した。磁場負荷により複合材料に生じた瞬間ひずみは、予想通り、磁場方向に伸び、垂直方向に縮みの方向であり、その大きさも予測値と一致していた。瞬間ひずみの発生後、磁化熱処理中にひずみは指数関数的に減少するのが観察された。その緩和時間は、粒子径と拡散係数から予測される値とほぼ一致しており、緩和時間のアーレニウスプロットから緩和の活性化エネルギーが求められた。以上より、選択方向強化複合材料創製の要となる磁化熱処理中の緩和プロセスを直接観察することができた。
1 0 0 0 IR 柳原白蓮における歌の変容と到達
- 著者
- 中西 洋子 Yoko NAKANISHI 目白大学外国語学部韓国語学科
- 雑誌
- 目白大学人文学研究 = Mejiro journal of humanities (ISSN:13495186)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.A1-A13, 2012
1 0 0 0 OA 地方自治体における女性の政治参加の研究
調査1年目として主に、選挙区定数ごとの女性の政治参加の実態を調査し、定数の増減と女性の立候補、当選の状況を考察した。また、調査2年目として主に、女性候補者リクルートメントに関する聞き取り調査を実施した。それらの調査の結果、①定数が大きければ大きいほど、女性の当選率は上昇傾向にあること、②選挙区定数が5以上の場合、全候補者に占める女性割合はほとんど変化がないこと、③政令指定都市と東京23区ではその他の自治体と比べて全候補者に占める女性割合が高いものの、当選率はより低いこと、④都道府県議選への立候補には所属政党の有無や選挙区内の候補者選考過程におけるジェンダー・バイアスが影響することを確認した。
- 著者
- 與谷 謙吾 今泉 英徳 桐本 光 北田 耕司 田巻 弘之 荻田 太 竹倉 宏明
- 出版者
- 日本生理人類学会
- 雑誌
- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.139-146, 2007
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
Visual stimulation-reaction time and subsequent strike time in the sport of kendo were assessed using electromyographic (EMG) reaction time. Fourteen male college students (kendo athletes (n=7), non-kendo athletes (n=7)) were asked to perform a kendo strikes in response to visual stimulation from a flashing light signal. The strikes employed, the Hiki-Men (HM) and Hiki-Kote (HK), were performed using a bamboo sword, or Shinai, using both of the upper limbs as quickly as possible. The EMG signals from the right (R) and left (L) biceps brachii, the R-, and L-triceps brachii, and R-flexor carpi ulnaris muscles were recorded simultaneously together with the elbow joint angle and hitting shock signals. Total task time (TTT), pre-motor time (PMT), motor time (MT), and action time (AT) were measured for the HM and HK tasks. The photo stimulation body reaction time (BRT) was also measured. Significant strong positive correlations were observed between PMT and TTT for both HM and HK tasks (p<0.01, r=0.93-0.94). Multiple regression analysis was used to determine the contribution of each component of the model in TTT. The standardized partial regression coefficient (β) was significant (P<0.01) for MT (β=0.36-0.38), AT (β=0.49-0.56) and was highest for PMT (β=0.79-0.80). The individual time ratio for PMT, MT and AT to TTT was approximately 50%, 20% and 30%, respectively. No significant correlations were observed between BRT and TTT for the HM and HK tasks (r=-0.02, 0.16). These results suggest that PMT is the most important component contributing to the TTT, and that BRT is not correlated to the TTT in kendo strikes.
1 0 0 0 OA がん細胞の認識、検出と治療を同時に達成する新規金属含有がん治療薬の創出
- 著者
- 久松 洋介
- 出版者
- 東京理科大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2012-08-31
TRAILは、細胞膜上に発現するデスレセプター(DR)に結合し、がん細胞選択的にアポトーシスを誘導する。本研究では、Ir錯体にDR結合性ペプチドを導入した化合物を設計・合成し、がん細胞に対する細胞死誘導活性評価とイメージングを行った。その結果、Jurkat細胞を用いた染色実験で、DR5結合性ペプチドを導入したIr錯体由来の緑色発光が、DR5を発現する細胞膜上で観察された。さらに、フローサイトメーターを用いて、Jurkat細胞、Molt-4細胞、K562細胞に対するIr錯体の結合量を評価した結果、DR5発現量と相関性が示唆された。現在、細胞死誘導活性の向上を指向し、化合物の最適化を検討している。
- 著者
- 前田 啓朗 大和 知史
- 出版者
- 外国語教育メディア学会
- 雑誌
- Language Laboratory (ISSN:04587332)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.143-162, 2000-03
- 被引用文献数
- 2
This paper points out problems in previous studies concerning the statistical procedure of analysis and of the way results are presented based on the most popular questionnaire format in Language Learning Strategy researches, namely SILL (Strategy Inventory for Language Learning ver. 7.0 for ESL/EFL). A more appropriate statistical procedure to analyse the data, is proposed called "Structural Equation Modelling" based on the results of both "Exploratory Factor Analysis" and "Confirmatory Factor Analysis" with Oblique Rotation and Maximum Likelihood Method. Presentation with more detailed statistics is also promoted, which allows readers to reanalyse or meta-analyse. In order to validate the proposed method above of analysing and presenting the necessary statistics, a case study was conducted on strategy use of Japanese High School students using data obtained from the SILL. This case study explored which language learning strategy contributes most to the achievement of language learning.
1 0 0 0 OA WBTを援用した授業で成功した学習者・成功しなかった学習者
- 著者
- 前田 啓朗
- 出版者
- 全国英語教育学会
- 雑誌
- ARELE : annual review of English language education in Japan (ISSN:13448560)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.253-262, 2008-03
This paper reports the practice of English language teaching for the first year university students in a listening class, intending to cooperate classroom teaching and individualized learning. A Web-Based Training (WBT) system is involved in order to overcome some problems which will be easily observed in the classroom teaching. Since each learner has different aptitudes, a certain instruction may be effective for some but ineffective for the others. It is true that instructions should be flexible so as to balance out the students' aptitudes. However, as far as a teacher controls the lessons, there still would be some difficulties for students to commit themselves to learning. Therefore, the present courses are planned to utilize the WBT system, named Gyuto-e, for the purpose of involving students into self-learning. Three kinds of questionnaires, which investigate learner beliefs, learning motivations, and vocabulary learning strategies, are conducted in the beginning and the end of the course. A hierarchical cluster analysis reveals the fact that the TOEIC test scores show there seem to be the positive tendencies compared with the students in other classes as well as that there are successful and unsuccessful learners who seem to show some particular tendencies of learner factors.
1 0 0 0 OA ジュディット・ゴーチエの日本関連作品研究―全体像と小説『簒奪者』の生成過程の解明
- 著者
- 吉川 順子
- 出版者
- 京都工芸繊維大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2014-08-29
ジュディット・ゴーチエは19世紀後半から20世紀初頭に文学作品を通してフランスに日本文化を伝えた作家である。本研究はその日本関連作品の全体像を構築し、第一作小説『簒奪者』の生成過程の解明を進めた。その結果、日本に関連する行事に触発された執筆、日本の神話や文学への関心、同時代的な問題の投影、身近な資料の駆使といった特徴を見出すことができた。これにより、各作品の源泉調査および時代背景との関連性の考察を行っていくための基盤が作られた。
上記研究課題のもとに、1992年から94年にかけて、関西国際空港の建設と開港をめぐる大阪地域の動向調査を中心として、東京都中野区、墨田区および秋田県稲川町における住民意識調査、ならびにパイロット・スタディーとして日本の「周縁」沖縄・離島地域の調査研究を行った。それらを、大阪地域の調査結果を中心として、報告する。大阪調査の全体をつうじて明らかになったのは、首都圏の場合とは対照的に意識的に民間主導で進められてきた関西地域浮揚策の、政治的文化的に個性豊かな積極面と技術的経済的に経営困難な消極面とのコントラストである。これは、関西のめざす「双眼型国土形成」が東京一極集中の流れに抗して行われねばならぬ以上、かなりの程度まで不可避の矛盾であるが、われわれが調査したかぎり、この矛盾を根本的に解決する展望は経営者団体や自治体あるいはそれらの協議機関にも現れていない。そのため関西地域の自己浮揚策は、しばしば「イベント型の連続」などといわれるような、一回生起的で不安定な側面をもたざるをえなくなっている。今年1月になって阪神地域が大震災に見舞われたが、この事件が関西地域の長期的浮揚策にいかなる影響を及ぼしていくか、なお今後が注視されなければならないであろう。日本全体の社会構造と社会意識については、世界経済の情報化と円高のなか構造改善を要求されている企業システムと、高齢化と少子化による社会問題をかかえる家族・生活体とを基礎に、やみくもに「国際化」しようとする文化装置のかたわら、「国際協力」などについて確固とした道が見いだせず、ますます混迷の度を深めていく政府システムの姿が鮮明になってきた。これについては、これからなお検討を加え、研究成果を刊行する予定である。
- 著者
- 峰岸 純夫
- 出版者
- 公益財団法人史学会
- 雑誌
- 史學雜誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.2, pp.250-251, 1988-02-20
- 著者
- HIROSHI WADA
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- Orient (ISSN:04733851)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.53-69, 1978 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 42
1 0 0 0 OA ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΘΕΙΟΝ ΑΠγΡΟΝ BEI MALALAS
- 著者
- HIROSHI WADA
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- Orient (ISSN:04733851)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.25-34, 1975 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 'ετι μαλλον εζ την τιμωριαν επηρτο
- 著者
- Hiroshi WADA
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- Orient (ISSN:04733851)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.81-95, 1989 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 35
1 0 0 0 OA KAISER LEON III ALS OZIAS, KÖNIG DER JUDÄER?
- 著者
- HIROSHI WADA
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- Orient (ISSN:04733851)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.122-131, 1985 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 25
1 0 0 0 OA Conservative Management in a Young Woman Affected by Isolated Left Subclavian Artery Dissection
- 著者
- Vincenzo Catanese Matteo Alberto Pegorer Daniele Bissacco Sara Di Gregorio Raffaello Dallatana Piergiorgio Settembrini
- 出版者
- Annals of Vascular Diseases 編集委員会
- 雑誌
- Annals of Vascular Diseases (ISSN:1881641X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.347-349, 2014 (Released:2014-09-25)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 5
Subclavian Artery Dissection (SAD) is a rare condition, generally due to arterial catheterization, blunt trauma or connective tissue disease. Spontaneous or minimally traumatic cases have also been reported. Clinical manifestations are usually chest and/or back pain, pulse loss and paresthesia, whereas nausea, dizziness and vomiting are present in case of involvement of the vertebral artery. We report an unusual case of a young woman presenting isolated left SAD after traffic accident, minimally symptomatic, and treated with medical therapy alone. A conservative management and a closed follow-up appear to be a safe approach in patients affected by uncomplicated SAD without other comorbidities.
テクネチウムおよびレニウム放射性同位体標識医薬品の合成を念頭において,テクネチウムおよびレニウム錯体の配位子置換反応を平衡論的および速度論的に検討した。テクネチウム錯体を用いて研究する際に問題となるテクネチウムの定量を,過テクネチウム酸イオンの還元・配位子置換反応による錯体合成の過程を必要としない過テクネチウム酸イオンをトリス(1,10-フェナントロリン)鉄(II)イオンとのイオン対抽出によってニトロベンゼンに抽出して,そのまま分光光度定量する簡便な方法を確立した。テクネチウム錯体で最近注目されているテクネチウム-ニトリド錯体についで,テトラクロロアルソニウム(TPA)イオンを用いての溶媒抽出法で検討した。テトラクロロニトリドテクネチウム(VI)酸イオンの加水分解反応機構を解明し,加水分解化学種の生成定数を求めた。Tc≡N結合のトランス位の置換活性度について,3,5-ジクロロフェノール(DCP)を用いて検討したが,有機相についてはニトリド基の著しいトランス効果は認められなかった。またDCPはTPAとのイオン対形成の為に,その協同効果も認められず,むしろニトリド錯体の抽出を阻害することがわかった。ビス(アセチルアセトナト)ニトリドテクネチウム(V)の塩基加水分解反応をアセトニトリル溶液中で速度論的に検討し,錯体へのアセトニトリルの置換に伴う水酸化物イオンの攻撃によって,アセチルアセトン錯体は分解するという機構を確立し,それぞれの速度定数を求めることができた。テクネチウム(III)錯体合成の出発物質として注目されているヘキサキス(チオウレア)テクネチウム(III)イオンの過テクネチウム酸イオンからの生成反応機構を,ジメチルチオ尿素,ジエチルチオ尿素など一連の化合物を用いて速度論的に比較検討した。さらにヘキサキス(チオウレア)テクネチウム(III)イオンとジエチレントリアミン五酢酸(DTPA)との反応を速度論的に検討し,テクネチウム(III)-DTPA錯体の生成機構を確立した。ヘキサキス(チオウレア)レニウム(III)錯体の加水分解反応機構を,分光光度法により検討し,テクネチウム(III)錯体のそれと比較した。この結果からヘキサキス(チオウレア)レニウム(III)錯体のレニウム(III)錯体合成の出発物質としての可能性に関して考察した。これらの結果を基にテクネチウムに関する置換反応について,レビューし,「第1回テクネチウムに関する日ロセミナー」において発表した。
1 0 0 0 魂の歌 : 西松文一の地唄
- 出版者
- Teichiku
- 巻号頁・発行日
- 1993