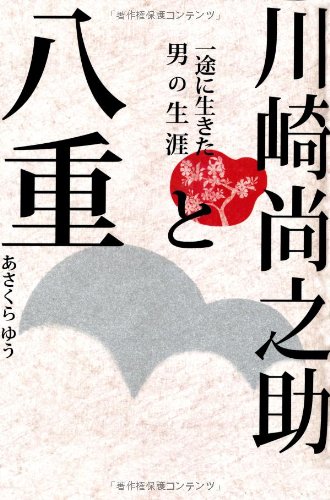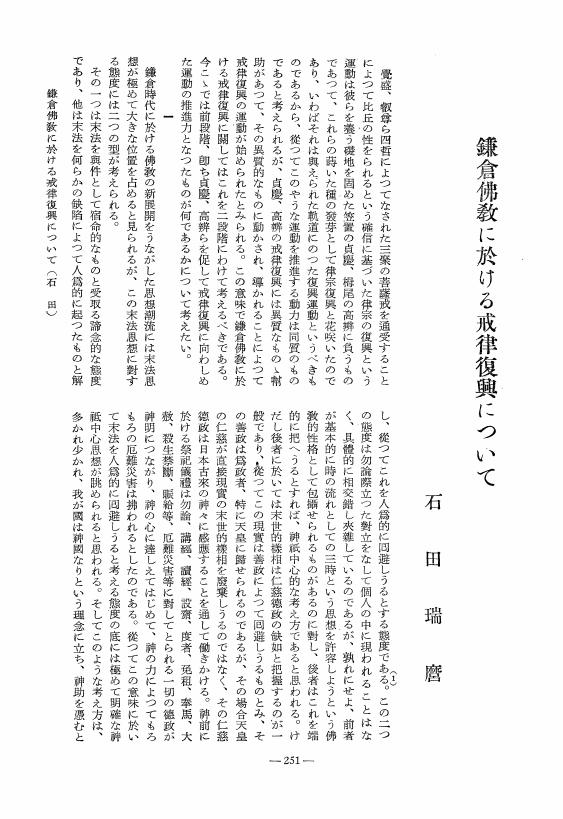1 0 0 0 OA パゾリーニ『カザルサ詩集』の詩語
- 著者
- 土肥 秀行
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.208-231, 2000-10-20
La prima raccolta poetica di Pasolini del '42, poesie a Casarsa, e significativa non solo eome evento bibliografico, ma anche per il fatto che con questa egli abbia esordito in veste di poeta dialettale. Pasolini stesso spiego il morivo della scelta del friulano riferendosi a un certo realismo e al rapporto viscerale con la madre. Ma il suo realismo, fortemente legato all'estetica bipolare fra il sacro e il selvaggio, non e quello ordinario che riguarda l'oggetto in se, la cultura popolaresca, la lingua compresa, visto che negli anni '50 applico la stessa retorica estetizzante all'amore verso i sottoproletari delle borgate romane. In merito al rapporto con la madre, va notato che la maternita non e assoluta in Pasolini, ma complementare alla paternita. Per questo la motivazione dell'uso del dialetto non si esaurisce solo con l'accostamento del dialetto friulano alla figura materna. Per di piu, essendo una insegnante colta, la madre non parlo in realta un idioma contadino come il friulano di Casarsa. Percio, a prescindere da questi due punti, soffermiamo l'attenzione sulla questione della lingua "non sua" (Pasolini nacque a Bologna, e visse prevalentemente al di fuori del Friuli), rendendoci conto che la scelta di un dialetto non "a priori" per scrivere poesia e un caso raro nella storia della letteratura. In questa tesi il motivo della scelta linguistica viene esaminato in base alla coscienza della lingua poetica. Da un saggio linguistico del '65 in cui il poeta racconto che lo spunto per scrivere la prima poesia in dialetto fu la parola "rosada", possiamo cogliere che la "scoperta" del friulano e decretata essenzialmente dal suo essere una lingua "mai scritta". La sonorita del dialetto rievoca a Pasolini l a"vecchia salute di volgare" e la "verginita" che la "coscienza letteraria" facilmente corrompe nal corso della tradizione intesa come percorso di degradazione. Percio Pasolini risale all'origine della lingua poetica per ottenere una lingua non ancora consunta, chiamata dal poeta una lingua "romanza". Dunque il dialetto friulano e una lingua "romanza", allo stesso tempo, se viene scritto, una lingua riservata alla poesia, esclusiva di Pasolini poeta, cioe il suo idioletto. A questo punto Pascoli, poeta della lingua morta e Ungaretti, poeta della lingua pura influiscono su Pasolini che aveva una idea concisa, potenzialmente confusa, sulla poesia novecentesca: "era addirittura possibile inventare un intero sistema lingiustico, una lingua privaga (secondo l'esempio di Mallarme), trovandola magari fisicamente gia pronta <…> nel dialetto" (1957). Pero Pasolini stesso possedeva la "coscienza poetica" e ne era consapevole, come si evince dalla dichiarazione nella nota finale della prima raccolta sulle "violenze" linguistiche, cioe l'uso del dialetto da egli modificato per "lenocinii arcaicizzanti o preziosismi linguistici". Una delle "violanze" e l'influsso dell'idioma del dizionario friulano-italiano, il Nuovo Pirona. Si nota che questa intrusione era intenzionale, confrontando le varie stesure: Pasolini conosceva ele alcune forme corrette del friulano di Casarsa e solo all'ultimo momento ha sostituito alcune di esse con l'idioma della koine friulana estrapolata dal vocabolario. Cost quando ha affrontato un dialetto "mai scritto" per scrivere, e ricorso alla variante standard letteraria. Per il poeta la letterarieta e spesso connotata dall'arcaicita delle parole: sceglieva appositamente le parole classicheggianti, tronvandole sempre nel vocabolario, che certamente non sarebbero mai state sulle bocche dei contadini. In altri casi per la versione italiana messa in calce sceglieva le parole non deducibili dal testo friulano. Questa scelta distacca le due versioni l'una dall'altra, e rende spesso quella italiana meno implicata e proporzionalmente quella friulana piu ermetica. La distanza fra le due versioni provoca l'indipendenza di entrambe, dovuta da un concetto particolare del poita sulla traduzione. Pasolini, spesso partendo dalla stesura italiana, compose le due versioni passando piu volte da una ligua all'altra cosi che non ha senso distinguere quale sia la versione originale o quale quella tradotta. Attraverso questo meccanismo di composizione si sono generate le parole "intraducibili", riportate nella nota finale. Di fatto queste parole sono dotate di una forte impronta pascoliana, quella fonosimbolia, e non sono destinate alla significazione contenutistica, ma piuttosto alla significazione sonora. L'importanza attribuita alla dimensione sonora condusse addirittura il poeta ad inventare alcuni termini come "tintinula" (trillare) e "svampidit" (che svanisce) che seguissero il vocabolo fonosimbolico tipicamente pascoliano e si accordassero con altre parole sia foneticamente sia metricamente. L'"intraducibilita" della poesia dialettale sulla quale Pasolini insistette sempre deriva anche dall'atribubo intrinseco delle parole "intraducibili" come "imbarlumide" (luminosa, dolcemente stralunata), "rampit" (spoglio)) e "tremul" (tremulo) che evocano immagini evanescenti o fievoli ossi adelle immagini che quasi negano le proprie presenze concrete. Descritto in questo modo il luogo deve le poesie sono situate, Casara, appare come "non-luogo". L' "intraducibilita" fu prevista dal poeta, dato che il dialetto avrebbe dovuto essere una lingua pura, assoluta. In conseguenza dell' "intraducibilita" nel '54 Pasolini ritenne che le versioni italiane "fanno parte insieme, e qualche volta parte integrante, del testo poetico", insomma hanno valore in se. Del resto quando indichicmo la lingua poetica di Poesie a Casarsa, dovremmo intendere una unica entita composta dalle due lingue utilizzate da Pasolini: l'una e un friulano artificiale e l'altra e l'italiano. Cosi Pasolini si situo nel punto neutro fra diverse lingue, appunto siu "confini" da cui il giovane poeta fu ossessionato.
1 0 0 0 OA 災害仮設住宅のための自助建設可能な木質系ボックスユニット構造の開発
- 著者
- 小澤 雄樹
- 出版者
- 芝浦工業大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2011
本研究は、災害発生時に仮設住宅として利用可能な木質系ユニット構造の開発を目的としている。ユニットタイプとしては、ボックス型、ラーメン型の2種類を想定し、これらを組み合わせて用いることで必要な容積を確保する計画である。建設方法を極力単純化し、入手しやすい材料を用いることで被災者自身により自助建設可能なシステムとすることを目指している。構造的検討が特に重要となるラーメン型を中心に、(1)システムの提案、(2)実大ユニット建設による施工性確認実験、(3)柱梁接合部の耐力実験、(4)数値解析等を通して検討を進め、その実現可能性を確認することが出来た。
- 著者
- 菅原 教修
- 出版者
- 特定非営利活動法人日本歯周病学会
- 雑誌
- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.555-574, 1980-12-28
歯周疾患の際に生ずる臨床所見と組織所見および臨床所見相互間の関連性を把握するために,歯周疾患評価指標による基準で,歯周疾患患者の前歯部歯肉について検索を試みた。その結果,臨床的炎症所見と組織学的炎症所見の一致率は辺縁部より歯間部で高く,約2/3であった。また,両者の間には明らかな相関関係が認められた。歯周ポケットは男性の歯間部で組織学的炎症所見と相関がみられたが,その他では明らかな相関関係はみられず,むしろ臨床的炎症所見との間に高い相関関係が認められた。歯槽骨の吸収は組織学的炎症所見とも,また臨床的炎症所見ともとくに明らかな相関関係は認められなかった。歯周ポケットと歯槽骨の吸収両者は男女間に差があり,両者とも男性で高度であるとともに,年代間にも差があり,20代と30代の間に有意の差が認められた。
1 0 0 0 OA 地すべり変位量に基づく地震力の定量化と新たな指標の提言
- 著者
- 岡本 隆 浅野 志穂 岡田 康彦
- 出版者
- 独立行政法人森林総合研究所
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2010
本研究は、地震動の中でどのような振動成分が地すべりに強い影響を与えるのかを明らかに することを目的とする。新潟県の地すべり地で観測された中越、中越沖、長野県北部の各地震 動の振動成分とその際に生じた地すべり変位量の関係を解析したところ、従来地震力指標とし て用いられてきた最大加速度はあまり調和的でなく、むしろ地形的に解放された方位における 最大速度を用いた方が地すべり変位量と調和的であることが分かった。
1 0 0 0 OA ビジュアルプログラミング言語におけるプログラム清書システムの構築
- 著者
- 稲垣 拓海
- 巻号頁・発行日
- 2010-02-01
1 0 0 0 OA ラッセル・シルバー症候群におけるエピジェネティック機構の解明
- 著者
- 白井 瑞子 内藤 直子 益岡 享代 真鍋 由紀子 山本 文子
- 出版者
- 日本母性衛生学会
- 雑誌
- 母性衛生 (ISSN:03881512)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.87-97, 2004-04
- 被引用文献数
- 3
本研究では,高校生(男女)が月経をどのようにイメージしているかを,初めての月経教育時に抱いた月経観,印象に残っているトピック,および女子の月経痛との関連から調査した。提示した月経イメージ10項について因子分析を行い,困難因子(つらい,いやなもの,腹立たしい),成熟因子(女性の特質,大切・必要なもの),嫌悪因子(暗い,病気のような,汚らわしい,怖い)が抽出された。3因子の平均は,困難因子3.52±0.99,成熟因子4.01±0.94,嫌悪因子2.19±0.84であり,困難因子点は,女子の中では月経痛レベル4以上で高かった。初めての月経教育で,男子は月経を肯定的・中立的に,女子は否定的・両価的にとらえる者が多かった。また,初めての月経教育が印象深いと,月経を肯定的に受け止め,成熟因子点が高く,困難因子点,嫌悪因子点が低かった。この結果をふまえて,高校生に対して月経を健康のバロメーターとして,および性行動か活発化している現状に役立つ教育を行う必要があることを提言した。
1 0 0 0 OA 日本の船大工と木造船の現在-伝統技術の今を記録する
今、日本の木造船が危ない。伝統技術をもった船大工のほとんどが70代後半から80代となり、後継者が育たないまま、腕のある作り手が急激にいなくなっている。日本は世界のなかでも特色ある木造船文化を継承しながら、今、その文化が消えようとしているのである。本研究プロジェクトでは、この終焉期にある日本の船大工の暮らしの民俗と木造船の技術の現実に正面から向き合ってきた。現役船大工による木造船の建造工程や、船造りにかかわる諸職の暮らしを詳細に調査記録し、日本の木造船の技と文化を保存継承するための諸条件について実地に考察した。
1 0 0 0 OA 右室流出路再建に用いるePTFE弁の弁開閉メカニズムの基礎研究
本研究の目的は,小児右室流出路再建に良好な京都府立大学山岸正明教授らの膨らみを有するePTFE弁内の弁葉形状,bulging sinus形状が,弁開閉に与える影響を検証することにある.初年度は模擬大動脈を用い,弁開口面積の変化に対する膨らみの影響と,最適寸法について検討し,流れ場解析により,膨らみ内の渦の重要性,弁葉形状変化の影響を検討した.研究2年目は,膨らみ具合に変化を加えた実験を実施し,実験範囲の拡大を図った.最終年度は,実寸法のePTFE弁モデルを使用し,更に精度の高い実験を実施し,大動脈モデルでの結果に類似した結果が得られ,膨らみ内の渦の動きにかなりの違いがあることを明らかにした.
1 0 0 0 OA 2.林内におけるカシノナガキクイムシの被害発生状況と被害木の空間分布様式
- 著者
- 曽根 晃一 牛島 豪 森 健 井手 正道 馬田 英隆
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 鹿児島大学農学部演習林報告 (ISSN:03899454)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.11-22, 1995-10-20
- 被引用文献数
- 5
- 著者
- 伊香賀 俊治 村上 周三 加藤 信介 白石 靖幸
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.535, pp.53-58, 2000
- 被引用文献数
- 23 14
Building sector has a heavy role to create sustainable society, because CO_2 emissions associated with construction and operation of buildings are estimated to be 1/3 of the whole CO_2 emissions in Japan. These CO_2 emissions were estimated from 1970 through 2050 and the following results were obtained. (1) CO_2 emission between 2008 and 2012 will increase by 15% than 1990 level. (2) CO_2 emission can be reduced by 6% between 2008 and 2012, and reduced by 40% in 2050, if the 30% energy saving, long life and environment-conscious materials are adopted to new buildings.
1 0 0 0 川崎尚之助と八重 : 一途に生きた男の生涯
1 0 0 0 IR 新島八重のブラック・ホール : 前夫・川崎尚之助のその後
- 著者
- 吉海 直人
- 出版者
- 同志社大学
- 雑誌
- 新島研究 (ISSN:02875020)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, pp.1-8, 2012-02
資料紹介(Historical Document)表紙の英文タイトルに誤りあり (誤)Llife → (正)lifeページは巻末一-八
1 0 0 0 七世紀の東アジアにおける塑像について(当麻寺の仏像をとおして)
今年度は、昨年度の当麻寺本尊の様式研究と当麻寺の伽藍配置の研究に引継ぎ、当麻寺における信仰の問題について検討することにした。まず当麻寺本尊の尊名の問題について検討した。現在当麻寺本尊の尊名は弥勒仏として伝わっているが、創建当初から弥勒であると伝える同時代の史料はなく、当麻寺本尊が創建当初から弥勒如来として制作安置されていたかははなはだ疑問である。当麻寺は古代日本において死者が往く場所として認識されていた二上山の東麓に立っており、当麻寺を建立した当麻氏は、その二上山の入口で喪葬関連の任務を担っていた氏族であったこと、そして、『日本書紀』や『続日本紀』などには当麻氏が天皇の死後に誄をのべるなど、喪葬関連の記事に多く登場していることに注目した。さらに七世紀後半の日本では、弥勒下生信仰に基づいた弥勒如来の造像例がないことを考慮すると、当麻寺本尊の尊名は弥勒ではなく阿弥陀とみるのがより自然な解釈である。つぎに当麻寺が浄土信仰の代表寺院として発展した背景について考察した。治承四年(1180)に平家勢の攻撃によって被害を受けた当麻寺では、復興するための手段として、聖徳太子信仰を利用しようとしたが、太子関連寺院として発展する要素がなかったため、新たに曼荼羅堂の当麻曼荼羅の存在に注目しなおし、太子信仰から当麻曼荼羅信仰に方向を転換した。その後、当麻曼荼羅は浄土宗西山派によって日本全国へ転写されるようになり、その結果当麻寺は当麻曼荼羅と中将姫の信仰の中心地として日本全国へ知られるようになった。鎌倉時代以降、当麻寺の復興事業が順調に進んでいることを考えると、当麻曼荼羅と中将姫を中心とする浄土信仰は成功したといえよう。報告者は、未だ解明されていない当麻寺史の全貌について美術史、仏教史、考古学の方向から新たな解釈を試みた。今後の当麻寺研究において新しい角度からより活発な議論が出ることを期待する。
1 0 0 0 OA 土壌型および樹種の相違による窒素の無機化と硝化活性
- 著者
- 沓名 重明 本庄 真 鈴木 道代 仁王 以智夫
- 出版者
- 一般社団法人日本森林学会
- 雑誌
- 日本林學會誌 (ISSN:0021485X)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.80-85, 1988-02-01
- 被引用文献数
- 13
1 0 0 0 OA 抗腫瘍性サポニン類の完全化学合成と生物活性評価
抗腫瘍性サポニン・シラシロシド類の全合成に向け、CDE環部の立体選択的な合成を行った。分子内O-H挿入反応と続くオレフィン化により生じたジヒドロフランカルボン酸エステルを用いてIreland-Claisen転位を行うと、望みの異性体が立体選択的に得られることを見出した。生成物に対し、分子内1,3-双極付加環化反応によるD環構築、シクロプロパン化を経る核間位へのメチル基導入を行い、目的フラグメントの合成を達成した。また、転位の際の立体化学制御に隣接位の置換様式が重要な役割を果たしていることを明らかにし、酸化型テルペノイド合成に利用可能なキラル合成素子2種を立体選択的に得る方法を確立した。
1 0 0 0 OA トルコギキョウのロゼット化と内生ジベレリンとの関係
- 著者
- 久松 完 腰岡 政二 大山 直美 Mander Lewis N.
- 出版者
- 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.527-533, 1999-05-15
- 被引用文献数
- 5 7
トルコギキョウのロゼット化と内生ジベレリンとのかかわりを明らかにするために, ロゼット化した実生に対する数種ジベレリンおよび前駆物質の影響ならびにロゼット化および非ロゼット化実生の内生ジベレリン含量を調査した.また, それらの開花に及ぼすジベレリン生合成阻害剤とGA_3の影響を調査した.その結果, ロゼット化した実生では初期13位水酸化経路上のGA_<53>より上流で生合成がブロックされている可能性が示された.また, ロゼット化および非ロゼット化実生にかかわらず, 葉と茎においてGA_<19>からGA_<20>に至る20位の酸化活性に違いがあることが示唆された.葉の伸展, 茎の伸長および花芽発達は活性型GAにより制御されているが, 花芽分化は制御されていない可能性が示された.
1 0 0 0 OA 戦間期における海軍技術研究所の活動
- 著者
- 沢井 実 サワイ ミノル Sawai Minoru
- 出版者
- 大阪大学経済学会
- 雑誌
- 大阪大学経済学 (ISSN:4734548)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.1-16, 2008-06
1 0 0 0 OA 鎌倉佛教に於ける戒律復興について
- 著者
- 石田 瑞麿
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.251-253, 1953-09-30 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 イスラム解放党のカリフ革命論
- 著者
- 中田 考
- 出版者
- 日本イスラム協会
- 雑誌
- イスラム世界 (ISSN:03869482)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.38-58, 1997-07