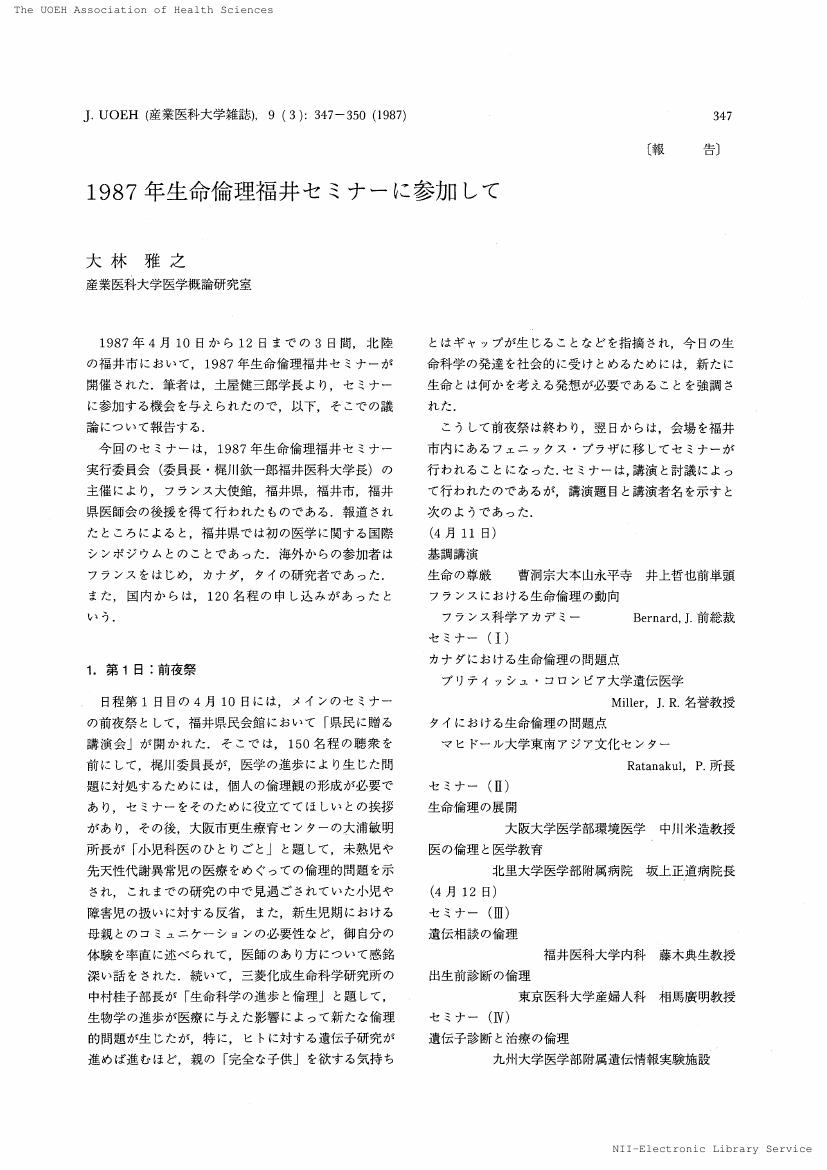2 0 0 0 OA MCH受容体の同定と最近の知見
- 著者
- 斎藤 祐見子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.1, pp.34-38, 2007 (Released:2007-07-13)
- 参考文献数
- 35
Gタンパク質キメラを利用したアッセイ法により,オーファン受容体SLC-1に対する内在性リガンドをラット脳から精製し,メラニン凝集ホルモン(MCH)であることを同定した.MCHは魚類の体色変化を引き起こす一方,哺乳類では視床下部外側野に著しく局在し,摂食行動に深く関与することが知られていた.このように注目される鍵分子でありながらもMCH受容体の正体は謎であった.本受容体の発見により,様々な遺伝子改変動物が作製され,また,選択的アンタゴニスト開発および行動薬理学的解析が大きく進展した.この結果,MCH系は摂食/エネルギー代謝の他に,うつ不安行動にも関与することが強く示唆されている.MCH受容体は創薬創出の有望な標的分子となりつつある.
- 著者
- Nanako YAMASHITA-KAWANISHI Chia Yu CHANG James K CHAMBERS Kazuyuki UCHIDA Katsuaki SUGIURA Iwao KUKIMOTO Hui Wen CHANG Takeshi HAGA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-0153, (Released:2021-06-15)
- 被引用文献数
- 11
Felis catus papillomavirus (FcaPV), especially type 2 (FcaPV2) is considered as one of the causative agents in squamous cell carcinoma (SCC) in cats. However, our previous study detected FcaPV3 and FcaPV4, but not FcaPV2 in feline SCCs collected in Japan, suggesting that the prevalence of FcaPV2 in SCC may vary depending on geographic locations. To evaluate this hypothesis, two conventional PCR reactions targeting E1 and E7 genes were performed to detect FcaPV2 in feline SCC samples collected in Taiwan and Japan. While 46.9% (23/49) of feline SCC cases from Taiwan were PCR positive for FcaPV2, only 8.6% (3/35) cases from Japan were positive. Our result suggests that the prevalence of FcaPV2 in feline SCCs may depend on the region.
2 0 0 0 OA 中国における「対日感情」に関する考察 各種世論調査結果の複合的分析
- 著者
- 小林 良樹
- 出版者
- 一般財団法人 アジア政経学会
- 雑誌
- アジア研究 (ISSN:00449237)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.87-108, 2008-10-31 (Released:2014-09-15)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
This paper examines the hypothesis that one of the possible reasons for the recent negative perception of Japan in China is the relatively low volume of mutual human exchange between the two countries.Based on an analysis of various opinion poll data, the characteristics of Chinese perceptions of Japan can be summarized as follows:(1) Since the mid-1990s, the Chinese perception of Japan has been consistently negative.(2) Such a negative perception of Japan is stronger in China than in other East Asian countries.(3) In terms of the medium- and long-term trend since the mid-1990s, Chinese perception of Japan has continued to worsen, which is a unique phenomenon unseen in other East Asian countries including South Korea.(4) Those Chinese who have experienced direct contact with the Japanese in general have a more moderate perception toward Japan than those Chinese who have not had such experience.Apart from the historical fact that Japan and China have fought against each other, such a uniquely negative perception toward Japan in China can be attributed to the following reasons:(1) The strengthening of patriotic education campaigns in China since the mid-1990s.(2) The upsurge in anti-China perceptions in Japan since the 1990s (which are reflected back to China).(3) Misperceptions and misunderstandings at an individual level in China, mainly due to the lack of objective knowledge about Japan as well as cultural differences.One of the possible reasons for the misperception and misunderstanding at the individual level in China could be the relatively low volume of human exchange between China and Japan, which is still relatively low compared with the volume of exchanges between Japan and other major Asian countries.For instance, Japan’s “visitor-population ratio” (ratio of the number of visitors to Japan compared to the nation’s population) in 2006 is as follows: China, 0.04% (one visitor per 2,500people); South Korea, 4.14% (one visitor per 24); Taiwan, 5.61% (one visitor per 18); Hong Kong, 5.04% (one visitor per 20); Singapore, 3.12% (one visitor per 32).Data analysis indicates that the current negative perception of Japan in China is unique compared with similar perceptions in other East Asian countries.There are several reasons for such a situation in China, and the current situation may not be due to only one reason.Nevertheless, the enhancement of human exchanges between the two countries could be useful to prevent any increase in mutual misunderstanding as well as for managing any outbursts of negative feelings.
2 0 0 0 OA 機械翻訳モデルの頑健性評価に向けた言語現象毎データセットの構築と分析
- 著者
- 藤井 諒 三田 雅人 阿部 香央莉 塙 一晃 森下 睦 鈴木 潤 乾 健太郎
- 出版者
- 一般社団法人 言語処理学会
- 雑誌
- 自然言語処理 (ISSN:13407619)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.450-478, 2021 (Released:2021-06-15)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1
ニューラル機械翻訳 (NMT) の登場により,ニュース記事など文体の整った入力に対する翻訳の品質は著しく向上してきた.しかし,ソーシャル・ネットワーキング・サービス (SNS) に代表されるユーザ生成コンテンツ (UGC) を対象とした NMT の翻訳には依然として多くの課題が残されている.異文化・多言語交流の促進に向けた機械翻訳システムの活用には,そうした特異な入力を正確に扱うことのできる翻訳モデルの構築が不可欠である.近年では,UGC における翻訳品質の向上に向けたコンペティションが開催されるなどその重要性は広く認知されている.一方で,UGC に起因するどのような要因が機械翻訳システムの出力に悪影響を及ぼすのかは明らかでなく,偏在するユーザコンテンツの翻訳に向けた確かな方向性は依然として定まっていない.そこで本研究では,言語現象に着目した日英機械翻訳システムの頑健性測定データセット PheMT を提案する.特定の言語現象を含む文に特化したデータセットにより,当該表現の翻訳正解率,および正規化に基づく翻訳品質の差分を用いた精緻なエラー分析を可能にする.構築したデータセットを用いた評価により,広く商用に利用される機械翻訳システムを含む,最先端の NMT モデルにおいても十分に扱えない,対処すべき言語現象の存在を明らかにする.
2 0 0 0 OA 1987年生命倫理福井セミナーに参加して
- 著者
- 大林 雅之
- 出版者
- 学校法人 産業医科大学
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.347-350, 1987-09-01 (Released:2017-04-11)
2 0 0 0 OA デジタル一眼レフ用の新撮像系
- 著者
- 川合 澄夫
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.Suppliment1, pp.8-9, 2004-05-27 (Released:2011-08-11)
OLYMPUS has developed a new digital SLR camera E-1 with high image quality and mobility. New imaging system is applied to E-1. This new imaging format has half the diagonal length of 35-mm film format (36mm×24mm). The focal length is half that of a 35-mm film camera lens to achieve the same angle of view.
2 0 0 0 OA キャリア・パス分析 パス解析に基づく組織内キャリア発達の規定要因分析
- 著者
- 若林 満 斎藤 和志
- 出版者
- 経営行動科学学会
- 雑誌
- 経営行動科学 (ISSN:09145206)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.9-17, 1989-04-30 (Released:2011-01-27)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 1
For the purpose of testing the hypothesized major contribution of vertical exchange quality to management development, 1058 line managers at four different hierarchical levels were sampled from five of the leading corporations in Japan. Hierarchical regrssion and path analysis results showed that both vertical exchange quality and the present hierarchical level contributed uniquely to managers' career development activities after the contributions of company, age, tenure, education, technical specialty and intrafirm mobility were controlled. In addition, the contributions of these control variables were estimated and a summary path diagram was presented.Implications of these findings for our understanding of Japanese management development were discussed, focusing upon the two dominant management career paths in Japanese organizations: one through the traditional nenko system and the other through the interpersonal (leader-member relations) path.
2 0 0 0 OA 我が国初のポストテンション方式PC道路橋十郷橋の健全性調査報告
- 著者
- 天谷 公彦 原 幹夫 吉田 雅穂 阿部 孝弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.12, pp.1067-1074, 2014 (Released:2015-12-01)
- 参考文献数
- 5
十郷橋は,我が国初のポストテンション方式のPC道路橋で,2013年で建設から60年が経過し,現在も供用中の歴史的な橋梁である。今回,この十郷橋の詳細調査を行い,その健全性を評価した。なお,PC鋼材などの調査は,十郷橋の4カ月後に施工され,同じ材料が使用されている石徹白橋(水害により落橋)にて実施している。調査の結果,コンクリートは緻密で高い強度を有しており,劣化も進行していないことが分かった。さらに,鉄筋・PC鋼材の品質およびグラウトの充填性も確認でき,十郷橋は建設から60年が経過した現在においても健全な状態にあることが明らかになった。
2 0 0 0 OA 外皮用薬による障害
- 著者
- 本田 光芳
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.539-543, 1984-10-15 (Released:2009-07-10)
- 参考文献数
- 22
2 0 0 0 OA 都市社会学の遷移と伝統
- 著者
- 松本 康
- 出版者
- 日本都市社会学会
- 雑誌
- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.21, pp.63-79, 2003-09-06 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 26
- 著者
- 板口 典弘
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.191-193, 2021-03-31 (Released:2021-06-05)
2 0 0 0 OA 広場恐怖を伴うパニック障害患者を対象としたエクスポージャーに及ぼす患者教育の効果
- 著者
- 陳 峻文 貝谷 久宣 坂野 雄二
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.57-68, 2000-09-30 (Released:2019-04-06)
本研究では、患者がエクスポージャーを実施する際の困難点を検討した上で患者教育を行い、患者教育がエクスポージャーの実施に及ぼす影響を検討することを目的とした。予備調査によって患者がエクスポージャーを実施する際に感じる困難点を明らかにした上で、研究1では、患者教育前後の患者の自己効力感の変化を検討した。その結果、患者教育前に比べ、患者教育後には、エクスポージャーを実施できるというセルフ・エフィカシーや、自らエクスポージャーを実行する意欲が高くなることがわかった。研究2では、エクスポージャー実施に及ぼす患者教育の効果を検討した結果、患者教育あり群は患者教育なし群よりも症状をコントロールできるというセルフ・エフィカシー、エクスポージャーが実施できるというセルフ・エフィカシーが有意に高く、エクスポージャー後の状態不安とSDSの得点が低下することがわかった。最後に、エクスポージャー実施に先立つ患者教育の意義が議論された。
- 著者
- Prashant KUMAR Rakesh GAIROLA 久保田 拓志 Chandra KISHTAWAL
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.3, pp.741-763, 2021 (Released:2021-06-14)
- 参考文献数
- 69
- 被引用文献数
- 9
インド夏季モンスーン(ISM)期間中の正確な降雨量推定はインド亜大陸およびその周辺で最も重要な活動の一つである。宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、Global Satellite Mapping of Precipitation(GSMaP)降雨プロダクトとして、全球客観解析データ等を補助データとして用いて計算した衛星プロダクトであるGSMaP_MVKや全球地上雨量計データで調整したGSMaP_Gaugeを提供している。本研究では、2016~2018年のISM期間で、インド南西部の州の1つであるカルナータカ州における高密度地上雨量計ネットワークを基準として、GSMaP降雨プロダクト(バージョン7)の日降雨量を検証する。さらに、本研究の主目的として、これらの高密度地上雨量計観測を、ハイブリッド同化法を用いてGSMaP降雨量に同化することで、最終的な降雨推定を改善する。ここで、ハイブリッド同化法は二次元変分(2D-Var)法とKalmanフィルタの組合せであり、2D-Var法を用いて地上雨量計観測を統合し、Kalmanフィルタを用いて2D-Var法の背景誤差を更新する。準備としての検証結果は、GSMaP_Gauge降雨量が北部内陸カルナータカ州(NIK)と南部内陸カルナータカ州(SIK)地域で十分な精度を持ち、西ガーツ山脈の地形性豪雨領域で大きな誤差を持つことを示唆する。これらの誤差はGSMaP_MVK降雨量の地形性豪雨領域でより大きかった。ランダムに選択した地上雨量計観測を用いたハイブリッド同化結果は、独立した地上雨量計観測と比較して、GSMaP_GaugeとGSMaP_MVK降雨量の精度を改善した。これらの日雨量における改善は地形性豪雨領域でより顕著である。GSMaP_MVK降雨プロダクトは、JAXAの運用処理において地上雨量計による調整が含まれていないので、より大きな改善を示した。また本研究は、Cressman法や最適内挿法と比較して、用いられた雨量計の数のインパクトに対するハイブリット同化法の優位性を示す。
2 0 0 0 OA 加齢とDNAメチル化異常
- 著者
- 坂本 快郎 市村 隆也 水流添 周 中尾 光善
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.2, pp.137-143, 2005-03-25 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 1 1
老化はヒトを含む全ての生物に共通した生命現象であるとともに, 多くの疾患や病態の発生と関わっている. 近年, DNAメチル化とクロマチンをはじめとするエピジェネティクスの研究が進展して,細胞の老化現象とも密接に関わることが明らかになってきた. 加齢とともにDNAメチル化パターンが徐々に変化する事実からも, 癌や自己免疫疾患, 代謝病, 神経疾患等の発症機序との相関性が注目されている. DNAメチル化検査は技術的に確立されており, 癌の早期診断, 治療薬剤の選択や予後因子に適用されている. さらに, エピジェネティクスを標的とする薬剤開発 (エピジェネティック治療) が提唱されており, 疾患の予防や治療に貢献できる可能性が高まりつつある.
2 0 0 0 OA コエンザイムQ10含有健康食品における成分含量と溶解性
- 著者
- 牧野 利明 中村 峰夫 野田 敏宏 高市 和之 井関 健
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.7, pp.505-510, 2005-07-10 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 3 2
Dietary supplements are gaining wide popularity in Japan and are used by a large number of patients as self-medication. Though dietary supplements cannot be considered as drugs, patients expect pharmacological benefits from them since they usually have very little knowledge of their effects. Thus, pharmacists have the responsibility to expand their knowledge of dietary supplements so that they can give better advice to patients who are using them. However, only a limited amount of information on dietary supplements is available to pharmacists.In the present study, we evaluated the content and solubility of coenzyme Q10 (ubidecarenone, CoQ10) in dietary supplements. CoQ10 is not only used as a dietary supplement, it is also prescribed as a drug by physicians. CoQ10 preparations were ground up and various techniques were used to extract the active ingredient, among them extraction using solvents, ultrasonication and heat. We found that the prescription drug preparations containing CoQ10, both original and generic products, had exactly the same content as stated on the label and had good solubility. Though dietary supplements containing CoQ10 also had the exact content stated on their labels, they showed poor solubility. Such poor solubility would give rise to major differences in elution and bioavailability between dietary supplements and prescription drugs containing CoQ10.
2 0 0 0 OA 静岡県太田川下流低地における液状化発生地点の地形条件に関する検討
- 著者
- 林 奈津子
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.4, pp.418-427, 2010-07-01 (Released:2012-01-31)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
静岡県西部の太田川下流低地において,1944年の東南海地震の際に生じた,噴砂地点と微地形・浅層堆積物との関係を考察した.液状化現象は一般的に,砂質の堆積物で構成される地表の微地形に対応して発生するとされるが,対象地域では局所的に後背湿地に集中して発生する場合がみられた.調査地における表層堆積物について検討したところ,後背湿地を構成する粘土-シルトの細粒堆積物の下位に,砂質シルト-砂の粗粒堆積物が検出され,噴砂地点の分布と対応することが明らかになった.さらに,この粗粒堆積物は遺跡で検出された埋没旧河道の両岸に認められ,地表の自然堤防構成層と同様の層相であるという特徴をもつことから,埋没した自然堤防構成砂層である可能性が高い.また,この自然堤防構成砂層が母材となった噴砂痕が弥生後期の考古遺跡から検出されており,1944年の地震時には,地表の微地形を構成する堆積物に加えて,このような埋没自然堤防構成砂層が液状化したと考えられる.
2 0 0 0 OA 沖縄, 種子島の茶
- 著者
- 早川 史子
- 出版者
- THE JAPAN ASSOCIATION FOR THE INTEGRATED STUDY OF DIETARY HABITS
- 雑誌
- 食生活総合研究会誌 (ISSN:0917303X)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.39-44, 1993-09-30 (Released:2011-01-31)
- 参考文献数
- 20
2 0 0 0 OA 人類は宇宙人へ進化をはじめた 越えられるか三つの壁
- 著者
- 菊山 紀彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.356-360, 1998-05-20 (Released:2011-08-11)
2 0 0 0 OA 食品摂取と「食餌誘発性体熱産生」 その“シグナル”とメカニズム
- 著者
- 河田 照雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.11, pp.1462-1465, 1987-11-15 (Released:2009-02-18)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 4 5
2 0 0 0 OA ヴィゴツキーの障害児発達論について
- 著者
- 明神 もと子
- 出版者
- 帯広大谷短期大学
- 雑誌
- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.41-46, 2011-03-31 (Released:2017-06-16)
- 参考文献数
- 4
心理学者ヴィゴツキーは障害児教育においても、先駆的な理論を展開しており、発達と発達診断、障害の理解、教育方法など、現代においても、大きい示唆を与えている。障害特性やTEACCHプログラム、行動分析など行動主義に根ざした指導が広く行われている現代にあって、ヴィゴツキーの理論は新しく、挑戦的、批判的である。 障害児と健常児の発達には共通性を認めたうえで、障害に由来する発達の独自性があると考えている。障害については、1次的障害(脳の障害など)と2次的障害(知的障害など)を区別した。教育の効果があがるのは、生物的なものではなく、文化的なものとし、感覚訓練などでなく、高次精神機能に働きかけることが重要であるとした。指導には集団が重要であるとした。個別指導が強調される現在の現場実践の再検討を迫るものであろう。