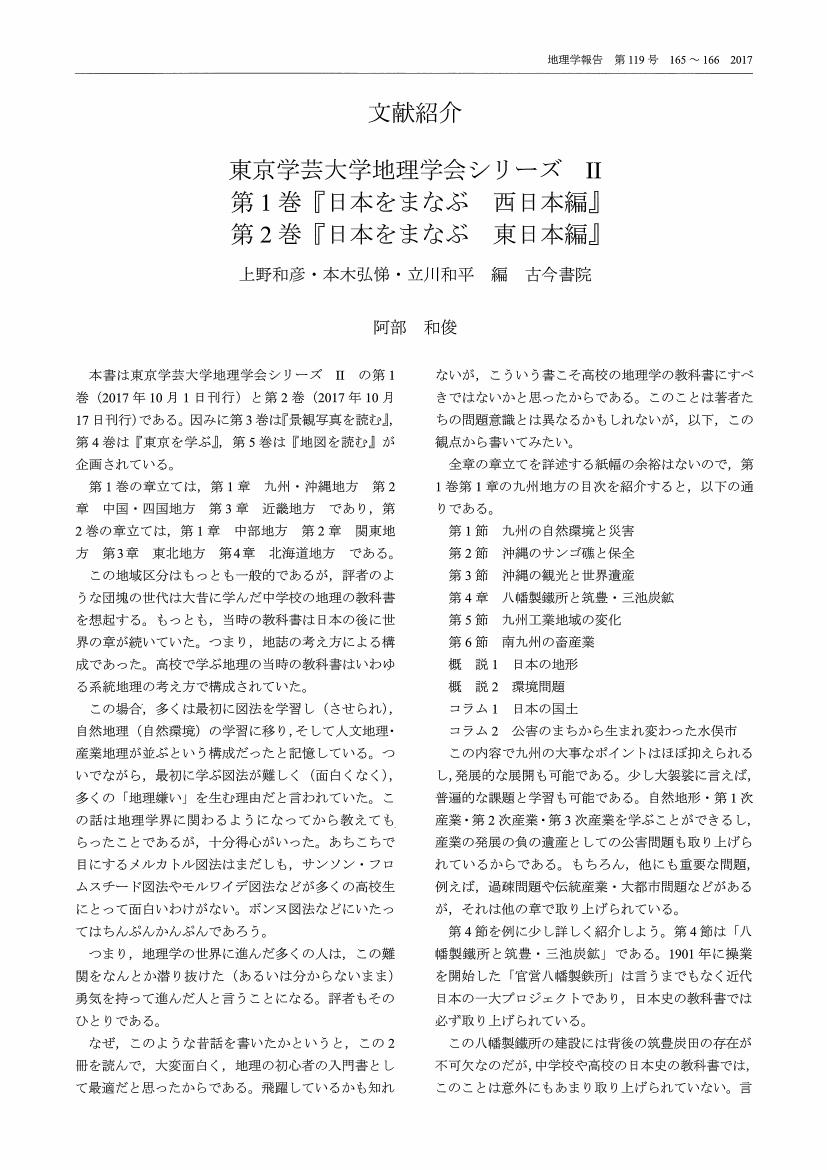- 著者
- 阿部 和俊
- 出版者
- 愛知教育大学地理学会
- 雑誌
- 地理学報告 (ISSN:05293642)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, pp.165-166, 2017 (Released:2019-10-29)
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1947年06月24日, 1947-06-24
4 0 0 0 OA カルチュラル・スタディーズが問いかけるもの
- 著者
- 伊藤 公雄
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.75-88, 2000-06-30 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 25
「カルチュラル・スタディーズとは何か」。この問いかけに対して、簡略に語ることはむずかしい。というのも、この研究スタイルはひとつの声で語ることがないし、またひとつの声で語ることができないからだ。また、ここには、二〇世紀後半の多様な知的潮流や政治的な流れが合流しているからでもある。本稿は、こうしたカルチュラル・スタディーズの輪郭を、その来歴を溯って描く試みである。カルチュラル・スタディーズの背後には、1960年代のニューレフトの影響が明らかに存在している。と同時に、イギリスにおける文化主義との結び付きもまた明らかなことだ。さらには、構造主義やポスト構造主義といった現代の思想潮流の積極的吸収も、この研究スタイルの特徴だろう。また、カルチュラル・スタディーズの登場は、グローバライゼーションやポストモダンと呼ばれる現代社会の変容とも密接に関連している。カルチュラル・スタディーズの輪郭を探るなかで、カルチュラル・スタディーズが、私たちに、つまり、社会学に何を提起しようとしているのかについて考えてみたい。
4 0 0 0 OA アジア諸国における教育と少子化の関連についての理論的背景
- 著者
- 松田 茂樹 佐々木 尚之
- 出版者
- 日本家族社会学会
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.169-172, 2020-10-31 (Released:2021-05-25)
- 参考文献数
- 9
東/東南アジアの先進国・新興国/地域は,いま世界で最も出生率が低い.この地域の少子化の特徴は,出生率低下が短期間に,急激に起こったことである.低出生率は,各国・地域の持続的発展に影を落としている.欧州諸国で起きた少子化は,第二の人口転換に伴う人口学的変化の一部として捉えられている.しかしながら,現在アジアで起こっている少子化は,それとは異なる特徴と背景要因を有する.主な背景要因のうちの1つが,激しい教育競争と高学歴化である.この特集では,韓国,シンガポール,香港,台湾の4カ国・地域における教育と低出生率の関係が論じられている.国・地域によって事情は異なるが,教育競争と高学歴化は,親の教育費負担,子どもの教育を支援する物理的負担,労働市場における高学歴者の需給のミスマッチ,結婚生活よりも自身のスペック競争に重きを置く物質主義的な価値観の醸成等を通じて,出生率を抑制することにつながっている.
4 0 0 0 OA 中枢神経系を標的としたmRNA医薬のDDSと治療応用
- 著者
- 内田 智士
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.125-133, 2023-03-25 (Released:2023-06-25)
- 参考文献数
- 35
中枢神経系難治疾患は、mRNA医薬の有力な標的であるが、デリバリーが課題である。送達経路として、脳実質や脳脊髄液への局所投与、全身投与からの血液脳関門(BBB)を介した送達、nose-to-brain経路があげられる。高分子ミセルは、中枢神経系への局所投与において、炎症反応を伴うことなく効率的なタンパク質発現を誘導し、モデル動物に対して治療効果を示した。例えば、アミロイドβに対する抗体断片のmRNAのマウス脳室内投与により、脳内アミロイドβ量が減少した。CRISPR/Cas9系のCas9タンパク質およびガイドRNAをマウス脳実質内に投与することで、in vivoゲノム編集に成功した。一方で、より低侵襲かつ簡便な投与を目指し、BBB経由やnose-to-brain経路によるmRNA送達システムも開発されている。
4 0 0 0 OA マイクロ波回路を複合した多機能アンテナ
- 著者
- 西山 英輔 豊田 一彦
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J106-B, no.5, pp.317-326, 2023-05-01
現在,IoT,近距離通信や無線センサネットワークなど無線を利用したシステムの多様化や5Gの実用化でアンテナの性能・機能の向上が求められている.例えば,指向性可変機能化,ビーム走査機能化,マルチバンド化,広帯域化やアダプティブアレー化などの多機能化が挙げられる.本論文では,アンテナの多機能化の手段としてアンテナとマイクロ波機能回路の複合技術を活用した平面型の多機能アンテナに注目する.このアンテナでは,多機能化のためにアンテナの直交共振モードを活用する.直交共振モードはお互いに独立であるために,その組み合わせで自在に所望の共振姿態を形成できる.マイクロ波機能回路は,アンテナに生じる直交する複数の共振モードを切替や合成するために活用する.ここでは,アンテナとマイクロ波機能回路との複合技術について説明し,それらを体系的にまとめている.また,アンテナとマイクロ波機能回路の複合による多機能アンテナの実際について概説する.
4 0 0 0 OA 貧困調査のクリティーク(2) : 『 排除する社会・排除に抗する学校』から考える
- 著者
- 宮内 洋 松宮 朝 新藤 慶 石岡 丈昇 打越 正行
- 出版者
- 北海道大学大学院教育学研究院
- 雑誌
- 北海道大学大学院教育学研究院紀要 (ISSN:18821669)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, pp.49-91, 2015-06-29
本稿は,貧困調査のクリティークの第2 弾として,西田芳正『排除する社会・排除に抗する学校』(大阪大学出版会,2012 年)を対象に,貧困調査・研究が陥りがちな諸課題を指摘した論考である。当該書は,1990 年代から西田が取り組んできた調査研究の知見を,貧困層の社会的排除という形でまとめ直したものである。当該書では,関西圏の「文化住宅街」や「下町」を中心的な対象とし,これらの地域に暮らす「貧困・生活不安定層」の生活や教育の実態・意識が明らかにされている。この研究に対し,「〈生活―文脈〉理解研究会」のメンバーが,理論的なレベル,方法的なレベル,そして若者,学校,地域という具体的なテーマのそれぞれの視点から批判的な検討を行った。これらの検討から浮かび上がったのは,当該書における〈文脈〉の捨象と,そのことが分析にもたらす問題である。本稿を通じて,貧困調査に求められる〈文脈〉のふまえ方が示された。
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1928年11月15日, 1928-11-15
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1928年11月24日, 1928-11-24
4 0 0 0 OA 徳川幕府の旗本の持参金養子に関する一考察 : 江戸時代前中期を中心に
- 著者
- 姜 鶯燕
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.43-84, 2009-11-30
江戸時代といえば、固定化された身分制社会としてのイメージが強い。しかし、身分移動の可能性が完全に閉ざされているわけではなかった。武士身分の売買が行われていたことから、個人レベルの身分上昇や身分移動は事実として存在した。
- 著者
- 佐野 孝 濱野 裕希
- 出版者
- 日本スポーツマネジメント学会
- 雑誌
- スポーツマネジメント研究 (ISSN:18840094)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-005, (Released:2022-12-12)
- 参考文献数
- 45
This study aimed to examine the effectiveness of the online examination system for grasping the psychological state of players in university sports club by clarifying the relationship between the psychological state and competition performance, and the transition of the state. During the month and a half before the target game, we conducted two tests on one track and field club to compare the scores of players who improved their records and those who did not, and examined changes in scores. As a result, the players who were able to break their own records had high patience and effectiveness in improving their performance at the start of the season. However, the endurance was significantly decreased at the second measurement. Additionally, the team's performance in the target game was better than in last three years. These findings suggest the effectiveness of grasping mental states in mental health care and team management.
4 0 0 0 OA 儒教の形成(V) : 緯書による孔子の神秘化
- 著者
- 浅野 裕一
- 出版者
- 東北大学大学院国際文化研究科
- 雑誌
- 国際文化研究科論集 (ISSN:13410857)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.204-180, 1995-12-20
4 0 0 0 OA IV.感染症の数理モデルと対策
- 著者
- 鈴木 絢子 西浦 博
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.11, pp.2276-2280, 2020-11-10 (Released:2021-11-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 6 1
新型コロナウイルス感染症(coronavirus disease 2019:COVID-19)のような新興感染症の流行下においては,感染症数理モデルを用いた流行データ分析やシナリオ分析が政策判断の核をなす重要なエビデンスとなる.日本ではこれまで広く取り上げられることが少ない領域であったが,COVID-19の世界的な流行により注目の集まる研究分野である.本稿では,COVID-19の疫学的な知見に加えて,感染症数理モデルの基礎的な考え方について述べる.
4 0 0 0 OA カルベジロール錠の粉砕・篩過および自動分包調剤による薬剤損失
- 著者
- 佐々木 誠 佐野 雅俊 田中 靖子 山本 育由
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.420-423, 2006-05-10 (Released:2007-11-09)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 5 3
Recently, at very low doses, carvedilol has improved the treatment of chronic heart failure. In Tenri Hospital, prescriptions for low dose carvedilol had been prepared by grinding a 10 mg tablet, adding lactose to it, and packaging the resulting powder. However, the drug loss in these processes had been causing problems in treating chronic heart failure. The present study examines the extent of drug loss in the grinding, sifting, and automatic packaging processes and the causes.The overall drug loss rate, as calculated by measuring the weight of the powder in the finished package, was 24.8±12.8, 33.9±13.2, and 28.0±9.3% for the 1.25, 2.5, and 5 mg packages, respectively, a considerable loss. The greatest loss was found to occur in the automatic packaging process. The drug loss rates for carvedilol itself were 56.4±8.1, 50.2±10.2, and 36.9±7.5% for the 1.25, 2.5, and 5 mg packages, respectively. The loss of carvedilol was greater for the 1.25 and 2.5 mg packages than the 5 mg package (p<0.05).These results suggest that the grinding of a 10 mg tablet gives rise to inaccurate dosing. Thus, low dose tablets available on the market should be used preferentially when low dosages of carvedilol are prescribed to patients with chronic heart failure.
4 0 0 0 OA 日本語母語話者とシンハラ語母語話者の感謝場面における「人間関係」についての理解と感謝表現
- 著者
- S.M.D.T. ランブクピティヤ
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.158, pp.112-130, 2014 (Released:2017-02-17)
- 参考文献数
- 12
本研究では,日本語母語話者(JNS)とスリランカ人シンハラ語母語話者(SNS)が感謝の送り手と受け手の「親疎関係」及び「同位・上位関係」を基に感謝場面をどのように理解し,どのような感謝表現を使用するかを調べた。調査方法では,JNSとSNS,各10組ずつを対象に,「友達が忘れ物を渡す」,「見知らぬ人が忘れ物を渡す」,「友達の家を訪問する」,「先生の家を訪問する」という4つの場面でロールプレイを行ってもらった後,フォローアップインタビューに応えてもらった。調査の結果,SNSは感謝の送り手と受け手の関係が親しいと認識した場合,相手に距離を感じさせないように感謝の表出をしないことと,感謝の受け手が先生の場合,上位関係に対する尊敬の念を込めて感謝を表出することがわかった。一方JNSは,互いの関係性の「親疎」及び「同位・上位」という要素を認識してはいるが,どの場面においても感謝を「定型表現」で表出することがわかった。
- 著者
- 佐藤 容子
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.111-122, 2002-09-30 (Released:2019-04-06)
本研究は、学級内で仲間達から拒否されている6歳の学習障害児の仲間関係を改善するために、コーチング法を用いた社会的スキル訓練を実施した。訓練前の教師評定と行動観察によると、対象児は仲間との間で、適切なやり取りが少なく、不適切(攻撃的および引っ込み思案的)なやり取りが多かった。訓練は、1回につき約60分間で、特別な訓練室の場面で5セッション、自由遊び場面で4セッション、合計9セッション行った。その結果、ターゲット児の不適切(攻撃的または引っ込み思案的)なやり取りは、教師評価と行動観察のいずれにおいても、訓練とともに減少した。好意的やり取りは行動観察においてのみ増加がみられた。エントリースキルについては明らかな訓練効果はみられなかった。また、本訓練によって、SCR尺度でみた自己コントロールが改善した。
4 0 0 0 OA 忘却と祈り - 君の名は大森荘蔵? -
- 著者
- 佐藤 英明
- 出版者
- 中央学院大学商学部・法学部・現代教養学部
- 雑誌
- 中央学院大学人間・自然論叢 = The Bulletin of Chuo-Gakuin University : man & nature (ISSN:13409506)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.13-41, 2023-01-31
4 0 0 0 OA 近世神社通史稿
- 著者
- 井上 智勝
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.148, pp.269-287, 2008-12-25
本稿は、近世における神社の歴史的展開に関する通史的叙述の試みである。それは、兵農分離・検地・村切り・農業生産力の向上と商品経済の進展など中世的在り方の断絶面、領主による「神事」遂行の責務認識・神仏習合など中世からの継承面の総和として展開する。一七世紀前半期には、近世統一権力による社領の没収と再付与、東照宮の創設による新たな宗教秩序の構築などが進められ、神社・神職の統制機構が設置され始めた。兵農分離による在地領主の離脱は、在地の氏子・宗教者による神社運営を余儀なくさせ、山伏など巡国の宗教者の定着傾向は神職の職分を明確化し、神職としての自意識を涵養する起点となった。一七世紀後半期には、旧社復興・「淫祠」破却を伴う神社および神職の整理・序列化が進行し、神祇管領長上を名乗る公家吉田家が本所として江戸幕府から公認された。また、平和で安定した時代の自己正当化を図る江戸幕府は、国家祭祀対象社や源氏祖先神の崇敬を誇示した。一八世紀前半期には、商品経済が全国を巻き込んで展開し、神社境内や附属の山林の価値が上昇、神社支配権の争奪が激化し始める。村切りによって、荘郷を解体して析出された村ではそれぞれ氏神社が成長した。また、財政難を顕在化させた江戸幕府は、御免勧化によって「神事」遂行の責務を形骸化させた。一八世紀後半期には、百姓身分でありながら神社の管理に当たる百姓神主が顕在化した。彼らを配下に取り込むことで神職本所として勢力を伸ばした神祇官長官白川家が、吉田家と対抗しながら配下獲得競争を展開し、復古反正の動向が高まる中、各地の神社は朝廷権威と結節されていった。また、神社は様々な行動文化や在村文化の拠点となっていた。明治維新に至るまでの一九世紀、これらの動向は質的・量的・空間的に深化・増大・拡大してゆく。近代国家は、近世までの神社の在り方を否定してゆくが、それは近世が準備した前提の上に展開したものであった。