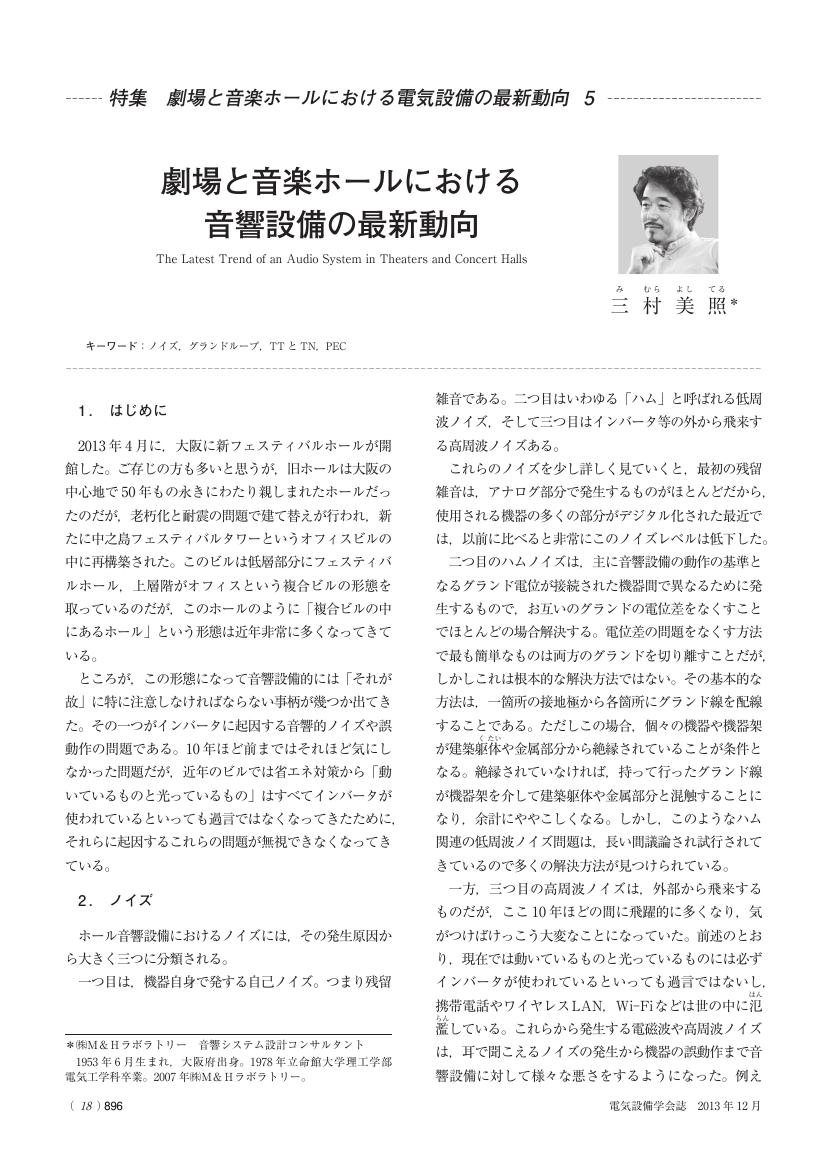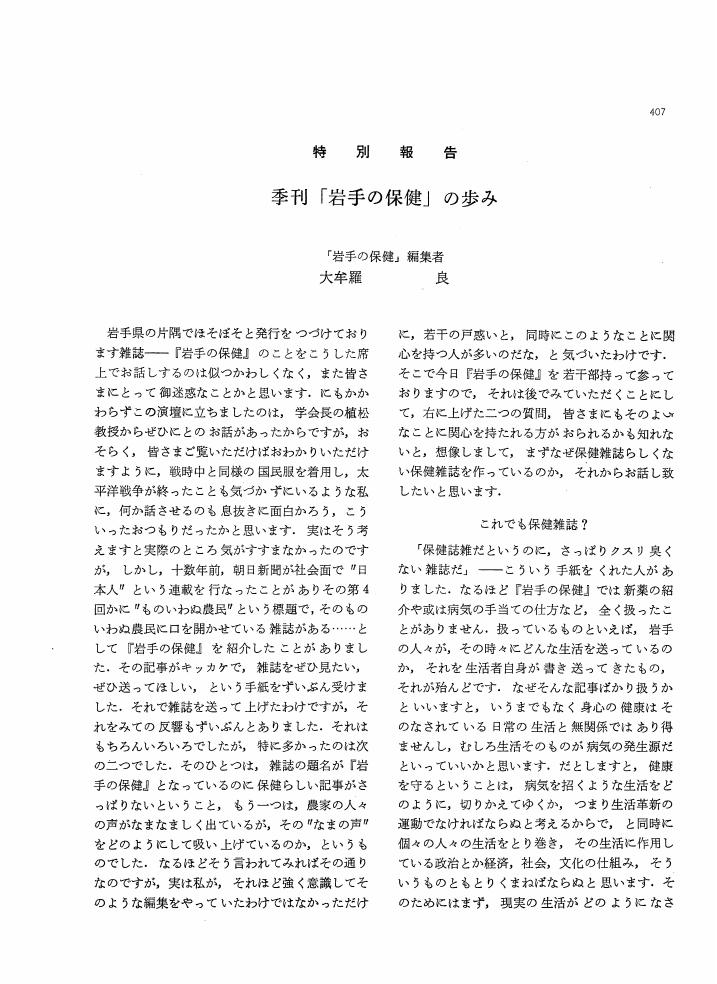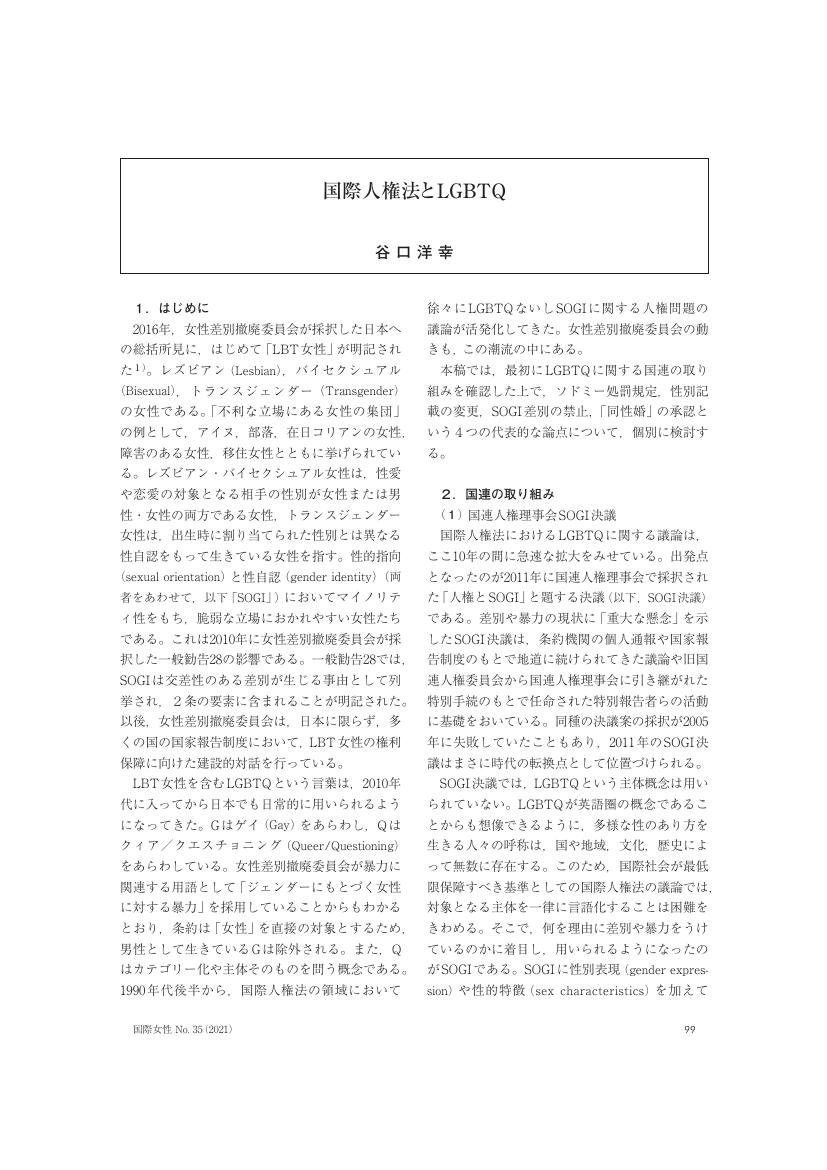4 0 0 0 魔眼と飛翔 : バルザック中世小説における〈魔女〉
- 著者
- 加倉井 仁
- 出版者
- 早稲田大学文学部フランス文学研究室
- 雑誌
- Etudes francaises (ISSN:13403095)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.40-56, 2019-03
4 0 0 0 OA 劇場と音楽ホールにおける音響設備の最新動向
- 著者
- 三村 美照
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.12, pp.896-899, 2013-12-10 (Released:2014-09-08)
4 0 0 0 強化学習によるマッチング数を最大化するジョブ推薦システム
4 0 0 0 OA 松本隆の歌詞の使用単語についての計量テキスト分析
- 著者
- 定村 薫
- 出版者
- 尚美学園大学総合政策学部
- 雑誌
- 尚美学園大学総合政策研究紀要 = Bulletin of policy and management, Shobi University (ISSN:13463802)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.17-33, 2019-09
本研究は、日本を代表する作詞家のひとりである松本隆の作詞した楽曲の歌詞を分析する。松本隆はそれまでの歌謡曲の歌詞の概念を大きく変える斬新な歌詞を発表し、後進の作詞家やシンガーソングライターにも大きな影響を与えている。本研究では歌詞に使用される単語の頻度から、松本隆の歌詞の特徴を他の作詞家との比較によって数的に捉えることを目的とする。
4 0 0 0 OA クルマエビの交尾栓
- 著者
- 伏屋 玲子
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.17-19, 2006-05-01 (Released:2017-07-05)
- 参考文献数
- 4
4 0 0 0 OA 特別報告季刊「岩手の保健」の歩み
- 著者
- 大牟羅 良
- 出版者
- 日本民族衛生学会
- 雑誌
- 民族衛生 (ISSN:03689395)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.6, pp.407-414, 1969 (Released:2010-06-28)
4 0 0 0 OA 国際人権法とLGBTQ
- 著者
- 谷口 洋幸
- 出版者
- 国際女性の地位協会
- 雑誌
- 国際女性 (ISSN:0916393X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.99-104, 2021 (Released:2023-03-01)
4 0 0 0 OA 景気循環と太陽活動周期 : 物理経済学的アプローチ
- 著者
- 嶋中雄二
- 出版者
- 日本経済研究センター
- 雑誌
- 日本経済研究
- 巻号頁・発行日
- no.16, 1986-12
4 0 0 0 OA 複合原子層科学を支えるファンデルワールス接合技術
- 著者
- 増渕 覚 町田 友樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.9, pp.550-558, 2020-09-05 (Released:2020-11-18)
- 参考文献数
- 63
60年ほど前に「原子を一つずつ配置して思い通りの物質を作れば,これまで考えられなかったほど多くの物性を引き出すことができる」と述べたのはリチャード・ファインマン教授でした.江崎玲於奈博士は半導体超格子を提案し,分子線エピタキシーによって「ボトムアップでナノサイズの人工物質を作る」という概念を実証しました.物質を構成する原子や分子を自在に積み上げて組み合わせることができれば,これまで見られなかった新しい電子物性を有する物質を創り出すことができる――物性科学を志した研究者であれば,このような想いを心に描いたことがあるのではないでしょうか.近年になり,グラファイトをはじめとする様々な二次元結晶が,スコッチテープを用いた剥離法により単原子層まで薄層化できるようになりました.剥離された原子層は様々な手法によって機械的に貼り合わせることができ,原子層単位で界面が制御された人工構造――ファンデルワールスヘテロ構造――が作製できます.接合界面における格子整合が不要であることから,様々な材料同士の組み合わせが実現でき,波動関数の混成と電子間相互作用によって,多彩な電子物性が発現します.例えば,結晶方位角のズレをθ~1.06°に正確に制御して単層グラフェンを二枚重ねると,両者のバンドの交点においてフラットバンドが形成され超伝導が発現します.グラフェンと六方晶窒化ホウ素を結晶方位を合わせて重ね,磁場を印加すると「ホフスタッターの蝶」と呼ばれるフラクタル状のバンドが形成されます.構成要素として利用可能な二次元結晶は20種類以上存在し,ファンデルワールスヘテロ構造は無限の可能性を秘めていると期待されます.これまで電子物性研究に用いられてきた最高品質のファンデルワールスヘテロ構造は,二次元結晶を剥離して貼り合わせるという極めて原始的な手法により作製されてきました.高品質な母結晶を剥離することが,最も不純物の取り込みが少ない試料作製法だからです.原子層を壊さずに重ねるため,過去10年間にわたり様々な手法が開発されてきました.ファンデルワールスヘテロ構造を舞台として物性科学研究をさらに進めるためには,それぞれの手法の特徴を理解し,これらを上手く組み合わせていくことが重要です.さらに最近,ロボティクス・機械学習・深層学習を用い,研究者が手作業で行ってきたファンデルワールスヘテロ構造の作製工程を自動化し,これまで考えられなかった複雑な試料を作製する研究が始まりつつあります.研究は今後,興味深い物性を示す組み合わせをシステマチックに探索する形へ移行していくと考えられます.その先には,物質を構成する原子や分子を自在に積み上げて組み合わせ,様々な機能を持つ材料を自在に設計するという,多くの科学者が抱く究極の夢が広がっています.
4 0 0 0 OA グラフィックソフトを用いたデジタル記載図の作成技法
- 著者
- 蛭田 眞平 角井 敬知
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.19-30, 2010-08-20 (Released:2018-03-30)
- 参考文献数
- 4
Personal computers (PCs) are now indispensable to any field of study, and it is important to master efficient ways to compose documents, analyze data, and manage literature. This is especially true of illustrations, which take much time and repeated editing prior to use in publications, posters, presentations, and so on. Although some reports exist on techniques for making digital illustrations there has been rapid progress in the development of new PC hardware and software, so that some types of previously intractable digital graphical processing methods are now feasible and even routine. In this report, we introduce an easy and efficient way to make digital illustrations based on recent progress in software development. Using as an example small arthropods, our main study subject, we demonstrate a digital illustration method implemented in Adobe^[○!R] Illustrator CS3^[○!R], and describe the use of CombineZ, a focus stacking software.
4 0 0 0 OA 小川正孝のニッポニウム発見—その劇的な展開
- 著者
- 吉原 賢二
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.4-7, 2018-01-20 (Released:2019-01-01)
- 参考文献数
- 8
ニッポニウムは小川正孝が1908年に発見を報告した元素名である。一時世界的に評価されたが追試が成功せず,周期表から消え去り,幻の元素のように思われていた。しかし,その後1990年代から東北大学の後輩教授である吉原による現代化学的再検討によって,ニッポニウムの実体は75番元素レニウムと判明した。小川の生涯にわたる研究への熱き情熱,その最期の悲劇,吉原に注がれたセレンディピティー(幸運な偶然)などまことにドラマティックというほかない。化学史上も化学教育上も興味深いものである。
- 著者
- Da HU Li ZHANG Rong JIANG Cuiting LIAO Juanjuan XU Shifang JIANG Yongqiang YANG Ling LIN Jiayi HUANG Yi SHEN Li TANG Longjiang LI
- 出版者
- Center for Academic Publications Japan
- 雑誌
- Journal of Nutritional Science and Vitaminology (ISSN:03014800)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.145-152, 2021-06-30 (Released:2021-06-30)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 9
Acetaminophen (N-acetyl-p-aminophenol, APAP) overdose causes hepatotoxicity, even liver failure, and oxidative stress plays pivotal role in its pathogenesis. Nicotinic acid (NA) is one form of vitamin B3, which has been used to treat a series of diseases in clinic for decades. To date, several studies have evidenced that NA has anti-oxidative property. Therefore, NA may have the hepatoprotective potential against APAP-induced toxicity. Here, our aim was to investigate the beneficial effect of NA against hepatotoxicity induced by APAP and its mechanism in vivo. BALB/c mice were intraperitoneally injected with NA (100 mg/kg) 3 times at 24, 12 and 1 h before APAP (600 mg/kg or 400 mg/kg) challenge. The results showed that pretreatment of NA markedly improved the survival rate, alleviated serum alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) levels and mitigated the histopathological injuries compared to APAP-exposed mice. Furthermore, NA significantly elevated the activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione (GSH) content, while reduced malondialdehyde (MDA) level. Finally, the signaling pathway was probed. The western blot revealed that NA up-regulated Sirtuin1 (Sirt1), nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and NAD(P)H quinone dehydrogenase-1 (NQO-1) expression and down-regulated Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1) level in liver followed APAP exposure, implying Sirt1/Nrf2 axis exerted an essential role in the protective mechanism of NA on APAP toxicity. In brief, pretreatment of NA effectively protects liver against hepatotoxicity due to overdose of APAP through an antioxidant dependent manner modulated by Sirt1/Nrf2 signaling pathway.
4 0 0 0 OA 内閣官房の研究 ‐副長官補室による政策の総合調整の実態‐
- 著者
- 高橋 洋
- 出版者
- 日本行政学会
- 雑誌
- 年報行政研究 (ISSN:05481570)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.45, pp.119-138, 2010 (Released:2015-12-09)
4 0 0 0 OA 現代を生きる
- 著者
- 森 毅 西村 健
- 出版者
- 日本精神衛生学会
- 雑誌
- こころの健康 (ISSN:09126945)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.3-16, 1993-10-31 (Released:2011-03-02)
4 0 0 0 OA 13項目7件法 sense of coherence スケール日本語版の基準値の算出
- 著者
- 戸ヶ里 泰典 山崎 喜比古 中山 和弘 横山 由香里 米倉 佑貴 竹内 朋子
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.232-237, 2015 (Released:2015-06-25)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
目的 健康保持・ストレス対処力概念である sense of coherence (SOC)に関する研究は近年増加しており,介入研究のアウトカム指標として用いられる例も多くなってきている。その一方で SOC スケール日本語版は標準化が行われていない現状にある。そこで全国代表サンプルデータを用いて13項目 7 件法版 SOC スケール日本語版の基準値を得ること,すなわち,性・年齢別の得点分布,居住地域および都市規模とスケール得点との関係を明らかにすることを本研究の目的とした。方法 日本国内に居住する日本人で居住地域,都市規模,年齢,性別による層化 2 段抽出により2014年 1 月 1 日現在で25歳から74歳の男女4,000人を対象とした。2014年 2 月から 3 月にかけて自記式質問紙による郵送留置法を実施し,2,067票を回収した(回収率51.7%)。分析対象者は男性956人,女性1,107人,平均年齢(標準偏差(SD))は50.0(14.3)歳であった。結果 SOC スケールの平均(SD)得点は59.0(12.2)点であった。性別では,男性59.1(11.8)点,女性58.9(12.5)点で男女間で有意差はみられなかった(P=0.784)。年齢階層別の検討では,一元配置分散分析の結果有意(P<0.001)となり,多重比較の結果概ね高い年齢階層であるほど高い SOC 得点であることが明らかになった。SOC を従属変数,居住地域(11区分),都市規模(4 区分)およびその交互作用項を独立変数とし年齢を共変量とした共分散分析の結果,いずれも有意な関連はみられなかった。結論 本研究を通じて,日本国内に在住する日本人集団を代表する SOC スケール得点を得ることができた。また性差,地域差はみられず,年齢による影響がみられていた。本研究成果を基準値とすることで年齢などの影響を考慮した分析が可能になり,今後,SOC スケールの研究的・臨床的活用が期待される
4 0 0 0 OA 岩石の熱疲労に関する実験的研究
- 著者
- 小林 良二 酒井 昇 松木 浩二
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.1140, pp.81-86, 1983-02-25 (Released:2011-07-13)
- 参考文献数
- 12
It is well known that rocks are more or less deteriorated by sudden cooling after being heated. Furthermore, by repeating the cycle of heating-cooling, rocks might be expected to be weakened more severely.In this paper, measuring the changes of the physical and mechanical properties of rocks including apparent specific gravity, P-wave velocity, Young's modulus and uniaxial compressive strength, the thermal fatigue process of rocks is characterized for four kinds of rocks, namely, OGINO tuff, EMOCHI welded tuff, AKIYOSHI marble and INADA granite. The cylindrical specimens are suddenly submerged into water after being heated and the cycle is automatically repeated in the testing machine.The maximum temperature and the maximum cycles in the experiment are 600°C and 54, respectively.The main results obtained are as follows:(1) The main failure mechanism is different between the crystalline rock and the sedimentary rock. The failure of the former takes place by the thermal interaction between minerals and that of the latter by the transient thermal stresses. As the result, crystalline rocks collapse to be particles or powders and sedimentary rocks are fractured initiating regular thermal cracks (Fig.6).(2) The strengths of the rocks except welded tuff decrease remarkably within 5 cycles if the temperature is sufficiently high and the cooling time is larger enough (Fig.3).(3) The strengths of the rocks except marble decrease as the cooling time increases. However, the additional effect is very small if the cooling time is larger than that needed for the specimens to be perfectly cooled (Fig.4).(4) The cycles at which the specimens collapse exponentially increase as the temperature decreases (Fig.5).
4 0 0 0 OA 『番人円吉蝦夷記 全』翻刻と解説(1)
- 著者
- 高橋 由彦 花輪 陽平 藤村 久和
- 出版者
- 学校法人國學院大學 國學院大學北海道短期大学部
- 雑誌
- 國學院大學北海道短期大学部紀要 (ISSN:21853517)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.47-87, 2014-03-19 (Released:2018-07-19)
4 0 0 0 OA てんかん放電と6 Hz棘徐波の鑑別および臨床的判断に難渋した1例
- 著者
- 原 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.82-86, 2020-04-01 (Released:2020-04-14)
- 参考文献数
- 15
症例は22歳男性である。11歳時に強直発作で発症し, 脳波で3 Hz棘徐波複合を認めた。全般てんかんの診断で治療開始され, 14歳以降発作は消失した。20歳時に当院に転医し, この時の脳波で6 Hz棘徐波を認めた。抗てんかん薬を減量したところ初診時にみられた6 Hz棘徐波に比べて振幅が増大し, 分布や波形の変化した活動を認めた。抗てんかん薬減量後の波形について, 6 Hz棘徐波とてんかん放電との鑑別, および6 Hz棘徐波と判断した場合のてんかん発作との関連について, 判断に難渋したが, てんかん発作との関連が強くなった可能性を疑い, 抗てんかん薬の減量を中止した。6 Hz棘徐波とてんかん発作との関連の強さを, その特徴からわけようとする報告がある。6 Hz棘徐波の一部はてんかん放電とは区別するべきとされる一方, 約半数にてんかん発作を認めるとの報告があり, 臨床的判断には注意を要する。6 Hz棘徐波とてんかん発作との関連と合わせて報告する。
4 0 0 0 OA 急性期脳損傷患者におけるBox and Block Testと食事動作の自立度の関連
- 著者
- 宮内 貴之 佐々木 祥太郎 佐々木 洋子 最上谷 拓磨
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.263-269, 2023-06-15 (Released:2023-06-15)
- 参考文献数
- 27
本研究はBox and Block Test(以下,BBT)が,急性期脳損傷患者に対して評価可能な食事動作に関連する評価指標となりうるかを明らかにすることを目的とした.対象は78名(食事動作自立群:54名,非自立群:24名)であった.その結果,2群間でBBTに有意な差があり,その効果量も大きいことが確認された.また,BBTは食事動作の自立度と高い相関関係を示し,Receiver Operating Characteristic曲線のArea Under the Curveでは良好な判別能を示した.そのため,BBTは急性期脳損傷患者の食事動作の自立度に関連する上肢パフォーマンスの評価指標となることが示唆された.