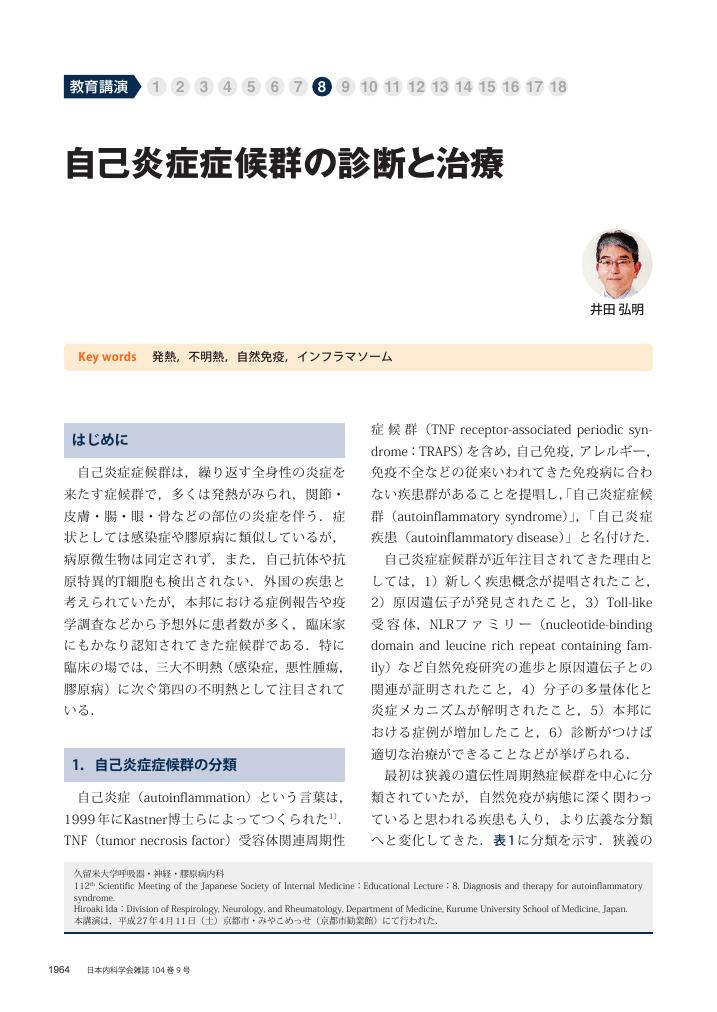4 0 0 0 OA 家族形成過程へのきょうだい数の影響
- 著者
- 廣嶋 清志
- 出版者
- 日本人口学会
- 雑誌
- 人口学研究 (ISSN:03868311)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.31-40, 1984-05-21 (Released:2017-09-12)
Since the middle of the 1970's, the major part of reproductive populatoin has been the generation born during the period of rapid fertility decline after the War. Author examined microscopically this trend through the observation of the effects of sibling number on marriage, birth etc., using survey data of 2,034 couples with at least one child younger than 6.25 years old. The main findings are as follows. (1) The effect of sibling number on school career has been robust and negative for both husband and wife and been strengthened for newer cohorts. (2) Residential relation which expresses whether a couple lives with or near their parents is negatively and strongly affected by the number of siblings. The number of siblings of spouse reversely affects it. (3) As for age at marriage, the indirect effects of sibling number is stronger through school career and co-residence with parents than direct effects. Nevertheless if wife is only child, which is assumed to be unadvantageous by the necessity to co-reside with her parents, wife's age at marriage is higher. But this effect has been being attenuated. Co-residence with parents or parent-in-laws has a positive effect on age at marriage for both husband and wife. Psychological cost accompanied by co-residence with parents may raise age at marriage. (4) School career of husband has positive effect on fertility. Indirect effect of sibling number through this can be inferred as negative. Effects through age at marriage are negative for wife and positive for husband. Direct effect of husband's sibling number on fertility is small but positive. These effects of sibling number allow us to speculate that the decrease in number of siblings has been one of the factors affecting the expansion in educational enrollment rate and also one of factors raising age at marriage through school career and co-residence with parents. The decrease in number of siblings is to continue for around 1965 birth cohort. Therefore changes in demographic behavior through the change of sibling number will last until the beginning of the 1990's.
4 0 0 0 OA 深海潜水調査船しんかい6500の運動性能について
- 著者
- 高川 真一 難波 直愛 森鼻 英征 手塚 久男 前田 逸郎 重国 清 石黒 慎二
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 関西造船協会誌 216 (ISSN:03899101)
- 巻号頁・発行日
- pp.201-207, 1991-09-25 (Released:2018-04-01)
Deep Submergence Research Vehicle "SHINKAI6500" is the latest manned research vehicle which can dive to the deepest existing in the world. The maneuverability of a submersible vehicle is highly dependent on its cofiguration. During the development of "SHINKAl6500" we have assumed great importance to its decending and ascending capability. "SHINKAI6500"'s configuration has been improved in various respects reflecting "SHINKAI2000"'s operation results, finally determined based on the results of twice wind tunnel tests and a tank test. In sea trials it is confirmed that hydrodynamics resistance of "SHINKAI6500" is remarkably reduced compared to that of "SHINKAI2000". This paper describes the outline of these model tests, sea trials and the process of the development of its streamlined cofigulation.
4 0 0 0 人間達 (アイヌタリ) のみた星座と伝承
- 著者
- 森下 知晃
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 岩石鉱物科学 (ISSN:1345630X)
- 巻号頁・発行日
- pp.230203, (Released:2023-06-28)
Ultramafic rocks, i.e., peridotites and pyroxenites, occur in a variety of tectonic settings on Earth. Ultramafic rocks can form as accumulation of mafic minerals from basaltic to komatiitic melts and be a major component of the Earth's mantle. The origin and history of ultramafic rocks are expected to provide information on the processes of partial melting and melt migration/extraction in the mantle and on the tectonic evolution of geologic units containing ultramafic rocks. I study ultramafic rocks in metamorphic belts, ocean floor, and mantle sections of ophiolites. My career began with a study of the Horoman Peridotite Complex in the Hidaka metamorphic belt in Japan. The ultramafic rocks and associated mafic rocks in the Horoman body record a very complex evolutionary history from the mantle conditions to crustal conditions. It is difficult to constrain the tectonic setting affecting events in the Horoman Peridotite Complex. On the other hand, ultramafic rocks in the mantle section of ophiolites and abyssal peridotites directly recovered from ocean floor to study melting processes and melt-rock interactions in the mantle can be used to constrain their tectonic setting, or at least as analogs to these tectonic settings. Studies on the Oman ophiolite by Japanese groups and literature studies of other ophiolites suggest that many ophiolites are later modified by subduction-related magmatism. Several ophiolites are being studied to elucidate the maturing process by subduction-related magmatism. Simple partial melting and melt extraction is expected in the adiabatically upwelling mantle beneath the mid-ocean ridge. In fact, abyssal peridotites directly recovered from mid-ocean ridges provided a unique opportunity to elucidate these processes. Comparison of abyssal peridotites recovered from the mid-ocean ridges and arc regions (fore arc and back arc) is key to understand the differences in magmatic processes in the two regions. Ocean science with research vessels has a well-defined working hypothesis that can only be addressed by direct sampling from the seafloor. To understand a crucial issue in Earth science as to why plate tectonics occurs on Earth, it is essential to elucidate the life of the oceanic lithosphere from its birth to its subduction into the mantle. Direct sampling of oceanic lithosphere by drilling is the key to solving this issue. I would like to emphasize that members of the Japan Association of Mineralogical science can play an essential role in leading analyses of rock samples directly recovered from seafloor. Rock samples recovered from seafloor by drilling and any methodology, as well as samples from anywhere on Earth, should be published in as papers, and these data would help integrate knowledge about the history of the Earth and planet and its future.
4 0 0 0 家庭用浄水器がフッ素濃度に及ぼす影響
水道水のフッ化物濃度調整(fluoridation)があり、公衆衛生学上優れたう蝕予防法である。わが国においても、地域住民の合意等を前提にfluoridationの実施が可能となった(2000年、厚生労働省)。国内では安全な水の供給に関心が高まっており、浄水器を設置する家庭が増加している。したがってfluoridationが実施された場合、浄水器通過後のフッ素(F)濃度を検討する必要がある。本研究では家庭用浄水器に多く使用されている2種類の濾材を用いて浄水装置を作製し、F濃度に及ぼす影響を検討した。家庭用浄水器の濾材として用いられている活性炭フィルターと中空糸膜フィルターを用いて、簡易浄水装置を作製した。NaFを純水および水道水に添加し、種々のF濃度(0.1〜10mg/L)の試験溶液を調製した。ついで浄水装置通過後の試験溶液とフィルター中のフッ素濃度を測定した。活性炭フィルターを用いた浄水装置通過後のF濃度は、すべての試験溶液で通過量10Lまでは通過前のおよそ1/10の濃度であった。その後通過量が多くなるにしたがって、F濃度は上昇した。中空糸膜フィルターを用いた浄水装置では通過前後のF濃度に変化がみられなかった。実験終了後の活性炭フィルター中に高濃度のFが含まれていた。以上より、活性炭フィルターを使用した家庭用浄水器はfluoridation後の水道水中のF濃度に影響を及ぼすことが明らかになった。従って、fluoridationによるう蝕予防効果を確実にするためには、使用する浄水器の種類を考慮する必要があることが明らかにされた。なお、F以外の陰・陽イオンについては、Cl、MgとCaは活性炭フィルターと中空糸膜フィルターに吸着されることが示された。その他のイオンについては明確な結果が得られなかった。
4 0 0 0 OA Rate of Advancement of Detection Limits in Mass Spectrometry: Is there a Moore’s Law of Mass Spec?
- 著者
- Mark Beattie Oliver A. H. Jones
- 出版者
- The Mass Spectrometry Society of Japan
- 雑誌
- Mass Spectrometry (ISSN:2187137X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.A0118, 2023-04-06 (Released:2023-04-06)
- 参考文献数
- 40
Mass spectrometry is a well-established analytical technique for studying the masses of atoms, molecules, or fragments of molecules. One of the key metrics of mass spectrometers is the limit of detection e.g., the minimum amount of signal from an analyte that can be reliably distinguished from noise. Detection limits have improved greatly over the last 30–40 years to the point that nanogram per litre and even picogram per litre detections are commonly reported. There is however, a difference between detection limits obtained with a single, pure compound in a pure solvent and those obtained from real life samples/matrixes. Determining a practical detection limit for mass spectrometry is difficult because it depends on multiple factors, such as the compound under test, the matrix, data processing methods and spectrometer type. Here we show the improvements in reported limits of detection on mass spectrometers over time using industry and literature data. The limit of detection for glycine and dichlorodiphenyltrichloroethane were taken from multiple published articles spanning a period of 45 years. The limits of detection were plotted against the article’s year of publication to assess whether the trend in improvement in sensitivity resembles Moore’s Law of computing (essentially doubling every two years). The results show that advancements in detection limits in mass spectrometry are close to, but not quite at a rate equivalent to Moore’s Law and the improvements in detection limits reported from industry seem to be greater than those reported in the academic literature.
4 0 0 0 OA ヒトゲノム研究の新しい地平
- 著者
- 斎藤 成也
- 出版者
- 一般社団法人 日本人類学会
- 雑誌
- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)
- 巻号頁・発行日
- vol.117, no.1, pp.1-9, 2009 (Released:2009-06-20)
- 参考文献数
- 31
20世紀末にはじまったゲノム研究は,ヒトゲノム解読をひとつの到達点とした。しかしそれは終わりではなく,始まりだった。ヒトゲノム配列をもとにして膨大なSNPやマイクロサテライト多型の研究が急激に進み,小数の古典多型マーカーを用いた従来の研究成果を追認しつつ,日本列島人の遺伝的多様性についても新しい光が当てられつつある。また個々人のゲノム配列を決定する研究も進展している。これらヒトゲノム研究の新しい地平を紹介した。
4 0 0 0 介護ロボット學の創成
- 著者
- 柴田 智広
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.5, pp.427-431, 2023 (Released:2023-06-22)
- 参考文献数
- 16
- 著者
- Tatsuto AOKI
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.105-118, 2000-12-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 9 10
Geomorphological equilibrium line altitude (ELAg), as defined by steady-state equilibrium line altitude estimated based on geomorphological method, has been used to reconstruct Last Glacial palaeoclimate. However, the ELAg is influenced not only by temperature, but also by other factors. This paper discusses factors affecting Last Glacial ELAg in the Kiso mountain range, central Japan. The weathering-rind thickness of gravel was used for dating moraines. The dating results have shown that glaciers advanced at the Last Glacial Maximum and the Younger Dryas stages. The ELAg for each stage was reconstructed based on the Accumulation-Area-Ratio method (AAR=0.6). The results indicate that the ELAg of each reconstructed glacier was affected not only by temperature but also by the altitude of mountain ridges. Although some previous studies have reconstructed palaeoclimate based on the ELAg, the results of the present study cast doubt on such reconstruction. For better reconstruction, the effects of temperature on the ELAg should be separated from those of topographic factors.
4 0 0 0 OA 8)自己炎症症候群の診断と治療
- 著者
- 井田 弘明
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.9, pp.1964-1973, 2015-09-10 (Released:2016-09-10)
- 参考文献数
- 16
4 0 0 0 OA 医療経済学系研究人材を取り巻く環境と課題
- 著者
- 石川 鎮清 木村 哲也 中村 好一 近藤 克則 尾島 俊之 菅原 琢磨
- 出版者
- 一般財団法人 日本健康開発財団
- 雑誌
- 日本健康開発雑誌 (ISSN:2432602X)
- 巻号頁・発行日
- pp.202244G01, (Released:2022-08-17)
- 参考文献数
- 12
背景・目的 医療経済学への社会的要請は高まっているが、担う人材は十分とは言えず、養成上の課題は多い。そこで医療経済学の人材養成の課題を把握し、解決策の方向を示すことを目的とした。方法 2つの調査を行った。量的調査では、主要2学会の抄録集を対象に近年10年間における医療経済学分野の研究発表数、人材数を調査した。質的調査では、国内の医療経済学分野における中堅研究者8人を対象に半構造化面接を行い、質的に分析した。結果 日本経済学会では一般演題に占める医療経済学関連の演題の割合が2000年代には2%~6%台だったが、2012年を境に8%~10%台へと増加していた。医療経済学会では、経済学系の発表者の割合が2000年代には4~7割の幅で上下していたが、2013年以降は、上昇に転じ、2015年~2016年は7割を超えていた。インタビュー調査からは、大学教育における医療経済学の課題、研究職ポストの不足、データ利用の促進の必要性、経済学系と医学系との協働の可能性の4つのカテゴリを抽出した。考察 量的・質的調査の結果、社会的ニーズの増大にもかかわらず、人材育成には課題があることが明らかになった。問題解決の方向性として1)重点的で継続的な人材養成、2)雇用ポストの創出、3)医療データの利用環境の改善促進、4)医学分野と経済学分野との協働の場の創設の4つが重要と考えられた。
4 0 0 0 OA アイヌ文化期における黒耀石の利用とその変容 ─ せたな町南川2遺跡を中心に ─
- 著者
- 大塚 宜明 池谷 信之 工藤 大
- 出版者
- 札幌学院大学総合研究所 = Research Institute of Sapporo Gakuin University
- 雑誌
- 札幌学院大学人文学会紀要 = Journal of the Society of Humanities (ISSN:09163166)
- 巻号頁・発行日
- no.110, pp.79-100, 2021-10-20
本論では,アイヌ文化期(中近世)に属する北海道せたな町南川2遺跡の黒耀石製石器を対象に,石器の技術的分析および黒耀石原産地推定分析を実施した。さらに,そのデータと、当該期の道内の遺跡や先行する擦文文化の事例との関連性を検討することで,アイヌ文化期における黒耀石利用の変遷とその歴史的意義について考察した。 その結果,①アイヌ文化期において黒耀石副葬と被葬者の性別(女性)に関係性がある一方,出土地域と黒耀石原産地の間に特定の結びつきがないこと,②擦文時代初頭の黒耀石角礫の副葬が,擦文時代後期頃に円礫に転じ,アイヌ文化期へとつながる状況が確認され,黒耀石の副葬様式が漸移的に成立したことが明らかになった。 こうした中で,15C~18C中頃と考えられる南川2遺跡の墓壙以後は黒耀石の副葬がみとめられないことから,擦文時代とアイヌ文化期の間にみとめられる黒耀石の儀器化が生じた後に,さらにアイヌ文化期内において儀器としての役割を終える過程があったことがわかった。ここに,利器としても,儀器としての役割も終える過程,すなわち北海道における黒耀石利用の終焉をよみとることができるのである。
4 0 0 0 OA 食事が血糖値に及ぼす影響 -米飯食とパン食の差-
- 著者
- 内田 あや 大橋 美佳 中村 美保 松田 秀人
- 出版者
- 学校法人滝川学園 名古屋文理大学
- 雑誌
- 名古屋文理大学紀要 (ISSN:13461982)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.33-39, 2008 (Released:2019-07-01)
米飯食は伝統的な日本型食生活の中心であり,日本食は肥満や糖尿病食として推奨されている.米飯食が血糖コントロールの面から良い食品であるかをパン食と比較検討した.被験者は19〜20歳の健常な女性35名で,被験食品(約350kcal)を10分間で摂取させた.空腹時,食後30分,60分,90分,120分の計5回指先より採血し血糖測定器で測定した.その結果,空腹時血糖値は全員110mg/dL未満で耐糖能異常者はいなかった.食後60分,90分,120分の米飯食の血糖値がパン食より有意に高かった.また,体脂肪率30%以上の被験者ではパン食と米飯食間での有意差はなく,30%未満では食後60分,90分,120分の米飯食の血糖値がパン食より有意に高かった.米飯食で比較すると体脂肪30%未満が30%以上に比べて食後30分値が有意に高かったが,パン食では有意差はなかった.体脂肪率30%以上の人には内臓脂肪によるインスリン抵抗性が惹起しているのではないかと考えられる.
4 0 0 0 OA 9.利尿薬を使い分ける
- 著者
- 木村 玄次郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.9, pp.2413-2417, 2013-09-10 (Released:2014-09-10)
- 参考文献数
- 16
4 0 0 0 OA 残留性有機汚染物質による地球規模の環境汚染と高次生物の曝露リスク
- 著者
- 田辺 信介
- 出版者
- 日本毒性学会
- 雑誌
- 日本毒性学会学術年会 第41回日本毒性学会学術年会
- 巻号頁・発行日
- pp.EL7, 2014 (Released:2014-08-26)
化学物質の中でヒトや生態系にとって厄介なものは、毒性が強く、生体内に容易に侵入し、そこに長期間とどまる物質であろう。こうした性質を持つ化学物質の代表に、PCBs(ポリ塩素化ビフェニール)やダイオキシン類などPOPs (Persistent Organic Pollutants:残留性有機汚染物質)と呼ばれる生物蓄積性の有害物質がある。私がPOPsの汚染研究を開始したのは1972年のことで、テーマは「瀬戸内海のPCBs汚染に関する研究」であった。当時の汚染実態はきわめて深刻化していたが、不思議なことに瀬戸内海に残存しているPOPs量は使用量に比べ予想外に少ないことに気がついた。この疑問は、「大気経由でPCBsが広域拡散したのではないか」という仮説を生み、地球汚染を実証する研究へと進展した。この研究の中で、ダイオキシン類やDDTは局在性が強く地域汚染型の物質であるが、PCBsや殺虫剤のHCHsは長距離輸送されやすい地球汚染型の物質であることを、大気や水質の調査だけでなく生物を指標とした研究でも明らかにした。また冷水域は、POPsの最終的な到達点となることを示唆した。さらに、POPsは食物連鎖を通して生物濃縮され高次の生物種ほど汚染が著しいこと、とくに海洋生態系の頂点にいる鯨類や鰭脚類などの水棲生物は、体内にきわめて高い濃度のPOPsを蓄積していることが認められた。この要因として、この種の動物は体内に有害物質の貯蔵庫(皮下脂肪)が存在すること、授乳による母子間移行量が大きいこと、有害物質を分解する酵素系が一部欠落していること、などが判明した。また、薬物代謝酵素等に注目した研究により、海棲哺乳動物はPOPs(親化合物)のリスクが最も高い生物種(ハイリスクアニマル)であること、一方陸棲の哺乳動物はPOPs代謝物のハイリスクアニマルであることを示唆した。以上の研究成果から、生態系本位の環境観・社会観を醸成する施策が必要なことを提言した。
4 0 0 0 OA <論文>中国地下鉄駅名の英語表記―国際化の指標として
- 著者
- 永田 高志 NAGATA Takashi
- 出版者
- 近畿大学文芸学部
- 雑誌
- 文学・芸術・文化 : 近畿大学文芸学部論集 = Bulletin of the School of Literature, Arts and Cultural Studies, Kindai University (ISSN:13445146)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.77-98, 2017-09-30
専門: 日本語学
4 0 0 0 OA 日本の美的概念に関する時代推移とその構成モデル 美的空間創造のための基礎的研究
- 著者
- 髙橋 浩伸
- 出版者
- 一般社団法人 芸術工学会
- 雑誌
- 芸術工学会誌 (ISSN:13423061)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, pp.158-165, 2017 (Released:2019-02-01)
筆者は、これまで美的空間創造のための基礎的研究として、環境心理学のフィールドにおいて「人間-環境モデル」に基づき、建築空間における美的価値観の研究を続けてきたが、現代の建築的テーマとして、“ 地域性” や“ 歴史性” などが重視される中、その地域ならではの風土や文化・思想にあった美的空間を創造するためには、西洋の美とは違う、日本の特徴的な美を理解・把握しなければならないと考えた。 本研究は、筆者のこれまでの既往の研究を補完するものであり、美的空間創造のための基礎的研究と位置付けられ、その根本となるべき日本の美の概要と特徴を知るための研究と言える。具体的な本研究の内容は、国語学における知見を基に、古代から現在までの日本の美的言葉の時間的推移を調査・整理し、その構成モデルを作成することで、建築的視点や既往研究との比較検討を行い、日本の美の概要と特徴を把握することを本研究の目的とする。そのために、まず日本の美に関する言葉に着目し、国語学による知見を基に、古代からの現代においての時間推移と意味・内容の変遷を調査することとした。その結果まず美を表す言葉は、「くわし」→「きよら」→「うつくしい」→「きれい」と移り変わってきたことが理解でき、美的言葉の時代推移が把握できた。また、日本の特徴的な美的言葉に注目してみると、「なまめかしい」「こころにくい」「もののあわれ」「さみしい」など、今日では直接的に美を表現する言葉としては、理解しづらいような言葉が、古の日本人が持っていた、さりげない深い配慮を尊び、決し て誇張しないという奥ゆかしさの美であり、今日の日本人が失いかけている美の言葉として浮かび上がってきた。 また、「うつくしい」や「きれい」などの日本において美一般を表す言葉に関する共通する意味合いとして、清潔さ・明瞭さが見いだせるが、これらは、筆者の既往研究における、インテリア空間に関する現代日本人の美的価値観として多くの人が挙げた『シンプルである』『物が少ない』などと合致し、日本人の美的概念の特徴があらためて確認された。 更に今後は、本研究で明らかにされた「現代の日本人が失いかけている美の言葉」や「現代の日本人に受け継がれている特徴的な美の言葉」における美的言葉に着目し、それを建築的空間に落とし込み、日本人が持つ特徴的な美的概念に応じた、美的空間創造のための基礎研究を続ける予定である。
4 0 0 0 OA 作業遂行の認識の差が改善され協業が可能になったパーキンソン病事例
- 著者
- 田代 徹 津本 要 澤田 辰徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.345-352, 2023-06-15 (Released:2023-06-15)
- 参考文献数
- 17
今回,自己の作業遂行能力を高く認識するパーキンソン病を呈したクライエント(以下,CL)に対してAssessment of Client’s Enablement(以下,ACE)を使用した結果,面接で挙げられた各作業におけるGAPスコアは高く,作業療法士とCL間の作業遂行能力の認識の差が明らかになった.作業遂行の認識のギャップを修正するために作業遂行場面を撮影し,フィードバックとともに協議することでACEのGAPスコアは減少した.このプロセスにより,作業療法士とCLは協業することができた.この実践から作業遂行の認識の差に着目し,作業遂行場面を共有することは,協業の一助となると考える.
- 著者
- 三宅 優紀 岩田 美幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本作業療法士協会
- 雑誌
- 作業療法 (ISSN:02894920)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.341-347, 2020-06-15 (Released:2020-06-15)
- 参考文献数
- 14
特別養護老人ホームに入所中で,生活全般において消極的な女性に対し,園芸活動を用い,作業機能障害の種類に焦点を当てた評価および介入を行った.観察を中心にした評価は,作業機能障害の4種類(作業不均衡,作業剥奪,作業疎外および作業周縁化)に対する必要な介入を明確にできた.その結果,症例は,笑顔が増え,外出するようになり,夜間の睡眠が十分とれるようになるなど,作業機能障害の改善に至り,健康な施設生活を送れるようになった.意味のある作業を同定しがたいクライエントに対して,作業機能障害の種類に焦点を当てた評価および介入は,有効であったと考える.
4 0 0 0 OA 代数的エフェクトハンドラを持つ言語のためのトレースエフェクト
- 著者
- 川俣 楓河 寺内 多智弘
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.2_19-2_48, 2023-04-21 (Released:2023-06-21)
代数的エフェクトとハンドラとは,プログラム中のエフェクトの発生を抽象化してその動作をハンドラで定義するものであり,実装が分離されることでエフェクトを含むプログラムを見通し良く書くことができる.トレースエフェクトとは,プログラムの実行中に生じるイベントの発生順の列を静的に見積もったものであり,プログラムの時間的な性質の検証を可能にする.本論文では,代数的エフェクトハンドラとトレースエフェクトを共に備えることで,代数的エフェクトハンドラのエフェクト実装分離の利便性を享受しつつプログラムの時間的な性質を捉えることのできる型・エフェクトシステムを提案する.また,この体系の型安全性,すなわち正しく型付けされた項の評価は行き詰まらず,かつ型付けで得られたトレースエフェクトはその項の評価で発生し得るエフェクト列を保守的に見積もることを示し,さらにこの体系に対する健全性を満足する型推論を構築する.