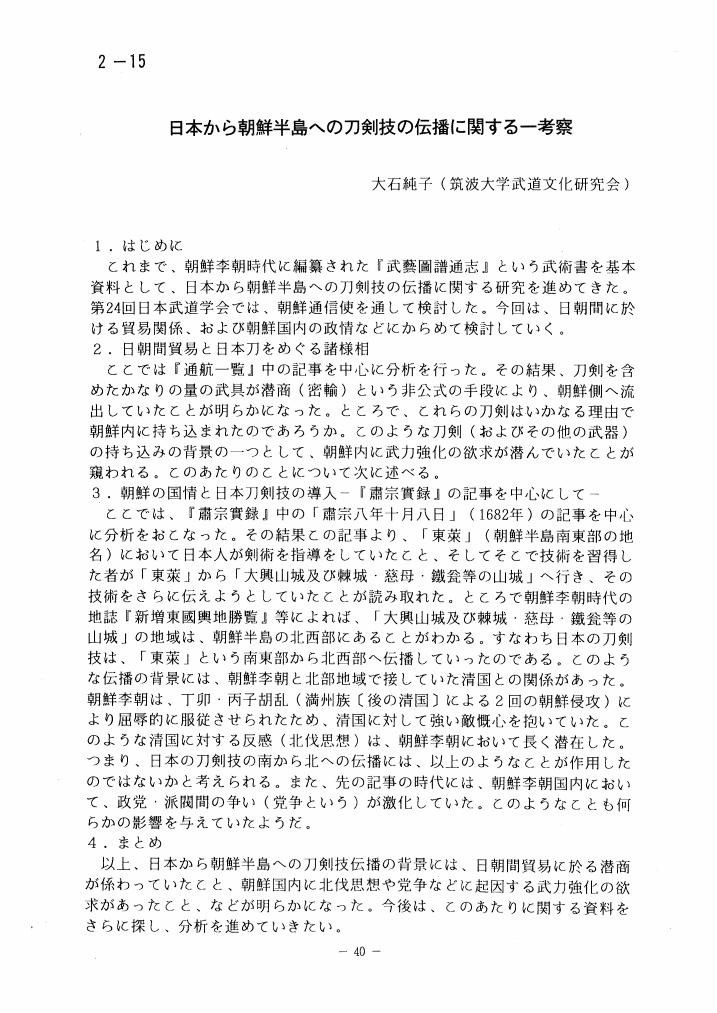4 0 0 0 OA 戦後日本の首相たちと歴史認識
- 著者
- 宇田川 幸大
- 出版者
- 中央大学商学研究会
- 雑誌
- 商学論纂 (ISSN:02867702)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.5-6, pp.1-31, 2023-03-01
- 著者
- Yoav LINDEMANN Gal EYAL Amatzia GENIN
- 出版者
- 日本サンゴ礁学会
- 雑誌
- Galaxea, Journal of Coral Reef Studies (ISSN:18830838)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.9-10, 2019 (Released:2019-10-11)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 3
4 0 0 0 ミノウミウシにおける盗刺胞機構:ミノおよび刺胞嚢の形成
刺胞動物を餌としているミノウミウシ類の一部は、餌由来の刺胞を体内に貯蔵する「盗刺胞」という現象が見られる。この現象は他の生物の細胞内器官を、そのまま取り込み利用するという点で非常に興味深い。本研究では、盗刺胞を行うムカデミノウミウシの組織切片を作成し、各種の分子マーカーを駆使した顕微鏡観察により、盗刺胞に関連する器官の形成過程を詳細に記載し、盗刺胞のメカニズム解明の足がかりを構築する。さらに盗刺胞のメカニズムを明らかにするため、盗刺胞に特殊化した器官のトランスクリプトーム解析を行い 、そこで特異的に高発現している候補遺伝子を同定し、機能解析を行う。
4 0 0 0 OA QED摂動論によるレプトン異常磁気能率の計算(最近の研究から)
- 著者
- 青山 龍美 早川 雅司 木下 東一郎 仁尾 真紀子
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.6, pp.376-380, 2014-06-05 (Released:2019-08-22)
電子やミュー粒子はスピンに伴う磁気能率を持ち,その大きさはボーア磁子を単位としてg因子で表される.g因子はDiracの相対論的量子力学による値g=2から仮想光子の量子効果により0.1%ほどずれ,これを異常磁気能率(g-2)と呼ぶ.電子の異常磁気能率は最も精密に測定されている物理量の一つであり,理論的には量子電気力学(QED)でほぼ説明できることから,高精度理論計算を通じてQEDの精密検証を与えてきた.最新の測定値はハーバード大グループによる円筒形のPenning trapを用いた実験で得られたもので,0.24ppb(ppb=10^<-9>)もの精度に達している.理論計算もそれに見合う精度まで進める必要があり,摂動論に基づく高次項の評価が急務であった.著者らのグループは数値的手法により摂動の10次項の完全な決定を行い,結果として電子g因子について10^<-12>のオーダーまで測定値と理論計算が一致することをみた.この精度までQEDの正しさが検証されたと言える.他方,QEDの理論が正しいとすると,QEDの結合定数である微細構造定数αの値を測定値と理論計算から求めることができる.その値は0.25ppbの精度を持ち,他のどの決定法によるものより精度の高い値である.電磁気的な相互作用は多岐にわたる物理現象に現れることから様々な決定法があり,これらの値が互いに無矛盾であるかは,QEDの正しさを検証するもう一つのアプローチとなる.電子の約207倍の質量を持つレプトンであるミュー粒子の異常磁気能率も0.5ppm(ppm=10^<-6>)の高い精度で測定されている.測定値と,QEDを含む素粒子標準模型からの理論値の間に約3σの差が見つかり,標準模型を超える新物理を探るプローブの一つとして注目されている.そのような議論の前提として,大半を占めるQEDの寄与を高精度に求めることが不可欠である.QED摂動論の10次項の決定と8次項の精度の改良により,QEDからの寄与は現在の測定の不確かさの1/1,000まで求まり,目下準備中の次の実験による測定精度の向上にも十分対応できると言える.理論値で最も不確かさの大きい寄与はハドロンの効果によるもので,標準模型との差を議論する上でこの寄与の精度の向上が現在の主要な課題である.QED摂動論を数値的に行うにあたって,著者らの手法は,中間くりこみの処方を用いて計算の各段階で発散量があらわに現れないようにするものであり,それによって計算機上での数値計算が可能になる.摂動の10次に寄与するファインマン図形は膨大かつ複雑であるが,これを系統的に扱う手法を開発した.著者らが約10年にわたって進めてきたQED摂動論の数値的研究について紹介する.
4 0 0 0 IR 太宰治「葉桜と魔笛」論 : 反転する〈美談〉/姉妹のエクリチュール
- 著者
- 川那邉 依奈 カワナベ ヨリナ Kawanabe Yorina
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 待兼山論叢 (ISSN:03874818)
- 巻号頁・発行日
- no.48, pp.19-37, 2014
4 0 0 0 OA 虚血再灌流障害に対する分子状水素の保護作用
- 著者
- 野田 百美
- 出版者
- 日本脳循環代謝学会
- 雑誌
- 脳循環代謝(日本脳循環代謝学会機関誌) (ISSN:09159401)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.77-81, 2015 (Released:2015-08-07)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 2 1
要旨 脳白質のモデルとして使われているマウス視神経を用い,飲用水中の分子状水素(H2)が虚血による視神経機能障害を改善させるかどうかを検討した.視神経機能の測定には,摘出後,複合活動電位(CAP)の面積を測定した.灌流チャンバーを脱酸素・脱グルコース(OGD)にすると,CAP は速やかに消失し,再灌流後は25%程度しか回復しない.ところが,10~14 日間,H2 水を飲用したマウスの視神経では,CAP が完全に消失することはなく,再灌流後の回復も顕著に改善された.虚血・再灌流後の視神経線維の脱落は,H2 水飲用群で有意に減少しており,グリア細胞(とくにオリゴデンドロサイト)の核8-オキソグアニン(nu8-oxoG:酸化DNA 障害のマーカー)の蓄積は,H2 水飲用群において,有意に抑制されていた.これらの結果は,有髄神経が占める白質の保護にH2 水飲用が有効であることを示唆しており,酸化ストレス耐性と治療の有用性が期待される.
- 著者
- 津野 香奈美 早原 聡子 木村 節子 岡田 康子
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.6, pp.367-379, 2022-11-20 (Released:2022-11-25)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
目的:ハラスメントの雇用管理上の措置が企業に義務付けられているが,企業に義務付けられている対策が実際にハラスメント防止に効果があるのかは検証されていない.そこで本研究では,ハラスメント指針の中でトップのメッセージ発信や研修実施等に着目し,従業員の対策認識度と企業ごとのハラスメント発生割合を比較した.対象と方法:日本国内の某グループ会社計68社(従業員数計約20,000名)を対象とした.ハラスメント対策は7項目,パワーハラスメント(パワハラ)は厚生労働省の6類型を参考に作成した11項目,セクシュアルハラスメント(セクハラ)は7項目,マタニティハラスメント・パタニティハラスメントは2項目,ケアハラスメントとジェンダーハラスメントは各1項目で測定した.組織風土はシビリティ(礼節),心理的安全性,役割の明確さ等の下位概念から成る10項目で測定し,ハラスメント防止対策実施後の従業員や職場の変化は7項目で測定した.ハラスメント防止対策の従業員認知割合並びに組織風土を高群・中群・低群の3群に分け,企業ごとのハラスメントの発生割合や職場の変化認識割合をKruskal-Wallis検定あるいはANOVAで比較した.結果:自社でハラスメント対策として実態把握等のアンケート調査,ポスター掲示や研修の実施,グループ全体の統括相談窓口の設置,コンプライアンス相談窓口の設置を実施していると7割以上の従業員が認識している企業では,認知度が低い企業と比べてパワハラ・セクハラの発生割合が低かった.一方,トップのメッセージ発信,就業規則などによるルール化,自社または中核会社の相談窓口の設置に関しては,従業員認知度によるパワハラ発生割合の差は確認できなかった.組織風土に関しては,シビリティが高い,心理的安全性がある,役割が明確であると8割以上の従業員が認識している企業では,パワハラ・セクハラの発生割合が低かった.また,従業員がハラスメント防止対策の実施状況を認知している割合が高い企業ほど,従業員が自身や周囲・職場の変化を実感している割合が高かった.考察と結論:各ハラスメント防止対策を実施していると多くの従業員が認識している企業では,ハラスメント発生割合も低い傾向にあった.心理的に安全である・役割が明確であると多くの従業員が回答した企業ではハラスメント発生割合が低かったことから,ハラスメント防止には組織風土に着目した対策も有効である可能性が示唆された.
4 0 0 0 OA arXivに着目したプレプリントの分析
- 著者
- 林 和弘 小柴 等 科学技術・学術政策研究所
- 出版者
- 科学技術・学術政策研究所
- 雑誌
- DISCUSSION PAPER
- 巻号頁・発行日
- vol.187,
- 著者
- Ali A. Thabet Anwar A. Ebid Mohamed E. El-Boshy Afnan O Almuwallad Elham A Hudaimoor Fatimah E Alsaeedi Rahaf H. Alsubhi Rahaf H. Almatrook Rawan F. Aljifry Saja H. Alotaibi Shuroq M. Almallawi Wejdan O. Abdulmuttalib
- 出版者
- The Society of Physical Therapy Science
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.9, pp.695-699, 2021 (Released:2021-09-01)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 6
[Purpose] To determine the effect of pulsed high intensity laser therapy (HILT) versus low level laser therapy (LLLT) in the treatment of primary dysmenorrhea. [Participants and Methods] This was a randomized clinical trial that included 30 females diagnosed with primary dysmenorrhea who were assigned randomly into two groups of equal numbers. The treatment was three sessions every cycle for three consecutive cycles, where group (A) received pulsed HILT and group (B) received LLLT. All participants were evaluated before and after treatment sessions by visual analogue scale (VAS) and at the end of treatment by pain relief scale (PRS). [Results] The results showed a significant decrease in the severity of pain in the two groups. Comparison between the two groups showed a statistically non-significant difference in the severity of pain and pain alleviation at the end of the treatment course. [Conclusion] Both pulsed HILT and LLLT are effective in the treatment of primary dysmenorrhea, with no significant differences between the two modalities.
- 著者
- 戸梶 民夫
- 出版者
- SHAKAIGAKU KENKYUKAI
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.69-85,178, 2009
The purpose of this paper is to clarify the aspect of the "Resolution of Shame" that Transgender individuals acquire through body transformation, in contrast to the concept of performativity in Queer Studies. In the 1980s, the body transformation of Transpeople changed its meaning from non-subjective subordination in the Institution of Patriarchyto queering "Subordination-Subjectivation" to the norm. However, in the mid-1990s, the equation of body transformation to the performativity of the Queer theory was strongly criticized by Transpeople and in transgender studies. In this criticism, two positions were taken. One position emphasized the restraint of the body transformative practice in an ontological context. The other position said that the body transformative practice could not be reduced to the construction of identity and a gender stereotype, and that it intended to have feelings of "Safety" and "Belonging." This position also showed that the body transformative practice of Transpeople includes two kinds of Performativity (identification and assimilation). By reading the trans-embodiment analysis by Jay Prosser (a theorist in transgender studies who represents the latter position) making use of the theoretical frame of Eve K. Sedgwick's "Absorption Performativity/Theatrical Performativity," this paper strives to show that there is a positifying of the goal of Safety and Belonging in the bodily transformation of Transpeople and this positifying is accomplished by a theatrical performativity distantiating shameful bodily parts.
4 0 0 0 OA 日本から朝鮮半島への刀剣技の伝播に関する一考察
- 著者
- 大石 純子
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.Supplement, pp.40, 1992 (Released:2012-11-27)
4 0 0 0 IR 風の祭祀の由来と変容
- 著者
- 田上 善夫
- 出版者
- 富山大学人間発達科学部
- 雑誌
- 富山大学人間発達科学部紀要 (ISSN:1881316X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.169-194, 2010
本論では,風の祭祀にかんして,まず現在の実態を明らかにする。とくに風の祭祀の分布密度の高い,信越地方とその周辺を例として,特色のある民間行事をとりあげる。こうした風の祭祀について,とくに以下の3点から分析を加える。まず共通点の多い,信州とくに諏訪周辺の風の祭祀からの分析である。次に記紀に始まる古文献にみられる風の祭祀からの分析である。さらに風の三郎とかかわりの深い,全国に進出した諏訪信仰からの分析である。最後にこれらの分析に基づいて,風の祭祀にみられる風の観念について,検討を試みる。
- 著者
- 正岡 美麻 坂口 菊恵 長谷川 寿一
- 出版者
- 日本性教育協会
- 雑誌
- 日本=性研究会議会報
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.12-18, 2009-11
4 0 0 0 遊戯の崩壊--三島由紀夫『禁色』論
- 著者
- 柴田 勝二
- 出版者
- 花書院
- 雑誌
- 敍説 (ISSN:13437542)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.72-79, 1995-11
4 0 0 0 OA 自己免疫性疾患と季節の関連
- 著者
- 小倉 剛久 亀田 秀人
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.25-32, 2014 (Released:2014-03-05)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1 1
関節リウマチや全身性エリテマトーデスなどに代表される自己免疫性疾患の発症,増悪と季節の関連が報告されている.季節性の特徴は各々の疾患,報告によって異なるが,日光(紫外線)や感染の関与など病態における環境因子を推測する上で重要な要素となり得る.近年ではビタミンDと疾患の関連や,同一疾患における自己抗体による病因の違いなどの報告も認められている.
4 0 0 0 OA 〈社会的な死〉を刻印された者たちへ 桐野夏生『グロテスク』における追悼のゴシップ
- 著者
- 駒居 幸
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.81-101, 2018 (Released:2019-10-09)
- 参考文献数
- 34
1997 年に発生した東電OL 殺人事件は、東京電力で総合職を勤める被害者が夜には売春婦 として客引きをしていたことが明らかになると、一気に報道が過熱した。週刊誌を中心に 行われた被害者の私生活を暴くような報道は、売春婦が規範的な市民から疎外され、それ 故にその死が嘆かれえないことを示している。本論では、こうした売春婦の死を悲嘆し追 悼する作品として、桐野夏生『グロテスク』(2003)を取り上げる。 東電OL 殺人事件をモチーフに書かれた本作では、二人の売春婦が殺害される。本論では、 二人の姉であり、同級生である語り手の「わたし」の語りに着目をする。「わたし」は売春 婦の悪口=ゴシップを言いながらも、最終的には彼女たちの「弔い合戦」を行う。こうし た弔いはどのようにして可能になるのか。本作には、客観的なゴシップの「語り手」であ ろうとしていた「わたし」が、徐々に「語られる対象」としての「わたし」に一致して行 く過程が描かれている。本論は、この過程の中に「わたし」のメランコリーを読み込み、「わ たし」のゴシップが彼女たちの喪失を回避し、自らの内側に引き込むための儀式として機 能していること、そして、そうした儀式こそが売春婦の死の追悼を可能にしていることを 指摘する。
4 0 0 0 OA 霧島国際音楽祭の誕生と成長 : 産・官・民の地域イベントの参加
- 著者
- 定藤 博子 サダトウ ヒロコ Hiroko Sadato
- 出版者
- 鹿児島国際大学附置地域総合研究所
- 雑誌
- 地域総合研究 = Regional studies (ISSN:09142355)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.55-65, 2019-03-30
Kirishima International Music Festival was founded under the name of "Kirishima International Music Festival / Master courses" in 1980. There were 3 aims, rising the cultural level in Kagoshima, rising the educational level of Japanese artists and the tourism resources development of Kagosima. Sharing these purposes, the people in Kagoshima, especially in Kirishima, support this festival, the foundation makes the programs and the local government offers the financial support. The inhabitants, the business and the government, these 3 elements certify the authenticity. This is why this festival has continued for 40 years.