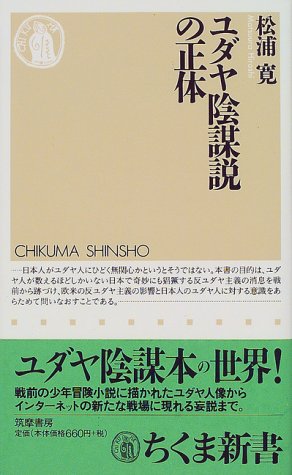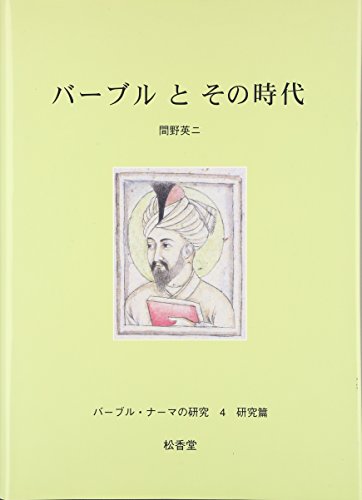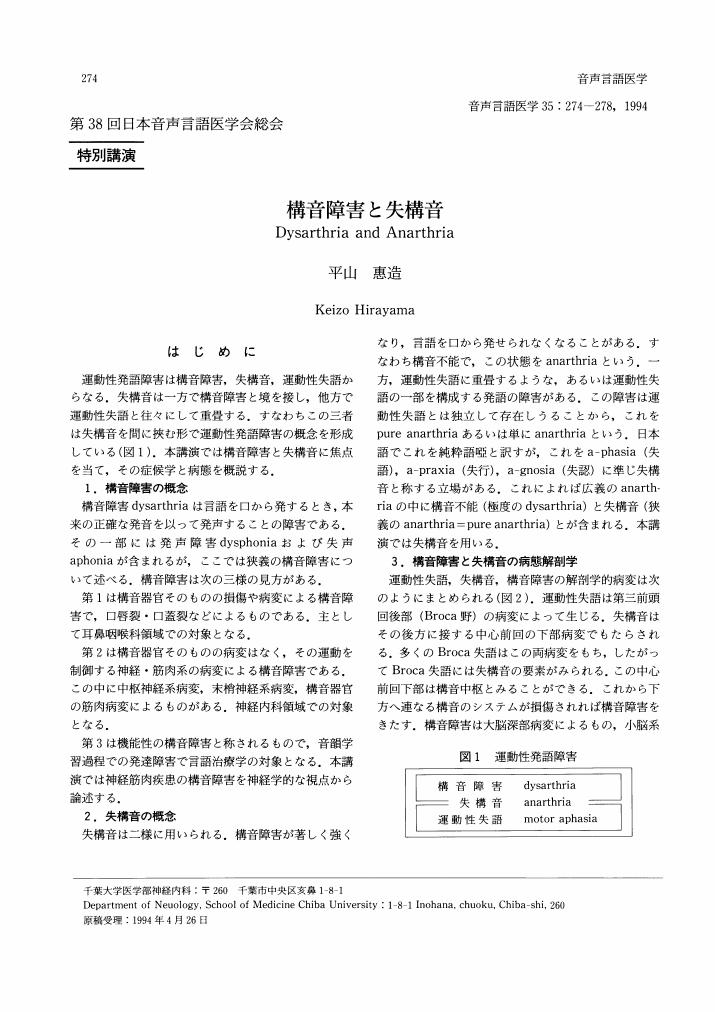3 0 0 0 OA 日本で見られる様々なイタチムシ(2012年度日本動物分類学会シンポジウム)
- 著者
- 鈴木 隆仁
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.11-17, 2013-02-28 (Released:2018-03-30)
- 参考文献数
- 19
Chaetonotids (Gastrotricha) are small 60-400μm in length, inhabit both the freshwater and marine environments. Their bodies are tenpin- or bottle- like shaped; flattened ventrally and arched dorsally. The sensory organs, brain, and pharynx are located in the anterior head. Posteriorly, a "furca" bears the adhesive organ. The locomotory cilia are restricted to the ventral surface, forming a pair of ciliary bands. The body wall is usually composed of the external cuticle of a flexible proteinous layer. In some gastrotrichs, the basal layer is locally thickened and specialized to form scales, spines, and hooks. The cuticular scales vary in arrangement and shape, depending on the species. The most common species are freshwater chaetonotid species that inhabit ponds, swamp, streams, and lakes. In these species male is entirely absent, thus the most chaetotonids reproduce by parthenogenesis. About 700 species of chaetonotids have been reported so far around the world. In Japan, 34 species were recorded from lakes, ponds, and swamps. Recently, 44 species have been found in the rice paddies. In this paper the natural history and diversity of chaetonotids are reviewed.
3 0 0 0 OA 文献学/Philologieをとらえ直す
- 著者
- 竹村 信治
- 出版者
- 中世文学会
- 雑誌
- 中世文学 (ISSN:05782376)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.11-20, 2021 (Released:2022-06-22)
3 0 0 0 OA Cetuximab 投与後に生じる低マグネシウム血症の発現頻度と発現時期の調査とその対策
- 著者
- 中本 恵理 川上 和宜 今田 洋司 式部 さあ里 杉田 一男 篠崎 英司 末永 光邦 松阪 諭 水沼 信之 濱 敏弘
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.403-409, 2011 (Released:2012-08-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 3
Cetuximab, a therapeutic agent for metastatic colorectal cancer, is a chimeric monoclonal antibody that binds and inhibits the epidermal growth factor receptor (EGFR). Adverse events associated with cetuximab include skin disorders, which occur at a high incidence, infusion reactions, and electrolyte disorders, such as hypomagnesemia. The incidence and time of onset of hypomagnesemia following the start of cetuximab treatment were investigated retrospectively. The efficacy of oral magnesium preparations in preventing hypomagnesemia was also examined.At The Cancer Institute Hospital of Japanese Foundation For Cancer Research, the incidence of hypomagnesemia in patients treated with cetuximab was 39.3%. However, there was no clear trend in the time of onset. In addition, there was no difference in the incidence of hypomagnesemia as a function of whether oral magnesium preparations were administered (p=0.097). Some patients developed severe hypomagnesemia and an intravenous magnesium preparation was not very effective in bringing about recovery, necessitating discontinuation of cetuximab therapy.Mild hypomagnesemia may be overlooked because subjective symptoms are not readily apparent. However, if it worsens, hypomagnesemia may lead to serious adverse events, such as arrhythmias, which would require discontinuation of cetuximab treatment. In pa tients receiving cetuximab, therefore, serum magnesium levels must be monitored regularly since early detection and treatment of hypomagnesemia are very important.
3 0 0 0 OA オルバースのパラドックスについて
- 著者
- 吉岡 一男 Kazuo Yoshioka
- 雑誌
- 放送大学研究年報 = Journal of the University of the Air (ISSN:09114505)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.107-120, 2000-03-31
夜空が何故暗いか? という疑問が17世紀に指摘されて以来,一部の天文学者を悩ましていた.それは,恒星が宇宙空間に無限に広がって輝いているならば夜空が昼間よりもはるかに明るいことになる,という現実とは異なる結論が導かれるからである.これをオルバースのパラドックスという.それを回避するために,宇宙有限説,孤立宇宙説,無限階前説,吸収説など様々な説が唱えられた.しかし,いずれの説も成り立たないことがわかった. 現在,ハッブルの法則に従う宇宙の膨張によりこのパラドックスが回避されると考えられている.すなわち,宇宙の膨張から帰結される宇宙年齢の有限性と宇宙の膨張に伴う膨張効果(ドップラー効果と希釈効果)によりパラドックスは回避される. しかし,通俗書に書かれているパラドックスの記述には,歴史の記述が不正確であったり,パラドックスの回避の説の記述が誤解を招いたり誤っている本が見られる.また,宇宙年齢の有限性の効果の方が膨張効果よりも圧倒的に効くのにその記述も見られない. 一方,宇宙の膨張を持ち出さなくても恒星の寿命が有限で空間密度が低いことでパラドックスを回避できる,と考えることもできるが,その場合も現在恒星が輝いていることの自然な説明を宇宙の膨張が与えることを指摘した.また,パラドックスが認識されるためには,背景となる理論が確立されている必要のあることも指摘した.
3 0 0 0 OA 大手不動産資本によるオフィス空間の形成
- 著者
- 松原 宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.7, pp.455-476, 1984-07-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 1
本稿では,大手不動産資本によるオフィス形成の特徴や役割を明らかにするため,オフィスビルの配置,テナントの特徴,都市形成への影響の3点について検討を行なった. 先発で東京都心部に大量の土地を所有する三菱地所は,丸の内に一点集中的にビルを配置させ,オフィス街を形成してきた.これに対し,三井不動産は所有地の少なさを超高層ビルによる点的開発で補い,オフィス空間の拡大を図った.そして両社とも,おのおののグループ企業の本社・支所の拠点を形成してきた.一方,後発の日本生命は,地方中核都市などに分散的にビルを配置させ,急成長で多事業所を必要とする企業に空間を提供した.また,森ビルは港区虎ノ門周辺で,戦前からの所有地を基盤に,住宅・商店と混在するかたちでビルを建設し,対事業所サービス関連企業を主なテナントとしてきた. このように,系列,参入時期,土地所有によりオフィス空間の形成はさまざまであるが,大手不動産資本は,オフィスのより一層の集積を可能にし,あわせて都心形成を特徴的におしすすめてきたのである.
- 著者
- 鈴田 泰子 小野 治子 宍戸 祐子 髙屋 隆男
- 出版者
- 東北福祉大学教育・教職センター特別支援教育研究室
- 雑誌
- 東北福祉大学教育・教職センター特別支援教育研究年報 (ISSN:21850275)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.25-34, 2020-03-31
発達障がいのある子どもを育てる親たちは、子育ての不安や悩みを長期間にわたり抱え続けなければならない場合がある。本稿では、親たちによる語り合いの場が持たれるまでの経緯と、そうした場が必要とされる理由やその効果を明らかにするための手がかりを記録した。また、低年齢の子どもを育てる母親たちと、思春期・青年期を迎えた子どもを持つ母親たちがともに集って語り合い、励ましと希望をもって交歓する「語ろう会」の意味について考察した。
3 0 0 0 IR イタリア刑法における企業犯罪の法的規制
- 著者
- 吉中 信人
- 出版者
- 広島大学法学会
- 雑誌
- 広島法学 (ISSN:03865010)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.192-174, 2011-01
3 0 0 0 OA 学習済みプログラムのパラメータを物の発明として把握できるのか
- 著者
- 松下 正
- 出版者
- 日本弁理士会
- 雑誌
- 別冊パテント (ISSN:24365858)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.27, pp.1-14, 2022 (Released:2022-11-24)
膨大なデータの収集や管理が可能になったことから,画像認識や予測ができるAI 学習用プログラムの提供が実用的になりつつある。かかるプログラムも自然法則を利用する限り,従来のコンピュータプログラムと同様に特許の保護対象となる。 ここで,AI 学習用プログラムは,通常のプログラムと異なり,本質は,そのパラメータにある。にもかかわらず,かかるパラメータ(データの集合物)の特許法による保護について,特許制度小委員会報告書案では,前記パラメータは法上の「物」に該当するのか疑義があるため,当該パラメータをネット配信等する行為を侵害とできない問題点について指摘がなされているものの保護すべきか否かについては言及がなされていない。 本稿では,前記パラメータを,特定の処理を行うプログラムを構築するための専用部品,すなわち,「プログラムの部品」として,「物」の発明に該当すると解釈できないかについて検討する。
3 0 0 0 OA リフレクションを中心とした経験学習支援―マネジャーによる部下育成行動の質的分析―
- 著者
- 永田 正樹
- 出版者
- 日本労務学会
- 雑誌
- 日本労務学会誌 (ISSN:18813828)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.4-19, 2021-06-01 (Released:2021-09-10)
- 参考文献数
- 27
In models of reflection in previous research, individual reflection processes have been considered, yet methods to support reflection and encourage learning among subordinates have not been examined. On the contrary, in manager coaching research, coaching behavior for reflection support has been examined, but the process of reflection support has not been clarified. To address these gaps, this paper aims to examine the research question, “What is the process by which a manager supports experiential learning centered on reflection to encourage the growth of his subordinates?”. Interviews of 17 managers who possessed advanced subordinate skills were conducted, and the process of experiential learning support centered on reflection was qualitatively analyzed using the grounded theory approach. The results show that experiential learning assistance consists of “preparing growth assistance,” “assigning work,” and “assisting with reflection.” In the “preparing growth assistance” , managers collaborate with mid-level employees and strive to build teams that encourage free dialogue and cooperation among members in order to psychologically reassure their subordinates. In addition, to prepare for assigning challenging works to subordinates, managers carefully observe their subordinates and gain an understanding of their career visions, characteristics, and strengths. In the “assigning work” , managers provide their subordinates with stretch experiences, which is necessary to encourage them to reflect. When doing so, they express the meaning of and expectations for the work and provide concrete guidance to improve their subordinates’ acceptance for working on the stretch assignments. In the “assisting with reflection” , managers check the facts about the experience of their subordinates strove towards and assist them in analyzing the operations. Then, they distill lessons from what they learned. This paper contributes to the existing literature by identifying the process of reflection-based experiential learning assistance, which has been insufficiently examined so far, from the viewpoint of preparing growth assistance, ensuring psychological safety, and assigning work.
3 0 0 0 OA 低温調理による野生鹿肉及び猪肉での中心温度挙動と細菌不活化効果に関する検討
- 著者
- 山本 詩織 秋元 真一郎 迫井 千晶 山田 研 壁谷 英則 杉山 広 髙井 伸二 前田 健 朝倉 宏
- 出版者
- 日本食品微生物学会
- 雑誌
- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.77-82, 2022-06-30 (Released:2022-07-07)
- 参考文献数
- 24
This study examined the thermal kinetics in wild deer and wild boar meats by low temperature cooking process as well as its bactericidal effect. The thermal processing so as to heat the inner-core of the samples at 65℃ for 15 min, 68℃ for 5 min, 75℃ for 1 min in steam convection oven exhibited faster elevation rate of the internal temperature of wild deer meat than wild boar meat, while their sterilization values after the thermal processes were estimated to be almost equal. Naturally contaminated fecal indicator bacteria were not recovered from all samples after the above-mentioned processing. Spike experiment resulted that approximately 6.6–7.8 log CFU/g of STEC O157 and/or Salmonella spp. were not recovered from the wild deer meats after the three types of thermal cooking. Thus, these data indicated aptitude of these low temperature cooking conditions to minimize the microbiological risks in the game meat.
3 0 0 0 OA 東京都心における視程の変化
- 著者
- 川端 康弘 梶野 瑞王 財前 祐二 足立 光司 田中 泰宙 清野 直子
- 出版者
- 公益社団法人 日本気象学会
- 雑誌
- 天気 (ISSN:05460921)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.5-12, 2021 (Released:2021-02-28)
- 参考文献数
- 53
Visibility is important information not only for meteorological analysis but also for operations of transport and monitoring air pollution. In this study, climatological features of visibility in the Tokyo urban area are investigated. The number of days with low visibility decreases year by year. The factors can be drying in urban areas and the improvement of air quality, and the reduction of suspended particle matters contributes more to improve the visibility than the relative humidity. The visibility shows seasonal changes; during summer, visibility decreases when photochemical smog is likely to occur, whereas the visibility increases in winter. Visibility in Tokyo can be largely affected by anthropogenic hygroscopic aerosols, which decrease visibility when relative humidity is high.
- 著者
- 志立 正知
- 出版者
- 説話文学会
- 雑誌
- 説話文学研究 (ISSN:02886707)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.129-136, 2009-07
- 著者
- Liqin Sun Jiaye Liu Fang Zhao Jun Chen Hongzhou Lu
- 出版者
- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement
- 雑誌
- BioScience Trends (ISSN:18817815)
- 巻号頁・発行日
- pp.2023.01009, (Released:2023-01-22)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
The tendency of the Omicron variant to rapidly became the dominant SARS-CoV-2 strain and its weaker virulence than other strains worldwide has prompted many countries to adjust their public health strategies. This work summarizes all appropriate clinical interventions to reduce the public health burden caused by COVID-19 according to guidelines from the World Health Organization and 10 countries, i.e., the United States of America (USA), India, France, Germany, Brazil, South Korea, Japan, Italy, the United Kingdom (UK), and China. Five stages of COVID-19 were identified: asymptomatic infection and mild, moderate, severe, and critical illness. Most guidelines recommend antivirals starting with mild cases for those from Germany and India. Since more drugs are being developed and are becoming available to COVID-19 patients, guidelines are increasingly being updated with new pharmacological intervention strategies. Thus, a global view needs to be adopted to provide helpful options and precise treatment strategies during the lasting fight against the COVID-19 pandemic.
3 0 0 0 OA コイン型リチウム電池によるイヌの食道壊死に対する黒鉛生食懸濁液による緊急処置効果
- 著者
- 武田 光志 荒井 裕一朗 長井 友子 安原 一 山下 衛
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.12-21, 2006-02-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 17
乳幼児がボタン型アルカリ電池やコイン型リチウム電池を誤飲する事故がしばしば発生する.その電池が消化管に停滞し, 消化管壊死を起す.その原因は電池が接触する組織の消化管分泌液や電解質液に電気が流れ, 電気分解が起こり水酸化ナトリウム等のアルカリが生成される.単位時間に流れる電気容量に比例し, アルカリの量は生成するため, 電池の電圧を低下させることが消化管壊死の程度を軽減すると考えた.電池を伝導性に富む素材でショートさせると, 電圧が低下することに着目し, イヌの食道にコイン型リチウム電池を留置し伝導性に富む黒鉛を用いて食道壊死の程度を検討した.6頭の犬を食道に電池を留置した群 (電池留置群, n=3) と留置した電池の周囲に5%黒鉛生食懸濁液を注入した群 (黒鉛処置群, n=3) に分けた.黒鉛処置群はさらに電池の挿入と同時に5%黒鉛生食懸濁液を注入した場合 (n=1) と電池挿入後1分後に5%黒鉛生食懸濁液を注入した場合 (n=2) とし, それぞれ電池留置60分後に食道組織を肉眼的および顕微鏡学的に観察した.電池留置群は肉眼的に, 電池との接触部分で組織の炭化が観察された.顕微鏡学的所見としては粘膜上皮から筋層深部の外縦筋層に至るまでに変性壊死が認められた.黒鉛処置群のうち電池の留置と同時に5%黒鉛生食懸濁液を注人した場合は, 肉眼的には電池外周部と接した組織の一部に充血が見られた.それ以外の部分に色調の変化は認められなかった.顕微鏡的所見では粘膜上皮から外縦筋層までに変性壊死は認められなかった.電池留置1分後に5%黒鉛生食懸濁液を注入し場合は, 電池の外周部が接触した組織で部分的に糜爛と潰瘍が肉眼的に観察された.顕微鏡学的には電池外周部が接触した組織では粘膜の消失が観察された.粘膜から筋層まで変性が見られたが電池留置群に比し, その程度は軽度であった.以上のことから, 5%黒鉛生食懸濁液を電池の周囲に注入し電池をショートさせると, 電池による食道壊死に対して組織保護効果があることが明らかとなった.ボタン型アルカリ電池やコイン型リチウム電池の誤飲時に起こる食道組織の壊死に対し, 黒鉛粉末懸濁液の投与が電池を除去するまでの対処法として有効な手段であることが示唆された.
3 0 0 0 OA コウモリのグアノを摂食するチョウ目昆虫の日本からの発見
- 著者
- 那須 義次 枝恵 太郎 富沢 章 佐藤 顕義 勝田 節子
- 出版者
- 一般社団法人 日本昆虫学会
- 雑誌
- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.77-85, 2016-07-05 (Released:2019-04-25)
- 参考文献数
- 31
日本で初めてコウモリのグアノを摂食するチョウ目ヒロズコガ科の3種,アトウスキヒロズコガMonopis crocicapitella,スカシトビイロヒロズコガ(新称)Crypsithyrodes concolorellaとウスグロイガNiditinea tugurialis,およびメイガ科の1種,カシノシマメイガPyralis farinalis,が記録された.アトウスキヒロズコガは越野(2001)によりMonopis sp.とされていたもので,今回学名が判明した.本種はキチン食性が強いと考えられた.スカシトビイロヒロズコガは日本新記録種であった.今回の調査においてケラチン食性が強いと考えられる種がコウモリのグアノから発生しなかったのは,グアノがコウモリの餌である昆虫の細破片からなり,主にキチン質であるためと考えられた.また,グアノから発生するヒロズコガ類の個体数が比較的多かったことから,グアノの分解者としてヒロズコガ類は重要であることが推測された.
3 0 0 0 OA 構音障害と失構音
- 著者
- 平山 惠造
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.274-278, 1994-07-20 (Released:2010-06-22)
- 被引用文献数
- 1 1
3 0 0 0 OA 「親学」についての一考察(1)
- 著者
- 高橋 史朗
- 出版者
- 明星大学教育学研究室
- 雑誌
- 明星大学教育学研究紀要 = Bulletin of science of education, Meisei University (ISSN:1346664X)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.95-109, 2006-03-20
3 0 0 0 OA 著明な肝逸脱酵素上昇を来たした神経性食思不振症の1例
- 著者
- 澁木 太郎 川副 広明 水田 敏彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.647-652, 2018-11-20 (Released:2018-11-28)
- 参考文献数
- 19
症例は32歳女性.30歳時(50 kg)から姑へのストレスにより体重減少が出現.32歳時には26 kgまで低下し体動困難となったため当院内科に紹介.常食1000 kcal/日で食事を開始しほぼ全量摂取できていたが,ASTは178 IU/l(第1病日),311 IU/l(第7病日)と上昇.Refeeding症候群による肝機能異常と考え摂取カロリーを500 kcal/日に制限したところ,その4日後に急激な肝機能増悪を認めた.少量の糖質を含む輸液を行ったところ肝逸脱酵素は急速に改善したが,血清K,P値の急速な低下があり適宜補充した.その後,肝逸脱酵素,PT%,電解質は全て正常化し他院精神科へ転院となった.近年,神経性食思不振症に伴う肝機能異常の原因としてautophagyが注目されている.本症例の経過をふまえて神経性食思不振症における肝逸脱酵素上昇の機序に関して考察した.