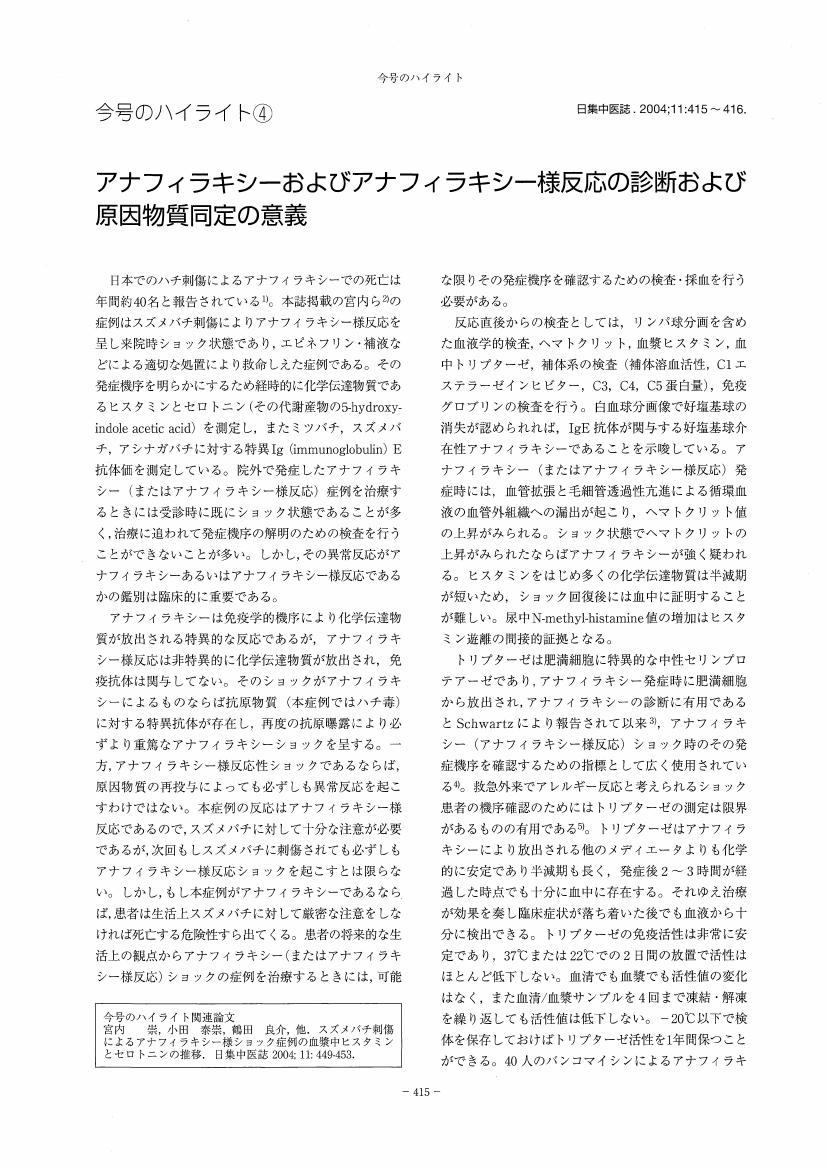- 著者
- 佐々木 宏
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, pp.113-136, 2014
現代福祉国家を構成する生活関連の諸施策(本稿では一括して「社会福祉」と呼ぶ)とそれにまつわる知は,学校教育,医療,司法の営みと同じく,20世紀後半にモダニズム批判として登場したポストモダニズムの諸論から「近代の抑圧的統治の装置」として,しばしば批判されてきた。本稿では,ポストモダニズムからの批判に対し,社会福祉政策とソーシャルワークにかんする諸理論がどのように応答してきたのかを整理した。この作業のねらいの一つは,ポストモダン以降の社会理論の可能性を検討することである。と同時に,日本社会において近年ますますその存在感を増している社会福祉という営みの内省の試みでもある。このような目的をおき,まずは,ポストモダニズムによる社会福祉批判を概観した。次いで,社会福祉からの応答を,社会福祉学の中核の動向と社会福祉という営みを哲学的に下支えする規範理論の動向に分けて整理した。これらの作業を通じては,ポストモダニズムからの批判に対する様々な応答のなかで,民主的対話の実現によって社会福祉の営みと知を常にオープンエンドにし続けておくという,「参加」を鍵概念とする応答が最も建設的であることが浮き彫りとなった。この点を確認した上で,「参加」を鍵概念とする応答が示唆している,後期近代における人間と社会をめぐる思考が錨を下ろすべき場の所在を,ポストモダン以降の社会理論の可能性として指摘した。
3 0 0 0 OA 科学における認知的価値と社会的価値
- 著者
- 横山 輝雄
- 出版者
- 科学・技術研究会
- 雑誌
- 科学・技術研究 (ISSN:21864942)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.37-41, 2022 (Released:2022-06-28)
科学と社会の関係が変化し、科学者は自分の専門領域で研究を進めるだけでなく、社会に対して積極的にかかわることが求められるようになり、「科学者の社会的責任」についても新たな視点が求められている。「科学と価値」の問題について科学哲学でなされてきた「認知的価値」と「社会的価値」についての議論,とりわけクーンやラウダンのそれを、科学技術社会論における、ラベッツの「ポスト・ノーマル・サイエンス」や、コリンズの「科学論の第三の波」の議論と関連させて、科学と社会の関係におけるタイプの違いを区別する必要がある。「不定性」がある場合、科学においても参加型が求められ非専門家の関与がなされるが、その場合社会的価値と認知的価値を区別し、専門家の暗黙知の役割に配慮することが必要である。
3 0 0 0 OA アナフィラキシーおよびアナフィラキシー様反応の診断および原因物質同定の意義
- 著者
- 光畑 裕正
- 出版者
- The Japanese Society of Intensive Care Medicine
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.415-416, 2004-10-01 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 13
3 0 0 0 OA 羽黒修験の中世史研究 : 新発見の中世史料を中心に
- 著者
- 松尾 剛次
- 出版者
- 山形大学大学院社会文化システム研究科
- 雑誌
- 山形大学大学院社会文化システム研究科紀要 = Bulletin of Graduate School of Social & Cultural Systems at Yamagata University
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.256-246, 2005-03-31
羽黒山といえば、月山・羽黒山・湯殿山とともに出羽三山を構成する修験の山として知られている。すなわち、山岳修験の霊場としてイメージされる。こうしたイメージは、戸川安章・岩鼻通明氏らによる近世を中心とした民俗学的・地理学的成果によって形成されてきた。他方、伊藤清郎氏らの歴史学的研究は、八宗兼学の地方有力学問寺院としての姿に光を当てた。ようするに、羽黒山寂光寺は、一方では修験の寺として、他方は、僧位・僧官を有する官僧の住む学問寺としての羽黒山に注目している。前者は近世に、後者は古代・中世に注目した結果といえる。いずれの指摘も、それぞれに説得力あるもので、示唆にとんでいるが、本稿では、中世の羽黒山に注目することで、両者を止揚する新たな像を提示したい。より言うなら、有力官僧寺院から(近世においても、その性格を完全に失うわけではないが)、どのようにして修験の寺に性格を変化させていったのか、見てみよう。しかし、羽黒山の中世史は、なぞに包まれている。それは残存する史料が極端に少ないことによる。だが、そのことは、奥州・出羽・佐渡・越後・信濃は羽黒権現の敷地といわれ、「西二十四ヶ国は紀州熊野三所権現の、九州九ヶ国は彦山権現の、東三十三ヶ国は羽黒山権現の領地だ」といわれた羽黒山の中世史が貧弱であったことを意味してはいない。たとえば、承元三(一二〇九)年に、羽黒山の僧侶たちが大泉庄地頭大泉氏平を所領「千八百枚」を押領し、羽黒山内の事に介入したとして鎌倉幕府に訴え、幕府も羽黒山の言い分を認めたことはよく知られている。一枚を一町とすれば千八百町の所領を有する地方の巨大寺院であった。また、『太平記』に見られる雲景未来記の作者雲景は羽黒の山伏であった。このように、中世の羽黒山はその存在を日本中に知られていたのである。そこで本稿では、中世の羽黒山の実態に迫ることを主眼とする。けれども、やはり資料の少なさは遺憾ともしがたい。しかし、幸いにも今回、以下のような注目すべき二点の新資料を見いだすことができたので、それらを紹介しつつ中世の羽黒山の実態に迫ろう。
- 著者
- 山田 壮志郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.17-29, 2008
本稿の目的は,ホームレス自立支援センターにおける支援記録の分析を通じて,ホームレス対策の課題を考察することである.近年のホームレス対策は,自立支援センターにおいて就労支援を行い,ホームレスの就労による自立を実現することを主要な目標としている.しかし,自立支援センターには,就労可能性が高く就労支援を特段必要としていないようにみえる層から,自立支援センターへの入所が適切でないと思われる層まで,多様な人々が入所しており,結果として目的の実現可能性に差異を生じさせている.また,劣悪な雇用環境やセンターでの集団生活,利用期限の設定といった問題も,入所者の就労による自立を困難にさせている.今後のホームレス対策は,ハウジング・ファースト・アプローチも視野に入れた居住場所の確保を前提に,自立を阻害する環境的な要因を取り除き,就労に偏らない多様な自立を容認しうる複線的なアプローチから形成される必要がある.
3 0 0 0 OA 「竹取物語」の潜勢力 : <始まりの>様式
- 著者
- 谷口 卓久
- 出版者
- 北海道教育大学
- 雑誌
- 札幌国語研究 (ISSN:13426869)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.59-68, 1999
3 0 0 0 OA ジローラモ・ルシェッリ校訂の『デカメロン』
- 著者
- 深草 真由子
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.71-91, 2011-10-15
Girolamo Ruscelli, poligrafo viterbese, senza dubbio risentendo dell'influenza del Bembo, si occupo della redazione del capolavoro del Boccaccio. La sua edizione del Decameron fu pubblicata nel 1552 a Venezia presso la tipografia di Vincenzo Valgrisio, corredata della dedicatoria Ai lettori, di note marginali, delle Annotationi aggiunte alla fine di ogni giornata (in cui si spiegavano le norme linguistiche e grammaticali) e del Vocabolario generale. Essa fu poi ristampata net 1554 e net 1557. Nel corso della polemica con Lodovico Dolce, che pubblico il suo Decameron presso Giolito net 1552 e tento di screditare l'edizione di Ruscelli che era ancora in corso di stampa, Ruscelli scrisse nel 1553 Tre discorsi, in cui metteva in discussione il criterio adottato dall'avversario, e preparo De'commentarii della lingua italiana, che sarebbero stati pubblicati postumi nel 1581. V. Branca, pur ritenendo che il Ruscelli fosse <<il piu colto>> dei poligrafi dell'epoca e <<il piu profondo negli studi grammaticali>>, giudica negativamente la sua edizione del Decameron, insieme a quella curata da Dolce, definendolo una <<sconciatura>> del testo. Viceversa, P. Trovato, in seguito alla collazione di alcune novelle con altre edizioni, nota frequenti interventi d'ordine ortografico e interpuntivo da parte di Ruscelli, ma, dato che le modifiche arbitrarie al testo sono poche, ritiene opportuno l'esame di un campione piu ampio. L'analisi sul testo dell'edizione del Ruscelli che si intende condurre in questo lavoro ha lo scopo di fare luce sul metodo filologico e sulle norme linguistiche da questi adottati, al fine di comprendere come valutarne il ruolo nella storia del Decameron in quanto modello della prosa volgare. Per quanto riguarda la correzione del testo, Ruscelli stesso dichiaro' di non aver visto l'autografo di Boccaccio e di avere seguito <<le stampe communi>>, di avere cioe adottato la lectio di molte stampe. Questa affermazione e degna di considerazione perche, nella prima meta del Cinquecento, i curatori del Decameron sostenevano che il testo della loro edizione fosse fedele all'originale, benche in realta spesso "contaminassero" il testo. Secondo P. Trovato e B. Richardson, il Decameron di Ruscelli riproponeva in particolare il testo delle giolitine anteriori al 1552 e anche della giuntina pubblicata nel 1527 a Firenze, testo che e alla base delle edizioni posteriori al 1527, incluse le sopraddette giolitine. Per mettere in chiaro il procedimento del lavoro redazionale compiuto da Ruscelli, esaminiamo qui i suoi riferimenti alle fonti che utilizzo. Ruscelli consulto almeno quattro manoscritti e due stampe antiche, probabilmente incunaboli difficili da identificare; consulto poi una stampa curata da Niccolo Delfino, ma non si puo dire che Ruscelli lo abbia seguito in modo consistente; le giolitine e, come risulta dalla nostra indagine, la giuntina del 1527. Possiamo senz'altro confermare che il Decameron del Ruscelli, se basato sul testo de <<le stampe communi>>, discendeva di conseguenza dalla giuntina. Ma la nostra collazione dell'edizione di Ruscelli con queue precedenti ci mostra come il nostro curatore non assumesse in realta sempre la lezione de <<le stampe communi>>, rifiutando a volte sia quella della giuntina sia quella delle giolitine, ma modificasse il testo seguendo le proprie norme linguistiche. Nel presente lavoro esaminiamo alcuni casi in cui Ruscelli non accetta la lectio comune, ma fa coincidere il testo con la propria prescrizione linguistica: il verbo aiutare; il passato remoto del verbo mettere; la terza persona plurale del congiuntivo presente del verbo essere; la preposizione articolata alle; Dio e Iddio. Per quanto riguarda la preposizione a con l'articolo determinativo maschile plurale, osserviamo che c'e un'oscillazione cronologica nella prescrizione grammaticale del Ruscelli, oscillazione che influenza la sua scelta della lezione nel testo: alli, considerata forma corretta nelle Annotationi, appare nella prima edizione, ma un anno dopo, nei Tre discorsi Ruscelli accuso Dolce per l'uso di li dopo le preposizioni tra cui include anche a. Respingendo quindi l'uso di questa forma, probabilmente per evitare un attacco da parte di Dolce, nella seconda e terza edizione, adotto' a' o a i, le forme proposte come corrette nei Tre discorsi e nei Commentarii. L'omologazione delle norme linguistiche nel testo, pero, non era un fenomeno raro in quell'epoca, perche in teoria lo stile boccacciano, essendo il modello migliore della prosa volgare, doveva coincidere con le norme linguistiche e grammaticali che, a loro volta, erano gia state elaborate basandosi sul suo stile. Ma il Ruscelli non mostro sempre il Boccaccio come prosatore perfetto e irreprensibile. Esaminiamo alcuni casi in cui il nostro curatore oso indicare apertamente gli errori del Boccaccio e consiglio ai lettori di non imitarlo: la ripresa della congiunzione subordinativa che; gliele indeclinabile; per+articolo determinativo maschile: per lo o per il. L'atteggiamento del Ruscelli di fronte al Boccaccio e alle norme linguistiche cui i letterati facevano riferimento dopo le Prose, puo dirsi assai critico; egli, infatti, liberandosi dall'obbedienza cieca alle lezioni bembiane, rivolse lo sguardo verso l'imperfezione del modello e sostenne la necessita di guardare con spirito critico alla lingua del Boccaccio. Queste considerazioni ci inducono a concludere che l'edizione del Ruscelli vada riconosciuta come uno dei processi piu importanti nella storia della tradizione testuale del Decameron.
3 0 0 0 OA アオバアリガタハネカクシの生活史に関する研究 : 有毒甲虫の研究, III
- 著者
- 黒佐 和義
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.245-276, 1958-12-10 (Released:2016-09-04)
- 被引用文献数
- 8 8
1)線状皮膚炎を惹起する有毒甲虫, Paederus fuscipes Curtisアオバアリガタハネカクシの生活史・習性について野外観察並びに実験的調査を行い, また各期の外部形態を記載した.2)成虫は体長7mm内外で一見蟻のような形状を有する.蛹は体長4.5mm内外の裸蛹で, 全体乳白色乃至橙黄色を呈し, 前胸背の前縁部と後縁部及び第1, 3〜7腹節の側端に各1対の非常に長い剛毛状突起がある.第2齢(終齢)幼虫は体長4〜6mmで, 細長く, 白色乃至橙黄色を呈し, 第9腹節に1対の長い尾突起を具える.第1齢幼虫は体長2.2〜2.4mm.卵は殆ど球形で, 産下当初は淡黄白色で長径約1.1〜1.2mmであるが, 発育に伴つて急速に増大し, 色彩も黄褐色に変る.3)本種は本邦では北海道から九州迄全土に亘つて広く分布するが, 概して暖地に多産し, 水田・畑・池沼の周辺・川岸などに棲息する.成虫は地表及び雑草上で生活する.東京都の成増では成虫は4月下旬乃至5月中旬頃から10月下旬に亘つて灯火に飛来し, 6・7月頃にピークを形成するのが認められた.成虫の灯火飛来活動はいわゆる前半夜型に属し, 暗化後2時間半以内の飛来個体が1夜の総飛来数の過半に達した.4)交尾の際, 雄は雌の背上に乗り, 大腮で雌の前胸と中胸の間の縊れた部分をくわえる.卵は地表の土壌間隙に1個ずつ産下される.1頭の雌の総産卵数は18〜100個(平均約52.3個)であつた.越冬した雌は4月下旬乃至5月中旬から通常7月中・下旬迄産卵を行い, 6月上旬に羽化した成虫は7月から9月に亘つて産卵を行つた.5)卵期間は3〜19日で, 孵化率は96.2%であつた.幼虫期は僅か2齢からなる.第1齢及び第2齢の期間はそれぞれ約4〜22日及び7〜36日であつた.老熟した幼虫は浅い土中に蛹室を造り, 約2〜9日後蛹化する.蛹の期間は約3〜12日であつた.6)成虫は雑食性であるが, 特に食肉性の傾向が強く, 野外では種々の昆虫, ダニ, 土壌線虫などを捕食し, また植物のやや腐敗した部分などを食するのが見られた.幼虫の食性も成虫と同様であつて, 捕食性の傾向が強く, 実験室内では牛肉或いはキュウリの一片の何れを与えても飼育することが出来た.7)周年生活環は東京附近では不規則で1年3世代のものと2世代或いは1世代のものがある.越冬は常に成虫態で行われる.越冬の際多数の個体が集団を作ることがある.8)有毒物質は卵・幼虫・蛹・成虫の何れからも証明された.成虫では有毒物質は体液中に含まれており, 虫体が破壊されて体液が外へ洩れ出ない限り皮膚炎を起すことはないと考えられる.本邦に産するPaederus属のハネカクシ8種のうち, fuscipes, tamulus, poweri, parallelusの4種は有毒物質を含むことが判明したが, 線状皮膚炎の原因として実際に重要なのはアオバアリガタハネカクシ唯一種である.本邦に於いて筆者により明かにされた灯火飛来性を有する68種のハネカクシの内には皮膚塗擦試験で軽微な皮膚炎を惹起するものがあるが, アオバアリガタハネカクシ以外に線状皮膚炎の症状を呈するものはない.
3 0 0 0 OA 戦後日本の子育て・子育て支援の社会史 : 高度経済成長期を中心に
- 著者
- 榊 ひとみ
- 出版者
- 北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター
- 雑誌
- 子ども発達臨床研究 (ISSN:18821707)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.109-125, 2017-03-15
3 0 0 0 OA 『栃木県史』史料編などにみる中世の遠野
- 著者
- 岩本 由輝
- 出版者
- 日本村落研究学会
- 雑誌
- 村落社会研究 (ISSN:13408240)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.1-11, 2002 (Released:2013-08-10)
The name “Tono” was first recorded in 1334, one year after the collapse of the Kamakura Regime, just prior to the split of the royal dynasty into Northern and Southern courts in the so-called “Nanpoku-cho” period. At that time, an agent dispatched by the Asonuma clan, whose main fief was in Shimotsuke province, ruled the Tono fief of Mutsu province. According to historical materials from 1350, the Asonuma clan ruled the fiefs of seven provinces by dispatching various administrative agents, and by aligning themselves at first with Southern court, and then with the Northern court, in order to maintain control over their fiefs. Around 1382, however, the Asonuma clan were uprooted from their main fief in Shimotsuke province by the Oyama clan, and in that process the Asonuma clan moved to strengthen their position in Tono, becoming the Tono-Asonuma clan. Henceforth, the Tono-Asonuma clan maintained an effective control over Tono until the end of the 16th century. During 1600, however, with the creation of the Morioka fief by the Sannohe-Nanbu clan, and in accordance with the process of establishing daimyo throughout the Japanese archipelago, the Tono-Asonuma clan was banished from Tono and disappeared from the main stage of history.
3 0 0 0 OA 新型コロナウィルスの蔓延下でのメンタルヘルスの変化:これまでの知見と将来への含意
- 著者
- 山村 英司 Eiji YAMAMURA
- 出版者
- 国立社会保障・人口問題研究所
- 雑誌
- 社会保障研究 = Journal of Social Security Research (ISSN:03873064)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.3, pp.236-245, 2022-12
特集論文
3 0 0 0 OA 日本古代移配俘囚・夷俘に関する考古学的研究
- 著者
- 平野 修 河西 学 平川 南 大隅 清陽 武廣 亮平 原 正人 柴田 博子 高橋 千晶 杉本 良 君島 武史 田尾 誠敏 田中 広明 渡邊 理伊知 郷堀 英司 栗田 則久 佐々木 義則 早川 麗司 津野 仁 菅原 祥夫 保坂 康夫 原 明芳
- 出版者
- 帝京大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2015-10-21
奈良・平安時代において律令国家から、俘囚・夷俘と呼ばれたエミシたちの移配(強制移住)の研究は、これまで文献史学からのみ行われてきた。しかし近年の発掘調査成果により考古学から彼らの足跡をたどることが可能となり、本研究は考古学から古代の移配政策の実態を探るものである。今回検討を行った関東諸国では、馬匹生産や窯業生産などといった各国の手工業生産を担うエリアに強くその痕跡が認められたり、また国分僧尼寺などの官寺や官社の周辺といったある特定のエリアに送り込まれている状況が確認でき、エミシとの戦争により疲弊した各国の地域経済の建て直しや、地域開発の新たな労働力を確保するといった側面が強いことが判明した。
3 0 0 0 OA 〈共通テーマ「民俗と文化」〉東北地方のアイヌ語地名の復元
- 著者
- 鏡味 明克
- 出版者
- 愛知学院大学人間文化研究所
- 雑誌
- 人間文化 : 愛知学院大学人間文化研究所紀要 = Transactions of the Institute for Cultural Studies, Aichi Gakuin University Ningen bunka (ISSN:09108424)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.368-361, 2008-09-20
3 0 0 0 OA 仮声帯発声の音声治療
- 著者
- 北川 洋子 北原 哲 田村 悦代 古川 太一 松村 優子
- 出版者
- 日本音声言語医学会
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.213-219, 2001-07-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2 3
発声時仮声帯も振動する仮声帯発声について, 自験例の音声治療経過を過去の文献と比較し報告した.症例は66歳の男性で, 嗄声を主訴とし来院した.軽度の声帯溝症を伴った仮声帯発声の診断で, 喉頭ファイバースコープを用いた視覚的フィードバック法および音声訓練を実施した.初診より90日後の最終評価では仮声帯の接近は解消され, 声帯による声門閉鎖が得られ, 音声も良好となった.GRBAS評価においては全般的嗄声度Gは2から0へと改善し, ソナグラムの分析でも倍音波形の振幅が大きくなり, 櫛型の明瞭な調波構造となった.本例の仮声帯発声の原因は声帯溝症による声門閉鎖不全を代償するものと考えられた.ファイバースコープでの発声運動の視覚的フィードバック, 音声治療手技が有効であった.当院の仮声帯発声の症例は発声障害患者400例に対して5例, 1.2%であり他の文献と一致していた.
3 0 0 0 OA 日米比較にうかがえる社会的制度としての公共図書館の現在と近未来の盛衰
- 著者
- 山本 順一
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.78-83, 2016-02-01 (Released:2016-04-01)
本稿は,OCLCの「世界図書館統計」やアメリカ連邦政府の労働統計局の統計,そして博物館・図書館サービス機構(Institute of Museum and Library Services)の『アメリカの公共図書館調査 2012会計年度』とピュー調査研究センター(Pew Research Center)が2013年に公表した『デジタル時代における図書館サービス』等を用いてアメリカ公共図書館の実態を数値で明らかにしつつ,21世紀の専門職ライブラリアンに求められる知識とスキルを確認しようとし,日本の公共図書館界の現実と重ね合わせ,「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)が提示する基本的方向性と一致することを確認しながら,日本にはアメリカのような(専門職)ライブラリアンの知識とスキルを育て,専門職を活かす社会の仕組みが十分には整っていないことを指摘し,このままでは日本の公共図書館総体の近未来が決して明るいものではないことを述べた。
3 0 0 0 OA 北海道アイヌの歴史
- 著者
- 齋藤 玲子 Reiko Saito
- 出版者
- アイヌ文化振興・研究推進機構
- 雑誌
- 千島・樺太・北海道アイヌのくらし : ドイツコレクションを中心に. アイヌ文化振興・研究推進機構編.
- 巻号頁・発行日
- pp.120-123, 2011-07-29
3 0 0 0 IR ケアワーカーの専門性に関する研究 : 社会福祉実践の共通基盤からの探索
- 著者
- 奥野 啓子
- 出版者
- 佛教大学大学院
- 雑誌
- 佛教大学大学院紀要. 社会福祉学研究科篇 (ISSN:18834019)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.17-33, 2014-03-01
高齢社会に伴う社会問題を発端として介護の社会化が進んでいる。高齢化による福祉ニーズの多様化に伴い,「量の確保」に加え「質の確保」が新たな課題として取り上げられ,介護の専門性が新たな問題として,問われ出している。本研究の目的は,組織としてとりくんでいるグループ会議と,個人の経験をインタビュー調査をすることで,実践場面におけるケアワーカーの専門性を明らかにすることである。調査は介護老人福祉施設に勤務するケアワーカーを対象に実施した。取材し得られたデータは,KJ 法を用いて統合し,その構造を明らかにした。介護の専門性は「ケアに潜む5 つの罠」「空転する思い」といった2 つの〈不全〉に流されることなく,価値に根拠をおき,そこに知識や理論が加わり,総体としての介護過程を実践し,「経験の質」「共有の質」があがり,その結果としてよい評価ややりがいといったケアワーカーにとっての強みと独自性が発揮されることまでを含むことが,本研究によって明らかになった。ケアワーカー専門性実践場面
3 0 0 0 OA 戦前期における電鉄会社系野球場と野球界の変容
- 著者
- 坂井 康広
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.71-80,109, 2004-03-21 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
本稿の目的は、電鉄会社あるいは電鉄会社の関連企業が設置経営した野球場が戦前期におけるわが国の野球界に占めた重要性を考察することである。電鉄会社が旅客誘致や住宅地開発の一環として沿線に野球場を設置したことは全国的にみられる傾向であった。公営の野球場がまだほとんど存在しなかった戦前において、中等学校優勝野球大会の地方大会の多くが学校のグラウンドを使用しているのに対して、スタンド設備も整った電鉄会社系野球場は野球界に先駆的存在であったといえよう。また、中等学校野球や少年野球などの野球大会は、電鉄会社にとって旅客収入を上げる優秀なアイテムであった。電鉄会社が野球場を所有していたということはプロ野球の誕生にも大きく貢献した。プロ野球結成当時、東京にはまだプロ野球が利用できる野球場がなかったのに対し、関西と名古屋に電鉄会社系野球場が存在していたことは特筆すべきことである。戦前期のプロ野球では公式戦の半数以上が電鉄会社系野球場で開催されたこともまたその重要性が伺える。
3 0 0 0 OA カタツムリと住宅材料
- 著者
- 井須 紀文
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.31-33, 2013-01-01 (Released:2014-02-20)
- 参考文献数
- 9
3 0 0 0 OA 現代方言の記述に基づく方言学習教材作成のための基礎的研究 (方言学習教材)
- 著者
- 加藤 和夫 Kato Kazuo
- 雑誌
- 平成18(2006)年度科学研究費補助金 基盤研究(C) 研究成果報告書 = 2006 Fiscal Year Final Research Report
- 巻号頁・発行日
- vol.2005-2006, 2007-03-31
金沢大学人間社会研究域歴史言語文化学系