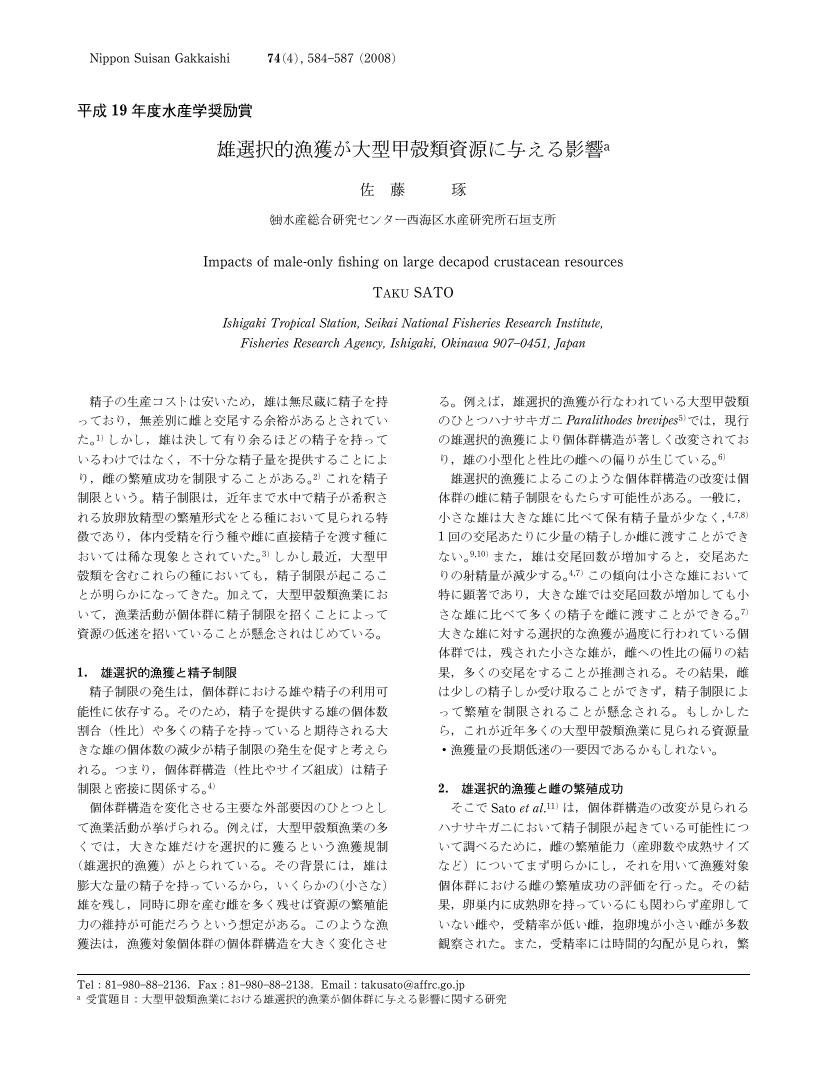3 0 0 0 OA 生物多様性情報の長期保管と長期利用
- 著者
- 細矢 剛 神保 宇嗣
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.159-162, 2022-11-01 (Released:2023-01-05)
- 参考文献数
- 18
自然史データの代表として生物多様性情報をとりあげ、その基盤となる標本情報の集積・利用上の課題を議論した。国立科学博物館においては、館内のデータ管理には「標本・資料統合データベース」が、国内の自然史博物館のデータの集積を目的として「サイエンスミュージアムネット(S-Net)」がある。両者のシステム導入とデータの長期保管・長期利用における課題をスペック、仕様書、長期の維持と保証、データフォーマットとデータ移行の点から比較した。これらの観点に加え、今後は外部連携・セキュリティなどが評価できる人材の育成や、システム構築のノウハウ共有が大切である。
3 0 0 0 IR 徳川家康の叙位任官
- 著者
- 藤井 讓治
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学大学院文学研究科内)
- 雑誌
- 史林 = The Journal of history (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.4, pp.663-698, 2018-07
徳川家康の叙位任官については、家康が歴史上重要な人物であるだけに、一般書も含め多く取り上げられてきたが、基礎的事実を十分に検討しないまま、その歴史的意味が論じられている。この問題についての専論は少なく、またこうした研究においても見解が一致していないのが現状である。本稿では、事実関係が不確定な家康の左京大夫・中納言・大納言・左大将任官を中心に分析する。家康は、三河守初任に続いて左京大夫に任じられるが、左京大夫は朝廷関係以外では使用することなく左京大夫任官後も前官の三河守を使用した。朝廷官位使用の特異な事例である。任中納言の年月日は、従来天正十四年(一五八六)十月四日とされてきたが、事実は同年十一月五日であるとし、その意味を秀吉への臣従儀礼の中に位置づけた。また家康の源氏改姓が聚楽第行幸を機になされたとされてきたものを、それに先立つ天正十五年八月には源姓であったことを明らかにした。さらに天正十五年の任左大将は、正保二年(一六四五)の将軍家光の要請をうけて口宣案が改められた折に遡及して任じられたものであり、天正十五年時点での任官の事実はなく、この任左大将をめぐる論争はそもそも成立しないとした。The study of early-modern Japanese political history has witnessed great progress in recent years. This progress includes a deeper understanding of the ranks and offices awarded to samurai. However, in regard to the fundamental facts and dating of samurai appointments to ranks and offices, there are several theories even regarding such an important political figure during the period as Tokugawa Ieyasu, and there are many misunderstandings. In order to create a political history of this age, confirming the facts and dating of Ieyasu's posts and ranks is a pressing issue. In this article I confirm the facts and dates of Ieyasu's ranks and offices, ascertain under what political circumstances they were granted, and furthermore determine their significance. To the extent that Ieyasu was an important political figure. Ieyasu's appointments to ranks and offices are dealt with in general works of history, but fundamental studies have not been sufficiently conducted, and there is no scholarly consensus regarding them. Ieyasu was first appointed governor of Mikawa province, then Sakyō Daibu (Commissioner of the Left Division of the Capital), Jijū (Chamberlain), Ushōshō (Junior Captain of the Palace Guards of the Right), Sachûjō (Middle Captain), Sangi (Consultant), Chûnagon (Middle Counselor), Dainagon (Major Counselor), Naidaijin (Minister of the Center), Udaijin (Minister of the Right), Seiitaishōgun (Babarian-subduing General), and finally Daijōdaijin (Chancellor). This article chiefly analyzes his appointment to the posts of Sakyō Daibu, Chūnagon, Dainagon, and Sadaishō, for which there has no confirmation in the historical record. Ieyasu was appointed Sakyō Daibu shortly after being named governor of Mikawa. In general, when someone was appointed to a new office, thr person would then be known by his new official title, but Ieyasu did not employ the Sakyō Daibu title except in relationship to the imperial court, and even after being appointed Sakyō Daibu continued to use his previous title, governor of Mikawa. This is an example of a unique use of an imperial title. The date of Ieyasu's appointment to the post of Chūnagon has been seen as having been on the fourth day of the tenth month of Tenshō 14 (1586) on the basis of a draft decree in the Nikkō Tōshōgû monjo found in Kugyō bunin, but I have confirmed that the actual date was the fifth day of the eleventh month of the same year and locate its significance within the course of the ceremonial relationship of lord and vassal with Hideyoshi. Furthermore, Ieyasu's adoption of Minamoto clan affiliation is seen within the context of the imperial progress to the Jurakutei, but I make clear that he had used the Minamoto clan name previously during the eighth month of Tenshō 15, and I present new evidence for consideration of this name change. The Ieyasu's appointment to Sadaishō (General of the Left) in Tenshō 15 can only be traced back to the occasion of request by the third Tokugawa shogun, Iemitsu, for reissuance of an oral decree in Shōho 2 (1645), and I clarify that the supposed appointment in Tenshō 15 is not historically accurate. Kasaya Kazuhiko's proposal of the existence of a Tokugawa Shogunate under a Toyotomi regency that is premised on the Ieyasu's appointment as Saidaishō and the arguments surrounding it are thus unsustainable.
3 0 0 0 OA 状況情報からの自発的感情推論―その生起と視点取得の役割の検討―
- 著者
- 小森 めぐみ 村田 光二
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.2-14, 2010 (Released:2010-08-19)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 3
本研究では,社会的状況を手がかりとした自発的感情推論が生じるかどうかを,そして視点取得がその推論に果たす役割を,記憶課題を用いて検討した。実験1では,参加者はさまざまな状況に置かれた人物についての記述文を記憶した。記述文から推論される感情語が後に手がかりとして呈示された場合には,手がかりがない場合と比べて記述文の再生が促進されることが示された。実験2では,参加者は特定の感情が表出された人物の顔と名前の対を記憶した。その表情が事前に呈示された同一人物の記述から推論される感情と一致する場合には,そうでない場合と比べて対連合記憶課題の成績が良いことが示された。これらの傾向は視点取得した場合(実験1)にはより強く見られ,状況に注目した場合(実験2)には記憶課題全体の成績を向上させた。二つの実験で見られた記憶の促進効果は,人が表情などの表出行動からだけでなく,他者の置かれた状況からも,その人の感情を自発的に推論する場合があることを示しているだろう。また,視点取得が他者の置かれた状況への注目を強め,推論を促進させる可能性も示しているだろう。
3 0 0 0 OA 大日本古文書
- 著者
- 東京帝国大学文学部史料編纂所 編
- 出版者
- 東京帝国大学
- 巻号頁・発行日
- vol.家わけ第7 (金剛寺文書), 1920
3 0 0 0 OA 忍者と探偵、近代日本におけるキャラクター表象の形成と海外伝播に関する文化研究
3 0 0 0 好きなことと突き詰めること
- 著者
- さかなクン
- 出版者
- 日立みらい財団
- 雑誌
- 犯罪と非行 (ISSN:03856518)
- 巻号頁・発行日
- no.176, pp.5-9, 2013-09
3 0 0 0 OA 炭酸水素ナトリウム(重曹)の洗浄力と環境影響の評価
- 著者
- 大矢 勝 甲斐 義明
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.8, pp.510-517, 2011-08-20 (Released:2016-12-03)
- 参考文献数
- 12
洗浄への炭酸水素ナトリウム(重曹)の利用に関して,インターネット上の消費者情報の実情を調査するとともに,関連事項の実験的検証を行った.インターネット上では炭酸水素ナトリウムの洗浄利用について肯定するものが大部分を占め,その洗浄力の根拠として水の軟化作用を挙げているものが多かった.洗浄試験の結果,一般の洗剤類に比べて油脂,パラフィン,カーボンブラック,酸化鉄,ヘモグロビンなどの汚れ除去性は劣り,石けんに加えた場合も石けん単独よりも洗浄力が低下するが,脂肪酸に関しては高い洗浄力を示した.炭酸水素ナトリウムは高濃度で利用することが前提なので,強いアルカリ緩衝作用によると考えられる.炭酸水素ナトリウムが水を軟化するには30~60分以上の時間を要するので実用上は関係しない.水生生物毒性は非常に低いが,洗浄へ利用する時は使用量が多いためにLCI評価で不利な結果が得られる.総合的にみて炭酸水素ナトリウムは環境配慮型の洗浄剤として高くは評価できない.
3 0 0 0 女性史研究
- 著者
- 家族史研究会 [編集]
- 出版者
- 共同体社
- 巻号頁・発行日
- 1975
3 0 0 0 OA ピア・リスニングの試み
- 著者
- 横山 紀子 福永 由佳 森 篤嗣 王 瑞 ショリナ ダリヤグル
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, pp.79-89, 2009 (Released:2017-06-21)
- 参考文献数
- 11
海外の日本語教育では,聴解技能が弱点であるばかりでなく,聴解技能開発の必要性やその方法論に対する認識が一般に低いことが指摘される。このような海外の日本語教育における課題を解決に導く事例として,カザフスタンおよび中国で非母語話者日本語教師が実践したピア・リスニングの試みを紹介した。ピア・リスニングとは聴解の過程をピア(学習仲間)で共有し,協力しながら理解を構築していく教室活動である。ピアの話し合いを文字化した資料および学習者からの意見聴取をデータとして,実践の成果を分析した。ピア活動では,言語知識の共有および欠落した理解を補う方策の共有が行われていた。また,ピア学習に合わせ,カザフスタンでは聴解を仮説検証的に進めていくためのタスク中国では学習者のモニターを促進するために「質問」を作るタスクを導入したが,これらのタスクとピア活動が相乗的な効果を上げたことを考察した。
3 0 0 0 OA 興味ある経過をとった餅誤嚥による急性呼吸不全の 1 例
- 著者
- 川村 雅文 渡辺 真純 橋詰 寿律 加藤 良一 菊池 功次 小林 絋一 石原 恒夫 堀 進吾 相川 直樹
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会
- 雑誌
- 気管支学 (ISSN:02872137)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.88-92, 1990-01-25 (Released:2016-10-01)
- 被引用文献数
- 1
症例は65歳の男性で, 焼いた餅を食べていてその小片を誤嚥した。その後徐々に呼吸困難が出現してきたため, 誤嚥から約1時間後に当院救急部に収容された。来院時の血液ガスは室内気でPaO_2 34Torr, PaCO_2 52Torrで著しいチアノーゼと努力性の呼吸を認めたが咽頭, 喉頭には餅を認めなかった。人工呼吸器を装着し, FiO_2 1.0としても, PaO_2は73Torrにしか上昇しなかった。人工呼吸器装着下に気管支鏡を施行したところ右下葉支に餅が嵌入していた。鉗子で餅を摘除すると人工呼吸器装着下FiO_2 1.0でPaO_2は369Torrと著明に改善した。患者は20歳時に左肺結核に罹患しており, 退院一か月後に行った肺シンチグラフィーでは左肺に換気, 血流とも認めなかった。このため右下葉支の閉塞だけで著しい呼吸困難に陥ったものと考えられた。
- 著者
- Hiroki Sato Sayaka Ban Tsuyoshi Hosoya
- 出版者
- The Mycological Society of Japan
- 雑誌
- Mycoscience (ISSN:13403540)
- 巻号頁・発行日
- pp.MYC594, (Released:2022-12-26)
Dr. Kobayasi and Mr. Shimizu described 31 species of Cordyceps infecting Lepidoptera. Holotype specimens of 14 species and two authentic specimens of one of the 31 species were rediscovered from a herbarium of the National Museum of Nature and Science (TNS). Registration numbers (TNS-F-number) were given to these 16 specimens, and one was lectotypified as follows. Holotypes: Metarhizium indigoticum TNS-F-230337; Yosiokobayasia kusanagiensis TNS-F-197994 (Clavicipitaceae); Beauveria hepialidicola (Kobayasi & Shimizu) Hirok. Sato, S. Ban & Hosoya, comb. nov. TNS-F-197986; Cordyceps ampullacea TNS-F-197981, Cordyceps militaris f. alba TNS-F-230340, Cordyceps ochraceostromata TNS-F-195471, and Cordyceps rosea TNS-F-197972 (Cordyceps sensu stricto, Cordycipitaceae); Ophiocordyceps aurantia TNS-F-195485, Ophiocordyceps cochlidiicola TNS-F-195470, and Ophiocordyceps hiugensis TNS-F-197978 (Ophiocordycipitaceae); and Cordyceps changpaishanensis TNS-F-195501, Cordyceps ootakiensis TNS-F-197976, Cordyceps shimizui TNS-F-197995, and Cordyceps sulfurea TNS-F-197974 (Cordyceps sensu lato). Lectotype: Cordyceps bulolensis TNS-F-230327 (Cordyceps sensu lato). A new combination Beauveria hepialidicola comb. nov., is proposed for Cordyceps hepialidicola based on morphological observations.
- 著者
- Nobuyuki Kagiyama Misako Toki Akihiro Hayashida Minako Ohara Atsushi Hirohata Keizo Yamamoto Toshinori Totsugawa Taichi Sakaguchi Kiyoshi Yoshida Mitsuaki Isobe
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.11, pp.1730-1735, 2017-10-25 (Released:2017-10-25)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 6 8
Background:As mitral valve (MV) repair for Barlow’s disease remains surgically challenging, it is important to distinguish Barlow’s disease from fibroelastic deficiency (FED) preoperatively. We hypothesized that the prolapse volume to prolapse height ratio (PV-PH ratio) may be useful to differentiate Barlow’s disease and FED.Methods and Results:In 76 patients with MV prolapse who underwent presurgical transesophageal echocardiography, the 3D MV morphology was quantified: 19 patients were diagnosed with Barlow’s disease and 57 with FED. The patients with Barlow’s disease had greater prolapse volume and height than the patients with FED, as well as greater PV-PH ratio (0.61±0.35 vs. 0.17±0.10, P<0.001). Receiver-operating characteristic analysis revealed that with a cutoff value of 0.27, the PV-PH ratio differentiated Barlow’s disease from FED with 84.2% sensitivity and 84.2% specificity. Net reclassification improvement showed that the differentiating ability of the PV-PH ratio was significantly superior to prolapse volume (1.30, P<0.001). After being adjusted by each of prolapse volume and height, annular area and shape, and the number of prolapsed segments, the PV-PH ratio had an independent association with Barlow’s disease.Conclusions:The PV-PH ratio was able to differentiate Barlow’s disease from FED with high accuracy. 3D quantification including this value should be performed before MV repair.
- 著者
- 中井 遼
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア経済 (ISSN:00022942)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.89-91, 2018-12-15 (Released:2019-03-25)
- 参考文献数
- 3
3 0 0 0 OA 大衆運動の多様化と変質
- 著者
- 高畠 通敏
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.323-359, 1979-09-18 (Released:2009-12-21)
3 0 0 0 OA 歌における「雨」の表象について
- 著者
- 内田 育恵 杉浦 彩子 中島 務 安藤 富士子 下方 浩史
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.222-227, 2012 (Released:2012-12-26)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 23
目的:我が国における高齢難聴者の現況を推計することを目的として,「国立長寿医療研究センター―老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)」データを検討した.方法:NILS-LSA第6次調査(2008~2010年実施)より男性1,118名,女性1,076名の計2,194名を対象として,地域住民の粗率に近似すると考えられる5歳階級別難聴有病率を算出した(算定A).また,聴力に有害な作用をもたらす耳疾患と騒音職場就労を除外した算出も行った(算定B).総務省発表人口推計を用いて全国難聴有病者数を推計した.次に第1次調査(1997~2000年実施)時点で,除外項目と難聴定義に該当せず,かつ第6次調査にも参加した男性212名,女性253名の計465名を対象として,10年後の難聴発症率を解析した.結果:難聴有病率は65歳以上で急増していた.算定Aでは,男性の65~69歳,70~74歳,75~79歳,80歳以上の年齢群順に43.7%,51.1%,71.4%,84.3%で,女性では27.7%,41.8%,67.3%,73.3%といずれも高い有病率を示した.算定Bでは,同様の年齢群順に男性で37.9%,51.4%,64.3%,86.8%で,女性では26.5%,35.6%,61.4%,72.6%であった.全国の65歳以上の高齢難聴者の数は,算定Aでは1,655万3千人,算定Bでも1,569万9千人に上った.10年後の難聴発症率は,調査開始時年齢60~64歳群では32.5%,70~74歳群では62.5%と,年齢上昇に伴い高くなったが,依然聴力を良好に維持する高齢者が存在した.結論:高齢者の難聴有病率は高く,全国難聴有病者数推計から,加齢性難聴が日本の国民的課題であることが再確認された.また年を経ても聴力を良好に維持することが可能であると示唆された.
3 0 0 0 OA 雄選択的漁獲が大型甲殻類資源に与える影響
- 著者
- 佐藤 琢
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.4, pp.584-587, 2008 (Released:2008-07-28)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 4 2