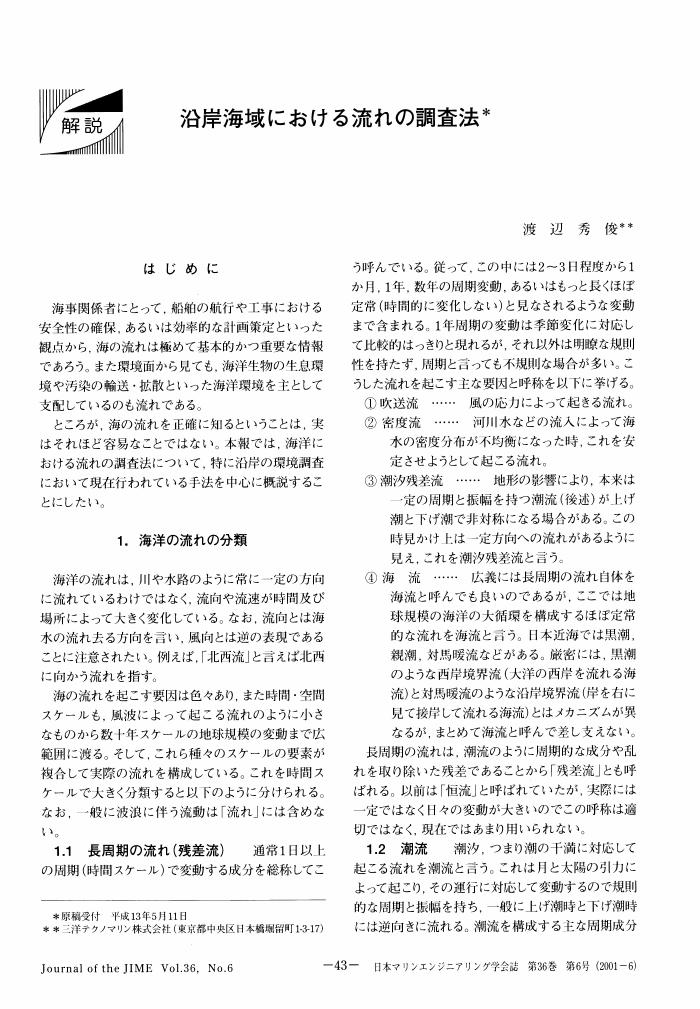2 0 0 0 OA コミュニケートするモノ——実在としてのモノとレトリカルな力
- 著者
- 柿田 秀樹
- 出版者
- 日本コミュニケーション学会
- 雑誌
- 日本コミュニケーション研究 (ISSN:21887721)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.Special, pp.95-107, 2023-01-31 (Released:2023-02-03)
- 参考文献数
- 15
2 0 0 0 OA 英語における主語・述語の倒置
- 著者
- 伊藤 清 Kiyoshi Ito
- 雑誌
- 人文論究 (ISSN:02866773)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.69-93, 1978-06-20
2 0 0 0 OA 地理学と都市問題:
- 著者
- 廣松 悟
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.98-113, 1991-12-31 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 71
当論文においては,英米圏の都市地理学における都市空間概念の展望に基づいて,英米の近代都市において社会問題群が確立,制度化されるための歴史的な条件の探求に関わる作業仮説が提示される。 注目に値するのは,都市自体は人類史を通じて重要ではあったが,特にそれが理論上重要な分析単位となったのは,地理学のみならず他の社会科学一般においても今世紀初頭になってのことに過ぎないといった事実である。この歴史的事実を説明しうる仮設の一つは,先の「都市問題」の形成は,社会空間の全域を覆う特異な政治的監視制度でもある近代国民国家の成立と密接に関連していたというものである。近代都市は,領域国家制度のもとでは,特にその社会的「監視」の観点からみた統治上の効率性の関数として規定された。従ってここに,都市地理学を含めた社会諸科学の都市に関する様々な言説と実践が登場し,先の問題群を制度化すべく,「社会と空間の連関」という特有の問題機制に従って,相異なる概念化に基づいた都市諸学の制度化を実現させることになったと考えられる。中でも,都市空間に関する一般理論は,都市問題を普遍的な既成事実として自明視するような,歴史社会上特異な「実践の閉域」の形成に大きく寄与してきた。今世紀初頭の初期シカゴ学派から最近の都市社会学や都市地理学に至る一貫した思考は,まさにこの特異な領野を構成する上で効果の大きな,都市の一般理論の構築に向けられていたのである。そこでは,この一般理論の対象となる「近代都市」の社会歴史的な存立条件自体を相対化するような,客観的な視座にはかなり欠如していた。そのため,こうした社会と空間に関する極度に.一般的な問題機制は,範域(空間)としての都市を社会として定式する観点と,個別社会を範域(空間)として把握する視点との狭間でほとんど解決不可能な不整合を生み出し,近代都市という歴史地理上特殊な空間に関して,ほとんど無秩序に形成されたかの如きパターン概念の束を生産する結果をもたらしてきた。 現在求められているのは,近代都市という,言説・制度を含んだ歴史社会的にきわあて特殊な閉じた領域に対する一貫して分析的な視座である。中でも,近代国民国家が各々の,歴史社会上特殊な集団や社団を,その領域社会統治上の組織支配単位の一っとして変容させ,主に法人都市の形式によって法的に包摂し,引き続いて,それを永続的な「社会問題の場」として維持することを通じて監視と管理の体系である都市諸学の成立を促し,それらの総合的な作用として結果的に社会の総体的な都市化を招いてきた一連の近代都市に関わる歴史過程が,改めて実証的かっ分析的な研究課題として掲げられなければならない。
- 著者
- Shunsuke Nashimoto Shungo Imai Mitsuru Sugawara Yoh Takekuma
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.230-236, 2023-02-01 (Released:2023-02-01)
- 参考文献数
- 32
The Child–Pugh score is widely used to assess liver function and estimate drug clearance in patients with liver cirrhosis. Recently, the albumin–bilirubin (ALBI) score, which objectively assesses liver function based only on albumin and total bilirubin levels, was developed as a new method. The purpose of this study was to analyze the relationship between the liver function assessment method and the plasma concentration of voriconazole (VRCZ), an antifungal drug for patients with liver cirrhosis. This single-center retrospective study enrolled 159 patients who received VRCZ between 2012 and 2020. In patients administered VRCZ orally, the median concentration to dose (C : D) ratio increased with the progression of Child–Pugh and ALBI grades. Positive correlations between the ALBI score and VRCZ C : D ratio were observed in patients with cirrhosis (r = 0.52 (95% confidence interval, 0.069–0.79); p < 0.05). In addition, a highly negative correlation was observed between the ALBI score and VRCZ daily maintenance dose (r=−0.79 (95% confidence interval, −0.92 to −0.50); p < 0.0001). In contrast, for patients administered VRCZ intravenously, no increase in C : D ratio was observed for both Child–Pugh and ALBI scores compared to the non-liver cirrhosis group. This may be because the injection is often used in severely ill patients, and factors other than impaired liver function may affect the plasma concentrations of VRCZ. In conclusion, the ALBI score was shown to be useful in predicting VRCZ clearance as well as the Child–Pugh score, and the initial dose of VRCZ might be determined according to the ALBI score.
2 0 0 0 OA 薩摩半島沖から得られた国内2例目のタイワンコロザメ
- 著者
- 畑 瑛之郎 大富 潤 岩本 航 本村 浩之
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.40-44, 2022-12-12 (Released:2022-12-13)
- 著者
- Xuping Huang Shunsuke Mochizuki Akira Fujita Katsunari Yoshioka
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, 2023-03-15
In recent years, malware-infected devices, such as Mirai, have been used to conduct impactful attacks like massive DDoS attacks. Internet Service Providers (ISPs) respond by sending security notifications to infected users, instructing them to remove the malware; however, there are no approaches to quantify or simulate the performance and effectiveness of the notification activities. In this paper, we propose a model of security notification by ISPs. In the proposed model, we simulate the security notification with composite parameters, indicating the nature of malware attacks such as persistence of malware, user response ratio, and notification efforts by ISPs, and then discuss their effectiveness. Moreover, we conduct a simulation based on the actual attack.------------------------------This is a preprint of an article intended for publication Journal ofInformation Processing(JIP). This preprint should not be cited. Thisarticle should be cited as: Journal of Information Processing Vol.31(2023) (online)DOI http://dx.doi.org/10.2197/ipsjjip.31.165------------------------------
2 0 0 0 OA 大学病院の看護師の職業的アイデンティティとバーンアウト
- 著者
- 塩見 直子 鈴木 英子 松谷 弘子 加古 幸子
- 出版者
- 日本健康医学会
- 雑誌
- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.205-217, 2021-07-27 (Released:2021-10-16)
- 参考文献数
- 42
大学病院の看護師のバーンアウト予防を意図し,職業的アイデンティティとバーンアウトの関連および職業的アイデンティティの高い者の特徴を明らかにした。調査協力の得られた関東圏の大学病院4施設に勤務する看護師長,助産師,非常勤看護師を除く全看護師2926名を対象として,Maslach Burnout Inventory Human Service Survey (MBI-HSS),看護師の職業的アイデンティティ尺度,短縮版3次元組織コミットメント尺度を使用した無記名自記式質問紙調査を実施した。有効な回答を寄せた看護師1452名を解析の対象とした。解析対象者の年齢(平均値±標準偏差,以下同じ)は32.53±9.56歳,臨床経験年数は9.49±8.36年であった。MBI-HSSの総合得点は,11.93±2.68点,職業的アイデンティティの合計点は61.92±8.40点であった。重回帰分析の結果,「職業的アイデンティティ」とMBI-HSSの総合得点との関連が認められ(β=-0.257, p<0.01),職業的アイデンティティが高い者は,バーンアウトしにくいことが明らかになった。職業的アイデンティティが高い者は,①年齢,臨床経験年数が高く,配偶者や子どもがあり,職位が副師長・主任であることが多く,②「病院はキャリアを支援してくれる」,「現在の給与に満足している」,「休みの希望が通りやすい」など組織を肯定的に評価する割合が高く,③「情動的コミットメント」,「継続的コミットメント」,「規範的コミットメント」の点数が高く,④「組織は個人の価値観を理解してくれない」,「今の職場を辞めたい」,「今の仕事を辞めたい」と回答する割合が少なかった。これらの職業的アイデンティティの高い者の特徴を参考に人材を育成していくことは,看護師のバーンアウト予防につながると考える。
2 0 0 0 OA 社会課題解決に向けたリビングラボの効果と課題
2 0 0 0 OA 唐朝氏族志の一考察 : いわゆる敦煌名族志残巻をめぐって
- 著者
- 池田 温
- 出版者
- 北海道大學文學部
- 雑誌
- 北海道大學文學部紀要 (ISSN:04376668)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.1-64, 1965-03-27
2 0 0 0 OA 徳川幕臣の身分的変容に関する研究―いわゆる「御家人株の売買」の問題を中心に―
- 著者
- 姜 鶯燕 Yingyan JIANG
- 出版者
- 総合研究大学院大学
- 巻号頁・発行日
- 2012-09-28
- 著者
- 黒岩 豊秋 小張 一峰 岩永 正明
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.257-263, 1990-03-20 (Released:2011-09-07)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 11 12
生菌性整腸剤の効果に対する作用機序解明並びに実験的評価を目的として, 各種腸管病原菌と酪酸菌MIYAIRI 588株を混合培養し, 経時的に菌数の増減を測定した. 腸管病原菌はいずれも患者由来株を使用し, 37℃ 嫌気培養を行った.混合培養において酪酸菌は, コレラ菌・ナグビブリオ・アエロモナス・赤痢菌の発育を強く抑制した. 酪酸菌は主として消化管下部において発芽増殖するので赤痢菌との関連を更に追求し, 次のような結果を得た. (1) 赤痢菌をBHIbrothで嫌気培養すると培養終了時に培地のpHは5.2程度まで下がったが, 菌は順調に発育した. (2) 酪酸菌と混合培養するとpHは5.6程度で留まったが, 赤痢菌の発育は強く抑制された. (3) 酪酸菌24時間培養液はpH5.5前後であり, この上清中で赤痢菌は全く増殖できなかった. (4) この上清をNaOHでpH7.2に調製すると赤痢菌は新鮮培地におけると同様に増殖した. (5) 培養中のpHを6.0以上に維持させるため燐酸緩衝液を加えたBHIbrothでも混合培養によって赤痢菌の増殖は抑制された. この様な結果から, 酪酸菌による赤痢菌の発育抑制は, 培地のpH, 代謝産物など単一の要因によるものではなく, その両者及び酪酸菌そのものの存在が作用しあっているものと考えられた.
2 0 0 0 IR 神楽と死者のまつり : 比婆荒神神楽における「祖霊加入説」の再検討
- 著者
- 井上 隆弘
- 出版者
- 佛教大学総合研究所
- 雑誌
- 仏教大学総合研究所紀要 (ISSN:13405942)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.1-14, 2016-03
広島県の比婆荒神神楽は、中世神楽の特徴である神がかり託宣の古儀を現代に伝える神楽である。その理解において今日でも大きな影響力をもっているのが牛尾三千夫の所説、すなわち荒神神楽は、死者の霊が「祖霊」たる本山荒神へ加入する儀礼であるとするものである。本稿では、そこで等閑視されている「小さき神」に焦点をあて神名帖や地域の小祭である地祭の検討を行い、牛尾の「祖霊神学」批判をとおして、牛尾に影響を与えている柳田民俗学の問題性にも言及した。荒神神楽祖霊加入説小さき神地祭祖霊神学
2 0 0 0 「社会の罪」の探索:――徳富蘇峰、森田思軒、樋口一葉――
- 著者
- 木村 洋
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, pp.1-16, 2017
<p>坪内逍遥『小説神髄』の登場を経た一八八〇年代後半から一八九〇年代は、写実主義小説の時代だったと要約できる。しかし徳富蘇峰は逍遥の小説観に沿わない考え方を抱いていた。そしてこの人物を主な推進者とする形で一八九〇年前後に始まった、ユゴー流の認識の導入によって日本文学の刷新を図るという企ては、「社会の罪」という提言(森田思軒)を得ることで多くの賛同者を集め、のちの樋口一葉たちの小説に結実する。こうした「社会の罪」をめぐる資料群を掘り起こしていくと、従来互いに関連するものとして論じられてこなかった蘇峰と一葉の文業も同じ「社会の罪」という系譜の上にあったことが見えてくる。</p>
2 0 0 0 OA わが国のサクラ(ソメイヨシノ)の開花に対する地球温暖化の影響
- 著者
- 丸岡 知浩 伊藤 久徳
- 出版者
- 日本農業気象学会
- 雑誌
- 農業気象 (ISSN:00218588)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.283-296, 2009-03-10 (Released:2009-10-30)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 24 15
This study predicts cherry blossom (Prunus yedoensis) flowering in Japan during global warming periods. First, by developing current models for cherry blossom flowering, a model suitable for assessing the climate impact is constructed. This model can predict the dormancy breaking and flowering dates by temperature data alone at any points and for any periods. Applying this model to actual data for 25 years (1979-2003), the average RMSE (root mean squared error) of predicted flowering dates in comparison to actual ones at 36 points in Japan is 2.87 days.An indicator of the southern border of flowering is also proposed. The flowering model is applied to projected future temperature based on the IPCC A2 scenario. The predictions for the years 2032-2050 and 2082-2100 indicate that flowering dates will become much earlier than at present in cold regions, while later along the coasts in warm regions. It also shows that cherry blossoms will not come out in Tanega-Shima and southern Kyushu, which are currently the southern flowering borders.
2 0 0 0 OA 沿岸海域における流れの調査法
- 著者
- 渡辺 秀俊
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.6, pp.417-424, 2001-06-01 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA イスラームと輪廻転生観 タナースフ及びタカンムスに見られる輪廻転生
- 著者
- 宇野 昌樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.88-102, 1995 (Released:2010-03-12)
“Tanasukh” and “Taqammus”, are terms that mean metempsychosis in Arabic. This concept is accepted by the Alawite and the Druze, but rejected by the Sunnis, who considered this concept as heretical and those who believe in the concept as heretics. There is some debate among scholars about the origins and the exact meanings of terms “Tanasukh” and “Taqammus”. The former derives from a Koranic reference to “the conception of the soul”. It has been interpreted by the method of the Isma'ili Shia doctrine of “Batin”. Finally, although “Tanasukh” predates “Taqammus”, both have apocalyptic overtones referring to the reincarnation of the Mahdi and the so-called “Day of Judgment”.
- 著者
- 林 直嗣
- 出版者
- 法政大学経営学会
- 雑誌
- 経営志林 = The Hosei journal of business (ISSN:02870975)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.1-19, 2011-07-31
目次 1.はじめに 2.少子化の主因=結婚率の低下 3.少子化対策・子育て政策の類型 4.子ども手当とは何か 5.高校無償化とは何か(以下本号) 6.2010年度の扶養控除廃止と子ども手当・高校無償化の増減税効果 7.今後の扶養控除廃止と増税効果 8.あるべき少子化対策・子育て政策:むすびにかえて
2 0 0 0 OA データ駆動型社会の人と品と質とのマネジメント
- 著者
- 椿 広計
- 出版者
- 応用統計学会
- 雑誌
- 応用統計学 (ISSN:02850370)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2-3, pp.89-98, 2018 (Released:2019-02-13)
- 参考文献数
- 29
日本の統計的品質管理活動は,虚偽のデータを企業から無くすことを目的の一つとして掲げてきた.しかし,2017年以降生じた品質データ改ざんは,データ駆動型社会に向かうわが国にとって大きな課題を突き付けた.本フォーラムでは,日本がデータ駆動型社会に向かう際に,必要な品と質と人財に関するマネジメントの在り方について議論する.特に,どのようなデータサイエンティストを育成すべきか,またデータがもたらす経済価値とは何か,そのデータが改ざんされた場合の社会損失はどのようなものかについて議論したい.