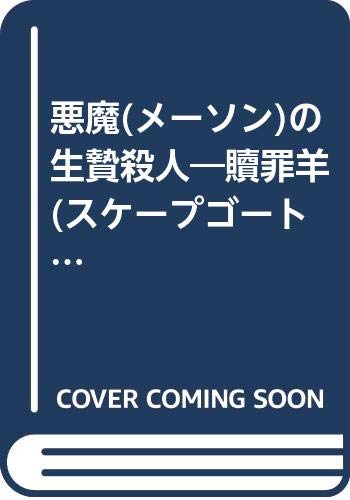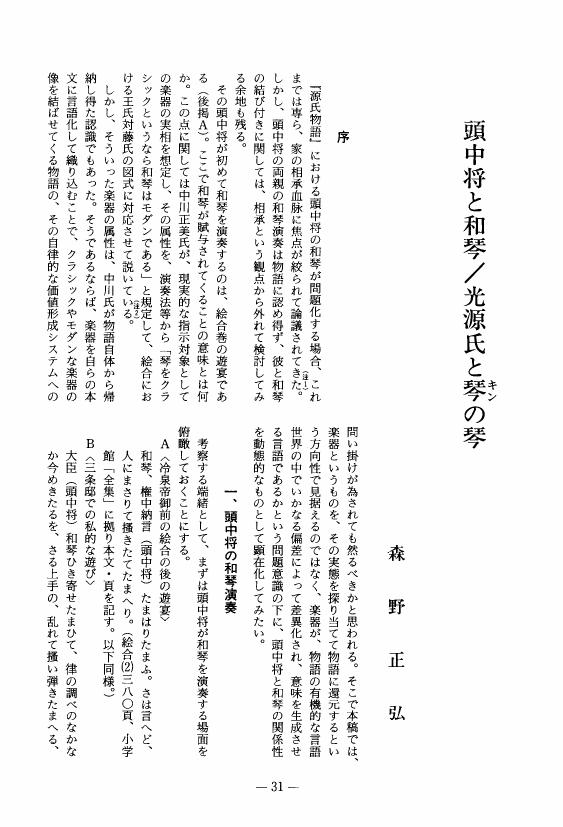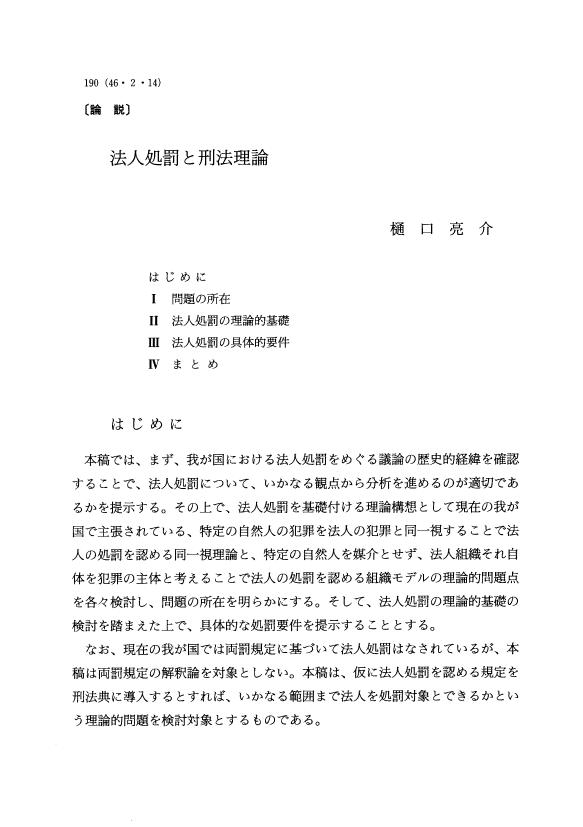2 0 0 0 OA わが国における高齢者に対するトランジショナル・ケアの概念分析
- 著者
- 小木曽 加奈子
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療・病院管理学会
- 雑誌
- 日本医療・病院管理学会誌 (ISSN:1882594X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.21-30, 2023-01-31 (Released:2023-01-27)
- 参考文献数
- 28
本研究は,文献を用いてわが国における高齢者に対するトランジショナル・ケア(TC)の概念を概念分析により明らかにすることを目的とした。データベースは,Pub Med,医学中央雑誌web版,メディカルオンライン,CiNii Researchを用い,さらに,ハンドリサーチにて,研究目的に合う書籍2件を加え,最終的に20文献を分析対象とした。Rodgersの概念分析の手法を用いて分析をした結果,6つの属性として【多職種協働のチームケア】,【さまざまな療養の場における同じ方向性をもつケア】,【高齢者と家族のもてる力の活用】,【包括的・統合的なケア】,【高齢者の病状変化に伴うケア】,【高齢者と家族の意思決定支援】。3つの先行要件として,【生活の場を変えなければならないシステム】,【移行先の生活の場の機能】,【TCの範疇】。4つの帰結として,【生活の場での暮らしの継続】,【TCのPDCAサイクル】,【介護負担の軽減】,【高齢者と家族の意向の実現】が抽出された。これらから,本概念は高齢者の多様な病状変化の特徴を反映し,多職種協働による包括的・統合的なケアの要素を含むことが示唆された。
2 0 0 0 OA 頭中将と和琴/光源氏と琴(キン)の琴
- 著者
- 森野 正弘
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.31-42, 1995-05-20 (Released:2019-05-18)
2 0 0 0 OA ユマニチュードの有効性と可能性
- 著者
- 竹林 洋一 本田 美和子 Yves Gineste
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第29回 (2015)
- 巻号頁・発行日
- pp.2M3NFC04a1, 2015 (Released:2018-07-30)
『ユマニチュード』は、「人と何か、ケアする人とは何か」という哲学をベースに開発された認知症ケア技法であり、「見る」「話す」「触れる」「立つ」「歩く」を基本とする具体的テクニックから構成されている。ユマニチュードは既存のケア技法との共通点も多いが、「人間尊重」を徹底して、マルチモーダルな介入(インタラクション)を行うことが特徴であり、心と脳に刺激を与え、認知症の人の心身の回復が促進することが実証されている。本報告では、MinskyとDamasioの感情・思考・身体に関わる研究の観点から、ユマニチュードの有効性と可能性について論じる。
- 著者
- 青木 弘枝 星野 奈生子 神田 明日香 崔 乘奎 手柴 富美 中村 光一 名和 宏樹 西城 卓也 今福 輪太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.198-204, 2016 (Released:2016-12-26)
- 参考文献数
- 11
目的:本研究は,男女医学生がどのようなキャリア認識を有しているのかを検証した.方法:男女医学生16名に半構造化インタビューを実施し,データ分析はグラウンデッド・セオリーの分析手法に従った.結果:男女医学生が有する「ジェンダー観」,「興味・関心」「家庭観」の概念が,両者のキャリア認識形成に影響した.キャリア選択において,男子医学生は医学への興味・関心を一貫して優先し,医師職に従事することで家庭を支えると認識した.女子医学生は,低学年では「興味・関心」と「家庭観」との両立で葛藤しキャリア選択を決めかねる傾向にあったが,高学年では「家庭観」を重視する者と「興味・関心」を優先する者とに分かれた.考察:本研究で明らかになった男女医学生のキャリア認識は,男女共同参画社会の意義を理解する卒前教育の必要性を支持するものである.
2 0 0 0 OA 日本人の世界一周旅行に見る行動の空間的特徴
- 著者
- 阿部 諒
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2020年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.240, 2020 (Released:2020-03-30)
かつて世界一周は限られた人が行うものであった。2000年代以降,世界一周する日本人旅行者は増加していると考えられる。その背景には治安の改善やSNSの普及,さらには世界一周航空券の販売がある。現代の世界一周旅行は多様性に富み,旅行を通じてさまざまな人びとが世界各地を訪れるようになった。しかし,筆者自身の世界一周旅行の体験からも,現代の世界一周旅行は多様化しつつも,それぞれの旅行者の行動には共通点や類似性があると考えられた。本研究では世界一周を「日本から西もしくは東方向に太平洋と大西洋を一度ずつ横断し,各地を観光・見物して戻ってくること」定義し,日本人世界一周旅行者の行動の空間的特徴を明らかにする。世界一周旅行は旅行者個人にとって,人生における「究極の旅行」であり,通常の旅行とは異なる意義をもつ。必然的に,その行動には世界一周旅行独自の様式や空間的特徴があると考えられる。 世界一周旅行者の情報は書籍,聞き取り調査,アンケート調査およびブログから入手した。聞き取り調査,アンケート調査は2019年3月に南米ボリビアのウユニで実施した。インターネット上で閲覧可能な100以上の世界一周旅行のブログから,既に旅行を終えている42のブログを対象とした。これらの方法で集めた世界一周旅行の情報を「訪問地」「移動」「イベント」の3つの視点から分析する。世界一周旅行者の訪問地を国別に見た場合,最も多いのはアメリカ(34人)であり,次いでペルー,スペイン(各30人),ボリビア,イギリス(各27人)であった。南米やヨーロッパ全体への訪問が目立つ一方で,東アジア各国への訪問者は少ない。具体的な訪問地として最も多かったのはウユニ塩湖(27人)で,他にも主にヨーロッパ,東南アジアの大都市と南米の有名観光地に集中している。世界一周旅行者は有名観光地,定番的観光地を中心に訪問するが,その中には通常の旅行では行きづらい場所も含まれる。一方でビザ取得の手間や治安の面から,秘境と呼ばれる地域を訪問する機会は少ない。世界一周は「無難な旅」である。 「移動」は「大陸間の移動」など,長距離移動に焦点をあてた分析を行った。その結果,アジア〜ヨーロッパ〜北米の北半球が移動の軸であり,そこから南に逸れるような形で南半球を訪れるのが一般的な世界一周ルートであるということが分かった。北半球は交通網が発達しており,移動しやすく,世界一周航空券も使用しやすい。訪問地の分析から,世界一周旅行者の多くは南米を一とする南半球の地域に強い指向性を持つことが明らかとなったが,長距離移動は北半球が中心である。南米から太平洋を横断し,帰国する際も,多くの旅行者は北半球,とくに北米の都市を経由する。世界一周旅行者は,一見行きたい場所に自由に行くように思われるが,現実的には,彼らの行動は既存の航空交通システムに強く制約される。世界一周は「制約のある旅」である。 「イベント」は旅行者が旅行中に遭遇した「想定外の出来事」を意味する。イベントは盗難,病気,交通機関のトラブル,人との出会い,の4つに大きくわけることができ,世界各地で遭遇する。世界一周旅行を通じて旅行者は「弱者」という立場に自分を置くことで自身の成長を期待する。最終的には「人との関わり」によって旅行者が少しずつ成長していき,旅行の意義を感じる。 現代の世界一周旅行は「弱者」が行う「無難ではあるが制約のある旅」である。これに加えて,各地を順番に巡っていく中で,彼らはさまざまなイベントを体験し,ゴール(帰国)する。旅行者は旅行中にイベントを通じて,困難な状況を解決するための力をつけていく。世界一周旅行はいわば「RPG」のようなものである。それが,ありきたりなコースをたどるだけの無難な旅行に,その人にとっては代え難い独自性を持たせ,世界一周旅行を意義づける。
2 0 0 0 OA 日本人男性労働者における主食の重ね食べと歯周病の関連についての横断研究
- 著者
- 岩﨑 正則 福原 正代 大田 祐子 藤澤 律子 角田 聡子 片岡 正太 茂山 博代 正木 千尋 安細 敏弘 細川 隆司
- 出版者
- 一般社団法人 口腔衛生学会
- 雑誌
- 口腔衛生学会雑誌 (ISSN:00232831)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.42-50, 2023 (Released:2023-02-15)
- 参考文献数
- 24
男性労働者における主食の重ね食べ(1回の食事で炭水化物の供給源となる主食を2種類以上同時に食べること)と歯周病の関連を明らかにすることを目的に横断研究を実施した.福岡県内の一企業で行われた定期健康診断にあわせて実施した歯科健診,食事調査,質問紙調査に参加した539名の男性従業員(平均年齢47.9歳)のデータを用いた.歯科健診では10歯の代表歯の歯周ポケット深さを計測した.食事調査では1日あたりの炭水化物摂取量を推定し,摂取量上位20% を多量摂取と定義した.そして4 mm以上の歯周ポケットを有する歯数を目的変数とし,主食の重ね食べの頻度「1日1食以上」「1日1食未満」を説明変数とする負の二項回帰モデルを用いて両者の関連を解析した.さらに,主食の重ね食べの頻度が高い者には炭水化物を多量に摂取している者が多く,歯周病へ影響を与えているとの関連を仮定し,一般化構造方程式モデリング(GSEM)を用いて3者の関連を分析した.解析対象集団の14.8%が1日1食以上の主食の重ね食べをしていた.主食の重ね食べの頻度が1日1食未満の群と比較して,1日1食以上の群では4 mm以上の歯周ポケットを有する歯数が有意に多かった(発生率比=1.47,95%信頼区間=1.10–1.96).GSEMを用いた分析の結果,主食の重ね食べの頻度が高いことは炭水化物の多量摂取と関連があり,主食の重ね食べが歯周病に与える影響の一部は炭水化物の多量摂取を介していることが示された.
2 0 0 0 OA 優生思想はどのように語られてきたか : 優生学の言説をめぐって
- 著者
- 西角 純志
- 出版者
- 専修大学学会
- 雑誌
- 専修人文論集 (ISSN:03864367)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, pp.311-327, 2021-11-30
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1937年08月26日, 1937-08-26
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1921年01月29日, 1921-01-29
2 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1939年05月24日, 1939-05-24
2 0 0 0 OA カフカ『失踪者』における「旅」のイメージ 亡命者と移住者のあいだの浮遊
- 著者
- 川島 隆
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.158, pp.90-103, 2018 (Released:2020-03-15)
In ihrem Essay Questions of travel: Postmodern discourses of displacement (1996) kritisierte Caren Kaplan die Polarisierung von „tourism“ und „exile“ in der Forschung, in der ein einsamer, entfremdeter Emigrant zur idealen Künstlerfigur der literarischen Moderne stilisiert wird, während die Reisen der Touristen in der modernen Gesellschaft als bloß banale, kapitalistische Vergnügungen abgewertet werden. Kaplans Kritik gilt auch der postmodernen Theorie der „déterritorialisation“, die Gilles Deleuze und Felix Guattari vor allem in Kafka: Pour une littérature mineure (1975) entwickelten, indem sie die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen realer Nomaden außer Acht lassen. Kaplan zufolge privilegieren die postmodernen Theoretiker die nomadenhafte Existenz im Exil bzw. in der Diaspora so, dass sie schließlich dem idealisierten Bild des Emigranten der modernen Literatur ähnlich wird. In der vorliegenden Arbeit möchte ich den Roman Der Verschollene (1912–1914), der bisher in der Forschung oft als typisches Beispiel einer deterritorialisierten Literatur mit einem nomadenhaften Helden gelesen wurde, anders zu lesen. Der Protagonist Karl Roßmann verhält sich danach nicht so sehr wie ein eigentlicher Emigrant, sondern vielmehr wie ein Tourist. Er sieht, was ihm sein Onkel Jakob vorwirft, die Großstädte in Amerika stets aus dem Blickwinkel eines „Vergnügungsreisenden“. Dadurch, dass der Leser mit der Hauptfigur diese Perspektive teilt, entsteht der durchgehend bewegliche und schwebende Eindruck dieses Romans. Auch im Vergleich mit dem Reisebericht Amerika — heute und morgen (1912) von Arthur Holitscher, einer der wichtigsten Vorlagen des Romans, tritt der touristenhafte Charakter Karl Roßmanns deutlich zutage. Während Holitscher in seinem Reisebericht die Integration der – vor allem jüdischen – Immigranten aus vielen Ländern in die amerikanische Gesellschaft plastisch darstellt, scheitert der von allem Jüdischen „emanzipiert“ habende Held Kafkas gerade bei diesem Integrationsprozess, weil er nicht imstande ist, die Position eines Touristen aufzugeben und sich wie ein wirklicher Immigrant zu verhalten.
2 0 0 0 『砂の女』論 : 欲望の物語
- 著者
- 宗 新悟
- 出版者
- 東アジア日本語教育・日本文化研究学会
- 雑誌
- 東アジア日本語教育・日本文化研究 (ISSN:13458892)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.371-386, 2015-03
- 著者
- Masamitsu Nakayama Shinichi Goto Shinya Goto
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF BIORHEOLOGY
- 雑誌
- Journal of Biorheology (ISSN:18670466)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.68-75, 2022 (Released:2022-10-25)
- 参考文献数
- 42
A1 domain of von Willebrand factor (VWF) binding with platelet glycoprotein (GP) Ibα play crucial roles in platelet adhesion and subsequent passive shape changes in the platelets such as pseudopod formation under high wall shear rate conditions. However, the effects of specific inhibitors of VWF binding with GPIbα on the length of pseudopods supporting platelet adhesion on VWF are still to be elucidated. Here we measured the length of pseudopods in the presence of VWF-GPIbα inhibitor of caplacizumab. The length of pseudopods was 6.5 ± 0.2 μm (mean ± 95% confidential interval [CI]) and 6.9 ± 0.2 μm (mean ± 95% CI) at 100 and 200 nM of caplacizumab concentrations and was longer than those formed in its absence (5.2 ± 0.2 μm, p < 0.05). Our experiments also revealed that the surface area coverage by platelets in the presence of caplacizumab at a concentration of 200 nM of 26.1 ± 6.4% after 60-second blood perfusion was smaller than its absence (45.2 ± 7.5%, p < 0.05). Our results suggest that fewer numbers of VWF-GPIbα bonds generating larger binding force with a longer length of pseudopods, support the platelet adhesion on VWF in the presence of caplacizumab at a wall shear rate of 1,500 s–1.
- 著者
- 藤田 昌也 松見 淳子
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.67-81, 2009-01-31 (Released:2019-04-06)
本研究では、3名の自閉症児の事例を通して、大学生に機軸反応訓練(Pivotal Response Treatments:PRT)を指導することにより、遊び場面で自閉症児と適切な相互作用を形成することができるかを検討した。大学生と自閉症児が1対1のペアとなる遊び場面を設け、4名の大学生に対して教示、モデリング、ロールプレイ、パフォーマンスフィードバックを用いてPRTの指導を行った。標的行動は自閉症児の社会的行動(相互作用行動と働きかけ行動)と大学生のPRT行動とし、遊び場面における標的行動の変化を観察した。その結果、3名の大学生のPRT行動は増加し、さまざまな遊びを通して3名のうち2名の自閉症児との相互作用を形成することができた。相互作用が増えても自閉症児からの働きかけ行動を引き出すことができなかったことは、今後の課題として残された。
2 0 0 0 OA Breen and Goldthorpeの相対的リスク回避仮説の検証
- 著者
- 藤原 翔
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.18-35, 2011-06-30 (Released:2013-03-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 2 6
本稿の目的は,Breen and Goldthorpe(1997)の教育達成の階級・階層間格差に関する理論を取り上げ,その中心となる相対的リスク回避仮説の日本社会における妥当性を検証することである.相対的リスク回避仮説によれば,子どもとその親は,子どもが少なくとも親と同程度の階級・階層に到達することを期待し,そのために必要とされる学歴を取得しようとする.その結果,出身階級・階層によって目標とする教育達成の水準が異なり,教育達成の階級・階層間格差が生じるのである.この仮説を検証するため,パネルデータを用いて計量分析を行った結果,(1)父親の職業は父親が子どもに期待する職業に影響を与えていること,(2)父親が子どもに期待する職業は父親が子どもに期待する教育に影響を与えていること,(3)父親が子どもに期待する教育は子どもの教育達成に影響を与えていることが示された.しかし,子どもへの教育期待の形成に対する父親の職業の影響を,子どもへの職業期待は大きく媒介しておらず,また,教育達成に対する父親の職業の影響を子どもに対する教育期待は大きく媒介してはおらず,これらの期待の効果は付加的なものであった.これらの結果から相対的リスク回避が教育達成の階級・階層間格差を説明するうえで中心的な役割を果たすという彼らの主張は支持されず,相対的リスク回避仮説は支持されなかった.
2 0 0 0 OA 法人処罰と刑法理論
- 著者
- 樋口 亮介
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.190-203, 2007-02-10 (Released:2020-11-05)
2 0 0 0 OA ロイヤルウィング (地図にないレストラン) (<特集>グルメ船)
- 著者
- ニッポン・シーライン株式会社
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- らん:纜 (ISSN:09160981)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.25-26, 1990-12-30 (Released:2018-02-24)
本船ロイヤルウィング号は,関西汽船株式会社が建造がした,阪神と別府を結ぶ瀬戸内海の新婚旅行ルートに就航していた『くれない丸』を動く海上レストランとして,大改造したものです. 首都圏では初めての,横浜港より東京湾内への洋上ラストラン船であり,平成元年3月より,藤木企業グループがマリンレジャー関連会社ニッポンシーラインを設立し,運行を開始したものです.
2 0 0 0 OA 鉄のコーティングは水稲の初冬直播き栽培における出芽率を向上させる
- 著者
- 及川 聡子 西 政佳 由比 進 柏木 純一 中島 大賢 市川 伸次 木村 利行 大平 陽一 長菅 輝義 黒田 榮喜 松波 麻耶 下野 裕之
- 出版者
- 日本作物学会
- 雑誌
- 日本作物学会紀事 (ISSN:00111848)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.4, pp.259-267, 2019-10-05 (Released:2019-11-12)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
寒冷地における水稲栽培の作期拡大を目的として,雪解け後の春作業の制約を受けない初冬播き乾田直播栽培の可能性が検討されている.水稲の初冬直播き栽培の実用化においては,出芽率の向上が極めて重要な課題である.本研究では,初冬直播き栽培での出芽率向上のため,種子表面へのコーティング素材 3種類(鉄,カルパー,デンプン)を検討した.2016/2017年に岩手県において,初冬直播き栽培での出芽率は無コーティングでは2%に低下するのに対して,3つの素材のうち鉄をコーティングした場合のみ24%まで有意に向上した.鉄のコーティングによる出芽率の向上効果を2017/2018年に4品種(ひとめぼれ,まっしぐら,あきたこまち,萌えみのり)について検討した結果,無コーティングでは1~3%であった出芽率が鉄のコーティングによって11~30%に有意に向上した.岩手県以外の4地点(北海道,青森県,秋田県,三重県)でも,同様の結果が得られた.以上,種子表面への鉄のコーティングが初冬直播き栽培での出芽率向上に高い効果を示すことを明らかにした.