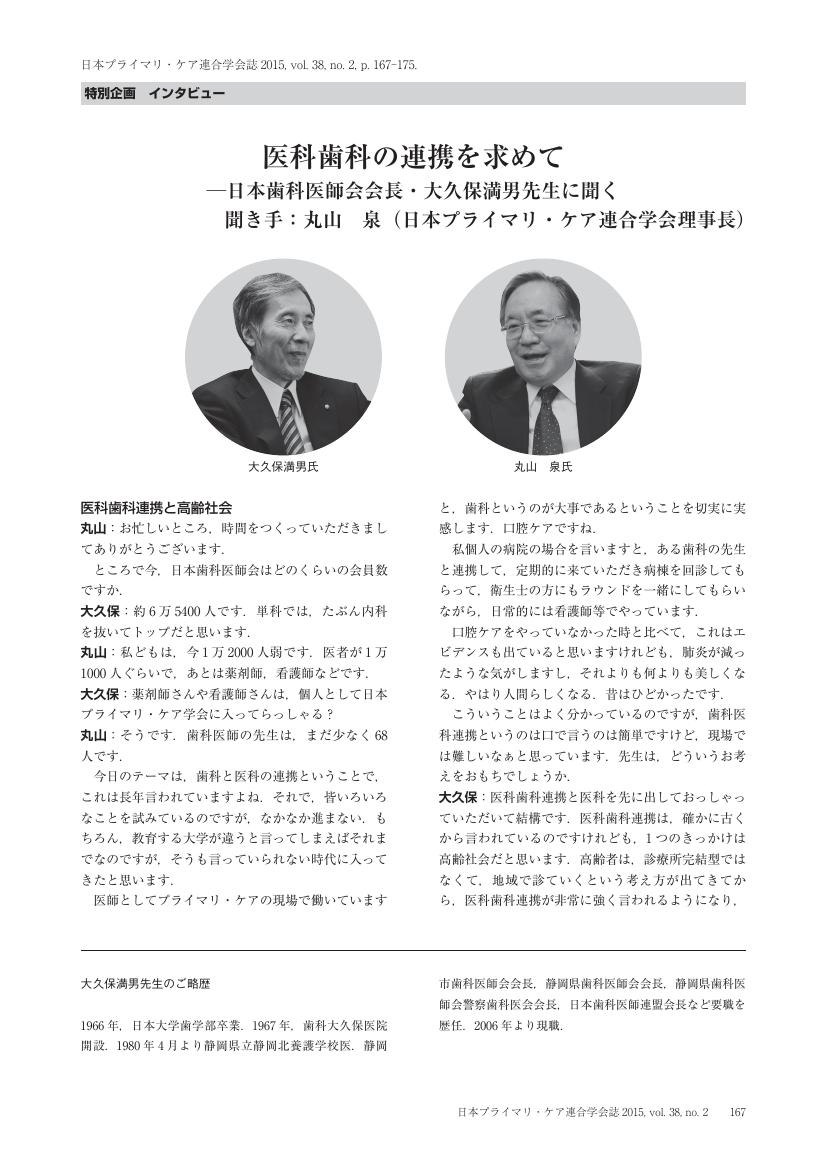4 0 0 0 日本行動分析学会「体罰」に反対する声明
4 0 0 0 OA 異なる学問分野のコーパスを利用した専門用語抽出手法の提案
- 著者
- 久保 順子 辻 慶太 杉本 重雄
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.15-31, 2010-02-26 (Released:2010-04-04)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
コンピュータを使用した専門用語自動抽出は,従来,対象とする専門分野のテキストコーパスのみをデータとして行っているものが多かった.しかし,専門用語の特徴として,対象分野のコーパスに頻出し,対象分野以外の他分野コーパスにはあまり多く出現しない点が挙げられる.そこで本研究では,対象分野コーパスと他分野コーパスとの用語の出現率の差を考慮した手法を提案する.実験では,女性学のテキストを対象分野のコーパスとして使用し,他分野のコーパスとして39分野のテキストを使用した.実験の結果,従来の代表的手法よりもかなり高い精度で用語が抽出できることが明らかとなった.また39分野のテキストから任意のテキストを選び他分野コーパスとして用いてコーパスの規模を縮小できるか実験を行った.その結果,対象分野と類似した分野のテキストを用いることで,39分野すべてのテキストを用いた場合の抽出精度・再現率に近づけることができた.
- 著者
- 梶本 修身 久保 行理 西川 和男 川添 尚子 杉野 友啓
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.19-30, 2012 (Released:2012-04-06)
- 参考文献数
- 15
本試験では,プラズマクラスターイオンのダニアレルゲン低減による通年性アレルギー性鼻炎および疲労に対する効果について検証するため,健常成人男女を対象としたランダム化二重盲検 2 試験区クロスオーバー試験を実施した.ヤケヒョウヒダニ特異的 IgE 陽性であり,ハウスダストによるアレルギー性鼻炎の諸症状を有する 13 名において,プラズマクラスターイオン 2.5 万個/cm3 またはイオンなしの試験室で,ダニアレルゲンを播種し 4 時間の精神負荷作業を実施した.その後,試験室外で 2 時間の回復期を設定した. その結果,プラズマクラスターイオンはダニアレルゲンを 80~90%低減することにより,アレルギー性鼻炎の症状である鼻づまりを緩和,QOL の低下を抑制し,通年性アレルギー性鼻炎に対して効果を有すること,さらに精神作業負荷中のパフォーマンスの低下を抑制し,疲労に対しても効果有することが明らかとなった.
4 0 0 0 OA 福島第一原子力発電所近傍における事故5年後の土壌中放射性物質の調査初期結果
- 著者
- 箕輪 はるか 北 和之 篠原 厚 河津 賢澄 二宮 和彦 稲井 優希 大槻 勤 木野 康志 小荒井 一真 齊藤 敬 佐藤 志彦 末木 啓介 高宮 幸一 竹内 幸生 土井 妙子 上杉 正樹 遠藤 暁 奥村 真吾 小野 貴大 小野崎 晴佳 勝見 尚也 神田 晃充 グエン タットタン 久保 謙哉 金野 俊太郎 鈴木 杏菜 鈴木 正敏 鈴木 健嗣 髙橋 賢臣 竹中 聡汰 張 子見 中井 泉 中村 駿介 南部 明弘 西山 雄大 西山 純平 福田 大輔 藤井 健悟 藤田 将史 宮澤 直希 村野井 友 森口 祐一 谷田貝 亜紀代 山守 航平 横山 明彦 吉田 剛 吉村 崇
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2017
- 巻号頁・発行日
- 2017-03-10
【はじめに】日本地球惑星科学連合および日本放射化学会を中心とした研究グループにより、福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質の陸域での大規模な調査が2011年6月に実施された。事故より5年が経過した2016年、その調査結果をふまえ放射性物質の移行過程の解明および現在の汚染状況の把握を目的として本研究プロジェクトを実施した。2016年6月から9月にかけて、のべ9日間176名により、帰還困難区域を中心とする福島第一原子力発電所近傍105箇所において、空間線量率の測定および土壌の採取を行った。プロジェクトの概要については別の講演にて報告するが、本講演では福島県双葉郡大熊町・双葉町の土壌中の放射性セシウム134Csおよび137Csのインベントリ、土壌深部への移行、134Cs/137Cs濃度比、また空間線量率との相関についての評価を報告する。【試料と測定】2016年6・7月に福島県双葉郡大熊町・双葉町の帰還困難区域内で未除染の公共施設36地点から深さ5 cm表層土壌を各地点5試料ずつ採取した。試料は深さ0-2.5 cmと2.5-5 cmの二つに分割し、乾燥処理後U8容器に充填し、Ge半導体検出器を用いてγ線スペクトルを測定し、放射性物質を定量した。【結果と考察】137Csのインベントリを航空機による空間線量率の地図に重ねたプロットを図1に示す。最大濃度はインベントリで137Csが68400kBq/m2、比放射能で1180kBq/kg・dryであった。インベントリは空間線量率との明確な相関がみられた。深部土壌(深さ2.5-5.0 cm)放射能/浅部土壌(深さ0-2.5 cm)放射能の比はおおむね1以下で表層の値の高い試料が多かったが、試料ごとの差が大きかった。また原子力発電所より北北西方向に134Cs/137Cs濃度比が0.87-0.93と明確に低い値を持つ地点が存在した。
4 0 0 0 飯に汁をかける食法の発展と展開
- 著者
- 石川 恵美 佐藤 幸子 大久保 洋子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.25, 2013
【目的】飯に水や湯をかけて食べる方法は、奈良・平安迄遡る。その後、煎茶をかけて食べる「茶漬け」が出現した。それは比較的あたらしく江戸時代に普及したものである。現在は漬茶け専門店もあり、茶のかわりにだし汁をかけても「茶漬け」としている。飯に汁をかける食法がどのように発展、展開していたのかを探ることが本報告の目的である。【方法】文献調査:通史資料として『古事類苑』、近世資料として『守貞謾稿』、料理本等現在状況調査には市場統計出版物などを対象とした。【結果】平安時代には飯に水や湯をかけて食べる記録がみられる。その後、飯に汁をかける食法は武士層などの酒宴の後に用いられている。江戸末期の『守貞謾稿』には庶民の日常食に言及し、京阪は朝食、江戸は夕食に茶漬けとしている。煎茶の普及がそれまでの水や湯をかけていたものから茶漬けに発展した。水と茶の品質にもこだわっていた話が料亭での茶漬けとして伝わっている。一方、江戸の料理書『名飯部類』には86品中45品が出汁や煎茶をかける物として記載されている。近代に入り、永谷園が1941年に刻み海苔に抹茶や塩を加えた「海苔茶」を発売、1952年に「お茶漬け海苔」と商品名にお茶漬を取り上げ、お茶漬がより日常的なものに発展した。懐石料理においては最後に飯に湯桶にお焦げを入れた湯が添えられ、食法が決められている。現在は外食店にだし汁を飯にかけて供する店名にお茶漬けを採用している現象が出現している。飯に汁をかける食法の総称として「お茶漬け」という言語が使用されるに至っていると言ってよい。
4 0 0 0 暗黒界に留置せる金魚
- 著者
- 久保田 一男
- 出版者
- 社団法人日本動物学会
- 雑誌
- 動物学雑誌 (ISSN:00445118)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.280, pp.97-98, 1912-03-15
4 0 0 0 OA 夜勤疲労を回復促進させる健康生成要因の解明
- 著者
- 久保 智英
- 出版者
- 作業条件適応研究グループ
- 雑誌
- 若手研究(スタートアップ)
- 巻号頁・発行日
- 2008
疲労の回復は勤務中の手休めや休憩時にも生じるが、疲労が回復する大きな機会は勤務と勤務の間の余暇にある。しかし、これまで、どのような余暇の過ごし方が疲労回復に効果的であるのか、とりわけ昼夜の逆転が頻繁に起こる交代制勤務者に焦点を当てた知見は数少ない。本研究の目的は、健康生成論的な観点より、交代制勤務に従事する看護師を対象として、夜勤による疲労回復と余暇の過ごし方の関係を明らかにすることであった。
4 0 0 0 OA Lobatolampea tetragona (クシクラゲ類)は南日本に広く分布する
- 著者
- 久保田 信 山田 守彦 築地新 光子 峯水 亮 多留 聖典 奥田 和美
- 出版者
- 黒潮生物研究財団
- 雑誌
- Kuroshio Biosphere (ISSN:13492705)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.35-39, 2013-03
Lobatolampea tetragona Horita, 2000 (Ctenophora) was found recently in various localities in Japan after previous record made in 2008, extending both northwards (Odaiba, Tokyo Bay) and southwards (Ishigaki Island, Okinawa Prefecture). All these observation records of this species, particularly of the largest individual in each locality, up to ca 50 mm in width, is summarized. Geographic distribution is mapped for this endemic species
4 0 0 0 OA 明治後期における学生風紀頽廃問題と徳育振興政策
- 著者
- 久保田 英助
- 出版者
- 早稲田大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院 教育学研究科紀要 別冊 (ISSN:13402218)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.1-11, 2004-09-30
4 0 0 0 OA 徳川幕府刑法の特色と概況 : 殺し、盗み、火付の事例
- 著者
- 大久保 治男
- 出版者
- 武蔵野学院大学
- 雑誌
- 武蔵野学院大学大学院研究紀要 (ISSN:18828515)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.7-15, 2008
本稿は「日本文化論」(持講を含む)を講述して行くに付、就中、日本法文化史的側面のうちで徳川幕藩体制下の刑事法分野における特色、刑罰体系、犯罪の事例(今回は殺人、盗罪、放火についてのみ)裁判制度等を理解する上で、最低限度知っていなければならない事項の概況について記述したものである。これは、前々よりその必要性を感じていた受講生の便宜のために用意したものである。拙著の「日本法制史概説」(芦書房)「日本法制史」(高文堂出版社)「公事方御定書百ヶ条」(高文堂出版社)「日本法制史史料60選」(芦書房)「江戸の犯罪と刑罰」(高文堂出版社)等の自著を基盤に拙者がまとめ記述した別冊歴史読本特別増刷「鬼平犯科帳のすべて」(新人物往来社)収録の「犯罪類型別・大江戸犯罪録」の内、前半よりの一部加筆変更して引用したものである。尚、「殺人」「盗罪」「放火」についての犯罪に関する具体的事件内容や適用刑罰については、総て、「御仕置例類集」「徳川禁令考」に収録してあるもの(原文は漢文調の幕府公用文)を筆者が現代文的に訳して引用しているものである。一部難解の処はニュアンスを加えて詳述・加筆してある処もある。
4 0 0 0 OA 幕末政治と政権委任問題 : 大政奉還の研究序説
- 著者
- 大久保 利謙
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- 史苑 (ISSN:03869318)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.1-20, 1959-06
4 0 0 0 英国産業革命史重要文献所在目録
- 著者
- 呰上勝哉, 大久保逸雄 共編
- 出版者
- [図書館職員養成所]
- 巻号頁・発行日
- 1961
4 0 0 0 OA 1F12 日本のアニメーションスタジオにおけるクラフト的生産体制 : 技術導入が分業体制に与える影響の歴史的考察(<ホットイシュー>知的資産経営(1),一般講演,第22回年次学術大会)
- 著者
- 久保 友香 七丈 直弘 馬場 靖憲
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 年次学術大会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.226-229, 2007-10-27
4 0 0 0 OA 国文研ニューズ No.20 SUMMER 2010
- 著者
- 谷川 惠一 久保木 秀夫 青田 寿美 山田 哲好 伊藤 鉄也
- 出版者
- 人間文化研究機構国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文研ニューズ = NIJL News (ISSN:18831931)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.1-17, 2010-08-31
●メッセージ国文学研究資料館の共同研究●研究ノート国文学研究資料館蔵古筆手鑑2点の紹介 その2『早稲田大学文学講義』特別附録「西鶴織留輪講」について(承前)平成21(2009)年度新収陸奥国弘前藩庁における文書管理史料紹介●トピックス第5回 インド日本文学会の報告平成22年度童休み子ども見学デー第3回日本古典文学学術賞受賞者の決定人間文化研究樹織璽携展示「チベットボン教の神がみ」連続講演「江戸文化再考」サテライト講座参加募集第34回国際日本文学研究集会総研大日本文学研究専攻博士後期課程 入試説明会のご案内表紙絵紹介『津軽家文書』
4 0 0 0 116 広島旧陸軍被服支廠の耐震対策に関する振動測定実験
- 著者
- 李 亮 柴戸 啓太 寺本 篤史 大久保 孝昭 荒木 秀夫 今本 啓一 楠 浩一
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会中国支部研究報告集
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.61-64, 2015-03
4 0 0 0 1024 広島県旧陸軍被服支廠倉庫の経年劣化調査(材料施工)
4 0 0 0 OA 図書館スタッフによる学修支援の実践,および事後評価 : 「プレゼン入門:話す基本技術」
- 著者
- 久保山 健 堀 一成 坂尻 彰宏 クボヤマ タケシ ホリ カズナリ サカジリ アキヒロ Kuboyama Takeshi Hori Kazunari Sakajiri Akihiro
- 出版者
- 大阪大学全学教育推進機構
- 雑誌
- 大阪大学高等教育研究 (ISSN:21876002)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.33-43, 2015-03-31
This paper describes a basic lecture on presentation as extracurricular education at the Osaka University Library, and the follow-up surveys to the lecture. Many university libraries in Japan have been working on learning support for years. Osaka University Library and the Center for Education in Liberal Arts and Sciences have been cooperating closely to implement writing support activities as extracurricular education since 2010. In 2011, a lecture on logical speaking was launched. The goal of the lecture was learning basic skills for logical speaking. According to questionnaire survey which was carried out after each class, the lecture seemed quite useful for participants. In 2014, the follow-up surveys were conducted to evaluate how beneficial the lectures proved for the participants. It is understood that the participants gained considerable benefit from the lecture. This paper, firstly offers the details of “Introduction to Presentation: Basic Skills for Logical Speaking,” and then describes the result of the follow-up surveys. The lecture was delivered by the first author of this paper.
4 0 0 0 OA 医科歯科の連携を求めて
- 著者
- 大久保 満男
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.167-175, 2015 (Released:2015-06-25)
4 0 0 0 OA 握力発揮が柔道選手の防御動作反応時間に及ぼす影響
- 著者
- 久保田 浩史 渡辺 直勇 渡辺 涼子 佐藤 武尊 山本 浩貴
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.99-104, 2014-01-31 (Released:2015-01-31)
- 参考文献数
- 18
It is possible that quick reaction of the whole body is delayed during exerting muscle strength, and this effect is larger when exerting larger muscle strength. This study aimed to examine the defensive motion reaction time in judo competitors, while exerting different handgrip strengths. Subjects were 46 young males (mean age, 19.7 ± 1.3 years; mean height, 172.5 ± 4.6 cm; and mean weight, 79.0 ± 13.9 kg) with black belt in judo. They performed the defensive motion reaction time test exerting handgrip strength. They placed only one leg on a mat with a device measuring the whole body reaction time, grasped a grip strength device with one hand, and reacted to a light stimulus under each condition (different grip strength levels): 0%, 20-30%, 50-60%, or >80% of their maximal handgrip strength. One way analysis of variance was used to evaluate the significant differences among the means of the defensive motion reaction time values for each condition. On statistical analysis, the reaction time was significantly longer in the 20-30%, 50-60%, and the >80% conditions than in the 0% condition, and significantly longer in the >80% condition than in the 20-30% condition. The size of difference (effect size) between the 0% and the 20-30% conditions was small, and that between the 0% and the 50-60% conditions were moderate, and that between the 0% and the >80% conditions were moderate, and it tended to be larger with increasing handgrip strength exertion. Moreover, as the handgrip strength became larger, also the reaction time was significantly delayed (Y=9.6X+332.6). In conclusion, the defensive motion reaction time in judo competitors is delayed with handgrip exertion, and the delay is larger when larger strength is exerted.