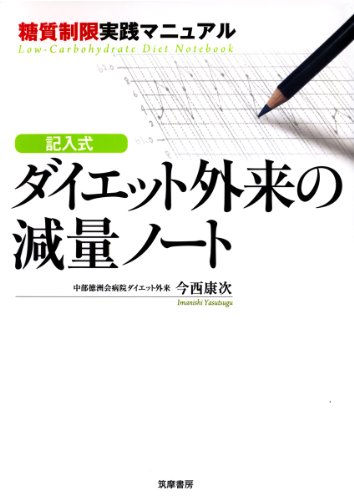2 0 0 0 IR シンポジウム グローバリゼーションと現代歴史学 シンポジウムへの経過
この研究は、留学生センターで初めて日本語を学ぶ国費研究留学生のための学習環境を開発することが目的である。彼らは来日から授業開始までの間、少なくとも一週間自由な時間がある。そして、未知である日本文化と日本語に対する学習動機が高いことがわかっている。そこで、この期間に彼らが日本語を学習する場所、学習する教材、学習を支援する人の3つの学習リソースを含んだ学習環境を開発した。学習場所には、留学生の宿舎、留学生センター、大学生協の店などを含み、支援者には日本語教師やそれぞれの場所で働く人々を含む。教材は、印刷教材とビデオ教材、マルチメディアによるひらがな学習教材がある。教材の項目は、以下の4項目である。1 挨拶おはようございます:こんにちは:こんばんは:行ってきます:ただいま:しつれいします:しつれいしました2 自己紹介はじめまして。〜です。〜とよんでください。〜からきました。専門は〜です。どうぞ、よろしくおねがいします。2 買い物ちょっとすいません:〜、ありますか:これ、いくらですか:じゃあ、これお願いします。すいません、またきます:どうも。4 質問をするこれは、なんですか:これは、日本語でなんですか:そうですか留学生は、熊本に来た翌日、留学生センターでオリエンテーションがある。キャンパスの案内や一週間後に始まる日本語コースの説明の他、今回開発した教材での学習方法を説明する。学生は、留学生センターでは、コンピュータとビデオを見たり、教師やボランティアスタッフと練習し、宿舎では、印刷教材などで練習する。こうした学習によって、日本語コースが始まるまでの間に、日本語学習のためのレディネスが高められると考えている。こうした学習の過程は、印刷教材やビデオ、写真等で記録する。日本語コース開始時に日本語教師がその記録を参照することで、その学習者の特徴や学習のレディネスについて理解を深めることができる。
2 0 0 0 OA 芦生研究林におけるシカ排除柵によるススキ群落の回復過程
- 著者
- 石原 正恵 今西 亜友美 阪口 翔太 福澤 加里部 向 昌宏 吉岡 崇仁
- 出版者
- 京都大学大学院農学研究科附属演習林
- 雑誌
- 森林研究 = Forest research, Kyoto (ISSN:13444174)
- 巻号頁・発行日
- no.78, pp.39-56, 2012-09 (Released:2013-10-08)
近年,日本各地でシカの採食による草地の植生改変が生じている。芦生研究林長治谷作業小屋の開地ではススキを主とする草本群落が見られたが,2007年以降シカの採食により衰退した。防鹿柵によるススキ群落の種多様性および現存量の回復過程を把握するため,柵設置1~3年後に柵内外で植生調査および刈り取り調査を行った。柵設置1年後から柵内は柵外に比べ種多様性が高く,機能形質を元に種を分類した機能群の多様性も高くなり,種組成にも明瞭な違いが見られた。調査地近辺で2003年に見られなくなったと報告されていた種を含む77種が柵内で見られた。群落高,植被率および現存量も2年後には一般的なススキ草地と同程度まで増加した。このようにススキ群落の多様性と現存量が早期に回復したのは,ススキ群落の衰退直後に柵を設置したためと考えられた。柵内では背丈の高いススキ,オカトラノオや小高木・低木種が優占し,一部の背丈の低い分枝型広葉草本は競争排除され,高木種の定着も見られなかったため,今後もしばらくはススキ群落が続き,多様性が低下すると予想された。柵外では不嗜好性のイグサと分枝型一年生広葉草本のトキンソウの被度が増加し,植生の単純化が進行した。
2 0 0 0 OA 日本古典籍における【表記情報学】の基盤構築に関する研究
- 著者
- 今西 裕一郎 伊藤 鉄也 野本 忠司 江戸 英雄 相田 満 海野 圭介 加藤 洋介 斎藤 達哉 田坂 憲二 田村 隆 中村 一夫 村上 征勝 横井 孝 上野 英子 吉野 諒三 後藤 康文 坂本 信道
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2010-04-01
本研究課題は、『源氏物語』における写本の単語表記という問題から、さらに大きな日本語日本文化の表記の問題を浮かび上がらせることとなった。当初の平仮名や漢字表記の違いというミクロの視点が、テキストにおける漢字表記の増加現象、またその逆の、漢字主体テキストの平仮名テキスト化という現象へと展開する過程で、テキストにおける漢字使用の変貌も「表記情報学」のテーマとなることが明らかになった。「文字の表記」は「文化の表記」「思想の表記」へとつながっている。「何が書かれているか」という始発点から「如何に書かれているか」に至る「表記情報学」は、今後も持続させるべき「如何に」の研究なのである。
2 0 0 0 アミ語の記述言語学的研究
4月にイギリスで行われた国際学会、International Conference on Tense,Aspect,Modality and Evidentialityにおいて、アミ語の動詞・名詞と状態アスペクトの関係について学会発表を行った。ここではフィールド調査によって得たデータをもとに、品詞とアスペクトの関係について論じた。その後帰国してすぐに、浜松で行われた学会The English Linguistic Society of Japan 4^<th> International Spring Forumに参加し、アミ語のデータも交えた複数の言語における使役文の特徴について、類型論的な研究発表をおこなった。また、5月には東京外国語大学で行われた第1回文法研究ワークショップ「『形容詞』をめぐる諸問題」で、上記のイギリスで発表した内容に改訂をくわえたものの発表を行った。7月には香港で行われたAssociation for Linguistic Typology 9^<th> Biennial Conferenceで、「雨降り」「肩たたき」などの複合語や、名詞を動詞に組み込む「抱合」と言われる現象について発表を行った。これらの現象では自動詞の主語と他動詞の目的語のみが許容され、他動詞の主語は許容されないという現象が世界各地の言語で見られる。この発表ではなぜそのような現象が世界の言語で現れるのか、その原因について考察を行った。11月には第143回言語学会において、『アミ語の母音連続と挿入規則』というタイトルの口頭発表を行った。この発表では、フィールド調査で得たデータをもとに、従来音素として考えられてきたアミ語の声門閉鎖音を音素ではないと分析し、音素同士の関係と挿入規則のみで声門閉鎖音の存在を説明する試みを行った。また、上記の発表活動と並行して、手持ちのデータの分析(音声データの書き起こしなど)と、博士論文の執筆を行った。
2 0 0 0 記入式ダイエット外来の減量ノート : 糖質制限実践マニュアル
2 0 0 0 遺伝子系統樹・種系統樹データベースの開発
本研究の目的は,遺伝子系統樹と種系統樹のデータベースを試作することである。3年のあいだに,以下のものについて,すべての系統樹の図の入力を行った。斎藤が担当したのはMolecular Phylogenetics and Evolutionは1992年(第1巻)〜1997年(第8巻),Molecu1cu Biology and Evolutionは1983年(第1巻)〜1998年(第15巻),Journa1 of Molecular Evolutionは1993年(第36巻)〜1998年(第46巻),田村が担当したのは遺伝学雑誌/Genes and Genetic Systemsが1981年(第56巻)〜1997年(第72巻),Geneticsが1980年(第95巻)〜1997年(第146巻),Zoological Scienceが1984年(第1巻)〜1997年(第14巻),今西が担当したのはNatreが1991年(第349巻)〜1995年(第376巻),Scienceが1991年(第254巻)〜1995年(第267巻),PNASが1991年(第88巻)〜1995年(第92巻),伊藤が担当したしたのはAmerican Journal of Botanyが1988年(第75巻)〜1997年(第84巻),Evolutionが1990年(第44巻)〜19956年(第50巻),Systematic Botanyが1990年(第15巻)〜1995年(第20巻)である。この系統樹データベース"Jung1e"は斎藤が本科研費で購入したワークステーションに移して集中管理しており,WWWですでに公開している(URL=http://smi1er.1ab.nig.ac.jp/jung1e/ungle.htme)。著者名,諭文名,図の題名などのテキストを検索する子システムを現在準備中である。CDROMでも配布する予定である。
2 0 0 0 OA 巨椋池干拓地およびその周辺地域の現存植生について
- 著者
- 松本 仁 今西 亜友美 今西 純一 森本 幸裕
- 出版者
- 日本景観生態学会
- 雑誌
- 景観生態学 (ISSN:18800092)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.79-88, 2012-02-15 (Released:2012-04-25)
- 参考文献数
- 15
The Oguraike area is now planned for natural environmental conservation and restoration under the Grand Design about Urban Environment Infrastructure in the Kinki Region. Actual vegetation at the Ograike area is expected as a seed source to conserve and restore wetland environment. The purpose of this study was to reveal species composition of actual vegetation in river bank of the Uji River, the Yokoojinuma and the Oguraike drained lands, Kyoto prefecture, Japan. Five quadrats were placed in these areas and all the vascular plant species were recorded. Two hundred and eight species including 10 endangered plant species and 71 alien plant species were recorded. Actual vegetation in the river bank of the Uji River and the two drained lands were useful seed sources of floodplain species and wetland species, respectively. Especially, we found the desirable vegetation with only one alien plant species and some endangered plant species at the center part of the river bank of the Uji River.
- 著者
- 阿部 裕輔 鎮西 恒雄 磯山 隆 満渕 邦彦 松浦 弘幸 馬場 一憲 河野 明正 小野 俊哉 望月 修一 孫 艶萍 今西 薫 吉澤 誠 田中 明 内山 賢一 藤正 巌 渥美 和彦 井街 宏
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY FOR ARTIFICIAL ORGANS
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.21-26, 1997-02-15
- 被引用文献数
- 7
1/R制御により、完全置換型人工心臓ヤギで532日の長期生存を得た. 術後経過としては、ポンプ内に血栓を生じたため、左右の血液ポンプを交換したこと、胸部の圧迫壊死層から出血をきたし、貧血の状態となったことなどがあったが、制御は順調に継続できた. 生存期間を通して、血行動態は安定し、右心房圧も低値に保たれていた. 血液生化学データ上も異常は見られず、ホルモン値にも異常は見られなかった. 剖検時に腹水はなく、肉眼的には肝臓病変も見られなかった. また、心拍出量は、大動脈圧とは関係が見られず、総コンダクタンスと相関が見られ、術後2週間および出血後2週間はヘマトクリット値と逆比例の関係が見られたが、それ以外の時期にはヘマトクリット値や総タンパク値とはあまり関係がないなどの興味深い所見も得られた. 本研究により、1/R制御の生理的な長期安定性が確認できた.
2 0 0 0 OA 古代インドの環境論
- 著者
- 原 實 川崎 信定 木村 清孝 デレアヌ フロリン ユベール デュルト 落合 俊典 岡田 真美子 今西 順吉 木村 清孝 末木 文美士 岡田 真美子 ユベール デュルト 田辺 和子 落合 俊典 デレアヌ フロリン 松村 淳子 今西 順吉 津田 眞一 北田 信 清水 洋平 金子 奈央
- 出版者
- (財)東洋文庫
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2006
平成18年度より3年間、「古代インドの環境論」と題し、同学の士を誘って我々の専攻する学問が現代の緊急課題とどの様に関連するかの問題を、真剣に討究する機会を持ち得た事は極めて貴重な体験であった。外国人学者を交えて討論を重ねる間に、我々の問題意識はインド思想や佛教の自然観、地球観にまで拡がって行ったが、それらは現代の環境破壊や無原則な地域開発に警告する所、多大なるものがあった。「温故知新」と言われる所以である
- 著者
- 関根 正人 今西 一男
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・意匠 (ISSN:13414542)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.351-352, 2008-07-20
2 0 0 0 OA Nerine の種間およびヒガンバナ科他属との交雑における種子形成と発芽
2 0 0 0 MCK形振動方程式に対する高精度・硬安定な時間積分法
- 著者
- 藤川 猛 今西 悦二郎
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学會論文集. C編 (ISSN:03875024)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.656, pp.929-934, 2001-04-25
- 被引用文献数
- 1
A precise and stiffly stable time integration method with numerical dissipation is presented for solving MCK type equations of motion. Its algorithm is assumed that acceleration during time step is expressed as a quadratic function. Stability and accuracy are investigated by numerical analysis to find out the best parameter values of the algorithm. Characteristics of this method are compared with other methods such as Newmark, Wilson, HHT-α method, etc, which showed that this method has much better accuracy for low frequency modes, and strong dissipation for high frequency modes. Some calculation examples are shown.
1 0 0 0 OA 生後1年間における育児用品の使用に関する研究:乳児の運動発達の視点から
- 著者
- カルマール 良子 今西 香寿
- 出版者
- Japan Society of Human Growth and Development
- 雑誌
- 発育発達研究 (ISSN:13408682)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.86, pp.44-51, 2020 (Released:2020-05-23)
- 参考文献数
- 26
Previous studies have shown that the use of a baby-walker during the first year after birth of a baby, when the motor skill is most significantly developed, may affect the subsequent development of the child. However, since trends in use of other infant equipment have not been investigated, it is not clear what kind of infant equipment is used at each stage of the infantile development. The present study was usage survey of infant equipment, including those other than baby-walkers, for newborns and infants during their first year of life. The survey was conducted by means of a questionnaire targeting 612 infants in Hyogo, Okayama, and Tottori prefectures in Japan, resulting in 307 valid responses, which have revealed their usage of infant equipment. Some items of infant equipment that are used for a longer time than baby-walkers may restrict infant. While the infant equipment increases the safety of the lives of infants, our data suggests the possibility that those devices may also limit their self-directed, which is important for gross motor development.
1 0 0 0 OA 頸部刺傷による鋭的気管損傷の治療経験
- 著者
- 島貫 茉莉江 戸塚 大輔 中原 奈々 佐藤 陽一郎 今西 順久
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.7, pp.912-920, 2018-07-20 (Released:2018-08-01)
- 参考文献数
- 23
頸部外傷の中でも, 特に気管損傷は気道緊急疾患で迅速な対応を要する. また早期に診断・治療がなされなかった場合, 急性期には皮下気腫の増悪や呼吸障害の出現, 長期的には瘢痕性気道狭窄が生じることがある. 当院で最近経験した3例の鋭的気管損傷例について報告し, その診断・治療について検討した. 3例いずれも刃物による頸部刺傷に起因し, 受傷機転は自傷1例, 他害2例で, いずれも緊急手術にて気管損傷を確認・閉鎖し, 気道の後遺障害を残さず治癒した. 術前に創部触診で気管損傷を直接触知し得たのは1例のみで, 診断にはそのほかの間接的臨床所見が重要と考えられた. 皮下気腫は全例に認められ, 非特異的ではあるが過去の報告に一致して高頻度であった. エアリークは2例に認められ, 気管損傷を強く示唆する重要な所見と考えられた. CT では気管損傷を疑う所見を2例に認めたが, 損傷の部位と程度の評価は困難であった. 損傷部位は他害の2例では胸部気管に位置していたが, いずれも経頸部アプローチにて閉鎖可能であった. 過去の報告を踏まえると, 他害例や胸骨上切痕部に皮膚切創がある場合には胸部気管損傷の可能性を考える必要がある. 鋭的気管損傷においては, 臨床所見および画像診断を合わせても確定診断のみならず損傷の部位や程度の評価に限界があることから, 疑われる場合には, 全身状態が許されれば創部の十分な展開による診断と評価および閉鎖術が勧められる.
1 0 0 0 OA リハビリテーションの枠組みの中で行う嗅覚刺激療法の確立
- 著者
- 金井 健吾 岡 愛子 赤松 摩紀 渡部 佳弘 上斗米 愛実 北村 寛志 今西 順久 野口 佳裕 岡野 光博
- 出版者
- 日本鼻科学会
- 雑誌
- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.300-309, 2023 (Released:2023-07-28)
- 参考文献数
- 26
嗅覚障害は,感冒罹患,鼻副鼻腔の慢性炎症,外傷,薬物や毒物の吸入,神経変性疾患や脳血管疾患などによって生じる。原疾患のコントロールを行うことで改善することもあるが,治療に難渋する症例も経験する。最近では新型コロナウイルス感染症に罹患し嗅覚障害を生じる症例も存在する。嗅覚機能検査として,T&Tオルファクトメーターを用いる基準嗅力検査や静脈性嗅覚検査などが一般的に施行される。嗅覚障害に対する新しい治療法として,患者が嗅素を積極的に嗅ぐことで,嗅覚の再生を促す嗅覚リハビリテーション(嗅覚刺激療法)が注目されており,欧州では安全で有効な治療法として診療に取り入れられている。嗅覚刺激療法は当院倫理審査で承認され,リハビリテーション科医師の指導の下で言語聴覚士が行っている。当院を受診し嗅覚障害と診断された患者を対象として,嗅覚刺激療法を3か月以上行い,治療前後の嗅覚を比較した。1日2回(朝・夕)4種類の嗅素(バラ・レモン・ユーカリ・シナモン)を一つの嗅素につき10秒ずつ嗅ぎ,3か月後には4種類の嗅素をラベンダー・オレンジ・ヒノキ・バニラへ変更している。治療前後の嗅覚の変化において,基準嗅力検査(平均認知域値と検知域値)では有意差は認めなかったが,日常のにおいアンケート,嗅覚に関するQOL質問紙,VASでは有意に改善を認めた。日本人にとって,より有効で統一的なプロトコールが確立されることが期待される。
- 著者
- 今西 ひとみ 森村 繁晴
- 出版者
- 関係性の教育学会
- 雑誌
- 関係性の教育学 (ISSN:13490206)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.57-70, 2023-05-01 (Released:2023-05-24)
- 著者
- 酒井 悠太 斉藤 由理恵 乘越 亮 今西 英雄
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.57-63, 2022 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 10
オリエンタル系ユリ ‘カサブランカ’ の国内産球根を用い,予冷温度と期間を変えてそれに伴うシュートの成長,茎先端部汁液のBrixと糖含有量の変化を調べた後に,球根を–2.0°Cの氷温に移して貯蔵した.それらの球根を7~10か月後に取り出して植え付け,開花調査を行い,長期氷温貯蔵後の障害発生と予冷温度・期間との関係を明らかにしようとした.1°Cの予冷期間を0~20週と変えた場合,予冷期間が12週以上になると,氷温貯蔵後の抑制栽培において開花率の低下と葉の障害発生がみられ,それと茎先端部汁液のスクロース含有量の低下とが関連すること,Brixの変動はスクロースの変動とほぼ一致することがわかった.次に1°C, 6°C, 8°Cおよび12°Cで8週間予冷した後,1°Cに移して10週間貯蔵を続け予冷温度の影響をみたところ,1°Cと6°Cの予冷はBrixと糖の含有量について同じような変動を示し,栽培試験でも葉の障害発生あるいは開花率の低下が認められ,同じように影響することが示された.また1°Cで18週間予冷した後に氷温貯蔵に移した場合,氷温貯蔵期間が8週間長くなると全く開花がみられなくなった.以上の結果,6°C以下の温度で長期間予冷することが,長期氷温貯蔵後の栽培において開花率の低下や葉の障害発生をもたらすことが明らかになった.
1 0 0 0 OA 大同江南の古墳と楽浪王氏との関係(正誤表)
- 著者
- 今西 龍
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = The Toyo Gakuho
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.282, 1912-05
1 0 0 0 OA 大同江南の古墳と楽浪王氏との関係
- 著者
- 今西 龍
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = The Toyo Gakuho
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.96-104, 1912-01