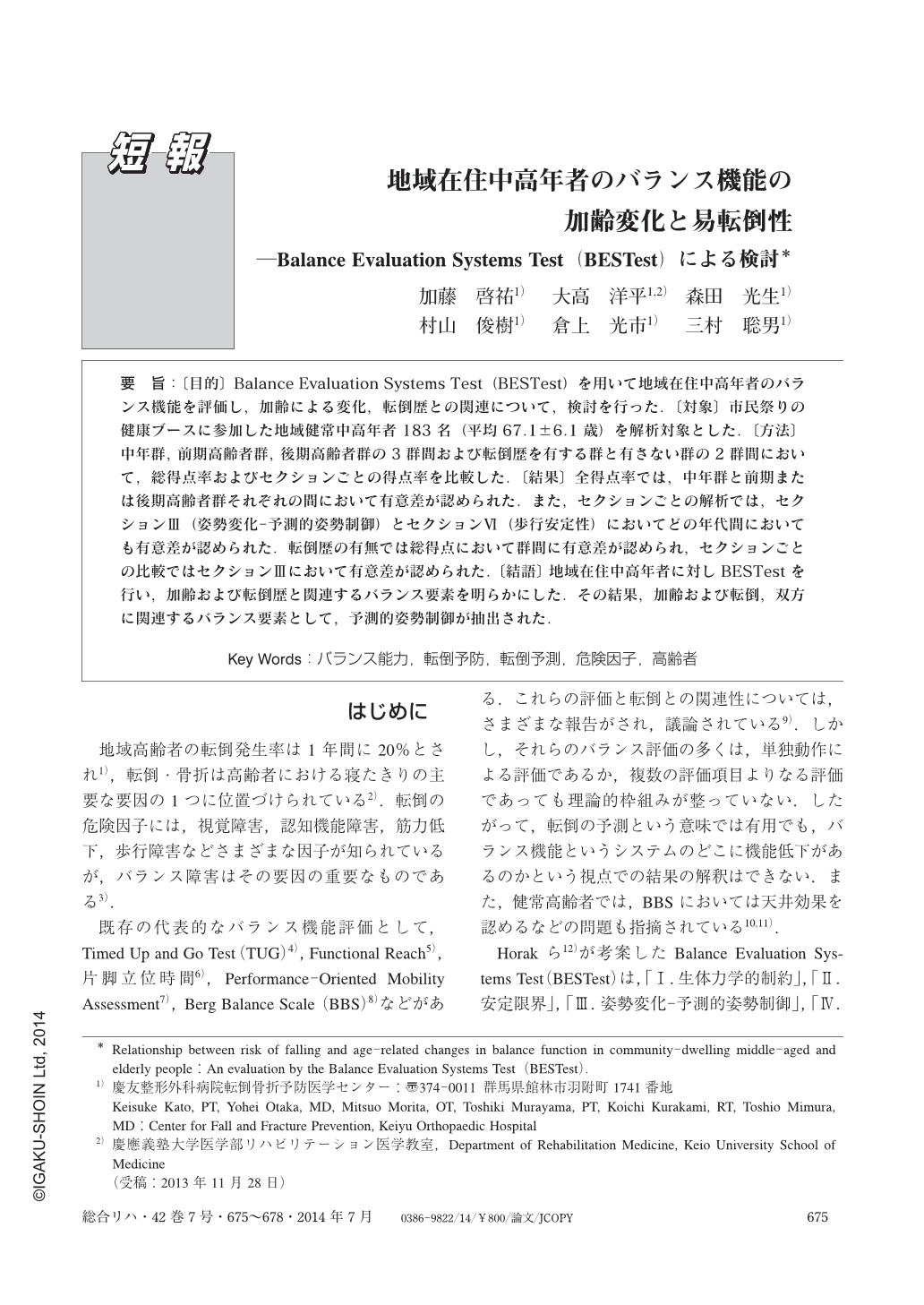1 0 0 0 IR 食品の持つ抗菌性を調べる実験の教材化
- 著者
- 高橋 大輔 鈴木 隆 加藤 良一
- 出版者
- 山形大学
- 雑誌
- 山形大学紀要 教育科学 (ISSN:05134668)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.1-20, 2010-02
要旨 : 植物性食品の抗菌性を簡便に調べることができる実験教材として、(A)YEB寒天培地又はPYG寒天培地の中央に直径10mmの穴を開け、腐葉土からの2倍希釈の上澄み液を培地表面に0.5ml塗布し、その中央の穴に抗菌性食品を約0.3g入れ、それらをシャーレで24時間培養する方法、(B)YEB寒天培地又はPYG寒天培地の中央に直径10mmの穴を開け、納豆からの5倍希釈の上澄み液を培地表面に0.5ml塗布し、その中央の穴に抗菌性食品を約0.3g入れ、それらをシャーレで24時間培養する方法、及び(C)6枚切り又は8枚切りの食パンの耳の部分を切り落とし、さらに1枚の食パンをほぼ均等に4つの四角形の切片にし、その切片の片面のみ腐葉土からの5倍希釈の濾液に浸し、その切片の中央に約0.3gの抗菌性食品を置き、それらを密封容器で5日間培養する方法の3つが簡便で分かりやすいものとして示された。
要旨:〔目的〕Balance Evaluation Systems Test(BESTest)を用いて地域在住中高年者のバランス機能を評価し,加齢による変化,転倒歴との関連について,検討を行った.〔対象〕市民祭りの健康ブースに参加した地域健常中高年者183名(平均67.1±6.1歳)を解析対象とした.〔方法〕中年群,前期高齢者群,後期高齢者群の3群間および転倒歴を有する群と有さない群の2群間において,総得点率およびセクションごとの得点率を比較した.〔結果〕全得点率では,中年群と前期または後期高齢者群それぞれの間において有意差が認められた.また,セクションごとの解析では,セクションⅢ(姿勢変化-予測的姿勢制御)とセクションⅥ(歩行安定性)においてどの年代間においても有意差が認められた.転倒歴の有無では総得点において群間に有意差が認められ,セクションごとの比較ではセクションⅢにおいて有意差が認められた.〔結語〕地域在住中高年者に対しBESTestを行い,加齢および転倒歴と関連するバランス要素を明らかにした.その結果,加齢および転倒,双方に関連するバランス要素として,予測的姿勢制御が抽出された.
- 著者
- 加藤 太郎 板東 杏太 有明 陽佑 勝田 若奈 近藤 夕騎 小笠原 悠 西田 大輔 髙橋 祐二 水野 勝広
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- pp.20022, (Released:2020-11-30)
- 参考文献数
- 18
目的:脊髄小脳変性症(spinocerebellar degeneration:SCD)に対する短期集中リハビリテーション治療(SCD短期集中リハビリテーション)の効果が,先行研究により示されている.しかし,SCD短期集中リハビリテーションの効果検証は,Scale for the Assessment and Rating of Ataxia(SARA)の総得点により報告されており,SARAの下位項目による詳細な検証はなされていない.本研究は,歩行可能なSCD患者の運動失調に対するSCD短期集中リハビリテーションの効果を,SARAの総得点と下位項目得点から検証することを目的とした.方法:対象は,SARAの歩行項目3点以下に該当し,4週間のSCD集中リハビリテーション治療プログラム(SCD集中リハビリテーション)に参加したSCD患者23名(男15名,女8名)とした.評価項目はSARAとし,SCD集中リハビリテーション実施前後に評価を実施した.対象者のSCD集中リハビリテーション実施前後のSARAの総得点および各下位項目得点を,後方視的に解析した.統計はWilcoxonの符号付き順位検定を用いて分析検討し,有意水準は5%とした.結果:SCD集中リハビリテーション実施前後において,総得点および下位項目得点のうち,歩行,立位,踵-すね試験に有意な点数の改善を認めた(p<0.05).一方,下位項目得点で座位,言語障害,指追い試験,鼻-指試験,手の回内・回外運動は有意な点数の改善を認めなかった.結論:本研究の結果は,SCD集中リハビリテーションはSCD患者のSARAにおける総得点と,特に体幹と下肢の運動失調を有意に改善させることを示した.
- 著者
- 鶴田 浩子 田代 淑子 丸茂 貴子 加藤 京子 菅原 哲也 米山 淳子 川井 三恵 金子 昌弘 須賀 万智
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養士会
- 雑誌
- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.12, pp.673-680, 2020 (Released:2020-12-01)
- 参考文献数
- 9
公益財団法人東京都予防医学協会は、人間ドック受診者のサービスの一環として検査終了時に弁当を提供している。2013年度より、食育を目的として弁当のリニューアルと管理栄養士による講話を実施した。併せてアンケートを実施して、結果に基づきサービスを改善するPDCA サイクルを取り入れた。 評価指標は、「満足度」、「講話の参加有無」、「今後も本企画のある人間ドックを受けたいと思うか」の3項目とした。5年間の継続的な取り組みの結果、3項目とも上昇傾向が見られた。PDCA サイクルを回しながら改善の努力を着実に積み重ねたことが、受診者に受け入れられやすい食育の実現につながったと考える。
1 0 0 0 OA 2017年におけるマリンエンジニアリング技術の進歩
1 0 0 0 OA 早強ポルトランドセメントと高炉セメントB種を混合した試製混合セメントの強度性状
- 著者
- 吉本 慎吾 新見 龍男 加藤 弘義 関 卓哉
- 出版者
- 一般社団法人 セメント協会
- 雑誌
- セメント・コンクリート論文集 (ISSN:09163182)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.1, pp.208-213, 2020-03-31 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 5
近年、環境問題として地球温暖化が深刻な問題となっており、普通ポルトランドセメントに比べてCO2排出量が少ない高炉セメントの使用推進が求められる。しかしながら、高炉セメントは初期強度発現性が低いことが課題である。本検討では、高炉セメントの初期強度発現性の改善として早強ポルトランドセメントと高炉セメントB種を混合した試製混合セメントの強度性状について検討を行った。その結果、材齢28日の圧縮強度が普通ポルトランドセメントと同程度となる水セメント比において、高炉セメントB種の混合率が70%未満であれば普通ポルトランドセメントと同程度以上の材齢1日強度を確保可能であり、CO2削減効果についても試算された。
1 0 0 0 OA 内側側頭葉発作における発作時心拍変化に関する研究
- 著者
- 加藤 量広
- 出版者
- Tohoku University
- 巻号頁・発行日
- 2015-03-25
課程
- 著者
- 加藤 孝宏 本多 一行
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経systems (ISSN:18811620)
- 巻号頁・発行日
- no.190, pp.92-97, 2009-02
情報漏洩や不正アクセスなどのニュースが世間を騒がせる昨今,企業や消費者のセキュリティに対する関心が高まってきています。セキュリティに関連する事件を起こすと,顧客からの信用を損なうだけでなく,売り上げの減少や問題に対応するための追加経費の発生などによって,企業の業績にも大きく影響します。セキュリティ対策は,企業全体で取り組むべき問題となってきています。
- 著者
- 玉井 泰子 加藤 久晶 山内 陸平
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.188-189, 2000
The purpose of this study is to identify the individual images of the areas on five private railroad lines in Kansai; Hankyu. Hanshin, keihan, Nankai, Kintetsu. The aim of this paper is to clarify it in terms of the word-image associated with each area, focusing on three types of image-analyses. First, an attempt will be made to explain the structural significance of the individual images that five private railroad line areas have. Secondly, a comparison will be made between subjective images of those people who living along the railroad lines and objective images of those who do not. Finally, the factors forming the individual images of those areas will be shown to be affected by the ' good impressions ' made to people by each image.
1 0 0 0 OA ダクトなし定速プロペラ性能の迅速自動計算法
- 著者
- 安東 茂典 加藤 三千代
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.455, pp.675-679, 1991-12-05 (Released:2010-12-16)
- 参考文献数
- 4
A quick automatic method is presented for computing performance of nonducted propeller with constant revolutional speed. This study is motivated by usefulness for developing WIG vehicles, namely in order to predict propeller data to be used. Results of computation examples show that constant-speed-propellers are considerably robust, viz. insensitive to change of some parameters such as diameter, solidity and rotational speed. It is noteworthy that these well-known properties are confirmed easily and quickly by the present method.
1 0 0 0 信頼性・有効性の視点よりみた経営診断技法の諸問題
- 著者
- 加藤 孝
- 出版者
- 日本経営診断学会
- 雑誌
- 日本経営診断学会年報
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.106-111, 1978
- 著者
- 菅野 重樹 田中 良治 大岡 俊夫 加藤 一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.339-353, 1985
- 被引用文献数
- 13
これからのロボットは, '力作業'だけでなく'情報作業'をも行う能力をもつ必要がある.そこでこの研究では, 鍵盤楽器演奏可能な人間形知能ロボットを開発することにより, 情報作業に必要となる機能である巧緻性, 高速性, 高度の知的能力などを実現することを目的としている.本論文では, そのためのロボットの4肢構成とその制御に焦点をおき開発した鍵盤楽器演奏ロボット'WABOT-2'の運動系について述ベる.<BR>このロボットは, 5本指をもつ両手と, ペダル操作用両足の4肢からなり, その自由度は合計で50である.このような多自由度ロボットは他に例がなく, その制御法が問題となり, また自律制御を行ううえでは, 楽譜情報から4肢の軌道を決定する方法が重要となる.<BR>以上のような制御問題を解決するために, WABOT-2運動系では53個のマイクロプロセッサからなる3重階層構造のコンピュータシステムを構成した.その上位コンピュータシステムは, 楽譜情報処理を担当し, 3種類に分類した知識, (1) 作業対象物, (2) 作業内容, (3) ロボット機構部仕様をもとに, 視覚系より転送される楽譜データから運指・手首位置の決定, 指・腕・足の各関節角度計算を行う.中位コンピュータシステムは, 上位コンピュータシステムで計算された軌道をもとに, 制御用データを下位コンピュータシステムへ出力し, また必要に応じて各自由度の状態をモニタすることにより協調制御を行う.そして, 下位コンピュータシステムは, 各自由度に1チップマイクロコンピュータが置かれており, ソフトウエアサーボをかけている.このようなコンピュータシステムにより, 50自由度の効率良い制御を実現した.<BR>以上の結果, WABOT-2は電子オルガン中級程度の曲について, 楽譜情報を入力するだけで自動的に演奏が可能となった.
1 0 0 0 IR M-3SII 型ロケットにおけるテレメータ・コマンド・集中電源
- 著者
- 林 友直 横山 幸嗣 井上 浩三郎 橋本 正之 河端 征彦 大西 晃 大島 勉 加藤 輝雄 瀬尾 基治 日高 正規
- 出版者
- 宇宙科学研究所
- 雑誌
- 宇宙科学研究所報告. 特集: M-3SII型ロケット(1号機から3号機まで)(第1巻) (ISSN:02859920)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.141-171, 1991-06
M-3SII型ロケットでは, M-3S型と異なり, 新たに装備されたサブブースタSB-735の性能計測等のために, サブブースタにテレメータ送信機を搭載した。また, サブブースタの分離状況を画像伝送するため第2段計器部に画像伝送用テレメータ送信機を搭載し, さらに3号機では新たに開発された第3段モータの性能計測のために, 第3段計器部を設けてテレメータ送信機を搭載する等の大幅なシステム変更がなされている。搭載テレメータ送信機で新規に開発されたのは, 画像伝送用テレメータ送信機で, M-3SII型ロケットの試験機であるST-735ロケットで予備試験を行い, 地上追尾系を含めて総合的に性能の確認を行ったのち, M-3SII型1号機から本格的に搭載された。地上系では, 第2段モータの燃焼ガスが通信回線に大きな障害をもたらす等の問題が生じ, 2号機から高利得の18mパラボラアンテナを使用し, 従来の高利得16素子アンテナに対する冗長系を構成した。また, 第3段目の機体振動計測データ等を伝送していた900MHz帯テレメータは3号機から送信周波数がS帯へ変更されたのに伴い, 地上受信アンテナとしてはこれまで使用していた3mφパラボラアンテナをやめ衛星追跡用10mφパラボラアンテナを使用する事となった。データ処理系では, 計算機によるデータ処理が本格化し, 姿勢制御系, 計測系, テレメータ系のデータ処理のほか, 従来のACOSやRS系へのデータ伝送に加えM管制室へもデータ伝送が出来るようになった。コマンド系では, 1∿2号機は従来と同様であるが, 3号機から第1段の制御項目等を増やす必要からトーン周波数を増し, コマンド項目を3項目から6項目にし, さらに操作上の安全性を向上させた。集中電源は, 充電効率や管理の点等から見直しをはかり, 従来M-3S型で用いられていた酸化銀亜鉛蓄電池に替わりニッケルカドミウム蓄電池が使用されるようになった。資料番号: SA0167008000
- 著者
- 野田 浩志 南谷 長俊 加藤 大介
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. C-2, 構造IV, 鉄筋コンクリート構造, プレストレストコンクリート構造, 壁構造・組積構造 (ISSN:13414488)
- 巻号頁・発行日
- no.1996, pp.367-368, 1996-07-30
1 0 0 0 世界の窓 バルト三国のアーカイブズ
- 著者
- 加藤 聖文
- 出版者
- 全国歴史資料保存利用機関連絡協議会
- 雑誌
- 記録と史料 = Records & archives : journal of the Japan Society of Archives Institutions (ISSN:09172343)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.62-66, 2020-03
1 0 0 0 OA 消化器外科におけるチーム医療による実践的手術侵襲軽減策とアウトカム
- 著者
- 中村 文隆 藤井 正和 七里 圭子 西 智史 篠原 良仁 伊橋 卓文 横山 新一郎 武内 慎太郎 今村 清隆 渡邊 祐介 田本 英司 高田 実 加藤 健太郎 木ノ下 義宏 安保 義恭 成田 吉明 樫村 暢一
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.71-77, 2018 (Released:2018-08-23)
- 参考文献数
- 29
ERAS の手術侵襲軽減策は,多職種のスタッフによる介入が不可欠である.入院前の不安要素は患者個々に異なり,消化器外科では,術後の食事摂取,人工肛門に対する不安は多い.各医療スタッフの専門的立場の助言が治療意欲を向上させる.術後の腸管機能の回復促進対策としては,輸液量の適正化,胸部硬膜外鎮痛,早期経口摂取,早期離床などチームで取り込む事項が多い.早期離床では,プログラム内容や行動目標を定め施行することが望ましい.疼痛管理としては,急性痛サービスAPS を組織することが,安心な周術期環境を効率的に提供し,今後わが国でも普及することが望まれる.回復を実感する環境づくりは,重要であり,チームメンバーは,各専門的な知識や技術を生かし患者のセルフケアーを支援することで,早期回復の実感と不安の解消につながり,満足度の高い退院につながる.
- 著者
- 清水 哲哉 中津 亨 宮入 一夫 奥野 智旦 加藤 博章
- 出版者
- 日本応用糖質科学会
- 雑誌
- Journal of Applied Glycoscience (ISSN:13447882)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.161-167, 2004 (Released:2008-03-24)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 2
エンドポリガラクツロナーゼ(EndoPG)は,inverting型の加水分解酵素であり,その触媒機構の詳細は不明であった。本研究では,リンゴ銀葉病菌(Stereum purpureum)の病徴発現蛋白として単離されたEndoPG Iを用いて触媒機構の解明を目的としてX線結晶構造解析を行った。イオンスプレー型質量分析装置を用いたEndoPG Iの糖鎖修飾の分析結果からEndoPG Iの結晶化には,3種のアイソフォーム,EndoPG Ia,Ib,Icのうち糖鎖の最も少ないEndoPG IaをEndoHで糖鎖切断した脱糖鎖型EndoPG Iaを用いた。この脱糖鎖型EndoPG IaをPEG 4000を沈殿剤に用いたハンギングドロップ蒸気拡散法により結晶化した。得られた結晶は,空間群P1に属し,格子定数はa=37.26 Å,b=46.34 Å,c=52.05 Å,α=67.17°,β=72.44°,γ=68.90°であった。この結晶を用いて大型放射光施設SPring-8によりX線回折実験を行った。結晶構造の決定は,多波長異常分散法で行った。SPring-8で収集したデータを用いて初期位相を決定し,最終的に0.96 Å分解能でR値11.4%,Rfree値14.0%という超高分解能のEndoPG Iの構造モデルを得た。得られたEndoPG Iの構造は,10回の完全ターンの平行β-へリックス構造であった。さらに反応生成物であるガラクツロン酸(GalA)を1分子を含むbinary複合体と2分子含むternary複合体の結晶構造を1.00 Åおよび1.15 Å分解能で決定した。binary複合体において1分子のピラノース型(GalpA)の結合がみられた。GalpAの結合位置は,活性残基と推定されているAsp153,Asp173,Asp174の還元末端側にあたることから,GalpAは+1サブサイトに結合していると考えられた。一方,ternary複合体においては,GalpAの他に,フラノース型のGalfAの結合がみられた。GalfAの結合位置は,活性残基の非還元末端側にあたる-1サブサイトと決定された。+1サブサイトでは,三つの塩基性残基,His195,Arg226,Lys228がGalpAのカルボン酸の結合に関与していた。一方,-1サブサイトでは,特異なcis型のペプチド結合がGalfAのカルボン酸の認識に関わっていた。そこで,二つのガラクツロン酸の結合状態を基に,基質の-1,+1結合した2量体部分のモデルを構築し,EndoPG Iの反応機構を検討した。まず,Asp173は切断される基質モデルのグリコシド結合と直接水素結合しうる位置にあった。したがって,Asp173はグリコシド結合にプロトンを供給する一般酸触媒残基と確認された。一方,Asp153とAsp174は,基質のアノマー炭素を求核攻撃すると考えられる水分子と水素結合していた。このことから,Asp153あるいはAsp174が水からプロトンを引き抜き活性化する一般塩基触媒残基と予想された。
1 0 0 0 IR リハビリテーション施行基準の導入 (第112回成医会葛飾支部例会)
- 著者
- 南本 新也 武石 英晃 梶原 一輝 加藤 正高 荒井 隆雄 長島 弘泰 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 又吉 由紀子 鈴木 禎 ミナミモト シンヤ タケイシ ヒデアキ カジワラ イッキ カトウ マサタカ アライ タカオ ナガシマ ヒロヤス リガクリョウホウシ サギョウリョウホウシ ゲンゴチョウカクシ マタヨシ ユキコ スズキ タダシ Minamimoto Shinya Takeishi Hideaki Kajiwara Ikki Kato Masataka Arai Takao Nagashima Hiroyasu Rigakuryohoshi Sagyoryohoshi Gengochokakushi Matayoshi Yukiko Suzuki Tadashi
- 雑誌
- 東京慈恵会医科大学雑誌 (ISSN:03759172)
- 巻号頁・発行日
- vol.130, no.5, pp.146, 2015-09-15
1 0 0 0 OA 吸入再指導のポイントはどこにあるか? ─ディバイス別の検討─
- 著者
- 後藤 幸 加藤 聡之 橋本 理恵 榊原 隆志 足立 守
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.236-241, 2008-12-29 (Released:2016-12-28)
- 参考文献数
- 8
吸入薬を使用中の呼吸器疾患症例では吸入再指導が重要である.今回,吸入継続中にどういう点ができなくなるのかを検討した.その結果,(1)吸入器の一連の操作を確認し,できていない点のみを是正する,(2)「吸入前の深呼気」,「吸入後の息止め」を再徹底する,(3)薬剤の効果と病態を再教育する,が再指導時の重要ポイントと考えられた.多忙な日常業務のなかではこれらに重点を置けば有効な再指導につながると思われる.
1 0 0 0 OA 画像情報圧縮の手ほどき (第10回) 2値・多値画像の符号化方式
- 著者
- 加藤 茂夫
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.265-274, 1990-03-20 (Released:2011-08-17)
- 参考文献数
- 30