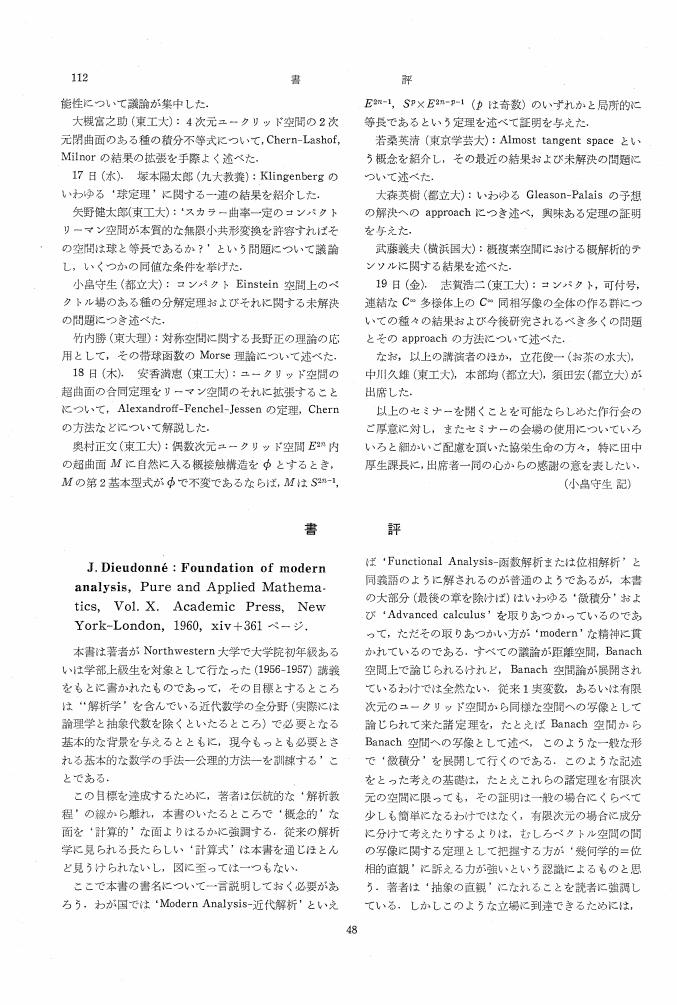4 0 0 0 OA 冬季雷雲のガンマ線測定を狙う多地点観測システムの新規開発
- 著者
- 榎戸 輝揚 湯浅 孝行 和田 有希 中澤 知洋 土屋 晴文 中野 俊男 米徳 大輔 澤野 達哉
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- 日本地球惑星科学連合2016年大会
- 巻号頁・発行日
- 2016-03-10
日本海沿岸の冬季雷雲から 10 MeV に達するガンマ線が地上に放射されていることが観測的に知られており(Torii et al., 2002, Tsuchiya & Enoto et al., 2007)、雷雲内の強電場により電子が相対論的な領域まで加速されていると考えられている。これまでの観測では単地点の観測が多く、電子加速域の生成・成長・消失を追跡を追うことは難しかった。そこで我々は、雷雲の流れにそって複数の観測点を設けたマッピング観測を行うことで、放射の始まりと終わりを確実に捉え、ガンマ線強度やスペクトル変化を測定し、加速現象の全貌を明らかにすることを狙っている。冬季雷雲の平均的な移動速度は ∼500 m/ 分で、単点観測で数分にわたりガンマ線増大が検出されるため、およそ数 km 間隔で約 20 個ほどの観測サイトを設けることを考えている。そこで、CsI や BGO シンチレータ、プラスチックシンチレータと独自に開発した回路基板、小型のコンピュータ Raspberry Pi を組み合わせ、30 cm 立方ほどの可搬型の放射線検出器を開発し、金沢大学と金沢大学附属高校に設置して観測を開始した。個々の放射線イベントの到来時間とエネルギー、温度などの環境情報を収集してる。今後、観測地点を増やして、マッピング観測を行いたい。なお、本プロジェクトは、民間の学術系クラウドファンディングからの寄付金によるサポートも得ておこなわれた。
4 0 0 0 OA 或る文學者の覺書 : 福田恆存素描
- 著者
- 和田 正美
- 出版者
- 明星大学
- 雑誌
- 明星大学研究紀要. 日本文化学部・言語文化学科 (ISSN:13444387)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.13-22, 1993-03-25
4 0 0 0 OA 近世西本願寺末正光寺の「貴族化」と朝廷権威
- 著者
- 和田 幸司
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.88-115, 2010-11-15
The primary concern of this paper is to clarify the approach of the Syoukouji Temple to the authority of the Tenno and his court. This paper is based on a study on the "Kizokuka" of the Hongwanji Temple that was suggested by TSUJI Zennosuke and WAKITA Haruko. I use two research methods. Firstly, I examin the incident in which the Nishi Hongwanji Temple seized the land of the Syoukouji Temple. Secondly, I consider the economic foundation of the Syoukouji Temple from the perspective of spreading the sect's teachings. This article is for people who are interested in Shin Buddhism and early modern Japanese history The main findings of this paper are as follows. 1. The Syoukouji Temple built up a relationship with Tenno and his court by maintaining a religious relationship with Kujoke and Chitokuin. 2. The sect's believers in Satsuma and Ryukyu supported the "Kizokuka" of the Syoukouji Temple. 3. Belief was orientated towards the Tenno and his court in early modern times.
4 0 0 0 大阪府の汽水域・砂浜域の無脊椎動物および藻類相
- 著者
- 石田 惣 山田 浩二 山西 良平 和田 太 渡部 哲也
- 出版者
- 大阪市立自然史博物館
- 雑誌
- 自然史研究 : Shizenshi-kenkyu, occasional papers from the Osaka Museum of Natural History (ISSN:00786683)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.15, pp.237-271, 2014-12-28
文献、標本、ならびに著者または研究者らによる調査・観察記録を渉猟することで、大阪府の汽水域・砂浜域の無脊椎動物および藻類相を調べた。その結果、記録種は総計で無脊椎動物が571 種群、藻類が57 種群となった。本報ではそれらの種と参照資料のリストを示す。
4 0 0 0 OA ステノン管が原発と考えられた扁平上皮癌の1例
- 著者
- 松下 直樹 井口 広義 和田 匡史 大石 賢弥 岡本 幸美 寺西 裕一 神田 裕樹 山根 英雄
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本頭頸部外科学会
- 雑誌
- 頭頸部外科 (ISSN:1349581X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.201-205, 2014 (Released:2015-02-11)
- 参考文献数
- 27
頰部に発生する腫瘍として耳下腺に付属するステノン管および副耳下腺を由来とするものが認められるがともに頻度は少ない。また原発がステノン管なのか副耳下腺なのかはっきりしないことも多い。しかし過去の報告からはステノン管を原発とするものは扁平上皮癌が多く,副耳下腺を原発とするものは粘表皮癌が多く扁平上皮癌は少ない。今回われわれはステノン管が原発と考えられた扁平上皮癌を1例経験したので,若干の文献的考察を加えて報告する。症例は71歳の男性。右頰部腫脹を主訴に受診され,画像所見から副耳下腺扁平上皮癌として手術を施行した。術後の病理所見などを含めて総合的に判断すると,ステノン管が原発の扁平上皮癌と考えられた。
4 0 0 0 OA コンテンツを活用した地域振興活動の発展要因と活用パターン
- 著者
- 和田 崇
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.100015, 2012 (Released:2012-09-14)
近年,漫画やアニメ,ゲームを始めとする日本のコンテンツが海外で注目されるようになり,日本政府もこれを踏まえるかたちで,日本独自のコンテンツを海外に積極的に発信する「クールジャパン」戦略を展開してきた。一方で,日本国内においても,地方の自治体や経済団体などが漫画やアニメ,映画などのコンテンツを活用した観光振興や文化振興に取り組む事例が増加している。本発表では,日本におけるコンテンツを活用した地域振興活動について,その発展要因と活用パターンを概観する。 コンテンツを活用した地域振興活動が活発となってきた要因(背景)として,製作者と消費者,地域それぞれの環境変化を指摘できる。コンテンツの製作者は,デジタル化に伴って情報の編集・複製が容易になったこともあり,リスク削減と収益拡大のために,コンテンツの二次使用を積極的に行うようになり,地域もメディアの一つとみなされるようになった。また制作に当たり,新たなストーリーやロケーションを地域に求める動きも活発となってきた。消費者は,メディアごとにコンテンツを楽しむ従来からの消費形態に加え,インターネット上でコンテンツをめぐるコミュニケーションを楽しむという形態が確立した。その一方で,コンテンツゆかりの場所やリアルに再現される場所を訪ねることにより,コンテンツをより深く味わおうとする行動もみられるようになってきた。 各地域の自治体や経済団体などは,地方分権が進展する一方で,地域間競争を勝ち抜くことが求められるようになり,地域資源を活用した地域の個性化・魅力化に取り組むようになった。その際,手軽に制作あるいは活用可能な資源としてコンテンツが注目されるようになった。 コンテンツを活用した地域振興活動にみられるコンテンツと地域の関係については,3つのパターンを見出すことができる。第一は,歴史や風景など場所の持つ力がコンテンツに組み込まれている点である。それによって,製作者はコンテンツの魅力を高め,自治体や経済団体などは地域の魅力を発信している。第二は,地域がキャラクターの新たな活動場所となっている点である。それによって,製作者は二次使用の機会を広げ,自治体や経済団体などは地域や商品の知名度向上とブランド化に結びつけている。第三は,地域がコンテンツ消費者のライブ体験,購買,交流の場所となっている点である。
4 0 0 0 OA ボストン美術館にみる岡倉覚三(天心)残像 : 2011 年春の「茶道具展」展示をもとに
- 著者
- 大和田 範子 オオワダ ノリコ Ohwada Noriko
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.193-210, 2013-03-31
100 年前の岡倉覚三を現在からどのように捉えればよいかと考えたことをきっかけとして、彼の展示表現をそのまま受け継いでいる仏像展示に岡倉の残像を求めることから今回の調査を始めた。ボストン美術館は1909 年の新築移転により、当時の東洋部(中国・日本部)の顧問として岡倉は設計から参加し、展示会場を現在の状態に作り上げた。日露戦争を背景として、アメリカのマサチューセッツ州ボストン市で活動した彼にとって、展示は日本主張の一つの方法であり、そのままの日本をボストン美術館に再現するという当時では斬新な方法で、日本文化を西洋人に向けて発信するために、仏像展示にこだわり工夫を凝らした。このような彼の姿勢が現在どう受け継がれているかを調査するため、2011 春開催の「茶道具展」展示をもとに岡倉の残像を浮かび上がらせようと分析したのが本論である。方法として、ボストン美術館の日本部門が開催した2 月12 日開始の「茶道具展」、「茶道具展」に関連した3 月13 日の「茶のシンポジューム」、そして中国部門が2010 年11 月20 日から2011 年2 月13 日まで開催した特別展「フレッシュ・インク」の展示との比較調査を行い、2 カ月にわたる資料収集から岡倉覚三を現在から捉える試みを行ったものである。
4 0 0 0 コード会のコードについて
- 著者
- 和田 弘 高橋 茂
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.107-109, 1960-09-15
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA 書評
- 著者
- 矢野 茂樹 一松 信 和田 淳蔵 藤田 宏 黒田 成俊 竹内 啓
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.112-127, 1965-10-10 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 堀田 浩貴 熊本 悦明 青木 正治 山口 康宏 佐藤 嘉一 鈴木 伸和 和田 英樹 伊藤 直樹 塚本 泰司
- 出版者
- 社団法人日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雜誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.12, pp.1939-1946, 1991-12-20
- 被引用文献数
- 1
夜間睡眠時勃起現象(NPT)は,ほとんどすべての健康男子に見られる生理現象であるが,小児での検討は少ない。そこで今回我々は,3歳から18歳までの小児30例で,NPT測定を行い,身体的発育と性的成熟度との関連について検討した。1.NPTの回数は各年齢でバラつきが大きいが,10歳過ぎ頃より増加傾向を認め,13,14歳の2例で14回と最高値を示した。2.陰茎周増加値(一晩のNPTのエピソード中,最大の陰茎周変化の値)は10歳まではすべて10mm以下であったが,12歳過ぎ頃に急激な増加が見られた。3.NPT時間(一晩のNPT時間の合計),%NPT時間(睡眠時間に占めるNPT時間の割合)は,ともに12歳頃より急激な増加が認められた。%NPT時間は,血清LH値とほぼ正の相関を示していた。また思春期発来の指標と考えられている夜間睡眠時のLH pulseが認められた例では,認められなかった例に比し,%NPT時間は明らかに高値であった。4.以上から,小児におけるNPTの測定は,他の内分泌的指標とともに思春期発来を知る上での生理学的指標となり得る可能性が示唆された。
4 0 0 0 活字体のゆれ
- 著者
- 和田 英一
- 出版者
- 計量国語学会
- 雑誌
- 計量国語学 (ISSN:04534611)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.p123-127, 1995-12
- 著者
- 増田 亜希子 伊東 孝通 和田 麻衣子 日高 らん 古江 増隆
- 出版者
- 日本皮膚科学会西部支部
- 雑誌
- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.353-355, 2016-08-01 (Released:2016-12-15)
- 参考文献数
- 8
27 歳,女性。小児期よりアトピー性皮膚炎に罹患していた。初診の 6 年前より夫の精液付着部位に蕁麻疹と瘙痒を認めた。その後,避妊具なしで性交した際に全身に蕁麻疹を認め,呼吸困難も出現した。同様のエピソードが過去 2 回あった。避妊具を使用した性交渉では同様の症状を生じたことはなかった。近医を受診し,精漿アレルギーの疑いで当科を紹介され受診した。10 倍から1000 倍に希釈した夫の精漿を用いたプリックテストでは,検査した全ての濃度で紅斑と膨疹が出現した。本疾患は精漿中に存在する前立腺由来の糖蛋白に対するⅠ型アレルギー反応であると考えられている。精漿アレルギーの患者の半数以上にアトピー性皮膚炎の既往があると報告されており,皮膚バリア機能の障害による経皮感作が発症に重要な役割を担っていることが推察される。本疾患は皮膚科領域での報告は比較的稀であるが,アトピー性皮膚炎関連アレルギー疾患の一つとして位置づけることができると考え報告した。
- 著者
- 宮﨑 勇輔 小尾口 邦彦 福井 道彦 加藤 之紀 和田 亨 横峯 辰生 小田 裕太 大手 裕之
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.255-258, 2018-07-01 (Released:2018-07-01)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
肺血栓塞栓症による心停止に対し,機械的胸部圧迫装置が有用であったが,外傷性肝・脾損傷を併発し,開腹手術が必要となった症例を経験した。症例は73歳女性で,呼吸困難感を主訴に救急搬送され,来院後に心停止となった。直ちに心肺蘇生を開始,機械的胸部圧迫装置AutoPulse®(旭化成ゾールメディカル)を使用した。気管挿管・アドレナリン投与を行い自己心拍再開が得られた。心停止は肺血栓塞栓症によるものと診断した。ICU入室後は,血行動態は比較的保たれていたが,約15時間後から不安定となり,貧血の進行も認めた。腹部超音波検査・CTを実施し,多発肋骨骨折に伴う外傷性肝・脾損傷による出血性ショックと診断した。開腹し,脾臓摘出術と肝裂創部凝固止血術を実施した。症例は肥満(BMI 38 kg/m2)だったこともあり,AutoPulse®のバンド位置が尾側にずれ,合併症を生じたものと推測された。機械的胸部圧迫装置の使用では特性を十分理解し,合併症に注意する必要がある。
3 0 0 0 OA 鰹だしのジペプチジルペプチダーゼ IV活性阻害性血糖上昇抑制作用
- 著者
- 関 英治 小塚 美由記 米田(和田) 実央 村尾 咲音 山根 拓也 荒川 義人 大久保 岩男 藤原 佳史
- 出版者
- 日本補完代替医療学会
- 雑誌
- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.21-28, 2018-03-31 (Released:2018-04-18)
- 参考文献数
- 19
鰹節の熱水抽出液(鰹だし)は,ジペプチジルペプチダーゼ IV(DPP IV)阻害活性(IC50 値; 3049 µg/ ml)を有することから,ヒトにおける鰹だしの血糖上昇抑制効果の有無について,ヒト試験を用いた糖負荷試験を実施した.鰹荒節500 gに10倍量の水を加え煮出して150 mlを供した.糖尿病やその他の重大な疾患がなく,かつBMIが30未満の健常人(男性14名)を対象とし,鰹だし摂取30分後に糖を負荷し,0 分~150分まで血糖値を測定した.鰹だし摂取時は,米飯摂取 75 分および90分後の血糖値 ± 標準誤差は,鰹だし摂取時110.0 ± 5.9 mg/ dl対白湯摂取時134.9 ± 6.9 mg/ dl値;p < 0.01( p = 0.006)および鰹だし摂取時110.3 ± 6.8 mg/ dl対白湯摂取時129.3 ± 6.6 mg/ dl値;p < 0.05( p = 0.036)が得られ,有意に血糖値の上昇抑制作用が認められた.鰹だしと白湯摂取後の血糖下曲線面積を比較すると 鰹だし摂取時の面積は4753.1 ± 439.7 mg/ dl × min,白湯摂取時の面積は6879.4 ± 728.1 mg/ dl × minであり,血糖降下作用が認められた( p < 0.01, p = 0.005 ).空腹時血糖に対して鰹だし摂取前と鰹だし摂取後30分後の血糖値には有意差が認められなかった.鰹だし摂取糖負荷150分後には,血糖値が空腹時血糖まで復帰した.本ヒト試験において鰹だしに糖負荷血糖上昇抑制作用が認められた.鰹だしにはα-グルコシダーゼ阻害活性が認められなかった.試験中に副作用と考えられる自・他覚症状は認められなかった.
3 0 0 0 OA 灸ともぐさの話
- 著者
- 和田 清吉 三輪 一司 昆 健一郎 勝野 由睦 北島 礼次郎 小木曽 信夫 中島 文市 斉木 展章 宝田 一男 大庭 昇二
- 出版者
- 日本良導絡自律神経学会
- 雑誌
- 日本鍼灸良導絡医学会誌 (ISSN:02861631)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.6-10, 1972 (Released:2011-10-18)
3 0 0 0 OA 灸ともぐさの話-その2-
- 著者
- 長倉 吉宏 押谷 次郎 和田 清吉 小木曽 信夫 三輪 一司 中島 文市 昆 健一郎 斉木 展章 勝野 由睦 宝田 一男 北島 礼次郎 大庭 昇二
- 出版者
- 日本良導絡自律神経学会
- 雑誌
- 日本鍼灸良導絡医学会誌 (ISSN:02861631)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.4, pp.7-14, 1973 (Released:2011-10-18)
3 0 0 0 OA 加熱食用油からの気化物質とその吸入による家兎循環・呼吸器系への影響
- 著者
- 岸 美智子 佐藤 修二 土屋 久世 堀口 佳哉 和田 裕
- 出版者
- Japanese Society for Food Hygiene and Safety
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.5, pp.318-323_1, 1975-10-05 (Released:2009-12-11)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 5
加熱食用油から発生する気化物質の吸入毒性について検討するため, ウサギを用いて, 循環呼吸系に及ぼす影響を調べた. 加熱食用油からの発生ガスを吸入させると, 著明な心拍数の減少と呼吸運動の抑制が発現し, 血圧上昇も認められた. 気化物質中, 比較的多く存在するエタン, ペンタン, アクロレインのうち, 発生ガスと同じ症状を発現させるのは, アクロレインのみであった. また, アクロレインを除去した発生ガスでは, 症状が現れず, これらの結果から, 加熱食用油からの発生ガス吸入によって循環呼吸系に現れる毒性症状の主たる原因物質は, アクロレインと思われる.
- 著者
- 多和田 裕司
- 出版者
- 京都大学東南アジア地域研究研究所
- 雑誌
- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.84-87, 2023-07-31 (Released:2023-07-31)