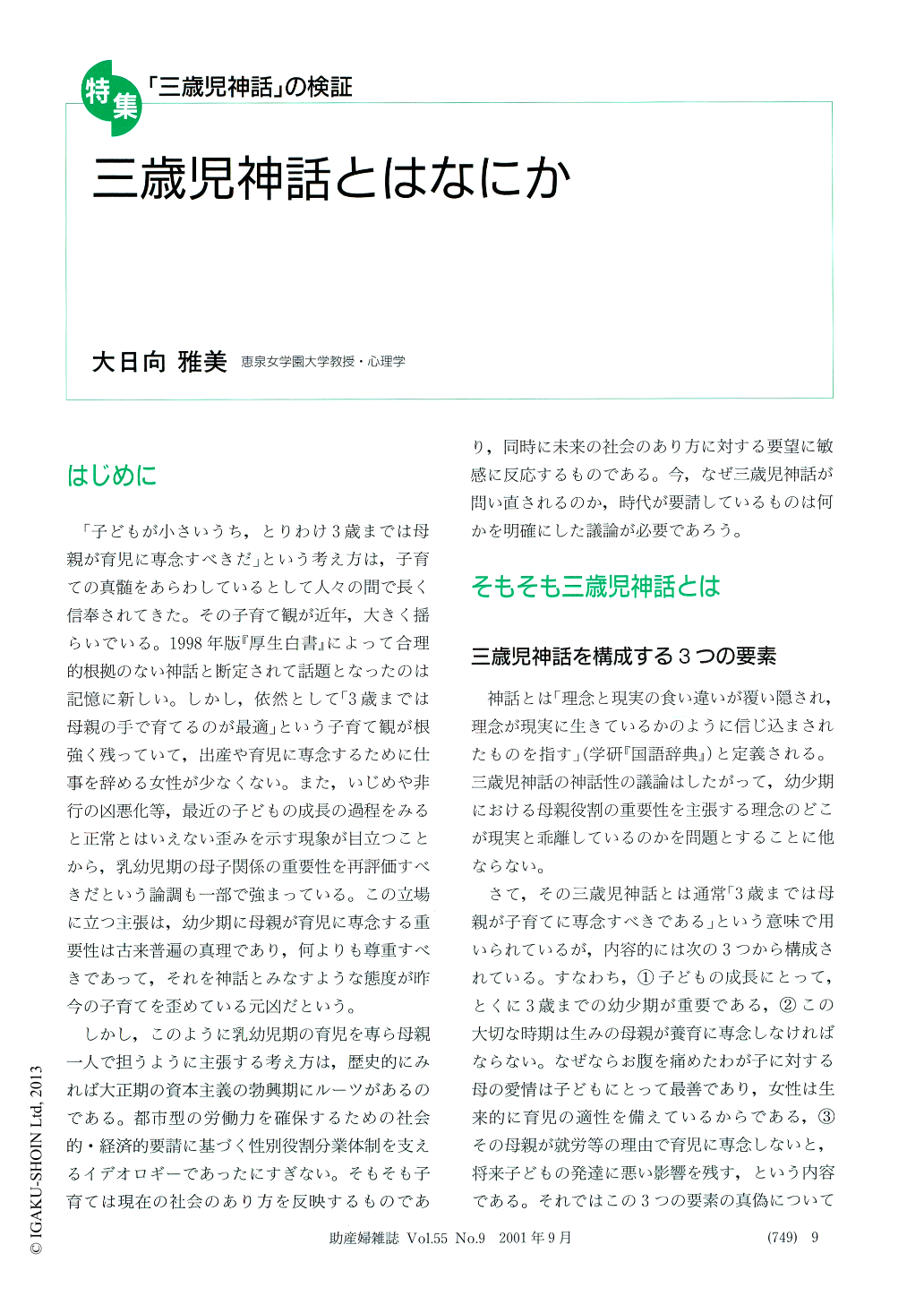17 0 0 0 OA 不登校と発達障害: 不登校児の背景と転帰に関する検討
- 著者
- 鈴木 菜生 岡山 亜貴恵 大日向 純子 佐々木 彰 松本 直也 黒田 真実 荒木 章子 高橋 悟 東 寛
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.255-259, 2017 (Released:2017-07-12)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 3
【目的】不登校児の発達特性と転帰に影響する因子を検討した. 【方法】2007年から2009年に当センターを受診した不登校児80名の発達障害や精神疾患の有無, 在籍学級, 転帰等を調査した. 【結果】不登校児の57%が広汎性発達障害や注意欠陥/多動性障害などの発達障害を, また24%が不安障害などの精神疾患を有していた. 87%が不登校になって初めて発達障害と診断された. 91%に睡眠障害や頭痛などの身体愁訴を認めた. 不登校となった誘因は複数混在し, 対人関係の問題を契機とする例が最も多かった. 1年後の転帰は完全登校48%, 部分登校26%, 不登校26%だった. 小学生は60%が完全登校に至ったが, 中学・高校生は41%に留まった. 1年後不登校の割合は, 発達障害をもたない児で42%であったのに対し発達障害を有する児では17%で, 特別支援学級へ転籍した児では1例もなかった. 【結論】不登校児は発達障害や精神疾患を背景に持つことが多く, 登校転帰の改善には発達特性の把握と教育的・心理的な支援が有用である可能性が示唆された.
8 0 0 0 OA ビオチンの薬理量摂取による高血圧上昇抑制効果の解析
- 著者
- 駒井 三千夫 神山(渡部) 麻里 神山 伸 大日向 耕作 堀内 貴美子 古川 勇次 白川 仁
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, no.4, pp.248-251, 2008 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 13
ビタミンは,基本的には食品から摂取されなければならないが,大量に摂取することによって,基本的な生理機能の働きのほかに疾病を予防するなどの新規な機能を発揮することが知られてきた.また,体力増強や疲労回復などにもビタミンが利用されるようになってきた.このように,ビタミンを所要量の数倍から数十倍摂取すると,体内におけるビタミンの薬理作用が期待されている(薬理量,保健量の摂取).当論文では,ビオチンによる新規生理作用のうち,とくに高血圧症改善効果に関してまとめた.ビオチンの摂取によって耐糖能とインスリン抵抗性の改善はすでに報告されているが,今回は脳卒中易発性高血圧自然発症ラット(SHRSP)を用いて,高血圧改善効果を証明できたので報告する.すなわち,毎日3.3 mg/L水溶液の飲水からのビオチンの摂取によって,飼育2週目以降で高血圧症が改善されることを見出した.このように,本態性高血圧症を呈するSHRSPにおいてビオチン長期摂取により血圧上昇抑制効果が確認され,またそれによる動脈硬化の軽減が実際に示された.さらに,ビオチンの単回投与による血圧降下作用の検討によって,この作用はNOを介さない経路での可溶型グアニル酸シクラーゼ活性化を介したcGMP量増加の機構(Gキナーゼ介在による細胞内Ca2+濃度の低下)による可能性が示唆された.
6 0 0 0 OA 日本国内における河川水中のマイクロプラスチック汚染の実態とその調査手法の基礎的検討
- 著者
- 工藤 功貴 片岡 智哉 二瓶 泰雄 日向 博文 島崎 穂波 馬場 大樹
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B1(水工学) (ISSN:2185467X)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.I_1225-I_1230, 2017 (Released:2018-02-28)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
近年,直径5mm以下の微細プラスチック片(microplastics,以下MP)による環境影響が懸念されている.海洋では多くの調査・研究が行われているが,河川での調査例は少なく,調査手法も統一されていない.現地観測を行う際,プラスチック製用具の使用や周辺環境中のプラスチックとの接触による予期せぬプラスチック混入はMP採取量の誤差要因となるため,プラスチック混入への十分な配慮が必要となる.そこでまずMP調査手法に関して基礎的検討を行った.検討結果を踏まえ,これまで国内18河川で実施したMP調査の結果を整理した.得られたMP数密度(0.0064~2.5 個/m3)は日本近海(0.6~4.2 個/m3)13)より1オーダー小さく,地点毎に材質構成に違いが見られた.サイズは2mm以下がほとんどであった.
6 0 0 0 テーブルトップゲームを記述するための概念モデルの開発
- 著者
- 福田 一史 井上 奈智 高倉 暁大 高橋 志行 橋崎 俊 日向 良和 藤倉 恵一 松岡 梨沙
- 雑誌
- じんもんこん2020論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, pp.275-282, 2020-12-05
近年,多くのテーブルトップゲームが創作され消費されるようになった.また図書館でのボードゲームの活用が進むなど文化資源として注目が集まっている.すでにいくつかの民間のデータベースなど実践が存在するが,体系的な目録作成や利用には課題がある.本研究は,1) 既存DBの記述要素分析,2) サンプル資料の分析,3) 産学で組織したワーキンググループでの検討,を通じて概念モデルを策定した.記述テストにより本モデルの有効性が確認できたものの,その妥当性検証や精緻化などの課題が示唆された.
5 0 0 0 OA 脳室内出血で発症した外側後脈絡叢動脈末梢部動脈瘤の1例
- 著者
- 山本 憲一 松本 隆 渡辺 隆之 日向 崇教 大島 望 庄田 幹
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.424-429, 2011 (Released:2011-07-27)
- 参考文献数
- 18
外側後脈絡叢動脈(LPChA)の動脈瘤は非常に稀でこれまでの報告例のほとんどがもやもや病に伴うものである.今回我々は,脳室内出血で発症した特発性と考えられるLPChA動脈瘤の1例を経験した.症例は60歳男性で,意識障害(JCS III-100)で発症し救急搬送された.頭部CTでは右側優位の側脳室から第四脳室に及ぶ鋳型状の脳室内出血を認め,緊急で内視鏡下脳室内血腫除去術を施行した.第17病日に施行した脳血管撮影で5 mm大の右LPChA動脈瘤を認めたため,第26病日にナビゲーションガイド下に動脈瘤切除術を施行した.本来高血圧性脳内出血の原因の一つとされるmicroaneurysmがLPChAに生じ,脳室内という周囲に接する構造物がない環境のため増大し出血をきたしたのではないかと推察した.
5 0 0 0 OA 学級集団内地位とパーソナリティ特性からみた対面苦手意識
- 著者
- 日向野 智子 小口 孝司
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.133-142, 2007 (Released:2007-09-05)
- 参考文献数
- 47
本研究では,児童が学級集団の中で,友だちの行いを注意しなければならない場面で覚える対面苦手意識(対人場面におけるわずらわしさや不快感,懸念を特徴とする)を取り上げた。本研究の主たる目的は,ソシオメトリック地位により,児童の対面苦手意識が異なるのかを検討することであった。小学校4年生から6年生の児童(男子102名,女子96名)が,児童用対面苦手意識尺度(注意場面版),肯定的ソシオメトリック指名法,パーソナリティ尺度から成る調査票に回答した。ソシオメトリック・テストの肯定的指名件数から,児童の学級集団内地位(スター群,平均群,孤立群)を定めた。分析の結果,スター群は孤立群よりも,児童用対面苦手意識尺度のわずらわしさ得点が有意に低かった。さらに,対面苦手意識は,シャイネスや公的自己意識との間に有意な正の相関があった。
5 0 0 0 OA 全球プラスチック漂着ゴミ量把握に向けた人工衛星画像解析アルゴリズムの開発
Worldview-2(Wv2)画像がもつ可視光域から近赤外域までの波長域におけるプラスチックのスペクトルを把握するため,ハイーパースペクトルカメラ(以下HSC)を用いた撮影実験を実施した.撮影実験は国総研屋上(標高12m) から真下にHSCを向けて行った.撮影実験にはNH-7(EBA JAPAN社製)を使用した.被写体は木片,海岸砂の上に設置したポリプロピレン(PP)とポリスチレン(PE)である.RGBの3バンドを使用してプラスチックを検出した場合,PPおよびPEが検出可能であるが背後の海砂もプラスチックとして検出されるが,Wv2の8バンドを使用した場合,海砂の誤検知はほとんど起きなかった.
4 0 0 0 OA 小学校理科において知的謙虚さを育成するために重要な視点は何か
- 著者
- 川崎 弘作 雲財 寛 中村 大輝 中嶋 亮太 橋本 日向
- 出版者
- Japan Society for Science Education
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.85-90, 2023-12-09 (Released:2023-12-07)
- 参考文献数
- 14
本研究では,生命領域における探究の特徴を踏まえた学習指導が知的謙虚さの育成に有効か否かを明らかにすることを目的とした.このために,小学校第6学年「植物のからだのはたらき」において授業実践を行った.その結果,量的分析から,知的謙虚さ得点の平均値が実践後に向上していたと判断できる結果が得られなかった.このため,生命領域における探究の特徴を踏まえた学習指導が知的謙虚さの育成に有効であるとはいえないと判断した.その一方で,本研究の成果と先行研究の知見を比較することを通して,知的謙虚さの育成に関する新たな視点として,「自身の考えが誤っている可能性を常に疑い続ける学習」が有効であるという示唆を得ることができた.
4 0 0 0 三歳児神話とはなにか
- 著者
- 大日向 雅美
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 助産婦雑誌 (ISSN:00471836)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.9, pp.749-753, 2001-09-25
はじめに 「子どもが小さいうち,とりわけ3歳までは母親が育児に専念すべきだ」という考え方は,子育ての真髄をあらわしているとして人々の間で長く信奉されてきた。その子育て観が近年,大きく揺らいでいる。1998年版『厚生白書』によって合理的根拠のない神話と断定されて話題となったのは記憶に新しい。しかし,依然として「3歳までは母親の手で育てるのが最適」という子育て観が根強く残っていて,出産や育児に専念するために仕事を辞める女性が少なくない。また,いじめや非行の凶悪化等,最近の子どもの成長の過程をみると正常とはいえない歪みを示す現象が目立つことから,乳幼児期の母子関係の重要性を再評価すべきだという論調も一部で強まっている。この立場に立つ主張は,幼少期に母親が育児に専念する重要性は古来普遍の真理であり,何よりも尊重すべきであって,それを神話とみなすような態度が昨今の子育てを歪めている元凶だという。 しかし,このように乳幼児期の育児を専ら母親一人で担うように主張する考え方は,歴史的にみれば大正期の資本主義の勃興期にルーツがあるのである。都市型の労働力を確保するための社会的・経済的要請に基づく性別役割分業体制を支えるイデオロギーであったにすぎない。そもそも子育ては現在の社会のあり方を反映するものであり,同時に未来の社会のあり方に対する要望に敏感に反応するものである。今,なぜ三歳児神話が問い直されるのか,時代が要請しているものは何かを明確にした議論が必要であろう。
4 0 0 0 図書館情報資源としての「ゲーム」
- 著者
- 日向 良和
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.8, pp.344-349, 2021-08-01 (Released:2021-08-01)
これまで図書館にとって,ゲームは読書推進と競合しており,収集,提供は進んでいなかったが,2018年以降,日本国内の公共図書館,学校図書館において,ボードゲームを遊ぶイベントや,テーブルトークロールプレイングゲームを遊ぶ事例が増えている。本稿はアメリカ,北欧,および国内の事例をもとに図書館情報資源として今後ゲームを図書館が収集,提供する意義と効果について検討をおこなった。その結果多彩な文化体験の機会を図書館が提供するならば,ゲームを図書館情報資源の1つとして導入する検討が必要であることがわかった。
4 0 0 0 行政調査会の設置と高等試験制度改正審議
- 著者
- 小日向 英俊
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.114-116, 2017 (Released:2018-03-15)
4 0 0 0 OA メディアと武道:伝統文化としての武道との関連から
- 著者
- 西森 大 和田 崇 小日向 藍菜 アレキサンダー ベネット
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.223-247, 2017-03-31 (Released:2018-03-12)
4 0 0 0 北海道旭川市における3歳児の睡眠習慣に関するアンケート調査
- 著者
- 荒木 章子 大日向 純子 鈴木 菜生 岩佐 諭美 雨宮 聡 田中 肇 藤枝 憲二
- 出版者
- The Japanese Society of Child Neurology
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:18847668)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.5, pp.370-374, 2008
北海道旭川市において, 3歳児健診受診児の保護者に対し, 子どもの睡眠習慣に関するアンケート調査を行った. 受診者450名のうち404名 (90.4%) から回答を得た. 就床時刻は平均21.4時で, 22時以降は36%であった. 起床時刻は平均7.5時であった. 夜間睡眠時間は平均10.1時間で, 就床時刻が22時以降の児は22時以前と比べて, 有意に夜間睡眠時間が短かった (p<0.01). 午睡をとる児の12%は終了時刻が17時以降で, それらの児の平均就床時刻は22.1時であった. 就床時刻の遅延は, 食欲低下やカッとなって怒りっぽいという愁訴と関係があった (いずれもp<0.05). 保護者は就床環境に対して高い意識を示すが, 日中の活動性や午睡への意識は低かった. 25%の保護者は子どもの睡眠に問題を感じていたが, 医師への相談はわずか3%であった. 睡眠リズムの確立は, 心身の健全な発達と関係があり, 医療機関は積極的に啓発活動する必要がある.
3 0 0 0 OA Webアンケート調査に基づく独居高齢者の個人属性および外出行動と「孤独感」の関係性分析
- 著者
- 山村 崇 後藤 春彦 伊藤 日向子
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.66, pp.914-918, 2021-06-20 (Released:2021-06-20)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 6
This research focuses on the social contact in urban spaces as a possible protective factor against the development of loneliness. We conducted an online questionnaire survey focusing on going-out activities, especially those for leisure purposes, which previous studies have suggested might be correlated with loneliness, and examined their association with it. Through web-based questionnaire survey and following text mining analysis, it was clarified that it is important for the senior citizens to go out in urban spaces, enjoy leisure time, and interact with others so that they can avoid feeling lonely.
- 著者
- 小日向 文世 深田 武志
- 出版者
- 日経BP社 ; 1985-
- 雑誌
- 日経マネー (ISSN:09119361)
- 巻号頁・発行日
- no.418, pp.100-103, 2017-04
──最新作の「サバイバルファミリー」は、世の中から突然、電気が消えてしまうという設定の作品で、撮影が大変そうでしたね。大きな川で溺れるシーンがありましたけど、大丈夫でしたか。 あれ11月29日だったんです。
3 0 0 0 OA 母性研究の課題
- 著者
- 大日向 雅美
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.146-156, 2001-03-30 (Released:2012-12-11)
- 参考文献数
- 83
- 被引用文献数
- 3 2
本論文は, 子育てに対する危機感が強まっている今日の日本社会にあって, 心理学領域の母性研究が果たすべき課題について言及している。母性に対する研究は, 女性であれば誰にでも画-的に育児の適性があるとした従来の母性観を検証することを課題としてきた。昨今では, 育児支援の方途を求める社会的要請に応えるためにも, 母性研究への期待は大きい。しかし, 子育てはきわめて個別性の高い営みであり, 平均的, 公約数的な母親理解で対処できるものではない。かつてに比べれば, 研究テーマも母親にまつわる諸側面が対象とされるなど多岐にわたっているが, データの数量的な解析を主とする手法に依存する研究が大半を占めているという問題を指摘している。同時に子育てのあり方には時代の要請が大きく反映されるものであり, 研究視点の取り方や知見の解釈において時代のイデオロギー性に流される危険性が高い。子育てに対する社会的な関心は, 往々にして性急かつ単純な因果関係を求める。母性研究は社会的な要請に応えるという課題を担いつつも, 長期的複眼的な視点で親になる過程を検討する必要性を社会に提起する必要性を本論文は訴えている。