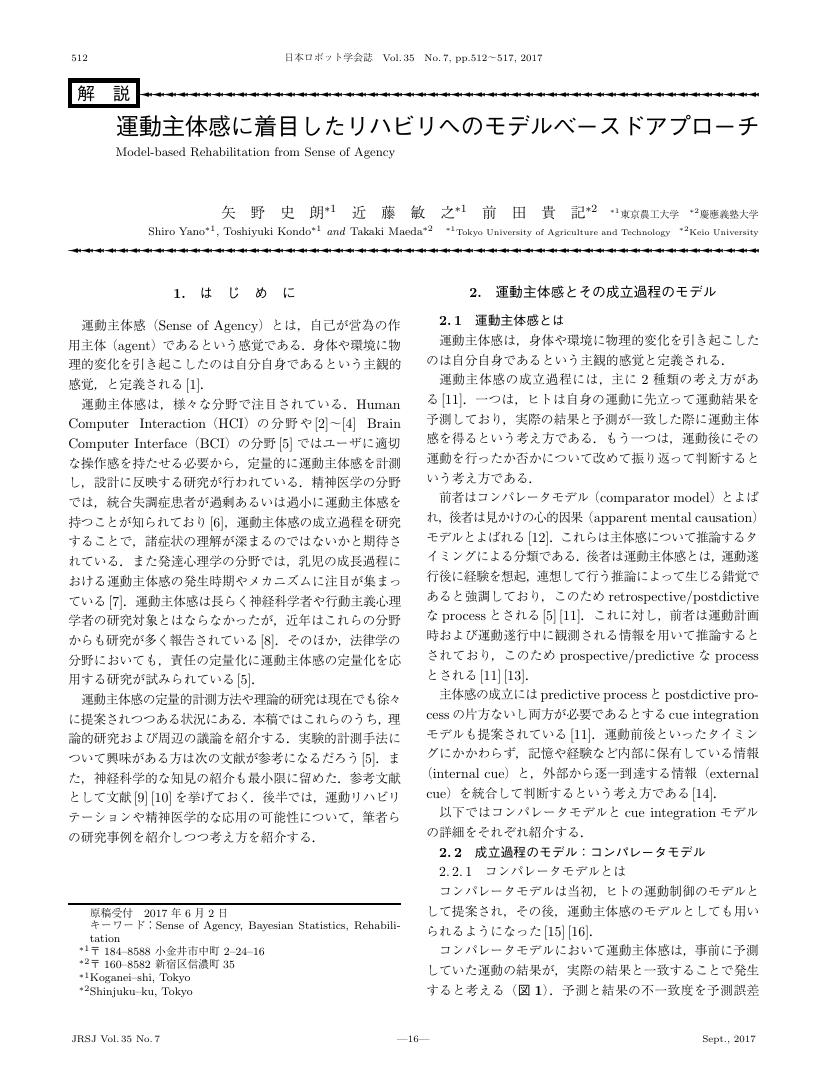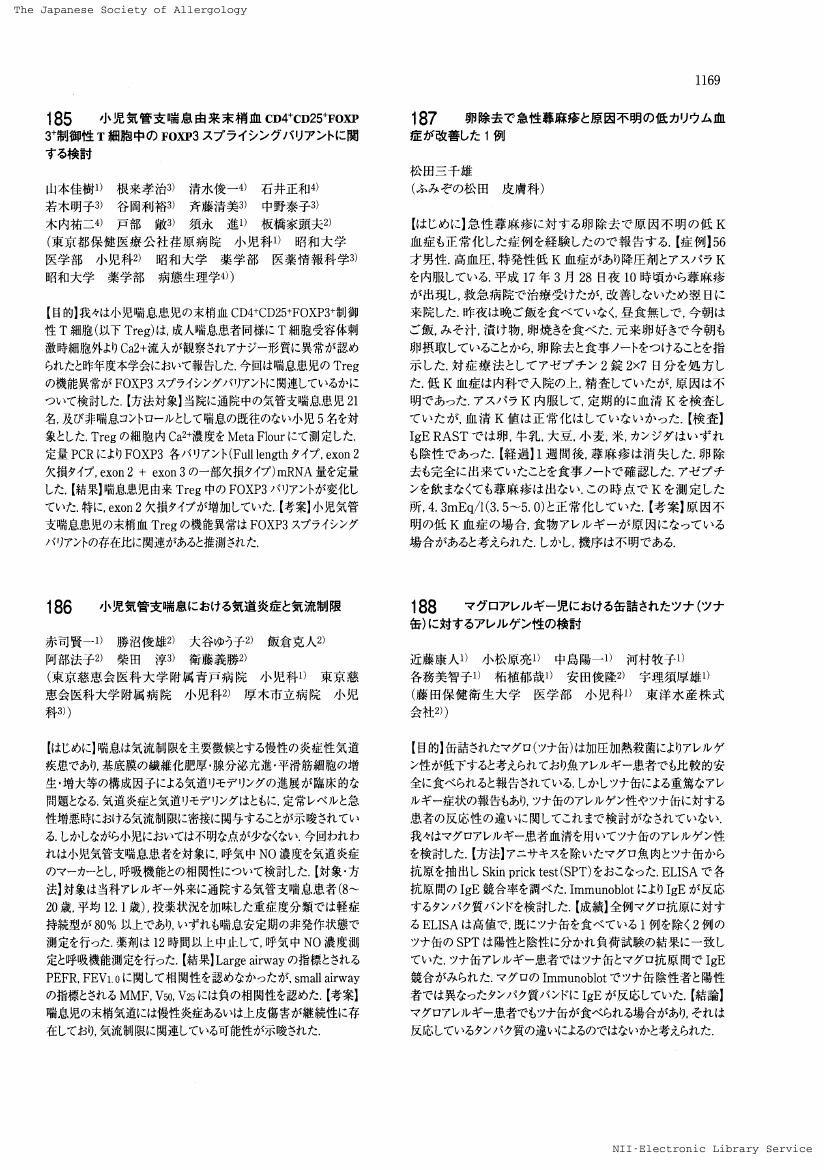1 0 0 0 OA 運動主体感に着目したリハビリへのモデルベースドアプローチ
- 著者
- 矢野 史朗 近藤 敏之 前田 貴記
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.7, pp.512-517, 2017 (Released:2017-10-01)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 海洋学の10 年展望2021:沿岸域
- 著者
- 木田 新一郎 栗原 晴子 大林 由美子 川合 美千代 近藤 能子 西岡 純
- 出版者
- 日本海洋学会
- 雑誌
- 海の研究 (ISSN:09168362)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.87-104, 2021
- 被引用文献数
- 4
<p>沿岸域において,今後10 年程度の期間で取り組むべき研究の方向性と意義,そしてその遂行に必要な研究基盤について論じた。沿岸域は外洋域と陸域を結びつける,フィルターかつリアクターとしての役割をもつ海域であると同時に,人間社会に身近であり,多様で生産性豊かな海域である。沿岸域の物質循環を理解し,将来にわたってその豊かな生態系を維持していくためには,物理・化学・生物が分野横断的に連結し,組織立ったプロセス研究を進める必要がある。変化の時空間規模が小さい沿岸域の現象を把握するには,観測データが依然として不足している。しかし,これまでの長期モニタリングデータに加えて新たな観測機器の開発,衛星観測の高解像度化,ドローンの登場によって状況は大きく前進しつつある。この現状をふまえて,今後必要と考える研究基盤と数値モデルの展望を議論した。</p>
1 0 0 0 針葉樹におけるSSRマーカーの開発とその適用
今回,2つの異なる方法によってアカマツのSSRマーカーを開発し,開発にかかる効率性や手法の簡便さといった観点から手法の比較を行なったので報告する。また,SSR分析を行なった際に1プライマー対から2領域以上の断片が検出され,解析に困難さが伴うことがある。スギを対象としたSSR分析の結果に基づいてその実例について報告する。まず,アカマツSSRの単離には2つの方法を利用した。一つはエンリッチメント法であり,Hamilton et al(1999)に従った。もう一つは,Lian and Hogetsu (2002)によって報告されたsuppression PCRを利用する方法である。エンリッチメント法では(AC)nを繰り返し単位とするSSRの単離を試みた。54プライマー対についてPCR増幅した結果,68.5%にあたる37プライマー対から期待されるサイズのフラグメントが得られた。アカマツ10個体を利用して,単一フラグメントの増幅と多型の有無について確認した結果,33プライマー対は単一な断片が増幅されることを確認した。このうち,3プライマー対は単型的であり,残る30プライマー対からは2_から_13個の対立遺伝子を確認した。エンリッチメント法と同様にアカマツ1個体を利用してLian and Hogetsu (2002)の方法に従ってSSRを単離した。63クローンについてプライマー設計し,増幅した36クローンについて二度目のシーケンシングを行なった。その結果,16クローンがSSRマーカー候補として選抜された。16クローンについてPCR増幅した結果,期待されるサイズの断片を増幅した14のうち,9プライマー対が単一の断片を増幅し,2_から_13の対立遺伝子を確認できた。 関東育種基本区のスギ精英樹936クローンのうち、765クローンをMoriguchiら(2003)が報告したスギSSR3プライマー対について実際にSSR分析した。使用したプライマーのうち,Cjgssr149では多くの個体で1領域に由来すると考えられる対立遺伝子を確認出来た一方で,2領域に由来すると考えられる断片が検出された。そこで,シーケンスしたところ,目的とした領域の一部が重複した類似領域であることが判明した。 Lian and Hogetsu (2002)の方法では,プライマー設計した63プライマーのうち,14.3%にあたる9プライマーのみを最終的にマーカーとすることが出来た。一方,エンリッチメント法ではプライマー設計し,PCR増幅した54プライマー対のうち,約60%にあたるプライマー対をマーカーとして考えることが出来た。しかし,この結果だけに基づいてエンリッチメント法が効率面で優れていると判断することは困難である。エンリッチメント法では,ポジティブクローンを選抜する段階でその3倍にあたるコロニー(768コロニー)を選抜しており,これらのコロニーにSSRが含まれているか確認する作業を行なう必要性がある上に,実験操作もハイブリダイゼーションなど熟練者以外には容易でない場合も多い。一方で,Lian and Hogetsu (2002)の方法は選抜したコロニーの90%以上がポジティブであり,操作もまたPCRを主体とした手法の連続であることから比較的容易にマーカー開発を進めることが出来る。但し,コスト面ではLian and Hogetsu (2002)の方法は,二度にわたるシーケンシングとプライマー設計を行なう必要性から,エンリッチメント法よりも負担は大きい。 SSRマーカーは開発に労力がかかる一方で,得られる情報量の大きさや再現性の高さから,きわめて有益なマーカーである。しかし,針葉樹は染色体倍加を伴わないゲノム重複が生じているとの報告もあり,類似する領域がゲノム中に散在している可能性も高い。実際,アカマツで増幅したプライマー対のうちマーカーとして選抜できなかった理由の多くは2領域以上と考えられる断片が検出されたことにあった。複数領域が検出されたとき,分離比検定やシーケンシングを行ない,領域間の関係を明確にすることで,初めて解析に利用できると考える。
1 0 0 0 図形の構造を考慮した絵描き歌自動生成システム
- 著者
- 久野 文菜 近藤 拓弥 松本 拓磨 山本 玲 畑中 衛 濱川 礼
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.737-745, 2020-03-15
本論文では任意の画像から,画像内に存在する物体の図形の構造を考慮した絵描き歌を自動生成するシステムについて述べる.相手に物事を説明するシーンにおいて,口頭のみでの説明と比べ,それに絵を加えた説明のほうが聞き手に強い印象を与えることができる.しかし絵を描くことに対して苦手意識を持つ人は,絵を描いて説明するということに対し羞恥心を感じ,口頭のみでの説明を行わざるを得なくなる.そこで我々は絵を描くことに対して苦手意識を持つ人が気軽に絵を練習できる方法として絵描き歌を提案する.任意の絵に対して,いちいち絵描き歌を人が作成するのは非常に手間がかかるため,我々は任意の画像から自動で絵描き歌を生成するシステムを開発した.さらに物体の構造に着目することでより人間に理解しやすい絵描き歌手法を提案する.従来の絵描き歌の歌詞は物体を構成するパーツの形状をとらえて作成されており形状に対するユーザの理解を促進するが,絵を描くのに必要な『位置関係』については触れられていないため,本手法では従来の歌詞に加えてパーツの位置関係も明示することにより,さらに詳しく物体の特徴をとらえることを可能にした.ユーザは絵描き歌にしたい対象を撮影し,システムに入力する.システムはユーザが撮影した画像を受け取り,パーツ分けをする.その後パーツごとの構造(形状・位置関係)を取得し,それに合わせた歌詞を自動生成する.本システムについて評価を行った結果,本システムを利用することにより絵を描くことに対する苦手意識の低減につながることが確認できた.
1 0 0 0 図形の構造を考慮した絵描き歌生成システムの提案
1 0 0 0 IR 富山市科学博物館への流星観測システムの設置
- 著者
- 近藤 秀作 竹中 萌美 林 忠史
- 出版者
- 富山市科学博物館
- 雑誌
- 富山市科学博物館研究報告 = Bulletin of the Toyama Science Museum (ISSN:1882384X)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.73-74, 2021-07-01
富山市科学博物館の屋上に流星観測を行うための観測システムを構築し、2020年4月~2021年1月までテスト観測を実施した。光害の影響が大きい場所での観測のため、流星をとらえる高感度ビデオカメラの設置方法や動体監視ソフトのパネラメーターを調整しながら観測を行った。結果、約-3。3~2。2等の明るさの流星を捉えることができ、ペルセウス座流星群やふたご座流星群の流星を検出することもできた。
1 0 0 0 IR スペイン史研究文献-1-
- 著者
- 西沢 竜生 近藤 仁之
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学文学部内)
- 雑誌
- 史林 (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.110-132, 1970-01
スペイン史学界の現況、並びに研究書誌につき一文をものすやう編輯子の依頼をうけたのは、昨年暮、筆者のマドリー滞在中であった。僅か一年そこそこの滞在であった上、明けて新年早々は帰国の旅に発つ身とあって、準備の暇もなく、取敢ずなほ年余に亙り滞在される近藤仁之氏(南山大学) に協力を仰いで快諾をえたのであった。ここに稿を起すにあたって最初にお断りしておきたいことは、この歴史的な「大国」の史学界につき紹介の筆を染めるのに筆者がいまだその任にたへぬ者であること、しかしならばこそまたなほのこと、拙文に盛られた以上に当の対象が遙かに深い奥行と大きな「問題」を含むことを御賢察いただきたいといふことである。従つて本篇の主たる内容は、生々しい現地報告もまじへた近藤氏の以下続篇に譲ることとし、ここでは僅かにその露払ひの役割を演じて当面の責を果すこととしたい。(西澤記)Al componer estas páginas bajo dicho título, he tenido el doble propósito de señalar importantes raíces de la historiografía moderna de España y de contribuir al estudio de la historia española en nuestro país, presentando un rico panorama de los rasgos fundamentales de esta ciencia : los archivos, colecciones de fuentes históricas, las revistas académicas etc., en un modo general. Acerca de los trabajos monográficos en cada ramo de investigación, esperemos que el señor profesor Y. Kondo los explicase profusamente en los números siguientes. R. N.
1 0 0 0 OA 界面活性剤の定義と種類
- 著者
- 近藤 行成
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.59-63, 2016-02-20 (Released:2016-05-20)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
界面活性剤の定義,基本的なはたらきおよび表面張力について概説する。また,界面活性剤の分類に基づき,アニオン,カチオン,非イオンならびに両性界面活性剤の特徴について紹介する。
1 0 0 0 鷺水の時間意識 : 『御伽百物語』の「過去」と「現在」
- 著者
- 近藤 瑞木
- 出版者
- 日本文学協会 ; 1952-
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.12, pp.50-53, 2021-12
- 著者
- 水野 建樹 近藤 裕昭 吉門 洋
- 出版者
- 社団法人日本気象学会
- 雑誌
- 天気 (ISSN:05460921)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.171-180, 1993-03-31
- 被引用文献数
- 9
関東地方では,移動性高気圧の後面から総観規模の寒冷前線が通過し去る間,内陸部下層に逆転層が形成され東京湾上に局地不連続線が生じる場合がある.初冬にはこの不連続線の形成に伴って大気汚染が悪化する.観測によれば,局地不連続線はそれまで関東平野部をおおっていた大気に比べて相対的に暖かい西よりの風が,中部山岳を北回りにあるいは南回りに関東内陸部上空に達したとき出現しており,これは関東内陸部では中部山岳部が壁となって下層によどみ域が発生する一方,関東南岸には障害物がないため西よりの風が卓越しているためと考えられる.局地不連続線は両者の気団間で出現する.このとき,館野上空 1000m程度の風向は約210〜310度にあり,館野高層データから求めたフルード数は風向によって変化するが,およそ0.3〜1.3程度であった.また局地不連続線は,それに先だって南〜西よりの風が少なくとも半日程度持続しているとき多く出現していることがわかった.
- 著者
- 鈴木 伸幸 水谷 潤 加藤 賢治 近藤 章 八木 清
- 出版者
- 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会
- 雑誌
- Journal of Spine Research (ISSN:18847137)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.737-740, 2020-04-20 (Released:2020-04-20)
- 参考文献数
- 3
近年,Lateral Interbody Fusion(LIF)手技の発展により,脊椎手術の手術時間と出血量の軽減が実現されている.しかし,その合併症の1つとして分節動脈損傷がある.今まで椎体側面の分節動脈の走行は研究され,注意喚起がなされてきたが,椎体前方でも,前方レトラクターの設置やAnterior Column Realignment(ACR)手技の際には重要であり,L1/2では89.1%,L2/3では81.0%,L3/4では34.5%と高頻度に分節動脈が椎間板と交差しておりこれらの手技の際には注意が必要である.
1 0 0 0 ペンの筆圧・傾き推定のためのグリップ型デバイスの設計と実装
- 著者
- 近藤 杏祐 寺田 努 塚本 昌彦
- 雑誌
- マルチメディア,分散協調とモバイルシンポジウム2018論文集
- 巻号頁・発行日
- no.2018, pp.1235-1243, 2018-06-27
- 著者
- 田村 元樹 服部 真治 辻 大士 近藤 克則 花里 真道 坂巻 弘之
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.12, pp.899-913, 2021-12-15 (Released:2021-12-24)
- 参考文献数
- 38
目的 本研究は,うつ発症リスク予防に効果が期待される65歳以上の高齢者のボランティアグループ参加頻度の最適な閾値を傾向スコアマッチング法を用いて明らかにすることを目的とした。方法 日本老年学的評価研究(JAGES)が24市町村に在住する要介護認定を受けていない65歳以上を対象に実施した,2013年と2016年の2時点の縦断データを用いた。また,2013年にうつ(Geriatric Depression Scale(GDS-15)で5点以上)でない人を3年間追跡し2013年のボランティアグループに年1回以上,月1回以上もしくは週1回以上の参加頻度別に,2016年に新たなうつ発症のオッズ比(OR)を,傾向スコアマッチング法とt検定などを用いて求めた。結果 参加群は,年1回以上で9,722人(25.0%),月1回以上で6,026人(15.5%),週1回以上で2,735人(7.0%)であった。3年間のうつの新規発症は4,043人(10.5%)であった。傾向スコアを用いたマッチングでボランティアグループ参加群と非参加群の属性のバランスを取って比較した結果,月1回以上の頻度では参加群は非参加群に比べて,Odds比[OR]0.82(95%信頼区間:0.72, 0.93)と,うつ発症リスクは有意に低かった。年1回以上の参加群ではORが0.92(0.83, 1.02),および週1回以上では0.82(0.68, 1.00)であった。結論 高齢者のボランティアグループ参加は,月1回以上の頻度で3年後のうつ発症リスクを抑制する効果があることが示唆された。高齢者が月1回でもボランティアとして関わることができる機会や場所を地域に増やすことが,うつ発症予防対策となる可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 訂正:高齢者の趣味の種類および数と認知症発症:JAGES 6年縦断研究
- 著者
- LINGLING 辻 大士 長嶺 由衣子 宮國 康弘 近藤 克則
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.12, pp.925, 2021-12-15 (Released:2021-12-24)
第67巻第11号(2020年11月15日発行)「LINGLING,他.高齢者の趣味の種類および数と認知症発症:JAGES 6年縦断研究」において,以下の箇所に誤りがありました。お詫びとともに下記のとおり訂正いたします。P800 筆者•共著者の所属•責任著者連絡先の修正 下線部が訂正箇所誤Ling LING∗,辻 大士2∗,長嶺由衣子2∗,3∗,宮國 康弘4∗,5∗,近藤 克則2∗,4∗ ∗千葉大学大学院医薬学府先進予防医学共同専攻博士課程 2∗筑波大学体育系 3∗東京医科歯科大学医学部付属病院総合診療科 4∗国立長寿医療研究センター老年学•社会科学研究センター老年学評価研究部 5∗医療経済研究機構研究部責任著者連絡先:〒260-8670 千葉市中央区亥鼻1-8-1 千葉大学大学院医薬学府Ling LING正LINGLING∗,辻 大士2∗,長嶺由衣子3∗,6∗,宮國 康弘4∗,5∗,近藤 克則4∗,6∗ ∗千葉大学大学院医学薬学府先進予防医学共同専攻博士課程 2∗筑波大学体育系 3∗東京医科歯科大学医学部付属病院総合診療科 4∗国立長寿医療研究センター老年学•社会科学研究センター老年学評価研究部 5∗医療経済研究機構研究部 6∗千葉大学予防医学センター責任著者連絡先:〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 千葉大学大学院医学薬学府LINGLINGP810 筆者•共著者の所属 下線部が訂正箇所WrongLing LING∗, Taishi TSUJI2∗, Yuiko NAGAMINE2∗,3∗, Yasuhiro MIYAGUNI4∗,5∗, Katsunori KONDO2∗,4∗ ∗Docter Course in Graduate School of Medical and Pharmaceutical Sciences, Chiba University 2∗Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba 3∗Department of Family Medicine, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University 4∗Department of Gerontological Evaluation, Center for Gerontology and Social Science, National Center for Geriatrics and Gerontology 5∗Research Department, Institute for Health Economics and PolicyCorrectLINGLING∗, Taishi TSUJI2∗, Yuiko NAGAMINE3∗,6∗, Yasuhiro MIYAGUNI4∗,5∗, Katsunori KONDO4∗,6∗ ∗Doctor Course in Graduate School of Medical and Pharmaceutical Sciences, Chiba University 2∗Faculty of Health and Sport Sciences, University of Tsukuba 3∗Department of Family Medicine, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University 4∗Department of Gerontological Evaluation, Center for Gerontology and Social Science, National Center for Geriatrics and Gerontology 5∗Research Department, Institute for Health Economics and Policy 6∗Center for Preventive Medical Sciences, Chiba University
1 0 0 0 遊び「届けよう!プレゼント」を通しての導入と結びの考察
- 著者
- 近藤 菜緒 小宮 加容子 平尾 美唯 畠中 彩
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.66, 2019
<p>本稿では、2018年12月15日(土)に実施した「とどけよう!プレゼント」の活動報告と、その活動結果を通して行った遊びの導入と終わりの効果についての考察を述べる。今回実施した遊びは子どもたちに主体的に遊んでもらうことを目的に、「サンタさんのお手伝いをしてください」という課題を遊びに取り入れた。また、遊びの導入と終わりが遊びにもたらす効果についての考察を行なった。その結果、導入と終わりは子どもを遊びの世界に入り込ませ、気持ちよく終わらせるための重要なプロセスであることがわかった。</p>
1 0 0 0 OA 炎症と活性酸素, フリーラジカル
- 著者
- 吉川 敏一 吉田 憲正 近藤 元治
- 出版者
- 日本炎症・再生医学会
- 雑誌
- 炎症 (ISSN:03894290)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.5, pp.413-421, 1993-09-30 (Released:2010-04-12)
- 参考文献数
- 64
- 被引用文献数
- 1 1
Oxygen-derived free radicals are mainly produced by phagocytic cells and hypoxanthine-xanthine oxidase system at inflammatory site. These oxygen metabolites and lipid peroxidation have been implicated in cell damage, interactions with other inflammatory mediators and modulation of vascular response. It is very important to modulate free radical-induced inflammatory reaction in various organs by administration of radical scavengers and antioxidants.
測器近傍の障害物の有無が気温に与える影響を定量的に評価するため,放射による観測誤差が最大で0.04℃の高精度な測器による気温観測を行い,空間広さ(「周囲の障害物と測器との距離」と「障害物の高さ」との比)に注目して解析した.観測は,首都大学東京南大沢キャンパスの陸上競技場の芝地上6地点において,2014年8月22日~9月17日に行い,その内1地点では不織布の囲いを設置して,空間広さが小さい状態を人工的に作り出した.その結果,日中は,空間広さが小さくて天気がよいほど気温が高くなり,いわゆる日だまり効果(測器近傍の障害物による風速の減少に伴う地上気温の上昇)の影響が示唆された.一方,夜間は,空間広さが小さい地点ほど気温が低くなった.これは,囲いによる風速減少により上空大気との熱交換が抑制されるとともに,囲いの中に冷気がたまりやすくなることで放射冷却の効果が強められたことが原因と考えられる.また,日中と比べて夜間には地点間の気温差は小さくなったが,これは日中と夜間の正味放射量および風速の違いを反映したものと考えられる.
1 0 0 0 OA 光の点滅と色で文字に感情を付加する研究
- 著者
- 三河 美幸 田邉 里奈 大谷 義智 近藤 邦雄
- 出版者
- Japanese Society for the Science of Design
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- pp.199, 2013 (Released:2013-06-20)
デジタルメディアを介したコミュニケーションの多くはテキストコミュニケーションである。対面コミュニケーションや電話と異なり、テキストコミュニケーションは非言語の情報を伝えるということが難しく、対面コミュニケーションや音声会話でのコミュニケーションに比べて、相手の感情が読み取りにくいといえる。非言語の情報が無く、線の幅などが統一され、素っ気ない印象を与えがちなデジタルフォントにおいて、手書き文字のように書いた時の感情が留められているような表現を、デジタル媒体でもうまく表現する事はできないだろうかと考えた。 本研究では光のゆらぎと色を用いて新たな文字の表現をすることを目的とする。文字に光の点滅を加えた文字で印象評価調査を行い、色の要素を加えて書き手の視点と読み手の視点の両方からの感情表現方法について調査を行う。光の点滅速度と感情との関係性を明らかにし、文字自身が感情情報を持つようなテキストの表現方法を提案する。