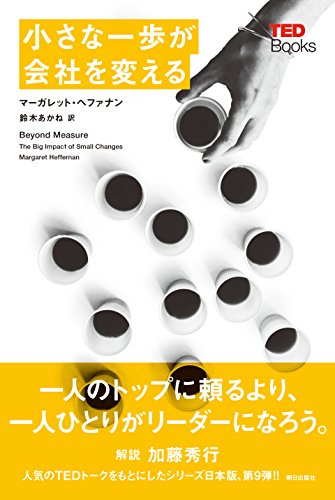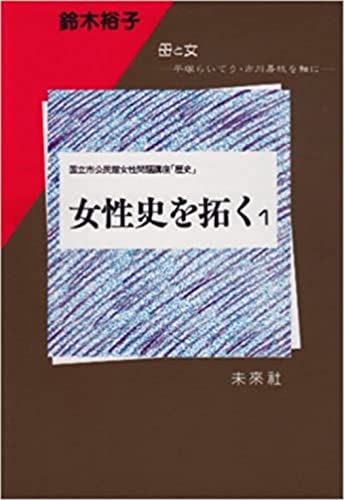1 0 0 0 システムファーマコロジー手法による医薬品副作用の予測
- 著者
- 苅谷 嘉顕 本間 雅 鈴木 洋史
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.415-419, 2018 (Released:2018-05-01)
- 参考文献数
- 11
分子標的薬は、副作用発現により治療中断となる場合があり、副作用機序解析や予測の基盤確立は大きな課題である。生体を多階層システム的に捉える手法には、チロシンキナーゼ阻害薬の副作用解析など複数の成功例があり、システムファーマコロジー手法は副作用解析に有効と考えられる。現在、in silico解析を含む様々な手法が開発されつつあり、システムファーマコロジーに基づく副作用解析や予測は更なる発展が期待される。
1 0 0 0 OA 遠心式液体クロマトグラフによる色素のクロマトグラフィーと溶離液の挙動
- 著者
- 宇津木 弘 遠藤 敦 鈴木 昇 高崎 完二
- 出版者
- 一般社団法人 色材協会
- 雑誌
- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.11, pp.707-715, 1983-11-20 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 6
遠心式液体クロマトグラフによる色素のトルエン溶液からの色素の流動及び分離機構を検討した。充テン剤を通しての色素の流動は同心円を描いて流動するが, 半径方向成分のみが関与し, 回転方向成分は関与していない。充テン剤は等容積の同心円状に配列した微小円環要素群から成るとし, 各要素がカラムクロマトグラフィーでの有効段と同じ作用をすると仮定すれば, 遠心クロマトグラフでの色素の分離もカラムクロマトグラフィーでのプレート理論に準じた取扱いで説明可能であることが認められた。この取扱いで求められる分配係数は, 吸着平衡測定結果から求められる分配係数と良い一致を示すことが認められた。
- 著者
- 寶示戸 雅之 伊藤 伸彦 佐藤 至 佐藤 衆介 岡田 啓司 鈴木 由美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学会講演要旨集 (ISSN:02885840)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, 2014
1 0 0 0 超電導発電機用大型Ni基合金回転子の開発
- 著者
- 松本 修 村井 康生 津田 陽一 鈴木 信久
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.4, pp.274-276, 1998
1 0 0 0 製塩プラントにおける腐食管理のための溶存酸素モニタリング法の開発
- 著者
- 八代 仁 荒木 渓 明 承澤 鈴木 映一
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.97-104, 2011-04-01
- 参考文献数
- 13
製塩プラントにおける構造材料の腐食を支配する重要な要因のひとつに溶存酸素が挙げられており,これを管理するため製塩プラント環境に適用可能な溶存酸素濃度分析法を提案した.プラントから採取された溶液は定量ポンプを用いて直接回転電極に送られるか,一旦サンプリングバックに採取される.サンプリングされた試料の一部は亜硫酸ナトリウムの添加等によって脱酸素され,ゼロ点校正に用いられる.<br>もうひとつの対照試料として空気飽和試料溶液を用意する.試料溶液中の溶存酸素は白金回転電極を用いるサイクリックボルタンメトリーによって,酸素還元の拡散限界電流を測定することで評価される.白金電極は周期的に酸化することで高い活性が維持される.酸素還元の拡散限界電流は溶存酸素濃度と,回転数の平方根に比例して増加する.<br>1 ppm以上のCu<sup>2+</sup>は,Pt上に還元析出することにより酸素還元電流を減少させるが,引き続きアノード分極するとアノードピークが得られたことから,Cu<sup>2+</sup>の存在を知ることが可能である.1 ppm以上のFe<sup>2+</sup>はFe(OH)<sub>2</sub>の析出によって酸素還元を著しく妨害したがNi<sup>2+</sup>はあまり影響しなかった.これらの妨害イオンが存在する場合は,カチオン交換樹脂による前処理が必要となる.試料溶液の絶対酸素濃度は,空気飽和試料の酸素濃度をWinkler 法によって別に評価することで決定できる.空気飽和試料の酸素濃度を塩類効果係数を用いて推算した結果,Winkler法によって求めた酸素濃度と比較的よく一致したことから,これを計算で行いうることが示された.
- 著者
- 川上 博士 西河 厚志 吉村 幸治 駒田 将樹 鈴木 実平
- 出版者
- 一般社団法人 溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会論文集 (ISSN:02884771)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.21-28, 2017
- 被引用文献数
- 1
The properties of rotating tool spot joining joints with different rotating tools by the combination between the shoulder diameter and the probe length were investigated in this study. The shoulder diameter of rotating tool affects the tensile strength of the joint significantly. An oversize shoulder diameter decreased the joint strength. The probe length affects more the fracture mode than the joint strength. Interface fracture mode occurred with a rotating tool of short probe length. Plug fracture occurred with a rotating tool of long probe length. Rotary motion of restricted area in the joining interface by the rotating tool was confirmed by displacements of the joining interfaces. Rankin vortex was observed on the joining interface by velocity distribution of rotary motion of joining interface. Al oxide film layers were formed spirally on upper joining interfaces
1 0 0 0 マカクザルの発声メカニズムに関する実験的研究
- 著者
- 西村 剛 ヘルブスト クリスチャン 香田 啓貴 國枝 匠 鈴木 樹理 兼子 明久 ガルシア マキシム 徳田 功 フィッチ W・テカムセ
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.53, 2018
<p>ニホンザルを含むマカクザルでは,音声行動の研究が精力的に行われており,多様な音声レパートリーが知られている。しかし,その発声メカニズムに関する知見は技術的限界により限られていた。本研究は,声帯振動の様態を声帯を通過する電流の変化により非侵襲的に観測する声門電図(EGG)を用いて,生体の音声条件付けおよび摘出喉頭の吹鳴実験により,音声の多様性をうむ発声メカニズムを明らかにした。生体からは,coo,glow,chirp発声中の計測に成功し,それぞれのEGG信号の特徴を明らかにした。摘出喉頭による実験により,その特徴を生じさせる発声運動を明らかにした。これら3つの音声の声帯振動は,声帯の内外転および呼気流の強弱により調整されており,ごくわずかな変化によって異なる音声タイプへと遷移することを示した。また,その声帯振動は,おおよそヒトの7歳児でみられるものに類似した。これらの結果は,ヒトを含む霊長類における発声メカニズムの共通性を示すとともに,サル類でも発声運動をわずかに変化させるだけで,大きく異なる音声タイプを作り出せることを示した。一方,ヒトとの相異もみられた。吹鳴実験では,マカクザルでは,声帯と同時に仮声帯も振動させている可能性を示した。それにより,音声の基本周波数を大きく下げる効果があることが示された。ヒトと異なり,喉頭室が発達したサル類では,前庭ヒダの自由度が高く,仮声帯も容易に振動し得ると考えられる。本研究は,科研費(#16H04848,西村; #17H06380, #18H03503,香田),APART(Herbst)の支援を受けた。</p>
1 0 0 0 秋巖萩原先生楷書法帖
1 0 0 0 IR 前立腺癌治療におけるLH-RHアゴニストとアンドロゲン遮断療法を振り返って
- 著者
- 勝岡 洋治 並木 幹夫 酒井 英樹 鈴木 和浩 鈴木 啓悦
- 出版者
- 医学図書出版
- 雑誌
- 泌尿器外科 = Japanese journal of urological surgery (ISSN:09146180)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.5, pp.809-823, 2013-05-01
前立腺癌に対する薬物療法の根幹ともいえるのはホルモン療法(内分泌療法)であり, 現在わが国で最も一般的に用いられているホルモン療法は, LH-RHアゴニストおよび抗アンドロゲン薬の併用療法あるいは単独療法である. LH-RHアゴニストであるリュープロレリン酢酸塩(リュープリン(R))は, 2012年9月に発売20周年を迎え, その有効性と安全性が医療現場で裏付けられた長い歴史をもつ薬剤であるが, 近年新たにGnRH(LH-RH)アンタゴニストが発売され, 現在, 他の新規ホルモン療法薬も次々と開発されており, 今後ホルモン療法による治療成績が, 飛躍的に向上することが期待されている. そこで, 本日は前立腺癌治療のエキスパートの先生方にお集まりいただき, 前立腺癌治療におけるLH-RHアゴニストとアンドロゲン遮断療法を振り返るとともに, 新薬GnRHアンタゴニストの位置付けについても論議していただいた.
1 0 0 0 OA 162. 手関節肢位と握力の関係について
- 著者
- 鈴木 徹 江原 皓吉 伊東 元 斉藤 宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.12 Suppl. (第20回日本理学療法士学会誌 第12巻学会特別号)
- 巻号頁・発行日
- pp.162, 1985-04-01 (Released:2017-07-03)
1 0 0 0 IR 経営情報学部教育プログラムにおける情報・コンピュータ教育の役割
- 著者
- 碇 朋子 岩崎 邦彦 大平 純彦 勝矢 光昭 小出 義夫 五島 綾子 小林 みどり 鈴木 直義 鈴木 竜太 高野 加代子 福田 宏 堀内 義秀 武藤 伸明 森 勇治 湯瀬 裕昭 渡邉 貴之 渡部 和雄
- 出版者
- 静岡県立大学
- 雑誌
- 経営と情報 : 静岡県立大学・経営情報学部/学報 (ISSN:09188215)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.69-82, 2002-03-25
School of Administration and Informatics (hereafter, AI) at the University of Shizuoka holds a monthly faculty research session. In the academic year of 2001-02, it was decided that the research session would adopt the systems conversation (i.e. brainstorming) style of the International Systems Institute, and have the following steps: 1. Decision on the theme to work on; 2. Input paper circulation and dialogue by email; 3. Conversation session; 4. Circulation of report from a conversation session, which also serves as the input paper for the next session; and, 5. Final report based on the above interactions. Participation in the input paper submission, conversation, and report writing is all-voluntary. It was decided that the theme be "Roles of Information Education and Computer Education in the Educational Program of the School of Administration and Informatics." This is a topic that all the AI faculty from various academic disciplines could work on. Through such a conversation process, we have two major outcomes: 1. Dialogue among the AI faculty across their A (Administration and Accounting), M (Mathematics and Model-building), and C (Computer and Communication) backgrounds. 2. Common understanding that the AI faculty members have various interpretations of the concepts such as information education; computer education; nature and levels of information and computer-related knowledge and skills the AI graduates are expected to have. Yet, regarding the necessary levels of knowledge and skills required for the AI graduates, the AI faculty seems to have, or have come to an agreement on their contents. Another point of agreement is that information education and computer education need to be linked not only to their advanced levels, but also the A and the M courses.
- 著者
- 内山 聖士 植村 聡 鈴木 宣仁 丹野 真己 田尻 洋輔
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 平成28年度大会(鹿児島)学術講演論文集 第6巻 温熱環境評価 編 (ISSN:18803806)
- 巻号頁・発行日
- pp.169-172, 2016 (Released:2017-10-31)
バドミントン競技はネットを挟み非常に軽いシャトルを挟み打ち合う競技である。筆者らはペリメータにループ状のダクトを配し、ダクトの下面に均一な風量で吹き出せる構造を有する吹出口を設けた温度成層空調システムを山形県立こころの医療センターの体育館に導入した。夏は温度成層を形成し、コート内はバドミントン競技への影響が少ない気流であることを確認した。冬はバドミントン競技に影響を与えることなく快適な空間を形成することが出来た
1 0 0 0 OA 孤立性脳有鉤嚢尾虫症の1例
- 著者
- 湯澤 泉 川野 信之 鈴木 祥生 藤井 清孝 伊藤 洋一
- 出版者
- 日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.5, pp.364-369, 2000-05-20 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 2 2
東南アジアなどに渡航歴を有する46歳男性が, 渡航先にて脳腫瘍を指摘されたため, 帰国後, 当院を受診した.主訴は頭重感であり, 神経学的には異常を認めなかった.CTとMRIでは左側頭葉皮質下に孤発性の小嚢胞を認めた.外科的に摘出された嚢胞は有鉤嚢尾虫の特徴を備えていた.近年, 本邦においては孤立性の脳有鉤嚢尾虫症が増加しており, 日常診療において孤立性嚢胞性病変を認めた場合, 本疾患を念頭において鑑別診断する必要がある.
1 0 0 0 OA 慢性肝疾患患者における頭部MRIの検討
- 著者
- 中村 太一 斎藤 聡 池田 健次 小林 正宏 鈴木 義之 坪田 昭人 鯉田 勲 荒瀬 康司 茶山 一彰 村島 直哉 熊田 博光
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.3, pp.157-162, 1997-03-05 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 12
従来より肝性脳症合併肝硬変症例では頭部MRIT1強調画像にて淡蒼球に高信号域を認めるとされる. 今回各種慢性肝疾患で頭部MRIを施行し若干の知見を得た. T1強調画像の淡蒼球の高信号は慢性肝炎では21例中1例 (4.8%), 肝硬変では41例中32例 (78%) に出現し, Child分類別ではA59%, B78%, C100%であり, 出現率は肝機能と相関がみられた.この所見は経過観察により不可逆性であった.さらに脂肪抑制画像では高信号域はより明瞭となり, その原因が脂肪沈着でないことが示唆された. MRIの所見は慢性肝炎ではほとんどみられず, 肝硬変では脳症を発症する以前より病変を認め, 慢性肝疾患の重症度の予測に役立つと考えられた.
1 0 0 0 小さな一歩が会社を変える
- 著者
- マーガレット・ヘファナン著 鈴木あかね訳
- 出版者
- 朝日出版社
- 巻号頁・発行日
- 2017
1 0 0 0 OA 体育科教育の過去・現在・未来
- 著者
- 鈴木 秀人
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.51-62, 2013-09-30 (Released:2016-08-01)
- 参考文献数
- 15
一般的には、現在行われている体育授業の直接的な起源は、19世紀後半に成立した「体操」の授業と考えられている。しかしながらここでは、英国のパブリック・スクールで課外活動として行われていたスポーツを、現在の体育授業の1つのルーツと措定する。なぜなら、現在の体育カリキュラムにおける内容の大半は「体操」ではなく「スポーツ」であり、かつ英国パブリック・スクールにおいて、それらのスポーツは単なる身体の規律訓練を超えた教育的な価値を見出されたからである。 本論文の目的は、英国パブリック・スクールに焦点を当てながら、体育科教育の過去を把握し、その過去に規定されていると思われる体育科教育の現在を描き出し、さらには、その超克を志向するという方向で体育科教育の未来を展望することである。 スポーツ活動が教育として承認されていく過程は、3つの段階にわけることができる。まず最初に、教師たちがスポーツを抑圧したり禁止したりした18世紀後半から19 世紀初頭の時期があった。次に、教師たちが校内の規律を維持するために、生徒たちの協力を得ることをねらってスポーツを公的に承認した19 世紀初めから半ば頃までの時期があった。そして第3番めに、教師たちが生徒の人格形成に役立つというスポーツの教育的な価値ゆえに、スポーツを積極的に奨励するに至った19 世紀半ば以降の時期があったのである。 最も重要な段階は第2番めの段階である。この時期のスポーツ活動の特徴は、教師たちにとっては社会統制の1つの手段であったスポーツも、生徒たちにとっては純粋に「遊び(プレイ)」であったに違いないということにある。我々は、教育としてのスポーツの出発点が、生徒たちの自発性によって導かれたというこの事実に注意を払うべきである。 このような体育科教育の歴史を振り返ると、これまでの体育科教育は運動を行う側にとっての根本的な意味、そこにある面白さを十分に考えてはこなかったことに気がつく。そういった視点からすると、運動のプレイとしての要素を重視する「楽しい体育」という体育授業論の可能性は、体育科教育の未来にとって1つの方向性を示しうる。
1 0 0 0 ビタミンB1の二形性(酵母型・菌糸型変換)調節因子としての役割
石油分解酵母Candida tropicalis Pk233株では、グルコースを炭素源とする半合成液体培地にエタノールを添加した培養で、高率に菌糸形成が誘導される。このエタノール添加培養と、無添加の酵母型増殖を示す対照培養との間での遺伝子発現の差異を利用し、サブトラクション法によって、パン酵母のチアミン合成遺伝子THI5と相同性の高いホモログ(CtTHI5と命名)がエタノール添加培養で特に発現が強い遺伝子として分離された。エタノール添加培養でのCtTHI5転写発現は、酵母の脱極性化の進む第一相で強く、菌糸の伸長が起こる第二相で微弱となった。第一相の増殖期にチアミンを培地に添加すると、その後の菌糸伸長に遅れを生じ、酵母型に近い短い菌糸が連鎖し枝分かれした菌糸体が形成された。この遺伝子を機能喪失させるため、URA3及びハイグロマイシン耐性の遺伝子を挿入させて遺伝子破壊を行ったところ、エタノール無添加培養でも細胞伸長が起こるようになり、またチアミンの類似物であるオキシチアミン添加によって、エタノール無添加培養で菌糸が形成されるようになった。そこで、CtTHI5の発現によるチアミン生合成は細胞伸長を第一相でむしろ抑制することにはたらいていることが示唆された。さらにこの遺伝子破壊株がチアミン要求性にはならないことから、この酵母には、CtTHI5以外にもチアミン生合成にはたらく同義遺伝子があることが示唆された。エタノール添加培養にバルブロ酸をさらに添加することにより、菌糸形成が抑制されることが新たに判明した。この菌糸形成の抑制は、すでに判明しているイノシトール添加の場合と同様に、第一相前半にこれらの薬剤を添加することによってもたらされ、チアミン生合成に先立ってイノシトールリン脂質生合成の調節系がはたらいていることが示唆された。バルブロ酸を添加したエタノール培養にチアミンをさらに加えると、菌糸形成の抑制が部分的に解除されることから、チアミンがこのイノシトールリン脂質生合成調節系にも関与する1因子であることが示唆された。
1 0 0 0 母と女 : 平塚らいてう・市川房枝を軸に
1 0 0 0 占領と再生
- 著者
- 鈴木安蔵 [ほか] 著 家永三郎編
- 出版者
- 汐文社
- 巻号頁・発行日
- 1976
1 0 0 0 OA 成人における1年間の自己申告の体重増減の妥当性
- 著者
- 冬賀 史織 鈴木 亜紀子 吹越 悠子 赤松 利恵
- 出版者
- 日本健康教育学会
- 雑誌
- 日本健康教育学会誌 (ISSN:13402560)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.306-313, 2014 (Released:2015-01-13)
- 参考文献数
- 14
目的:成人を対象に,1年間の自己申告の体重増減の妥当性を調べ,3 kg以上体重増減があった者において,自己申告と実測の一致・不一致による特徴を比較した.方法:1年目(2009年度)と2年目(2010年度)の両方に特定健診を受診したA健康保険組合員2,982名(男性1,492名,女性1,490名)を対象とした縦断研究である.標準的な質問票の項目「この1年間で体重の増減が±3 kg以上あった」の2年目の回答により,自己申告増減あり群・なし群に分けた後,1年間の実測の体重増減により各々で実測増減 3 kg以上と未満に分け,4群とし,自己申告の妥当性を検討した.その後,実測増,実測減に分け,8群とし,実測増減 3 kg以上の者において,自己申告と実測の一致・不一致による特徴を比較した.結果:不一致 3 kg未満増減は679名,不一致 3 kg以上増減は191名であり,全体の29.2%(870/2,982)の者が自己申告と実測が不一致だった.不一致 3 kg以上増加は,一致 3 kg以上増加よりも,男性が多かった(64.8%,p=0.012).また,男女ともに体重増加量,体重増加率に有意差がみられ,不一致 3 kg以上増加の方が小さかった(すべてp<0.05).結論:全体で約3割の者が体重変化を正しく認識できていなかった.また,実測で 3 kg以上増加していたにもかかわらず,認識できていなかった者には男性が多く,男女ともに体重増加は小さかった.