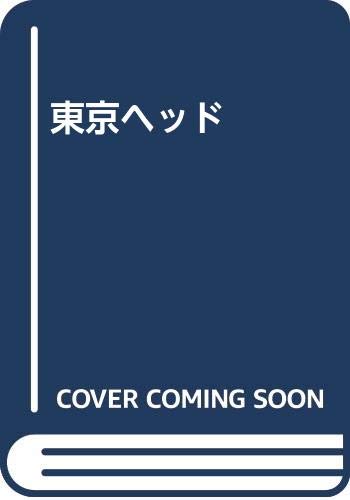1 0 0 0 OA 故障時に於ける並行送電回路の撰擇遮斷に就て
- 著者
- 弘山 尚直
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.461, pp.1454-1469, 1926 (Released:2008-11-20)
近時送電電壓が高くなり送電系統が複雜になるに從つて故障時に於て故障回路を誤り無く正確に撰擇遮斷することは困難な問題と成つて來た。ことに日本に於ては電信電話線に對する誘導電壓の關係から中性點を高抵抗を以て接地する故送電線に一線接地の起つた場合には完全なる撰擇遮斷は困難で有った。其れ故著者は此の點に關して多少研究を成して現今行はれて居る高電壓送電線にも應用し得る方法を考へ其の二三を述べてある。
1 0 0 0 OA 横浜市・横浜国立大学の通勤・通学事情
- 著者
- 土井 日出夫
- 出版者
- 交通権学会
- 雑誌
- 交通権 (ISSN:09125744)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.16, pp.56-67, 1998 (Released:2017-04-10)
1 0 0 0 OA スコットランドにおける狩猟者研修会の参加報告 ~シカ類の保護管理について~
- 著者
- 宇野 裕之
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.327-335, 2011 (Released:2012-01-21)
- 参考文献数
- 22
2010年10月27日及び28日,ダンフリース州ドラムランリグ城においてScottish Natural Heritage(SNH)が開催したレクリエーション狩猟者のための研修会に参加した.この研修会は次の6つのパートから構成されていた.1)計画と生息地アセスメント,2)シカの行動,3)動物福祉と責任,4)衛生管理,5)協力関係(組織化)及び6)ライフル射撃である.これらの講師は,SNH,Forestry Commission Scotland(FCS)及びThe Deer Initiativeなどのスタッフが連携して務めていた.FCSは公有林における木材生産や植林,野外レクリエーション,野生生物管理など幅広い活動をしている.FCSのレンジャー及び雇用された職業狩猟者がシカ類の個体群管理と森林の保護を行っている.本稿では,スコットランドのシカ類管理の概要と狩猟者教育プログラムの事例を紹介する.日本には,シカ管理体制とシカ肉の持続的利用システムを確立することが求められている.シカ管理は森林管理の一環として位置づけられるべきだと考えられる.
1 0 0 0 OA 高齢者の皮膚における温度感受性の部位差
- 著者
- 内田 幸子 田村 照子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.9, pp.579-587, 2007 (Released:2010-07-29)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 9
Twenty-eight healthy female subjects aged 61 to 88 years old wearing only shorts and brassieres lay in a supine position on a bed and their cold/warm thresholds were measured over 26 body regions under the conditions of 28°C ambient temperature and 50% R.H. Ten female subjects aged 20 to 25 years old were also measured under the same conditions as the control. The cold/warm thresholds of the leg, foot and sole were high and those of the forehead, cheek and chin were low for each group. Both thresholds were higher for the elderly than they were for the young women, and they increased with age. In addition, principal component analysis of the cold/warm thresholds revealed that individual differences in regional contrast between the front-back/trunk-peripheral of the cold/warm threshold were greater among the elderly than they were among the young women and they increased with age.
- 著者
- 岡 真理 宮下 遼 新城 郁夫 山本 薫 藤井 光 石川 清子 岡崎 弘樹 藤元 優子 福田 義昭 久野 量一 鵜戸 聡 田浪 亜央江 細田 和江 鵜飼 哲 細見 和之 阿部 賢一 呉 世宗 鈴木 克己
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2020-04-01
難民や移民など人間の生の経験が地球規模で国境横断的に生起する今日、人間は「祖国」なるものと様々に、痛みに満ちた関係を切り結んでいる。ネイションを所与と見なし、その同一性に収まらぬ者たちを排除する「対テロ戦争パラダイム」が世界を席巻するなか、本研究は、中東を中心に世界の諸地域を専門とする人文学研究者が協働し、文学をはじめとする文化表象における多様な「祖国」表象を通して、人文学的視点から、現代世界において人間が「祖国」をいかなるものとして生き、ネイションや地域を超えて、人間の経験をグローバルに貫く普遍的な課題とは何かを明らかにし、新たな解放の思想を創出するための基盤づくりを目指す。
1 0 0 0 世阿弥伝書のデジタル写本の作成および書承・伝播・受容の分析
- 著者
- 山中 玲子 MCGAUGHEY-SLANE HANNA
- 出版者
- 法政大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2021-09-28
This project's goal is a digital text corpus of Zeami's critical writings, with a focus on his first and most famous text Fushikaden, and their analysis using computational methods. The corpus will include not only transcriptions of historical manuscripts to digitally model their genealogy but also Yoshida Togo's first print publication and Nose Asaji's first annotated edition for an analysis of Zeami's modern reception. A critical evaluation of the results achieved during this fellowship will inform further consideration for building a digital scholarly edition of Fushikaden.
1 0 0 0 東京ヘッド : New edition
- 著者
- 羽田 尚子 栗原 仰基 小野 有人 文部科学省科学技術・学術政策研究所第1研究グループ
- 出版者
- 文部科学省科学技術・学術政策研究所
- 雑誌
- DISCUSSION PAPER
- 巻号頁・発行日
- vol.209,
1 0 0 0 OA ロビンソン物における子ども : 「自然」の子どもを追って
- 著者
- 長嶺 宏作
- 雑誌
- 帝京科学大学教職指導研究 : 帝京科学大学教職センター紀要 = Bulletin of Center for Teacher Development, Teikyo University of Science (ISSN:24241253)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.1-8, 2016-10-31
本稿ではロビンソン物と呼ばれる児童文学に焦点をあてながら, 近代的な主体としての子どもが, どのように描かれてきたのかを明らかにしたい. ルソーが, 『エミール』の中で成人の理想像としてロビンソンを見たように, ロビンソンは子どもにとって目指される人間像の一つでもあった. ルソー以降, ロビンソン物は, 主人公を子どもに変えて, 子どもの物語として再生産され,どんな状況においても理性的な行動をしえる「自然人」, あるいは近代的な主体の物語となった.そこでバランタインの『珊瑚島』, スティーブンスの『宝島』, ヴェルヌの『十五少年漂流記』, ゴールディングの『蠅の王』の4 つの作品を取り上げ, 「自然」の子どもの変遷を明らかにする. 4つの作品の子ども像を考察したうえで, 自明視されなくなった現代の子ども像・人間像が, どのように再び語られうるのかについて考察する.
- 著者
- 明治大学文学部読書感想文コンクール選考委員会編
- 出版者
- [明治大学文学部読書感想文コンクール選考委員会]
- 巻号頁・発行日
- 2021
1 0 0 0 OA 歯科治療を契機に口腔内不潔恐怖ならびに強迫行為を示した心因性口腔顔面痛の一症例
- 著者
- 神野 成治 海野 雅浩 鈴木 長明
- 出版者
- Japanese Society of Psychosomatic Dentistry
- 雑誌
- 日本歯科心身医学会雑誌 (ISSN:09136681)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.191-195, 2000-12-25 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 10
We report a case of psychogenic oro-facial pain with mysophobia and compulsive behaviors related to dental treatment.The patient was a 36-year-old housewife. She complained of spontaneous pain in all teeth of the upper and lower jaws. The pain had appeared suddenly in the upper incisors, around 2 years before her first visit to our hospital. In spite of dental treatment, the pain diffused to all of her teeth and gingiva. She also suffered from oral mysophobia and compulsive behaviors in the form of prolonged teeth brushing.There was no organic disease to cause her pain and no other abnormal findings were noted. The psychological tests showed that she was in a slightly depressive, anxiety state and had a psychosomatic disease type. The Yatabe-Guildford test and egogram showed her personality to be compulsive. We diagnosed her condition as psychogenic oro-facial pain with mysophobia and compulsive behaviors.We treated her with drug therapy and brief psychotherapy. The antidepressant agent (amitriptyline, clomipramine) and antianxiety agent (bromazepam) were effective for pain relief, but not for the compulsive behaviors. We also performed brief psychotherapy. She was alarmed that she had grown old when her dentist diagnosed the pain as being due to periodontal disease and afraid that the periodontal disease would worsen. This led her to clean her mouth very earnestly. The dentist suggested that her excessive brushing was bad for her at every dental examination, but she slipped into mysophobia and compulsive behaviors, avoiding food intake in order to keep her oral cavity clean and engaging in prolonged brushing. These behaviors were related to her compulsive personality. We recommended that she change her lifestyle and work outside her house, because a person of her personality type needed a social activity. Fourteen months later, she began to work again and her compulsive behaviors had diminished.This case suggested that her compulsive personality was a causal factor in her development of psychosomatic oro-facial pain and the dental treatment induced mysophobia and/ or compulsive behaviors. Psychosomatic agents and brief psychotherapy were effective.
1 0 0 0 OA 日本書紀 : 国宝北野本
1 0 0 0 OA <特集> 政治学における実験研究 その2
- 著者
- 多湖 淳
- 出版者
- 早稻田大學政治經濟學會
- 雑誌
- 早稻田政治經濟學雜誌 (ISSN:02877007)
- 巻号頁・発行日
- vol.397, pp.2-7, 2021-11-30
1 0 0 0 OA 神社本殿の分類と起源
- 著者
- 三浦 正幸
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.148, pp.85-108, 2008-12-25
寺院の仏堂に比べて、神社本殿は規模が小さく、内部を使用することも多くない。しかし、本殿の平面形式や外観の意匠はかえって多種多様であって、それが神社本殿の特色の一つと言える。建築史の分野ではその多様な形式を分類し、その起源が論じられてきた。その一方で、文化財に指定されている本殿の規模形式の表記は、寺院建築と同様に屋根形式の差異による機械的分類を主体として、それに神社特有の一部の本殿形式を混入したもので、不統一であるし、不適切でもある。本論文では、現行の形式分類を再考し、その一部を、とくに両流造について是正することを提案した。本殿形式の起源については、稲垣榮三によって、土台をもつ本殿・心御柱をもつ本殿・二室からなる本殿に分類されており、学際的に広い支持を受けている。しかし、土台をもつ春日造と流造が神輿のように移動する仮設の本殿から常設の本殿へ変化したものとすること、心御柱をもつ点で神明造と大社造とを同系統に扱うことを認めることができず、それについて批判を行った。土台は小規模建築の安定のために必要な構造部材であり、その成立は仮設の本殿の時期を経ず、神明造と同系統の常設本殿として創始されたものとした。また、神明造も大社造も仏教建築の影響を受けて、それに対抗するものとして創始されたという稲垣の意見を踏まえ、七世紀後半において神明造を朝廷による創始、大社造を在地首長による創始とした。また、「常在する神の専有空間をもつ建築」を本殿の定義とし、神明造はその内部全域が神の専有空間であること、大社造はその内部に安置された内殿のみが神の専有空間であることから、両者を全く別の系統のものとし、後者は祭殿を祖型とする可能性があることなどを示した。入母屋造本殿は神体山を崇敬した拝殿から転化したものとする太田博太郎の説にも批判を加え、平安時代後期における諸国一宮など特に有力な神社において成立した、他社を圧倒する大型の本殿で、調献された多くの神宝を収める神庫を神の専有空間に付加したものとした。そして、本殿形式の分類や起源を論じる際には、神の専有空間と人の参入する空間との関わりに注目する必要があると結論づけた。
1 0 0 0 OA DASH型クリプトクロムのDNA修復機能発現に関する理論的考察
- 著者
- 佐藤 竜馬 森 義治 松井 理紗 沖本 憲明 山元 淳平 泰地 真弘人
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.116-118, 2022 (Released:2022-05-25)
- 参考文献数
- 10
DASH型クリプトクロムは発見当初,紫外線損傷DNAを光回復できると推定された.しかし,現実にはその機能を発現せず,その明確な理由は明らかではない.本稿では,紫外線損傷DNAの光回復に欠くことのできない電子移動反応および基質の認識・結合の観点から機能の非発現の理由について調べた研究について紹介する.
1 0 0 0 OA 醫學中央雜誌 = Japana centra revuo medicina
- 出版者
- 医学中央雑誌刊行会
- 巻号頁・発行日
- vol.385(3), no.3075, 1980-11
1 0 0 0 OA 森田正馬の「土佐の犬神憑き調査」について : 祈祷性精神病提唱への粗描
- 著者
- 大宮司 信
- 出版者
- 北翔大学北方圏学術情報センター
- 雑誌
- 北翔大学北方圏学術情報センター年報 = Bulletin of Northern Regions Academic Information Center, Hokusho University (ISSN:21853096)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.133-138, 2020
1 0 0 0 OA 人類はどんな穀物酒を飲んできたか(バイオミディア2003)
- 著者
- 佐藤,洋一郎
- 出版者
- 日本生物工学会
- 雑誌
- 生物工学会誌 : seibutsu-kogaku kaishi
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.12, 2003-12-25