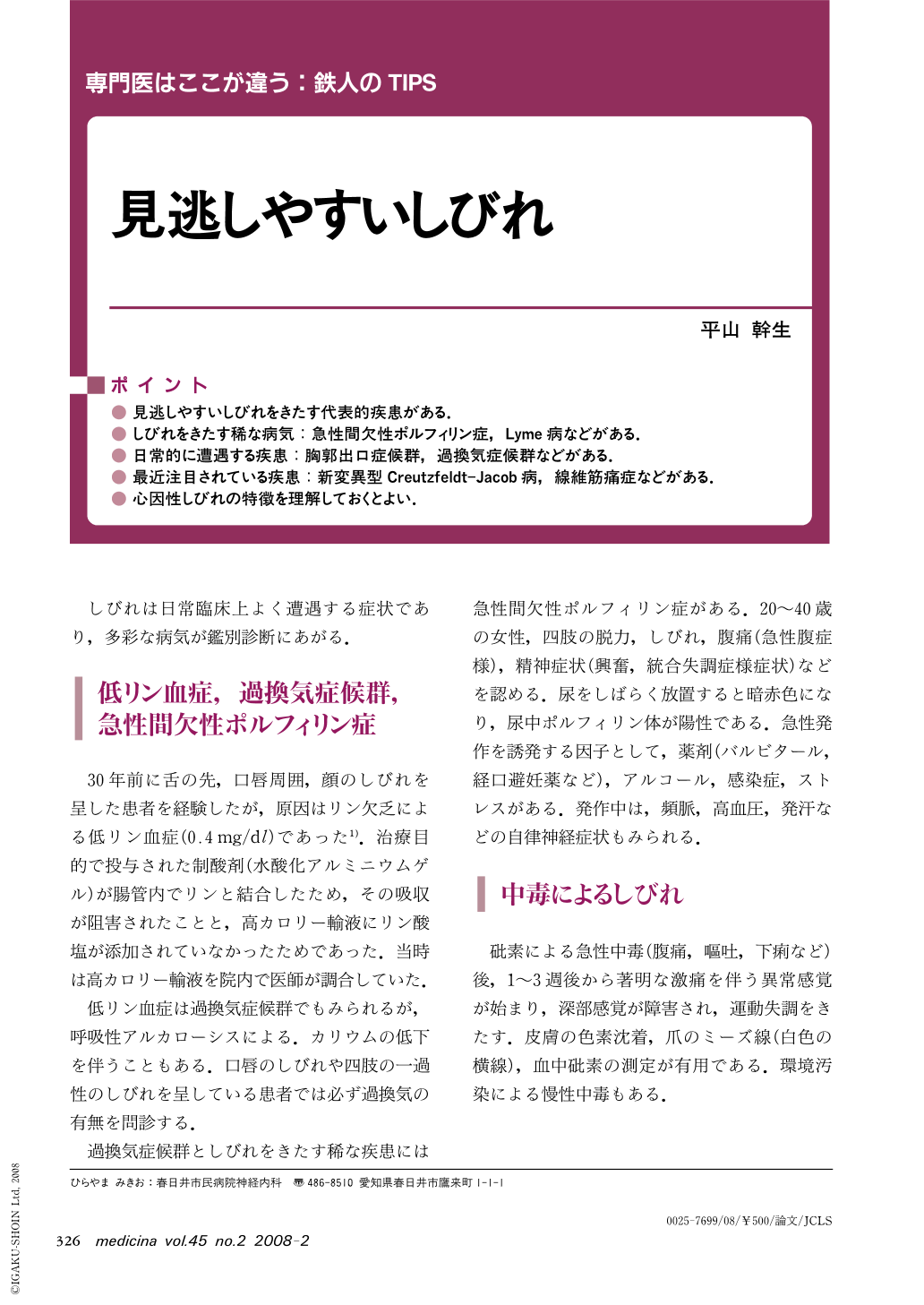1 0 0 0 OA ガンマ線照射を模擬した湿度制御環境での腐食モニタリング
- 著者
- 大森 惇志 秋山 英二 阿部 博志 端 邦樹 佐藤 智徳 加治 芳行 井上 博之 田口 光正 清藤 一 多田 英司 鈴木 俊一
- 出版者
- 公益社団法人 腐食防食学会
- 雑誌
- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.107-111, 2020-04-10 (Released:2020-10-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
ガンマ線照射による水のラジオリシスで生成する酸化剤が炭素鋼の気相中の腐食に及ぼす効果を評価するために,オゾンをモデル酸化剤として用いて50℃の湿度制御下に導入し,ACMセンサを用いた腐食モニタリングを行なった.ACM電流はオゾンの濃度に伴って高くなったことから,オゾンによる腐食促進の効果が示された.これはオゾンの還元反応あるいは水への溶解反応が早く,カソード反応を促進したためと考えられる.
1 0 0 0 見逃しやすいしびれ
1 0 0 0 日本列島域における古環境変遷の研究
- 著者
- 箱崎 真隆 坂本 稔 篠崎 鉄哉
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 学術変革領域研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2023-04-01
本研究では、先史時代の日本列島域の古環境変遷を「酸素同位体比年輪年代法」および「炭素14スパイクマッチ法」を用いて高い時空間解像度で復元する。特に①「鬼界アカホヤ噴火」の誤差0年決定、②過去6400年間の降水量と太陽活動の復元、③世界的寒冷化イベント(4.2-4.3kaイベント)の影響評価を目的とする。そのために、埋没木と遺跡出土木材の網羅的な酸素同位体比分析と炭素14分析を実施する。並行して新規の木材資料獲得と年代決定を行ない、より古い時代まで復元できる基盤形成を進める。本研究によって、日本列島域における古環境の形成と先史人類の適応について明らかにする。
1 0 0 0 OA 過去1万年間の太陽活動
- 著者
- 三宅 芙沙 堀内 一穂 宮原 ひろ子 早川 尚志 笹 公和 箱崎 真隆 前原 裕之 栗田 直幸 木村 勝彦 門叶 冬樹
- 出版者
- 名古屋大学
- 雑誌
- 基盤研究(S)
- 巻号頁・発行日
- 2020-08-31
樹木年輪の14Cや氷床コアの10Be、36Clといった宇宙線生成核種は、観測史上最大とされる1956年のSEP(Solar Energetic Particle)イベントの数十倍という過去の超巨大SEPイベントの優れた代替データである。本研究は、年輪の14Cと氷床コアの10Be、36Cl分析から、完新世(過去1万2千年間)における最大のSEPイベントの同定と、超巨大SEPイベントの発生頻度及びその発生特性の解明を目的とする。我々の太陽における発生特性を、太陽型恒星の恒星フレアと比較することで、太陽型恒星における太陽の普遍性と特殊性を評価する。
1 0 0 0 OA 衣服設計のための三次元人体形状における計測点設定 頚側点および肩先点の自動設定
- 著者
- 柳田 佳子
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 感性工学研究論文集 (ISSN:13461958)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.1-10, 2006 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 20
As part of the process of automating the steps of clothing pattern design, this research studied methodologies for automatically setting human body measurement points using a 3-dimensional human body measurement device. The subjects of the research were young women. From among the measurement points for the neck and shoulders-which are crucial for clothing design but difficult to objectively set-the research focused on the neck side points and shoulder end points. In the setting algorithm, a setting hypothesis is derived by deriving a graphical relationship between the human body form and the measurement point positions set by conducting 3-dimensional measurement and directly touching the surface of the body. Furthermore, the adopted measurement point setting theory covers issues such as necessities involved in clothing design. The adequacy of the theory was determined by verifying the following: (1) There should be a statistical match between the coordinate values of directly set measurement points and theoretically set measurement points, (2) When upper body clothing pattern development drawings are created using, respectively, the directly set and theoretically set measurement points, the shape of those patterns should match, (3) When sensory testing is performed by persons experienced in clothing design using the created patterns, they should be judged appropriate in terms of clothing form. In the results, measurement points were set with a precision approximating directly set measurement points in all verification tests, and thus it was possible to demonstrate the adequacy of the algorithm.
1 0 0 0 OA 第1回UEC杯コンピュータ囲碁大会報告
1 0 0 0 OA 共感の女性君主 ――ヴィクトリア女王が拓いた可能性――
- 著者
- 井野瀬 久美惠
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.5-19, 2020-10-20 (Released:2021-09-01)
- 参考文献数
- 37
As we saw in the enthronement ceremony in 2019 as well as the abdication message of the Emperor (now Emeritus) in 2016, the phrase “always staying together with the people” is characteristic of the Japanese constitutional system called symbolic monarchy. But we must be careful in interpreting what that phrase really means to the Emperor system in Japan.This paper will discuss this phrase in reference to the change in the British constitutional monarchy, partly because the British monarchy was and has been an ideal or model for the Japanese symbolic monarchy after 1945, and partly because both Emperors, Hirohito and Akihito, once confessed that they had been influenced by the British constitutional monarchy, particularly that of King George V (1910-1938). The important point is what types of monarchy George V had inherited under a constitutionally organized government from his father, Edward VII (1901-1910).In Britain, the phrase “staying together with the people” or “sympathy to the people” became widely applied to the monarchy during the reign of Queen Victoria (1837-1901), especially after the mid 1870s. This is usually discussed in relation to the idea of “the invention of tradition”, represented by the Golden (1887) and Diamond Jubilee (1897) of Queen Victoria. But the critical moment resulting in “the invention of tradition” and changing the essence of the monarchy, was during the 1860s, when the British monarchy lost one future that might have existed by the sudden death of the Queenʼs beloved husband, Prince Albert, and the Queenʼs withdrawal from public life to mourn him. This period led Walter Bagehot to write his farsighted essay on monarchy which was to be collected in his famous book, the English Constitution (1867). In addition, the peopleʼs feeling towards the monarchy also dramatically changed at that time. Since then, the importance of the monarchʼs popularity, as well as the sympathy between a monarch and the people, has grown.The monarchy the two Japanese Crown Princes observed while they visited Britain, in 1921 and 1953 respectively, and thought ideal under the new Japanese Constitution when they were Emperors, had been the one personalized and de-masculinized, even if we do not call it “feminization of the monarchy”.
1 0 0 0 OA 多発家系・一卵性双生児不一致例の解析による精神疾患・発達障害の新規候補遺伝子同定
1 0 0 0 OA ARMSと発達障害特性を中間表現型とした統合失調症大家系の遺伝子解析
本研究で我々は、統合失調症のrare-risk variantを同定することを目標として、統合失調症の多発大家系を対象として、遺伝学的解析を行った。統合失調症多発大家系に属する10名に全エクソン解析を行った。同定された2つの候補遺伝子に関して、統合失調症288名、健常者419名のtarget sequencingを行った。その結果、候補遺伝子はGene Aだけに絞られた。Crispr-cas9にて作成した遺伝子改変マウス(Gene Aのノックインマウス)の行動解析を行った。行動解析の結果、遺伝子改変マウスは活動性が低いまたは運動機能が減衰している可能性が示された。
1 0 0 0 OA ニュース
- 著者
- 小島 あゆみ 高橋 真理子
- 出版者
- 日本科学技術ジャーナリスト会議
- 雑誌
- 日本科学技術ジャーナリスト会議 会報 (ISSN:24364525)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.103, pp.4, 2022 (Released:2022-06-30)
ZOOM井戸端会議 医療ジャーナリズムの日米比較 第13回ZOOM井戸端会議は3月16日に開催され、新会員で、日本医学ジャーナリスト協会(MEJA)会長の浅井文和さんが「医学ジャーナリズムの現状と課題」と題して話題提供した。 (会員 小島あゆみ)2年ぶりに科学ジャーナリスト塾 9月から開催 JASTJの看板事業の一つである科学ジャーナリスト塾を2年ぶりに開講する。第20期となる。世の中がDX化に大きく動いているのに合わせ、通常の講義はオンデマンド配信し、2週に1度のライブZOOM講義では双方向のやりとりを重視、これらにリアル講義や取材実習も組み合わせるというきめ細やかなカリキュラムを考えている。講師、アドバイザーに多くの会員の協力が得られており、9月開講に向けて精力的に準備を進めている。 (第20期塾長 高橋真理子)
1 0 0 0 OA 足関節内反捻挫を繰り返し受傷した脚の長腓骨筋の筋輝度に関する研究
- 著者
- 酒井 章吾
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.44 Suppl. No.2 (第52回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1201, 2017 (Released:2017-04-24)
【はじめに,目的】超音波診断装置では,骨格筋量の指標である筋厚測定に加え,骨格筋の質の指標となる筋エコー輝度(以下,筋輝度)の測定が可能である。筋輝度は筋内脂肪などの非収縮性組織を反映し,筋輝度が筋力と負の相関を示すことが報告されている(Fukumotoら2011)。筆者らは骨格筋の質的評価が重要であると考えている。足関節内反捻挫では,受傷時の急激な伸張による筋損傷や疼痛による不動,関節の腫脹などによって神経筋の活動が低下し,長腓骨筋に代表される足関節外反筋の筋力低下が生じるとされる(Konradsen 1998)。本研究の目的は,足関節内反捻挫を繰り返した脚の筋力,筋厚,筋輝度を足関節内反捻挫の既往のない脚と比較することで,その特徴を明らかにすることを目的とした。【方法】対象は,足関節内反捻挫を繰り返し受傷した経験(受傷回数7.3±2.9回)を持つ男性(I群)7名7脚(年齢22.0±1.3歳,身長170.4±5.9cm,体重62.5±9.3kg)と内反捻挫の既往がない健常男性(N群)6名12脚(年齢21.8±1.5歳,身長174.5±10.6cm,体重61.0±10.7kg)とした。足関節外反筋力の測定は,Biodex System3(Biodex Medical Systems)を使用し,等速性(120°/s)の求心性・遠心性筋力の最大値を体重で除した値を算出した。超音波診断装置(Noblus;Hitachi,Ltd)による長腓骨筋の評価は,腓骨頭と外果を結んだ線の近位25%の部位で長腓骨筋の画像を描出した後,筋厚および筋輝度を算出した。筋輝度はImage J(NIH社製)を用いて,0から255の256階調で表記される8bit-gray-scaleによって算出され,値が大きいほど非収縮性組織が多いことを示す。統計学的解析は,SPSS statistics20にて,筋力,筋厚,筋輝度の比較に対応のないt検定を使用した。危険率5%未満を有意とした。【結果】足関節の求心性外反筋力(Nm/kg)はI群0.34±0.11,N群0.53±0.18,遠心性外反筋力はI群0.48±0.13,N群0.72±0.25であり,I群で求心性36%,遠心性33%の有意な低下を示した(p<0.05)。筋厚(mm)はI群24.59±1.7,N群26.28±2.8であり有意な差はなかった。筋輝度はI群102.96±16.97,N群77.46±5.34であり,I群で25%の有意な高値を示した(p<0.01)。【結論】N群に比べI群では有意に筋力が低値を示したにも関わらず,筋厚は群間で差がなかった。I群では長腓骨筋内の筋内脂肪などの非収縮性組織の割合の増加が,足関節外反筋力の低下に関与している可能性が示唆された。
1 0 0 0 超音波エコー輝度を用いた骨格筋内脂肪の評価
- 著者
- 福元喜啓
- 雑誌
- 第49回日本理学療法学術大会
- 巻号頁・発行日
- 2014-05-08
骨格筋量は筋力発揮のための主要な要因であることから,臨床において筋萎縮の評価や筋肥大に向けたトレーニングは重要である。特に高齢期における筋量減少(サルコペニア)は,転倒・骨折や総死亡リスクの因子ともなるため,その早期発見や予防は極めて重要である。筋萎縮の評価手段としては従来,高価で大がかりなCTやMRIを用いた筋断面積が推奨されてきたが,近年の安価で非侵襲的な超音波画像診断装置の普及により,臨床でも簡便に評価できるようになった。超音波画像で計測される筋厚は,CTやMRIなどとも高い相関があるなど,筋量指標のひとつとしての妥当性・信頼性も示されている。 しかし問題点として,筋量だけの評価では筋力や身体機能との関連性は中等度に過ぎないことが報告されている。この理由のひとつとして,筋萎縮に伴い筋内の脂肪浸潤といった非収縮組織の増加も生じることが挙げられる。そのため筋断面積や筋厚による筋量評価では,そのような筋内脂肪も含めて筋量として過大評価してしまい,筋力や身体機能との関連を減弱させてしまうと考えられる。このことから,筋萎縮の程度を正確に把握するためには,筋量のみでなく併せて筋内脂肪量も評価する必要性がある。 近年,超音波診断装置を用いた筋内脂肪増加の評価方法として,筋エコー輝度(以下,筋輝度)が注目されている。超音波画像上では萎縮筋は,筋厚が減少するだけでなく白っぽく映る(すなわち筋輝度が高くなる)が,この筋輝度の上昇が筋内脂肪の増加を反映することが明らかとなっている。筋輝度の定量的評価手段としては,256階調(0~255)で数値化される8bit gray scaleが用いられ,数値が高くなるほど筋輝度が高い,つまり筋内脂肪量が多いということを示す。このように超音波画像診断装置は簡便に筋量・筋内脂肪量の双方を評価できることから,理学療法学分野における臨床応用も期待されている。本講演では,筋内脂肪量の指標としてこの筋輝度を用いた我々の研究結果を紹介する。1)筋内脂肪量と筋力との関連 筋輝度の有用性を示すには,筋輝度が筋力に影響するかどうかを調べる必要がある。そこで我々は,地域在住の中高齢者を対象とし,大腿四頭筋の筋厚・筋輝度と筋力との関連性を調べた。その結果,筋力の影響因子として筋厚と筋輝度がともに抽出されたことから,筋量だけでなく筋内脂肪量も筋力に影響を及ぼすことが明らかとなった。また,筋輝度は体脂肪率やBMI,皮下脂肪厚とは相関がなかったことから,個々の筋の筋内脂肪量は体脂肪率やBMIなどからは予測できないことが明らかとなった。(Fukumoto et al. Eur J Appl Physiol 2012)2)四肢・体幹筋における筋厚と筋内脂肪量の加齢変化 加齢に伴う筋萎縮と筋内脂肪増加の程度が四肢・体幹筋によって異なるかを調べる目的で,若年者および地域在住の中高齢者を対象として,上腕二頭筋,大腿四頭筋と腹直筋の筋厚と筋輝度を計測した。若年者との比較の結果,上腕二頭筋と大腿四頭筋の筋厚減少は中年期では生じておらず前期高齢期から始まっていたが,筋輝度の上昇は中年期からすでに始まっていた。一方,腹直筋においては筋厚の減少・筋輝度の上昇ともに,中年期から生じていた。このことから,四肢筋では加齢に伴う筋内脂肪増加は筋萎縮よりも早期に生じること,体幹筋では中年期から筋萎縮・筋内脂肪増加の双方が生じることが明らかとなった。3)変形性股関節症(股OA)患者における下肢・体幹筋の筋萎縮・筋内脂肪増加の特徴 股OA患者の筋力低下は多くの研究で報告されており,運動能力低下の因子となることが明らかとなっている。しかしいくつかの研究で,股OA患者は健常者と比較しても有意な筋萎縮はしていないとの報告がなされている。そこで我々は,股OA患者の筋力低下には筋萎縮ではなく筋内脂肪の増加が関連しているとの仮説を立て,股OA患者と健常者の下肢・体幹筋の筋厚・筋輝度を比較した。結果,健常者と比べ股OA患者の筋厚は股関節周囲筋ではなく大腿四頭筋で減少していた。また股OA患者の筋輝度は,中殿筋,大腿四頭筋,腹直筋で上昇していた。以上のことから,股OAでは中殿筋と腹直筋は筋萎縮をしていないが筋内脂肪増加が生じていること,大腿四頭筋では筋萎縮・筋内脂肪増加の双方が生じていることが明らかとなった。(Fukumoto et al. Ultrasound Med Biol 2012)4)筋力トレーニングによる筋内脂肪量の変化 筋力トレーニングによって,筋量の増加だけでなく,筋内脂肪減少も生じることが報告されている。しかし,どのようなトレーニング方法がより効果的かは明らかではない。近年,高齢者に対する高速度での筋力トレーニング(パワートレーニング)の効果が報告されている。我々は股OA患者を対象とし,高速度および低速度での筋力トレーニングを8週間実施し,運動速度により筋厚および筋内脂肪量の変化に違いがあるかどうかを調べた。結果,筋厚の増加は両トレーニングで同程度であったが,筋内脂肪減少は低速度と比べ高速度筋力トレーニングで大きかった。また,一部の運動能力の改善においても高速度トレーニングの方が大きいという結果が得られた。このことより,高速度での筋力トレーニングは筋内脂肪減少に有効であることが示唆された。(Fukumoto et al. Clin Rehabil 2014) 本講演ではこれらの研究結果を紹介するとともに,筋輝度研究の今後の展望や課題についても述べる。
- 著者
- 渡井 康之 松井 岳巳
- 出版者
- 公益社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- 生体医工学 (ISSN:1347443X)
- 巻号頁・発行日
- vol.54Annual, no.Proc, pp.3T5-3-6-1-3T5-3-6-2, 2016 (Released:2016-11-19)
- 参考文献数
- 4
To prevent heat stroke, we will develop a system to determine presence or absence of a rise in deep body temperature using physiological indices, i.e., heart rate, respiratory rate and body surface temperature. Prior to development, we conducted tests using ergometer for 15 min. with nine male students. We measured three physiological indices and deep body temperature for 15 min. with one-minute intervals after the exercise and conducted linear discriminant analysis by leave-one-out cross-validation. 37.5 degrees of deep body temperature was set as boundary and we classified heat stroke preliminary group from normal one. The sensitivity was 90.5% and the positive predictive value was 47.5%.
1 0 0 0 OA 米国ベンチャーキャピタルのパフォーマンスの実態
- 著者
- 小野 正人
- 出版者
- 日本ベンチャー学会
- 雑誌
- 日本ベンチャー学会誌 (ISSN:18834949)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.45-53, 2011-09-15 (Released:2019-04-12)
本稿では、米国のベンチャーキャピタルの行動とパフォーマンスを個別ファンドに踏み込んで実証分析を試みた。米国のVCファンドで一般に言われる高い収益率はインターネットバブル期に限られたものであり、2001年以降は全体として収益率がマイナスとなっている。また、高いリターンを上げた一部のファンドがVCファンド全体の収益の大半を占めており、ファンド間で収益の偏りが大きい構造にあることが確認された。この偏在は、IPOやM&AによってVCが実現する売却額(投資先の企業価値)に大きな格差があるためであることが、投資モデルと史的分析により推定できる。さらに、好成績をあげたファンドは一流と評価されるVCファームに偏在し、その成績は次回以降も続く傾向がある。このような特定のVCが持つ競争力は、その実績、評価、ネットワークによって形成された可能性が高い。今後、VCファンドの収益の大幅な回復は期待しにくく、他方でVC以外からの資金調達で成長するベンチャーも存在感を高めているなど、米国のベンチャー投資は大きな転換点にある。
- 著者
- 齋藤 翔太朗
- 出版者
- 東京大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- 経済学論集 (ISSN:00229768)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.4, pp.93-116, 2023-01-31 (Released:2023-09-20)
- 参考文献数
- 26
イギリスの移民政策の歴史において,1905年外国人法は,入国管理の政策基調が「開放」から「規制」へと一転し,現在の入国管理制度の原型が成立した画期として位置づけられている.ところが,その一方で,実際の効果については消極的にしか評価されてこなかった.本稿では,1905年外国人法に基づいて実施された外国人の入国管理制度の特質と,その歴史的意義について,同法をめぐる様々な対立・欠陥・相違に注目しながら考察する.本稿は次の点を指摘する.第1に1905年外国人法には,入国管理政策として移民規制と難民庇護という対立的な要素が併せて制度化され,さらに政治的・宗教的難民については「推定無罪」の原則が指示されていた.第2に実際に入国管理の対象となる外国人旅客は限定されるとともに,入国規制の対象となる基準が不明瞭であるという欠陥が存在していた.第3に施行者であった自由党の内務大臣は,戦時の入国管理には積極的であった一方で,平時の入国管理には消極的であった.また「外国人問題」の発生に対しては移民規制よりも社会改良を主張していた.
- 著者
- 吉田 悦章
- 出版者
- 立命館大学 アジア・日本研究所
- 雑誌
- 立命館アジア・日本研究学術年報 (ISSN:2435421X)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.45-69, 2023 (Released:2023-09-20)
This paper is intended to comprehend the recent fiscal behavior of the Government of the Republic of Uzbekistan, focusing on its measures against the Covid-19 pandemic, which was first found in the country in March 2020. The fiscal discipline of the Republic has been regarded as prudent, and as shown in several statistics, it has a low level of public debt compared to its GDP. The Government responded quickly upon the outbreak of the pandemic to cope with the social and economic downturn, partly sacrificing its prudent fiscal discipline. This paper depicts and analyzes the facts and background of the situation, not just by referring to statistical development, but also by observing political considerations as well. Furthermore, this paper describes a recent government initiative of issuing sukuk (Islamic bonds). In conclusion, the fiscal situation of the Republic is evaluated as stable, and forecasted to remain so unless several worse-than-expected scenarios happen.
1 0 0 0 OA 日本漢方医学における吐方について:江戸時代医学の一様相
- 著者
- 舘野 正美
- 出版者
- 立命館大学 アジア・日本研究所
- 雑誌
- 立命館アジア・日本研究学術年報 (ISSN:2435421X)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.1-19, 2023 (Released:2023-09-20)
Toho 吐方(emetic remedy)is one of the three distinctive techniques in traditional Chinese/Japanese medicine. In the Edo era 江戸時代 in Japan, it is alleged that Okumura Ryochiku 奥村良筑(1689–1761)was the pioneer of this medical technique, and after him, his disciples Nagatomi Dokushoan 永富独嘯庵(1732–1766), Ogino Daishu 荻野台州(1737–1806), and Tanaka Hitsudai 田中必大(1725–1801)succeeded him both in practice and theoretical formulations. At the same time, Emi Sanpaku 恵美三白(1707–1781)implemented it in his own method. However, it was an extremely difficult technique for the followers to emulate. Therefore, we cannot find any further practitioners in his school. Then, Nakagami Kinkei 中神琴渓(1744–1833)integrating the attainments above, establishing this method as one of his repertoire of treatments. Though his achievement was also enormously challenging for his apprentices to follow, they efficaciously succeeded even in a part of it, as he taught them diligently. Kako Kakushu 加古角洲(1776–1832)was one who practiced it, and Kitamura Ryotaku 喜多村 良宅(18C-19C)was another who predominantly used it in the treatment of psychiatry. Finally, Watanabe Kunʼyo 渡邉君耀(19C)described those phases almost at the end of the Edo era in one short work. We should learn the philosophy but just clever techniques from them for our medicine today.
1 0 0 0 OA フランス海軍士官が函館で計測した弁才船の図面
- 著者
- 小嶋 良一
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 日本船舶海洋工学会誌 KANRIN(咸臨) (ISSN:18803725)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.ii, 2023-03-10 (Released:2023-09-20)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 中世における呉音漢音混読現象の展開 『色葉字類抄』と『日葡辞書』の漢語語形の比較を通じて
- 著者
- 大島 英之
- 出版者
- 計量国語学会
- 雑誌
- 計量国語学 (ISSN:04534611)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.6, pp.373-388, 2022-09-20 (Released:2023-09-20)
- 参考文献数
- 15
現代語では,言語(漢音ゲン+呉音ゴ)のように,呉音と漢音を混ぜ読み(以下「混読」と呼ぶ)する漢語は多くあるが,中世以前にはほとんどなく,後出の形とされている.しかし,特定の時代における混読の実態や,その通時的変遷については詳らかでない部分が多い.本稿では,呉音・漢音の音形が明らかに対立する漢字同士で構成される熟語を分母とした時の,呉音ないし漢音同士で読まれる漢語に対する,混読される漢語の割合を,「混読率」と定義し,中世の両端に位置する辞書資料における混読率を求めた.その結果『色葉字類抄』の混読率は約15%,『日葡辞書』の混読率は約24%と求まり,中世において混読現象が拡大していることが明らかとなった.中世に混読が増加した背景については,二資料に共通する漢語の語形を比較した結果から,特定の漢字に呉音・漢音どちらか一方が固定化する「漢字音の一元化」の影響が大きいことを論じた.