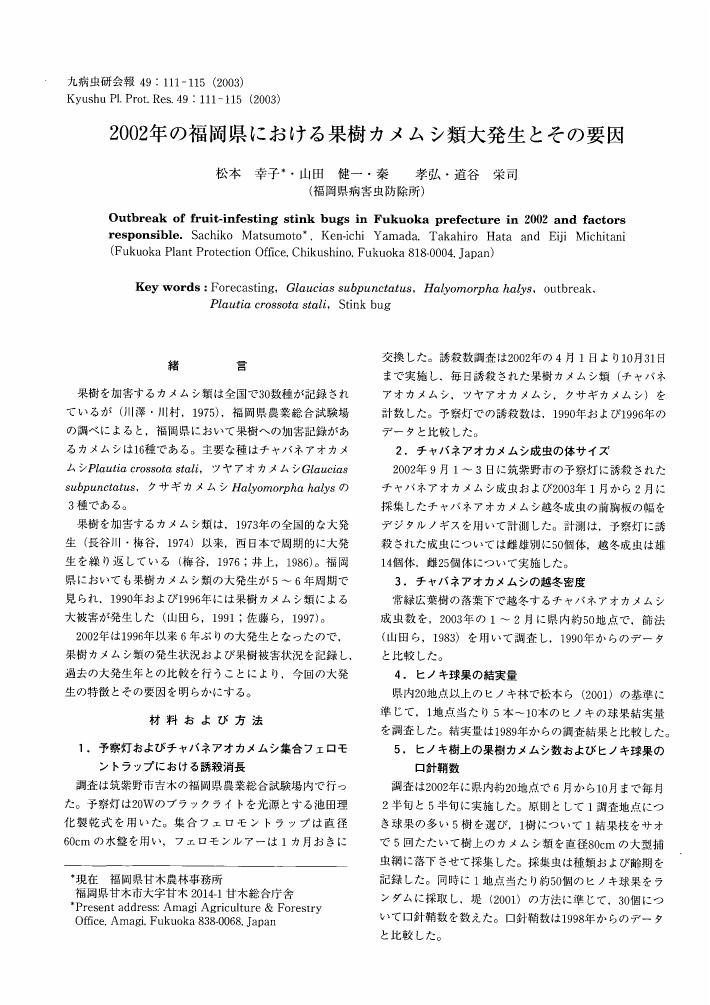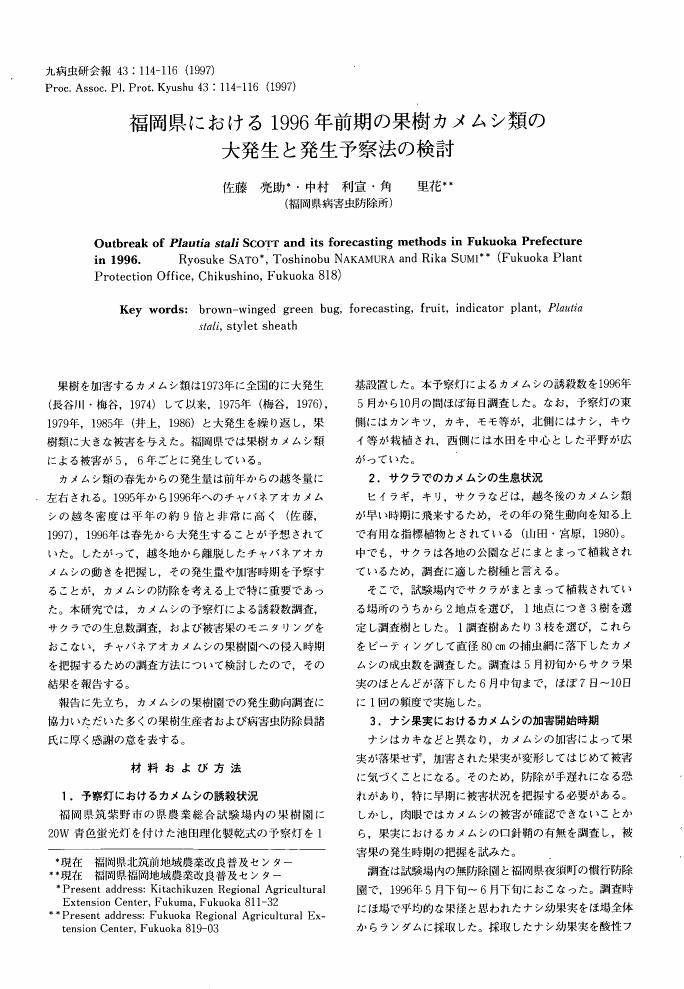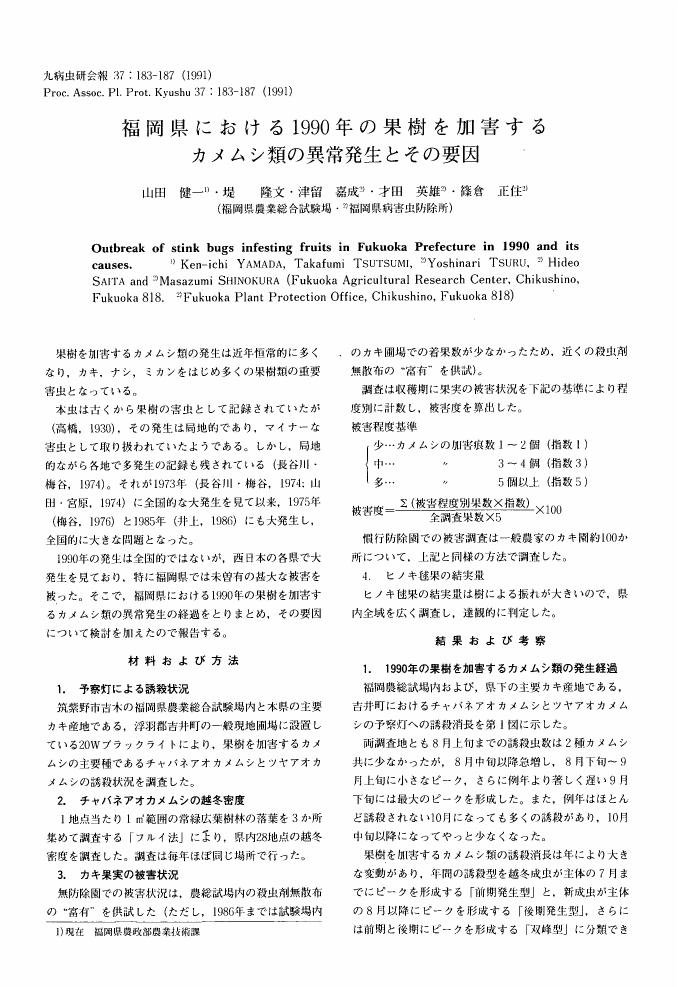1 0 0 0 OA 最終処分場における水銀廃棄物固化体の埋立特性(その2)
- 著者
- 伊東 賢生 川瀬 敬三 平田 修 柳瀬 龍二 加藤 貴史 高岡 昌輝 日下部 武敏 高橋 史武
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第33回廃棄物資源循環学会研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.397, 2022 (Released:2022-11-30)
廃水銀の中間処理・処分方法に関しては廃水銀を硫化設備で硫化し、硫化水銀の固化体を処分すると定められている。筆者らは、水銀廃棄物の埋立手法を確立するため、埋立地における水銀の環境リスクを低減させる最適条件として、黒色硫化水銀のセメント固化体を準好気性埋立地の中層部(非滞水部)に処分する手法を提案した。そこで、水銀廃棄物の埋立処分において、さらに水銀の流出リスクの低減化手法を確立させるため、水銀廃棄物固化体に注目し、作成手法の異なる3種類の固化体(改質硫黄固化体、エポキシ樹脂固化体、低アルカリセメント固化体)を用いた埋立実験を2020年7月より開始した。その経過20ヶ月間の浸出水への水銀流出は、水銀廃棄物固化体を実験槽中央部に埋立処分した場合、いずれの埋立手法においても、水銀流出率は0.000006%以下となり、固化体から浸出水への水銀流出はほとんどないと考えられた。
1 0 0 0 OA 医療機関における弁護士の役割:病院経営の立場から
- 著者
- 三宅 京子
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.101-104, 2020-01-15 (Released:2020-02-19)
- 参考文献数
- 2
弁護士は医師と敵対する立場にあると考えていませんか.弁護士を病院に常駐させることは,病院やスタッフにとって多くのメリットがあります.発展を続ける医療分野では,医療従事者は新たな知識や技術を身に着け実践することに労力を費やすため,その他の急激な社会変化や院内外の事情変化への対応を負担と感じる人も多い現状があると考えます.そのような現状に対して,病院内に病院運営や経営に関わる弁護士を常駐させ,院内外の調整役として活用すれば,コミュニケーションや交渉がスムーズに進みます.
1 0 0 0 OA 医療機関における弁護士の役割:コンプライアンスの視点から
- 著者
- 竹本 昌史
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.97-100, 2020-01-15 (Released:2020-02-19)
情報化社会の到来により,コンプライアンス運営が非常に重要な時代になっている.これまで閉鎖的であった医療機関もその例外ではない.医療機関におけるコンプライアンス対応としてリスクに対する予防や事後対応システムの強化が強く求められている.医療機関は,医療の専門職種の集まりであり,その性質や制度上コンプライアンス対応に関して統制が困難な面がある.そこで,法律の専門家である弁護士を登用し,予防や事後対応システムとして機能させることが考えられる.医療機関内に弁護士をシステムとして置くことで,法律や裁判例を意識した対応が浸透され,医療機関の内部からコンプライアンス運営が支えられることを期待する.
1 0 0 0 OA 医療機関における弁護士の役割:イントロダクション
- 著者
- 水沼 直樹
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.92-96, 2020-01-15 (Released:2020-02-19)
- 参考文献数
- 16
弁護士が職員として医療機関に常駐した歴史は浅く,現在,医療機関の常勤弁護士は20名に満たない.院内弁護士は,医療機関のあらゆる法務・経営のみならず,医療安全分野にも関与し,調査,支援,助言等を尽くしている.また関連施設(介護施設やリハ病院等)の問題も取り扱う.院内弁護士の雇用形態や条件は所属機関によって異なる.院内弁護士の質は,顧問弁護士との協働作業や同職者間での研究会等によって維持されている.院内弁護士は,新たに起こる問題に対して,所属機関の実情に応じた解決を導いている.院内弁護士の活動には,患者からの相談に応ずる場合には病院サービスとして,また職員からの相談に応ずる場合には福利厚生サービスとしての側面がある.
1 0 0 0 OA 医療機関における弁護士の役割:医療安全管理の視点から
- 著者
- 瀬尾 雅子
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.105-109, 2020-01-15 (Released:2020-02-19)
- 参考文献数
- 2
医療安全管理は,医療機関内弁護士の活躍が期待される領域である.医療機関内弁護士は,医療安全上の事例から紛争リスクを早期に覚知して法的な助言を行い,紛争化を予防することができる.その他,事故調査における事実認定や報告書作成,インフォームド・コンセント文書や各種マニュアルの作成,法改正に対応した院内体制整備など,医療安全管理において法律家の能力が活用される場面は多岐にわたる.一方で,医療機関内弁護士には,ガバナンス,契約,人事労務など,医療安全管理にとどまらない院内法務機能も期待される.医療機関内弁護士の能力を最大限に生かすために組織内でどのように処遇するかは,今後検討されるべき課題である.
1 0 0 0 OA 医療機関における弁護士の役割:医療機関管理者の視点から
- 著者
- 古家 仁
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.110-113, 2020-01-15 (Released:2020-02-19)
医療機関における弁護士の役割について医療機関管理者の視点から現状と今後の展望,課題について検討した.現在奈良県立医科大学では3名の弁護士と契約をし,大学法人では職員や学生に関わるいろいろな懸案に対して主に相談を,病院では患者とのトラブルに関する相談に加えて訴訟,裁判への参加など種々の業務を担っていただき役に立っている.今後大学法人や病院での弁護士の役割は増大すると考えられる.
1 0 0 0 OA 私はここでその幻影を観ているのか? : マラルメの『エロディアード』上演をめざして
- 著者
- 中畑 寛之
- 出版者
- 学校法⼈ 大阪音楽大学
- 雑誌
- 大阪音楽大学研究紀要 (ISSN:02862670)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.55-71, 2007 (Released:2021-04-01)
19世紀末パリに生きた象徴派詩人ステファヌ・マラルメの未完の遺作『エロディアードの婚礼神秘劇』(1957年に死後出版)を採りあげ、その上演可能性を考えてみたい。22歳のときに制作が始まる「エロディアード」は、「もはや悲劇ではなく、詩篇とする」という若き詩人自身の言明ゆえに、その作品が根底に持っている演劇との繋がりをしばしば見失わせてきたように思われる。書簡などから再構成した30年以上に及ぶその制作過程、詩人自身の演劇論、そしてテクストそれ自体の解釈によって多角的に、この作品が晩年のマラルメが夢想した<祝祭>の譜面であること、そしてその演劇性を考察することで、来るべきその舞台上演の姿を明らかにする。
1 0 0 0 ケニア、「過疎地域」に見るヒョウと人々のかかわりの変容と共存
本研究の目的は、保全生態学と社会学の異分野融合的な手法を用いて、野生動物であるヒョウと人との関係を解明し、共生の方策を追求していく。そのためには、ケニアのバリンゴ県において、1)GPS首輪を野生のヒョウに装着を試み、センサーカメラを設置。個体識別し、生息域の推定を行う。2)ヒョウの複数個体間の生息密度や家畜のいる集落との距離から、ヒョウの社会性や環境適応性を明らかにする。3)地域住民に対する参与観察や半構造的インタビューを通じて住民感情を把握し、その関係性からヒョウの生態調査結果との整合性を検証する。調査地は人々の生活が密集しておらず、野生動物の生息についてもデータが乏しい地域である。
1 0 0 0 OA 2002年の福岡県における果樹カメムシ類大発生とその要因
1 0 0 0 OA 福岡県における1996年前期の果樹カメムシ類の大発生と発生予察法の検討
1 0 0 0 OA 福岡県における1990年の果樹を加害するカメムシ類の異常発生とその要因
1 0 0 0 OA 線虫を用いた次世代膵癌診断法の有効性についての検討
膵癌の予後は極めて不良であり、新規診断・治療法の開発が急務となっている。本研究では野生型線虫の嗅覚を応用したN-NOSE法を用いることで癌の匂いを科学的に検討し線虫が膵腫瘍発生を組織学的に確認された膵腫瘍自然発生モデルマウスの尿に対してもヒト同様の誘引行動を呈することを示した。線虫の行動をげっ歯類で再現できたことの重要性は、これまではヒトの臨床検体を用いていたため、サンプルの多様性も影響し、原因物質の同定までは至らなかった可能性も示唆されるが、このマウスモデルを利用することで、走行性を惹起する物質の同定が可能となることが期待され、N-NOSE法が膵癌の早期診断の一助になる可能性も示唆された。
- 著者
- Taeko Mizutani Ryota Mori Misaki Hirayama Yuki Sagawa Kenji Shimizu Yuri Okano Hitoshi Masaki
- 出版者
- Japan Oil Chemists' Society
- 雑誌
- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.12, pp.993-1001, 2016 (Released:2016-12-01)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 24 24
Sodium lauryl sulfate (SLS), a representative anionic surfactant, is well-known to induce rough skin following single or multiple topical applications. The mechanism by which SLS induces rough skin is thought to result from the disruption of skin moisture function consisting of NMF and epidermal lipids. However, a recent study demonstrated that topically applied SLS easily penetrates into the living cell layers of the epidermis, which suggests that physiological alterations of keratinocytes might cause the SLS-induced rough skin. This study was conducted to clarify the effects of SLS on keratinocytes to demonstrate the contribution of SLS to the induction of rough skin. In addition, the potentials of other widely used anionic surfactants to induce rough skin were evaluated. HaCaT keratinocytes treated with SLS had increased levels of intracellular ROS and IL-1α secretion. Application of SLS on the surface of a reconstructed epidermal equivalent also showed the increased generation of ROS. Further, SLS-treated cells showed an increase of intracellular calpain activity associated with the increase of intracellular Ca2+ concentration. The increase of intracellular ROS was abolished by the addition of BAPTA-AM, a specific chelator of Ca2+. In addition, IL-1α also stimulated ROS generation by HaCaT keratinocytes. An ESR spin-labeling study demonstrated that SLS increased the fluidity of membranes of liposomes and cells. Together, those results indicate that SLS initially interacts with cell membranes, which results in the elevation of intracellular Ca2+ influx. Ca2+ stimulates the secretion of IL-1α due to the activation of calpain, and also increases ROS generation. IL-1α also stimulates ROS generation by HaCaT keratinocytes. We conclude from these results that the elevation of intracellular ROS levels is one of the causes of SLS-induced rough skin. Finally, among the other anionic surfactants tested, sodium lauryl phosphate has less potential to induce rough skin because of its lower generation of ROS.
1 0 0 0 OA 送電における変圧器の働きと仕組みの教材開発
- 著者
- 本多 満正 田邉 康夫 村石 幸正 小松 寛 前田 香織 山岡 寛人
- 出版者
- 日本教科教育学会
- 雑誌
- 日本教科教育学会誌 (ISSN:02880334)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.37-42, 2005-12-01 (Released:2018-05-08)
中学校理科の学習項目である「電磁誘導」と技術・家庭科の電気領域の学習項目である「エネルギー伝送」と「交流」について視覚をともなって学習する教材を開発し,実験授業でその学習効果を調べた。開発した教材は,豆電球2個を抵抗値の大きいニクロム線で並列に接続した回路に交流を流す実験,そのニクロム線部分の前後に昇圧用・降圧用の変圧器を組み込んだ回路に交流と直流を流す実験,および電磁誘導の実験から構成される。変圧器によって高電圧・低電流で送電した場合には電圧降下が少なく,豆電球2個の明るさの違いが目立たない。変圧器の有無によって,明るさが違うことから変圧器の働きを理解する。変圧器に直流を流し豆電球が点灯しないことから変圧器の仕組みと交流の作用を学習する。本教材による実験授業の結果,送電における変圧器の働きと仕組みに関する認識の定着が向上することが明らかとなった。
- 著者
- 萩原 里紗
- 出版者
- 公益財団法人 三菱経済研究所
- 雑誌
- 三菱経済研究所 経済研究書 (ISSN:27587711)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.121, pp.1-83, 2018-03-27 (Released:2023-08-01)
1 0 0 0 OA オイルダンパーを付加した木質ラーメン構造の振動台実験
- 著者
- 篠原 昌寿 五十田 博 清水 秀丸
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会構造系論文集 (ISSN:13404202)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.729, pp.1859-1868, 2016 (Released:2016-11-30)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2 2
1. Introduction In Japan, high performance damping buildings and houses are required to improve seismic safety and to minimize damage, because of many occurrences of severe earthquakes. On the other hand, Japanese wooden houses do not have enough shear walls to keep large and many openings and semi-rigid timber portal frame has been developed and has increased. However, semi-rigid timber frame structure is relatively soft. This paper presents seismic performance of semi-rigid timber frame structure with damper through full-size shaking table tests. We compared response deformations during moderate and severe ground motions among only frame, frame with oil damper and frame with shear wall to verify damping effect of oil damper. 2. Overview of damping wall with oil damper Damping wall system consist of a oil damper set horizontally through a ∧ shape steel member installed between two columns and below a beam of wood (hereinafter, referred to as "∧-type damping wall"). ∧-type damping wall is a system where damper deformation becomes almost the same as the story deformation. ∧-type damping wall has a high damping force compared to other damping walls that exist in the field of wooden houses nowadays in Japan. Relief force of the oil damper is 12 kN and the relief velocity is 70 mm/sec. 3. Overview of shaking table tests Planar shape of box-shaped one-story specimen is 5460mm (direction of vibration) × 3640mm (Orthogonal direction of vibration), and its height is 2835mm. Ground motion is input in one direction. There are three types of structures set in series in the direction of vibration, the outer two structures are semi-rigid timber frames and the structure at the center is ∧-type damping wall or seismic wall of plywood. The detail for each structure is described as follows. (1)Semi-rigid timber frame with oil damper. (2)Semi-rigid timber frame with seismic wall of plywood. (3)Semi-rigid timber frame only. The total weight of specimen is 87.0kN. Moment resisting joint of semi-rigid timber frame is using lagscrewbolt, metal connector and nut. Procedure of construction is embedding the lagscrewbolt into the column and beam, and setting up a metal connector, and binds with nut. Size of column is 120mm × 300mm and wood specimen is engineering wood of European red pine (E105-F300). Size of beam is 120mm × 360mm and wood specimen is engineering wood of European red pine (E105-F300). For column base anchor bolt (M14, SNR490B) with growth capacity was used. Semi-rigid timber frame is considered to have a Co=0.51 seismic performance for elastic frame analysis. Seismic walls are placed in the center of structure row and are bonded both sides of plywood (t=12, N50 nail, @150). Seismic performance of this wall is almost equivalent to ∧-type damping wall. ∧-type damping wall and Seismic wall are considered to have a Co=0.11 seismic performance. Input seismic wave are three observation waves and one artificial wave. Observation waves are "ELCENTRO 1940 NS", "TAFT 1952 EW" "JMA Kobe 1995 NS". Artificial wave is "BSL wave" whose acceleration response spectrum is provided in the Building Standard Law. Seismic waves were scaled to two levels that represents medium and extreme earthquakes. 4. Results and Conclusions of shaking table tests Maximum response deformation of " Semi-rigid timber frame only " for Taft wave(25kine) is 1 / 106rad, for BSL wave(80%) is 1 / 45rad. This is large response deformation by specific seismic wave. "Semi-rigid timber frame with oil damper" reduces the response deformation for all evaluated seismic waves and can avoid damage to the structure.
1 0 0 0 OA 外傷性大動脈損傷診断と治療
- 著者
- 川田 忠典
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.105-116, 2007-04-28 (Released:2010-09-09)
1 0 0 0 OA パーソナリティ・認知・状況要因がリスクテイキング行動に及ぼす効果
- 著者
- 上市 秀雄 楠見 孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.81-88, 1998-06-25 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 13 3
This study examined the effects of individual difference and situation on risk taking behavior. In Experiment 1, 115 undergraduates completed a questionnaire of personality (sensation seeking, optimism, etc.) and their risk taking behavior, risk perception, and anxiety in eight situations: personal, social, gain-loss, and loss situations. Results indicated an effect of personality on risk taking behavior in personal gain-loss situations (sports and life event), which was mediated by perceived risk controllability. In Experiment 2, 137 undergraduates completed a questionnaire of personality, cognitive variables (risk perception, own competence, and perceived cost and benefit), and risk taking behavior in personal gain-loss situations (sports, life event, and gambling). Results of covariance structure analysis showed that perceived risk controllability affected the relationship between the variables. For instance, risk significance and perceived cost and benefit mediated the effect of ‘controllability with skills’ on risk taking behavior in the controllable situation (e.g., sports). Similarly, competence and risk perception mediated the effect of ‘uncontrollable luck factors’ in the chance situation (e.g., life event).
近年、グロ―バル・ガバナンス(GG)構造の複雑性が増している。国連気候変動枠組み条約の下で排出権取引に関わる様々な実施枠組みが普及し、企業のサステナビリティやESG投資に関わる取組が林立し、持続可能な開発目標(SDGs)の実施に関わる取組は全体像の把握が難しいほどである。この構造の複雑性は、①問題領域の複雑化、②ガバナンスの手段の多様化、③アクターの多様化(権威の多元化)という3次元での「密度」の増加によって特色づけられる。本研究はSDGsにかかわる主要な問題領域(気候変動、人道、難民、保健等)を事例として「GGの複雑化とアクターとの間にどのような相互作用が見られるか」という問いに取り組む。
1 0 0 0 OA 猫のウイルス研究の人医領域への貢献 ―猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症―
- 著者
- 石田 卓夫
- 出版者
- 日本歯内療法協会
- 雑誌
- 日本歯内療法協会雑誌 (ISSN:03895238)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.145-154, 1992 (Released:2020-02-22)
- 参考文献数
- 54
Feline immunodeficiency virus (FIV) was first isolated from a cluster of cats with suspected immunodeficiency syndrome. The genetic studies have confirmed that FIV is an innate virus with some homology to human and simian immunodeficiency viruses. Furthermore, FIV fails to grow in other mammalian cell cultures including human, but grows in feline peripheral blood mononuclear cells, kidney cells and interleukin 2 dependent T-cell lines. Infection of cats with FIV results in five distinctive clinical stages similar to those observed in human immunodeficiency virus (HIV) infection. Following acute phase and asymptomatic carrier phase, a number of chronic diseases occur in infected animals, and the clinical manifestations are closely associated with development of immunodeificiency as measured by lymphocyte subset studies or by blastogenesis assay. The advantage of this feline system as an animal model for human AIDS includes ease of experimental infection using specific pathogen free cats with a relatively smaller cost and space, safety to other species including human, and similar clinical manifestations as well as the virologic relations. The safety is a major consideration in carrying out large scaled screening studies. Thus, basic pathogenesis studies and drug therapy screening will be the major fields that this system potentially can contribute to the human medicine.