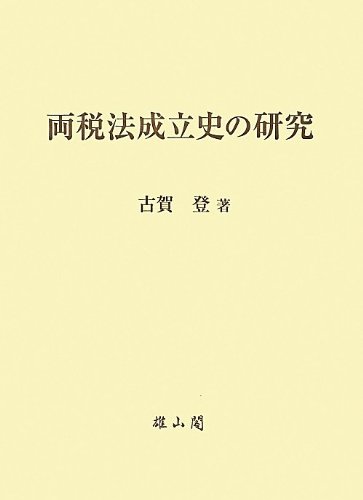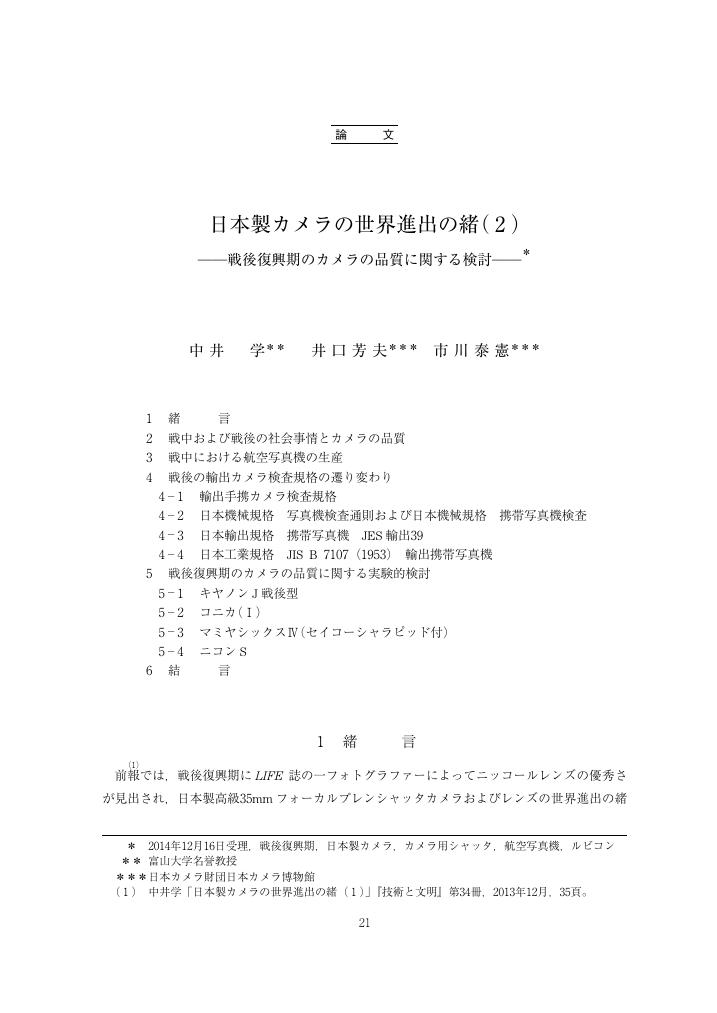- 著者
- Girma Gezimu Gebre
- 出版者
- 九州大学
- 巻号頁・発行日
- 2020
1 0 0 0 OA 豆類の調理について 吸水率、調理方法による大豆のビタミンB1量の変化
- 著者
- 吉田 恵子 伊部 さちえ 古庄 律 四十院 成子 岡本 洋子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成27年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.61, 2015 (Released:2015-08-24)
- 被引用文献数
- 1
【目的】現在の「調理学」の教科書に記載されている豆類の吸水率は、1983年に松元文子先生によって作成されたものがほとんどである。演者らは改めて各種豆類(大豆など7種類)について吸水率を測定し新データを作ることを目的とした。また大豆を調理するときに、0.3%重曹水中で調理するとアルカリにより大豆中のビタミンB1が減少するという記述も、多くの教科書に記述されている。ビタミンB1は水溶性であり、アルカリで分解されるというデータはあるが、大豆中のB1が重曹添加で減少するという報告はみあたらない。そこで大豆の調理方法とビタミンB1量の関連についても検討することを目的とした。【方法】吸水率の測定には、黒大豆、大豆、大福豆、金時豆、うずら豆、ささげ、小豆を用い、水に浸漬後2時間ごとに24時間吸水量を測定した。調理方法によるビタミンB1量については、丹波錦白大豆を用い、水中加熱、1%食塩水中加熱、0.3%重曹水中加熱を行った豆について、pHを測定後、ビタミンB1量を定量した。定量方法は前処理後、TSKgel Amide-80カラムを用いHPLC で定量した。【結果】吸水率:7種の豆類のうち吸水率の高かった豆は黒大豆で、他の豆類も以前のデータとは異なる挙動を示した。ささげは小豆と違い種瘤からのみではなく、表皮全体から吸水され吸水曲線のカーブも大豆に似ていた。3種の調理方法による大豆のビタミンB1量:水煮での煮豆、1%食塩水での煮豆、0.3%重曹水での煮豆ともに、生の時の約30%に減少した。この減少は添加物の影響はなく、調理することにより水溶性であるビタミンB1が煮汁などに溶出したためと熱で分解したものと推察される。
1 0 0 0 OA イチゴ果実におけるビタミン C 含量の品種間差異および収穫時期による変動特性
- 著者
- 曽根 一純 望月 龍也 野口 裕司
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE
- 雑誌
- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.5, pp.1007-1014, 1999-09-15 (Released:2008-01-31)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 7 7
国内外から導入した幅広い特性を有するイチゴ品種について, 促成および露地栽培におけるビタミンC含量を調査した.1995年には293品種を用いて5回の収穫時期で, また1996年には149品種を用いて7回の収穫時期で調査した.これをもとにビタミンC含量の品種・収穫時期間における変動を明らかにするとともに, ビタミンC含量と平均果重, 果皮色, 糖および有機酸の含量・組成等の果実品質関連形質との関係を検討した.1) 1995年作における収穫期間を通じた各品種のビタミンC含量の平均値は, 15.9mg/100g∿114.8mg/100gの範囲に分布し, 供試した293品種の総平均は59.1mg/100gであった.ビタミンC含量およびその時期的安定性には幅広い品種間差がみられた.Finlay・Wilkinson (1963)の方法による回帰係数を用いて環境変動に対する安定性を検討したところ, 高いビタミンC含量の品種ほど環境変動に敏感な傾向がみられた.しかし, '静紅', 'あかしゃのみつこ', 'さちのか'等は高いビタミンC含量を有し, かつ環境変動に対して比較的鈍感であり, 安定して高いビタミンC含量の品種を育成するための育種母本として有望と考えられた.2) ビタミンC含量の品種間差は収穫時期間の安定性が高く, 品種特性としてのビタミンC含量を評価するに当たっては, 大まかなスクリーニングのための調査を収穫期間中に数回行ない特性を把握し, より詳細な環境変動に対する調査が必要な場合には収穫期全体を通じた評価を行うことにより, 合理的な評価が可能と考えられた.3) ビタミンC含量と全糖含量および全糖含量に対するスクロースの割合(スクロース比率)との間には, 有意な正の相関がみられたが, 有機酸含量および有機酸含量に対するリンゴ酸の割合との間には有意な相関が認められなかった.また, ビタミンC含量の収穫期間を通じた変動係数は, スクロース比率およびグルコース/フルクトース比率の変動係数との間に正の相関を示した.従って, ビタミンC含量の安定して高い品種を育成するに当たっては, 糖含量が高く, かつ糖組成の安定性の高い素材の利用が可能であり, これらを用いることにより食味とのバランスが取れた安定して高いビタミンC含量を有する品種の育成が可能と考えられた.
1 0 0 0 OA 聾学校の数学指導改善のためのWeb教材の開発と実践
- 著者
- 中村 好則 黒木 伸明
- 出版者
- 一般社団法人 数学教育学会
- 雑誌
- 数学教育学会誌 (ISSN:13497332)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3-4, pp.91-98, 2004 (Released:2020-05-29)
- 著者
- 中村 好則 黒木 伸明
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会年会論文集 28 (ISSN:21863628)
- 巻号頁・発行日
- pp.281-284, 2004-07-30 (Released:2018-05-16)
- 参考文献数
- 3
本研究では,聾学校における数学的モデル化を取り入れた指導の可能性について,高等部生徒に対する「お湯の冷め方」の授業実践を通して考察した。その結果,現実の事象を日常的経験や既習の数学的事項と関連づけながら学習できること,数学の有用性や現実事象と数学との関わりを感得できることの効果が示唆され,聾学校生徒の数学学習を質的に改善する手だてとして有効であるという知見が得られた。今後は,さらに実践を重ねることと,数学的モデル化を取り入れた指導を行う時期や内容を検討することが課題である。
1 0 0 0 OA 高い雑音耐性と推定精度を両立する基本周波数推定法の提案と評価
- 著者
- 森勢 将雅
- 雑誌
- 研究報告音声言語情報処理(SLP) (ISSN:21888663)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016-SLP-114, no.23, pp.1-6, 2016-12-13
基本周波数 (F0,最近は FO と表記することもあるが本稿では F0 に統一する) は,周期的に生じる声帯振動間隔の最も短いものの逆数として定義され,知覚する音声の高さに概ね対応する音声の主要なパラメータである.F0 は様々な音声処理に利用されるパラメータであり,例えば Channel vocoder の考えに基づいた高品質音声合成では,音声から F0 を可能な限り高い精度で推定することが要求される.筆者らは,これまで高 SNR の音声を対象とした実時間処理が可能な推定法について検討し,SNR が 30 dB 以上であれば実時間処理が可能であり,かつ最新の方法と比較しても遜色ない性能が達成可能な方法を提案してきた.一方,例えば統計的音声合成では,学習に必要な音声パラメータは事前に分析しておけば良いため,実時間性よりも高い精度と雑音に対する頑健性を備えた方法が望ましいといえる.本稿では,計算速度ではなく,高い耐雑音性と推定精度にフォーカスを絞った F0 推定法 Harvest を提案する.Harvest は,音声スペクトルが調波構造を持つことに着目し,基本波に相当するピークを検出する方法を採用している. まず,高調波と低域雑音を除去するため,様々な中心周波数のバンドパスフィルタによるフィルタリングを実施し,得られた多チャネル信号から F0 の可能性がある候補を全て選定する.その後,選定された候補を瞬時周波数を用いて補正し,時系列の連続性を考えて接続することで最終的な F0 軌跡を生成する.本稿では,音声データベースを用いた評価,および筆者らが 2016 年に提案した耐雑音性評価法により提案法の有効性を示す.
1 0 0 0 OA 基本波検出に基づくF0推定法の耐雑音性向上
- 著者
- 森勢 将雅
- 雑誌
- 研究報告音声言語情報処理(SLP) (ISSN:21888663)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016-SLP-110, no.5, pp.1-6, 2016-01-29
本稿では,筆者らが 2010 年に提案した基本波検出に基づく基本周波数 (F0) 推定法の耐雑音性向上手法について述べる.2010 年に提案した F0 推定法は,周期信号の調波構造における基本波を低域通過フィルタにより抽出し,基本波の周波数を求める.F0 が未知であるため,カットオフ周波数の異なる複数の低域通過フィルタを用意し,各フィルタにより処理された信号から F0 候補と信頼度を求め,全ての候補中最も信頼できる候補を選択していた.基本波検出に基づく方法は,低域に雑音が混入する環境では充分な SNR の確保が困難であるため,高 SNR 環境で収録された音声を対象としていた.提案法では,滑らかな F0 軌跡を描くよう候補を再選択するアルゴリズム,および推定結果に対し瞬時周波数により結果を補正する処理を導入することで雑音に対する頑健性を向上させる.本稿では,耐雑音性向上手法について述べ,耐雑音性に限定した評価から提案法が期待通り動作することを示す.
1 0 0 0 OA 絶滅危惧種ナガボナツハゼ・菌根菌・マツにおける3者間共生メカニズムの解明
ナガボナツハゼはツツジ科スノキ属の絶滅危惧種であり、絶滅回避技術確立のためには絶滅危機に至った原因を究明することが必須である。この原因について、ツツジ科およびマツ科植物が代表的な菌根菌共生植物であることと、ナガボナツハゼがマツの樹周辺にのみ自生するという調査に基づき、「ナガボナツハゼは、地下部で菌根菌の菌糸を経由してマツと繋がっており、マツの養分に依存して生きているのではないか?」と考え、植物・菌・植物の3者間共生の仮説を立てた。本研究ではこれを検証し、我が国のマツ林の激減とナガボナツハゼの絶滅危機との因果関係を科学的に解明するとともに、絶滅危惧種の絶滅回避技術確立のための基盤を形成する。
1 0 0 0 OA 日本製カメラの世界進出の緒(2) 戦後復興期のカメラの品質に関する検討
1 0 0 0 OA ホーネットシルクの塩化カルシウム水溶液への溶解
- 著者
- 亀田 恒德 張 薔
- 出版者
- 日本シルク学会
- 雑誌
- 日本シルク学会誌 (ISSN:18808204)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.109-116, 2014 (Released:2015-04-02)
- 参考文献数
- 27
Aqueous solution of calcium chloride (CaCl2) is a promising solvent for biomaterial like silk fibroin, thereby offering potential application in industrial purposes. We observed that the silk, produced by larvae of hornets (Vespa), dissolved in an aqueous solution of CaCl2 in the concentration range of 3-6 M. The solubility of hornet silk was the maximum when CaCl2 concentration was 4.5 M. The rate of dissolution of the hornet silk in the aqueous solution of CaCl2 was sensitive to temperature. The hornet silk was found to dissolve in 4.5 M CaCl2 solution even at 20°C. Such high solubility of the hornet silk in the aqueous solution of CaCl2 could be attributed to the low content of β-sheet structure. The silk dissolved in the aqueous solution of CaCl2 within 1 h when the temperature was between 40 and 80°C, and less protein degradation occurred under the aforementioned condition.
1 0 0 0 OA 醸造食品と水分活性
- 著者
- 好井 久雄
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.4, pp.213-218, 1979-04-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 5
醸造食品についてのいろいろの現象を, 理論の面から長い間追求しておられる著者に, 水分活性についてお願いした。食品の保存, 低食塩化, 有用微生物の添加等に参考になると考える。
1 0 0 0 OA 死の場面における状況的人格の表出 ヴァヌアツ・アネイチュム島の事例から
- 著者
- 福井 栄二郎
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第55回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.G16, 2021 (Released:2021-10-01)
近年の人格論はストラザーンのdividual/individualという議論をいかに乗り越えるかという点に焦点が当てられており、そのなかでバード=デイヴィッドらは「状況的人格」という概念を提起している。本発表はこれを手がかりに、ヴァヌアツ・アネイチュム島における死の場面の事例を考察し、ストラザーンの議論の限界を指摘する。そして状況的人格の特徴を「二人称的」であることとし、その学術的意義を再考する。
1 0 0 0 OA 我國に於ける石鹸の歴史(其の一)石鹸の渡來期
- 著者
- 中江 大部
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.8, pp.580-588, 1927-08-05 (Released:2011-09-02)
1 0 0 0 OA 多発性骨髄腫患者の脊椎MRI所見
- 著者
- 渡辺 剛史 権藤 学司 田中 雅彦 山本 一徹 堀田 和子 玉井 洋太郎 田中 聡
- 出版者
- 日本脊髄外科学会
- 雑誌
- 脊髄外科 (ISSN:09146024)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.170-174, 2019 (Released:2019-09-10)
- 参考文献数
- 12
The purpose of this article is to analyze the characteristics of spinal magnetic resonance images (MRI) in multiple myeloma patients. Two hundred and eighteen patients were diagnosed with multiple myelomas at the Shonan Kamakura General Hospital from January 2009 to April 2018. Spinal MRIs were evaluated in 66 cases. Initial symptoms, spinal MRI findings, and blood sample test findings at the time of diagnosis were investigated. There were 37 males and 29 females analyzed. Mean age at the time of diagnosis was 70.1 years (42 to 87 years). Main initial symptoms were low back pain (n=23), back pain (n=15), neck pain (n=1), lower limb weakness (n=6), lower limb pain/paresthesia (n=4), cranial nerve palsy (n=2), respiratory symptoms (n=6), renal failure (n=4), anemia (n=3) and asymptomatic (n=6). Spinal MRI revealed vertebral fracture (n=42), intravertebral tumor (n=35), epidural tumor (n=9), diffuse spotty signal (n=13), and diffuse low signal (n=4). There were only five cases where no abnormality was observed beyond the vertebral body fracture. Dural sac compression was observed in 16 cases, of which 12 cases were co-localized with the tumor and 4 cases were by a fractured bony fragment. The results of the blood sampling were confirmed in 65 patients. Anemia, decreased albumin/globulin ratio, hyperproteinemia, hypercalcemia, and increased alkaline phosphatase were observed in 57, 44, 29, 13, and 12 patients, respectively. Only 9 cases showed normal blood test results. The most common symptom of multiple myeloma was lower back pain. As such, half of the patients had visited an orthopedic or spinal surgery clinic. Spinal MRI findings were classified as intervertebral focal lesion, epidural mass, diffuse spotty signal, or diffuse low signal. The presence of an abnormal finding was observed in 92% of patients by spinal MRI and in 86% by blood sampling. Spinal MRI and blood sampling examination should be considered in cases of vertebral fracture in order to prevent the misdiagnosis of multiple myeloma as an osteoporotic vertebral fracture.
1 0 0 0 OA 1920年代の企業内養成工制度 : 日立製作所の事例分析
- 著者
- 菅山 真次
- 出版者
- 土地制度史学会(現 政治経済学・経済史学会)
- 雑誌
- 土地制度史学 (ISSN:04933567)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.34-50, 1985-07-20 (Released:2017-11-30)
With regard to the corporation apprenticeship in the 1920's, there exist two opposing views at present: According to one view its role is highly estimated in relation to the formation of "the prototype" of "the Japanese Employment System"; in the other, on the contrary, its retrocession at this period is stressed. The purpose of this paper is to give meaningful material to solve this problem by making clear the change from the period of WWI to the 1920's in Totei-Yoseijo, the corporation apprenticeship school, of the Hitachi Company. In the period of WWI, Yoseijo was faced by a critical situation, which was expressed in outstandingly high rates of turnover and of absence under tightening of the labor market and development of the labor movement. Removal of the influence of the labor unions in 1919-20 and the following panic of 1920, however, changed the situation drastically: the both rates sharply declined. Since these occasions, about 40% of Yoseijo graduates, presumably much more after the late 1920's, have been involved in "the Life Long Employment System". The change didn't stop here. Around the year of 1920, the workers of the Hitachi Co. were thought to be a kind of "stragglers" or "bankrupts." But such a low social status of the workers did change dramatically in the late 1920's, when Hitachi district developed as a company town through the growth of the Hitachi Co. in spite of the depression at that time. This brought a remarkable increase in the number of applicants for Yoseijo, and the competitive rate increassed nearly 10 times as much in 1930. Thus, Yoseijo could employ as apprentices those who had earned good grades at school. This, on the one hand, contributed to further decline of the rates of turnover and absence, and, on the other, made it possible to meet the need of skill based on scientific knowledge at this period.
- 著者
- 笠井 勝也 西前 出 小林 愼太郎
- 出版者
- 一般社団法人 環境情報科学センター
- 雑誌
- 環境情報科学論文集 Vol.23(第23回環境情報科学学術研究論文発表会)
- 巻号頁・発行日
- pp.285-290, 2009 (Released:2011-02-15)
- 被引用文献数
- 1
富士山の山小屋が補助金を受けて設置した自己処理型トイレの維持管理コスト確保が困難な状況に陥っている。本研究では,総合パフォーマンス評価による自己処理型トイレの評価,PSM 分析を用いた適正トイレ使用料金の推定,CVM による入山料に対するWTP の推定を通じ,設置場所の環境に適した屎尿処理装置が導入されているか,協力金の設定金額は妥当であるか,入山料徴収制度の実現可能性について検討した。その結果,総合パフォーマンス評価を用いた屎尿処理装置の選定および入山料徴収制度の導入が,富士山における山小屋トイレ維持管理費確保問題の解決に寄与しうることが確認された。
- 著者
- Rie Kishida Kazumasa Yamagishi Isao Muraki Mizuki Sata Akiko Tamakoshi Hiroyasu Iso for the JACC Study Group
- 出版者
- Japan Atherosclerosis Society
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.12, pp.1340-1347, 2020-12-01 (Released:2020-12-01)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 16 25
Aim: Seaweed is a popular traditional foodstuff in Asian countries. To our knowledge, few studies have examined the association of seaweed intake with mortality from cardiovascular disease. We examined the association of frequency of seaweed intake with total and specific cardiovascular disease mortality. Methods: We examined the association of seaweed intake with mortality from cardiovascular disease among 40,234 men and 55,981 women who participated in the Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk. Sex-specific hazard ratios for mortality from cardiovascular disease (stroke, stroke subtypes, and coronary heart disease) according to the frequency of seaweed intake were calculated stratified by study area and adjusted for potential cardiovascular risk factors and dietary factors. Results: During the 1,580,996 person-year follow-up, 6,525 cardiovascular deaths occurred, of which 2,820 were due to stroke, and 1,378, to coronary heart disease. Among men, the multivariable analysis showed that participants who ate seaweed almost every day compared with those who never ate seaweed had hazard ratios (95% confidence interval; P for trend) of 0.79 (0.62–1.01; 0.72) for total cardiovascular disease, 0.70 (0.49–0.99; 0.47) for total stroke, 0.69 (0.41–1.16; 0.11) for cerebral infarction. Among women, the multivariable-adjusted hazard ratios were 0.72 (0.55–0.95; 0.001) for total cardiovascular disease, 0.70 (0.46–1.06; 0.01) for total stroke, and 0.49 (0.27–0.90; 0.22) for cerebral infarction. No associations were observed between seaweed intake and risk of intraparenchymal hemorrhage and coronary heart disease among either men or women. Conclusions: We found an inverse association between seaweed intake and cardiovascular mortality among Japanese men and women, especially that from cerebral infarction.