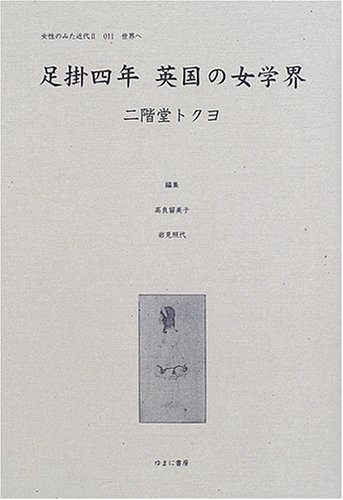1 0 0 0 OA 原著3『食品におけるプリン体含有量の測定-和食の食材および健康食品について』
- 著者
- 金子 希代子 工藤 優子 西澤 裕美子 堀場 沙世 茂木 淳一 馬渡 健一 中込 和哉 山辺 智代 藤森 新
- 出版者
- 一般社団法人 日本痛風・核酸代謝学会
- 雑誌
- 痛風と核酸代謝 (ISSN:13449796)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.23-29, 2007 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 2
食品中のプリン体含量を測定した.今回対象とした食品は,和食で使用される野菜を中心とした食材で今までに測定されていない食品とおつまみ類,および健康食品である.プリン体含量は,四塩基合計値として,空豆,おくら,もやしは40mg/100g以下であった. 豆もやし, 貝割れ大根,おから,ブロッコリースプラウト,舞茸は50~130mg/100gとpurine-rich vegetablesに分類された.おつまみ類(生ハム,さきいか,アーモンド),調味料(唐揚げ粉),粉末スープ類(ポタージュ, コンソメ) には3 0~180mg/100gのプリン体が含有されていた.一方,健康食品(ケール,ローヤルゼリー, ビール酵母, クロレラ,DNA/RNA)は40~21500mg/100gと大量のプリン体を含有するものがあった.今回測定した食品では,健康食品に,非常に多くのプリン体を含むものがあり,推奨される1日のプリ体摂取量400mgの半量を占めることから,これらの健康食品の日常的な服用には注意が必要であると考えられた
1 0 0 0 OA 2-2 聴覚におけるメカニズム
- 著者
- 黒住 幸一
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会誌 (ISSN:03866831)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.438-445, 1991-04-20 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 18
1 0 0 0 OA 標本合計が負の場合へ拡張されたジニ係数の評価
- 著者
- 伊藤 尚 前田 義信 谷 賢太朗 林 豊彦 宮川 道夫
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.117-130, 2012 (Released:2013-03-18)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
ジニ係数は標本間格差を評価する代表的な指標のひとつである.しかし,ジニ係数は全標本が非負であることを前提としているため,負の標本を含む標本間格差を評価することは出来ない.Chenらはこの場合でも標本間格差を評価できるようにするためジニ係数の拡張を試みた.しかし彼らの提案した拡張ジニ係数は全標本の合計が0以下である場合において標本間格差を評価することが不可能であった.そこで本論文では,負の標本を含む場合および全標本の合計が0以下の場合においても標本間格差を評価するために,ジニ係数の幾何的表現の拡張を提案する.提案された拡張ジニ係数では負の標本を含む場合および全標本の合計が0以下の場合においても標本間格差を評価することが可能であり,全標本が非負である場合において拡張ジニ係数は従来のジニ係数と一致する.さらに,拡張ジニ係数の代数的表現を検討し,得られた代数的表現から本論文で提案する拡張ジニ係数が母集団原理と拡張移転原理を満たすことを示す.
1 0 0 0 OA カイコガチアミナーゼの酵素学的検討
- 著者
- 渡辺 喜弘 岡崎 英規 西宗 高弘
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.155-160, 2001-02-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 12
カイコガを食材として利用する際, その安全性を検討する必要がある.本報では, カイコガ体内に存在するチアミナーゼに着目し, 以下の結果を得た.(1) カイコガの幼虫及び蛹にビタミンB1分解酵素チアミナーゼを見出した.(2) 酵素反応温度がチアミナーゼ活性におよぼす影響を検討したところ, 60℃から70℃で活性が最も強かった.(3) 本酵素のpH依存性を検討した結果, pH9.0において最大の分解活性が認められた.(4) 本酵素はビタミンB1を分解するときに第2基質としてシステイン, タウリン, リジン, プロリン, グルタチオン, ピリドキシン等を要求することがわかった.(5) 本酵素をプロテアーゼ処理すると失活し, 蛋白質性である事が確認された.また, 透析後の酵素液中にも第2基質依存性の酵素活性は残り, 本酵素は非透析性の高分子量物質であることが確認された.(6) ビタミンB1のモノリン酸エステル, ジリン酸エステル, トリリン酸エステルには本酵素は反応せず, 遊離のビタミンB1のみを分解することがわかった.
1 0 0 0 OA 東京低地と中川低地における沖積層の形成機構
- 著者
- 田辺 晋
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.1, pp.55-72, 2019-01-15 (Released:2019-04-15)
- 参考文献数
- 79
- 被引用文献数
- 5 4
東京低地と中川低地における沖積層のシーケンス層序と古地理を詳細に解明した結果,沖積層の形成機構に関する次の3つの知見を得ることができた.(1)蛇行河川堆積物を構成するチャネル砂層は,海水準上昇速度が大きい時期にはアナストモーズ状の形態を有し垂直方向に累重するのに対して,海水準上昇速度が小さい時期にはシート状の形態を有し水平付加する.(2)一部の海進期のエスチュアリーシステムは,河川卓越型エスチュアリーとして分類されるべきであり,その湾頭部の潮下帯にはローブ状で上方細粒化する砂体が存在する.(3)潮汐の卓越した溺れ谷などの内湾では,湾内に流入する河川が存在しなくても,湾外から運搬された泥質砕屑物が側方付加することによって埋積され,上方細粒化相が形成される.特に(1)は海水準の変動率が浅海成層と同様に沖積平野の河成層の地層形成に重要な支配要因であることを示す.
- 著者
- Yoshinobu NAYATANI Hiroaki SOBAGAKI Kenjiro HASHIMOTO
- 出版者
- The Illuminating Engineering Institute of Japan
- 雑誌
- Journal of Light & Visual Environment (ISSN:03878805)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.2_16-2_24, 1993 (Released:2011-02-25)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 6 7
Using the nonlinear color-appearance model, predicted are the four kinds of color-perception phenomena, which are the Go function studied by Evans, Munsell Values for different hues, purity discrimination, and the Helmholtz-Kohlrausch effect. The analysis confirmed that all the four phenomena are caused by the same common factor, the chromatic strength of spectral color stimulus reported by Evans in 1967.
1 0 0 0 足掛四年 : 英国の女学界
1 0 0 0 OA 造影CT検査で確定診断に至った外傷性持続勃起症の一症例
- 著者
- 伊藤 弘 村尾 修平 中村 洋平 小倉 裕司
- 出版者
- 一般社団法人 日本外傷学会
- 雑誌
- 日本外傷学会雑誌 (ISSN:13406264)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.299-302, 2021 (Released:2021-10-20)
- 参考文献数
- 7
症例は21歳, 男性. バイク走行中に乗用車と接触事故を起こし, 当院高度救命救急センターに搬送された. 搬入時, 身体所見では陰茎に打撲痕と持続する勃起症状がみられた. 造影CT検査では内陰部動脈からの造影剤漏出と海綿体洞瘻が確認され, 動脈流入過剰型持続勃起症と診断した. 緊急で血管造影検査を行い, 選択的に内陰部動脈塞栓術を施行した. 造影剤漏出と海綿体洞瘻は消失し, 術直後から勃起症状も消失した. また受傷2ヵ月後には勃起可能となり, 機能障害を伴うことなく経過した. 今回, 比較的稀とされる外傷に伴う動脈流入過剰型持続勃起症に対して受傷当日に造影CT検査で診断し, 血管内治療により治癒した症例を経験したので報告する.
1 0 0 0 OA 天然染料による皮革染色の試み ―豚革のコチニール浸染の可能性―
- 著者
- 佐々木 麻紀子 中林 あずみ 川村 あゆみ
- 出版者
- 東京家政学院大学
- 雑誌
- 東京家政学院大学紀要 (ISSN:21861951)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.85-90, 2019 (Released:2022-02-25)
- 参考文献数
- 18
コチニールはカイガラムシとも呼ばれ古くから染料として用いられ、天然染料の中でも比較的安定した堅ろう性を持った染色布を得られることがわかっている。本研究では、試料を豚革としてコチニールを用いて浸染を試み、手工芸染色として簡便に利用できるような染色・媒染条件を探り、豚革を用いた手工芸染色の可能性を広げることを目的とした。豚革を 60℃で浸漬をすると3.0~4.3%程度の収縮が生じ、部位によっては変形、黄変、硬化などを伴ったため、染色実験では、染色温度40~50℃と設定した。低温染色であるため、アルミ媒染、スズ媒染ともに1回の染色で濃色に染色することは難しく、5回の繰り返し染色を行った。豚革の銀面及び床面において、繰り返し染色による濃色効果が認められた。豚革は、コチニールを用いた低温浸漬によるろうけつ染めが可能であり、繰り返し染色や媒染剤を変えることで色のバリエーションを増やすことが可能であった。
1 0 0 0 OA LITHOSPHERE CREEP
- 著者
- Robert C. BOSTROM
- 出版者
- The Seismological Society of Japan, The Volcanological Society of Japan, The Geodetic Society of Japan
- 雑誌
- Journal of Physics of the Earth (ISSN:00223743)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.145-161, 1981 (Released:2009-04-30)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1 2
Flexure of the mantle by the east-west M2 wave imposes non-reversing small body torques. The stress and displacement have been evaluated for the plausible range of the elastic quality factor Q. The non-cancelling stresses are of the order 5×10-7dyn/cm2, varying as the magnitude of Q-1. The displacement varies as Q-2 and is correspondingly minute, but is cumulative through geologic time. The role of the lithosphere becomes dominant, because stress diffusion causes it to act as a transmission channel. Stress acting on isostatic lithosphere is additive horizontally, as wind stress is additive across a floating ice sheet. In respect to oceanic lithosphere, within a period of about 106 years the stress reaches a value of tens of bars and its displacement rate several cm/yr. It is surmised that the values reached are limited by imperfect elasticity of the lithosphere. The energy consumption based upon gravimetric values of the phase lag, between 1.3 and 2.3×1026erg/yr, is a fraction of the dissipation astronomically observed but not found in the seas. The effect of lithosphere creep is compared with Pacific and Atlantic tectonic features.
1 0 0 0 OA ヘーゲル論理学「本質論」における世界了解
- 著者
- 竹村 喜一郎
- 出版者
- つくば国際大学
- 雑誌
- 研究紀要 = Bulletin of Tsukuba International University (ISSN:13412078)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.13-36, 2018-03-25
1 0 0 0 OA 韓国伝統的麹「ヌルク」を用いた焼酎製造の可能性
- 著者
- 吉﨑 由美子 金 顯民 奥津 果優 池永 誠 玉置 尚徳 髙峯 和則
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.3, pp.170-178, 2015 (Released:2018-04-16)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3 3
本研究では韓国麹「ヌルク」を用いた焼酎商品化の可能性について検討した。10種類のヌルクの発酵能力を確認したところ,米麹と比べ全てのヌルクで発酵能が弱かった。しかし,その中でも2種のヌルクは比較的高い発酵能力を示した。ヌルクに含まれるα-アミラーゼとグルコアミラーゼは米麹とほぼ同等であり,生デンプン分解活性に関してはヌルクの方が高かった。ヌルクに含まれるデンプン質の糊化度は米麹と比較して低く,糊化度の低さがヌルクの緩やかな発酵に影響していることが強く示唆され,糊化度をもとに発酵能力の高いヌルクを選抜できる可能性が示された。ヌルクを用いて製造した米焼酎の官能評価は,米麹を利用した焼酎より酸臭と酸味がある一方で,華やかであった。さらに,一次仕込み時に焼酎酵母を添加することでヌルクを使用した米焼酎の酸臭および酸味を抑制できる可能性が示唆された。また,ヌルクに含まれる酵母の1つとしてSaccharomyces cerevisiaeを同定し焼酎製造に適した微生物をもつことが確認された。 本研究は韓国RDAとの共同研究(Project No. PJ008600)で実施された。
1 0 0 0 OA ある方言地図の解釈
- 著者
- 加藤 正信
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1962, no.42, pp.31-46, 1962-10-31 (Released:2010-11-26)
As an experiment in linguistc geography, the writer takes up in the present paper the distribution of a variety of forms denoting salix caprea in the Island of Sado. This word may not belong to the basic Japanes vocabulary, nor can its variation constitute such an important dialectological feature as the word for “bought”, which divides Japan into two areas, one (east) with the form katta and the other (west) with the form kota. Even the conclusion about the changes the word has undergone in that island may have little significance in itself. The writer's aim here is to present the procedures that have led him to his conclusion and invite critical comments from his colleagues.In actual field work, the writer was assisted by Mrs. Sadako Kato. They visited almost all the communities (160 communities in all) in the island except the northern region, from 1959 to 1962. In each community, they examined one informent, who was native to the community and born in the Meiji Era i. e. before 1912. As a result of the survey, 34 different forms have been recorded. If we represent these forms on the maps as they are, their distribution would look so complicated that it would be impossible to know where to draw a dividing line. Matters can be made much simpler, however, by classifying our forms into two groups, one containing the element inu ‘dog’ and one containing the element neko ‘cat’. Thus we find the ‘dog’ group distributed in the central part, and the ‘cat’ group along the seacoast.With respect to the history of the island, we know that it was the central part that was prosperous untill the sixteenth century, and, only later, important lines of communications developed along the coast. On the other hand, the ‘dog’ group contains certain forms affected by a law of vocalic change that must have been completed in the seventeenth or eighteenth century. These two considerations have led the writer to the conclusion that the ‘dog’ group belong to an older layer than the ‘cat’ group. If so, how did some forms of the ‘dog’ group come to be replaced by those of the ‘cat’ group? In order to answer this question, the writer reconstructs an approximate process of innovation on the basis of further material provided by his map, and considers factors involved in each case.
- 著者
- 杉田 智美
- 出版者
- 至文堂
- 雑誌
- 国文学解釈と鑑賞 (ISSN:03869911)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.79-86, 2001-03
1 0 0 0 OA 施肥時期改善による露地栽培ニホンナシの発芽不良発生軽減技術の検証
- 著者
- 腰替 大地 坂上 陽美 阪本 大輔 杉浦 裕義 木﨑 賢哉 内野 浩二 杉浦 俊彦
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.433-440, 2022 (Released:2022-12-31)
- 参考文献数
- 16
近年の温暖化に伴い,九州などの暖地で,ニホンナシ露地栽培における発芽不良の発生が顕在化してきている.そこで本研究では,発芽不良の発生軽減が期待される春施肥の有効性を,‘豊水’ および ‘幸水’ において,5年間継続して検証した.両品種において,施肥時期を慣行の秋施肥から春施肥に変更することで,耐凍性が向上し,5年間安定して発芽不良の発生が軽減された.一方,9月と3月に分施する秋春施肥では,耐凍性の向上効果および発芽不良の軽減効果は見られなかった.なお,春施肥に変更したことによる果実品質への悪影響は認められなかった.以上のことから,凍害によるニホンナシの発芽不良発生の軽減策として,全量を春に施用する施肥法は,有効的かつ実用的なニホンナシ露地栽培技術であることが明らかになった.
1 0 0 0 OA 日本語受動の類型論
- 著者
- 宮腰 幸一
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.157, pp.113-147, 2020 (Released:2020-12-10)
- 参考文献数
- 34
本稿は日本語受動の新たな類型論を提案・実証する。主な提案は次の7つである。[I]日本語受動は[1]受影主受動と[2]経験主受動に大別され,それぞれさらに下位分類される。[II]ラレルは2(+1)項助動詞であり,意味と統語の両レベルで[1]よりも[2]の方が階層的に上位の構造を持ち,[2]の中でもあるタイプ([A]直接・[B]所有1)よりも別のタイプ([C]所有2・[D]間接)の方がより複雑な構造を持っている。[III]すべてのタイプにおいて意味レベルの束縛が重要な役割を果たす。[IV]受動の本質的特性である〈受影性〉は6つの認可条件と3つの階層で複合的に規定される。[V]日本語受動の典型は[2A]タイプであり,それは主体的把握・内界表出文である。[VI]それがプロトタイプであることは三重受影性階層から定理として導き出される。[VII]非典型的なタイプも,受影主や複合事象/複雑述語文の一般的な派生度測定基準/方法の導入により,原理的に説明される。
- 著者
- 石松 菜摘 鮎澤 聡 櫻庭 陽 成島 朋美
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.1, pp.45-52, 2021 (Released:2021-10-28)
- 参考文献数
- 16
【はじめに】骨盤骨折後に便漏れ(切迫性便失禁)と仙骨部から肛門周囲の感覚障害が残存した患者に対し、仙骨部に低周波鍼通電を行い症状の改善が得られた一症例を経験したので報告する。 【症例】60歳代、男性。主訴は便漏れと左側仙骨部から左側肛門周囲の痺れおよび感覚鈍麻。X-1年5月、交通事故により骨盤骨折を受傷し外科治療を受けるも上記症状が残存し、その後も改善を認めず。X年4月当センターに来所し、鍼治療が開始された。 【治療及び評価】左右の第2~4後仙骨孔部(次・中・下穴)および会陽穴に斜刺にて40mm程度刺入し会陰部に得気を得た後、1~3診は1Hz15分、4~7診は20分、8診以降は50Hz 間欠波で20分施行した。評価には、便失禁の程度にNumerical Rating Scale(NRS)を、便失禁に関連したQOLに日本語翻訳版Fecal Incontinence Quality of Life Scale(FIQL)を用いた。また痺れについてVisual Analogue Scale(VAS)で評価を行った。 【経過】便失禁の程度は初診時NRS8が7診時に2まで減少し、FIQLでも改善がみられた。肛門周囲の痺れは初診時VAS69mmであったが9診目で消失した。感覚鈍麻は残存した。 【考察・結語】切迫性便失禁は陰部神経障害による外肛門括約筋の障害で生じる。今回の治療では後仙骨孔部で鍼通電を行うことで仙骨神経叢後枝を刺激し、陰部神経の活動に影響を与えた可能性がある。近年便失禁に対しては外科手術によるSacral Neuromodulation Therapy(SNM療法)が行われるが、侵襲度が小さい仙骨部の低周波鍼通電療法は、便失禁に対する安全で簡便な治療法の1つとなりうる可能性が示唆された。
1 0 0 0 中近世の神社にみる移動と再生に関する建築史学的研究
本研究は、神社本殿の細部装飾が発展してゆく時期にあたる中世後期から近世に焦点をあてて、これまでに刊行された文化財修理工事報告書や修理現場で公開された情報から新たに得られた建築の変遷の情報を包括的に分析し、(1)造営に関与した各地の工匠別にみる神社本殿の特性と本殿背後の境内整備および敷地内移築との関係、(2)春日大社旧社殿にみる神社本殿の特性と河川等に基づく立地および境内環境との関係、を考察することで、工匠の移動と神社本殿の移動(移築)の実態を捉え、その流通に支えられた神社の再生の手法を明らかにするものである。