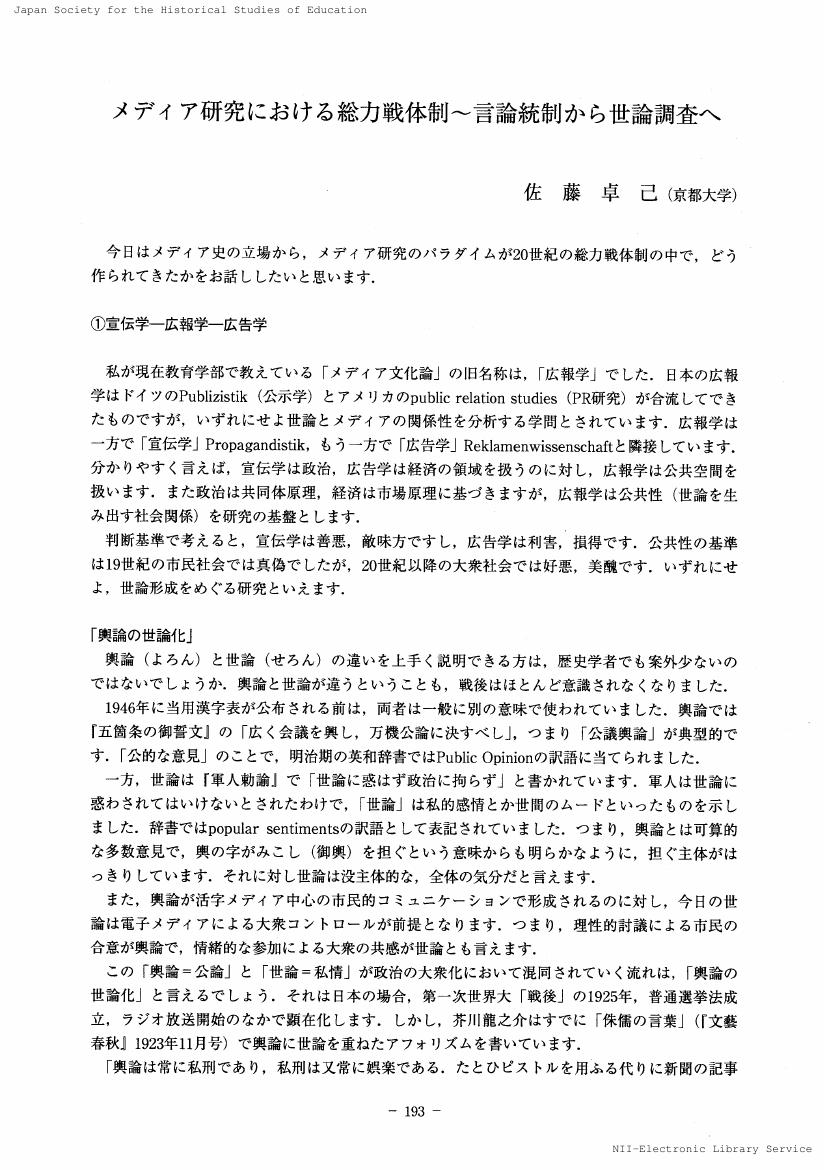1 0 0 0 将棋上達構座
- 出版者
- 近代将棋社近代将棋編集局
- 巻号頁・発行日
- 1956
1 0 0 0 OA 軽量混合処理土工法の港湾施設への適用
- 著者
- 輪湖 建雄 土田 孝 松永 康男 濱本 晃一 岸田 隆夫 深沢 健
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.602, pp.35-52, 1998-09-20 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 9 6
阪神・淡路大震災で被災した神戸港のケーソン式岸壁の復旧方法として背面固化による方法が考えられた. 特に嵩上げと耐震性向上を必要とする場合, 従来, 港湾・海洋環境での施工実績が乏しかった軽量混合処理土工法を, 港湾施設へ増粘剤等を用いないで水中施工で適用することが要求された. このため, 筆者らは室内試験・現場打設試験を行って課題を抽出し, それらを満たす施工システムを構築して本施工を実施した. その後, 追跡試験によりその妥当性を検証できた. こうした一連の課題解決方策は, 軽量混合処理土工法ばかりでなく, 他の固化処理工法を適用する上で役立つものと期待される.
1 0 0 0 OA 港湾施設の空洞化調査に関する報告
- 著者
- 佐藤 徹 加藤 絵万 川端 雄一郎 岡﨑 慎一郎
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.I_552-I_557, 2014 (Released:2014-10-01)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2 9
港湾施設の点検診断については,施設の設置環境等から目視に頼らざるを得ない部分が多く,港湾利用の制約を伴う機器を使用した点検調査については,あまり実施されてこなかった.しかしながら,高齢化した社会資本の安全性確保や,的確な点検実施など維持管理の重要性の高まりなどを背景として,昨年,老朽化した港湾施設を主対象に,全国的な点検調査が実施された.この調査においては,はじめて全国規模で地中レーダを用いた係留施設の空洞化調査が実施された.本報告では,係留施設を対象に実施された空洞化調査の結果について整理し,空洞化と目視により判定されたエプロン舗装等の劣化度の関係等についてとりまとめた.また,これらの分析を踏まえて,係留施設に発生する空洞化に対して今後対応すべき事項等について考察した.
- 著者
- 西澤 泰彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文報告集 (ISSN:09108017)
- 巻号頁・発行日
- vol.452, pp.187-196, 1993-10-30 (Released:2017-12-25)
Okada Tokitaro (1859〜1926) was one of Japanese colonial architects, in 1886 with whom famous architect Tatsuno Kingo established the first one of architectural offices in Japan. In the Russo-Japanese war Okada moved into Dalny, and in 1906 extending his building activities, opened Okada-komusho (architect and contractor) in Dalny. This paper introduces his building activities and shows them linked up with Japanese ruling over the Northeastern Province of China "Manchuria".
1 0 0 0 OA 外来血液透析患者におけるカルニチン代謝障害の現状についての検討
- 著者
- 松坂 貫太郎 緒方 浩顕 山本 真寛 伊藤 英利 竹島 亜希子 加藤 雅典 坂下 暁子
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.389-396, 2019 (Released:2019-11-08)
- 参考文献数
- 16
血液透析患者では,摂取不足,腎での生合成の減少や透析療法による除去などのためにカルニチンが極めて高頻度で欠乏すると報告されており,カルニチン欠乏がさまざまな腎不全合併症(エリスロポエチン抵抗性貧血,低左心機能や筋痙攣等)に関与することが想定されている.本研究ではカルニチン代謝障害の実態を検討するため,カルニチン静脈投与の有効性を検証する前向き観察研究(「透析患者の合併症に対するL-カルニチン静注製剤の有効性の検討」)に登録された昭和大学横浜市北部病院およびその関連施設の外来血液透析患者501名に対して,血中カルニチン分画を測定し,その関連因子を横断的に検討した.主要評価項目として遊離カルニチン(Free)濃度とアシルカルニチン濃度/Free濃度(A/F比)を解析した.Free濃度を3群間(充足群(36≦Free≦74µmol/l),不足群(20≦Free<36µmol/l),欠乏群(Free<20µmol/l))に分類したところ,充足群は全体のわずか8.4%であり,A/F比も>0.4が98.8%と,ほとんどの患者がカルニチン代謝障害を合併していた.Free濃度とA/F比それぞれに関連する因子を多変量解析で検討したところ,カルニチン代謝障害と血清尿素窒素濃度(SUN),透析歴,性別,アルブミン,リンや標準化タンパク異化率(nPCR)との間に有意な関連がみられた.一方,血液透析療法の差異(血液透析と血液ろ過透析)は,カルニチン代謝障害に関連していなかった.興味深いことに,ともに栄養状態,タンパク摂取状況の指標とされるSUNとnPCRがFree濃度との関連では全く反対の関連性を示したことである.透析患者におけるカルニチン代謝障害の病態生理について更なる検討が望まれる.
1 0 0 0 OA 疑似科学信奉と向社会的行動の関連性―素朴で善意の人が,疑似科学を信じるのだろうか―
- 著者
- 菊池 聡
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第84回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.PC-119, 2020-09-08 (Released:2021-12-08)
科学的な主張のように見えながら正当な科学としての要件を欠く疑似科学的は,医療・健康・教育・環境など幅広い領域でしばしば社会的な問題を引き起こしている。こうした中には,疑似科学ユーザーが,さまざまな「善意から」,よかれと思って使用や推奨を行い,批判を受け入れない態度が多く見られる(菊池,2012)。こうした無自覚の善意が,正当な科学知識の欠如と結びついて疑似科学を促進するという一般的な言説を検証するため,疑似科学信奉と,愛他的向社会的行動や科学リテラシーの関連について検討した。大学生325人(男171,女154)人に対して,疑似科学信奉尺度(超常・日常),超常信奉尺度,向社会的行動尺度,科学技術基礎リテラシー知識テストなどを実施した。その結果,性別や専攻を統制しても,疑似科学(超常)信奉は向社会的行動と正の関係が認められた。ただし,科学知識レベルと交互作用は見られなかった。また,一般的な超常信奉と向社会的行動の関連が見られ,疑似科学信奉においても超常的なスピリチュアルな要素が向社会行動に影響する可能性が推測された。
- 著者
- 堀口 嵩浩 橘川 雄亮 古谷 航一 福井 範行
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J105-B, no.8, pp.637-639, 2022-08-01
高速FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)レーダにレーダ信号帯域外の連続波(CW: Continuous wave)電磁ノイズを印加した場合,ノイズ周波数に対応した距離値と相対速度値に誤検出が生じる.本論文では,高速FMCWレーダのCW電磁ノイズによる誤検出の相対速度値の定式化を行い,実測値との比較によりその妥当性を示す.
1 0 0 0 OA 日本語版幸せへの恐れ尺度と日本語版幸せの壊れやすさ尺度の信頼性・妥当性の検討
- 著者
- 生田目 光 猪原 あゆみ 浅野 良輔 五十嵐 祐 塚本 早織 沢宮 容子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.92.20206, (Released:2021-01-31)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 1
This study investigated the reliability and validity of the Japanese versions of the Fear of Happiness Scale and the Fragility of Happiness Scale. The scales were administered to 341 Japanese undergraduates. Confirmatory factor analysis showed that, like the original versions, the Japanese Fear of Happiness Scale and the Fragility of Happiness Scale each had a one-factor structure. The two scales also each had good internal consistency, test-retest reliability, and construct validity. Furthermore, the scales showed incremental validity by predicting psychological elements (life satisfaction, depression, anxiety, stress) better than the behavioral inhibition system (BIS) and the behavioral activation system (BAS). The results of the present study revealed that the Fear of Happiness Scale and the Fragility of Happiness Scale had an adequate reliability and validity in this Japanese group.
1 0 0 0 OA 政治的悪の規範理論的分析 -政治的リアリズムを中心に-
- 著者
- 松元 雅和
- 出版者
- 關西大學法學會
- 雑誌
- 關西大學法學論集 (ISSN:0437648X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.98-119, 2016-05-21
1 0 0 0 OA 配電作業用活線ロボットの開発
- 著者
- 株式会社安川電機 九州電力株式会社
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.47-48, 1997-01-15 (Released:2010-08-10)
1 0 0 0 独裁者の学校
- 著者
- エーリヒ・ケストナー 著
- 出版者
- みすず書房
- 巻号頁・発行日
- 1959
1 0 0 0 OA 開発が進む直流送電システム
- 著者
- 長谷川 泰三
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会誌 (ISSN:13405551)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.10, pp.658-661, 1996-09-20 (Released:2008-04-17)
1 0 0 0 OA 中国における製鉄業の展開過程:南京政権期の経済建設の一側面
- 著者
- 萩原 充
- 出版者
- 北海道大学經濟學部
- 雑誌
- 經濟學研究 (ISSN:04516265)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.63-81, 1987-09
1 0 0 0 OA 多房性胸水で発見され,膿胸との鑑別を要したリウマチ性胸膜炎の1例
- 著者
- 立石 遥子 菅原 望 園田 浩生 藤巻 哲夫 杉山 雅也 埜村 智之
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.509-514, 2017-11-30 (Released:2017-12-20)
- 参考文献数
- 10
65歳男性。来院1か月前から咳嗽が出現し,当院内科を受診した。画像にて右多房性胸水を認め,胸水は滲出性であった。膿胸,結核性胸膜炎,入院中に関節リウマチと診断されたことからリウマチ性胸膜炎などを疑った。抗生剤投与と胸腔ドレナージを行なったが,多房性のためドレナージ効果が不十分であった。胸水所見に有意所見無く,病状も改善乏しいため治療診断目的に胸腔鏡下右胸膜剥皮術,胸膜生検を施行した。 病理では好塩基性の変性と壊死が非常に目立つ組織で,リンパ球などの単核細胞の浸潤も認められ,非特異的慢性炎症の所見であった。全身ステロイド投与にて速やかに病状が軽快した事から臨床経過と合わせてリウマチ性胸膜炎と診断した。リウマチ性胸膜炎が疑われるが,膿胸との鑑別に苦慮する場合は,胸腔鏡下胸膜生検を積極的に行なうのが望ましいと思われた。
1 0 0 0 OA ARDS(acute respiratory distress syndrome)
- 著者
- 田中 明彦
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.6, pp.675-681, 2018 (Released:2018-06-07)
- 参考文献数
- 19
1 0 0 0 OA 倉沢愛子著『日本占領下のジャワ農村の変容』
- 著者
- 蔡 史君
- 出版者
- Japan Society for Southeast Asian Studies
- 雑誌
- 東南アジア -歴史と文化- (ISSN:03869040)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.23, pp.63-81, 1994-06-01 (Released:2010-02-25)
- 被引用文献数
- 1 1
The war ended nearly 50 years ago and yet the truth of the Japanese Occupation years in many parts of Southeast Asia has not been fully known. Opinions on whether it was a “holy war” or “one of aggression” are still divided in Japan. In other words, it is still a very sensitive issue. As a result, academic research on the subject has been restrained to some extent.The book's reviewer gives high regards to efforts made by the author in ploughing through voluminous historical records and materials when doing the research in an attempt to achieve objectivity. But at the same time, the reviewer also voices her disagreement with some views held by the author in the book. They include:1. The great extent with which details of activities and policies carried out by the Japanese military government, both the positive and negative ones, and the impact they created are reported in the book. Some of them, which seem to be mere facts and observations, appear unconvincing for lack of sufficient evidence. The author's views on “Tonarigumi” is one example.2. On the author's view that certain policies carried out under Japan's military rule had brought about some “unexpected contributions”, the reviewer disagrees, pointing to the fact that all policies spelt out then were based on one central national objective, which was to serve Japan's interest in the domination of others during that time. Under such circumstances, therefore, when policies being implemented could not achieve results as desired by the political masters, they should not even be evaluated at all and be viewed as some kind of “contributions”. They were matters of a different nature, and should not be put together on equal footing for elaboration or discussion purposes.3. On the role of “Senmukan”, those who implemented cultural policies and others who led in agricultural development, the author held some very positive views on them, believing that their “good personal intentions” should not be dismissed all together simply by such term as “invasion”. The reviewer, on the other hand, is of the opinion that the so-called “Senmukan” and the other two groups were all organised groups under the command of the Japanese military government. Thus, even if some of them held very “strong ideas and views on Asianism”, one should not therefore interpret or explain it as their general good feelings towards the people in Southeast Asia.
- 著者
- 佐藤 卓己
- 出版者
- 教育史学会
- 雑誌
- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.193-198, 2006-10-01 (Released:2017-06-01)
- 著者
- 植田 雄一 牧野 裕子 西田 卓弘 落合 昂一郎 丸塚 浩助 盛口 清香 大友 直樹
- 出版者
- 日本大学医学会
- 雑誌
- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.3, pp.155-159, 2022-06-01 (Released:2022-08-11)
- 参考文献数
- 8
42 歳の女性.HER2 陰性転移性乳癌に対する標準治療 が終了後,遺伝子パネル検査 FoundationOne®CDx を施行 した.ERBB2 遺伝子の増幅を認めた.また,生検検体 での HER2 IHC 法で 2+ であったため,FISH 法を施行し たところ陽性であった.抗 HER2 療法を開始したところ, 部分奏功を認めた.既存の HER2 テストでは抗 HER2 療 法の適応とならなかった症例でも,遺伝子パネル検査を 行うことで,抗 HER2 剤の適応となる症例を拾い上げる ことが可能であり,一部の乳癌患者の予後を大きく変え る可能性がある.