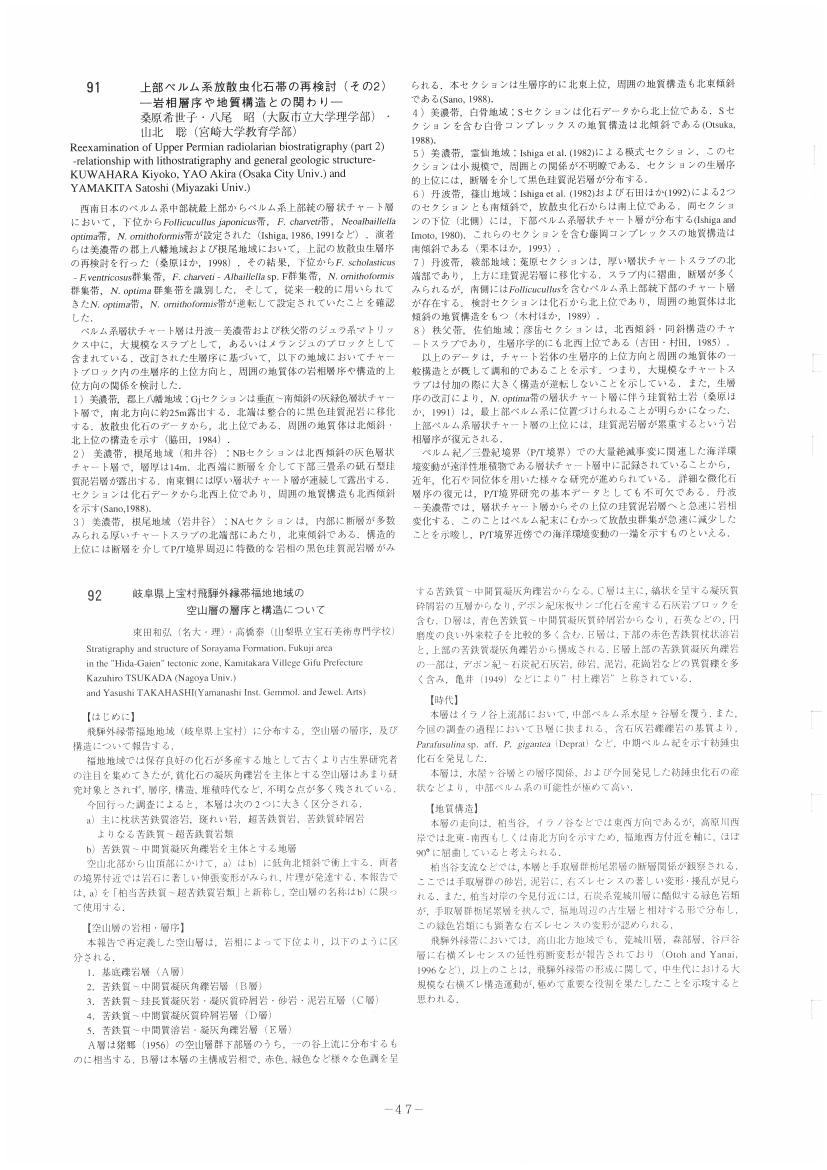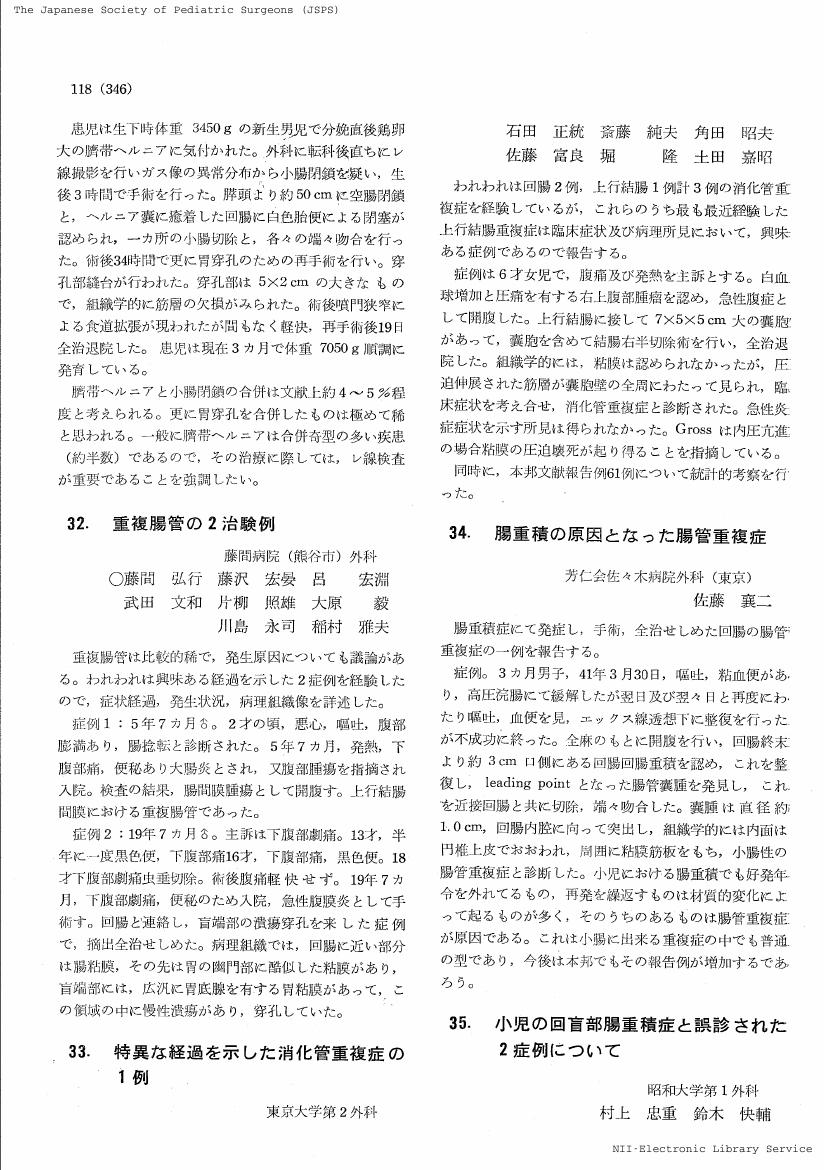1 0 0 0 OA 日本における初期の国際法にまつわる逸事
- 著者
- 宮永 孝
- 出版者
- 法政大学社会学部学会
- 雑誌
- 社会志林 = 社会志林 (ISSN:13445952)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.434-350, 2011-03
1 0 0 0 OA 〈脱中心化〉から〈再中心化〉へ : オギュスタン・ベルクと日本
- 著者
- 木岡 伸夫
- 出版者
- 関西大学東西学術研究所
- 雑誌
- 関西大学東西学術研究所紀要 (ISSN:02878151)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.63-75, 2008-04-01
Le problème de la «rencontre avec le monde moderne» se réduit à deux questions : «Comment les hommes européens ont-ils rencontré les autres 'inconnus' jusqu'alors ?» et «Quelles réflexions ont-ils eu sur eux-mêmes à travers cette expérience de rencontre ?». On doit presque nécessairement vivre entre «décentralisation» et «recentralisation» lorsqu'on sort de son propre monde afin d'entrer dans un nouveau monde qui nous est étranger. C'est justement le cas d'Augustin Berque qui s'est mis en relation extrêmement cordiale avec le Japon.La rencontre avec le Japon n'était pour lui pas autre chose qu'un processus d'établissement de la mésologie (fûdogaku) en tant que discipline. Comme le sens des milieux (fûdo) s'exprime en paysages dans la théorie mésologique, Berque ne put s'empêcher de s'accoutumer, dans ses études sur la culture japonaise, à ces paysages très différents de ceux dans son pays. La diversité des expressions paysagères se fond sur la pluralité des «types» de culture. Il devait donc «décentraliser» en comparant la culture japonaise avec celles de l'Europe, ce qui constitua une étape nécessaire à sa réflexion sur lui-même.Il n'en est pas de même des recherches urbaines, parce qu'on n'aperçoit dans toutes les villes qu'un seul prototype : l'union de la substance physique (astu ; ville ; town) et de la communauté spirituelle(polis ; cité ; city), laquelle est typique des villes historiques à l'Occident. Pour ce qui est de l'unité complète de la «structure» et du «sens», on ne l'a trouvé nulle part ailleursque dans les villes européennes de tout temps historiques. C'est pourquoi Berque leur accorde une position de modèle idéal.Il nous marque son attitude de «recentralisation» en ce qu'il fait de la ville occidentale son cadre de référence. Pourtant ce n'est pas de l'ethnocentrisme, car il fait aussi du Japon une sorte de miroir réfléchissant sur lui-même et il fait par cela même le trajet entre «décentralisation» et «recentralisation», c'est-àdire qu'il accomplit une dialectique proprement mésologique. Et ce qui y joue un rôle de médiateur n'est pas le Japon, ni l'Europe, mais l'Amérique. Une triade «Japon-Amérique-Europe» apparaîtra ainsi avec l'intérêt de se situer dans une structure multipolaire internationale.Le Japon fonctionne alors comme miroir en ces sens : il reflète avant tout l'image positive ou idéale de la France(ou de l'Europe) et puis celle de l'Amérique avec sa réalité négative. Il reflète enfin l'image négative de l'Europe qui se laisse ronger par son double ennuyeux, l'Amérique. Tout cela signifie qu'il y a toujours, dans la pratique de la mésologie, un processus circulaire de «décentralisation- recentralisation». C'est ainsi que le «centre» se prépare à échanger sa place avec la «périphérie».
1 0 0 0 OA 防災集団移転促進事業と気仙沼市舞根地区におけるオーラルヒストリーの収集
1 0 0 0 書評と紹介 猪瀬千尋著『中世王権の音楽と儀礼』
- 著者
- 豊永 聡美
- 出版者
- 吉川弘文館
- 雑誌
- 日本歴史 (ISSN:03869164)
- 巻号頁・発行日
- no.849, pp.92-94, 2019-02
1 0 0 0 OA JADERを用いた抗うつ薬による高血糖/糖尿病の発症の可能性に関する検討
- 著者
- 向井 潤一 丸山 沙季 尾鳥 勝也 久保田 理恵
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.4, pp.591-598, 2020-04-01 (Released:2020-04-01)
- 参考文献数
- 23
Few studies have examined the relationship between the use of antidepressants and the onset of hyperglycemia and diabetes mellitus in Japan. We herein explored the possibility of this relationship using the Japanese Adverse Drug Event Report database (JADER). The present study included 20 individual antidepressants, consisting of 6 subclasses, which have been approved for use in Japan. We used Standardized MedDRA Queries 20000041 to extract patients who developed hyperglycemia/new onset diabetes mellitus (NODM) in JADER between April 2004 and September 2016. We calculated reporting odds ratios (RORs) with 95% confidence intervals (CI). We also calculated odds ratios defined as the ratio of odds of hyperglycemia/NODM to all other adverse drug events (ADEs) by the age cut-off group or sex in the cases of antidepressants. The lower limit of 95%CI of RORs for 13 antidepressants (imipramine, clomipramine, nortriptyline, amitriptyline, amoxapine, maprotiline, mianserin, sertraline, paroxetine, escitalopram, duloxetine, mirtazapine, and trazodone), which included all subclasses, exceeded 1. Younger age group was associated with hyperglycemia/NODM for 5 antidepressants (imipramine, amitriptyline, maprotiline, duloxetine, and trazodone), and female was associated with the ADEs for trazodone, although these results should be interpreted cautiously. Healthcare personnel need to be aware that the use of antidepressants may lead to hyperglycemia/NODM.
1 0 0 0 OA 日本刀の伝統的作刀技術と美術的価値
- 著者
- 水木 良光
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.5, pp.270-275, 2019-05-01 (Released:2019-11-01)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 上部ペルム系放散虫生層序の再検討
1 0 0 0 OA 上部ペルム系放散虫化石帯の再検討(その2)
- 著者
- 桑原 希世子 八尾 昭 山北 聡
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第105年学術大会(98松本) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.091, 1998-09-20 (Released:2016-10-17)
1 0 0 0 OA ポリシラン変性アルキド樹脂に関する研究
- 著者
- 森川 徳幸 湊 盟
- 出版者
- 社団法人 日本印刷学会
- 雑誌
- 日本印刷学会誌 (ISSN:09143319)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.384-392, 2016 (Released:2016-11-15)
- 参考文献数
- 20
Using vegetable origin materials, the synthesis of a new polysilane modified alkyd resin was carried out to produce functional biodegradable polymer materials. Polysilane was added during the transesterification step or the condensation polymerization step. We observed that the rheological properties of the resulting alkyd resins were markedly changed.
1 0 0 0 OA 下顎の開口動作に先行する開口筋筋活動に関する筋電図的研究
- 著者
- 岡田 正博 内田 愼爾
- 出版者
- 大阪歯科学会
- 雑誌
- 歯科医学 (ISSN:00306150)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.173-188, 1995-06-25 (Released:2017-03-09)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 3
咀嚼時に観察される開口筋の開口動作に先行する筋活動の動作学的な意義を明らかにするため, 咀嚼に比べ比較的単純で再現性に優れたopen-close-clench cycle (OCC運動)を被験運動とし, 開閉口運動速度, 咬みしめ力, 運動の繰り返しの有無, 歯の接触の有無, 歯根膜感覚の有無などの条件が外側翼突筋下頭(Lpt), 顎二腹筋前腹(Dig)の onsetに及ぼす影響について観察した. 有歯顎者のOCC運動では, Lpt, Digともに開口開始に先行する筋活動がみられ, それぞれの筋の onsetは, 開閉口相時間, 咬合相時間の変化によっては有意な変動を示さなかったものの, 咬みしめ力に対応する咬筋(Mm)平均筋活動量の変化によって有意に変動し, Mmの活動量が大きくなると開口筋 onsetはより先行する傾向を示した. 最大開口速度の変化は開口前の筋活動量に影響を及ぼした. 咬合相におけるMmの平均筋活動量が増すと, 開口筋の開口前に認められる筋活動が大きくなる傾向を示した. 開口筋の先行活動は, OCC運動のような繰り返し運動のみならず, 一度だけの咬みしめ後開口においても認められた. 歯を接触させない開閉口運動では, Lpt, Digともに開口に先行した活動が認められず, cycle timeの変化によってもOTは影響されなかった. 総義歯患者におけるOCC運動では, LptおよびDigの onsetが, 開口開始より先行したが, Mmの平均筋活動量の変化によって onsetは有意な変動を示さなかった. 以上の結果より, 開口筋 onsetの開口開始からの先行は, 下顎を開口方向に向けるための準備的活動であることが示唆され, これらは開口筋としての動作的特徴であることが示された. また, 開口筋 onsetを変化させる重要な要因は咬みしめ力であることが明らかとなったが, 総義歯患者では, 開口筋 onsetの調節性が有歯顎者に比較するとやや劣る傾向が示された.
1 0 0 0 OA 高齢者夫婦二人暮らしの介護継続の意思を支える要素と妨げる要素
- 著者
- 高橋(松鵜) 甲枝 井上 範江 児玉 有子
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.3_58-3_66, 2006-09-20 (Released:2011-09-09)
- 被引用文献数
- 4 2
本研究は,高齢者夫婦二人暮らしの介護がどのように継続されているかについて示唆を得るため,介護継続の意思を支える要素と妨げる要素の二つの側面から介護する配偶者の内的心情を探求した.その結果,介護継続の意思を支える要素は,『やりがい』,『被介護者への愛着』,『慈愛の気持ち』,『献身的な思い』,『被介護者への恩義』,『安心感』,『気晴らしがあること』,『負担に思わないこと』の8つのカテゴリーが抽出された.『被介護者への愛着』は『慈愛の気持ち』とともに『献身的な思い』という自己犠牲の感情を支えていると考えられ,『やりがい』は介護継続の意思を直接的に支えていると考えられた.一方,介護継続の意思を妨げる要素は,『いらだたしさ』,『閉塞感』,『不安感』,『諦めの気持ち』,『孤独感』,『周囲への気兼ね』の6つのカテゴリーが抽出された.『いらだたしさ』は直接的に介護継続の意思を妨げる要素だと考えられた.介護者は,夫婦二人暮らしの中で,『諦めの気持ち』から生じたやらざるを得ない気持ちと『献身的な思い』とのせめぎあいの中で介護を行っていることが推察された.看護職は,介護者自身が介護の効果を確認できるように関わり,自己犠牲の思いにつながる負担を軽減することの必要性が示唆された.
1 0 0 0 OA 回転電界中の誘電体の回転現象について
- 著者
- 野村 精一 本田 久
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.884, pp.802-806, 1962-05-01 (Released:2008-11-20)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 運動イメージ想起能力とメンタルプラクティスの効果との関係
- 著者
- 梅野 和也 中村 浩一 井元 淳 白澤 浩太郎 石田 猛流 加来 謙治 土井 康太
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.313-317, 2018 (Released:2018-04-27)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 2 1
〔目的〕3種類の運動イメージ評価法とmental practice(MP)でのパフォーマンスの変化との関係を検討することとした.〔対象と方法〕健常学生20名とした.MP前後における運動課題の成績比較からMPの有効性を検討し,Movement Imagery Questionnaire-Revised Japanese Version(JMIQ-R),メンタルクロノメトリー,メンタルローテーションの3種類の評価結果とMPの効果との関係を検討した.〔結果〕MP前後の運動課題に有意な改善が認められ,メンタルクロノメトリーとパフォーマンスの変化量との間に中程度の相関関係が認められた.〔結語〕メンタルクロノメトリーで測定した運動イメージ能力が,MPの効果と関わりがある可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 35. 小児の回盲部腸重積症と誤診された 2 症例について
- 著者
- 村上 忠重 鈴木 快輔 小笠原 英治 中村 寿
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会
- 雑誌
- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.346-347, 1967 (Released:2017-01-01)
- 著者
- 仙石 泰雄 市川 浩 野村 武男
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 日本体育学会大会号 第53回(2002) (ISSN:24330183)
- 巻号頁・発行日
- pp.493, 2002-08-30 (Released:2017-08-25)
1 0 0 0 OA マックス・ウェーバーの方法論 (1) : メディア研究の方法論構築に向けて
- 著者
- 山田 吉二郎
- 出版者
- 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院
- 雑誌
- 国際広報メディア・観光学ジャーナル
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.69-97, 2008-11-28
This paper aims at discussing Max Weber's methodology, specifically based on his essay "Objectivity in Social Science and Social policy". It is well known that Max Weber made continuous efforts to construct modern social science; his Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre are full of highly suggestive ideas and concepts for students who are interested in methodology generally. If media studies is also expected to be one of genuine social and cultural sciences, every piece of Weber's thought will be important. Every social reality is unique, concrete and infinitely rich; we cannot grasp it without constructing "ideal type" which is not real image of reality, but its edited one. It will be shown that Weber's "ideal type" is composed of three ingredients, that is, economy, value and history.
1 0 0 0 空気中に噴霧された次亜塩素酸の挙動
1 0 0 0 OA 蜘蛛方言録(第一輯)
- 著者
- 植村 利夫
- 出版者
- 日本蜘蛛学会
- 雑誌
- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.4, pp.170-171, 1937-12-06 (Released:2008-12-19)
- 著者
- 廣澤 隆行 沖田 一彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.C0962, 2007
【目的】我々は第10回広島県理学療法士学会にて,理学療法士(PT)が長期化した外来患者を単に医学的側面からだけでなく,心理・社会的側面を含む複数の視点から捉え悩んでいることを報告した。今回,その結果をもとに,整形外科疾患患者の痛みの訴えに対するPTの認識や悩みについてアンケート調査を実施したので報告する。<BR>【方法】広島県下で整形外科の標榜を掲げる医療機関に勤務するPT 250名に対し,郵送によるアンケートを実施した。質問は,基礎項目および患者の痛みの訴えで悩んだ経験とそれに関わる項目の計21項目であった。返送された126部の回答(回収率50.4%)から,顕著な記入漏れ・ミスがあるものを除外した112部(有効回答率88.9%)を分析対象とした。分析はまず,患者の痛みの訴えに悩んだ頻度(4段階)の差を,性別,婚姻,同居者,勤務地,関わっている診療科,勤務先の変更経験の6項目についてχ<SUP>2</SUP>検定により比較した。次に,年齢,経験年数,学歴,勤務先の規模,常勤PT数,疾患別の診療頻度,重視する専門知識,治療内容と頻度,痛みと理学所見との不一致性,患者‐PT間での認識のギャップ,効果がない場合の治療の継続性,患者の社会的側面への注意の12項目についてSpearmanの相関を調べた。そのうえで,有意差のあった項目を独立変数としたロジスティック解析(漸減法)を行い,悩みの頻度への影響因子を抽出した。<BR>【結果】患者の痛みの訴えに悩んだ経験は「ない」1名(0.9%),「ときどき」25名(22.3%),「しばしば」58名(51.8%),「常に」28名(25.0%)であった。χ<SUP>2</SUP>検定を行ったすべての項目において回答の分布に有意差はなかった。一方,相関を調べた項目については,年齢(r=-0.23, p<0.05),経験年数(r=-0.38, p<0.01),学歴(r=0.23, p<0.05),診療頻度・関節リウマチ(r=0.21, p<0.05),同・五十肩(r=0.21, p<0.05),専門知識・心理学(r=0.25, p<0.05),同・教育学(r=0.21, p<0.05),同・行動科学(r=0.27, p<0.05),理学所見との不一致性(r=0.29, p<0.01),認識のギャップ(r=0.40, p<0.01),治療の継続性(r=0.28, p<0.01)との間に有意な相関を認めた。ロジスティック解析の結果(OR=オッズ比, CI=95%信頼区間),経験年数(OR=0.25, CI=0.11-0.56, p<0.01),行動科学(OR=2.97, CI=1.33-6.62, p<0.01),認識のギャップ(OR=3.08, CI=1.12-8.44, p<0.05)が有意な影響因子として抽出された。<BR>【考察】整形外科疾患患者の痛みの訴えは治療の長期化を招く重大な要因であり,当然PTもその対応に苦悩することになる。今回の結果から,臨床経験が浅く,痛みの改善について患者との間に認識のギャップがあると感じているPTほど悩んでいることが分かった。またそのようなPTは,必要な専門知識として行動科学を重視していると考えられた。