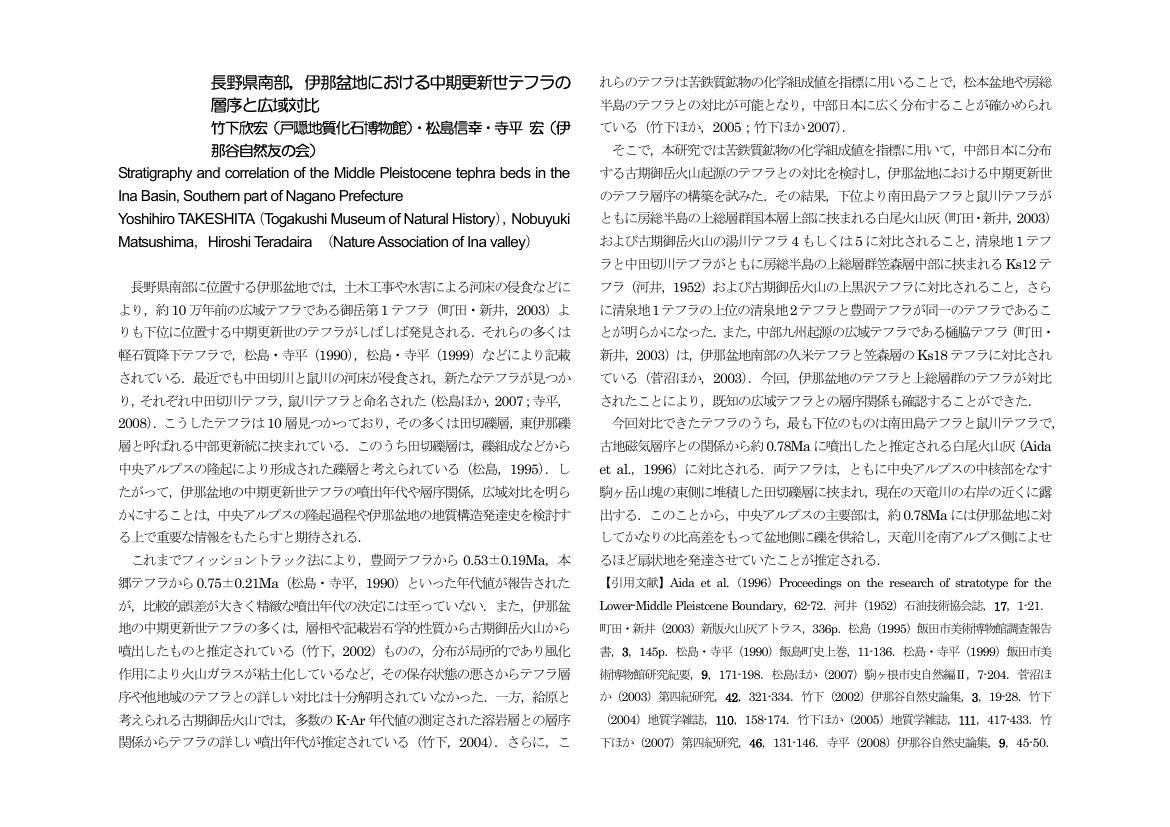3 0 0 0 OA 植物メタボロミクスの開拓と薬用資源植物ゲノミクスへの展開
- 著者
- 齊藤 和季
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.138, no.1, pp.1-18, 2018 (Released:2018-01-01)
- 参考文献数
- 245
- 被引用文献数
- 7
A variety of chemicals produced by plants, often referred to as ‘phytochemicals’, have been used as medicines, food, fuels and industrial raw materials. Recent advances in the study of genomics and metabolomics in plant science have accelerated our understanding of the mechanisms, regulation and evolution of the biosynthesis of specialized plant products. We can now address such questions as how the metabolomic diversity of plants is originated at the levels of genome, and how we should apply this knowledge to drug discovery, industry and agriculture. Our research group has focused on metabolomics-based functional genomics over the last 15 years and we have developed a new research area called ‘Phytochemical Genomics’. In this review, the development of a research platform for plant metabolomics is discussed first, to provide a better understanding of the chemical diversity of plants. Then, representative applications of metabolomics to functional genomics in a model plant, Arabidopsis thaliana, are described. The extension of integrated multi-omics analyses to non-model specialized plants, e.g., medicinal plants, is presented, including the identification of novel genes, metabolites and networks for the biosynthesis of flavonoids, alkaloids, sulfur-containing metabolites and terpenoids. Further, functional genomics studies on a variety of medicinal plants is presented. I also discuss future trends in pharmacognosy and related sciences.
3 0 0 0 OA 許容濃度等の勧告(2017年度)
- 著者
- 日本産業衛生学会
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.5, pp.153-185, 2017-09-20 (Released:2017-10-05)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 山本 尚樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.183-198, 2014 (Released:2016-06-20)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1
本論文では,自己組織化現象に関する近年のシステム論の研究動向の観点から語られることの多かったEsther Thelenの発達理論を,George E. Coghillの発生研究を嚆矢とし,Arnold L. Gesell,Myrtle B. McGrawによって展開された古典的運動発達研究の延長戦上に位置づけ,再検討した。特に,Gesell,McGraw,Thelen,三者の発達研究・理論を比較検討し,類似点と相違点を明確にすることで,運動発達研究の基礎と今後の課題を明確にすることを目的とした。この検討により運動発達研究は,i.下位システムの相互作用から系全体の振る舞いの発達的変化を捉える,ii.発達的変化を引き起こす要因を時間軸上で変化する系の状態との関係から考察し特定する,という基本的視座をもつこと,さらにiii.系の固有の状態が発達に関与するという固有のダイナミクスの概念,iv.様々なスケールが入れ子化された時間の流れから発達を捉えるという多重時間スケールの概念,がThelenによって新たに加えられたことが確認された。最後に,このiii.,iv.の点について近年の研究動向を概観し,今後の課題を整理した。
3 0 0 0 OA Groupthink trap
- 著者
- Ryota MATSUI
- 出版者
- The Academic Association for Organizational Science
- 雑誌
- Transactions of the Academic Association for Organizational Science (ISSN:21868530)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.14-19, 2017 (Released:2017-12-23)
- 参考文献数
- 13
On March 11, 2011, the Great East Japan Earthquake triggered an extremely severe nuclear accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, owned and operated by Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Before the accident, several experts and researchers had repeatedly pointed out a high possibility that tsunami would reach beyond the level assumed by TEPCO, as well as a possibility that such level of tsunami might cause severe accidents. However, TEPCO and the regulatory body (NISA) overlooked these warnings and did not take any preventive measure against tsunami. Consequently, Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant was incapable of withstanding the tsunami that hit on the day. Due to these facts, the accident is regarded as a man-made disaster. Even today, more than 6 years after the accident, it has not been revealed why they underestimated the risk of tsunami and couldn't prevent the accident. This article suggests that this question can be partially answered by applying “groupthink” model which was developed by Irving Janis. This study analyzes the descriptions of two official reports on the Fukushima accident by Japanese government and National Diet. As the result, all antecedent conditions, six symptoms of groupthink and six symptoms of defective decision making are found in the accident reports. This study also suggests that an additional antecedent condition "existences of obvious and obscure risks" and a symptom of groupthink "procrastination of problem solving" could be included in the groupthink model.
3 0 0 0 OA 家族性膵癌
- 著者
- 高折 恭一
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.8, pp.1479-1483, 2015-08-05 (Released:2015-08-05)
- 参考文献数
- 23
「膵癌に罹患した一対以上の第一度近親者がいる家系で,既知の家族性癌家系を除いたもの」を家族性膵癌家系と定義する.家族性膵癌家系における膵癌発生リスクは,一般家系の約9倍と有意に高い.膵癌発生リスクは,第一度近親者の膵癌患者数とともに上昇し,2人の第一度近親者に膵癌患者がいる場合には一般家系の約6.4倍であるが,3人以上の場合には約32倍となる.膵癌のうち5~10%が家族性膵癌であることが判明している.したがって,家族性膵癌は,膵癌のリスクファクターとして非常に重要である.しかし,家族性膵癌を引きおこす遺伝子異常などのメカニズムには不明な点が多く残されている.
3 0 0 0 OA 内視鏡下甲状腺手術ワーキンググループの成績と今後の課題
- 著者
- 五十嵐 健人 清水 一雄 岡村 律子 赤須 東樹 長岡 竜太 眞田 麻理恵 杉谷 巌
- 出版者
- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
- 雑誌
- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.200-204, 2016 (Released:2017-01-26)
- 参考文献数
- 12
甲状腺・副甲状腺疾患に対する内視鏡手術が開発され,他の領域で内視鏡手術が次々と保険収載されるなか,医療行政変遷のため保険収載には至らなかった。2016年の診療報酬改定においてようやく甲状腺良性疾患や副甲状腺機能亢進症やバセドウ病に対して内視鏡下手術が保険収載された。内視鏡下甲状腺手術ワーキンググループ(WG)は2014年に内分泌外科領域における内視鏡下手術の先進医療Aを開始する時に設立された。2015年WGで臨床成績を検討し,通常手術と比較し安全性や有効性に遜色ない結果を示した。また,整容性に対する高い患者満足度や在院日数の短縮などの医療経済面への貢献も示す結果であった。それらの結果が評価され保険収載されたものと思われる。一方,甲状腺癌に対しては同様のデータであったが先進医療Aの継続となった。今後は保険収載に伴う問題や甲状腺悪性腫瘍に対する保険収載の課題など検討すべき問題が存在する。
3 0 0 0 OA JSTサービス紹介 J-GLOBAL これからもイノベーション創出に貢献していく
- 著者
- 佐藤 恵子
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.10, pp.753-756, 2018-01-01 (Released:2018-01-01)
- 参考文献数
- 5
3 0 0 0 OA 球技における視触覚刺激提示がプレイスキルに及ぼす影響
- 著者
- 佐野 祐士 佐藤 晃矢 白石 僚一郎 大槻 麻衣
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.493-502, 2017 (Released:2017-12-31)
- 参考文献数
- 35
We focused on the effect that applying visual and haptic stimuli reduce the task load of situation awareness during a ball game, and we hypothesized that as a result, they also reduce the number of misplays. We developed the system which can provide the visual and haptic stimuli for supporting 3-on-3 soccer game in real-time; for visual stimuli, the position relationship of opponent players are shown, and for haptic stimuli, the position of opponent player who are in the out of view angle. Through the experiment we evaluated whether the visual and haptic stimuli can reduce the task load in a ball game. As a result, the proposed visual or haptic stimuli itself reduced the player's task load and improved the ball handling skill. On the other hand, we found that the combination of visual and haptic stimuli did not reduce the task load of player, and did not contribute to the reduction of misplay.
3 0 0 0 OA 全周囲立体モニタ技術の実用化
- 著者
- 清水 誠也 水谷 政美 鶴田 徹
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.J24-J29, 2014 (Released:2013-12-20)
- 参考文献数
- 8
筆者らは,駐発車を含むさまざまな運転状況でのドライバ視覚支援を目的とし,4台の車載カメラ映像をもとに,自車両の近傍だけではなくより広い範囲の状況を立体感のある全周囲立体映像として合成し,視点を自由に動かしながら表示できる全周囲立体モニタ技術を開発した.本技術により,駐車時,交差点右左折時,高速道路の本線合流時などさまざまな運転状況に応じて死角のない車両周辺映像をリアルタイムに合成し,車載モニタで確認できるようになった.全周囲立体モニタ技術は,すでにドライバ視覚支援製品として実用化されており,ドライバの安心・安全の向上を通して社会に貢献している.本稿では,全周囲立体モニタ技術の原理について述べた後,実用化の課題であったカメラ間の視差と輝度差への対処について示す.さらに車載組込み系システムへの実装と,実車両への適用について報告する.
3 0 0 0 OA 地域課題の発見から解決に向けた地理学と隣接分野のアプローチ
- 著者
- 秋山 千亜紀
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.322-328, 2017 (Released:2017-12-28)
3 0 0 0 OA 長野県南部,伊那盆地における中期更新世テフラの層序と広域対比
- 著者
- 竹下 欣宏 松島 信幸 寺平 宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第116年学術大会(2009岡山) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.141, 2009 (Released:2010-03-31)
- 参考文献数
- 13
3 0 0 0 OA 光の感受性障害に関する研究の動向について
- 著者
- 尾形 雅徳 熊谷 恵子
- 出版者
- 障害科学学会
- 雑誌
- 障害科学研究 (ISSN:18815812)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.149-161, 2016-03-31 (Released:2017-07-20)
- 参考文献数
- 27
Scotopic Sensitivity Syndrome(以下、SSS)と言われる視知覚に関連した障害がある。 この障害は、文字や文章を読む際に歪みや不快感が生じるものである。その症状は有色フィルムやレンズを使用することで改善が見られる。欧米では、1980年に、そして日本では2006年にこの障害の研究が始まり様々な視点からSSSは検証されている。日本において、このSSSの研究を進めていくにあたって、どのような視点で研究を行っていくかの知見を得るため、本稿ではSSSのスクリーニング方法、有色フィルムの効果、SSSの有症率についての研究に焦点を当て、それぞれの課題を明らかとすることした。第一にスクリーニング方法においては、様々な方法で試みられ検証されたスクリーニング検査において、チェックリストでのスクリーニングが重要であることが明らかとなった。第二に有色フィルムの効果においては、読みに困難がある場合でも条件によってその効果は変わるということが明らかとなった。最後に有症率においては、欧米では20%から38%、日本では6%と推定されることが明らかとなった。
3 0 0 0 OA 作用素環への入り口
- 著者
- 竹崎 正道
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.89-101, 2003-01-24 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 9
3 0 0 0 OA 三重県の発電所のRDF 貯蔵サイロでの火災と爆発
- 著者
- 八島 正明
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.169-176, 2011-06-15 (Released:2016-08-31)
- 参考文献数
- 35
2003 年8 月14 日,多度町(現・桑名市)にあるごみ固形化燃料(RDF)貯蔵サイロ内で小爆発が発生し,その後サイロ内でくすぶり続けていた.19 日,サイロが爆発し,サイロの屋根で消火活動を行っていた消防職員2 名が死亡,サイロのそばにいた作業員1 名が負傷する災害が発生した.RDF(Refuse Derived Fuel)は新燃料の一つとして脚光を浴びたが,この事故災害を契機に,爆発・火災の危険性があることが社会に知れ渡ることになった.本件では3 回に分けて報告するが,その1 では災害の概要と被害状況を述べる.
3 0 0 0 OA 鉄隕石の微細構造と磁性
- 著者
- 小嗣 真人 三俣 千春
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.103-109, 2010 (Released:2012-11-01)
- 参考文献数
- 49
3 0 0 0 OA 「あやとり」「折り紙」の学習過程における脳波及び心理的変化
- 著者
- 野田 さとみ 佐久間 春夫
- 出版者
- 日本バイオフィードバック学会
- 雑誌
- バイオフィードバック研究 (ISSN:03861856)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.29-36, 2010-04-25 (Released:2017-05-23)
- 被引用文献数
- 1
本研究では,手指の運動を伴う遊びであるあやとりの特徴を明らかにするために,類似する遊びとして折り紙を取りあげ,動作パターンの学習過程について比較検討を行なった.被験者は健康な女性10名であった.あやとり課題・折り紙課題はそれぞれ動作パターンを記憶するための練習時間を設定し(練習中),練習後は3分間連続して課題を行なった.測定項目は,生理指標として脳波の周波数帯域別含有率の変化,心理指標として坂入らによる「心理的覚醒度・快感度を測定する二次元気分尺度」および遂行の自己評定とした.脳波の結果から,前頭部においては課題に関わらず練習中よりも練習後でα1波,α2波,β波の含有率の増加が認められた.中心部・頭頂部では,あやとりは練習中・練習後にβ波が変化しないのに対し,折り紙では練習中に比べ練習後でβ波の増加が認められ,あやとりよりも折り紙の方が動作パターンを記憶して行うことで中心部・頭頂部が活性化することが示された.自己評定の結果からは,練習中・練習後に関わらず折り紙に比べあやとりの方が集中して取り組んでいたことが示された.以上の結果から,動作パターンを記憶して行なった場合,あやとり・折り紙ともに意識的に手順を想起しながら行うことにより覚醒が高まること,あやとりに比べ折り紙は視覚情報への依存度が高く動作手順の遂行への集中を要することが示された.一方,自己評定の結果からは動作パターンを記憶しているかに関わらず折り紙よりもあやとりの方が集中していたと報告され,これは,あやとりは常に糸を一定の形に保たなければならないという活動特性によるものと考えられた.
3 0 0 0 OA 南川文里著『アメリカ多文化社会論――「多からなる一」の系譜と現在』
- 著者
- 塩原 良和
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.345-347, 2016 (Released:2017-12-31)
- 著者
- Toshihisa Ishikawa Kohtaro Yuta Yukio Tada Akihiko Konagaya
- 出版者
- Chem-Bio Informatics Society
- 雑誌
- Chem-Bio Informatics Journal (ISSN:13476297)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.110-111, 2017-12-31 (Released:2017-12-04)
- 参考文献数
- 3
藤田稔夫氏(ふじた・としお=京都大名誉教授、医農薬化学)が今年8月22日午前11時47分、病気のため京都市内の病院で死去されました。享年88歳。昨年10月には京都大学で開催された第44回構造活性相関シンポジウムで米寿をお祝いしたところでした。藤田先生はCorwin Hansch教授(米国)と共に定量的構造活性相関の方法を確立され、医薬農薬などの多方面で分子設計に多大な影響を与えてきました。さらに、藤田先生はEMIL (Example-Mediated Innovation for Lead Evolution)の方法を開発して、人工頭脳(AI)に基づく創薬分子デザインの可能性を追求されてこられました。藤田先生の先進的な考えとアプローチは私どもの模範とするところです。この追悼文をもって藤田稔夫先生の偉業をかみしめつつ、ご冥福をお祈り申し上げます。
3 0 0 0 OA 職業性ストレスと抑うつの関係における職場のソーシャルサポートの緩衝効果の検討
- 著者
- 小松 優紀 甲斐 裕子 永松 俊哉 志和 忠志 須山 靖男 杉本 正子
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.140-140, 2010 (Released:2010-06-02)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 5 10
職業性ストレスと抑うつの関係における職場のソーシャルサポートの緩衝効果の検討:小松優紀ほか.東邦大学医学部看護学科―目的:本研究は,職業性ストレスと抑うつの関連性における職場のソーシャルサポート(以下サポート)の緩衝効果について検証することを目的とした. 対象と方法:調査方法は無記名自記式質問紙を用いた横断的研究である.対象者は某精密機器製造工場に勤務する40歳以上の男性712名であった.調査項目は,年齢,職種等の属性,抑うつ,職業性ストレス(仕事の要求度・仕事のコントロール),職場のサポート(上司のサポート・同僚のサポート)等であった.職業性ストレスと職場のサポートの測定はJCQ職業性ストレス調査票(JCQ)を用いた.抑うつは抑うつ状態自己評価尺度(CES-D)を用い,得点が16点以上の者を抑うつ傾向とした.職業性ストレス,サポートについては各尺度の得点を中央値で二分し,得点の高い群を高群,低い群を低群とした.職業性ストレスおよびサポートの高低別のCES-D得点の平均値の比較をt検定にて行った.またCES-D得点を従属変数とし,対象者の属性,職業性ストレス,サポート,職業性ストレスとサポートの交互作用項を独立変数として階層的重回帰分析を行った.交互作用が有意であった場合には,年齢を共変量として共分散分析を行い,職業性ストレスの高低別にサポートの高低がCES-D得点に及ぼす効果を検討した. 結果:調査の結果,全対象者のうち抑うつ傾向者は23.2%であった.仕事の要求度の高低別のCES-D得点は,高群が低群よりも有意に高かった.仕事のコントロール,上司のサポート,同僚のサポートそれぞれにおけるCES-D得点は,各低群が高群よりも有意に高値であった.階層的重回帰分析を行った結果,仕事の要求度,仕事のコントロール,上司のサポート,同僚のサポートはそれぞれCES-D得点に対する有意な主効果が認められた.さらに仕事のコントロールと上司のサポートの要因間でCES-D得点に対する有意な交互作用が認められた.また,仕事のコントロールの低い状況でのみ,上司のサポート高群よりも低群のCES-D得点が有意に高値であった. 結論:これらのことから,上司によるサポートは仕事のコントロールの低さと関連する抑うつを緩衝する効果がある可能性が示唆された. (産衛誌2010; 52: 140-148)
- 著者
- 的井 愛紗 矢田 憲孝 廣田 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.6, pp.748-752, 2017-12-31 (Released:2017-12-31)
- 参考文献数
- 10
症例:78歳女性。現病歴:C型肝硬変・肝細胞癌の既往があり,5年前よりグリチルリチン製剤80mg/日を週4回静注されていた。路上で倒れているところを発見され救急要請となり,救急隊到着時の心電図所見は心室細動であった。除細動とアドレナリンの投与を行い,心拍再開後に当院へ搬送された。来院後経過:来院時,血清K 値は1.6mEq/lと低値であり,心電図ではQTc延長(631ms)を認め,低K 血症により心室細動をきたしたものと考えられた。入院後,低K 血症にもかかわらず尿中K 排泄量は多く,第6病日のレニン活性・アルドステロン値はともに低く,偽性アルドステロン症と診断した。グリチルリチン製剤の中止とカリウム補充により血清K値は正常化し,その経過中に致死性不整脈を併発しなかったが,第18病日に低酸素脳症で死亡した。考察:静注グリチルリチン製剤による偽性アルドステロン症から心室細動をきたした稀な1例を経験した。