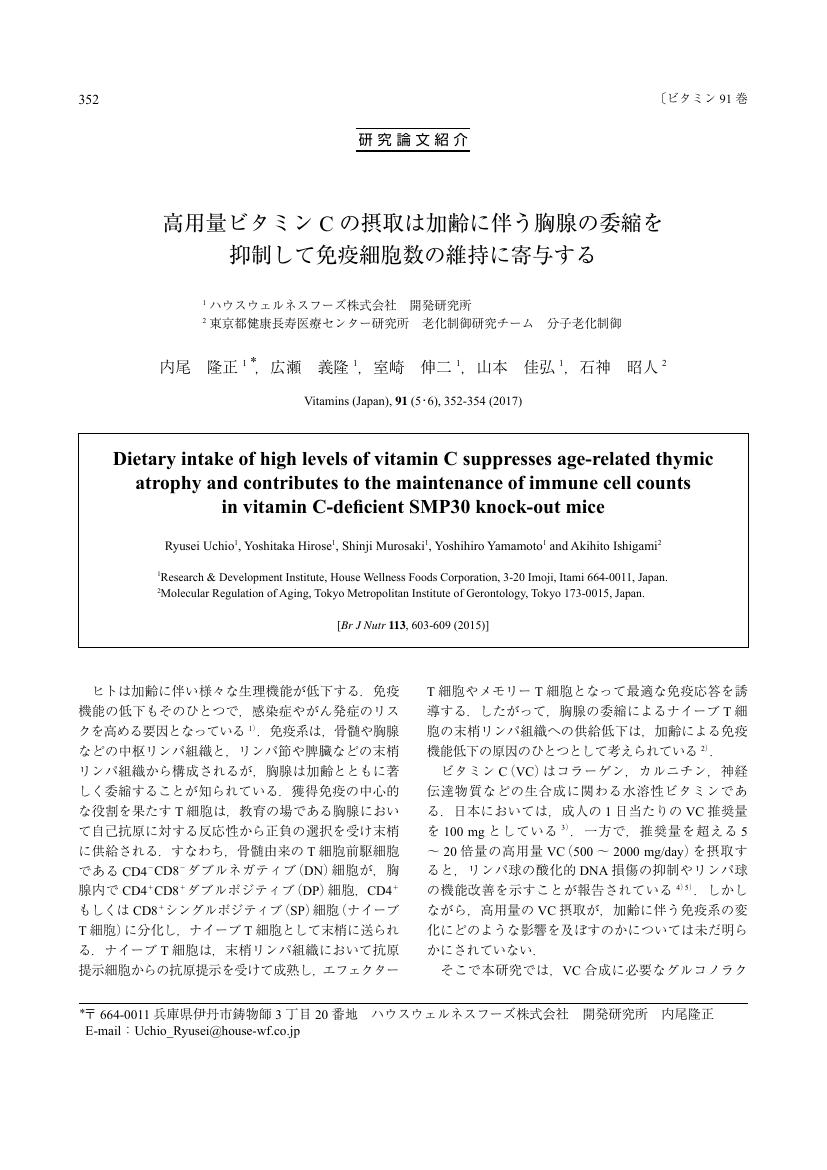23 0 0 0 OA 超音波フェーズドアレイを用いた3次元非接触マニピュレーション
- 著者
- 星 貴之
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.8, pp.453-459, 2019-08-01 (Released:2020-02-01)
- 参考文献数
- 28
23 0 0 0 OA サイエンスフィクションにおける人工知能描写の分析
- 著者
- 大澤 博隆 宮本 道人 長谷 敏司 西條 玲奈 福地 健太郎 三宅 陽一郎
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第34回全国大会(2020)
- 巻号頁・発行日
- pp.2Q5OS13b02, 2020 (Released:2020-06-19)
人工知能の様々な可能性とリスクが、現在現実の応用のための迅速なAI開発の緊急課題として議論されている。メディアや研究者でさえ、未来のビジョンを示すものとしてSFを引き合いに出すことがある。しかし、エンターテイメントに対する技術的不正確さのため、SFにおけるこれらのAIを将来の真剣な議論に持ち込むことは必ずしも適切ではない。一方で、SFのテーマの中には、人々に新たなビジョンを思い起こさせるような積極的な役割を果たすものもある。AI分野におけるSFの混合した影響を解明するために、著者らはSF評論家や作家とともにSFにおけるAIの記述方法を分析した。まず、SFにおける115のAIストーリーを、知能の多様性、社会的側面、および人間の知能の拡張という三つの方針の基準に基づいて選択した。AI特性を表す11つの要素をクラスタ分析と主成分分析を用いて分析した。その結果、SFには4つの特徴的なAIクラスタが存在することが示唆された。それらは人間、機械、ヘルパー、インフラストラクチャであり、2次元空間にマッピングされている。それらは知能と人間性である。
- 著者
- 是枝 伶旺 本村 浩之
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.27-52, 2021 (Released:2021-08-21)
23 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言期間における予防行動の関連要因:東京都在住者を対象とした検討
- 著者
- 樋口 匡貴 荒井 弘和 伊藤 拓 中村 菜々子 甲斐 裕子
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-112, (Released:2021-06-11)
- 参考文献数
- 21
目的 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は2020年前半に世界規模に広がった。日本においても同年4月7日に緊急事態宣言が発出され,国民生活に大きな影響を与えた。本研究では,COVID-19の感染予防および感染拡大予防行動として個人が行う外出・対人接触の回避行動および手洗い行動を取り上げ,東京都在住者を対象に緊急事態宣言中のこれらの行動の関連要因について検討した。方法 2020年4月26~29日に,東京都在住の20~69歳の男女を対象としたインターネット調査を行った。検討の枠組みとして,リスク低減行動を説明する防護動機理論と,他者による行動が自身の行動実施へ与える影響を説明する規範焦点理論を組み合わせて用いた。最近1週間での外出・対人接触の回避行動および手洗い行動の頻度,COVID-19へのリスク認知に加え,各行動の評価として,どの程度効果があるのか(反応効果性認知),どの程度実行できるのか(実行可能性認知),必要なコスト(反応コスト),どの程度すべきかの認識(命令的規範),他者がどの程度実行しているかの認識(記述的規範)について測定した。各行動を目的変数とする階層的回帰分析を行った。結果 分析対象は1,034人(男性520人,女性514人,平均年齢44.82歳,標準偏差14.00歳)であった。外出・対人接触回避行動については,命令的規範が高いほど行動をとる傾向にある(標準化偏回帰係数(β)=0.343, P<0.001)一方で,記述的規範が高いほど行動をとらない傾向にある(β=−0.074, P=0.010)ことが示された。さらにリスク認知・反応効果性認知・実行可能性認知の交互作用が有意であり(β=0.129, P<0.001),反応効果性認知および実行可能性認知のいずれかが低い場合にのみリスク認知と外出・対人接触回避行動に正の関連が見られた。また手洗い行動については,命令的規範(β=0.256, P<0.001)および実行可能性認知(β=0.132, P<0.001)が高いほど行動をとる傾向にあり,一方で反応コスト(β=−0.193, P<0.001)が高いほど行動をとらない傾向にあることが示された。結論 防護動機理論および規範焦点理論の変数がCOVID-19の予防行動と関連していた。予防行動の関連要因を検討する上で,これらの理論の適用が有用であることが示唆された。
23 0 0 0 OA 強制水泳の神経科学
- 著者
- 大橋 綾子 柳田 諭 林 美穂 本村 啓介
- 出版者
- 日本生物学的精神医学会
- 雑誌
- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.117-126, 2011 (Released:2017-02-16)
- 参考文献数
- 66
強制水泳試験は,抗うつ薬のスクリーニングをはじめとして,ラットやマウスのうつ病様行動を評価する行動試験として,広く用いられてきた。しかし,強制水泳試験の行動上の結果と,脳内各部位におけるニューロンの活動性との関係には,未だ不明な点も多い。本稿では強制水泳試験の神経基盤について,これまでの研究の知見から主なものを紹介する。
23 0 0 0 OA これまでの研究人生で学んだこと ―測る人生に悔いはなし―
- 著者
- 福永 哲夫
- 出版者
- 日本バイオメカニクス学会
- 雑誌
- バイオメカニクス研究 (ISSN:13431706)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.8-13, 2021 (Released:2021-08-06)
- 参考文献数
- 10
23 0 0 0 OA 鍼治療をがん患者に提供するためのガイドライン ピアレビューに基づく方針の実例
- 著者
- 福田 文彦 石崎 直人 山崎 翼 川喜田 健司 北小路 博司
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.75-86, 2008 (Released:2008-05-27)
- 参考文献数
- 72
- 被引用文献数
- 2 1
臨床ガイドラインは、 臨床医師が特定の疾患を治療する際の意思決定を支援することによって最高の診療を推進するという目的のもとに、 系統的に作成されるものである。 それらはエビデンスと連動しており、 より良い診療を行うために作成される。 鍼灸治療は、 医師や看護師、 理学療法士、 助産婦などの保健医療従事者や医療訓練を受けていない施術者などによってさまざまな状況で行われる可能性があるにもかかわらず、 一般の保健医療施設における安全な鍼灸診療のためのガイドラインはない。 ここに示すガイドラインはがん患者の症状、 特に疼痛症状の緩和やその他 (ホットフラッシュなど) の非疼痛性の症状に用いるために作成された。 本ガイドラインは、 がん患者における鍼治療の方針を提示する必要がある鍼灸師のための雛形として示すものである。 本稿には、 ガイドライン及びガイドラインとともに利用するための、 鍼治療のメカニズムや効果、 安全性についての総括的レビューが含まれている。 付記には、 自分自身で鍼治療を行うための方法を示した。 ガイドラインには、 役割と責任、 鍼治療の基準、 適応、 禁忌及び注意事項、 鍼治療、 調査及び監査のセクションが含まれている。 これらのガイドラインは治療に関する基本的で最低限の標準を示すものであり、 今後のデータとエビデンスの蓄積に応じた再評価と確認が必要である。
23 0 0 0 太陽光,風力発電の供給特性の基礎的検討
- 著者
- 新田目 倖造
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, no.8, pp.551-558, 2021-08-01 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
According to rapid increase of photovoltaic (PV) and wind generations in recent power system of Japan, the cases arise that power generation exceeds demand, so PV generations must be curtailed in some area. Hereafter, part of PV and wind generations may be curtailed in other areas too. In Europe and America too, similar surplus electricity are genetated and capacity of battery to withdraw surplus electricity are researched. This paper analyzes basic supplying characteristics of PV and wind generations in the simplified model system based on the actual power system in north-east area in Japan. As a result, when penetration ratio of PV or wind generation exceed 10~20%, surplus energy arise. It needs much capacity of battery to withdraw surplus energy, so supplying cost including battery is several ten times of cost of generation alone. If minimum output of stable generations except PV and wind generations could be lowered, surplus energy, capacity of battery and supplying cost will lower remarkably. But unit supplying cost of stable generations increases. According to introduction of much PV and wind generations, more coordination of power system and PV, wind generations is necessary, i.e. scaling up and cost down of energy storage, extension of power control range of stable generations, demand side management, etc.
23 0 0 0 OA 誤った直線閾値なしモデルの頑迷な適用による膨大な人的,社会的,経済的な損失
- 著者
- 須藤 鎮世
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.135, no.11, pp.1197-1211, 2015-11-01 (Released:2015-11-01)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 5 7
The linear no-threshold model (LNT) was recommended in 1956, with abandonment of the traditional threshold dose-response for genetic risk assessment. Adoption of LNT by the International Commission on Radiological Protection (ICRP) became the standard for radiation regulation worldwide. The ICRP recommends a dose limit of 1 mSv/year for the public, which is too low and which terrorizes innocent people. Indeed, LNT arose mainly from the lifespan survivor study (LSS) of atomic bomb survivors. The LSS, which asserts linear dose-response and no threshold, is challenged mainly on three points. 1) Radiation doses were underestimated by half because of disregard for major residual radiation, resulting in cancer risk overestimation. 2) The dose and dose-rate effectiveness factor (DDREF) of 2 is used, but the actual DDREF is estimated as 16, resulting in cancer risk overestimation by several times. 3) Adaptive response (hormesis) is observed in leukemia and solid cancer cases, consistently contradicting the linearity of LNT. Drastic reduction of cancer risk moves the dose-response curve close to the control line, allowing the setting of a threshold. Living organisms have been evolving for 3.8 billion years under radiation exposure, naturally acquiring various defense mechanisms such as DNA repair mechanisms, apoptosis, and immune response. The failure of LNT lies in the neglect of carcinogenesis and these biological mechanisms. Obstinate application of LNT continues to cause tremendous human, social, and economic losses. The 60-year-old LNT must be rejected to establish a new scientific knowledge-based system.
23 0 0 0 OA 大学生の自室へのひきこもりに関与する住居および心理要因の検討
- 著者
- 小俣 謙二
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.77-87, 1998-01-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 44
The aim of this study is to clarify residential and psychological factors related to the Japanese students who tend to confine themselves in their own rooms. The questionnaire was answered by 268 students, 134 males and 134 females. The findings are as follows. Their tendency to withdraw to their rooms was not particularly strong, but some residential and psychological factors were ascertained to explain their withdrawal tendency. Two residential factors (density, number of equipment in a room) and two psychological ones (degree of self-identity, exclusive attitude) were identified to be related to the withdrawal by both sexes. Some differences, however, were found between male and female students. Furthermore, the female seemed more sensitive to the factors studied here. The mechanism of withdrawal must be further studied, but, in the meantime, the findings strongly suggest the necessity of empirical study on what their rooms mean to adolescents.
23 0 0 0 OA 二酸化塩素ガス発生ゲル剤によるネコカリシウイルスの不活化の検討
- 著者
- 森野 博文 小泉 朋子 三浦 孝典 福田 俊昭 柴田 高
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, no.9, pp.1017-1022, 2013-09-01 (Released:2013-09-01)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 1
Noroviruses are one of the most important causes of acute gastroenteritis throughout the world. The aim of this study is to evaluate the efficacy of a chlorine dioxide gas-generating gel (ClO2 gel, 60 g) against feline calicivirus (FCV), a norovirus surrogate, in the wet state on glass dishes in a test sink (43 cm long, 75 cm wide, and 29 cm deep). The ClO2 gel permits sustained release of gaseous ClO2 (1.7 mg/h at 25°C), and was placed in one corner of the test sink. The glass dishes containing FCV suspension were placed at three positions in the test sink. We demonstrated that FCV was inactivated within 5h (>2 or >3 log10 reductions at three positions, n=20) in the test sink where the ClO2 gel was placed. These small quantities of ClO2 gel might be a useful tool for reducing the risk of infection by norovirus in wet environments such as kitchens and bathrooms under optimal condition.
23 0 0 0 OA ボランタリーな行動に見いだされる贈与の可視化/不可視化
- 著者
- 富井 久義
- 出版者
- The Kantoh Sociological Society
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, no.25, pp.156-167, 2012-09-10 (Released:2015-06-12)
- 参考文献数
- 11
This paper examines how ASHINAGA movement defines the “Ongaeshi” relationship and how the ASHINAGA scholarship students recognize this focusing on how the actors deal with the concept of gift. ASHINAGA provides scholarships for orphans funded by contributions from private individuals. The students recipients conduct the street-corner fundraising campaigns. The thought of “Ongaeshi” is the key concept of ASHINAGA movement. It calls for a multilayered serial reciprocity among the contributor, the students, and their juniors (other orphans).However, some students conduct campaigns while avoiding defining this as “Ongaeshi” as a means of avoiding the burden associated with a gift. But in any case, since the students are conducting campaigns, the “Ongaeshi” relationship is still realized in the movement.
23 0 0 0 OA ネットワーク伝播による生物ネットワーク解析
- 著者
- 千代丸 勝美 竹本 和広
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会
- 雑誌
- JSBi Bioinformatics Review (ISSN:24357022)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.26-36, 2021 (Released:2021-04-23)
- 参考文献数
- 60
生物ネットワーク解析はバイオインフォマティクスやシステム生物学における重要なアプローチのひとつである。特に、ネットワーク医学の観点からは、疾病遺伝子や薬剤標的分子の推定のような優先順位づけや疾病モジュールの同定のようなネットワーククラスタリングなどが求められる。本総説では、そのような多様なネットワーク解析に有効なネットワーク伝播について紹介する。ネットワーク伝播は半教師あり学習手法の一種であり、既知のラベルをネットワーク上で伝播させることによって重要なノードや部分ネットワークを見つける。ネットワーク伝播は理論背景が平易であり、拡張性が高い。そのため様々な問題に適用することができる。また、解析結果の解釈性が高く、異質なデータへの適用も容易であるという利点も持つ。ここでは、いくつかの代表的な手法を題材にしながら、ネットワーク伝播の基礎から応用までを解説する。
23 0 0 0 OA 高用量ビタミンCの摂取は加齢に伴う胸腺の委縮を 抑制して免疫細胞数の維持に寄与する
- 著者
- 内尾 隆正 広瀬 義隆 室崎 伸二 山本 佳弘 石神 昭人
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.5.6, pp.352-354, 2017 (Released:2018-06-30)
23 0 0 0 OA 深層学習と人工物工学
- 著者
- 松尾 豊
- 出版者
- 横断型基幹科学技術研究団体連合(横幹連合)
- 雑誌
- 横幹連合コンファレンス予稿集 第10回横幹連合コンファレンス
- 巻号頁・発行日
- pp.F-5-2, 2019 (Released:2019-12-16)
This document describes several topics on research into artifact from the perspective of deep learning. We first introduce the high-dimensional science proposed by Maruyama. Then, we explain the current research on model-based and model-free reinforcement learning, its integration, and world models. Then we bring the discussion by Yoshikawa about the academic domains and design. All the discussion is based on how the phenomenon is models either by a large number of parameters, or a small number of parameters which human can understand. Finally we discuss how the large-parameter models can be used in our society.
23 0 0 0 OA フランス人には聞こえない舌打ち音 : 日仏対照言語学的観点から(研究論文)
- 著者
- 森田 美里
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.159-174, 2015-03-25 (Released:2017-03-30)
Cette etude a pour objectif de determiner la fonction d'un son produit avec la langue sur les points d'articulation alveolaire ou dental sans flux respiratoire, dans le discours de locuteurs francophones natifs. Le <<shitauchi>> pourrait se traduire litteralement par <<petit claquement de langue>>. Dans la communication entre Japonais et Francais, il est cause de malentendus et de quiproquos du fait qu'en japonais il marque principalement l'agacement. Neanmoins, il n'a jamais fait l'objet d'etude dans ce contexte car il est considere comme une simple emission buccale que, par ailleurs, les Francais ne percoivent pas. Nous avons sollicite des Francais pour l'execution de trois taches : d'abord, raconter un recit ; ensuite, indiquer un chemin ; enfin, observer des sequences televisuelles comme une interview d'artiste, un debat politique, etc. Ces recherches permettent de formuler trois hypotheses majeures : 1) en francais, il y a congruence entre le shitauchi et Les marques du travail de formulation (Candea 2000), 2) fonctionnellement, il s'agit d'attirer l'attention sur soi ou sur son propos, 3) les emplois concernent le traitement de l'information ou de l'expression, le changement de sujet ou de niveau du discours, l'amorcage de l'information, la prise de parole ou une manifestation de l'agacement du locuteur.
23 0 0 0 OA 齋藤慈子・平石界・久世濃子 編/監修者・長谷川眞理子『正解は一つじゃない 子育てする動物たち』一般財団法人 東京大学出版会 2019年10月刊 2600円(別税)(337ページ)
- 著者
- 水野 友有
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.80-81, 2020-12-20 (Released:2020-12-23)
23 0 0 0 OA 海底地すべりと災害 -これまでの研究成果と現状の問題点-
- 著者
- 川村 喜一郎 金松 敏也 山田 泰広
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.12, pp.999-1014, 2017-12-15 (Released:2018-03-28)
- 参考文献数
- 142
- 被引用文献数
- 2 6
本論では,海底地すべりの一般的な特徴,短期および長期の発生メカニズム,海底地すべりによる海洋ハザードについて概説する.海底地すべりは,その形状から,一般的に滑落ドメイン,移動ドメイン,末端ドメインの3つの領域に区画される.滑落ドメインでは開口亀裂,移動ドメインでは剪断変形に起因する非対称変形構造が見られる.末端ドメインでは,圧力隆起部によって特徴づけられる.滑り面は粘土層であると推測されるが,南海トラフで報告されているように非条件下では,砂層も滑り面となる可能性がある.短期的な発生メカニズムは,斜面における荷重の急激な増加や間隙水圧の急激な上昇など,地震に最も関連している.長期的な発生メカニズムは,気候変動によるメタンハイドレートの分解とそれに伴う間隙水圧の増加,長期的な間隙水圧の増加,海山の沈み込み/衝突による地盤の変形,火山活動による斜面勾配の急斜化などがある.
23 0 0 0 OA 三宅島でのウツボ類の産卵行動
- 著者
- Jack T. Moyer Martha J. Zaiser
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.466-468, 1982-02-27 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 4
1980年8月15日16時30分, 三宅島の水深12mの地点で全長約90cmの2尾のウツボGymnotborax kidakaが産卵しているのを観察した.両者は尾部をゆるくからませていたが, 突然腹部を押しつけ合ってから離れた.その瞬間精子による水の白濁が観察された.卵は直径約2mmの丸い浮性卵で, 親魚による卵の保護は観察されなかった.1980年7月29目19時30分には, 岸近くの水深2.5mの地点で, 全長約25cmのUropterygtus necturus4尾が群がって行動しているのを観察した.これは産卵直前の行動と思われた.