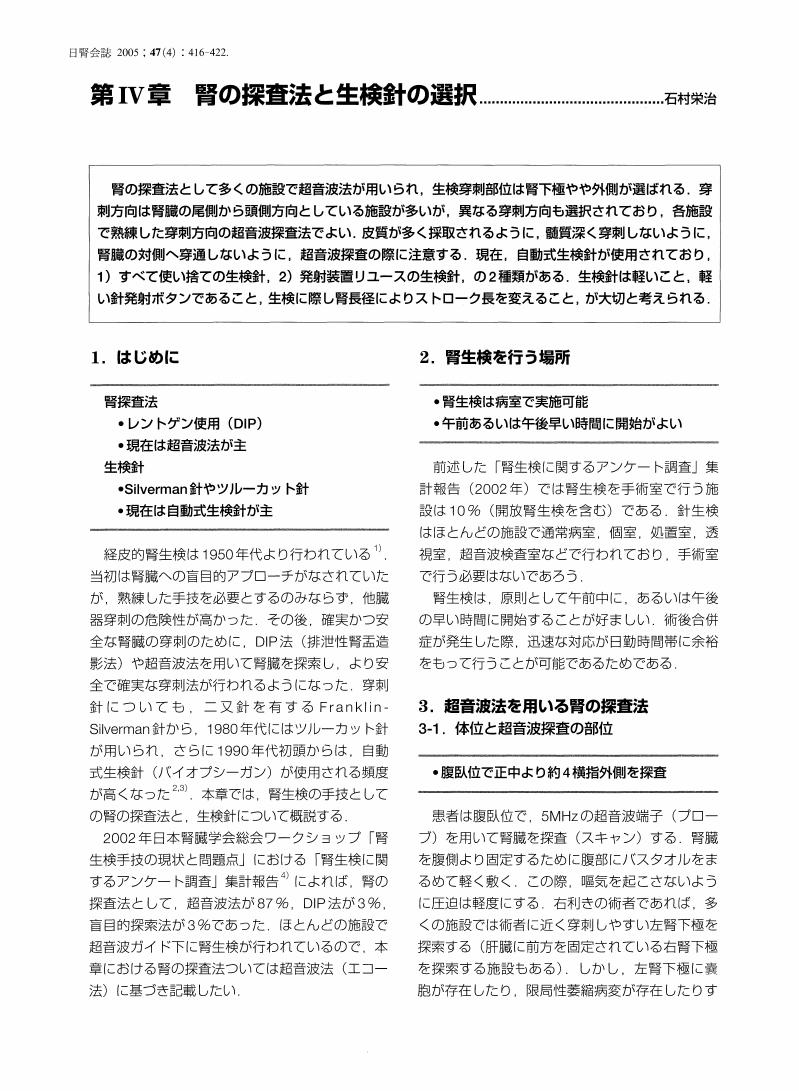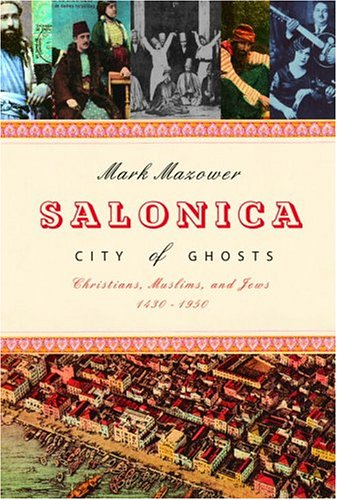1 0 0 0 IR 日本民謡の地域性研究に向けての試論--日本民謡の日本海側と瀬戸内海側
- 著者
- 小島 美子
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.p375-388, 1991-11
日本民謡には,一般に西物と東物の違いがあるといわれているが,私は以前に山口県と秋田県の民謡を例として,『日本民謡大観』所載の民謡を分析し,音階や旋律法などいろいろな点でこの2つにはやはり大きな違いがあることを明らかにした。本稿では,県全体としては西物の特徴をもつ山口県の民謡を,さらに日本海側の長州地方,瀬戸内海側の周防地方に分けて同じ資料を集計し直し,日本海側と瀬戸内海側では違いがないかどうかを調べてみた。その場合,前論文でもっとも鮮やかな違いが現われた音階を本稿ではとり上げた。資料の多少や,民謡の種類による音階の偏りなど,偶然的要因を考慮しても,なお違いがはっきりしていたからである。その結果,長州では周防よりも民謡音階がかなり大きい割合を占めることがわかった。そのため日本海側に隣接する島根県と,瀬戸内海側に隣接する広島県の民謡の音階を分析してみた。その結果,島根県の民謡は圧倒的に民謡音階の世界であることが明らかになった。とくに島根県の東半分にあたる出雲では,秋田県を超えるほどの高い比率で民謡音階が現われた。これに対して広島県側では,民謡音階の曲が約半数あり,律音階系の曲(律音階とその変種,都節音階とその変種を含む)が残り半分を占めていた。やはり日本海側と瀬戸内海側では大きな差が現われたわけである。これらの結果をいささか飛躍して,音階が比較的変わり難い要素であることを考え,日本音楽の起源の問題にまで広げて考えてみると,民謡音階の民謡を歌っていた人々は,日本海側の地に入り,そのまま瀬戸内海側に進むのではなく,東に進んだ可能性も考えられるし,日本海側には継続的に民謡音階の刺激があった可能性なども考えられるのではないかと思われる。またこれらの音階分析の過程で,核音とテトラコルドの存在が不明確な例が約20曲現われた。このような形はこれまでもまったくなかったわけではないが,この場合のようにまとまって現われた例は珍しく,今後音階上の問題として検討する必要があるだろう。It is generally said that there are differences in Japanese folk songs between the western group and the eastern group. I have analyzed folk songs contained in the "Complete Collection of Japanese Folk songs", taking examples from the songs of Yamaguchi and Akita prefectures, and have clarified that there is a large difference between them in the scales and melodies.In this paper, I have classified the folk songs of Yamaguchi prefecture, which have the characteristics of the western group as a whole, into those of the Chōshū region on the Japan Sea side and those of the Suō region on the Inland Sea side. I then collected the statistics of the two groups again to determine whether there was any difference between them. For the purpose of this study, I used the scale which showed the most distinct characteristic in my previous paper. The scales showed clear distinctions even after considering accidental factors, such as the volume of materials, and imbalance of scales according to the types of folk songs.My results showed that the Minyō (folk song) scales accounted for a considerably larger part of the folk songs in the Chōshū region than the Suō region. I then analyzed the folk song of Shimane prefecture, adjacent to Yamaguchi prefecture on the Japan Sea side, and that of Hiroshima prefecture, adjacent on the Inland Sea side. The results showed that the Minyō scale is found in an overwhelmingly large part of the folk songs in Shimane prefecture. In particular, in the Izumo region, which corresponds to the eastern half of Shimane prefecture, the Minyō scales appeared with a very high ratio, almost exceeding that of Akita prefecture. On the other hand, in Hiroshima prefecture, the Minyō scales appeared in about half of the songs examined, and the Ritsu-type scales (including the Ritsu scale and its variations, and the Miyakobushi <capital city melody> scale and its variations) accounted for the remaining half. A large difference has been seen again between the Japan Sea side and the Inland Sea side.Considering that the scale is an element rather difficult to change, and admitting a certain extent of logic jumping with these results in considering the problem of the origin of Japanese music, the people who sang songs with the Minyō scale entered the country on the Japan Sea side, and instead of proceeding to the Inland Sea side, they possibly proceeded to the east. Or it is possible that there was a continuous flow of people who sang folk songs with the Minyō scale to the Japan Sea side.Also in the process of this analysis, I found that the existence of nuclear notes and tetracords was not clear in about 20 pieces. Such examples existed elsewhere, but it was rare for them to appeare in such a large number as in this case. This problem will require further discussion as to how it relates to the scales.
- 著者
- 村上 浩康 石原 舜三
- 出版者
- The Society of Resource Geology
- 雑誌
- 資源地質 (ISSN:09182454)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.V-VI, 2008
1 0 0 0 OA 腎生検ガイドブック: 第IV章 腎の探査法と生検針の選択
- 著者
- 石村 栄治
- 出版者
- 社団法人 日本腎臓学会
- 雑誌
- 日本腎臓学会誌 (ISSN:03852385)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.416-422, 2005-05-25 (Released:2010-05-18)
- 参考文献数
- 5
1 0 0 0 免疫学の新しい話題(IV)
- 著者
- 旭 正一
- 出版者
- 日本皮膚科学会西部支部
- 雑誌
- 西日本皮膚科
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.685-693, 1985
免疫反応は, 生体が「異物」と認識した「抗原」に対する排除反応であると考えられる。抗原の認識からはじまつて, 抗体や感作リンパ球の産生がおこり, この抗体やリンパ球が抗原と反応し, さらにいくつものメカニズムが作用して, 最終的には炎症反応などの生体反応がおこつてくる。この間に多くの反応段階があり, 複雑な経路をたどつて反応が進行してゆく。この各段階において, いろいろな活性物質が細胞から放出されたり, 細胞外でつくられたりする。これらの微量活性物質は, 反応を進行させたり, 抑制したり, 細胞間の情報伝達をおこなつたり, 組織反応をおこしたりする。免疫学の研究がすすむにつれて, 新しい生体物質や活性因子が次々と報告され, ぼう大な数に達している。免疫学を理解するには, このうちのおもなのだけでも理解しておく必要があるが, あまりにも数が多くて, それぞれ長い名前がついており, BCGFだのMAFだのIFNだのといつたまぎらわしい略語が続出するために, 免疫の話が敬遠される大きな理由になつているように思われる。今回は, これらの物質のうちからリンフォカインをとりあげる。このような微量活性物質は, その機能(活性)が分つているだけで, 物質的性状は分らないものが大部分であり, 統一的に分りやすく解説するなどということは望むべくもないが, 本稿では, その存在が確実にみとめられ, 解析がすすんでいるものを重点的に解説した。
1 0 0 0 経絡・経穴の解剖学的並びに臨床的検討
- 著者
- 山田 鑑照 尾崎 朋文 松岡 憲二 坂口 俊二 王 財源 森川 和宥 森 俊豪 吉田 篤 北村 清一郎 米山 栄 谷口 和久
- 出版者
- 社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.27-56, 2006-02-01
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 2
経穴研究委員会 (前経穴委員会) は福岡で開催された第54回全日本鍼灸学会学術大会ワークショップIIにおいて、経絡・経穴について3つの検討テーマを6名の委員により報告した。<BR>第1テーマ : 経絡・経穴の解剖学的検討<BR>1) 経絡と類似走行を示す解剖構造について (松岡憲二) : 遺体解剖による経絡の走行と神経・血管の走行との類似性についての研究。<BR>2) 上肢経絡・経穴の肉眼解剖学的研究 (山田鑑照) : 豊田勝良元名古屋市立大学医学部研究員の学位研究である上肢経絡・経穴の解剖学的研究紹介並びに山田の研究として皮下における皮神経・血管の走行と経穴・経絡との関係についての報告。<BR>第2テーマ : 日中における刺鍼安全深度の研究<BR>1) 中国における刺鍼安全深度の研究と進展状況 (王財源) : 中国刺鍼安全深度研究で権威のある上海中医薬大学解剖学教室厳振国教授のデータの紹介と最近の中国における刺鍼安全深度研究の進展状況報告。<BR>2) 経穴の刺鍼安全深度の研究を顧みて (尾崎朋文) : 尾崎が今まで発表してきた経穴部位の刺鍼安全深度の研究並びに厳振国教授のデータと同じ経穴との比較研究。<BR>第3テーマ : 少数経穴の臨床効果の検討<BR>1) 少数穴使用による鍼灸の臨床効果 (坂口俊二) : 1~4穴使用による鍼灸臨床効果ついての医学中央雑誌文献の検索・分析。<BR>2) 合谷-穴への各種鍼刺激が皮膚通電電流量に及ぼす影響 (森川和宥) : 合谷穴-穴への置鍼刺激、直流電気鍼刺激、鍼通電刺激が皮膚通電電流量に及ぼす影響についての研究。
- 著者
- 遠藤 耕太郎
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.6, pp.82, 1998-06-10 (Released:2017-08-01)
1 0 0 0 IR フランス会社法における業務執行鑑定人制度--会社経営者の専横に対する法規制
- 著者
- 清弘 正子
- 出版者
- 大阪大学大学院国際公共政策研究科
- 雑誌
- 国際公共政策研究 (ISSN:13428101)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.157-168, 1998-03
1 0 0 0 OA 医学部における入学者選抜方法と入学後の経過について-山口大学における追跡調査から
- 著者
- 原田 規章 中本 稔
- 出版者
- 日本医学教育学会
- 雑誌
- 医学教育 (ISSN:03869644)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.167-171, 1997-06-25 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 5
医学部入学者318名を対象に, 入試における面接評価点と留年・退学, 医師国家試験 (以下, 国試) 合否との関連を検討した.一般入試では面接評価の低い者に留年の発生率が高いことが明らかに認められ, とくに面接評価点が11点以下では12点以上の学生に比べて学生あたりの平均留年年数が3倍以上であった. これは現役入学生に限定しても同様であった. 推薦入試では面接評価と留年・退学, 国試合否との関係は明確でなかった. これには選抜効果を考慮する必要がある. また, 留年経験者は国試不合格率が明らかに高いことが認められた. 今後, 面接方法の改善をはかるとともに一般入試においても面接評価をより積極的に取り上げる必要があると考える.
- 著者
- 丹生 越子 E653 Collaboration
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, 1994
1 0 0 0 OA 降雨を模擬するための装置
- 著者
- 山崎 和彦 橘田 萌 前田 亜紀子 ヤマサキ カズヒコ キッタ モエ マエダ アキコ Kazuhiko Yamasaki Moe Kitta Akiko Maeda
- 雑誌
- 実践女子大学生活科学部紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.107-110, 2010-03-19
1 0 0 0 IR Measurement of the Lifetimes of Charged and Neutral Beauty Hadrons : Particles and Fields
- 著者
- FermilabE653Collaboration USHIDA N. MOKHTARANI A. PAOLONE V.S. VOLK J.T. WILCOX J.O. YAGER P.M. EDELSTEIN R.M. FREYBERGER A.P. GIBAUT D.B. LIPTON R.J. NICHOLS W.R. POTTER D.M. RUSS J.S. ZHANG C. ZHANG Y. JANG H.I. KIM J.Y. KIM T.I. LIM I.T. PAC M.Y. BALLER B.R. STEFANSKI R.J. NAKAZAWA K. CHUNG K.S. CHUNG S.H. KIM D.C. PARK I.G. PARK M.S. SONG J.S. YOON C.S. CHIKAWA M. ABE T. FUJII T. FUJIOKA G. FUJIWARA K. FUKUSHIMA H. HARA T. TAKAHASHI Y. TARUMA K. TSUZUKI Y. YOKOYAMA C. CHANG S.D. CHEON B.G. CHO J.H. KANG J.S. KIM C.O. KIM K.Y. KIM T.Y. LEE J.C. LEE S.B. LIM G.Y. NAM S.W. SHIN T.S. SIM K.S. WOO J.K. ISOKANE Y. TSUNEOKA Y. AOKI S. GAUTHIER A. HOSHINO K. KITAMURA H. KOBAYASHI M. MIYANISHI M. NAKAMURA K. NAKAMURA M. NAKAMURA Y. NAKANISHI S. NIU K. NIWA K. NOMURA M. TAJIMA H. YOSHDA S. ARYAL M. DUNLEA J.M. FREDERIKSEN S.G. KURAMATA S. LUNDBERG B.G. OLEYNIK G.A. REAY N.W. REIBEL K. SIDWELL R.A. STANTON N.R. MORIYAMA K. SHIBATA H. KALBFLEISCH G.R. SKUBIC P. SNOW J.M. WILLIS S.E. KUSUMOTO O. NAKAMURA K. OKUSAWA T. TERANAKA M. TOMINAGA T. YOSHIDA T. YUUKI H. OKABE H. YOKOTA J. ADACHI M. KAZUNO M. NIU E. SHIBUYA H. WATANABE S. OHTSUKA I. SATO Y. TEZUKA I. BAHK S.Y. KIM S.K. Aichi University of Education Aichi University of Education University of California (Davis) University of California (Davis) University of California (Davis) University of California (Davis) University of California (Davis) Carnegie-Mellon University Carnegie-Mellon University Carnegie-Mellon University Carnegie-Mellon University Carnegie-Mellon University Carnegie-Mellon University Carnegie-Mellon University Carnegie-Mellon University Carnegie-Mellon University Chonnam National University Chonnam National University Chonnam National University Chonnam National University Chonnam National University Fermi National Accelerator Laboratory Fermi National Accelerator Laboratory Gifu University Gyeongsang National University Gyeongsang National University Gyeongsang National University Gyeongsang National University Gyeongsang National University Gyeongsang National University Gyeongsang National University Kinki University Kobe University Kobe University Kobe University Kobe University Kobe University Kobe University Kobe University Kobe University Kobe University Kobe University Korea University Korea University Korea University Korea University Korea University Korea University Korea University Korea University Korea University Korea University Korea University Korea University Korea University Korea University Nagoya Institute of Technology Nagoya Institute of Technology Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University Nagoya University The Ohio State University The Ohio State University The Ohio State University The Ohio State University The Ohio State University The Ohio State University The Ohio State University The Ohio State University The Ohio State University The Ohio State University Okayama University Okayama University University of Oklahoma University of Oklahoma University of Oklahoma University of Oklahoma Osaka City University Osaka City University Osaka City University Osaka City University Osaka City University Osaka City University Osaka City University Science Education Institute of Osaka Prefecture Science Education Institute of Osaka Prefecture Toho University Toho University Toho University Toho University Toho University Utsunomiya University Utsunomiya University Utsunomiya University Wonkwang University Wonkwang University
- 出版者
- Published for the Research Institute for Fundamental Physics by Physical Society of Japan
- 雑誌
- Progress of theoretical physics = Progress of theoretical physics (ISSN:0033068X)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.3, pp.679-696, 1993-03-25
- 被引用文献数
- 3
We report on the characteristics of 9 bb^^- pair events produced by a 600 GeV/c π^- beam and detected in the hybrid emulsion spectrometer of Fermilab experiment E653. The measured lifetimes for samples of 12 neutral and 6 charged beauty hadrons are τ_<b^0>=0.81^<+0.34+0.08'>_<-0.22-0.02> ps, and τ_<b^±>=3.84^<+2.73+0.80>_<-1.36-0.16> ps.
- 著者
- Kavanagh Barry
- 雑誌
- 青森県立保健大学雑誌 = Journal of Aomori University of Health and Welfare (ISSN:13493272)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.283-292, 2007-12
Contrastive analysis is the systematic study of the linguistic systems of two languages with a view to identifying their structural differences and similarities. Examining the phonetic inventories of the languages of Japanese and English this paper will first define and give descriptions of the phonemes of the two languages highlighting how this contrastive analysis may bring benefits or otherwise within the EFL classroom.
1 0 0 0 いじめ予防のための心のワクチンプログラムの開発
いじめ予防プログラムの基盤となる「ポジティビティ・フォーカスト・アプローチ」について、前年度の理論研究を踏まえて、実際のカウンセリング場面、心理教育場面に利用できるように手続きや方法論を明確にする作業を行った。ポジティブ心理学の中でも肯定的感情側面に焦点を当てたB.Fedricksonらの研究成果を基盤に、対人コミュニケーション場面において、自身の肯定的感情が、認知的枠組みを拡大・再構築していくというプロセスを、教育プログラムとして実行できるように調整している。最初は、カウンセラーとクライエントという特殊な2者関係、つまりカウンセリングの一場面でこのプログラムを想定し、そこでパイロットスタディを踏まえて、集団場面、教育場面での応用が可能な形にブラッシュアップを図っていった。プログラムは大きく分けて2つのフェーズから構成され、1.ポジティブ感情喚起フェーズ、2.認知再構築フェーズの2段階に分けられる。それぞれのフェーズでは、一定のタスクが参加者に課される。例えば、1.のフェーズでは、過去の失敗経験と成功経験を同時に想起してもらい、成功経験のみについてその後詳細に事実を説明してもらう。このような作業を行うと、次いで思い出してもらった失敗経験の記憶が想起しずらくなる、価値が低下するなどの効果が見込める(検索誘導性忘却という現象を利用したトレーニング)。また、これと並行して、ここまでの研究成果を学会発表という形で公表し、他の研究者からプログラム実施に関して様々な意見をいただき、ブラッシュアップを図った。遂行過程で大幅な改変の必要性や手続きの補強、倫理的配慮をご指摘いただき、考慮に入れることとなったため、年度内で予定していた実際に施行するプログラム開発まで至ることは難しかった。なお、この遅れについては、年度をまたいで、次年度の計画施行スピードを調整することでも解消可能と考える。
- 著者
- Mark Mazower
- 出版者
- Alfred A. Knopf
- 巻号頁・発行日
- 2005
1 0 0 0 OA サンドイッチ法による雑草および薬用植物のアレロパシー活性の検索
- 著者
- 猪谷 富雄 平井 健一郎 藤井 義晴 神田 博史 玉置 雅彦
- 出版者
- 日本雑草学会
- 雑誌
- 雑草研究 (ISSN:0372798X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.258-266, 1998-10-30 (Released:2009-12-17)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3 7
サンドイッチ法は寒天培地中に包埋した供試植物の乾燥葉から浸出する物質のアレロパシー活性を, 寒天培地上に播種した検定植物の種子根等の伸長抑制程度から判定する方法である。この方法によって, 広島県立大学キャンパスおよび広島大学医学部薬用植物園内で採取した雑草・薬用植物計152種のレタスに対するアレロパシー活性を検定した。その結果, カタバミ, ヒメスイバ, イシミカワ, ヤブラン, メギ, ショウジョウバカマがレタス根長の伸長程度 (対照区比) 10~20%と強いアレロパシー活性を示した。上記のような強いアレロパシー活性の認められたもの23種を供試植物とし, 検定植物としてレタスの他にアカクローバー, キュウリおよびイネの4種を用い, サンドイッチ法によって供試植物のアレロパシー活性を検討した。得られたデータの主成分分析の結果, 50%の寄与率を持つ第1主成分は4種の検定植物が共通して示すアレロパシーに対する感受性を表し, かつ検定植物中レタスで最も高い第1主成分の因子負荷量が得られた。これより, サンドイッチ法の検定植物として従来用いられているレタスが適当であることが示唆された。また, 26%の寄与率をもつ第2主成分は, 検定植物のレタス・アカクローバーとキュウリ・イネとで同一物質に対して異なる感受性の方向を示すと考えられた。このことから検定植物間で選択性をもつアレロパシー物質の存在が推定された。
1 0 0 0 進行性腎不全の治療成績:-60例についての交差法による検討-
- 著者
- 椎貝 達夫 桑名 仁 神田 英一郎 前田 益孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日農医学術総会抄録集 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.114, 2005
<B>目的</B>:進行性腎不全(PRF)の治療は世界の腎不全対策を考えるとき、きわめて重要である。前医での腎不全進行速度がわかっているPRF60例について治療成績をまとめた。<BR><B>方法</B>:対象は前医での進行速度がScrの経時的変化からわかっている60例のPRFで、男42人、女18人、年齢58.2±14.7歳、原疾患は多発性のう胞腎以外の非糖尿病性腎症(NDN)57例、糖尿病性腎症3例である。<BR> 当院診療開始時のScr3.60±1.80mg/dl、Ccr26.3±16.0ml/minで、前医と当院での進行速度をScr<SUP>-1</SUP>・時間(月)勾配で求め比較した。当院の診療は24時間蓄尿による食事内容モニタリング、各種データの腎臓病手帳への記入・説明、家庭血圧測定によりプログラム化されている。<BR><B>結果</B>:図は60例のPRFの当院受診前と受診後の速度のちがいを示している。一番左は前に較べて進行速度が80%以上遅くなったグループで、31人(51.7%)がこのグループに属した。中央は進行速度の減少が前に較べて79%未満に止まったグループで、21人(35%)だった。一番右は当院受診後進行速度が前よりかえって速くなったグループで8人(13.3%)だった。<BR> 全体として、前医での治療が続けられていた場合、透析導入まで平均78.2か月を要するが、当院での治療で187.0か月となり、腎臓の寿命が2.4倍延長される。<BR><B>結論</B>:60例のPRFを対象とした交差法による検討で、従来の治療に比べ、腎臓寿命が全体として2.4倍延長された。今後当院が行っている治療法の全国への普及が必要である。
1 0 0 0 OA 空気抵抗をうける放物体の運動
- 著者
- 村田 浩 阿部 邦昭 立川 法清
- 出版者
- 日本歯科大学
- 雑誌
- 日本歯科大学紀要. 一般教育系 = Bulletin of Nippon Dental University. General education (ISSN:03851605)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.25-30, 1986-03-25
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ネットビジネス (ISSN:13450328)
- 巻号頁・発行日
- no.62, pp.94-98, 2000-09
「BSデジタル放送でテレビとネットビジネスの融合が始まる。今こそ投資するべきと決断した」——。大手レコード会社エイベックスのネット事業子会社、エイベックスネットワークの上田正勝取締役は話す。 エイベックスは毎日新聞社などが設立したメガポート放送に資本参加、2000年12月のBSデジタル放送開始に合わせて双方向型の音楽プロモーション番組を始める。
1 0 0 0 OA 算術科の教育測定
- 著者
- 大阪市小学校共同研究会 編
- 出版者
- 隆文堂
- 巻号頁・発行日
- 1934