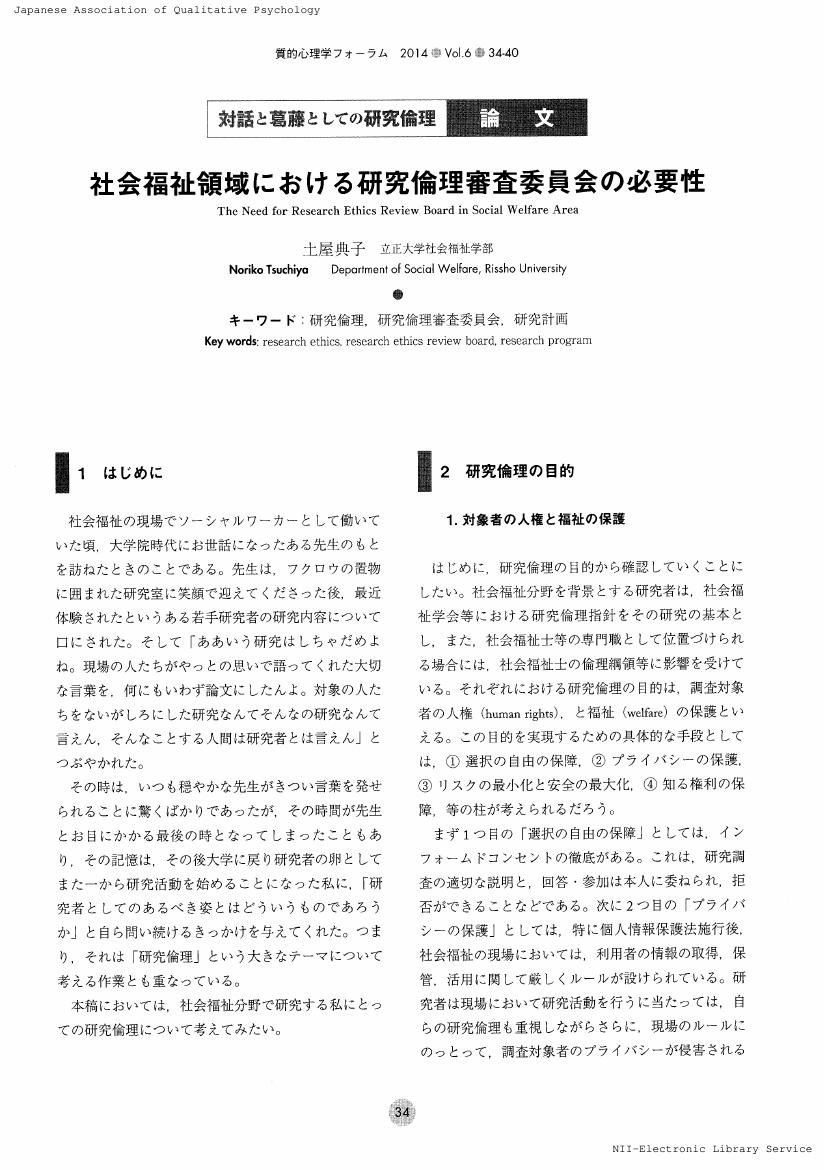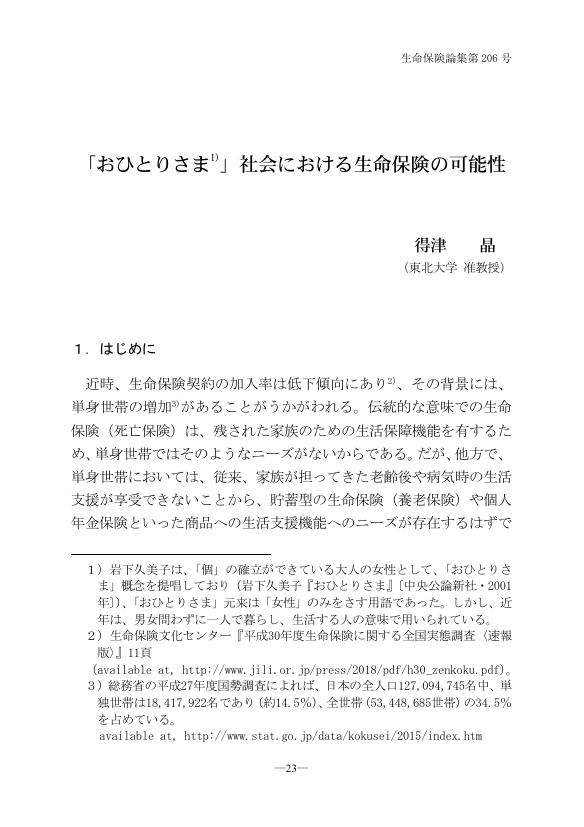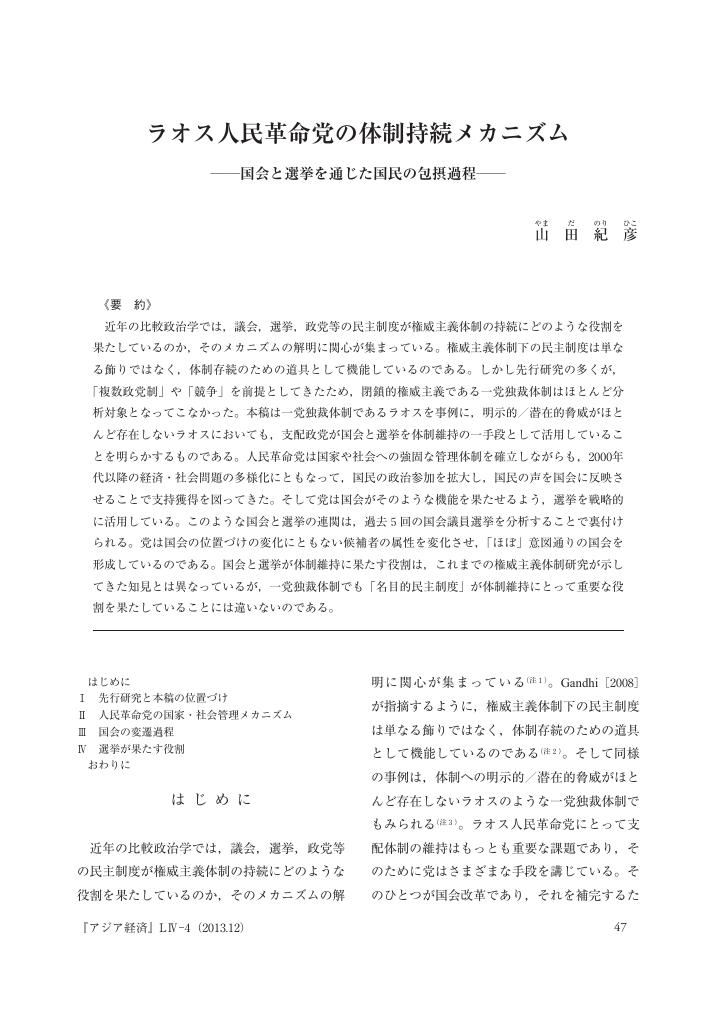2 0 0 0 OA P2-10 関係妄想的認知の生起メカニズム : 情報補完モデルの検討(ポスター発表)
- 著者
- 津田 恭充
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- 日本パーソナリティ心理学会発表論文集 17 (ISSN:24332992)
- 巻号頁・発行日
- pp.106-107, 2008-11-15 (Released:2017-09-01)
2 0 0 0 OA 在来線特急のトンネル突入による圧力波の形成と伝播に関する小型モデル実験
- 著者
- 前野 一夫 太田 匡則 大村 一弥 遠藤 洋一
- 出版者
- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」
- 雑誌
- 理論応用力学講演会 講演論文集 第58回理論応用力学講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.96, 2009 (Released:2009-10-22)
近年の車両性能の向上による在来線の高速化に伴い,トンネル圧力波の問題が報告されている在来線特急の走行速度(130~160km/h)に着目し,車両図面を基に2種類の実験用の軸対称模型を製作し,高圧ガスにより加速走行される小型模型実験装置を用い,列車模型をトンネル模型に突入させる実験を行った.列車模型がトンネルに突入した際のトンネル内の圧力波変動を計測し,圧力波の形成と伝播の様子を捉え,圧力変化・圧力勾配の比較を行う.また,トンネル模型中間部に駅模型を設置した際のトンネル内の圧力波変動を計測し,トンネル断面積の変化が圧力波の伝播に及ぼす影響について調べた.
2 0 0 0 抗U3 RNP抗体陽性全身性強皮症8例の臨床的特徴について
- 著者
- 濱口 儒人 藤本 学 長谷川 稔 小村 一浩 松下 貴史 加治 賢三 植田 郁子 竹原 和彦 佐藤 伸一 桑名 正隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.9, pp.1837-1843, 2009-08-20 (Released:2014-11-28)
抗U3RNP抗体は代表的な抗核小体型抗体の1つであり,全身性強皮症に特異的とされる.今回われわれは,金沢大学皮膚科で経験した抗U3 RNP抗体陽性全身性強皮症(systemic sclerosis:SSc)8例(女性6例,男性2例,発症時の平均年齢44歳)における臨床症状,治療,予後について検討した.病型分類ではdiffuse SSc(dSSc)が4例,limited SSc(lSSc)が4例だった.全例でレイノー症状を認め,指尖陥凹性瘢痕,手指の屈曲拘縮,びまん性の色素沈着を伴う例が多く,dSScでみられる皮膚症状を高率に有していた.一方,内臓病変に関しては,1例で強皮症腎を発症したものの,肺線維症や肺高血圧症,心病変など重篤な臓器病変を有する頻度は低かった.6例で皮膚硬化に対し中等量のプレドニゾロンが投与され,皮膚硬化の改善がみられた.観察期間中に死亡した症例はなかった.欧米では,抗U3 RNP抗体陽性SScはdSScの頻度が高く,肺線維症や肺高血圧症,心筋線維化による不整脈や心不全,強皮症腎などの重篤な臓器病変を有することが多いと報告されている.また,その予後は抗トポイソメラーゼI抗体陽性SScと同等で,予後不良例が少なくないことが知られている.したがって,本邦における抗U3 RNP抗体SScは欧米の症例と比較し,皮膚症状は類似しているものの臓器病変は軽症であると考えられた.しかし,抗Jo-1抗体陽性の抗ARS症候群を合併した症例や強皮症腎を生じた症例もあり,抗U3 RNP抗体SScの臨床的特徴についてさらに多数例での検討が必要と考えられた.
2 0 0 0 OA 明治前期の法と初生子相続 栃木県の一農村・冬室を中心として
- 著者
- 前田 卓
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1-2, pp.180-207, 1971-10-31 (Released:2017-12-09)
2 0 0 0 OA 特集論文 社会福祉領域における研究倫理審査委員会の必要性
- 著者
- 土屋 典子
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.34-40, 2014 (Released:2020-03-11)
2 0 0 0 OA ニホンヤマネにおける繁殖巣の巣材・構造および繁殖事例の報告
- 著者
- 湊 秋作
- 出版者
- 日本環境動物昆虫学会
- 雑誌
- 環動昆 (ISSN:09154698)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.1-7, 2016 (Released:2016-10-25)
2 0 0 0 OA 神戸市における阪神・淡路大震災復興公営住宅の立地展開
- 著者
- 本岡 拓哉
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.6, pp.633-648, 2004-12-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 1 1
The Hanshin-Awaji Great Earthquake (17 January 1995) caused a lot of damage to Kobe's housing stock (mainly wooden rental houses, for example, wooden apartments and row houses), especially in the inner city area. Against the background of providing a safety net for many people who lost their homes, Kobe City and Hyogo Prefecture provided about 26, 000 recovery public housing units. In this paper, the author aims to clarify the locational process and the background of the Hanshin-Awaji Great Earthquake Recovery Public Housing (HAERPH) project provided in Kobe City. In particular, the author focuses on how Kobe City and Hyogo Prefecture were able to supply HAERPH in the built-up area according to the needs of the victims.There are three methods of supplying HAERPH. The first is direct supply by local government, in this case Kobe City and Hyogo Prefecture. The second is based on local government supplying public housing which is leased from the Urban Development Corporation (UDC). The last method is that local government supplies public housing which is leased from the private sector and which is made possible by the Public Housing Act revision of 1996. This paper shows that each method succeeded in supplying HAERPH in the built-up areas in different ways.Direct supply by the local government, particularly in Kobe City, was applied by using existing techniques of site acquisition of new construction areas, of rebuilding public housing, and of coordinating housing supply together with the urban redevelopment project.The UDC launched its own project team for site acquisition for housing, and coordinated it with Kobe City and the Kobe City housing supply corporations. They were able to provide some housing in the inner city. Kobe City and Hyogo Prefecture leased some of these houses from the UDC.All private houses leased by Kobe City are located in the built-up area. This is because Kobe City had set particular leasing standards towards private owners. These particular standards state that those private houses should be located near a train station in the built-up areas, especially in the west central area.
2 0 0 0 OA キノコ摂取によるアマニタトキシン中毒の1例
- 著者
- 森下 啓明 坂本 英里子 保浦 晃徳 石崎 誠二 月山 克史 近藤 国和 玉井 宏史 山本 昌弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第55回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.120, 2006 (Released:2006-11-06)
<症例> 61歳男性、既往歴に脳梗塞がある。アレルギー歴なし。 平成17年10月29日昼頃、自宅近くの山林で採取した白色のキノコ約20本を調理して摂取した。同日20時頃より腹痛、嘔気、嘔吐、下痢等の消化器症状が出現したが自宅で経過観察していた。10月31日には経口摂取不能となったため、当院救急外来を受診。受診時は意識清明、バイタルサインに大きな異常はなく、神経学的異常所見も認めなかった。しかし、血液検査に於いて肝機能障害、腎機能障害を認めたことからキノコ中毒を疑い緊急入院となった。 患者の持参したキノコの特徴および、経過(消化器症状に続発する肝機能障害)よりドクツルタケ(アマニタトキシン)中毒を疑い、日本中毒センターに問い合わせを行った上で治療を開始した。補液、活性炭投与(25g/回、6回/日、2日間)、血液還流療法(2日間)、ペニシリンG大量投与(1800万単位/日、2日間)を施行し、肝機能障害は改善傾向、第26病日には正常化した。また、第7病日より急性膵炎を発症したが、メシル酸ガベキサート投与などを行い第28病日には改善したため、平成17年12月26日退院となった。 入院時に採取した血液、尿および持参したキノコは日本中毒センターに送付し、分析を依頼している。<考察> ドクツルタケ、タマゴテングタケなどに含まれるアマニタトキシンは、ヒトにおいては約0.1mg/kgが致死量とされており、日本におけるキノコ中毒の中で最も致死率の高いものである。急性胃腸症状とそれに続発する肝機能障害が典型的な経過であり、肝不全が死因となる。本例は典型的な臨床経過よりアマニタトキシン中毒と診断したが、ドクツルタケでは1から2本で致死量となることから、今回摂取したキノコは比較的アマニタトキシン含有量の少ない種類であったものと推測された。治療法としては腸肝循環するアマニタトキシンを活性炭により除去すること及び対症療法が中心となり、解毒薬として確立されたものはない。血液還流療法が有効とする報告もあるが、未だに確固たる証拠はない。ペニシリンG大量投与によってアマニタトキシンの肝細胞への取り込みが阻害されることが動物実験によって確認されているが、臨床における有効性は確立されていない。その他、シリマリン、シメチジン、アスコルビン酸、N-アセチルシステイン等が使用されることもあるが、いずれの有効性も未確立である。 本例では活性炭投与、血液還流療法、ペニシリンG大量投与を行い、肝機能障害を残すことなく生存退院に至った
- 著者
- 西澤 忠志
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.32-48, 2022 (Released:2023-10-15)
日本において西洋音楽は、明治時代(1868-1912)から本格的に受容され始めた。当初、教育やナショナリズムの涵養に資するものと見なされた西洋音楽は、明治20 年後半から学生や学者といった知識人によって「芸術」と見なされた。その中でも、文芸評論家として知られる上田敏は、学生時代に日本で初めて演奏批評を文芸雑誌に掲載した。 本論文は、日本において西洋音楽が芸術として評価された過程と、その思想的・社会的背景を、上田敏が演奏批評で使用した評価基準である「エキスプレッション」の意味を分析することで明らかにする。 まず、本論文は上田が演奏批評で使用した「エキスプレッション」の意味について検討する。「エキスプレッション」の重要性は、既に上田が演奏批評を発表する前に、精神や感情を表現する語として、洋書を通じて日本の音楽界に紹介されていた。上田はこれを、初めて演奏の評価基準として使用した。次に本論文は、上田が「エキスプレッション」を演奏批評で使用した思想的・社会的背景を検討する。上田は、音楽において具現化された精神と感情を強調した、ショーペンハウアーに代表される19世紀のヨーロッパにおける芸術観を特に高く評価した。彼はまた音楽を、主に女性と子供のための娯楽と見なす既存の音楽観とは異なる、「青年」層の情熱を表現する芸術であることを示そうとした。 以上の特徴を持つ上田の演奏批評は、限定されていた日本の音楽観に対して新たな視点を示すこととなった。そして、彼の音楽批評は、日本における洗練された文化としての西洋音楽の普及を助けることとなった。
2 0 0 0 OA 日本企業の取締役兼任ネットワークにおけるリスク指標の同類性の検証
- 著者
- 森田 啓介 黒木 裕鷹
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.FIN-031, pp.156-162, 2023-10-10 (Released:2023-10-12)
企業のガバナンスは経営の透明性やステークホルダーからの信頼と大きく関連する.コーポレートガバナンス・コードが,独立社外取締役の知見に基づいた助言に期待して,その選任を推奨する中で,一人の個人が複数企業の取締役および社外取締役を兼任するケースがある.取締役兼任ネットワークを分析した先行研究の多くは,ネットワーク中心性と企業の業績や情報開示の相関分析に焦点を当てている.しかし,同じ人物による異なる取締役会への参画によって,その人物の知見やノウハウが共有・伝播されるとすれば,接続の同類性やクラスター構造をはじめ,より複雑なネットワーク構造を捉えた分析が重要である.また,ネットワークデータを直接扱う機械学習技術の開発が進んできていることからも,兼任ネットワークにおいて,こうした豊富なネットワーク情報を考慮する意義を見定めることが必要である.本稿では,日本における兼任ネットワークの最近の動向を調査するとともに,条件付き一様グラフ検定と指数ランダムグラフモデル(ERGM)を適用し,ガバナンスとの関連が知られる諸指標の同類性(assortativity)を検証する.結果として,ベータや残差リスクは同類性をもつことがわかり,取締役の兼任によって企業間で知見が共有されている可能性が示唆された.取締役兼任ネットワークのもつ豊富な情報を活用して,ガバナンス構造の分析・予測を行う余地があると考えられる.
2 0 0 0 OA レンタルレコードにおける貸与権とレンタル禁止期間
- 著者
- 大場 博幸
- 出版者
- THE SOCIETY FOR EDUCATIONAL RESEARCH OF NIHON UNIVERSITY
- 雑誌
- 教育學雑誌 (ISSN:02884038)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.1-16, 2020-03-25 (Released:2021-04-09)
- 参考文献数
- 27
- 著者
- Motoyasu Otani Kosuke Kitayama Hiroki Ishikuro Jun-ichiro Hattan Takashi Maoka Hisashi Harada Yuko Shiotani Akane Eguchi Eiji Nitasaka Norihiko Misawa
- 出版者
- Japanese Society for Plant Biotechnology
- 雑誌
- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.219-226, 2021-06-25 (Released:2021-06-25)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 2
Ipomoea obscura, small white morning glory, is an ornamental plant belonging to the family Convolvulaceae, and cultivated worldwide. I. obscura generates white petals including a pale-yellow colored star-shaped center (flower vein). Its fully opened flowers were known to accumulate trace amounts of carotenoids such as β-carotene. In the present study, the embryogenic calli of I. obscura, were successfully produced through its immature embryo culture, and co-cultured with Agrobacterium tumefaciens carrying the β-carotene 4,4′-ketolase (crtW) and β-carotene 3,3′-hydroxylase (crtZ) genes for astaxanthin biosynthesis in addition to the isopentenyl diphosphate isomerase (idi) and hygromycin resistance genes. Transgenic plants, in which these four genes were introduced, were regenerated from the infected calli. They generated bronze (reddish green) leaves and novel petals that exhibited a color change from pale-yellow to pale-orange in the star-shaped center part. Especially, the color of their withered leaves changed drastically. HPLC-PDA-MS analysis showed that the expanded leaves of a transgenic line (T0) produced astaxanthin (5.2% of total carotenoids), adonirubin (3.9%), canthaxanthin (3.8%), and 3-hydroxyechinenone (3.6%), which indicated that these ketocarotenoids corresponded to 16.5% of the total carotenoids produced there (530 µg g−1 fresh weight). Furthermore, the altered traits of the transgenic plants were found to be inherited to their progenies by self-crossing.
2 0 0 0 OA 山口瑞穂著『近現代日本とエホバの証人――その歴史的展開――』
- 著者
- 中西 尋子
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.3, pp.126-132, 2022-12-30 (Released:2023-03-30)
2 0 0 0 OA 「おひとりさま」社会における生命保険の可能性
- 著者
- 得津 晶
- 出版者
- 公益財団法人 生命保険文化センター
- 雑誌
- 生命保険論集 (ISSN:13467190)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.206, pp.23-50, 2019-03-20 (Released:2022-03-18)
- 参考文献数
- 59
2 0 0 0 OA 原子力分野におけるマネジメントの基礎理論
- 著者
- 足立 文緒 関村 直人
- 出版者
- 特定非営利活動法人 横断型基幹科学技術研究団体連合
- 雑誌
- 横幹 (ISSN:18817610)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.13-28, 2021-06-15 (Released:2021-06-15)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
This paper tries to mark the beginning of developing a basic theory that people should understand to conduct management in nuclear sector. First, we make a hypothesis on conceptual level definition of what management in the nuclear sector is, and then, test the hypothesis by comparing it with the case of the ongoing management of decommissioning of Fukushima Daiichi nuclear power plant.
2 0 0 0 OA 農薬暴露と出生障害について
- 著者
- 永美 大志
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.681-697, 2009-01-30 (Released:2009-04-08)
- 参考文献数
- 76
農薬による慢性的人体影響は,神経・精神障害,臓器障害,発癌,出生障害,発達障害など多岐に渡る。今回筆者は,出生障害について,近年の内外の文献を収集し,総括した。 出生障害については,出生児欠損,流産,死産,早産,出生体格の低下,出生性比異常について近年の農業用農薬使用,住居近傍での農薬散布,住居内での農薬曝露,有機塩素農薬残留との関係を検討した報告が欧米を中心に多数あった。それぞれの影響について過半数の報告が関係を認めていた。出生時欠損については,全般について関係が認められた報告が多く,無脳症など特定の欠損についても報告があった。尿道下裂・停留精巣については,DDT類よりはむしろ,クロルデン類,農薬暴露全般との関係が認められていた。 一方,東南アジア,南アフリカで行なわれた,2つの地域における研究からは,農業農薬暴露と出生時欠損,流産との間に強い関係が見出されていた。熱帯・亜熱帯地域の発展途上国では,農薬用防護具の使用が,気候的にまた経済的に困難であり,農薬暴露が多いことも推察され,これらの知見を検証する疫学研究が求められる。同時に,低毒性農薬への移行,農薬暴露の低減のための施策,活動も求められよう。さらには,欧米でも都市部および農村部の低所得マイノリティーについて,有意な危険度がみられているようで,農薬による人体影響についても社会経済的な因子が重要と推測された。 残念ながら日本国内では疫学的研究が極めて少ないのが現状である。出生障害は,農薬のヒトへの影響の中でも重要な位置を占めると考えられ,農村医学会として取り組むべき課題の一つといえよう。また,東南アジア地域における農薬曝露と慢性影響の疫学調査,低毒性農薬への移行,農薬暴露を低減させる活動が推進されるために,日本農村医学会も貢献すべきであろう。
2 0 0 0 OA 修道院とビール
- 著者
- 村上 満
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.12, pp.869-873, 1984-12-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 7
ビール醸造の歴史を語るときに修道院の果した功績を忘れることは出来ない。近代的なビール醸造に携わる著者が, 中世のビール醸造に寄せる夢は男のロマンともいえよう。
2 0 0 0 OA 生き残った〈懸賞作家〉・芹沢光治良 ――『改造』懸賞創作と〈懸賞作家〉への考察――
- 著者
- 和泉 司
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.11, pp.13-23, 2013-11-10 (Released:2018-11-10)
総合誌『改造』が〈戦前〉に実施していた『改造』懸賞創作と、その当選者たちの当時の〈文壇〉及び現在の日本近代文学史上における存在意義を問い直すことを目的として、その当選者の一人である芹沢光治良に注目した。芹沢の〈作家〉デビューから〈文壇〉における立場を確立させるまでの過程から、〈戦前〉における〈文学懸賞〉とその当選者である〈懸賞作家〉たちの状況を考察し、〈文学懸賞〉である『改造』懸賞創作が現在の〈文学賞〉の発展の基礎となったことを指摘し、その研究の重要性を訴えた。
- 著者
- Ryosuke Sato Yasushi Matsuzawa Tomohiro Yoshii Eiichi Akiyama Masaaki Konishi Hidefumi Nakahashi Yugo Minamimoto Yuichiro Kimura Kozo Okada Nobuhiko Maejima Noriaki Iwahashi Masami Kosuge Toshiaki Ebina Kazuo Kimura Kouichi Tamura Kiyoshi Hibi
- 出版者
- Japan Atherosclerosis Society
- 雑誌
- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)
- 巻号頁・発行日
- pp.64368, (Released:2023-10-12)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 1
Aim: Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) level reduction is highly effective in preventing the occurrence of a cardiovascular event. Contrariwise, an inverse association exists between LDL-C levels and prognosis in some patients with cardiovascular diseases—the so-called “cholesterol paradox.” This study aimed to investigate whether the LDL-C level on admission affects the long-term prognosis in patients who develop acute coronary syndrome (ACS) and to examine factors associated with poor prognosis in patients with low LDL-C levels. Methods: We enrolled 410 statin-naïve patients with ACS, whom we divided into low- and high-LDL-C groups based on an admission LDL-C cut-off (obtained from the Youden index) of 122 mg/dL. Endothelial function was assessed using the reactive hyperemia index 1 week after statin initiation. The primary composite endpoint included all-cause death, as well as myocardial infarction and ischemic stroke occurrences. Results: During a median follow-up period of 6.1 years, 76 patients experienced the primary endpoint. Multivariate Cox regression analysis revealed that patients in the low LDL-C group had a 2.3-fold higher risk of experiencing the primary endpoint than those in the high LDL-C group (hazard ratio, 2.34; 95% confidence interval, 1.29-4.27; p=0.005). In the low LDL-C group, slow gait speed (frailty), elevated chronic-phase high-sensitivity C-reactive protein levels (chronic inflammation), and endothelial dysfunction were significantly associated with the primary endpoint. Conclusions: Patients with low LDL-C levels at admission due to ACS had a significantly worse long-term prognosis than those with high LDL-C levels; frailty, chronic inflammation, and endothelial dysfunction were poor prognostic factors.
2 0 0 0 OA ラオス人民革命党の体制持続メカニズム――国会と選挙を通じた国民の包摂過程――
- 著者
- 山田 紀彦
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア経済 (ISSN:00022942)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.47-84,202, 2013-12-15 (Released:2022-09-07)
- 被引用文献数
- 1