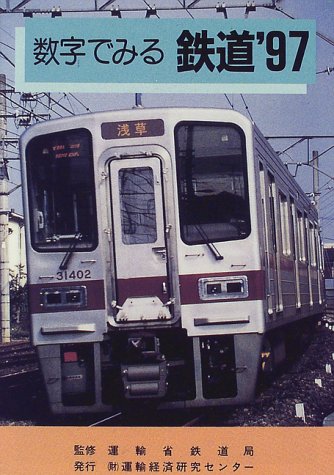1 0 0 0 OA 旧諸侯所用旗指物図 2巻
- 出版者
- 刊
- 巻号頁・発行日
- vol.[1],
1 0 0 0 数字でみる鉄道
- 出版者
- 運輸経済研究センター
- 巻号頁・発行日
- 1990
1 0 0 0 数字でみる鉄道
- 著者
- 運輸省大臣官房国有鉄道改革推進部 地域交通局 [監修]
- 出版者
- 運輸経済研究センター
- 巻号頁・発行日
- 1990
1 0 0 0 OA 瀬戸内海におけるマクロベントスの現存量と生産量
- 著者
- 辻野 睦
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- pp.17-00042, (Released:2018-03-09)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 5
瀬戸内海のマクロベントス生産量は0.19-11.2 g C/m2/yearで,水深が深く,泥分率の低い有機物量が少ない底質の海域で高い傾向があった。水深が浅く泥分率の高い播磨灘,燧灘,広島湾および周防灘西部のほとんどの海域では1 g C/m2/year以下であった。大阪湾湾奥部では,水深が浅い泥底で有機物量が多いにもかかわらず生産量が最も多かった。大阪湾湾奥部や燧灘の中央部,および広島湾のマクロベントス現存量は,10-15年前に対して減少していると推察された。
1 0 0 0 OA 金属酸化物を利用した高機能濾過材の開発
- 著者
- 西垣内 祐太 佐橋 栞太 豊原 治彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- pp.17-00021, (Released:2018-03-09)
- 参考文献数
- 20
酵素吸着能に優れた濾過材の作製を目的として,各種金属酸化物のアミラーゼ吸着能について調べた結果,酸化鉄,酸化アルミニウム及び酸化マンガンの吸着能が高いことが判明した。これらの金属酸化物及びこれら固化物に吸着したアミラーゼは,アルカリ性域の反応性が向上し,pH安定性や熱安定性も向上した。以上のことから,酸化鉄,酸化アルミニウム及び酸化マンガンは,優れた酵素吸着能力を有し,これらを用いることで微生物の増殖による溶存酸素濃度の低下を伴わない高機能な濾過材を作製できる可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 位置情報取得によるたこいさり樽流し漁の漁具の流向・流速解析
- 著者
- 高 博昭 和田 雅昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- pp.16-00053, (Released:2018-03-09)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
本論文では,北海道沿岸域で行われているたこいさり樽流し漁を対象として,操業の効率化を実現するための知見を得るために漁具(樽)の位置情報取得に取り組んだ。操業で用いられる樽にGPS腕時計を装着して位置情報を取得し,流向,流速を算出した。その結果,樽の流速は約9 cm/sであること,流向は気象・海象条件によって異なること,流速の変化から船上に樽を引き揚げた時刻を推定できることを示唆した。今後,樽の流向・流速と漁獲量の関係性を明らかにすれば,操業に適した条件の解明につながることが期待される。
- 著者
- Yoshiko Somura Fuminori Mizukoshi Koo Nagasawa Kana Kimoto Mayuko Oda Takayuki Shinkai Koichi Murakami Kenji Sadamasu Kazuhiko Katayama Hirokazu Kimura
- 出版者
- National Institute of Infectious Diseases, Japanese Journal of Infectious Diseases Editorial Committee
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- pp.JJID.2017.264, (Released:2018-02-28)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 4
- 著者
- 渡邊 啓文 船越 公威
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.323-328, 2017 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 33
大分県南東部の隧道内天井は,2013年~2017年の春~夏季の調査でテングコウモリMurina hilgendorfiとノレンコウモリMyotis bombinusの活動期のねぐらとして利用されていた.テングコウモリは5月~6月に10頭前後の個体が密集した集団を形成していた.この群塊は妊娠後期から末期に入った雌の集団であり,九州では初めての発見である.群塊体表の温度は単独個体よりも高く高体温を保持しており,胎児の成長促進に寄与していることが示唆された.テングコウモリは妊娠末期に移動して,他所で出産・哺育すると考えられる.
1 0 0 0 OA 不妊の「マクドナルド化」 : 生殖の医療化の事例として
- 著者
- 白井 千晶
- 出版者
- 日本保健医療社会学会
- 雑誌
- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.102-114, 2001-05-19 (Released:2016-11-16)
本稿は、生殖の医療化を不妊のマクドナルド化を事例に論じるものである。マクドナルド化という分析用具は、アメリカの理論社会学者G・リッツアがM・ウェーバーの合理化理論を拡張して提示したものであり、効率性、計算可能性、予測可能性、制御という4つの次元から構成される。本稿の前半では、生殖の医療化を考察するためには、分析水準と考察対象領域を操作的に設定する必要性が主張され、本稿では不妊患者領域の行為水準に照準を定めることが示されている。後半では具体的にマクドナルド化の4つの次元を使用して不妊患者の行為やそれを取り巻く現象のマクドナルド化を論じている。これらを踏まえて、筆者は最終的に「マクドナルド化」という趨勢の把握から、マクドナルド化メカニズムおよび医療化メカニズムの探究に進むべきであることを主張している。
1 0 0 0 OA 道中膝栗毛 8編続12編
1 0 0 0 いやなさわられかただいきらい
- 著者
- ロリー・フリーマン作 キャロル・ディーチ絵 田上時子訳
- 出版者
- 女性と子どものエンパワメント関西
- 巻号頁・発行日
- 2017
1 0 0 0 OA 分配論からみた教育の在り方
- 著者
- 田原 宏人
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, pp.91-112, 2014-05-31 (Released:2015-06-03)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
教育において平等をいかにして実現するか。数多の研究がこの課題に取り組んできた。だが,苅谷剛彦によれば,日本における教育の平等を求めるレトリックはきわめて特異であり,「能力主義的差別」という言い回しは,彼の見るところ,一種の範疇錯誤である。以来20年,平等主義者たちはこの批判にうまく対応しきれていない。本論文は,教育の内外における分配の正義に関する諸論点を論じる。そのさい,平等主義,優先主義,十分主義(適切性)という異なる三種の分配原理に着目する。平等が教育における正義の重要な価値であるとしても,それは一つの価値に過ぎない。いかなる原理に基礎を置くかに応じて,何をいかに分配すべきかに関する規範的な判断は変わってくる。よって,本稿は,各原理の相違点と,その含意を理解するために,それぞれを支持する論者たちによって繰り広げられている論争に多くの紙数を費やしている。結果,分配の正義に関する今日の知見に照らすならば,40年前の教育実践集に記録されたバナキュラーな声には,大方の予想に反して,平等だけではなく,十分性が,そして時として優先性が,教育における正義の要求であるとの実践感覚が,暗黙裏に反映されていた,ということが明らかになる。彼らには,望ましい教育を構築するために利用可能な言語的資源が欠けていたのである。
1 0 0 0 OA Webにおける聴覚障害者の視覚情報利用特性に関する研究
- 著者
- 生田目 美紀 北島 宗雄
- 出版者
- Japanese Society for the Science of Design
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集
- 巻号頁・発行日
- pp.81-81, 2005 (Released:2005-07-20)
聴覚障害者にとってアクセシブルなWebコンテンツは,聴覚情報にアクセスする代替手段だけでは実現できない.眼球運動および操作過程を詳細に比較観察し,聴覚障害者がどのようにウェブを介して提供される情報と対話するのかという研究を基に,聴覚障害者のウェブページの視覚情報の利用特性を解明した.ウェブ利用における聴覚障害者と健聴者の特性の違いは,1)聴覚障害者がテキスト情報を理解するレベルは健聴者より浅い.2)聴覚障害者のスキャンパスは,健聴者のものと比較して戦略性が見られない.というものであった.したがって,聴覚障害者にとってアクセシブルなコンテンツは,1)リンクラベルの表現が直観的に理解できること.2)コンテンツの構造が視覚的に理解しやすいことが重要であると考えられる.このように,ウェブページ上の視覚情報の利用特性を理解することによって,はじめて,音声情報の補償という観点を越えた聴覚障害者のためのデザインによるコンピュータ支援の道が拓けてくる.
1 0 0 0 OA 皐鶴堂批評第一奇書金瓶梅100回
- 著者
- 明笑笑生撰
- 巻号頁・発行日
- vol.[19], 1695
- 著者
- 中村 圭爾
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1995, no.45, pp.246-248, 1996-03-30 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 IR WEBコミックにおける新たな文法形式の研究/~映画的手法の組み替えと「伝統」の更新~
- 著者
- 本多 マークアントニー 泉 政文 山本 忠宏 大塚 英志 橋本 英治 Mark Anthony HONDA Masafumi IZUMI Tadahiro YAMAMOTO Eiji OHTSUKA Eiji HASHIMOTO
- 出版者
- 神戸芸術工科大学
- 雑誌
- 芸術工学2013
- 巻号頁・発行日
- 2013-11-25
WEB表現へのまんがの適応について、その方向性として、①縦及び横の「スクロール形式 」、②「見開き」に基づくまんがの文法を解体し、一頁単位の表示に基づく文法にシフトした形式 、③静止画のスライドショー形式、の3つが仮説としてたてられ、今回の共同研究では、①のうち「縦スクロール形式」と③の「スライドショー形式」について、そこで採用されるべき文法を仮定し、それに基づき実験作品を制作した。縦スクロール形式においては日本まんが表現の「映画的手法」をいかに導入するかに研究の主眼を置いた。その結果、アイレベルを基準とし、それに続くコマでのアングルの極端な切り換え、コマの縦幅の極端な変化における「尺」(時間)の表現などの、紙媒体で成立した手法の中心的な部分が、WEBへの置き換えが可能であることが確認された。その結果、「横スクロール形式」よりも「縦スクロール形式」の方が映画的手法の移植に向いているという仮説が新たに得られた。また「横スクロール」においては、画面の天地ほぼ中央に視線誘導の基準となる中心線を置くことで視覚の流動性を確保したが、「縦スクロール」では画面を二分割して構図を構成することで画面の左右中央に基準線が存在するのに近い印象を与えることができた。Based on the hypothesis that there are three major directions taken by modes of adaptation of web expression to manga, namely, 1) Forms that adopt vertical or horizontal scrolling; 2) Forms that dismantle the conventional manga grammar based on the double-page spread, and shift to a grammar based on the single-page display; and 3) Forms involving slide shows of still images, this joint study looked at vertical scrolling among the forms under category 1), and also 3), the slide show format, hypothesizing the kind of grammar suitable for these forms, and creating experimental works based on the hypothesized grammar. Research on vertical scrolling webcomics focused on how the movie-style techniques of Japanese manga were incorporated. The research showed that the main movie-style techniques realized in print—such as starting from normal eye level and then abruptly changing the angle in the subsequent panel, or radically altering the height of the panel to represent length of time—could be successfully transferred to the web. Another outcome of the research was the new hypothesis that vertical scrolling is better-suited to the transplantation of movie-style techniques than horizontal scrolling. It was also found that in horizontal scrolling, smooth eye movement for the reader could be retained by placing a central line, which serves as a reference for guiding the eye, roughly at the mid height of the screen, whereas in vertical scrolling, partitioning the screen into two halves to create the composition achieved an impression similar to having a reference line dividing the width of the screen.
1 0 0 0 IR 縦スクロール表示された文章の快適な読み速度と眼球運動
- 著者
- 石井 亮登 森田 ひろみ
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.1784-1793, 2013-06-15
スクロール表示は,狭い領域に多量の情報を提示するために用いられる.本論文では,横書きの文章が下から上へと流れる縦スクロール表示について,その基本的な読み特性を調べることにより,携帯端末などのデザインに資することを目的とする.実験1ではスクロール表示の読みの基本的評価指標の1つとされる快適速度(読み手が快適に読めると感じる速度)と,移動単位(スクロールする際に1度に移動する距離,ここでは1ピクセルまたは1行)や表示枠サイズ(表示行数および1行内の表示文字数)の関係を調べた.その結果,移動単位が1ピクセルの条件の方が快適速度が速いこと,また表示行数および表示文字数の増加にともない快適速度が速くなること,表示枠内の広さが同じであれば,行数を犠牲にして行内の文字数を多くとる方が快適速度が速くなることが示された.実験2では,読み最中の眼球運動を測定した結果,移動単位により読み方が異なることが分かった.ピクセル単位のスクロール表示を読む場合は,1行を読み終えたら速やかに次の行の行頭に視線移動するのに対し,行単位のスクロール表示を読む場合,1行を読み終えてもそのまま行末で行送りを待つ読み方をする.また,移動単位によらず読み手は表示枠内の最下行に視線を向けて読むことが多いことが分かった.結果から,移動単位により異なる縦スクロール表示の読みモデルを提案する.Scrolling text is a useful way for presenting a large volume of materials within a limited display area. To investigate the basic characteristics of vertical text scrolling in terms of readability, we measured the rate of scrolling when one reads comfortably (Experiment 1), and eye movements during reading (Experiment 2). The comfortable reading rate was higher when text was scrolled by pixel (per-pixel scrolling) rather than by line (per-line scrolling), and increased as more lines or more characters per line were presented in the window. It was also found that if the display area is limited, increasing the number of characters per line rather and decreasing the number of lines is effective for improving comfortable scrolling rate. Eye movement data indicated that the lower comfortable scrolling rate for per-line scrolling was mainly due to longer fixation duration at the end of the bottom line. This is probably because readers tend to waits for the next line to appear from the bottom of the window, whereas in the per-pixel scrolling case, they immediately move their eyes to the beginning of a new line.
- 著者
- 清水 龍瑩
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 三田商学研究 (ISSN:0544571X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.117-160, 1995-12-25
今回のサーベイは,次のような環境の下で行われた。1〜4月頃までは景気は回復基調にあると,政府,ジャーナリストに言われていたが,実態はそれ程回復せず,6月になったら足踏状態と言わざるをえなくなり,各企業の経営者は一般論的なリストラ,リエンジニアリングでは対応できなくなった。各企業経営者の対応は各企業ごとの強みを強化し,弱みから思い切って撤退すること,すなわち個性化の一層の深化に力を入れていることである。その個性化の方向を的確にとらえるために,一歩踏み出して情報を収集し,迅速な対処行動をとる。この個性化,積極的情報収集・迅速な行動がこの期の特色である。金融機関のように独自の個性化を出し難いところは,以前よりましてきめ細かな資金管理に力を入れている。また今回の調査には,積極的な経営を行っている,一般企業とは異なった農協についても調査した。農協と一般企業の経営の仕方の最も異なるところは,前者の経営の目的が赤字にならないという制約条件の下で社会的貢献を最大にするのに対し,後者は一定の社会貢献,企業倫理の制約の下で利益・成長を最大にすることであった。<大学>早大総長は,大学の変革は非常に難しいという。民主的手続き・根本的・百年の計という口実で改革に反対する。これに対して従来の延長ではなく,大学の理想をかかげて予算の傾斜配分を行い,突出部分を育てていく。人事で中途採用は易しいが中途追放は難しい。<製造業関係>[大日本印刷];海外進出の必要はない。自社の強みは,顧客の近くに立地していること,シャドウマスクの製造などは装置産業であって人件費に関係ないからである。[宇部興産];従来から事業部ナショナリズムが強かった。個性化をすすめるために,強い事業部はさらに強く,弱い事業部からは撤退する。人事は公平に,財務はアンバランスに,をモットーにする。[東京製鐵]:高炉メーカーとの競争激化。高炉メーカーが価格維持をはかっている分野に進出して,逆に高価格品を売る。当社の1人当りの生産性は5,000トン,高炉メーカーは700トン。十分に競争できる。[日製産業];技術水準が高く海外で生産できない製品は値上げする。日本以外でできるものは生産中止。異能の個性的な人間は1人で仕事をさせる。それをトップが長期的に支援する。[大正製薬]:リポビタンDを中心に大衆薬の販売促進や,新しい効果をもった大衆薬の開発に力を入れる。この大衆薬の研究開発,販売促進にはつねに社長が直接指揮をとる。社長のチェックポイントはあくまで生活者の立場からであり,その薬の将来の発展性がその立場からチェックされる。[大塚製薬];研究所が独創的,革新的な製品を開発できないのは,研究組織中央の大きなミッションに力があるすぎること,および,専門研究者がその専門にこだわりすぎること,とによる。これからは遺伝子研究所に注力する。遺伝子によって発ガン性物質をコントロールする酵素の発生が異なるから,個体の病気予防に役立つ。<流通業関係>[丸広百貨店];カジュアル百貨店という個性を明確にし,都心百貨店と,地域DSとの中間をねらう。価格は中間でも感性,品質は高いものを開発する。この戦略を実行しながら情報を収集し,つねに新しい方向を探していく。[名鉄丸越百貨店];百貨店晩めし論強調。スーパーは昼めし。予め価格をきめておいてその範囲内でおいしいものを探す。晩めしは,おいしくて,雰囲気がよく,楽しいことが第1条件。その条件のもとで安いものを探す。またスーパーは不特定多数の客を取扱うが,百貨店は特定多数の客。[花正];まず一歩を踏み出す。そして新しい視点にたち情報をとり,最適な方向をつかむ。最初に成功した着眼点は業務用食材スーパーの展開であり,次に成功した着眼点は中国進出であり,それを足掛りにして世界展開を考えている。<金融・保険関係>[名古屋銀行];土地問題に抜本的なメスを入れなければ,不良債権問題は解決しない。金融自由化の本格化で,金融機関同士の競争は弱肉強食になってきた。対処策は,金を集めるときは運用までも予め考えるALM管理などのきめこまかい金融業務。[明治生命];逆ザヤ現象と金融の自由化というマクロ問題に直撃され,日本の金融は世界単一市場化の方向に自然に流れていく。株式,不動産の含み益がなくなった現在,個性的な戦略はたて難い。長期的な自由化に対処するために,損保,証券スキルの教育に力を入れている。<農協関係>[東伯農協];農協の目的は赤字にならない範囲内で社会的貢献を最大にすることである。社会的貢献,企業倫理を制約条件として利益,成長の最大化を目ざす一般企業とは異なる。そのためには,集約農業,遺伝子融合などの新技術情報・新市場情報を積極的に収集し,迅速に実行する。[大野市農協];制約条件として最低配当率をきめ,そこから逆算して事業計画をたてる。一般企業の経営とは逆である。一農場方式を標榜し農業をやらない農家から農地を借り,農業専門家を雇い,高品質米を生産する。組合長はつねに地域集会に出席し,組合員に接触しこの一農場方式についての理解を求める。
- 著者
- 茂木 太一 吉川 大輝 曽根 大地 村田 佳子 渡邉 雅子 渡邉 裕貴
- 出版者
- 一般社団法人 日本てんかん学会
- 雑誌
- てんかん研究 (ISSN:09120890)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.31-38, 2014 (Released:2014-07-11)
- 参考文献数
- 15
良性成人型家族性ミオクローヌスてんかん(benign adult familial myoclonic epilepsy:BAFME)における難治性の振戦様ミオクローヌスにプリミドンの追加投与が有効であった症例を報告する。症例は39歳女性。てんかん及び振戦様ミオクローヌスの濃厚な家族歴が存在した。17歳時、手のふるえが出現。24歳時、全身けいれんが初発。29歳時、てんかんと診断されバルプロ酸およびクロナゼパムが開始されたが手のふるえは改善せず、年単位での全身のけいれんが持続した。36歳時、レベチラセタム追加以降、全身のけいれんは消失した。しかし、手のふるえは悪化し下肢や体幹にもふるえが出現し39歳時に当院紹介。各種検査にてBAFMEと確定診断したうえでAmerican Academy of Neurologyによる本態性振戦の治療ガイドラインを参考にプリミドンを追加したところ振戦様ミオクローヌスは抑制された。このことから本態性振戦に有効性が示されているプリミドンはBAFMEにおける振戦様ミオクローヌスにも効果が期待できる可能性が考えられた。