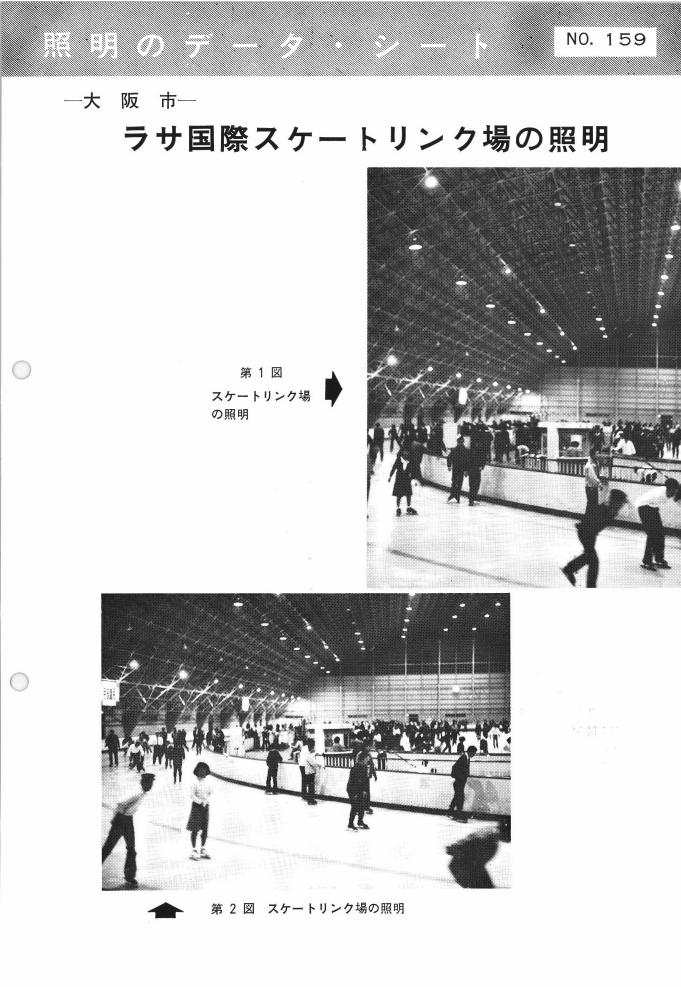1 0 0 0 清心語文
- 著者
- ノートルダム清心女子大学日本語日本文学会 [編集]
- 出版者
- ノートルダム清心女子大学日本語日本文学会
- 巻号頁・発行日
- 1999
1 0 0 0 OA 照明のデータ・シート (No.160)
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会雑誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.9, pp.plate1-plate2, 1964-09-25 (Released:2011-07-19)
1 0 0 0 IR 永井亨論素描 : 人口問題・社会道徳・新生活運動 (川東竫弘教授記念号)
- 著者
- 松田 忍
- 出版者
- 松山大学総合研究所
- 雑誌
- 松山大学論集 (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.215-237, 2016-10
1 0 0 0 OA バックグラウンド計測を必要としない電解濃縮トリチウム水測定法
- 著者
- 斎藤 正明 今泉 洋 加藤 徳雄 石井 吉之 高橋 優太 斎藤 圭一
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.1-6, 2007-01-15 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 12
濃縮試料の計数率から未濃縮試料の計数率を差し引いたものは, 正味の計数率に (濃縮倍率-1) を乗じたものである。この関係を利用して, バックグラウンド計数を差し引くことなく正味の計数率を得ることができる。トリチウムの電解濃縮測定法に適用し, その結果を検証した。環境濃度レベルにおいて, 測定値及び測定誤差は従来法と同程度であった。この測定法はトリチウム濃縮分析において実用的にも有効であることが確認できた。
1 0 0 0 OA 環境水中トリチウム濃縮のための新規電解素子の特性
- 著者
- 島 長義 村中 健
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.8, pp.455-461, 2007-08-15 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 10
A newly designed electrolytic device to enrich tritium in environmental water is proposed. This device is composed of a solid polymer electrolytic film (SPE film) and porous, dimensionally stable electrodes (DSE) . In our design a platinum mesh was inserted between the SPE film and the anode DSE so that the device can be easily disassembled and the used SPE film can be replaced with a new one after each use. A thin gold plate with a number of minute holes in it is used as current collector in both electrodes allowing the electrolytic gas to be released progressively.An electrolytic current of 6A was passed through the device to obtain a volume reduction factor of five by keeping a temperature of water bath at 2°C or lower. After that, our device achieved a tritium recovery factor of 0.836 ± 0.021 (n=4) . Such a value is greater than the value obtained using a commercially available apparatus operated under the same experimental conditions. It is thought that this greater efficiency depends on the difference between electrolytic temperature produced in our device and the temperature in the commercially available one.
- 著者
- 山口 訓史 後藤 丹十郎 小日置 佳世子 大谷 翔子 田中 義行 吉田 裕一
- 出版者
- 園芸学会
- 雑誌
- 園芸学研究 (ISSN:13472658)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.161-167, 2014
- 被引用文献数
- 1
最低気温がシュッコンカスミソウ'アルタイル'の形態異常花序発生および切り花形質に及ぼす影響を調査した.形態異常花序を異常の特徴と程度に基づき3つのタイプ(1:茎が短いもの,2:2本の茎が癒着,3:ひどく湾曲し変形したもの)に分類した.形態異常花序の発生は初冬から早春にかけて増加した.軽度なタイプ1とタイプ2による形態異常は,開花時期に関係なくほぼ一定の割合で発生が認められたのに対して,切り花の外観を大きく損なうタイプ3は3月開花の個体で大幅に増加した.最低気温(7°C, 11°C, 15°C)が形態異常発生に及ぼす影響を調査したところ,タイプ3は最低気温が低いほど発生率が高かった.一方,切り花長,切り花重は最低気温が高いほど劣ることが明らかになり,形態異常花序発生を抑制したうえで,十分なボリュームの切り花を得るためには11°Cの加温が有効であると考えられた.栽培期間中の低温への積算遭遇時間とタイプ3の発生割合の関係を分析したところ,発蕾から開花までの積算低温遭遇時間と形態異常花序発生の間に相関は認められず,摘心から発蕾までの積算低温遭遇時間と形態異常花序発生との間には有意な相関が認められたことから,摘心から発蕾の期間における9°C以下の低温遭遇が重度の形態異常花序(タイプ3)の発生に関与することが示唆された.
1 0 0 0 シュッコンカスミソウの夏秋期出荷作型における窒素施用量と採花本数
- 著者
- 大竹 真紀
- 出版者
- [東北農業試験研究協議会]
- 雑誌
- 東北農業研究 (ISSN:03886727)
- 巻号頁・発行日
- no.67, pp.133-134, 2014-12
福島県会津地域はシュッコンカスミソウの夏秋期の主産地であり、市場性の高い品種を導入するとともに収量を上げる摘心方法の改善を進めている。主要品種「アルタイル」は、育成した谷によると、吸肥力が強く茎葉が剛直になりやすいため施肥量を控える必要があるが、窒素吸収の実態は明らかになっていない。そこで、高冷地の夏秋出荷作型において摘心方法にあった窒素施用量と採花本数について検討した。
1 0 0 0 IR 釧路市街地域における河川津波遡上・氾濫の予測手法とその活用に関する一提案
- 著者
- 阿部 孝章 佐藤 好茂 船木 淳悟 吉川 泰弘 中津川 誠
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集A1(構造・地震工学) (ISSN:21854653)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, pp.I_1004-I_1011, 2015
本稿では北海道でも人口が低平地に密集する釧路市を対象地域とし,河川周辺域における自治体等行政の減災対策を支援する手法の開発を目的として検討を実施した.まず,波源域から河道域までの津波解析を簡易に実施可能な一連のモデル開発を行い,実際に発生した津波波源モデルのパラメータ及び河川流量を変化させた解析を行い,各構造物が受ける津波外力を評価した.次に,北海道庁により検討が行われた最大クラスの津波のデータを用いて地盤沈下量を変化させた解析を行い,上水道や下水処理施設等に対する津波外力を評価した.その結果,津波の規模と河川流量,地盤変化量の条件次第では,施設の被災可能性は変化する可能性がある事が分かった.複数の津波想定を事前に行っておくことで河川管理者や自治体の減災支援となる可能性が示された.
1 0 0 0 IR 河川津波に伴い発生した北海道鵡川のアイスジャム再現計算
- 著者
- 吉川 泰弘 阿部 孝章 平井 康幸
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集B2(海岸工学) (ISSN:18842399)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.I_416-I_420, 2012
- 被引用文献数
- 3
The tsunami of 2011 Tohoku Pacific-Coast Earthquake broke river-ice, and generated ice jam in Hokkaido, Japan. This study aimed to clarify the phenomenon of ice jam generated by tsunami in ice covered river. We built the river-ice calculation model. In order to check the accuracy of this calculation model, we conducted ice jam experiment and a calculation value reproduced an experiment value. We understood that it was important to set up "the conditions to generate of ice jam" and "the allowable stress of river-ice" appropriately in this calculation model. This following phenomenon was found by Simulation of Ice Jam. At the time of tsunami intrusion to ice-covered river, River-ice was destroyed and moved to the upstream. River-ice was deposited in narrow river-width. Ice jam was generated at this point.
1 0 0 0 一枚の絵はがきがもたらした変化からみる在宅生活支援
1 0 0 0 OA 自己に向いた注意の硬着性と抑うつとの関係
- 著者
- 坂本 真士
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.4, pp.407-413, 1993-12-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 3
The self-focus theory of depression (Ingram, 1990) predicts that the depressives remain self-focused when the external environment changed as compared with the nondepressives. Fifty-three male students participated in the following experiment. They were administered a self-rating depressive scale. About half of the subjects were heightened self-focused attention whereas the other half of the subjects were not. All subjects were instructed to solve tasks that required much attention. The results generally supported the hypothesis: (a) among subjects who were heightened selffocused attention, the depressives solved less tasks than the nondepressives; and (b) during the task-solving, the depressives focused more attention on themselves than the nondepressives did. On the other hand, among the subjects not showing heightened self-focused attention, the above mentioned differences were not found. The role of the self-focused attention in maintenance of depression was discussed.
1 0 0 0 OA 江戸市民と葛西金町村の半田稲荷
- 著者
- 加藤 貴
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.155, pp.59-85, 2010-03-15
江戸市民にとっての名所は、自然との交流と神仏との交感によって、「延気」を約束してくれる場所であった。江戸市民は、一八世紀以降になると、名所をめぐる広範な行楽行動を展開するようになっていき、江戸の近郊では、新たに多彩な名所が成立していった。その多くは、日本橋からほぼ半径二里半(約一〇キロメートル)の範囲におさまっている。ところが、本稿でとりあげた半田稲荷社は、江戸から四里の距離にある葛飾郡東葛西領金町村に所在しており、日帰りが不可能ではないが、江戸市民にいわば小旅行をさせたのは、それだけの利益を半田稲荷社が約束してくれたからである。当時の医学では対症療法しかなく、しかも罹患すると死亡率の高い疱瘡除の利益である。こうした半田稲荷社と江戸市民との関係を、信仰主体・願人坊主・江戸出開帳などからみていった。半田稲荷社の疱瘡除の利益を江戸で宣伝して回ったのが願人であり、板東三津五郎が歌舞伎の舞台で踊ってみせたことで、さらにその存在が江戸市民に周知されていった。しかし、江戸市民からの信仰を集め、多くの参詣者があったものの、それほどの潤いを半田稲荷社や金町村にもたらさなかったようである。ここに同じく江戸市民から信仰を集めた王子稲荷社や王子村との大きな違いがみられる。江戸からの距離が、王子稲荷社は二里半、半田稲荷社は四里と、それほどの違いにはみえないが、江戸市民にとってはこの一里半の違いが大きかったようである。また、王子が四季を通じた行楽地として、多くの江戸市民を集めたのに対して、半田稲荷社が疱瘡除の強力な利益を与えても、それだけで江戸市民を常時魅きつけることはできなかったようである。王子稲荷社と半田稲荷社の違いは、江戸市民の名所をめぐる日帰り行楽行動の範囲が、日本橋を中心に一〇キロメートルの範囲にとどまったことを再確認させてくれる。それでもなおかつ江戸市民が半田稲荷社に参詣したのは、疱瘡除の強力な利益を約束してくれたからである。
1 0 0 0 森鴎外と自然主義
- 著者
- 細田 明彦
- 出版者
- 花袋研究学会
- 雑誌
- 花袋研究学会々誌 (ISSN:09118667)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.26-35, 1999-03
1 0 0 0 アサトン型ネオリグナンの結晶構造と分子内 [2+2] 光反応
- 著者
- 吉原 涼子 森 一樹 西山 繁 山村 庄亮 大場 茂 伊藤 義勝
- 出版者
- The Crystallographic Society of Japan
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.62-62, 1998
- 著者
- 上野 善子
- 出版者
- 奈良女子大学
- 雑誌
- 人間文化研究科年報 (ISSN:09132201)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.89-106, 2013-03-31
Since the child abuse and neglect case judgment in late 1880s, in the United States hasrapidly promoted child protection activity mainly in an urban area. Initially, social recognitionof child abuse and neglect was seen as an often-unwarranted behavior on the intimate sphereof the family. However, after the 1990s, child welfare became the target of social security. In the mid 1990s, visualization technology of the physical abuse became possible dueto the progress of medical science and skills, thus accelerating the movement to prevent childabuse and neglect, which by then had been carefully defined abuse. The issue of child abuseand neglect, in which children are targeted for protection, had been recognized as requiringsimultaneous support for parents and as a family problem.Although the recognition of abuse had been inconsistent among the states, it wasgiven a consistent federal definition by CAPTA in 1974. Along with the federal definition ofabuse, came the improved ability of child protective services to intervene in dysfunctionalfamily as specialists in social welfare with an official position and procedure in the matter.Nevertheless, since the 1990s, when the United States had to deal with financialproblems and the deterioration of security caused by domestic and global poverty following theeconomic crisis, CAPTA was also repeatedly adjusted and modified against the changing social background.
1 0 0 0 OA 貝殻廃棄物を利用した酸性雨 · 強酸性土壌地の緑化
- 著者
- 吉田 寛 古田 智昭 福永 健司
- 出版者
- 日本緑化工学会
- 雑誌
- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.512-519, 2003 (Released:2004-08-27)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 3 3
貝殻廃棄物を利用した酸性雨対策や強酸性土壌地における緑化手法「アルプラス工法」の概要について紹介する。本緑化工法は, 酸性矯正材 (中和材) として臨海施設や養殖産業から排出される貝殻廃棄物を調整加工したリサイクル資材「シェルレミディ」を用いることを特徴としている。この資材は, 中和効果が長期間持続するほか, 多くのミネラルを含んでいることから一般的な中和剤である炭酸カルシウムを使用した場合と比較して植物の成長を促進することができ, 植生基材や酸性矯正層の材料として使用することにより, 酸性雨や強酸性土壌が原因で植生の回復が困難な法面等における良好な緑化が期待できる。
1 0 0 0 IR 米国の児童虐待 : 医療化以前の虐待認識と社会
- 著者
- 上野 善子
- 出版者
- 奈良女子大学
- 雑誌
- 奈良女子大学社会学論集 (ISSN:13404032)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.55-72, 2012
In this paper, described in a historical perspective about the medicalization andcriminalization of public awareness of child abuse before medicalization in the U.S.In the early 1960s, pediatrician named H. Kenpe discovered " child abuse " and defined"disease". Then, Child Abuse is increasing concern as a social problem, and it legislation to preventchild abuse proceeds rapidly, the enacted of the Federal Child Abuse Prevention and Treatment Actin 1974. However, before medicalization for the American society, child abuse had been identifiedas delinquent behavior, were subject to corrected.It is usually considered that the child is a menaceof a community, and recognized that a community - juvenile justice system or court of law - has thechildren's rights in this area. The reason in which Mary Ellen's rescue operation succeeded is notthat the public system of right protection of a child was ready. It comes out that this incidentattracts attention in the meaning that it was the transition stage of child protective when privaterescue attempt was performed.This paper describes the historical outline about puritanical United States society(including parents and community) of those days having recognized how about the right of a childand the child itself from ancient times to the 19th century and clarifies the violence probleminvolving the people and the family who were concerned with protection of a child from thehistorical background. A view to the child of those days becomes clear in particular fromconsideration of the Mary Ann Cruise's Judgment and PARENS PATRIAE.This historical analysis is aimed at clarifying the foundation for the newest methodologycoping with a social problem by clarifying the measure and background of the child protection inthe 19th century America which had big influence on child protection activities towards discoveryand prevention of child abuse in the United States of America.