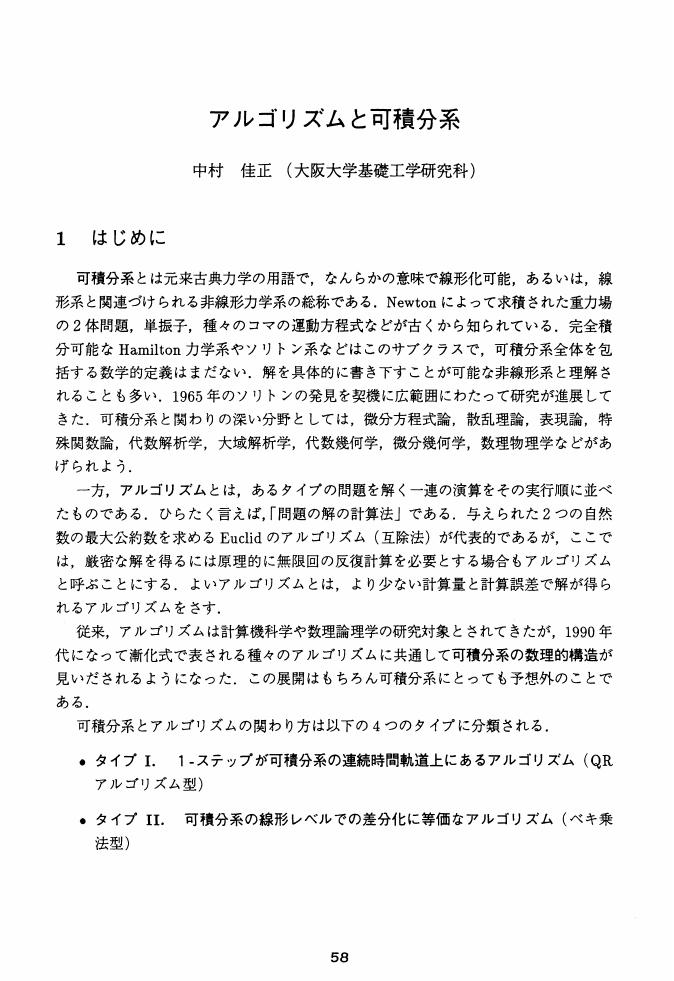2 0 0 0 OA コキン法以前
- 著者
- 森 まゆみ
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.11, pp.11_7-11_8, 2021-11-01 (Released:2022-03-25)
2 0 0 0 OA 集団間交渉時の認知的バイアス ―他集団の参入が既存集団の影響力の知覚に及ぼす効果―
- 著者
- 岡本 卓也
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.26-36, 2007 (Released:2007-09-05)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1 1
本研究は既存集団のもとへ他の集団(参入集団)が参入した時,既存集団成員が内集団の影響力を過小評価することを確認し,この過小評価の発生量の規定要因として内集団アイデンティティ(内集団Id)と共通内集団アイデンティティ(共通集団Id)の効果を明らかにした。実験1では,実験参加者36名から12個の3人集団を構成し,半数を既存集団に,残りを参入集団に割り当てた。集団ごとにある課題について討議・決定させた後,既存-参入集団を組み合わせた6人集団(上位集団)を構成し,再度同一課題について意思決定を求めた。その結果,既存集団は参入集団に比べて再決定時の自分達の影響力を過小評価していた。実験2では参入集団をサクラが演じ,49名の参加者を全て既存集団とし内集団Id(高・低)と共通集団Id(形成・無し)を操作した。その結果内集団Id高群で影響力の過小評価が認められた。共通集団Idの高さは過小評価の発生には影響を与えず,相手集団との対立度を低く認知させた。両実験の結果に基づき,既存集団における影響力の過小評価および対立度の認知と集団Idとの関係について考察した。
- 著者
- 甲能 直樹 安藤 佑介 楓 達也
- 出版者
- 瑞浪市化石博物館
- 雑誌
- 瑞浪市化石博物館研究報告 (ISSN:03850900)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.125-135, 2020 (Released:2021-04-09)
- 参考文献数
- 25
A pinniped fossil was found at the construction site of the Togari-Tsukiyoshi City Road in Akeyo-cho, Mizunami City, Gifu Prefecture, Japan in September 2020. We briefly report this new discovery of a partial skeletal bones belonging to a single individual (MFM18009), which was recovered from the lowermost part of the Yamanouchi Member of the Akeyo Formation, the Mizunami Group (lower Miocene: ca 18 Ma). MFM18009 is consisted from a complete skull, distal half of the left mandible, the atlas, distal half of the left humerus, proximal half of the left ulna, the third metacarpus, thoracic vertebrae and ribs. MFM18009 seems to belong in the Pteronarctos-Pacificotaria species complex of pinnipediforms, and is provisionally identified as Enaliarctine genus and species undetermined.
2 0 0 0 OA 慢性腎臓病(CKDステージ1)の猫に対する電子水給与の抗酸化能への影響
- 著者
- 櫻井 玲奈 金野 好伸 小沼 政弘 内田 直宏 井口 愛子 小林 沙織 山﨑 真大 佐藤 れえ子
- 出版者
- 動物臨床医学会
- 雑誌
- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.157-162, 2019-01-15 (Released:2020-01-15)
- 参考文献数
- 16
人の慢性腎臓病(CKD)では生体内での活性酸素種(ROS)の産生増加と,抗酸化能の低下が知られており,猫のCKDでも腎組織内のROSによる酸化障害が尿細管と間質の線維化につながることが報告されている。本研究では,初期のCKD猫に電子水を給与し,血中酸化度マーカーと抗酸化能マーカーの変化を観察して,その効果について検討した。1カ月の電子水給与により,対照群にて有意に抗酸化能マーカーが増加し,またCKD群でも有意差はないものの増加傾向を示した。また,血中酸化度マーカーは両群に有意差はないものの低下傾向が認められた。電子水の給与は猫でも人と同様に生体内における酸化ストレスの緩和と抗酸化能の活性化に寄与する可能性があると示唆された。
2 0 0 0 OA X線検出器(イメージングプレート)の放射能汚染に対する 効果的な除染方法の提案
- 著者
- 西原 貞光 林 裕晃
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.8, pp.912-915, 2011-08-22 (Released:2011-08-24)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 5 1 5
Several hospitals have been observing black spots in medical images, and the radioisotopes (RIs) that cause the spots needs to be removed from the X-ray receptors. Our purpose is to show a flowchart for finding out under which conditions an imaging plate (IP) and other parts (for example, the cassette) are contaminated by RIs and to propose an effective method to remove them. The procedure follows. (1) Is RI activity low? (2) Are the surfaces of other parts contaminated? (3) Is the surface of the IP contaminated? (4) Are the insides of the other parts contaminated? To remove the adhered RIs, we applied a wipe test method using a wet type of chemical wiper. A certain hospital that observed black spots experimented with this method. As a result, the contaminated condition of the X-ray receptor was identified. In addition, we were able to remove the RIs from the IP. Therefore, our procedure is very effective for decontaminating adhered RIs from receptors.
2 0 0 0 OA 『和漢朗詠集』データベースの 制作について ―高校「書道」教材としての活用を中心に―
- 著者
- 山本 まり子 山本 晃立
- 出版者
- 日本大学文理学部中国語中国文化学科
- 雑誌
- 中国語中国文化 (ISSN:02882604)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.19, pp.18-31, 2022 (Released:2022-03-30)
2 0 0 0 OA Caloric restriction suppresses exercise-induced hippocampal BDNF expression in young male rats
- 著者
- Shohei Dobashi Chinatsu Aiba Daisuke Ando Masataka Kiuchi Mitsuya Yamakita Katsuhiro Koyama
- 出版者
- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine
- 雑誌
- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.239-245, 2018-07-25 (Released:2018-07-18)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 2 2
Both exercise training and chronic caloric restriction contribute to brain health through enhanced expression of brain-derived neurotrophic factor (BDNF). This study investigated the synergistic effects between 12-week low-intensity exercise training and caloric restriction on hippocampal BDNF expression with redox status in rats. Twenty-six, 7-week-old male Wistar rats were randomly divided into the following 4 groups: (1) sedentary control (Con, n = 7), (2) exercise (Ex, n = 6), (3) caloric restriction (CR, n = 7), and (4) caloric restriction and exercise training (ExCR, n = 6). Although Con and Ex rats were fed ad libitum over time, CR and ExCR rats consumed 40% less food compared to Con rats. Ex and ExCR rats underwent low-intensity treadmill running (30 min/day, 5 days/week). Forty-eight hours after the termination of the 12-week intervention, rats were sacrificed and the hippocampus was quickly dissected for measuring BDNF expression and markers of oxidative stress, including 4-hydroxy-2-nonenal (4-HNE). Hippocampal BDNF expression was significantly increased in Ex compared to Con rats (p = 0.007), whereas the exercise-induced increase in BDNF was completely suppressed by a combination with caloric restriction. Furthermore, we observed a significant relationship between hippocampal BDNF and 4-HNE expression (r = 0.725, p < 0.001). Our findings indicate that exercise training combined with caloric restriction might not have a synergistic effect on hippocampal BDNF expression in young rats. Moreover, exercise-induced oxidative stress can trigger BDNF expression in the hippocampus.
2 0 0 0 OA タウリンによる運動後における筋グリコーゲン再合成の促進
- 著者
- 八田 秀雄 高橋 祐美子
- 出版者
- 国際タウリン研究会
- 雑誌
- タウリンリサーチ (ISSN:21896232)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.37-39, 2016 (Released:2019-11-11)
タウリンが持久的運動後のエネルギー代謝に与 える影響を検討した。マウスに 25m/min の速度で 90 分のトレッドミル走行を行わせ、運動直後にタ ウリンを与えた条件で自由運動を行わせたところ、 回復 3 時間までの総自由運動量がタウリン投与群 で水投与群より有意に高かった。そこでタウリンが 持久的トレーニング運動後の代謝に対して影響を 与え、疲労回復を促進する可能性が高いことがわか った。これを受けて同じ 90 分間の持久的運動後に タウリンを与えて安静を保ち、回復期に筋など組織 を採取して検討した。その結果、回復 2時間におけ る前脛骨筋のグリコーゲン濃度がタウリン群が対 照群よりも有意に高かった。また運動後にグルコー スを与えた条件で回復 1 時間の血中グルコース濃 度の低下がタウリン群で有意に早かった。さらに同 条件での回復 2 時間の前脛骨筋中基質濃度につい てメタボローム解析を行った結果、解糖系の律速段 階の1つであるホスホフルクトキナーゼ以降の中 間基質がタウリンで有意に低かった。したがって持 久的運動後のタウリン投与で筋グリコーゲンの再 合成が促進されることがわかった。そしてこのこと にはタウリンによって糖取り込みの促進や糖分解 の低下が起きていることが関係していることが示 唆された。
2 0 0 0 OA アジピン酸の工業的合成とその利用(基礎化学品製造の実際と高校での教育実践)
- 著者
- 熊本 卓哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.266-269, 2012-06-20 (Released:2017-06-30)
- 被引用文献数
- 1
アジピン酸の工業的合成とその利用について述べる。アジピン酸は,シクロヘキサンの酸化より合成されるシクロヘキサノン-シクロヘキサノールの混合物(KA oil)を硝酸酸化して得るKA法が一般的であるが,副生する一酸化二窒素が環境に対して問題があるため,硝酸酸化を用いない方法や一酸化二窒素の再利用法の開発も進んでいる。本稿では,アジピン酸の製造について,KA oilを経由する方法のほか,シクロヘキセンを経由する製造法や,シクロヘキサンからの1段階合成法などについて概説し,その利用について簡単に述べる。
2 0 0 0 OA 職業アスピレーション再考 職業間類似判定と選好度データに基づく計量分析
- 著者
- 林 拓也
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.359-375, 2012-12-31 (Released:2014-02-10)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
職業アスピレーションは, 職業達成のプロセスに関わる社会心理的な媒介要因として位置づけられる志向である. 近年の日本の状況を扱った実証研究によると, それが達成プロセスと遊離しつつあるということが示唆されているが, こうした結果については慎重な検討を要する. アスピレーションの測定に際して, 「地位」の優位性と一次元性が前提とされているためである. そこで本稿では, 職業の一次元的な「地位」に限定されない, 職業間の「類似性」に着目するアプローチから職業志向を導出し, それに基づいてアスピレーションについての再検討を加えていく. 分析に用いたデータは, 2008年に東京23区在住の25~39歳男性雇用者を対象とした調査により得られたものである. このデータに対し, 職業間類似度に基づく認知構造の析出, その構造における職業選好の方向, そして志向と達成プロセスとの連動について段階的な分析を展開した. 認知特性の次元としては, 「安定的地位」「組織/技能」「裁量」が析出され, 個々人の選好データに基づいてそれらに対する志向が計測された. また, 各志向が回答者自身の職業など客観的属性と関連していることから, 達成プロセスとの連動も確認された. そのうえで, これまでのアスピレーション研究との接合や今後の課題について議論を展開した.
2 0 0 0 OA 生薬成分ゲラニインに抗インフルエンザウイルス活性を発見
- 著者
- 吉野 悠希
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.346, 2020 (Released:2020-04-01)
- 参考文献数
- 4
現在日本では,インフルエンザウイルス感染症に対する治療薬として,ノイラミニダーゼ(NA)阻害薬とキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬が使用されている.しかし,これらの薬剤には既に耐性ウイルスの存在が報告されており,将来薬剤耐性を獲得した強毒性ウイルス,あるいは新型のインフルエンザウイルスによるパンデミックが生じることが危惧されるため,現在新しい抗インフルエンザ薬の開発研究が活発に行われている.本稿では,民間薬として知られるゲンノショウコの抗インフルエンザ活性に着目し,その評価と活性成分の探索を行ったChoiらの研究成果について報告する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) 齋藤玲子,日耳鼻,115, 663-670(2012).2) Uehara T. et al., J. Infect. Dis., 221 346-355(2020).3) Choi J. G. et al., Sci. Rep., 9, 12132(2019).4) Bastian F. et al., Molecules, 23, 1346(2018).
- 著者
- 松井 豊 菅原 明彦 石井 健介
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.252-253, 2022 (Released:2022-03-01)
- 参考文献数
- 7
2021年3月、ケトチフェンフマル酸塩を含有したソフトコンタクトレンズが世界で初めて承認された。海外におけるプラセボレンズを対照とした無作為化二重盲検試験において、対照群に対する眼そう痒感スコアの差は-1.05(p<0.001)であり、一定の有効性が認められたこと等から承認は可と判断した。本品は、医師の指示に基づき、アレルギー性結膜炎を有するソフトコンタクトレンズ装用者のみが適応対象であり、適正使用のための留意事項等がある。
2 0 0 0 OA 失語を呈する変性疾患の病理背景
- 著者
- 吉田 眞理
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3+4, pp.130-144, 2021 (Released:2021-04-29)
- 参考文献数
- 21
【要旨】 臨床的に失語症が記載されている13例の病理像を概説した。意味型失語症を示した6例の背景病理は、TDP-43蛋白蓄積を示す前頭側頭葉変性症(frontotemporal lobar degeneration, FTLD-TDP) type Bが3例、 Pick病が1例、 FTLD-TDP type AとADの合併例が2例であった。病変分布は、側頭葉極を含む前方側頭葉の変化が強く、後方では軽度になる傾向を認めた。非流暢性失語症を示した例は、大脳皮質基底核変性症(corticobasal degeneration, CBD)1例、進行性核上性麻痺(progressive supranuclear palsy, PSP)3例、FTLD-TDP type A 1例、Pick病1例であった。CBD、PSP、Pick病などのタウオパチーが83%、内67%は4Rタウオパチーで、50%はPSPで、左優位のシルビウス裂周囲の前頭側頭葉皮質変性を示した。発語失行の例ではFTLD-TDP type Aを示し右中心前回弁蓋部に強い萎縮を示した。語減少型失語症の1例はdiffuse neocortical typeのレビー小体型認知症とアルツハイマー病の合併病理を認めた。失語症の背景病理として、FTLD-TDP、CBD、PSP、Pick病などのタウオパチー、アルツハイマー病が存在していたが、意味型失語症ではFTLD-TDP、非流暢性失語症ではタウオパチーの比率が高かった。
2 0 0 0 OA 脳梗塞後に万引きを繰り返す症例への環境構造化の取り組み
- 著者
- 甲斐 祥吾 笹原 紀子 野村 心 芝尾 與志美 中島 恵子
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.320-329, 2016-06-30 (Released:2017-07-03)
- 参考文献数
- 29
左内頸動脈閉塞に起因する脳梗塞後に, 高次脳機能障害による社会的行動障害として万引きを繰り返し, 時刻表的行動, 失語症を呈した症例を経験した。今回, 責任病巣から先行研究と比較・検討したうえ, 万引きの対象品, 要因等を行動観察により評価した。介入内容として, 多職種の協力体制のもと, (1) 万引きの対象は特定の嗜好品であったことから金銭管理, 嗜好品の保管, チェックリスト作成を行い, (2) 時刻表的行動をプラスの側面と捉えて買物・摂食をスケジュール化したことで, 万引きは消失した。今回, 前頭葉に損傷がなく, 一側性の病変により常同的な食行動異常を呈する万引きに対しては, 環境の構造化により, 不適切行動が早期に消失する可能性が示された。これらのことから, 病巣と行動観察から原因を評価し, 地域生活にわたるまで多職種で関わることが, 万引きのような触法行為を伴う社会的行動障害にも有効であると示唆された。
2 0 0 0 OA MMRによる文選択とTF-IDFによる文圧縮を用いたニュース記事要約
- 著者
- 石原 祥太郎 澤 紀彦
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第35回 (2021)
- 巻号頁・発行日
- pp.1D2OS3a03, 2021 (Released:2021-06-14)
本研究では,ニュース記事を文章選択・圧縮で要約する手法を提案する.具体的には,記事を代表するN個の文章を抽出し,構文解析で各文章を圧縮する.指標としてMMR(Maximal Marginal Relevance)とTF-IDF(Term Frequency - Inverse Document Frequency)を用いた.実験の結果,提案手法は人間の編集者の作業と約26.7%の割合で同一の話題に言及していた.必ずしも高い一致率とは言えないが,それ以外の生成物も日本語として誤りが少なく,候補として採用できるものが多かった.提案手法には特定の語句の重み付けなどで編集者の意図を組み込みやすく,編集者の負担軽減に繋がる利点がある.
2 0 0 0 OA 音楽聴取時の覚醒度と外部/内部テンポの関連
- 著者
- 阿部 晃気 日根 恭子 金塚 裕也 中内 茂樹
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.PM-029, 2021 (Released:2022-03-30)
音楽聴取時の覚醒度は,音楽の選好と関連があり,選好の決定機序を明らかにするうえで重要な要素の一つである。これまで,覚醒度は音楽のテンポ(外部テンポ)により変化することが明らかとなっているが,歩行や指タッピングのような自発的な運動動作(内部テンポ)が覚醒度とどのように関連するのか直接的な検討はなされていない。本研究では,外部/内部テンポが音楽聴取時の覚醒度とどのように関連があるか調査した。実験参加者21名に対して,初めに指タッピングで内部テンポを計測した。その後,3種類(遅い,速い,中程度)のテンポで演奏されたクラシックピアノ音楽を各2曲,計6曲の聴取を求めた。実験中は,実験参加者に対して覚醒度の客観的指標となる皮膚電気活動の計測が行われ,各曲聴取後は,音楽によって誘発された覚醒度の主観的評価を求めた。結果として,主観的覚醒度は,外部テンポが遅いと下降,外部テンポが速いと上昇した。一方,客観的覚醒度は,内部テンポと外部テンポの差が小さい場合に上昇する傾向がみられた。この結果は,外部テンポと内部テンポの両方が音楽聴取時の覚醒度に影響を与えることを示唆している。
2 0 0 0 OA 消費行動に対する文化的自己観の影響に対する考察 〜弁証法的自己観に着目して〜
- 著者
- 鈴木 智子 阿久津 聡
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.75-87, 2012-06-30 (Released:2021-01-12)
- 参考文献数
- 35
- 著者
- 千田 有紀
- 出版者
- 日本女性学会
- 雑誌
- 女性学 (ISSN:1343697X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.33-42, 2018-03-31 (Released:2021-11-12)
2 0 0 0 OA フレーゲ哲学の現代的意義
- 著者
- 佐藤 雅彦
- 出版者
- The Philosophy of Science Society, Japan
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.67-84, 2016-07-31 (Released:2016-11-10)
- 参考文献数
- 16
“The Full Picture of Frege’s Philosophy” (Keiso Shobo, 2012) by Kazuyuki Nomoto gives a detailed account of Gottlob Frege’s life devoted to a failed attempt to develop mathematics formally and entirely from scratch based upon his logicism and his semantical understanding of mathematical entities. In the present paper, I review the book and recommend it as a challenging and inspiring book to anyone who wishes to understand the modern meaning of Frege’s philosophy.
2 0 0 0 OA アルゴリズムと可積分系
- 著者
- 中村 佳正
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 総合講演・企画特別講演アブストラクト (ISSN:18843972)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.Spring-Meeting, pp.58-71, 1999 (Released:2010-07-01)
- 参考文献数
- 20